
〈ノーベル生理学・医学賞授賞 坂口志文さん〉道程――切り拓いたがん・免疫疾患治療への可能性 坂口志文(免疫学研究者)
2025.10.09
Wedge ONLINE
「定年で自由になったこともあって、臨床応用の研究を進めて、自分の研究を一刻も早く医療で実用化して病気を治したいという気持ちが強くなってきましてね。公的資金を待つだけではなく、自分たちの手で投資を呼び込んで、自分たちの意志が発揮できる形を追求しています」
一日千秋の思いで、治療法が生まれる日を待っている人は多い。
「長年制御性T細胞の研究に携わってきて、いつも節目となる研究に貢献できたことは、学者人生としてありがたいことだと思っています」
免疫学との出会い

学者人生は、京都大学医学部に入学した時から始まったわけだが、医学部を志望したのは「何となく」だったという。中学の時は美術部で絵描きになりたいと漠然と考えていたが、本格的に決心するまでは至らず、次は人間の心に関心を抱き哲学に興味を持った。ここまではどうみても文科系志望である。
「父が京大で哲学を学んでいて、そんな本がいっぱい家にあったんですよ。でも戦後父は苦労したせいか、僕が理科系に進むことを望み、母方には医者が多くて、それで漠然と医学部に入って精神科医になろうと考えたわけです。北杜夫(もりお)さんとかなだいなださんとかをイメージして、医学と哲学と両立できるかなという程度で、先のことを深く考えていたわけじゃないんですよね。当時は大学も学園紛争の影響が残っていてワサワサしていましたし、とりあえず基礎医学を勉強して、面白そうなところを探そうかなという感じでした」
そんな時に講義で興味を持ったのが免疫学だったという。免疫の何が坂口を引き付けたのだろうか。
「自分を守るために異物を認識して攻撃する免疫が、時に過剰に反応したり、自己の組織や細胞を異物と認識してしまって攻撃することもある。自己と自己でないものの境界にゆらぎがある。たとえば、体外に流れた血液は凝固することで血を止めて身を守るわけだけれど、血管の中で凝固することはないし、もし固まったら血栓になって脳梗塞や心筋梗塞を起こす。こっちで反応してこっちでは反応しない。どこにスイッチのオンとオフが存在するのか。そこに生物学的に、あるいは医学的にちょっと深淵でちょっと哲学的なものを感じて、面白そうと思っちゃったんですよね。そこからのめり込んで、結局40年以上。のめり込み過ぎましたねえ」
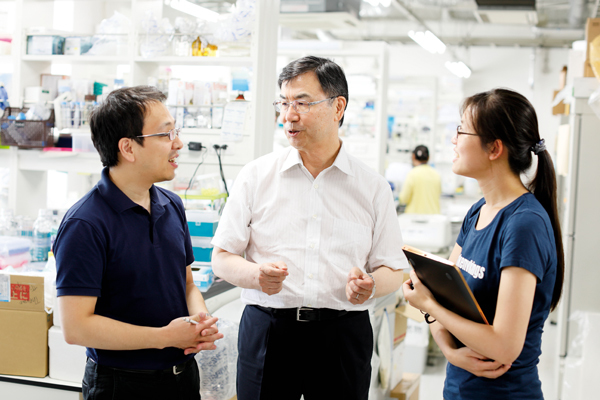
京大の大学院に進み、研究者の道を本格的に歩み出した坂口は、ある日、医学誌で愛知県がんセンターの西塚泰章(やすあき)教授たちの論文「免疫細胞をつくる胸腺を摘出したマウスの実験」を目にした。胸腺で作られるT細胞には、異物を排斥する司令塔のヘルパーT細胞と攻撃するキラーT細胞があり、理屈ではそれらを取り除いてしまえば免疫反応は起きなくなってしまうはずだ。しかし、なぜか結果は逆で、免役反応が過度に表れてさまざまな臓器への攻撃を始めるというものだった。もしかしたら取り除かれたT細胞の中には、攻撃だけではなくブレーキをかける未知の細胞も含まれているのではないか。覗(のぞ)き込んだ深淵に何かがチラッと見えた。
坂口はすぐさま大学院を中退し、愛知県がんセンターの研究生になった。心が動くものがあったらまっしぐら。求めるものに頑固で動きは軽やかな研究者としての姿勢がうかがわれるエピソードである。
しかし坂口にとって不運だったのは、当時は、免疫反応を抑える「抑制性T細胞」なるものが存在するという仮説が提唱され世の注目を浴びたものの、ヒトの疾患との関連が見えないままサイエンスとしての証明ができずに、やっぱり存在しないと否定された時期だったこと。時流に逆行し、まさに研究者が次々下船している船に乗って、真冬の海に乗り出すような出発だったのだ。




























