2 / 22
2
しおりを挟む
果樹園の中の一本道ではない抜け道を使って魔導士の家に着くと魔導士は、小さな家の横に設えたテラスでお茶を楽しむところだった。
「やぁ、ロハンデルト、今日もまた道を外れてきたね。そのうち罰が当たるよ――お茶はいかがかな。カモミールだ」
「ふむ、いただこう」
魔導士が優雅な仕種で湯をポットに注ぐ。芳香が辺りに漂い始め、ロハンデルトと呼ばれた男がテラスの椅子に腰かける。
「七日前と四日前、そして昨日、何か起こっただろう?」
カップに茶を注ぎ分けながら、魔導士のほうから話を切り出してきた。でも……四日前?
「五日前ではないのか?」
ロハンデルト、つまりロファーが問うと
「近頃感じた異変の中で、その三回は人の命の終焉だった。が、ちょっと変だった」
と、魔導士は答えた。
「ちょっと変?」
「無理やりの終焉、あるいは突然の終焉。だからロファーがわが結界の内に現れたとき、この件で来たと直感した」
ふむ……思わずロファーが唸る。この魔導士、どこまで見渡せるのだろう?
魔導士ジゼェーラ通称ジゼル、街の評判に反して並みの魔導士ではないらしい。見た目、まだ若いが年を聞くと『五千年くらい生きてるかな』などと嘯く。これは冗談だと後で判ったが、言っているときの表情は冗談などと思えない。冗談だと言うのが冗談なんじゃないかと未だに思う。
いつだったか、おまえはミステリアスだな、とロファーが言ったら
「神秘王と呼ばれているよ」
と笑った。これも冗談なのか本当なのか、常人のロファーには判断付かない。
死にかけた牛や馬を蘇らせるところは何度も見た。川で溺れた男の子を生き返らせたこともある。
魔導士にだって、死者を復活させられないことは常識だ。なのにそれをやってのけた。
ジゼルにそんなことができるなんて知っているのは、少なくともこの街ではロファーだけだ。そんな術を使うとき、ジゼルは必ず助手以外の人を遠ざける。助手はジゼルが指名したロファーだけだ。そして事後、必ず『他言無用』と釘を刺した。ロファーにしても見たままを他人に話す気になんかなれない。
ジゼルが呪文を唱えだすと、部屋は明るくなったり暗くなったりを繰り返す。そしてジゼルの様相ががらりと変わる。何やら聞き取れない言葉を唱え、対象をじっと見つめ手を翳す。その瞳は赤々と燃え、光を放つ。翳した掌から閃光が迸ることもあり、夢ではないかと疑うほどだ。初めてその光景を見たとき、ロファーは腰を抜かしてしまった。なるほど、巨大なドラゴンを退治したと言うのは事実、長老が言うようにまぐれなんかじゃ決してない。そう確信した。
で、助手のロファーの役目と言えば、元気になった牛や馬、あるいは病人・怪我人をジゼルに代わって持ち主や家族のところに届けることだ。
「間に合ってよかったと魔導士が言っていた」
と伝えることを忘れずに、だ。
たとえ魔導士のところに連れてこられた時に手遅れで死んでいたとしても、生きていたと相手に思わせなくてはならない。死者が蘇ることはないのだ。
そして報酬を受け取って帰る。報酬は時によりかなりの高額だった。が、いつでも相手が払える範囲だったのは、ジゼルが相手を見て金額を決めているからだと、ロファーは思っている。
帰ると魔導士はたいてい眠っていて、あるいは眠ろうとして眠れないのか、どちらにしろ寝床で丸まっていた。
力を使うと体が冷えるらしく、時どきジゼルは
「お願い、暖めて」
ロファーに甘えた。そんな時のジゼルはとてもか弱く見えて、ロファーは従わずにいられなくなる。
寝床に入ってジゼルを包むように抱きしめると、幼子が母親を求めるようにジゼルは抱き返してきた。そんなジゼルを可愛いと、思わずにいられないロファーだ。
ひょっとしたら生気を吸い取られているのかもしれないと恐怖したが、ロファーの健康状態に問題が起こることは、今のところない。
「と、言う訳で、『愛人』の俺がおまえを引っ張り出すよう命じられたのだ」
カモミールティーを啜りながら、現時点で判っていること全てをロファーはジゼルに伝えた。
「魔導士が犯人かどうか見てこい、犯人でなければ犯人捜しを手伝わせろと言われてしまった。まったく、面倒な訴状作成の案件があって、ただでさえ忙しいのに……って言うかさ、犯人かそうじゃないかなんて、どう見極めたらいいんだ?」
「長老のご命令ですか。相変わらずあのおかた、自分勝手だね。それにしてもなんだよ、その『愛人』って。あなたはわたしの助手ではなかった?」
「街で俺はおまえの愛人だってもっぱらの噂さ。ヒモだってヤツもいるけどね――てな訳でさ、ジゼルさんよ、魔導士様よ、なんとかしておくれ」
「わたしのせいで申し訳ない噂を立てられてしまったね。修正の風を流しておくよ、生業はなんだったっけ?――てな訳で、なんて言われても、それはいやです。犯人じゃないなら犯人を探せ、だと? 無料で人を使う気だ。要請にはお応えし兼ねる」
「代書屋さ、なんとか暮らしが困らない程度には儲かってる。いやだなんて、そんなこと言わないでよ、俺を見捨てるのか?」
「代書屋ね。そうそう、文字が書けるし、バターブロンドの髪で好みの顔だから、あなたを助手に選んだのだった。流行過ぎて助手をお願いできなくなったら困るので、そこそこ流行るようにしておくね」
唇を尖らせてフーーッと息を吹くと、額の前でひらひらさせた掌で散らすような動作をした。きっとこれで『愛人』とか『ヒモ』とは言われなくなるのだろう。
「お茶のお替わりはいかが? いらないならさっさと帰って」
どうやらジゼルは説得されたくないらしい。だけどロファーは、説得できずに帰るわけにはいかない。
「お替わり、貰おうじゃないか。美味いお茶だね」
嘘つきめ……ぼそりと言いながら、ジゼルはカップにお茶を足した。
「一口飲んで顔をしかめたのを見逃すわたしと思ったか?」
「ばれてたか……苦くて渋くて香りだけが変に甘い――って、おいっ! 今、何を入れた?」
「そんなお子ちゃまにはハチミツ入れてあげまちょね」
「ばっかやろ……」
言いながら、ロファーは笑いだしてしまった。
「ロファー、あなたの馬鹿笑い、馬小屋にまで届いているよ」
「シンザンがまた笑ってる?」
「いーや怒ってる。馬小屋には近づかないことだな、蹴り殺されるぞ」
ロファーと牡馬のシンザンはもともと折り合いが悪い。ジゼルをロファーに取られてなるものかと、シンザンは思っているようだ。
「それで、五日前じゃないのか、とは?」
急に話が元に戻り、ハチミツが入れば美味くなるのかと口元にカップを持って行ったロファーが、慌ててカップをソーサーに戻す。
「ボブの娘ミーナが家を出たのは五日前の明け方だ。お前の庭の野イチゴを摘みに行くと言って家を出た」
「あぁ。うちの庭のを摘むがいいと教えてやった。野イチゴを摘むにはミーナの家からはうちが一番近い。うちの野イチゴはたくさん実ったが、摘むのは面倒だと思っていたところに野イチゴを摘むミーナの夢が飛び込んで来たから、そう言った」
「おまえ、人の夢まで覗き見るのか」
「波長があえばね。向こうから勝手に飛び込んでくるのさ。あの時はきっとミーナも夢の中で、うちの庭の野イチゴを思い浮かべていたのだろう。ロファー、おまえの夢に入り込んだことはないから安心していい」
疑わしいもんだと思いながら、
「で、ミーナはここに来たのかい」
とロファーが問う。
「ここって、この家? 来てないよ。摘んでいいと夢の中でわたしが言ったことは、彼女の中では本当に起こったことになっている。断りに来なくていいとも言っておいた。朝早くの安眠妨害、お断り」
ミーナと顔を合わすことはなかったが、野イチゴを摘みにわたしの結界にミーナは入っているし、程なくして結界を出ている、とジゼルは言った。眠っていても、自分の結界内で起きたことくらい掌握してるってことらしい。
「そのまま家に帰ったと思っていたのは、わたしの不覚だな」
ミーナが自分の家の戸を開ける音まで追わなかった。そんな必要があるなど思いもしない。
「しかしミーナは家に帰らなかった。どこにいたのだろう?――殺されて命が絶たれたのなら、それは翌日の朝だ」
彼女の命が弾ける衝撃波を感じたのは翌朝だ。そしてそれまで、ジゼルはなんの異変も感じていない。なんの音も聞いていない。
「つまり、なんだ、行方不明になってから翌日の朝までミーナは無事だった。何一つ変化がなかった。そういうことか」
ロファーが唸る。
「うん、しかも助けを求めるなんてこともなかった」
求めていれば、わたしが気付かないはずはないとジゼルは言った。
確かにそうだろうとロファーも思う。男の子が川で溺れたときも、突然頭上にやってきたツグミが、目の前に紙片を落とした。紙片には『川へ急げ、ブランが溺れている 連れてこい』とジゼルの字があった。
驚いて、大急ぎで駆けつけると、ジゼルが言う通りブランが川に落ちたと、子供たちが騒ぎ、数人の大人も集まってきていた。ロファーは考える間もなく川に飛び込んで、ブランを岸にあげた。ブランはもう、息をしていなかったが、ジゼルは連れてこいと言っている。
集まって来た街人たちに『魔導士のところに連れて行く』とだけ言ってブランを抱えてロファーは走った。結果、ブランは息を吹き返し、家族の元に戻された。
似たようなことが何度もあった。『意識に飛び込んでくる』とジゼルは言うが、それはそれで、気が休まる時がなかろうとロファーは思う。そんな能力は絶対持ちたくないと思っている。
そんなロファーと打って変わり、ジゼルはいたって事務的だ。
「落命の瞬間の波動は感じたが、ロファーが言うように誰かに殺されたのならば直前に恐怖を感じているだろうに、それはちっとも届かなかった」
事も無げに言う。
「恐怖は強い感情だ。まして命を奪われるかもしれぬ恐怖は底知れず強いはず。それをわたしが感じられなかったということは、三人とも死に際でさえも自分が死ぬとは思っていなかった、ということだ」
「じゃ、殺されたわけではない、と?」
「いーや、恐怖を感じる間もなく殺された、ということだよ」
ニヤリとジゼルが笑う。
「それと『残忍な手口』……目玉を抉りだす魔虫はいるにはいるが、この辺では冬の虫だ。爽やかな風が青葉を揺らす今時期に出てくるのは奇怪しいし、そいつなら目を抉った後、耳と鼻も抉る。当然出血も並大抵じゃない」
つい想像してしまい、やっと吐き気を抑えているロファーに気づかず、ジゼルはさらにこう続けた。
「だから、虫ではない。犯人は人間だ」
ここでやっとロファーの様子に気が付き、背を撫で始める。
「納まらないようなら、梅酒を少し上げよう。楽になる――人間だとしたら、そんなことができるヤツを探せばいい。わたし以外のね」
「探すったって、どうやって?」
「まずはもっとヒントがほしいな。明日、ボブにあって、こう聞いてみて。それと炭屋のジェシカ姐さん、これは体調次第だな。明日、牛飼いのマーシャに薬を頼むから、いくらかよくなっているとは思うけど聞けたらでいい。レイモンのところは娘のマナミにも話を聞いてきて。頼んだよロファー」
そうと決まれば、こんな話は終わりにしよう、梅酒を出すかい? 夕飯までゆっくりしてるといい、もちろん食べてくよね。誰かと一緒に食事をするのは久しぶり、ちょうど珍しい食材が手に入ったところなんだ。きっと、凄く美味しいよ……
ジゼルの機嫌は悪くないようだ。そして――
とりあえずジゼルは犯人ではない。そして犯人探しに協力してくれるようだ。ほっと胸を撫でおろすロファーだった。
「やぁ、ロハンデルト、今日もまた道を外れてきたね。そのうち罰が当たるよ――お茶はいかがかな。カモミールだ」
「ふむ、いただこう」
魔導士が優雅な仕種で湯をポットに注ぐ。芳香が辺りに漂い始め、ロハンデルトと呼ばれた男がテラスの椅子に腰かける。
「七日前と四日前、そして昨日、何か起こっただろう?」
カップに茶を注ぎ分けながら、魔導士のほうから話を切り出してきた。でも……四日前?
「五日前ではないのか?」
ロハンデルト、つまりロファーが問うと
「近頃感じた異変の中で、その三回は人の命の終焉だった。が、ちょっと変だった」
と、魔導士は答えた。
「ちょっと変?」
「無理やりの終焉、あるいは突然の終焉。だからロファーがわが結界の内に現れたとき、この件で来たと直感した」
ふむ……思わずロファーが唸る。この魔導士、どこまで見渡せるのだろう?
魔導士ジゼェーラ通称ジゼル、街の評判に反して並みの魔導士ではないらしい。見た目、まだ若いが年を聞くと『五千年くらい生きてるかな』などと嘯く。これは冗談だと後で判ったが、言っているときの表情は冗談などと思えない。冗談だと言うのが冗談なんじゃないかと未だに思う。
いつだったか、おまえはミステリアスだな、とロファーが言ったら
「神秘王と呼ばれているよ」
と笑った。これも冗談なのか本当なのか、常人のロファーには判断付かない。
死にかけた牛や馬を蘇らせるところは何度も見た。川で溺れた男の子を生き返らせたこともある。
魔導士にだって、死者を復活させられないことは常識だ。なのにそれをやってのけた。
ジゼルにそんなことができるなんて知っているのは、少なくともこの街ではロファーだけだ。そんな術を使うとき、ジゼルは必ず助手以外の人を遠ざける。助手はジゼルが指名したロファーだけだ。そして事後、必ず『他言無用』と釘を刺した。ロファーにしても見たままを他人に話す気になんかなれない。
ジゼルが呪文を唱えだすと、部屋は明るくなったり暗くなったりを繰り返す。そしてジゼルの様相ががらりと変わる。何やら聞き取れない言葉を唱え、対象をじっと見つめ手を翳す。その瞳は赤々と燃え、光を放つ。翳した掌から閃光が迸ることもあり、夢ではないかと疑うほどだ。初めてその光景を見たとき、ロファーは腰を抜かしてしまった。なるほど、巨大なドラゴンを退治したと言うのは事実、長老が言うようにまぐれなんかじゃ決してない。そう確信した。
で、助手のロファーの役目と言えば、元気になった牛や馬、あるいは病人・怪我人をジゼルに代わって持ち主や家族のところに届けることだ。
「間に合ってよかったと魔導士が言っていた」
と伝えることを忘れずに、だ。
たとえ魔導士のところに連れてこられた時に手遅れで死んでいたとしても、生きていたと相手に思わせなくてはならない。死者が蘇ることはないのだ。
そして報酬を受け取って帰る。報酬は時によりかなりの高額だった。が、いつでも相手が払える範囲だったのは、ジゼルが相手を見て金額を決めているからだと、ロファーは思っている。
帰ると魔導士はたいてい眠っていて、あるいは眠ろうとして眠れないのか、どちらにしろ寝床で丸まっていた。
力を使うと体が冷えるらしく、時どきジゼルは
「お願い、暖めて」
ロファーに甘えた。そんな時のジゼルはとてもか弱く見えて、ロファーは従わずにいられなくなる。
寝床に入ってジゼルを包むように抱きしめると、幼子が母親を求めるようにジゼルは抱き返してきた。そんなジゼルを可愛いと、思わずにいられないロファーだ。
ひょっとしたら生気を吸い取られているのかもしれないと恐怖したが、ロファーの健康状態に問題が起こることは、今のところない。
「と、言う訳で、『愛人』の俺がおまえを引っ張り出すよう命じられたのだ」
カモミールティーを啜りながら、現時点で判っていること全てをロファーはジゼルに伝えた。
「魔導士が犯人かどうか見てこい、犯人でなければ犯人捜しを手伝わせろと言われてしまった。まったく、面倒な訴状作成の案件があって、ただでさえ忙しいのに……って言うかさ、犯人かそうじゃないかなんて、どう見極めたらいいんだ?」
「長老のご命令ですか。相変わらずあのおかた、自分勝手だね。それにしてもなんだよ、その『愛人』って。あなたはわたしの助手ではなかった?」
「街で俺はおまえの愛人だってもっぱらの噂さ。ヒモだってヤツもいるけどね――てな訳でさ、ジゼルさんよ、魔導士様よ、なんとかしておくれ」
「わたしのせいで申し訳ない噂を立てられてしまったね。修正の風を流しておくよ、生業はなんだったっけ?――てな訳で、なんて言われても、それはいやです。犯人じゃないなら犯人を探せ、だと? 無料で人を使う気だ。要請にはお応えし兼ねる」
「代書屋さ、なんとか暮らしが困らない程度には儲かってる。いやだなんて、そんなこと言わないでよ、俺を見捨てるのか?」
「代書屋ね。そうそう、文字が書けるし、バターブロンドの髪で好みの顔だから、あなたを助手に選んだのだった。流行過ぎて助手をお願いできなくなったら困るので、そこそこ流行るようにしておくね」
唇を尖らせてフーーッと息を吹くと、額の前でひらひらさせた掌で散らすような動作をした。きっとこれで『愛人』とか『ヒモ』とは言われなくなるのだろう。
「お茶のお替わりはいかが? いらないならさっさと帰って」
どうやらジゼルは説得されたくないらしい。だけどロファーは、説得できずに帰るわけにはいかない。
「お替わり、貰おうじゃないか。美味いお茶だね」
嘘つきめ……ぼそりと言いながら、ジゼルはカップにお茶を足した。
「一口飲んで顔をしかめたのを見逃すわたしと思ったか?」
「ばれてたか……苦くて渋くて香りだけが変に甘い――って、おいっ! 今、何を入れた?」
「そんなお子ちゃまにはハチミツ入れてあげまちょね」
「ばっかやろ……」
言いながら、ロファーは笑いだしてしまった。
「ロファー、あなたの馬鹿笑い、馬小屋にまで届いているよ」
「シンザンがまた笑ってる?」
「いーや怒ってる。馬小屋には近づかないことだな、蹴り殺されるぞ」
ロファーと牡馬のシンザンはもともと折り合いが悪い。ジゼルをロファーに取られてなるものかと、シンザンは思っているようだ。
「それで、五日前じゃないのか、とは?」
急に話が元に戻り、ハチミツが入れば美味くなるのかと口元にカップを持って行ったロファーが、慌ててカップをソーサーに戻す。
「ボブの娘ミーナが家を出たのは五日前の明け方だ。お前の庭の野イチゴを摘みに行くと言って家を出た」
「あぁ。うちの庭のを摘むがいいと教えてやった。野イチゴを摘むにはミーナの家からはうちが一番近い。うちの野イチゴはたくさん実ったが、摘むのは面倒だと思っていたところに野イチゴを摘むミーナの夢が飛び込んで来たから、そう言った」
「おまえ、人の夢まで覗き見るのか」
「波長があえばね。向こうから勝手に飛び込んでくるのさ。あの時はきっとミーナも夢の中で、うちの庭の野イチゴを思い浮かべていたのだろう。ロファー、おまえの夢に入り込んだことはないから安心していい」
疑わしいもんだと思いながら、
「で、ミーナはここに来たのかい」
とロファーが問う。
「ここって、この家? 来てないよ。摘んでいいと夢の中でわたしが言ったことは、彼女の中では本当に起こったことになっている。断りに来なくていいとも言っておいた。朝早くの安眠妨害、お断り」
ミーナと顔を合わすことはなかったが、野イチゴを摘みにわたしの結界にミーナは入っているし、程なくして結界を出ている、とジゼルは言った。眠っていても、自分の結界内で起きたことくらい掌握してるってことらしい。
「そのまま家に帰ったと思っていたのは、わたしの不覚だな」
ミーナが自分の家の戸を開ける音まで追わなかった。そんな必要があるなど思いもしない。
「しかしミーナは家に帰らなかった。どこにいたのだろう?――殺されて命が絶たれたのなら、それは翌日の朝だ」
彼女の命が弾ける衝撃波を感じたのは翌朝だ。そしてそれまで、ジゼルはなんの異変も感じていない。なんの音も聞いていない。
「つまり、なんだ、行方不明になってから翌日の朝までミーナは無事だった。何一つ変化がなかった。そういうことか」
ロファーが唸る。
「うん、しかも助けを求めるなんてこともなかった」
求めていれば、わたしが気付かないはずはないとジゼルは言った。
確かにそうだろうとロファーも思う。男の子が川で溺れたときも、突然頭上にやってきたツグミが、目の前に紙片を落とした。紙片には『川へ急げ、ブランが溺れている 連れてこい』とジゼルの字があった。
驚いて、大急ぎで駆けつけると、ジゼルが言う通りブランが川に落ちたと、子供たちが騒ぎ、数人の大人も集まってきていた。ロファーは考える間もなく川に飛び込んで、ブランを岸にあげた。ブランはもう、息をしていなかったが、ジゼルは連れてこいと言っている。
集まって来た街人たちに『魔導士のところに連れて行く』とだけ言ってブランを抱えてロファーは走った。結果、ブランは息を吹き返し、家族の元に戻された。
似たようなことが何度もあった。『意識に飛び込んでくる』とジゼルは言うが、それはそれで、気が休まる時がなかろうとロファーは思う。そんな能力は絶対持ちたくないと思っている。
そんなロファーと打って変わり、ジゼルはいたって事務的だ。
「落命の瞬間の波動は感じたが、ロファーが言うように誰かに殺されたのならば直前に恐怖を感じているだろうに、それはちっとも届かなかった」
事も無げに言う。
「恐怖は強い感情だ。まして命を奪われるかもしれぬ恐怖は底知れず強いはず。それをわたしが感じられなかったということは、三人とも死に際でさえも自分が死ぬとは思っていなかった、ということだ」
「じゃ、殺されたわけではない、と?」
「いーや、恐怖を感じる間もなく殺された、ということだよ」
ニヤリとジゼルが笑う。
「それと『残忍な手口』……目玉を抉りだす魔虫はいるにはいるが、この辺では冬の虫だ。爽やかな風が青葉を揺らす今時期に出てくるのは奇怪しいし、そいつなら目を抉った後、耳と鼻も抉る。当然出血も並大抵じゃない」
つい想像してしまい、やっと吐き気を抑えているロファーに気づかず、ジゼルはさらにこう続けた。
「だから、虫ではない。犯人は人間だ」
ここでやっとロファーの様子に気が付き、背を撫で始める。
「納まらないようなら、梅酒を少し上げよう。楽になる――人間だとしたら、そんなことができるヤツを探せばいい。わたし以外のね」
「探すったって、どうやって?」
「まずはもっとヒントがほしいな。明日、ボブにあって、こう聞いてみて。それと炭屋のジェシカ姐さん、これは体調次第だな。明日、牛飼いのマーシャに薬を頼むから、いくらかよくなっているとは思うけど聞けたらでいい。レイモンのところは娘のマナミにも話を聞いてきて。頼んだよロファー」
そうと決まれば、こんな話は終わりにしよう、梅酒を出すかい? 夕飯までゆっくりしてるといい、もちろん食べてくよね。誰かと一緒に食事をするのは久しぶり、ちょうど珍しい食材が手に入ったところなんだ。きっと、凄く美味しいよ……
ジゼルの機嫌は悪くないようだ。そして――
とりあえずジゼルは犯人ではない。そして犯人探しに協力してくれるようだ。ほっと胸を撫でおろすロファーだった。
11
あなたにおすすめの小説

神様の忘れ物
mizuno sei
ファンタジー
仕事中に急死した三十二歳の独身OLが、前世の記憶を持ったまま異世界に転生した。
わりとお気楽で、ポジティブな主人公が、異世界で懸命に生きる中で巻き起こされる、笑いあり、涙あり(?)の珍騒動記。

わたくしが社交界を騒がす『毒女』です~旦那様、この結婚は離婚約だったはずですが?
澤谷弥(さわたに わたる)
恋愛
※完結しました。
離婚約――それは離婚を約束した結婚のこと。
王太子アルバートの婚約披露パーティーで目にあまる行動をした、社交界でも噂の毒女クラリスは、辺境伯ユージーンと結婚するようにと国王から命じられる。
アルバートの側にいたかったクラリスであるが、国王からの命令である以上、この結婚は断れない。
断れないのはユージーンも同じだったようで、二人は二年後の離婚を前提として結婚を受け入れた――はずなのだが。
毒女令嬢クラリスと女に縁のない辺境伯ユージーンの、離婚前提の結婚による空回り恋愛物語。
※以前、短編で書いたものを長編にしたものです。
※蛇が出てきますので、苦手な方はお気をつけください。

帰国した王子の受難
ユウキ
恋愛
庶子である第二王子は、立場や情勢やら諸々を鑑みて早々に隣国へと無期限遊学に出た。そうして年月が経ち、そろそろ兄(第一王子)が立太子する頃かと、感慨深く想っていた頃に突然届いた帰還命令。
取り急ぎ舞い戻った祖国で見たのは、修羅場であった。

華都のローズマリー
みるくてぃー
ファンタジー
ひょんな事から前世の記憶が蘇った私、アリス・デュランタン。意地悪な義兄に『超』貧乏騎士爵家を追い出され、無一文の状態で妹と一緒に王都へ向かうが、そこは若い女性には厳しすぎる世界。一時は妹の為に身売りの覚悟をするも、気づけば何故か王都で人気のスィーツショップを経営することに。えっ、私この世界のお金の単位って全然わからないんですけど!?これは初めて見たお金が金貨の山だったという金銭感覚ゼロ、ハチャメチャ少女のラブ?コメディな物語。
新たなお仕事シリーズ第一弾、不定期掲載にて始めます!

転生小説家の華麗なる円満離婚計画
鈴木かなえ
ファンタジー
キルステン伯爵家の令嬢として生を受けたクラリッサには、日本人だった前世の記憶がある。
両親と弟には疎まれているクラリッサだが、異母妹マリアンネとその兄エルヴィンと三人で仲良く育ち、前世の記憶を利用して小説家として密かに活躍していた。
ある時、夜会に連れ出されたクラリッサは、弟にハメられて見知らぬ男に襲われそうになる。
その男を返り討ちにして、逃げ出そうとしたところで美貌の貴公子ヘンリックと出会った。
逞しく想像力豊かなクラリッサと、その家族三人の物語です。

実家を没落させられ恋人も奪われたので呪っていたのですが、記憶喪失になって呪わなくなった途端、相手が自滅していきました
麻宮デコ@SS短編
恋愛
「どうぞ、あの人たちに罰を与えてください。この身はどうなっても構いません」
ラルド侯爵家のドリィに自分の婚約者フィンセントを奪われ、実家すらも没落においやられてしまった伯爵家令嬢のシャナ。
毎日のように呪っていたところ、ラルド家の馬車が起こした事故に巻き込まれて記憶を失ってしまった。
しかし恨んでいる事実を忘れてしまったため、抵抗なく相手の懐に入りこむことができてしまい、そして別に恨みを晴らそうと思っているわけでもないのに、なぜか呪っていた相手たちは勝手に自滅していってしまうことになっていった。
全6話
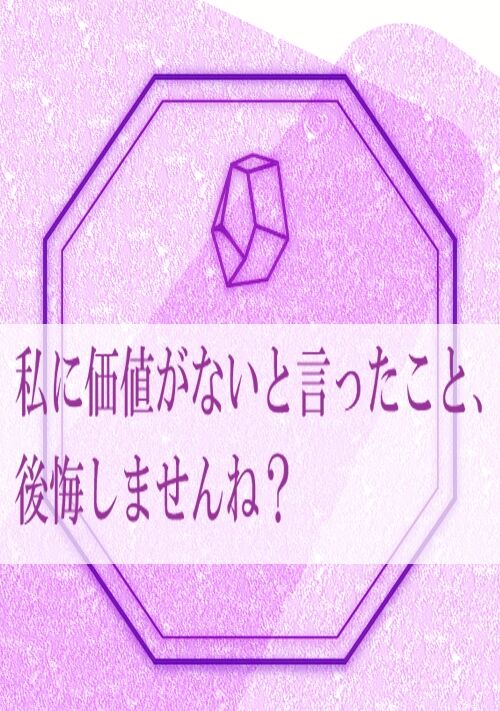
私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね?
みこと。
恋愛
鉛色の髪と目を持つクローディアは"鉱石姫"と呼ばれ、婚約者ランバートからおざなりに扱われていた。
「俺には"宝石姫"であるタバサのほうが相応しい」そう言ってランバートは、新年祭のパートナーに、クローディアではなくタバサを伴う。
(あんなヤツ、こっちから婚約破棄してやりたいのに!)
現代日本にはなかった身分差のせいで、伯爵令嬢クローディアは、侯爵家のランバートに逆らえない。
そう、クローディアは転生者だった。現代知識で鉱石を扱い、カイロはじめ防寒具をドレス下に仕込む彼女は、冷えに苦しむ他国の王女リアナを助けるが──。
なんとリアナ王女の正体は、王子リアンで?
この出会いが、クローディアに新しい道を拓く!
※小説家になろう様でも「私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね? 〜不実な婚約者を見限って。冷え性令嬢は、熱愛を希望します」というタイトルで掲載しています。

精霊に愛される(呪いにもにた愛)少女~全属性の加護を貰う~
如月花恋
ファンタジー
今この世界にはたくさんの精霊がいる
その精霊達から生まれた瞬間に加護を貰う
稀に2つ以上の属性の2体の精霊から加護を貰うことがある
まぁ大体は親の属性を受け継ぐのだが…
だが…全属性の加護を貰うなど不可能とされてきた…
そんな時に生まれたシャルロッテ
全属性の加護を持つ少女
いったいこれからどうなるのか…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















