42 / 50
38
しおりを挟む
小さな口でうどんを啜るゆえを視界の端に捉えながら食べるジェノベーゼは味がしなかった。亨の向かいでペスカトーレを巻く沙彩も「味が薄い」と言ったきり黙っているので、二人の間は周囲の喧騒から隔絶されたように深閑としている。
ゆえと誠が、額があたりそうな距離で同じスマホの画面を見ている。二人の背景になっている薄ら寒い青空にすら苛々して、亨が頬の裏側を噛むと、沙彩が、
「声掛ければいいじゃないですか」
と尖りのある声で言った。
「偶然会ったことにすればいいじゃないですか」
「それでどうするんだ。俺には二人でいるのをとやかく言う権利はないんだろ?」
沙彩を責めるような口調になったことに亨は気付かなかなかった。
彼女はぼんやりと仲良さげなゆえと誠を眺める。どこからか子どもの泣き声が聞こえる。泣きたいのは目の前の男も同じだろうと、沙彩は自覚のない彼に代わってうら寂しい気持ちになった。
ふいに亨がコートから煙草の箱とオイルライターを取り出して腰を浮かせた。
「ごめん、一本吸ってきていい?」
沙彩を一人にさせる懸念はあったが、この場にいることへの苦衷に彼は堪えかねた。
亨は喫煙常習者ではないが、鬱屈とした気分にとどめを刺す手段として煙草を用いることは時折ある。吸っている姿を見たことが無い沙彩に「先生煙草吸う人でしたっけ?」と疑惑の目を向けられながら「たまに」と口元だけで笑って亨は席から静かに離れた。
フードコートの隅にある喫煙室には数名の男性がいて、一様にスマホを弄りながら煙を立ち上らせていた。換気扇が回っていても淀み濁った空気が衣服に纏わりつく。溜息を誤魔化すように吐き出した紫煙が他人の呼気と混ざるのを見るとますます気分が悪くなった。
吸い込んだニコチンの重さに目が回る。
「先輩たち行っちゃいましたけど」
二人分のトレーを片付けて待っていた沙彩が、亨を見上げて平坦な口調で言った。
一瞬立ち眩みを起こした亨がよろけてテーブルに手をつき呻く。
「ほら、無理して吸うから」
「ほんとにたまには吸うんだよ。あーこれからどうしようかなあ」
「どうでもいいですけど。そろそろ『ストーンレンジャーショー』始まるので観に行ってきてもいいですか?」
「ああ、そういえばそうだった。じゃあ終わったら連絡して。俺あの人たち探すから」
「それなんですけど、少なくとも赤木さんはそこにいると思いますよ」
「何で分かるの?」
テーブルを避けながらフードコートを出て、人通りの多い通路を隣り合って歩く。アジア系雑貨を扱う店から甘いお香の匂いが流れてきて、沙彩は足を止めた。
「あの人も特撮好きらしいんで」
沙彩がデフォルメされたゾウのぬいぐるみを手に取ってひっくり返した。足の間には何もついていない。――それを確認したかったのだろうと亨は思う。
「藍澤さんと趣味合うんじゃないの」
亨も彼女に倣って隣のキリンを逆さにする。
「同じ趣味のオタクはみんな気が合うなんて思わないでくださいよ」
「そんなもんか」
そんなもんです、と答えながらぬいぐるみを手放し、沙彩はエレベーターを二階ぶん降りた。
イベント広場にはすでに人だかりが出来ていて、ステージの中心には子どもが、そしてその周りを大人が囲み、ヒーローを待っていた。大音量で流れている曲――恐らく主題歌――に臆した亨は、一転して目を輝かせ始めた沙彩を送り出して近くのカフェでホットコーヒーを注文した。
仕切りが無いせいで音楽が遮られず、大きな音が耳の中で反響する。
三十分のショーをここで耐える自信は無かったが、別の場所に移動するのも億劫だった。
黒い水面にミルクとスティックシュガーを二本入れて、ふうふうと息を吹きかけると、香ばしい匂いがふわりと香る。火傷しないように控えめに口に含むと、溶けた砂糖の甘さが味覚を揉みほぐし、緊張や疲労で凝り固まっていた心が柔らかくなった気がした。
一人用のソファーにだらりと身を任せて、開演の歓声を聞くともなしに聞いていた。男性の声よりも、若手俳優目当てに放送を見ているのであろう女性ファンの声のほうが目立つ。
騒音のせいか店内にいる客はまばらだった。注文を待つ若い女性の視線が刺さる。煩わしくて目を伏せたとき。
ソファーの横を、ベージュのコートが通り過ぎた。
亨は引かれたように顔を上げ、見開いた双眸でその後ろ姿を追った。
ウェーブが掛かった長い髪。見覚えのあるコート。流行外れのブーツ。
一番端のテーブルに座ってソーサーを置く白い手。行儀正しく揃えられた爪先。
亨は立ち上がった。
広場のほうから盛大な拍手が上がる。ヒーローの登場の文句が響き渡り、ひそやかに流れていたカフェの音楽が掻き消える。世界中の音が失せ、自分以外の人間が透明になったような錯覚を覚えながら、亨は彼女のもとへ歩を進めた。たった数歩がその何倍も遠く感じる。肩を叩こうとして、思いとどまった。一瞬考えた亨は、彼女の座る椅子の傍で片膝をついた。その気配を感じ取り、彼女が顔を向ける。
それが亨だと気付いたゆえは、驚いた様子で中途半端に口を開けた。
「お買い物?」
亨は微笑んだが、頬が強張った気がした。
「は、はい。まさかお会いできると思わず、ビックリしました」
「うん、驚かせるだろうなと思った」
膝をついたままの亨に席を勧めて、ゆえは温和な笑顔を零した。
「お一人ですか?」
「あー……いや、友達と一緒」
それは楽しいですね、とゆえは置いていたカップを両手で包む。亨は気まずさを感じてコーヒーを啜った。「あなたは?」とは訊けなかった。その問いは自傷のように痛みを生む気がした。
ショーのつんざくような音響が会話の間を埋める。
親しい人と会えたことを喜ぶ無垢な子どものような彼女の表情に、亨は安堵と不安と、そしてある欲望が芽生えたのを亨は感じた。
思わずゆえから視線を外す。
見透かされることが恐かった。
ゆえと二人でいられることに喜悦し、彼女が他の男のもとに帰っていく未来を悲嘆する。自分の情緒を乱す原因になっているそれは、――――幼子の渇望とよく似ている。
自分のものにしたいという、独占欲。
亨は俯いたまま、わざと思考を遮るように子どもたちが叫んでいるヒーローの名前に耳を傾けた。
――頑張れ!○○○レッド!
ゆえと誠が、額があたりそうな距離で同じスマホの画面を見ている。二人の背景になっている薄ら寒い青空にすら苛々して、亨が頬の裏側を噛むと、沙彩が、
「声掛ければいいじゃないですか」
と尖りのある声で言った。
「偶然会ったことにすればいいじゃないですか」
「それでどうするんだ。俺には二人でいるのをとやかく言う権利はないんだろ?」
沙彩を責めるような口調になったことに亨は気付かなかなかった。
彼女はぼんやりと仲良さげなゆえと誠を眺める。どこからか子どもの泣き声が聞こえる。泣きたいのは目の前の男も同じだろうと、沙彩は自覚のない彼に代わってうら寂しい気持ちになった。
ふいに亨がコートから煙草の箱とオイルライターを取り出して腰を浮かせた。
「ごめん、一本吸ってきていい?」
沙彩を一人にさせる懸念はあったが、この場にいることへの苦衷に彼は堪えかねた。
亨は喫煙常習者ではないが、鬱屈とした気分にとどめを刺す手段として煙草を用いることは時折ある。吸っている姿を見たことが無い沙彩に「先生煙草吸う人でしたっけ?」と疑惑の目を向けられながら「たまに」と口元だけで笑って亨は席から静かに離れた。
フードコートの隅にある喫煙室には数名の男性がいて、一様にスマホを弄りながら煙を立ち上らせていた。換気扇が回っていても淀み濁った空気が衣服に纏わりつく。溜息を誤魔化すように吐き出した紫煙が他人の呼気と混ざるのを見るとますます気分が悪くなった。
吸い込んだニコチンの重さに目が回る。
「先輩たち行っちゃいましたけど」
二人分のトレーを片付けて待っていた沙彩が、亨を見上げて平坦な口調で言った。
一瞬立ち眩みを起こした亨がよろけてテーブルに手をつき呻く。
「ほら、無理して吸うから」
「ほんとにたまには吸うんだよ。あーこれからどうしようかなあ」
「どうでもいいですけど。そろそろ『ストーンレンジャーショー』始まるので観に行ってきてもいいですか?」
「ああ、そういえばそうだった。じゃあ終わったら連絡して。俺あの人たち探すから」
「それなんですけど、少なくとも赤木さんはそこにいると思いますよ」
「何で分かるの?」
テーブルを避けながらフードコートを出て、人通りの多い通路を隣り合って歩く。アジア系雑貨を扱う店から甘いお香の匂いが流れてきて、沙彩は足を止めた。
「あの人も特撮好きらしいんで」
沙彩がデフォルメされたゾウのぬいぐるみを手に取ってひっくり返した。足の間には何もついていない。――それを確認したかったのだろうと亨は思う。
「藍澤さんと趣味合うんじゃないの」
亨も彼女に倣って隣のキリンを逆さにする。
「同じ趣味のオタクはみんな気が合うなんて思わないでくださいよ」
「そんなもんか」
そんなもんです、と答えながらぬいぐるみを手放し、沙彩はエレベーターを二階ぶん降りた。
イベント広場にはすでに人だかりが出来ていて、ステージの中心には子どもが、そしてその周りを大人が囲み、ヒーローを待っていた。大音量で流れている曲――恐らく主題歌――に臆した亨は、一転して目を輝かせ始めた沙彩を送り出して近くのカフェでホットコーヒーを注文した。
仕切りが無いせいで音楽が遮られず、大きな音が耳の中で反響する。
三十分のショーをここで耐える自信は無かったが、別の場所に移動するのも億劫だった。
黒い水面にミルクとスティックシュガーを二本入れて、ふうふうと息を吹きかけると、香ばしい匂いがふわりと香る。火傷しないように控えめに口に含むと、溶けた砂糖の甘さが味覚を揉みほぐし、緊張や疲労で凝り固まっていた心が柔らかくなった気がした。
一人用のソファーにだらりと身を任せて、開演の歓声を聞くともなしに聞いていた。男性の声よりも、若手俳優目当てに放送を見ているのであろう女性ファンの声のほうが目立つ。
騒音のせいか店内にいる客はまばらだった。注文を待つ若い女性の視線が刺さる。煩わしくて目を伏せたとき。
ソファーの横を、ベージュのコートが通り過ぎた。
亨は引かれたように顔を上げ、見開いた双眸でその後ろ姿を追った。
ウェーブが掛かった長い髪。見覚えのあるコート。流行外れのブーツ。
一番端のテーブルに座ってソーサーを置く白い手。行儀正しく揃えられた爪先。
亨は立ち上がった。
広場のほうから盛大な拍手が上がる。ヒーローの登場の文句が響き渡り、ひそやかに流れていたカフェの音楽が掻き消える。世界中の音が失せ、自分以外の人間が透明になったような錯覚を覚えながら、亨は彼女のもとへ歩を進めた。たった数歩がその何倍も遠く感じる。肩を叩こうとして、思いとどまった。一瞬考えた亨は、彼女の座る椅子の傍で片膝をついた。その気配を感じ取り、彼女が顔を向ける。
それが亨だと気付いたゆえは、驚いた様子で中途半端に口を開けた。
「お買い物?」
亨は微笑んだが、頬が強張った気がした。
「は、はい。まさかお会いできると思わず、ビックリしました」
「うん、驚かせるだろうなと思った」
膝をついたままの亨に席を勧めて、ゆえは温和な笑顔を零した。
「お一人ですか?」
「あー……いや、友達と一緒」
それは楽しいですね、とゆえは置いていたカップを両手で包む。亨は気まずさを感じてコーヒーを啜った。「あなたは?」とは訊けなかった。その問いは自傷のように痛みを生む気がした。
ショーのつんざくような音響が会話の間を埋める。
親しい人と会えたことを喜ぶ無垢な子どものような彼女の表情に、亨は安堵と不安と、そしてある欲望が芽生えたのを亨は感じた。
思わずゆえから視線を外す。
見透かされることが恐かった。
ゆえと二人でいられることに喜悦し、彼女が他の男のもとに帰っていく未来を悲嘆する。自分の情緒を乱す原因になっているそれは、――――幼子の渇望とよく似ている。
自分のものにしたいという、独占欲。
亨は俯いたまま、わざと思考を遮るように子どもたちが叫んでいるヒーローの名前に耳を傾けた。
――頑張れ!○○○レッド!
0
あなたにおすすめの小説

甘すぎるドクターへ。どうか手加減して下さい。
海咲雪
恋愛
その日、新幹線の隣の席に疲れて寝ている男性がいた。
ただそれだけのはずだったのに……その日、私の世界に甘さが加わった。
「案外、本当に君以外いないかも」
「いいの? こんな可愛いことされたら、本当にもう逃してあげられないけど」
「もう奏葉の許可なしに近づいたりしない。だから……近づく前に奏葉に聞くから、ちゃんと許可を出してね」
そのドクターの甘さは手加減を知らない。
【登場人物】
末永 奏葉[すえなが かなは]・・・25歳。普通の会社員。気を遣い過ぎてしまう性格。
恩田 時哉[おんだ ときや]・・・27歳。医者。奏葉をからかう時もあるのに、甘すぎる?
田代 有我[たしろ ゆうが]・・・25歳。奏葉の同期。テキトーな性格だが、奏葉の変化には鋭い?
【作者に医療知識はありません。恋愛小説として楽しんで頂ければ幸いです!】


虚弱なヤクザの駆け込み寺
菅井群青
恋愛
突然ドアが開いたとおもったらヤクザが抱えられてやってきた。
「今すぐ立てるようにしろ、さもなければ──」
「脅してる場合ですか?」
ギックリ腰ばかりを繰り返すヤクザの組長と、治療の相性が良かったために気に入られ、ヤクザ御用達の鍼灸院と化してしまった院に軟禁されてしまった女の話。
※なろう、カクヨムでも投稿

お兄ちゃんはお兄ちゃんだけど、お兄ちゃんなのにお兄ちゃんじゃない!?
すずなり。
恋愛
幼いころ、母に施設に預けられた鈴(すず)。
お母さん「病気を治して迎えにくるから待ってて?」
その母は・・迎えにくることは無かった。
代わりに迎えに来た『父』と『兄』。
私の引き取り先は『本当の家』だった。
お父さん「鈴の家だよ?」
鈴「私・・一緒に暮らしていいんでしょうか・・。」
新しい家で始まる生活。
でも私は・・・お母さんの病気の遺伝子を受け継いでる・・・。
鈴「うぁ・・・・。」
兄「鈴!?」
倒れることが多くなっていく日々・・・。
そんな中でも『恋』は私の都合なんて考えてくれない。
『もう・・妹にみれない・・・。』
『お兄ちゃん・・・。』
「お前のこと、施設にいたころから好きだった・・・!」
「ーーーーっ!」
※本編には病名や治療法、薬などいろいろ出てきますが、全て想像の世界のお話です。現実世界とは一切関係ありません。
※コメントや感想などは受け付けることはできません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
※孤児、脱字などチェックはしてますが漏れもあります。ご容赦ください。
※表現不足なども重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけたら幸いです。(それはもう『へぇー・・』ぐらいに。)

ハイスぺ幼馴染の執着過剰愛~30までに相手がいなかったら、結婚しようと言ったから~
cheeery
恋愛
パイロットのエリート幼馴染とワケあって同棲することになった私。
同棲はかれこれもう7年目。
お互いにいい人がいたら解消しようと約束しているのだけど……。
合コンは撃沈。連絡さえ来ない始末。
焦るものの、幼なじみ隼人との生活は、なんの不満もなく……っというよりも、至極の生活だった。
何かあったら話も聞いてくれるし、なぐさめてくれる。
美味しい料理に、髪を乾かしてくれたり、買い物に連れ出してくれたり……しかも家賃はいらないと受け取ってもくれない。
私……こんなに甘えっぱなしでいいのかな?
そしてわたしの30歳の誕生日。
「美羽、お誕生日おめでとう。結婚しようか」
「なに言ってるの?」
優しかったはずの隼人が豹変。
「30になってお互いに相手がいなかったら、結婚しようって美羽が言ったんだよね?」
彼の秘密を知ったら、もう逃げることは出来ない。
「絶対に逃がさないよ?」

ズボラ上司の甘い罠
松丹子
恋愛
小松春菜の上司、小野田は、無精髭に瓶底眼鏡、乱れた髪にゆるいネクタイ。
仕事はできる人なのに、あまりにももったいない!
かと思えば、イメチェンして来た課長はタイプど真ん中。
やばい。見惚れる。一体これで仕事になるのか?
上司の魅力から逃れようとしながら逃れきれず溺愛される、自分に自信のないフツーの女子の話。になる予定。
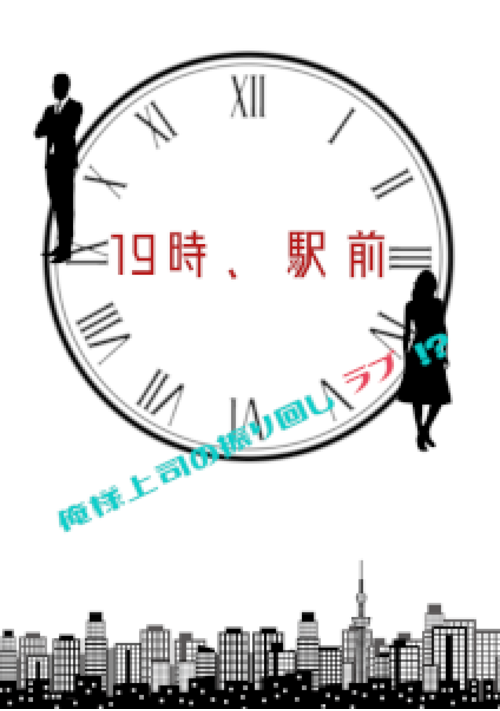
19時、駅前~俺様上司の振り回しラブ!?~
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
【19時、駅前。片桐】
その日、机の上に貼られていた付箋に戸惑った。
片桐っていうのは隣の課の俺様課長、片桐課長のことでいいんだと思う。
でも私と片桐課長には、同じ営業部にいるってこと以外、なにも接点がない。
なのに、この呼び出しは一体、なんですか……?
笹岡花重
24歳、食品卸会社営業部勤務。
真面目で頑張り屋さん。
嫌と言えない性格。
あとは平凡な女子。
×
片桐樹馬
29歳、食品卸会社勤務。
3課課長兼部長代理
高身長・高学歴・高収入と昔の三高を満たす男。
もちろん、仕事できる。
ただし、俺様。
俺様片桐課長に振り回され、私はどうなっちゃうの……!?

【完結】育てた後輩を送り出したらハイスペになって戻ってきました
藤浪保
恋愛
大手IT会社に勤める早苗は会社の歓迎会でかつての後輩の桜木と再会した。酔っ払った桜木を家に送った早苗は押し倒され、キスに翻弄されてそのまま関係を持ってしまう。
次の朝目覚めた早苗は前夜の記憶をなくし、関係を持った事しか覚えていなかった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















