1 / 10
もう戻れない(現代)
しおりを挟む
…………やってしまった。
昨日は忘年会だった。課も年も関係なく無礼講の忘年会。いつもなら羽目なんか外したりはしない。
だが、昨日は違った。
私の隣には片思いの相手がいて、私の名前を知っていてくれていたのだと知った。そして、年甲斐もなく浮かれて大量のお酒を頼んだ。
初恋ってわけでもないのに何を話していいかもわからず、ただお酒を煽って飲み続けた。別にお酒に弱いわけではないし、自分の限界だって心得ている。だが、そんなことさえも忘れて飲み続けた結果がこれ。
私は今片思いの相手に初めて見る天井の下、ベッドの中で抱きしめられている。
これは私の夢なのではないか。そう思いもしたが、確かに感じる自分以外の温かさとばっちり残っている私の記憶がこれが夢ではないことを告げていた。悲しいことにあれだけのアルコールを飲んだ私の記憶はしっかりと残っていたのだ。
自分の醜態と他人に迷惑をかけてしまったこと。そのすべてを鮮明に思い出すことが出来る。
私が自己嫌悪に陥っている中、ぐっすりと気持ちよさそうに寝ている彼が布団の中でもぞもぞと動き出した。
もうすぐ起きてしまうかもしれない。そう感じた私のそれからの行動は早かった。
床に散乱している自分の服を急いで身につけ、ほっぽり投げてあるカバンを中身も確認せずに拾った。腰が重くズキズキと身体が痛むことなんて無視をしてここがどこかもわからないまま私はその場を立ち去った。
それからどうやって帰ったのかは覚えていない。必死で帰って気付いたら自分の部屋にいたのだ。
ああ、私はなんてことをしてしまったのだろう。
彼は会社の製作グループのエースで、私なんかの手の届くような人ではない。
なのに、なのになんで彼は私を抱いたのか。
その答えはきっとたまたま私がそこにいたからだ。だって社内外のいろんな女性にもてる彼は女性なんか選びたい放題で、何の特徴もなくて家族にすら「あんたはよくて中の下ね」と言われるような見た目の私を選ぶ意味などどこにもない。
彼はたまたま私を抱いた。彼にとってはきっといつものことなのだろう。昨日だって、私を抱く手つきは手慣れたものだった。私に男性との経験があるわけではないけれど、そんな私にもわかるほどに彼は上手だった。
「初めては痛いのよ」――友人が言った言葉。
そんなのは嘘ではないだろうかと思ってしまったほどだったのだから。
「明日からどうしよう」
今日は休日だが、明日からはまた仕事だ。彼にどんな顔を見せればいいのか、なんて思ったりもしたがきっと彼は覚えていないだろう。
たまたま私だっただけ。
今までたくさん抱いたうちの一人。
だったら時期に忘れる。いや、私のことなど覚えてないかもしれない。私の記憶では彼は相当酔っていた。そうだ、彼は酔っていた。私に「愛してる」と言ってしまうほどに。
まあ、その言葉を聞いたせいで拒めなかったっていうのもあるけど。
きっと彼は覚えていない。
そうだ、覚えていないに違いない。私さえ何も言わなければわかるはずもない。
そもそもよく考えてみれば一般事務の私と製作グループに所属している彼が会うことなど約束でもしていない限りそうそうないものだ。
「なんだ、悩むことなんかないじゃない!」
そう自分に言い聞かせながら、もうごまかすことはできない腰の痛みを和らげるため温かい湯につかるのだった。
** *
「白鷺さん」
「ひっ」
ここは庶務課。製作課の2階上にある。
そんなところに颯爽と現れ私の名前を呼んだのは、製作課の神崎だった。
先日の出来事もあるが、何より女性人たちの目が怖い。
久々に獲物を見つけたオオカミのように鋭い目つきだ。
ライオンなんて言わない。彼女たちは皆、群れているようで獲物が来たら我先にと仲間ですら何食わぬ顔で蹴落としていくのだから。
今の私の状況がそれだ。
今まで私なんか敵でもないと思っていたのであろう、隣の席の同僚は今にも食い殺さんという目つきでこちらを睨んでくる。
「今日の夜、ちょっといいかな? 話、あるんだけど……」
彼のその言葉でさらに彼女の目つきが鋭くなったのは言うまでもない。
「は、はい……」
断れるはずもなく、そう返事をした私は朝礼からわずか1時間足らずで今日一日の就業時間全てを針の筵で過ごすこととなったのだった。
「それで話ってなんですか?」
就業後、彼の後を無言で着いていくと辿り着いたのは駅から少し離れた、路地裏の居酒屋だった。
月末の今日はどこの居酒屋も満席だろうが、ここはちらほらと空席が見える。知る人ぞ知る穴場といったところだろう。
そんなところに連れ込むとはまさかこの前の醜態の口封じとか?
悪い想像が一瞬で頭の隅から隅を駆け巡る。
「この前、返事聞く前に帰っちゃったからさ。聞かせてもらおうと思って」
「返事……とは?」
「俺、中途半端なのは嫌いなんだ。イエスかノーのどちらかで答えてほしい」
「いや、だから返事って何のことですか?」
「え? もしかして記憶……ない? 参ったな。だから逃げられちゃったのか……」
「神崎さん?」
「白鷺さん、愛しているので俺のお嫁さんになってください!」
「初耳ですけど!?」
あの日の記憶はある。忘れたいことまではっきりと残っている。
だが、その記憶にそんなプロポーズまがいのものはない。
というか付き合って何年目かの彼氏ならともかく、ほぼ接点のない憧れの人兼片思いの相手からいきなりそんなこと言われたら、どんなに酔っぱらってようとそんなの忘れるわけないでしょ!
「忘れてるだけだって。で、答えは?」
どうやら彼はそのまま突き通すつもりのようだ。
私ももう20代後半。高校時代の友人も大学時代の友人も絶賛結婚ラッシュ中である。
結婚は、したい。
神崎さんのことを好きかと聞かれると、好きだ。
だが今となってはそれは果たして憧れなのか恋なのかわからずにいる。
純度100パーセントを装った笑顔で、結婚を迫ってくる彼を愛せるのか。
答えはノーだ。
「ごめんなさい」
結婚なんて一大イベントを決心するには私はまだ彼のことを知らなさすぎる。
「そっか……。ならイエスって言うまで頑張るだけだね」
「え?」
「お勘定、ここに置いておくね」
「はいよ」
お財布から一万円札を一枚、机に置くと神崎さんは私の手を引いて店の外へと出ていく。
「いやぁ、この店にしておいて良かったよ。イエスでもノーでも家は近いほうがいいからね」
「え?」
不穏な言葉を口にした彼は慣れた足取りで、先日テレビで特集していた高級高層マンションへと入り込む。
真黒なカードをエレベーターの入り口にかざし、私の僅かな抵抗を無視してエレベーターは上昇していく。
「さぁてと、子作りしようか」
「な!?」
「子供ができたら真面目な白鷺さんは結婚してくれるって信じてるよ」
そして彼はドアが開く直前、強引な息苦しくなるキスをした。
酸素は奪い取られ、入り口がふさがれているせいでまともに入ってさえ来ない。
角度を変えるたびに深まるキスに、彼の表情も楽しいものへと変わっていく。される私はたまったものではない。
身体に力を入れることすらままならず、手近な彼へと手を放した瞬間、記憶は途絶えた。
「…………ん、ぁぁん」
目が覚めるとすぐに最近になって初めて感じたあの感覚が身体を襲った。
今までに感じたことのないような、我をも簡単に手放してしまう『快感』。
「ねぇ、気持ちいいでしょう?」
私の下の口を好き勝手に貪る彼は大きなモノを突き刺しては抜きを繰り返しながら笑った。
私が意識を手放してからもうどのくらいの時間がたったのかはわからない。
けれど彼の額にうっすらと浮かび上がった汗と、見ずともわかる私に放たれた彼の精がもう戻れないことを告げていた。
昨日は忘年会だった。課も年も関係なく無礼講の忘年会。いつもなら羽目なんか外したりはしない。
だが、昨日は違った。
私の隣には片思いの相手がいて、私の名前を知っていてくれていたのだと知った。そして、年甲斐もなく浮かれて大量のお酒を頼んだ。
初恋ってわけでもないのに何を話していいかもわからず、ただお酒を煽って飲み続けた。別にお酒に弱いわけではないし、自分の限界だって心得ている。だが、そんなことさえも忘れて飲み続けた結果がこれ。
私は今片思いの相手に初めて見る天井の下、ベッドの中で抱きしめられている。
これは私の夢なのではないか。そう思いもしたが、確かに感じる自分以外の温かさとばっちり残っている私の記憶がこれが夢ではないことを告げていた。悲しいことにあれだけのアルコールを飲んだ私の記憶はしっかりと残っていたのだ。
自分の醜態と他人に迷惑をかけてしまったこと。そのすべてを鮮明に思い出すことが出来る。
私が自己嫌悪に陥っている中、ぐっすりと気持ちよさそうに寝ている彼が布団の中でもぞもぞと動き出した。
もうすぐ起きてしまうかもしれない。そう感じた私のそれからの行動は早かった。
床に散乱している自分の服を急いで身につけ、ほっぽり投げてあるカバンを中身も確認せずに拾った。腰が重くズキズキと身体が痛むことなんて無視をしてここがどこかもわからないまま私はその場を立ち去った。
それからどうやって帰ったのかは覚えていない。必死で帰って気付いたら自分の部屋にいたのだ。
ああ、私はなんてことをしてしまったのだろう。
彼は会社の製作グループのエースで、私なんかの手の届くような人ではない。
なのに、なのになんで彼は私を抱いたのか。
その答えはきっとたまたま私がそこにいたからだ。だって社内外のいろんな女性にもてる彼は女性なんか選びたい放題で、何の特徴もなくて家族にすら「あんたはよくて中の下ね」と言われるような見た目の私を選ぶ意味などどこにもない。
彼はたまたま私を抱いた。彼にとってはきっといつものことなのだろう。昨日だって、私を抱く手つきは手慣れたものだった。私に男性との経験があるわけではないけれど、そんな私にもわかるほどに彼は上手だった。
「初めては痛いのよ」――友人が言った言葉。
そんなのは嘘ではないだろうかと思ってしまったほどだったのだから。
「明日からどうしよう」
今日は休日だが、明日からはまた仕事だ。彼にどんな顔を見せればいいのか、なんて思ったりもしたがきっと彼は覚えていないだろう。
たまたま私だっただけ。
今までたくさん抱いたうちの一人。
だったら時期に忘れる。いや、私のことなど覚えてないかもしれない。私の記憶では彼は相当酔っていた。そうだ、彼は酔っていた。私に「愛してる」と言ってしまうほどに。
まあ、その言葉を聞いたせいで拒めなかったっていうのもあるけど。
きっと彼は覚えていない。
そうだ、覚えていないに違いない。私さえ何も言わなければわかるはずもない。
そもそもよく考えてみれば一般事務の私と製作グループに所属している彼が会うことなど約束でもしていない限りそうそうないものだ。
「なんだ、悩むことなんかないじゃない!」
そう自分に言い聞かせながら、もうごまかすことはできない腰の痛みを和らげるため温かい湯につかるのだった。
** *
「白鷺さん」
「ひっ」
ここは庶務課。製作課の2階上にある。
そんなところに颯爽と現れ私の名前を呼んだのは、製作課の神崎だった。
先日の出来事もあるが、何より女性人たちの目が怖い。
久々に獲物を見つけたオオカミのように鋭い目つきだ。
ライオンなんて言わない。彼女たちは皆、群れているようで獲物が来たら我先にと仲間ですら何食わぬ顔で蹴落としていくのだから。
今の私の状況がそれだ。
今まで私なんか敵でもないと思っていたのであろう、隣の席の同僚は今にも食い殺さんという目つきでこちらを睨んでくる。
「今日の夜、ちょっといいかな? 話、あるんだけど……」
彼のその言葉でさらに彼女の目つきが鋭くなったのは言うまでもない。
「は、はい……」
断れるはずもなく、そう返事をした私は朝礼からわずか1時間足らずで今日一日の就業時間全てを針の筵で過ごすこととなったのだった。
「それで話ってなんですか?」
就業後、彼の後を無言で着いていくと辿り着いたのは駅から少し離れた、路地裏の居酒屋だった。
月末の今日はどこの居酒屋も満席だろうが、ここはちらほらと空席が見える。知る人ぞ知る穴場といったところだろう。
そんなところに連れ込むとはまさかこの前の醜態の口封じとか?
悪い想像が一瞬で頭の隅から隅を駆け巡る。
「この前、返事聞く前に帰っちゃったからさ。聞かせてもらおうと思って」
「返事……とは?」
「俺、中途半端なのは嫌いなんだ。イエスかノーのどちらかで答えてほしい」
「いや、だから返事って何のことですか?」
「え? もしかして記憶……ない? 参ったな。だから逃げられちゃったのか……」
「神崎さん?」
「白鷺さん、愛しているので俺のお嫁さんになってください!」
「初耳ですけど!?」
あの日の記憶はある。忘れたいことまではっきりと残っている。
だが、その記憶にそんなプロポーズまがいのものはない。
というか付き合って何年目かの彼氏ならともかく、ほぼ接点のない憧れの人兼片思いの相手からいきなりそんなこと言われたら、どんなに酔っぱらってようとそんなの忘れるわけないでしょ!
「忘れてるだけだって。で、答えは?」
どうやら彼はそのまま突き通すつもりのようだ。
私ももう20代後半。高校時代の友人も大学時代の友人も絶賛結婚ラッシュ中である。
結婚は、したい。
神崎さんのことを好きかと聞かれると、好きだ。
だが今となってはそれは果たして憧れなのか恋なのかわからずにいる。
純度100パーセントを装った笑顔で、結婚を迫ってくる彼を愛せるのか。
答えはノーだ。
「ごめんなさい」
結婚なんて一大イベントを決心するには私はまだ彼のことを知らなさすぎる。
「そっか……。ならイエスって言うまで頑張るだけだね」
「え?」
「お勘定、ここに置いておくね」
「はいよ」
お財布から一万円札を一枚、机に置くと神崎さんは私の手を引いて店の外へと出ていく。
「いやぁ、この店にしておいて良かったよ。イエスでもノーでも家は近いほうがいいからね」
「え?」
不穏な言葉を口にした彼は慣れた足取りで、先日テレビで特集していた高級高層マンションへと入り込む。
真黒なカードをエレベーターの入り口にかざし、私の僅かな抵抗を無視してエレベーターは上昇していく。
「さぁてと、子作りしようか」
「な!?」
「子供ができたら真面目な白鷺さんは結婚してくれるって信じてるよ」
そして彼はドアが開く直前、強引な息苦しくなるキスをした。
酸素は奪い取られ、入り口がふさがれているせいでまともに入ってさえ来ない。
角度を変えるたびに深まるキスに、彼の表情も楽しいものへと変わっていく。される私はたまったものではない。
身体に力を入れることすらままならず、手近な彼へと手を放した瞬間、記憶は途絶えた。
「…………ん、ぁぁん」
目が覚めるとすぐに最近になって初めて感じたあの感覚が身体を襲った。
今までに感じたことのないような、我をも簡単に手放してしまう『快感』。
「ねぇ、気持ちいいでしょう?」
私の下の口を好き勝手に貪る彼は大きなモノを突き刺しては抜きを繰り返しながら笑った。
私が意識を手放してからもうどのくらいの時間がたったのかはわからない。
けれど彼の額にうっすらと浮かび上がった汗と、見ずともわかる私に放たれた彼の精がもう戻れないことを告げていた。
21
あなたにおすすめの小説

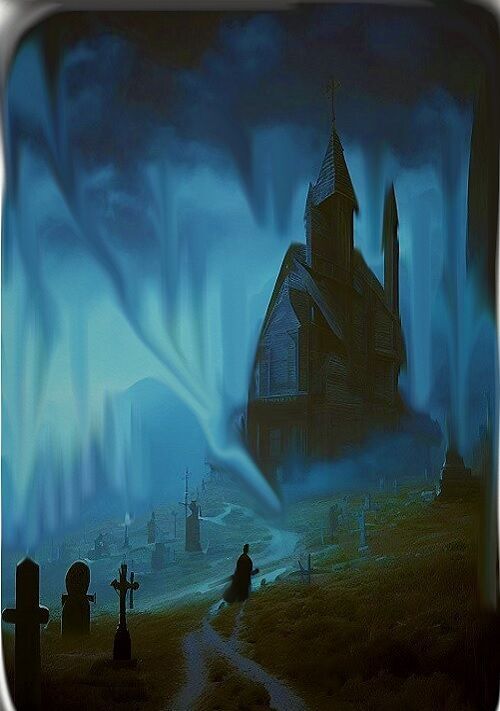


地味な私を捨てた元婚約者にざまぁ返し!私の才能に惚れたハイスペ社長にスカウトされ溺愛されてます
久遠翠
恋愛
「君は、可愛げがない。いつも数字しか見ていないじゃないか」
大手商社に勤める地味なOL・相沢美月は、エリートの婚約者・高遠彰から突然婚約破棄を告げられる。
彼の心変わりと社内での孤立に傷つき、退職を選んだ美月。
しかし、彼らは知らなかった。彼女には、IT業界で“K”という名で知られる伝説的なデータアナリストという、もう一つの顔があったことを。
失意の中、足を運んだ交流会で美月が出会ったのは、急成長中のIT企業「ホライゾン・テクノロジーズ」の若き社長・一条蓮。
彼女が何気なく口にした市場分析の鋭さに衝撃を受けた蓮は、すぐさま彼女を破格の条件でスカウトする。
「君のその目で、俺と未来を見てほしい」──。
蓮の情熱に心を動かされ、新たな一歩を踏み出した美月は、その才能を遺憾なく発揮していく。
地味なOLから、誰もが注目するキャリアウーマンへ。
そして、仕事のパートナーである蓮の、真っ直ぐで誠実な愛情に、凍てついていた心は次第に溶かされていく。
これは、才能というガラスの靴を見出された、一人の女性のシンデレラストーリー。
数字の奥に隠された真実を見抜く彼女が、本当の愛と幸せを掴むまでの、最高にドラマチックな逆転ラブストーリー。


病弱な彼女は、外科医の先生に静かに愛されています 〜穏やかな執着に、逃げ場はない〜
来栖れいな
恋愛
――穏やかな微笑みの裏に、逃げられない愛があった。
望んでいたわけじゃない。
けれど、逃げられなかった。
生まれつき弱い心臓を抱える彼女に、政略結婚の話が持ち上がった。
親が決めた未来なんて、受け入れられるはずがない。
無表情な彼の穏やかさが、余計に腹立たしかった。
それでも――彼だけは違った。
優しさの奥に、私の知らない熱を隠していた。
形式だけのはずだった関係は、少しずつ形を変えていく。
これは束縛? それとも、本当の愛?
穏やかな外科医に包まれていく、静かで深い恋の物語。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

旦那様の愛が重い
おきょう
恋愛
マリーナの旦那様は愛情表現がはげしい。
毎朝毎晩「愛してる」と耳元でささやき、隣にいれば腰を抱き寄せてくる。
他人は大切にされていて羨ましいと言うけれど、マリーナには怖いばかり。
甘いばかりの言葉も、優しい視線も、どうにも嘘くさいと思ってしまう。
本心の分からない人の心を、一体どうやって信じればいいのだろう。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















