3 / 37
第一章
3
しおりを挟む
予定の時間どおりに名古屋に着いたのぞみから、ホームへ降り立った鮎原は、人の流れのままに改札に向かった。誰もが無口で先を急ぐように歩いている。
手にしていた荷物を駅コンコースの一角に設えられたコインロッカーに放り込むと、覚えた気だるさに小さな溜め息を一つ零した。
できるならこのまま帰って眠りたい。だが社会人である以上そんな身勝手は許されない。今から、東京の恋人のもとから直接きましたなどとおくびにも出さず、出勤するのだから。
「起きれたかな、武村」
腕の時計に目をやり時間を見る。武村も今ごろは会社に向かっているはずだった。
新幹線改札からすぐの太閤通口から外に出た鮎原は、噴水広場と呼ばれるひらけたスペースと道路を挟んだ向こうにある大手電気店の入っているビルを仰いだ。
昔このビルが名古屋の流行をリードするファッションビルだったなどと知っている者は、どれくらいいるのだろう。自分も上司から何かの話のときに聞いた口だ。
そのビルを左手に望みながら歩く。少し行けばレンガ調の外壁のビルが見えてくる。そこが鮎原の勤めるレディスファッション・マキノだった。
社名どおり、おもに女性向けの衣料を扱うマキノは、もとは名古屋市の隣、古くから繊維の街として知られる一宮市で洋装店として先代が興した。店が大きくなるにつれ拠点を名古屋に移し、今は東京に支社、大阪に営業所を持つ業界の中堅どころのアパレル会社だ。
社員用通用口から入りタイムカードを押す。始業にははまだ時間があった。
「どっかでコーヒーでも飲んでくればよかったな」
駅から会社までの道中にあったファストフーズに寄ってくればよかった。朝の淹れたてならそれほど酸味は強くないだろう。車内販売を利用してもよかったか。あのときは何か面倒臭く眠った振りをして遣り過ごしてしまったが。
鮎原は部署に寄り、業務連絡用のボード横にかけられた出勤札を黒字に返すと、商談室がある五階の給湯室に向かった。そこに飲料の自動販売機が置いてあるからだ。
おはようございます、とすれ違う同僚たちと挨拶をしながら着いた給湯室には先客がいた。入ってきた鮎原に気づき、すぐに人好きのする笑みを浮かべる。
「おはようございます、鮎原さん」
妹尾雄輔だった。妹尾は去年武村と入れ替わりに東京支社から異動してきた。営業を希望していたと聞くが、転属先は商品管理部で確か入社は三年目。詳しくは知らないが、ベテランが多い商品管理部で若手の妹尾は貴重な存在のようで、女子社員に人気があるらしいと聞く。
「おはよう」
言葉を返しながら鮎原は、小銭を取り出し鮎原は目当てのブラックコーヒーのボタンを押した。
「昨日、鮎原さん何してました?」
コーヒー液がカップに注がれるのを待つ鮎原に、妹尾が聞いてきた。
どういうわけか妹尾は、部署も違うというのに自分に懐いていた。二歳違いと年が比較的に近いからかもしれない。こうして顔を合わせるたび、話しかけてくる。
人はあきらかに好意を見せる相手に対して、よほどのことでもない限り、悪くは思わない。鮎原もそうだった。「先輩」と自分に向けられる親しみのこもった妹尾の態度は、くすぐったくも嬉しいものだ。
だがこの質問は困る。何をしていたかなど、前日から東京に行って、恋人に会っていたと正直に言うのは憚られる。
「別に何も。ずっと家にいたよ」
恋人がいると話せたらよかったのかもしれないが、その相手が同性でしかも同期の武村だと知られるのは当然不味い。しかしそこだけを上手くぼかして誤魔化せる自信がなかった。だから、嘘をついた。
妹尾が意外そうな目向けた。嘘がばれたのだろうかと、鮎原は内心ぎくりとしたが、すぐにいつのように笑みを浮かべた。
「そうだったんですか。なら電話すればよかったな。暇にしてたんですよね」
子供が見せる邪気のない顔で、妹尾は厚かましいことを口にする。
「はぁ? 何だよ、お前の暇つぶしの相手させる気か?」
そんな妹尾に鮎原はむっとした口調で返すが、本気で言っているわけではもちろんない。
「へへへ、いいじゃないですか。あっ、でもオレ、その前に鮎原さんの番号知らないや」
「お前なあ――」
それでよく、電話すればよかったなどと言えたものだ。さすがに呆れた鮎原は小さく首を振った。
「だから、次のために教えてください」
「何が次だ。お前に教えたら用もないのにかけてきそうだ」
「えー、そんなことしませんよ。かけるときは用があるときだけですって。都合が悪いようならすぐ切りますし」
手にしていたカップを脇に置いた妹尾は、鮎原に向かって「はい」と右手を出してきた。もう片方の手には内ポケットから取り出した自分の携帯電話を握っている。
「何するんだ?」
「赤外線通信ですよ。オレの番号教えておきます。鮎原さんの携帯貸してください」
それくらいならいいか、とまだ熱く冷めるのを待つカップの中身を零さないように気をつけながら、鮎原も携帯を出す。
「じゃあ」
鮎原から携帯を受け取った妹尾はボタンを操作し、二つの通信ポートを合わせた。
その慣れた手つきから鮎原は、妹尾は結構そういうことをやっているのだと思った。こんな人好きのする顔を見せ、「携帯貸して」と言われれば、今の自分のように警戒することなく渡してしまうだろう。
「これ、オレの番号ですから。いつでも構いませんから、かけてきてくださいね」
鮎原は、妹尾が返してきた自分の携帯電話を見る。ディスプレイ画面には番号が表示されていた。
「ちゃんと登録しておいてくださいよ」
画面をクリアされてしまうのを心配してか、窺うように覗き込んでくる妹尾に苦笑してしまう。
「お前なあ――」
そこまでやるなら、アドレス登録まですればいいのだ。ボタンを一つ押すだけだ。なのに最後の決定権はこうして返してきて。
「――だったら、登録まですればいいんだよ」
「え、でも、勝手にそこまでするのは……」
語尾を濁し、妹尾は弱り顔を見せる。ここがボーダーラインと、気遣いだった。
どんなに厚かましい言動をしても、心の機微を読むのに長けてでもいるのか、鮎原が抵抗を覚える境界を越えてこない。それも、この後輩に好感を持つ理由だ。
おかげで鮎原には、身構えることなく話せる相手だった。
「気が変わったら、消すかもしれないけどな」
照れ隠しのようにうそぶいて鮎原は、妹尾の番号を携帯電話のアドレス登録した。
手にしていた荷物を駅コンコースの一角に設えられたコインロッカーに放り込むと、覚えた気だるさに小さな溜め息を一つ零した。
できるならこのまま帰って眠りたい。だが社会人である以上そんな身勝手は許されない。今から、東京の恋人のもとから直接きましたなどとおくびにも出さず、出勤するのだから。
「起きれたかな、武村」
腕の時計に目をやり時間を見る。武村も今ごろは会社に向かっているはずだった。
新幹線改札からすぐの太閤通口から外に出た鮎原は、噴水広場と呼ばれるひらけたスペースと道路を挟んだ向こうにある大手電気店の入っているビルを仰いだ。
昔このビルが名古屋の流行をリードするファッションビルだったなどと知っている者は、どれくらいいるのだろう。自分も上司から何かの話のときに聞いた口だ。
そのビルを左手に望みながら歩く。少し行けばレンガ調の外壁のビルが見えてくる。そこが鮎原の勤めるレディスファッション・マキノだった。
社名どおり、おもに女性向けの衣料を扱うマキノは、もとは名古屋市の隣、古くから繊維の街として知られる一宮市で洋装店として先代が興した。店が大きくなるにつれ拠点を名古屋に移し、今は東京に支社、大阪に営業所を持つ業界の中堅どころのアパレル会社だ。
社員用通用口から入りタイムカードを押す。始業にははまだ時間があった。
「どっかでコーヒーでも飲んでくればよかったな」
駅から会社までの道中にあったファストフーズに寄ってくればよかった。朝の淹れたてならそれほど酸味は強くないだろう。車内販売を利用してもよかったか。あのときは何か面倒臭く眠った振りをして遣り過ごしてしまったが。
鮎原は部署に寄り、業務連絡用のボード横にかけられた出勤札を黒字に返すと、商談室がある五階の給湯室に向かった。そこに飲料の自動販売機が置いてあるからだ。
おはようございます、とすれ違う同僚たちと挨拶をしながら着いた給湯室には先客がいた。入ってきた鮎原に気づき、すぐに人好きのする笑みを浮かべる。
「おはようございます、鮎原さん」
妹尾雄輔だった。妹尾は去年武村と入れ替わりに東京支社から異動してきた。営業を希望していたと聞くが、転属先は商品管理部で確か入社は三年目。詳しくは知らないが、ベテランが多い商品管理部で若手の妹尾は貴重な存在のようで、女子社員に人気があるらしいと聞く。
「おはよう」
言葉を返しながら鮎原は、小銭を取り出し鮎原は目当てのブラックコーヒーのボタンを押した。
「昨日、鮎原さん何してました?」
コーヒー液がカップに注がれるのを待つ鮎原に、妹尾が聞いてきた。
どういうわけか妹尾は、部署も違うというのに自分に懐いていた。二歳違いと年が比較的に近いからかもしれない。こうして顔を合わせるたび、話しかけてくる。
人はあきらかに好意を見せる相手に対して、よほどのことでもない限り、悪くは思わない。鮎原もそうだった。「先輩」と自分に向けられる親しみのこもった妹尾の態度は、くすぐったくも嬉しいものだ。
だがこの質問は困る。何をしていたかなど、前日から東京に行って、恋人に会っていたと正直に言うのは憚られる。
「別に何も。ずっと家にいたよ」
恋人がいると話せたらよかったのかもしれないが、その相手が同性でしかも同期の武村だと知られるのは当然不味い。しかしそこだけを上手くぼかして誤魔化せる自信がなかった。だから、嘘をついた。
妹尾が意外そうな目向けた。嘘がばれたのだろうかと、鮎原は内心ぎくりとしたが、すぐにいつのように笑みを浮かべた。
「そうだったんですか。なら電話すればよかったな。暇にしてたんですよね」
子供が見せる邪気のない顔で、妹尾は厚かましいことを口にする。
「はぁ? 何だよ、お前の暇つぶしの相手させる気か?」
そんな妹尾に鮎原はむっとした口調で返すが、本気で言っているわけではもちろんない。
「へへへ、いいじゃないですか。あっ、でもオレ、その前に鮎原さんの番号知らないや」
「お前なあ――」
それでよく、電話すればよかったなどと言えたものだ。さすがに呆れた鮎原は小さく首を振った。
「だから、次のために教えてください」
「何が次だ。お前に教えたら用もないのにかけてきそうだ」
「えー、そんなことしませんよ。かけるときは用があるときだけですって。都合が悪いようならすぐ切りますし」
手にしていたカップを脇に置いた妹尾は、鮎原に向かって「はい」と右手を出してきた。もう片方の手には内ポケットから取り出した自分の携帯電話を握っている。
「何するんだ?」
「赤外線通信ですよ。オレの番号教えておきます。鮎原さんの携帯貸してください」
それくらいならいいか、とまだ熱く冷めるのを待つカップの中身を零さないように気をつけながら、鮎原も携帯を出す。
「じゃあ」
鮎原から携帯を受け取った妹尾はボタンを操作し、二つの通信ポートを合わせた。
その慣れた手つきから鮎原は、妹尾は結構そういうことをやっているのだと思った。こんな人好きのする顔を見せ、「携帯貸して」と言われれば、今の自分のように警戒することなく渡してしまうだろう。
「これ、オレの番号ですから。いつでも構いませんから、かけてきてくださいね」
鮎原は、妹尾が返してきた自分の携帯電話を見る。ディスプレイ画面には番号が表示されていた。
「ちゃんと登録しておいてくださいよ」
画面をクリアされてしまうのを心配してか、窺うように覗き込んでくる妹尾に苦笑してしまう。
「お前なあ――」
そこまでやるなら、アドレス登録まですればいいのだ。ボタンを一つ押すだけだ。なのに最後の決定権はこうして返してきて。
「――だったら、登録まですればいいんだよ」
「え、でも、勝手にそこまでするのは……」
語尾を濁し、妹尾は弱り顔を見せる。ここがボーダーラインと、気遣いだった。
どんなに厚かましい言動をしても、心の機微を読むのに長けてでもいるのか、鮎原が抵抗を覚える境界を越えてこない。それも、この後輩に好感を持つ理由だ。
おかげで鮎原には、身構えることなく話せる相手だった。
「気が変わったら、消すかもしれないけどな」
照れ隠しのようにうそぶいて鮎原は、妹尾の番号を携帯電話のアドレス登録した。
0
あなたにおすすめの小説


完結|好きから一番遠いはずだった
七角@書籍化進行中!
BL
大学生の石田陽は、石ころみたいな自分に自信がない。酒の力を借りて恋愛のきっかけをつかもうと意気込む。
しかしサークル歴代最高イケメン・星川叶斗が邪魔してくる。恋愛なんて簡単そうなこの後輩、ずるいし、好きじゃない。
なのにあれこれ世話を焼かれる。いや利用されてるだけだ。恋愛相手として最も遠い後輩に、勘違いしない。
…はずだった。

兄ちゃんの代わりでもいいから
甘野えいりん
BL
将来の夢もなく、ただ毎日を過ごしていた高校二年の青垣直汰。
大学三年の教育実習生として来た尾原悠は、綺麗で、真面目で、少し不器用な──ほっておけない人だった。
そんな悠が気になって仕方なく、気づけば恋にのめり込んでいく直汰。
けれど悠には、直汰の兄に忘れられない想いがあって……。
それでも直汰は、その兄の代わりでもいいと気持ちをぶつける。
ふたりの距離が少しずつ縮まるにつれ、悠への想いはあふれて止まらない。
悠の想いはまだ兄に向いたままなのか──。

経理部の美人チーフは、イケメン新人営業に口説かれています――「凛さん、俺だけに甘くないですか?」年下の猛攻にツンデレ先輩が陥落寸前!
中岡 始
BL
社内一の“整いすぎた男”、阿波座凛(あわざりん)は経理部のチーフ。
無表情・無駄のない所作・隙のない資料――
完璧主義で知られる凛に、誰もが一歩距離を置いている。
けれど、新卒営業の谷町光だけは違った。
イケメン・人懐こい・書類はギリギリ不備、でも笑顔は無敵。
毎日のように経費精算の修正を理由に現れる彼は、
凛にだけ距離感がおかしい――そしてやたら甘い。
「また会えて嬉しいです。…書類ミスった甲斐ありました」
戸惑う凛をよそに、光の“攻略”は着実に進行中。
けれど凛は、自分だけに見せる光の視線に、
どこか“計算”を感じ始めていて……?
狙って懐くイケメン新人営業×こじらせツンデレ美人経理チーフ
業務上のやりとりから始まる、じわじわ甘くてときどき切ない“再計算不能”なオフィスラブ!

本気になった幼なじみがメロすぎます!
文月あお
BL
同じマンションに住む年下の幼なじみ・玲央は、イケメンで、生意気だけど根はいいやつだし、とてもモテる。
俺は失恋するたびに「玲央みたいな男に生まれたかったなぁ」なんて思う。
いいなぁ玲央は。きっと俺より経験豊富なんだろうな――と、つい出来心で聞いてしまったんだ。
「やっぱ唇ってさ、やわらけーの?」
その軽率な質問が、俺と玲央の幼なじみライフを、まるっと変えてしまった。
「忘れないでよ、今日のこと」
「唯くんは俺の隣しかだめだから」
「なんで邪魔してたか、わかんねーの?」
俺と玲央は幼なじみで。男同士で。生まれたときからずっと一緒で。
俺の恋の相手は女の子のはずだし、玲央の恋の相手は、もっと素敵な人であるはずなのに。
「素数でも数えてなきゃ、俺はふつーにこうなんだよ、唯くんといたら」
そんな必死な顔で迫ってくんなよ……メロすぎんだろーが……!
【攻め】倉田玲央(高一)×【受け】五十嵐唯(高三)

イケメンモデルと新人マネージャーが結ばれるまでの話
タタミ
BL
新坂真澄…27歳。トップモデル。端正な顔立ちと抜群のスタイルでブレイク中。瀬戸のことが好きだが、隠している。
瀬戸幸人…24歳。マネージャー。最近新坂の担当になった社会人2年目。新坂に仲良くしてもらって懐いているが、好意には気付いていない。
笹川尚也…27歳。チーフマネージャー。新坂とは学生時代からの友人関係。新坂のことは大抵なんでも分かる。
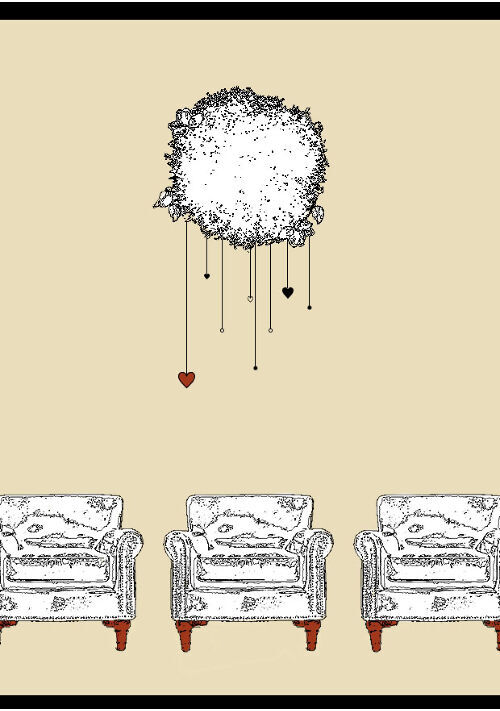
隣のチャラ男くん
木原あざみ
BL
チャラ男おかん×無気力駄目人間。
お隣さん同士の大学生が、お世話されたり嫉妬したり、ごはん食べたりしながら、ゆっくりと進んでいく恋の話です。
第9回BL小説大賞 奨励賞ありがとうございました。

【完結】愛されたかった僕の人生
Kanade
BL
✯オメガバース
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。
今日も《夫》は帰らない。
《夫》には僕以外の『番』がいる。
ねぇ、どうしてなの?
一目惚れだって言ったじゃない。
愛してるって言ってくれたじゃないか。
ねぇ、僕はもう要らないの…?
独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















