4 / 13
第3話「黒狼と醤油もどき」
しおりを挟む
レオンハルトと出会ってから、数日が経った。
彼は本当に「また来た」。それも毎日。決まって昼食の時間になると、どこからともなく僕の小屋の前に現れるのだ。
相変わらず口数は少なく、表情も険しいままだったが、僕の作る料理を黙々と、そして実においしそうに平らげていく。ニンジンのポタージュ、採れたてレタスのサラダ、ホクホクのジャガイモの塩ゆで。僕が作る素朴な料理を、レオンハルトはいつも空になるまで食べてくれた。
その日も、僕はレオンハルトのための昼食を準備していた。今日のメニューは、森で採れたキノコと野菜をたっぷり入れた炒め物だ。味付けは塩と、香りの良いハーブ。
『やっぱり、醤油があったらもっと美味しくなるんだろうな』
そんなことを考えていた時、森の奥から獣の苦しそうな呻き声が聞こえてきた。それは、ただの鳴き声ではない。明らかに助けを求めるような、悲痛な叫びだった。
「レオンハルトさん!」
ちょうど薪割りを手伝ってくれていたレオンハルトに声をかける。彼はすでに剣の柄に手をかけ、警戒態勢に入っていた。
「ユキナリは小屋の中にいろ」
「でも……」
「いいから!」
レオンハルトの厳しい声に、僕はしぶしぶうなずいた。でも、心配でじっとしていられない。僕は彼の背中を追って、声のする方へと向かった。
森の少し開けた場所に、信じられない光景が広がっていた。
そこにいたのは、巨大な黒い狼だった。体長は二メートルを優に超えているだろう。その漆黒の毛皮は土と血で汚れ、後ろ足には動物を捕らえるための無骨な罠が深く食い込んでいた。狼は苦痛に喘ぎながら、僕たちを睨みつけて低くうなっている。
「下がっていろ。こいつは危険だ」
レオンハルトは僕をかばうように前に立ち、ゆっくりと剣を抜いた。
「待ってください! 殺さないで!」
僕は思わず叫んでいた。狼の瞳は凶暴さよりも、怯えと苦痛の色が濃かったのだ。
「こいつは手負いだ。下手に近づけば襲われる」
「でも、助けを求めてるみたいなんです。罠を外してあげれば、きっと……」
僕の必死の訴えに、レオンハルトは一瞬ためらったようだった。その隙に、僕はゆっくりと狼に近づいた。
「大丈夫、怖くないよ。助けてあげるからね」
僕はできるだけ優しい声で話しかけながら、一歩、また一歩と距離を詰める。狼は依然としてうなり声を上げているが、攻撃してくる様子はない。僕が本気で助けようとしていることが伝わったのだろうか。
狼の足元までたどり着き、罠に手を伸ばした瞬間だった。狼が苦痛に耐えかねたのか、がぶりと僕の腕に噛みつこうとした。
「危ない!」
レオンハルトが僕を突き飛ばす。その直後、彼の分厚い革の手甲が、狼の牙をがしりと受け止めていた。
「レオンハルトさん!」
「問題ない。お前は罠を外せ」
彼は狼の牙を腕で受け止めたまま、冷静に僕に指示を出す。僕はうなずくと、【万能農具】をペンチの形に変化させ、罠のバネに差し込んだ。硬い金属の罠が、いとも簡単にこじ開けられる。
足から自由になった狼は、それでもまだ僕たちを警戒していた。しかし、レオンハルトがゆっくりと腕を引くと、攻撃するでもなく、ただその場でくたりと横たわった。体力を消耗しきっているようだ。
「……終わったか」
「はい。レオンハルトさん、腕は大丈夫ですか?」
「ああ。この手甲のおかげで傷一つない」
レオンハルトはそう言うと、おもむろに水袋を取り出し、狼の口元に水を垂らしてやった。狼は、おとなしくその水を飲んでいる。
僕たちは、動けない狼を二人で担ぎ、僕の小屋まで運んだ。傷口を洗い、薬草をすり込んで布で巻いてやる。幸い、骨は折れていないようだった。
手当が終わる頃には、狼はすっかり落ち着きを取り戻し、僕の足元ですうすうと寝息を立て始めた。
「……お前に懐いたようだな」
レオンハルトが、少しだけ呆れたように言う。
「名前、クロって呼んでもいいですかね。真っ黒だから」
「好きにしろ」
ぶっきらぼうに言いながらも、レオンハルトの表情はどこか柔らかい。彼も、クロのことが心配だったのだろう。
その日の昼食は、少し遅くなってしまった。僕とレオンハルト、そして足元で眠るクロ。奇妙な三人と一匹の食事が始まった。
「そうだ。レオンハルトさん、ちょっと試してみたいものがあるんです」
僕はそう言うと、数日前から試作していた液体を小皿に入れて持ってきた。大豆に似た豆と小麦に似た穀物を発酵させて作った、醤油もどきだ。
「これは?」
「僕の故郷の調味料です。魚の塩焼きにつけてみてください」
ちょうど焼いていた川魚を一切れ、レオンハルトの皿に乗せる。彼は半信半疑といった顔で、醤油もどきを少しだけつけて、魚を口に運んだ。
次の瞬間、レオンハルトの目が見開かれた。
「なっ……なんだ、これは!?」
驚きのあまり、声が裏返っている。
「塩辛いだけじゃない。深い……味わいがある。魚の旨味を何倍にも引き立てている……!」
彼は夢中になって、魚を食べ進めていく。よほど気に入ったらしい。その食べっぷりを見ているだけで、僕まで嬉しくなってくる。
「ユキナリ。お前は、一体何者なんだ……」
食事を終えたレオンハルトが、真剣な眼差しで僕を見つめてきた。
「ただの、しがない農夫ですよ」
僕は笑ってごまかした。まさか、異世界から来ましたなんて言えるはずもない。
レオンハルトは何か言いたげだったが、結局何も聞かずに、ただ僕の顔をじっと見つめていた。
その横顔を眺めながら、僕は思う。
無愛想で、言葉足らずで、いつも険しい顔をしている人。でも、本当はすごく優しい。動物にも、そして僕にも。
もふもふのクロが加わったことで、僕たちの奇妙な同居生活は、さらに賑やかになりそうだ。そして、僕の作る料理が、彼の閉ざした心を少しずつ開いていってくれるなら、これほど嬉しいことはない。
醤油もどきの成功に気を良くした僕は、次は味噌作りに挑戦してみようと心に決めたのだった。
彼は本当に「また来た」。それも毎日。決まって昼食の時間になると、どこからともなく僕の小屋の前に現れるのだ。
相変わらず口数は少なく、表情も険しいままだったが、僕の作る料理を黙々と、そして実においしそうに平らげていく。ニンジンのポタージュ、採れたてレタスのサラダ、ホクホクのジャガイモの塩ゆで。僕が作る素朴な料理を、レオンハルトはいつも空になるまで食べてくれた。
その日も、僕はレオンハルトのための昼食を準備していた。今日のメニューは、森で採れたキノコと野菜をたっぷり入れた炒め物だ。味付けは塩と、香りの良いハーブ。
『やっぱり、醤油があったらもっと美味しくなるんだろうな』
そんなことを考えていた時、森の奥から獣の苦しそうな呻き声が聞こえてきた。それは、ただの鳴き声ではない。明らかに助けを求めるような、悲痛な叫びだった。
「レオンハルトさん!」
ちょうど薪割りを手伝ってくれていたレオンハルトに声をかける。彼はすでに剣の柄に手をかけ、警戒態勢に入っていた。
「ユキナリは小屋の中にいろ」
「でも……」
「いいから!」
レオンハルトの厳しい声に、僕はしぶしぶうなずいた。でも、心配でじっとしていられない。僕は彼の背中を追って、声のする方へと向かった。
森の少し開けた場所に、信じられない光景が広がっていた。
そこにいたのは、巨大な黒い狼だった。体長は二メートルを優に超えているだろう。その漆黒の毛皮は土と血で汚れ、後ろ足には動物を捕らえるための無骨な罠が深く食い込んでいた。狼は苦痛に喘ぎながら、僕たちを睨みつけて低くうなっている。
「下がっていろ。こいつは危険だ」
レオンハルトは僕をかばうように前に立ち、ゆっくりと剣を抜いた。
「待ってください! 殺さないで!」
僕は思わず叫んでいた。狼の瞳は凶暴さよりも、怯えと苦痛の色が濃かったのだ。
「こいつは手負いだ。下手に近づけば襲われる」
「でも、助けを求めてるみたいなんです。罠を外してあげれば、きっと……」
僕の必死の訴えに、レオンハルトは一瞬ためらったようだった。その隙に、僕はゆっくりと狼に近づいた。
「大丈夫、怖くないよ。助けてあげるからね」
僕はできるだけ優しい声で話しかけながら、一歩、また一歩と距離を詰める。狼は依然としてうなり声を上げているが、攻撃してくる様子はない。僕が本気で助けようとしていることが伝わったのだろうか。
狼の足元までたどり着き、罠に手を伸ばした瞬間だった。狼が苦痛に耐えかねたのか、がぶりと僕の腕に噛みつこうとした。
「危ない!」
レオンハルトが僕を突き飛ばす。その直後、彼の分厚い革の手甲が、狼の牙をがしりと受け止めていた。
「レオンハルトさん!」
「問題ない。お前は罠を外せ」
彼は狼の牙を腕で受け止めたまま、冷静に僕に指示を出す。僕はうなずくと、【万能農具】をペンチの形に変化させ、罠のバネに差し込んだ。硬い金属の罠が、いとも簡単にこじ開けられる。
足から自由になった狼は、それでもまだ僕たちを警戒していた。しかし、レオンハルトがゆっくりと腕を引くと、攻撃するでもなく、ただその場でくたりと横たわった。体力を消耗しきっているようだ。
「……終わったか」
「はい。レオンハルトさん、腕は大丈夫ですか?」
「ああ。この手甲のおかげで傷一つない」
レオンハルトはそう言うと、おもむろに水袋を取り出し、狼の口元に水を垂らしてやった。狼は、おとなしくその水を飲んでいる。
僕たちは、動けない狼を二人で担ぎ、僕の小屋まで運んだ。傷口を洗い、薬草をすり込んで布で巻いてやる。幸い、骨は折れていないようだった。
手当が終わる頃には、狼はすっかり落ち着きを取り戻し、僕の足元ですうすうと寝息を立て始めた。
「……お前に懐いたようだな」
レオンハルトが、少しだけ呆れたように言う。
「名前、クロって呼んでもいいですかね。真っ黒だから」
「好きにしろ」
ぶっきらぼうに言いながらも、レオンハルトの表情はどこか柔らかい。彼も、クロのことが心配だったのだろう。
その日の昼食は、少し遅くなってしまった。僕とレオンハルト、そして足元で眠るクロ。奇妙な三人と一匹の食事が始まった。
「そうだ。レオンハルトさん、ちょっと試してみたいものがあるんです」
僕はそう言うと、数日前から試作していた液体を小皿に入れて持ってきた。大豆に似た豆と小麦に似た穀物を発酵させて作った、醤油もどきだ。
「これは?」
「僕の故郷の調味料です。魚の塩焼きにつけてみてください」
ちょうど焼いていた川魚を一切れ、レオンハルトの皿に乗せる。彼は半信半疑といった顔で、醤油もどきを少しだけつけて、魚を口に運んだ。
次の瞬間、レオンハルトの目が見開かれた。
「なっ……なんだ、これは!?」
驚きのあまり、声が裏返っている。
「塩辛いだけじゃない。深い……味わいがある。魚の旨味を何倍にも引き立てている……!」
彼は夢中になって、魚を食べ進めていく。よほど気に入ったらしい。その食べっぷりを見ているだけで、僕まで嬉しくなってくる。
「ユキナリ。お前は、一体何者なんだ……」
食事を終えたレオンハルトが、真剣な眼差しで僕を見つめてきた。
「ただの、しがない農夫ですよ」
僕は笑ってごまかした。まさか、異世界から来ましたなんて言えるはずもない。
レオンハルトは何か言いたげだったが、結局何も聞かずに、ただ僕の顔をじっと見つめていた。
その横顔を眺めながら、僕は思う。
無愛想で、言葉足らずで、いつも険しい顔をしている人。でも、本当はすごく優しい。動物にも、そして僕にも。
もふもふのクロが加わったことで、僕たちの奇妙な同居生活は、さらに賑やかになりそうだ。そして、僕の作る料理が、彼の閉ざした心を少しずつ開いていってくれるなら、これほど嬉しいことはない。
醤油もどきの成功に気を良くした僕は、次は味噌作りに挑戦してみようと心に決めたのだった。
416
あなたにおすすめの小説

植物チートを持つ俺は王子に捨てられたけど、実は食いしん坊な氷の公爵様に拾われ、胃袋を掴んでとことん溺愛されています
水凪しおん
BL
日本の社畜だった俺、ミナトは過労死した末に異世界の貧乏男爵家の三男に転生した。しかも、なぜか傲慢な第二王子エリアスの婚約者にされてしまう。
「地味で男のくせに可愛らしいだけの役立たず」
王子からそう蔑まれ、冷遇される日々にうんざりした俺は、前世の知識とチート能力【植物育成】を使い、実家の領地を豊かにすることだけを生きがいにしていた。
そんなある日、王宮の夜会で王子から公衆の面前で婚約破棄を叩きつけられる。
絶望する俺の前に現れたのは、この国で最も恐れられる『氷の公爵』アレクシス・フォン・ヴァインベルク。
「王子がご不要というのなら、その方を私が貰い受けよう」
冷たく、しかし力強い声。気づけば俺は、彼の腕の中にいた。
連れてこられた公爵邸での生活は、噂とは大違いの甘すぎる日々の始まりだった。
俺の作る料理を「世界一美味い」と幸せそうに食べ、俺の能力を「素晴らしい」と褒めてくれ、「可愛い、愛らしい」と頭を撫でてくれる公爵様。
彼の不器用だけど真っ直ぐな愛情に、俺の心は次第に絆されていく。
これは、婚約破棄から始まった、不遇な俺が世界一の幸せを手に入れるまでの物語。

【土壌改良】スキルで追放された俺、辺境で奇跡の野菜を作ってたら、聖剣の呪いに苦しむ伝説の英雄がやってきて胃袋と心を掴んでしまった
水凪しおん
BL
戦闘にも魔法にも役立たない【土壌改良】スキルを授かった伯爵家三男のフィンは、実家から追放され、痩せ果てた辺境の地へと送られる。しかし、彼は全くめげていなかった。「美味しい野菜が育てばそれでいいや」と、のんびり畑を耕し始める。
そんな彼の作る野菜は、文献にしか存在しない幻の品種だったり、食べた者の体調を回復させたりと、とんでもない奇跡の作物だった。
ある嵐の夜、フィンは一人の男と出会う。彼の名はアッシュ。魔王を倒した伝説の英雄だが、聖剣の呪いに蝕まれ、死を待つ身だった。
フィンの作る野菜スープを口にし、初めて呪いの痛みから解放されたアッシュは、フィンに宣言する。「君の作る野菜が毎日食べたい。……夫もできる」と。
ハズレスキルだと思っていた力は、実は世界を浄化する『創生の力』だった!?
無自覚な追放貴族と、彼に胃袋と心を掴まれた最強の元英雄。二人の甘くて美味しい辺境開拓スローライフが、今、始まる。
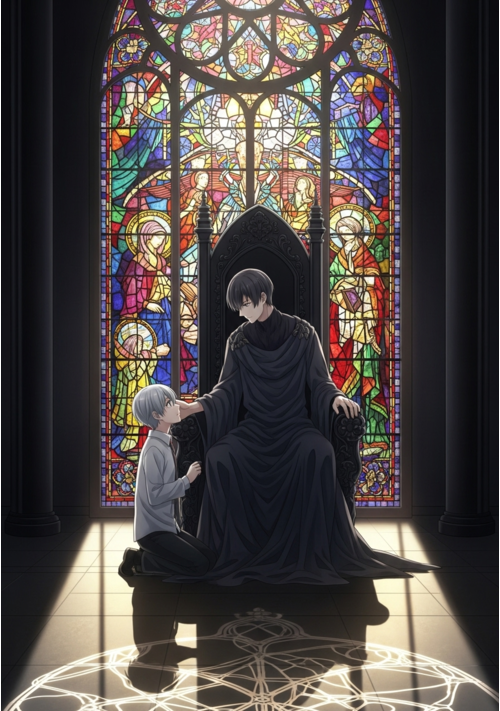
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

最強賢者のスローライフ 〜転生先は獣人だらけの辺境村でした〜
なの
BL
社畜として働き詰め、過労死した結城智也。次に目覚めたのは、獣人だらけの辺境村だった。
藁葺き屋根、素朴な食事、狼獣人のイケメンに介抱されて、気づけば賢者としてのチート能力まで付与済み!?
「静かに暮らしたいだけなんですけど!?」
……そんな願いも虚しく、井戸掘り、畑改良、魔法インフラ整備に巻き込まれていく。
スローライフ(のはず)なのに、なぜか労働が止まらない。
それでも、優しい獣人たちとの日々に、心が少しずつほどけていく……。
チート×獣耳×ほの甘BL。
転生先、意外と住み心地いいかもしれない。

猫カフェの溺愛契約〜獣人の甘い約束〜
なの
BL
人見知りの悠月――ゆづきにとって、叔父が営む保護猫カフェ「ニャンコの隠れ家」だけが心の居場所だった。
そんな悠月には昔から猫の言葉がわかる――という特殊な能力があった。
しかし経営難で閉店の危機に……
愛する猫たちとの別れが迫る中、運命を変える男が現れた。
猫のような美しい瞳を持つ謎の客・玲音――れお。
彼が差し出したのは「店を救う代わりに、お前と契約したい」という甘い誘惑。
契約のはずが、いつしか年の差を超えた溺愛に包まれて――
甘々すぎる生活に、だんだんと心が溶けていく悠月。
だけど玲音には秘密があった。
満月の夜に現れる獣の姿。猫たちだけが知る彼の正体、そして命をかけた契約の真実
「君を守るためなら、俺は何でもする」
これは愛なのか契約だけなのか……
すべてを賭けた禁断の恋の行方は?
猫たちが見守る小さなカフェで紡がれる、奇跡のハッピーエンド。

【完結済】スパダリになりたいので、幼馴染に弟子入りしました!
キノア9g
BL
モテたくて完璧な幼馴染に弟子入りしたら、なぜか俺が溺愛されてる!?
あらすじ
「俺は将来、可愛い奥さんをもらって温かい家庭を築くんだ!」
前世、ブラック企業で過労死した社畜の俺(リアン)。
今世こそは定時退社と幸せな結婚を手に入れるため、理想の男「スパダリ」になることを決意する。
お手本は、幼馴染で公爵家嫡男のシリル。
顔よし、家柄よし、能力よしの完璧超人な彼に「弟子入り」し、その技術を盗もうとするけれど……?
「リアン、君の淹れたお茶以外は飲みたくないな」
「君は無防備すぎる。私の側を離れてはいけないよ」
スパダリ修行のつもりが、いつの間にか身の回りのお世話係(兼・精神安定剤)として依存されていた!?
しかも、俺が婚活をしようとすると、なぜか全力で阻止されて――。
【無自覚ポジティブな元社畜】×【隠れ激重執着な氷の貴公子】
「君の就職先は私(公爵家)に決まっているだろう?」
全8話

沈黙のΩ、冷血宰相に拾われて溺愛されました
ホワイトヴァイス
BL
声を奪われ、競売にかけられたΩ《オメガ》――ノア。
落札したのは、冷血と呼ばれる宰相アルマン・ヴァルナティス。
“番契約”を偽装した取引から始まったふたりの関係は、
やがて国を揺るがす“真実”へとつながっていく。
喋れぬΩと、血を信じない宰相。
ただの契約だったはずの絆が、
互いの傷と孤独を少しずつ融かしていく。
だが、王都の夜に潜む副宰相ルシアンの影が、
彼らの「嘘」を暴こうとしていた――。
沈黙が祈りに変わるとき、
血の支配が終わりを告げ、
“番”の意味が書き換えられる。
冷血宰相×沈黙のΩ、
偽りの契約から始まる救済と革命の物語。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















