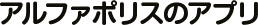385 / 551
五章 ローレル迷宮編
傀儡の乱、終焉
しおりを挟む
この世には数えきれない程の精霊が存在する。
その殆どが自我を持たず自発的な行動も起こさない無害な存在である。彼らは多くのヒューマンからは認識さえされていない。
明確な自我が持たずとも個として存在し、本能による自発的行動を起こす存在がそれなりに。彼らは下位精霊と呼ばれている。
確固たる個体として存在し意思を疎通できる存在が少ないながらに在り、彼らは中位精霊と呼ばれている。
精霊魔術を扱う多くの術師にとってこの中位精霊と意思を交わし使役する事は人生の目標でもある。
その形状から実力に幅がある中位精霊の更に上、属性の頂点に君臨する唯一つの存在が上位精霊だ。
世界に上位精霊は六体のみ。火水風土光闇にそれぞれ一体のみが存在し、女神の使い、又は彼女に準ずる存在として畏敬の対象となっていた。
上位精霊を精霊魔術によって使役する事は不可能。
その意思に触れ、助力を得られるだけでもヒューマンにとっては偉業。
だからこそローレル連邦の巫女は代々、水の精霊と交信が出来る存在として尊敬を集めている。
急流河川が多いローレルでは治水において大きな恩恵を授かれる水の精霊との交信は国の維持と発展に欠かせないものだ。
火や風、土といった他属性は国を挙げて信仰されているという事はなく時折出現する英雄と個々に関わりを持つ程度という事を考えると、ローレル連邦と水の精霊の関係がいかに特殊なものかがわかる。
その成り立ちには符術の祖にして稀代の精霊使いでもあった初代の巫女、緋綱が大きく関わっているのだが……ともあれ現在のローレルにおいて水の精霊への信仰は絶大なものがある。
はっきりさせてしまうなら、女神よりもよほど熱心に拝まれていた。
女神は水の精霊の主人だからと、ついでに祈られている存在。
賢人を自ら望んで抱える事といい、異色な国家である。
されど大国の一角に名を連ね、変わらぬ在り方も貫く。
治水や数々の奇跡。
ローレルにおいて水の精霊がもたらす利益は小さなものから大きなものまで幅広い。
だが……では上位精霊としての力はどれほどのものなのか。
この世界において、大国一つ分の人々の信仰を一身に受ける水の上位精霊。彼女は女神に次ぐ存在といって過言ではない。
「一瞬女神の介入かと思うたが……精霊の方じゃったか」
やや面白くなさそうに呟いたのは巴。
上空の戦いを見上げつつ、嫌な奴に会ったような表情を浮かべていた。
先ほどまで妖怪大戦争を目をキラキラさせて時にテンションの上がり過ぎで地団駄を踏む程だった彼女とは随分な変わり様だ。
「巴さんと識が二人がかりで諦めざるを得なかった相手でしたっけ?」
「誤解を招く言い方はよさんか。あの女が若の魔力を吸収したのが気にくわんのはわかるがの」
「……ふん」
「この国への影響を考えると、どうやっても表沙汰になると判断したから一旦手を引いただけじゃよ。それだけローレル連邦と水の上位精霊の関係は旧く濃い」
「アレら精霊というモノは女神の使いですものね。上位竜とは違って信仰を得る事でも力を増す……」
「まったく。上位竜から見れば、奴らは我が物顔で好き勝手に振る舞う厄介な寄生虫のような存在、じゃろーなー。あくまで上位竜に立って考えてみたら、じゃがー」
「……上位竜から見れば、ですか。はいはい」
金色の光と、淡く澄んだ青光を纏った遥歌と真の戦い。
それは上空で展開され、時に街に破壊の光を降らせながら、今も継続中だ。
真は藍色を纏い、金と藍の光がたなびく尾を残しながら激突し合い、時に絡み合い。
出鱈目な魔力量から繰り出される高位魔術とスキルの入り乱れる様は、さながら博物館の様。
だがそんなとびっきりの戦いを目にしても巴と澪の様子は特に変わりない。
それ以前と同じこの場に残り、学生を保護し雑談をする程度。
「精霊様が、お母様に?」
「いくら巫女様がご不在だからといって、そんな事が……」
かすれ震える声で唖然と呟いたのはいろは。
疲労か精神的な要因かは不明だが未だ立ち上がれず横になっている彼女を支えるイズモもまた青い顔をしている。
無理もない。
彼らにとって水の上位精霊は信仰の対象。
神に等しい存在なのだから。
巫女としか交信しない神に等しい存在が今、その力の一端を遥歌に貸しているかもしれないと考えるだけで身が震えるのだ。
「で、どうみます、巴さん? アレの力の程を」
「儂らと同格、もしくはそれ以上じゃろ」
「対策なくぶつかれば分が悪いと。癪ですけど同感です」
「とはいえ儂らは若ではないしの。無策で上位精霊とエンカウントなんぞあり得ん。そして対策をしっかりした上でなら、負ける事はあるまいよ」
「ですわね」
『!?』
特に感慨もなく言い放った巴の言葉に澪は少しだけ瞳を細め、聞いていたジン達は一様に目を見開いた。
それは、超人や英雄そのものな戦いをやっている遥歌と巴、澪が互角であるかもしれないという事への驚き。
詳細には遥歌がそれくらいヤバイ存在だったという事への驚きと、巴と澪がこれほどの猛者だったのかという二つの驚きによる反応だった。
(という事はそのお二人を追い回すらしい先生は……一体……)
ただ一人、ジンだけはその先にいる人物、ライドウへの畏怖も一足先に心に刻んでいたが。
最早首の疲れも気にする事なく起こっている事全てを目に焼き付けておこうとする学生達。
回復してもらい体の負傷は治っても気力まで満ち溢れるものではない。
それでも、横になって休みたいという気持ちよりも、全てを見届けたいと思う気持ちの方が全員一致で勝っていた。
「巴、殿」
「ん? ……おお、コウゲツ殿か。貴殿が見えられたという事は乱心した者どもの回収も粗方終わったとみても?」
弱弱しいながら、低くはっきりした声で名を呼ばれた巴が振り返る。
そこには遥歌の奇襲に対応して出動したカンナオイの部隊をまとめていた男、コウゲツの姿があった。
「ああ。アレを除いては、だが。水色と金色のが……遥歌なのだろう?」
「うむ」
「で相対するのが君たちの主、ライドウ、殿という訳か」
「御推察の通り」
「彩律め、あんなモノを一体どうやって……。いや、最早詮無き事か。ともあれ巴殿。この老い先短い命と未来を担う若い命を救ってくださった事、改めてお礼申し上げる」
「構わんよ」
「事もなげに仰る。あのような奇跡――」
「儂も自分の力に馴染んでおく必要があった。若の命令もあった。故に貴殿らはただ、そう運が良かったのだと思えばいい。それに一度死んだ身なら、そこから数多の教訓を得てもいよう。これより先、存分にそれを伝えていけば良いさ」
巴は蘇生を行なった事への礼をさもどうでもよい事の様に流す。
ただその経験を大事にして次に活かせと、それだけ伝えた。
教訓。
今回のソレがどんなモノになるのかは、コウゲツらの想像力にもよるが、巴からの巧妙な恩の押し売りでもある。
恐怖の刷り込みともいう。
遥歌に惨殺された彼らだけに、トラウマを抱え今後兵士という職を辞する者も出てくるだろう。
「あれさえも、巴殿には造作もない事と?」
「まさか。随分と手間のかかる面倒な仕事であったよ。若の命でなければ二度と御免じゃな」
「……」
あれだけの行い。
コウゲツが口にしたそれは、ただの死者蘇生ではない。
無論死者の蘇生自体も凄まじい高等魔術であり、おいそれと扱えるものではない。
しかし巴がやったそれは、遥歌によってミンチにされたり、文字通り赤い飛沫にされて絶命した者、それに炎と熱で焼かれて影だけしかこの世に残っていなかった者までを全て五体満足の状態で復活させるというもの。
土くれからの再生。最早それは奇跡と呼んで遜色ない御業だった。
片足だけ残っている状態から最初にこの世に呼び戻されたコウゲツはその奇跡の全てを目の当たりにしたのだ。
あー、いきすぎじゃー! とか。
そこは違うじゃろ!? とか。
どうしていきなりそっちに繋がるかー! とか。
そんな緊張感のない言葉で奇跡が為されるのを見ていたコウゲツに、既にクズノハ商会へのわだかまりはなかった。
ずぶずぶと土から人の体が成っていき、その肉に生気が宿り目が開き、そして自分を見て隊長と呟く。
まるで神話だ。
コウゲツは野心より何よりこの事態の収束を望んだ。
自分の焦りが生んだこの悲劇から街を救いたいと切に願った。
だから、彼は奇跡を終えた巴から協力を求められた時、内容が襲撃者の保護だったとしても即断で了承した。
その決意は上空の光景を見ても変わらない。
彼とて敬虔とは言えないが人なみに精霊への信心はある。
遥歌に精霊が力を貸しているのかもしれないと考えはしても、一度死を経験し、復活を遂げた彼はどこか冷めた目で事実を受け入れていた。
第一その遥歌と少なくとも互角に戦いをしている者がいる。
ただの遥歌とでさえ驚異的なのに、精霊が力を貸しているらしい彼女と。
だからこの両方の事実をきちんと自身の天秤に置き、戦いの推移を気にしながらコウゲツは巴と澪、いろはがいる場に足を運んだ。
恩人と戦いの結末と、以後の自らの身の振り方を決める為に。
「あの女の人、どんどん……強くなってる。今攻撃を受けたらジュウキが一撃で粉々にされそう」
「正解です。流石若様の生徒、中々良い目をしてますね。もっと精進しなさいな、上手に扱えるならその内マークツーをあげますから」
「ええ!?」
ユーノの悔しさを通り越した諦めの言葉に、澪が予想外の言葉を掛ける。
「それにミスラ、ですか。お前も中々どうして。もう英雄の領域に片足突っ込んでますね。潔いまでの防御特化。とことんまでパーティ主義。気に入りました」
「え、ええ!?」
「巴さんが食いつくのもわかる気がします。ユーノとの連携も実戦の中で主導し構築していく防御の鬼。ふふ、一点特化に惹かれるのは若様の影響かしら」
楽し気にユーノとミスラを撫でる澪。
巴一人でも十分な地獄を見ているというのに、この上もう一人増えたら身が持たないと恐怖に震えるミスラ。
一方ユーノはマークツーという響きに目を輝かせつつ、先の戦いでのミスラを振り返り、うんうんと何度も頷いていた。
(そうだった。ミスラ先輩からの指示で連携するようになって凄く動きやすかった。思えばパーティの盾としての心構えなんて、私全然出来てなかったもん。本当に、凄かったな……今日のミスラ先輩……)
しかも火力としてスキルを使う時にはきっちりユーノを前線に送り届ける。
彼はまさに防御職人だった。その技量の高さを彼女は肌で感じ取ったのだった。
澪からはお褒めの言葉を、ユーノからは微かに熱い視線を送られつつミスラは直立不動で上を見上げていた。
「確かに凄い。凄いけど……何か違う。あれは初めて目にする濃さの精霊の力だけど……何か……」
シフが上を見ながらブツブツと呟いている。
巴から精霊の存在を教えられ、納得できたようで出来ていない。
精霊の力を借りる魔術師である彼女からみて、今の遥歌の状態はよくわからないものだった。
精霊を自身の身体に降臨させているようでそうではない。
そもそも上位精霊を身に宿そうなどとすれば大抵の場合人の器が消し飛ぶ。
ローレルでも巫女の数人が降臨の儀を行ない大きな奇跡を起こしてはいるものの、例外なく数分で命を落としている。
生命力と精神力が焼き切れての死。まだ五体満足な遺体が残るだけ巫女は凄い。
しかし遥歌はまだ生きている。もう数分などとうに過ぎ去ったというのに。
では上位精霊の力を貸与されているのか。
それにしては場に何者かの意思が濃密に存在している。
今の遥歌はまるで、精霊とヒューマンが一体となって戦っているような、精霊単体での顕現と人の器をかりての降臨の良いとこどりをしている、そんな奇妙な様子だった。
現実にはそんな虫の良い状況など作り出せる筈がなく、もしも顕現にせよ降臨にせよこれほどに効率の良い方法があるのなら誰もが飛びつくであろう。
シフとてその一人だ。
遥歌のこの在り様を頭に焼き付ける。
いずれ大地の精霊を召喚、顕現させ自らの力とする時に参考にする為に。
今はまだ叶わない目標ではあるけれど、未来の為に現状唯一出来る事はこの戦いを見て考える事と彼女は結論付けた。
(とはいえこのローレルで水の精霊が巫女以外にこれ程力を貸した戦いなんてものは、すぐに箝口令が敷かれるとみて間違いないけれど、ね)
他言は出来なくとも、価値は色褪せない。
「あの高みに……識さんがいる」
アベリアは学ぶ、考えるというよりも胸に秘めた一つの決意を確かめるように上を見ていた。
クズノハ商会との関わり方が少し前に変わった彼女にとって、目指す人の背中があそこにあるとわかる光景は貴重だった。
遥歌の姿は今はまだ遥か彼方。
一合も叶わず斬り捨てられる。
肩を並べる事はない、三歩後ろで良いんだと考えてみたところでやはり目標と現在の自分の距離はあまりにも遠い。
ライドウとぶつかり合う遥歌の姿は、しかし、アベリアをさほど絶望させる事はなかった。
(でも識さんは私の手をとって引っ張ってくれている。今は無理でも、いつか、絶対に。ライドウ先生にも私を見てもらう。そうしたら、先生の事、若様って呼んでもいいよね)
別に今のままでも真は乞われれば諦めたように頷いてくれるであろう。
しかし、アベリアは少しだけずれた自分の目標を胸に力強く導いてくれる識の為にも、自分ではなく識を信じて力を尽くそうと改めて覚悟を決めた。
ちらりと横目でその様子を見ていた巴が呆れたような、少し楽しそうにも見える表情で小さく溜息をついていた。
「……すげえよな」
『?』
ぼそりとダエナが口を開いた。
短くそれだけ口にした彼に学生たちの視線が集まる。
「あの遥歌って女性、滅茶苦茶強かった。本気を出してなくても俺らなんかとは格が違った」
『……』
「なのに先生はそんな人を相手にしても、やり返してくれてる。追い詰めて、引き出しを開けさせて全力を出させて。その上で一歩も引かないどころか……押してる。世界って、こんなに広いもんなのか? こんな……途方もないもんなのか?」
『……』
「冒険者でも騎士でも魔術師でもさ。生え抜きだのアカデミーだの学園卒だの……本当にくだらねえレベルの争いなんだな。外の世界はこんなだぜ。絶対の存在に見えてもそれを押し潰す絶対がいる。終わりがねえ……」
返ってくる言葉は無かった。
上空の戦いは確かに、レベルが違っていたから。
自らの糧にする事は出来ても、将来そこに自分が参加できるかといえばその答えは否、だろう。
選ばれた者の戦い。
実際にそれがあると受け止めた時に、自分のやってきた事が虚しくなる経験は誰にでもある。
しかし如何に虚しく思えようと、無駄ではない。
ダエナの言葉には自棄をうかがわせる悔しさを超えた諦めがあったが、誰もそれを否定してやる事が出来ずにいた。
「……ぷ、はは、っあはははは! なるほどなるほど、中々どうして。ひよっこはひよっこなりに思い悩むという事か!」
「っ?」
唐突に噴きだした巴の姿を見てダエナが言葉を詰まらせる。
見れば澪も扇を口元に当て、笑いをこらえている様子だった。
ダエナから見て選ばれた者の側にいる二人の反応に、彼はおおいに戸惑った。
「と、巴さん。いち、一応、ふふ、この子どもとて、己を、ぷふ、儚んでの思いの丈と……うふっ」
フォローらしき澪の言葉も今一つ意味を成していない。
ダエナの自虐を含んだ告白が如き独白が、どういう訳か巴と澪のツボに入ったらしかった。
「あー……子持ちのカトンボ。ダエナじゃったか。まず、一言良いかの?」
ひとしきり笑った後、わざわざダエナの正面まで出向き巴は彼の肩に手を置いて瞳を真正面から見つめて口を開いた。
一方のダエナはただ頷くのみ。
「思いあがるな」
「っ!!」
「お前たちは確かに若と識の指導と好奇心の結果、学生にあるまじき力を手にし、今己の持つ可能性に夢も見ていよう。それは良い。大いに突っ走れ。じゃがな、思いあがるな」
「思いあがっているつもりなんて、ありませんけど」
「良いか? ここには若がおらんで、まあ言葉を選ばず分かりやすく言ってやるが。今あそこでやりあっとるのはな?」
「……」
「片方は天才じゃ。それも儂の見る限りたった一つしか弱点がないような、御伽噺に出てくる英雄クラスの天賦の極み」
「……なら、もう片方は……」
「その英雄サマでも手も足もでん大魔王、化け物じゃよ。そんな戦いに未だ凡人に片足つけとるお前らが挑戦できる訳ないじゃろう? あの中に飛び込めば儂とて怪我をする」
「確かに、私も着物だけじゃ済みそうにありません。怪我もそこそこするでしょうねぇ」
巴の言葉に澪が頷く。
笑いのツボからはどうにか脱出できたようだ。揺り返しへの油断は禁物だが。
「良いか? 今日この戦いを頭に刻み込んでおいてな、いつか自分の力が最盛期にあると感じた時、あの女の方をイメージして戦ってみよ。一分も持てば立派なもんじゃ。その力で守れぬようなモノを抱えていたなら、それは分不相応というものじゃろうよ」
「一分……ですか」
「そうじゃ。あれはそういう戦いじゃよ。お主らにとってはな。これ以上ない程の物差しになろう」
「でも巴さん。天賦の極みと仰いましたけど、先生は圧倒的じゃないですか。ああなった遥歌という女性ですら必死で……」
「ジンか。馬鹿者、若と比較してどうする? それこそ全くの無意味。ほれ、やつの動きをよく見てみい」
「え?」
ダエナが口を一文字に結び思考モードに入ったタイミングで、今度はジンが巴に尋ねた。
巴が英雄と化け物の戦いと評した事に違和感を覚えたからだろう。
問われた巴は馬鹿者とジンをたしなめ、そして戦いの様子を指さした。
「限界まで高められた肉体、そして技。更に水の精霊の力を駆使した数々の回復魔術に五十を超えるスキルの駆使。これが天才でなくて一体何を才と呼べば良い?」
「……」
遥歌が揮う必殺の一撃の連発。
力と技と経験を駆使した攻め、受け、守り、回避。
空中という特殊な地形でありながらまるで地上を駆けるかのように縦横無尽に動く様は、生まれた時から空の住人だったかに思えてならない程。
一振りの隙をもう一振りで消し、両手の武器を叩きつけた隙は術で消す。
真の反撃を正確に把握し、回避しきれない攻撃は予め回復魔術を仕込んで対応、攻め手を緩める事は一切ない。
例え真が人の反応を逆手に取り、防御回避はおろか反応さえ難しい攻撃を仕掛けてもスキルの強制動作で避けてみせる。
更にはスキルを次のスキルで上書きして隙を無くす。
そんな行動に加えて精霊の力によるトラップや攻撃魔術まで活用する。
確かに、注目してみればどれもが凄まじい技術ばかり。
攻撃力や防御力などはもとより、遥歌の行動全てが誰かにとっての糧になるような。
まさに戦闘の天才というべき戦いぶりだった。
ただ大魔王がその全てに笑うしかない切り返しをしているだけ。
そう、大魔王は倒せない。理不尽の塊。
「ほれ、迎撃でそこを撃ち抜かれるとわかっておりながら事後発動の魔術を仕込んで加速、若の首を狙いにいきおった。いや、それだけでは飽き足らず斬り抜き様に背から心の臓を一突き、叶わず反撃に晒されても……更に上に逃げおった。最後のアレは上に跳んで斬りかかるスキルの初動かのう」
「……凄い」
「じゃろ? あの女が見せておるのはヒューマンとして、ある意味で最善の戦い。ソフィアや響とは違う目線からの戦い。故に……アレも今を好機と見てあの女に乗ったんじゃろうが……そこは早計よな」
ならどうして、自分はどこかで遥歌を大した事がないと感じてしまったのか。
ジンが抱いた疑問への答えは単純だ。
彼の先生という立場にいる人物が、彼女を圧倒しているから。
だから……ジンは遥歌を、精々が自分たちの延長線上にいる存在なんだと過小評価してしまっていた。
「いやはや、見惚れる程の高等技術のオンパレード。対等な相手がいないからと戦いを厭うておった女がブランク明けの実戦でこれじゃからな。人とは恐ろしいものよ」
その高等技術も全て受けられ、もしくは撃ち落とされてしまっては若い目には正当な評価が下せなくとも無理はない。
「ええ、本当に。やはりヒューマン、人という種こそが本当に恐ろしいのでしょうね……」
どこか哀れむような声音の澪。
「む……」
「巧妙に隠していますけど、気勢が変わりましたね。これは、仕掛けますか」
『え!?』
巴と澪が感じた微かな変化は、ジン達の目には全く見て取れなかった。
変わらずぶつかり合うライドウと遥歌の戦いを見守る事しか出来ない。
決着が近いのかもしれないと感じたいろはの手が、イズモの手を強く握る。
そして上の戦いを見つめたまま、彼は小さな手を握り返した。
「つまり決着か。フツからの頼まれ事など面倒の匂いしかせんかったが、得るモノも多い夜になったのう」
「お味噌もお醤油も守れましたし、夜更かし一回程度の価値は十分ありました」
遥歌の手から黒と白の薙刀が離れる。
束の間、戦いに静寂が差し込んだ。
◇◆◇◆◇◆◇◆
怯えた目だ。
遥歌さん。
この人は、戦いに向いてない。
技も体も信じられないレベルで身に付いた人だけど。
ただ一つ。
彼女には、心が備わっていない。
僕とは……違った意味でね。
同じレベルかそれ以上の相手がいれば戦いに意味を見出す?
遥歌さんに関して言うのなら、それは間違いだ。
ここまで……適度に追い詰めて、彼女の扱うスキルや術を晒させてみた。
閃きやその場での成長もあって結構な作業だったけど、もうそろそろ必殺の策くらいしか残っていないだろう。
怖いんだ、遥歌さんは。
負傷が怖い、敗北が怖い、死が怖い。
そんな恐怖を全く克服できてない。
というか、これまでの人生で彼女はその恐怖を感じる事なく圧倒的な才能で生きてこられたのだろう。
戦場に出る事を強いられながらも。
そっちは正直驚異的だし、なんという勝ち組と驚くばかりだ。
巫女でもないのに上位精霊をその身に受け入れて自我も失わず戦えているというのも滅茶苦茶。
無駄な仮定だけどタイマンまで持ち込めるなら、ゼフさんでさえ生まれ持ったものだけでミンチにしかねない。
……そういう意味では智樹と直接接触してなかったのは良かったというべきなんだろうか。
ん。
不意に肩を荒々しく上下させていた遥歌さんが手から薙刀を二本とも手放した。
黒と白の彼女の得物は下に落下していく事なく、主の左右に浮遊してる。
「終わりにする覚悟は出来ました?」
「……そう簡単に終わりにする気はありません。お前に、一矢報いる事さえ叶わぬ今は、特に」
「確かに。戦いというものを教えてくれる、筈でしたっけ」
「!」
「今のところ、立場が逆みたいですけどね。遥歌さん、確かに貴女は才能溢れる人だ。素直に凄い。その貴女が持てる力の全てで僕にぶつかる。なるほど、水の上位精霊がその身に降臨するなんて博打に出る気持ちもわからんでもないです」
「……そう、気付いていたの」
「ええ、まあ。ただ……そこについては全部が計画通りって訳じゃなく、期せずしてこれ以上を望めない状況が揃って勝負に出た、って感じがするんですけどね。後で聞くのも悪くないかな。って、今はそんな事はどうでもよくて」
「……っ」
「……怖いんでしょ、遥歌さん」
「!?」
「わかりますよ。バレバレです。もう必死で、本当に必死で僕に食らいついてきたその瞳。かつてない位苛烈で独創的で強力で……なのに全く戦士の闘志は感じなかった。戦いへの渇望? 貴女にはそんなものはありませんよ。何かを感じたのだとしたら、それはきっとこ――」
おっと。
子どもを授かるか産むかして母性をこじらせた時期じゃないんですか。
そんな事を言おうとして何とか言いとどまる。
わざわざ指摘する事もない。
女性として、ただ幸せに、愛する男性と子どもと家族を作って生きていく事に一番の幸せを感じるのが本性なのだと。
既に血に塗れここにいる彼女には、もう余りに遅過ぎるだろう。
「う……」
「智樹の魅了も解いて、精霊の意思さえ不完全ながら支配下に置きながら、貴女は僕とじゃなく恐怖と戦ってた。心だけが伴わない。ふふっ、なんというか……僕と似てる」
「化け物に似てると言われて喜ぶ者などいませんよ」
「認めますか。もうアイツの魅了の影響下にないって事は」
「っ」
なら投降すればいい。
それで戦いは終わる。
でも彼女は己と精霊の力をもって僕に挑んできた。
全能感への慢心、僕を排そうとする精霊の意思の影響?
確かにそれもあるかもしれない。
「……死ぬ心算ですか?」
恐怖と戦いながら。
死にたくないと全力を尽くしながら。
この女性は、ここで死のうとしている。
「心を読むのは下衆な行いとしりなさい」
「読んだ訳じゃありませんよ。ただ、貴女がそう心で叫びながら僕に攻撃をし続けていただけだ。嫌でも伝わる」
「……私は」
「最良の結末は、僕を殺して死ぬか、僕と一緒に死ぬか。そういう最後を貴方は望んでる」
「……」
「魅了が解けた所で、過去は変わらない。智樹への愛慕を理由に奪った命も、本当に大切にすべき人達に対してとり続けた態度も行いも、無かった事になりはしない。ただ、その記憶を持ったまま正気に戻った者だけが、残される」
あまりにも残酷だ。
魅了の影響下にあった期間やしでかした事にもよるだろうけど、生きていく事に絶望する程。
いっそ、そのまま命を摘み取ってやった方が慈悲である程。
といいながら、今回の僕については……。
遥歌さんから返事は無かった。
代わりに彼女の中にある圧倒的なまでの水の力の塊が圧縮され、練り込まれながら体の外に出てくるのを感じた。
僅かな水の精霊の抵抗の意思も。
けれど、今あの体にある全ての力の優先権は遥歌さんの方が持ってる。
僕への敵意や遥歌さんへのアドバイスなど、意思はあるようだけど力の行使は出来ないみたいだな。
もっともその方が上手く力を扱えている辺り、人の才の行き着く果てへの畏敬を感じるところだ。
元々百鬼夜行のスキルで召喚に関連する力の扱いは慣れていたってのもあるかもなあ。
しかし……つくづく召喚って凄い可能性がある魔術分野だな。
アズさんといい遥歌さんといい、人外クラスばかりを目にしているからというのもあるけど……うん、終わったら識と相談してジン達や下の生徒への講義に加えられないか検討。
「嘘ぉ、精霊の力の創ぞ、いや、これは百鬼夜行との……コラボ的な?」
新しい講義に意識が向いている間に遥歌さんと僕の間に奇妙な形をした六枚の氷の盾らしきものが出現した。
一瞬精霊の魔力を利用して創造をやってのけたかと思ったけど、違った。
水か氷と相性が良い妖を同時に呼び出して核にし、濃密な精霊の力を武具の形に映した。
ぼ、僕の魔力体よりも高度な気がする。
いや今だって重宝してますよ? かけた時間に後悔もありませんとも。
でもさ、僕はひと夏かけたのに……今?
ここまでもやたらとセンス溢れるスキルと魔術の連携を見せつけてくれたのに、そうかー……今かー今出来ちゃうのかー。
「もう、語るべき事もない。ただ、砕けるのみ!」
泣きそうな目でそう言われても!
六枚の盾、二本の薙刀。
近接戦闘のエキスパートが八刀流で遠距離型の僕を詰めにかかるとか、死にたくない癖に死ぬって決めてる人は迷いが無い! 意味が分からん!
どう考えてもあの盾はただの盾じゃないし。
服を赤に変えて一気に後退するも、遥歌さんはお構いなしの考えなしってな風に追ってきた。
右手の人差し指と中指を伸ばした先に作った仮死針はそのまま、とりあえず様子見のブリッドを六枚の盾全部に当ててみる。
はい、軌跡が曲げられた。
盾に当たる事もなく、六つのブリッドが遥歌さんを避ける様に明後日の方向に消えていく。
なら次だ。
意識を遥歌さんと盾の一つに合わせ、必中を確信して再度ブリッドを放つ。
威力は月の術よりも少し強め。
当たれば相応に痛い、筈。
さて……。
「マジか、おい」
結論から言えばどっちも失敗した。
盾に命中したブリッドは一瞬で砕かれてキラキラした塵になった。
凍らされて砕かれた? ってとこだろうか。
まあ、そっちはとりあえずいい。
問題は本体を狙った方だ。
こともあろうに……外れた。
正確には、今回は狙ってなかった盾の一つが一瞬遥歌さんの姿になってブリッドが、それ目指して逸れた。
もちろん、その後はもう一つと一緒。
砕けてキラキラになった。
……ちっ。
「っ」
「……」
上の僕と下の遥歌さん。
このまま次を仕掛けると、下手に逸らされるとブリッドじゃ街に被害が出るかもしれない。
だけど他の手で終わらせるのは……面白くない。
確かに中る絵は見えてたのに、外れたってのが、面白くない!
あの盾、舐めくさってくれる!
手の位置に魔力を固めて姿勢を反転。
そのまま下に向けてその足場を思い切り蹴る。
即座に距離を詰めてくる僕に対応して遥歌さんが六枚の盾を僕を囲む様に展開しつつ薙刀を操って斬撃から刺突のコンビを仕掛けてくるも、何とか彼女を通り過ぎる事に成功。
位置関係は逆、上の遥歌さんと下の僕に変わった。
これなら思い切り、試せる。
「ほんの数秒だろうけど、やらせてもらう」
威力は高く保ったまま属性を入り乱れさせ、遥歌さんと盾のあらゆる場所に狙いを定め、撃ち抜く。
カラフルなブリッドのガトリングが僕を追う彼女と盾の間を埋めつくす。
「あれ? 時間稼ぎと考証材料のつもりだったのに……」
遥歌さんの盾が前進に連れて一枚ずつ、崩れていく。
速度こそさした減衰はないけど、この分だとここに来るまでに彼女の切り札らしい盾は全部なくなる。
どういう事だ?
「これでっ!!」
最後の一枚を失って元の武装に戻った彼女が薙刀で既に見せた技を放ってきた。
ただ、これじゃ僕の魔力体を一撃じゃ砕けない。
それどころか……。
「……砕けましたね、武器」
「ええ、よくやってくれたわ」
「今度は何を思いつ――っ!!」
体が動かない!
これはっ、マリコさんのあの奥義を受けた時みたいなっ!
呼吸は出来るけど、一体?
「七、枚目?」
視界の右端近く。
さっきまで、ほんの数秒死角になっていた場所にあの盾があった。
薄めに展開していた魔力体に触れている。
ああ。
そうか。
この盾に触れたブリッドは凍って砕け散った。
だが本来、ブリットは凍らない。
だって魔力で構成された術なんだから。
実体がある訳じゃない。
それを、凍らせたんだ。
なら魔力体にだって何らかの干渉が出来ても不思議じゃない。
「いいえ、一枚目よ」
っ。
ああ、そういう。
つまりソフィアの時と反対の事をされたのか。
あの盾は、容易く、かどうかはわからないけどごく短時間で再生が可能。
もしくは破壊そのものが巧妙なフェイクだった。
「つまり、距離を詰め、一瞬でも反応できない死角を作る。その為にあの薙刀を見切った。玉砕覚悟、そのままの、特攻」
僕の推論を裏付けするように、二枚目、三枚目、と氷の盾が復活し今やクロスレンジになった僕と遥歌さんをごく近い距離で囲んでいく。
「ええ。更に言えば、これを盾の様に扱ったのも貴方の誤解を誘う為。初めて見るものでも問答無用で破壊しかねないライドウにはやり過ぎて困る事などないと感じたもの」
「……?」
盾だと……思わせる?
その時、噛み合った。
僕の方の時間稼ぎも、どうやら終わりみたいだ。
「私では、いいえ、きっとこの世の誰にだってお前は殺せない。ならば、ライドウという存在を終わらせる手段はただ一つだけ」
「これは、盾じゃなく……棺か」
「一時とはいえ、私自身と水の精霊様が持つ力の全てを見渡したこの身で見出した最善手。さあライドウ、共に朽ちましょう」
「封印が貴女の!」
「氷の六棺よ。開け!!」
幸い魔術が封じられた訳じゃない。
魔力体は動かす事も解除もできず、僕の動きを封印する働きをしているけれど。
残念。
僕にはまだ転移魔術がある。
ブリッドと同じくらい慣れ親しんだ魔術で僕は遥歌さんの後方に座標を定め、転移を発動させる。
「……おいおい」
しかし馴染みの術は発動してくれなかった。
「転移魔術なら、水の精霊様が術式を見張って完全に封印しています。無駄ですよ」
いつの間に。
遥歌さんの中から水の精霊の意識が消え去っていた。
出し抜かれたね、こりゃ。
「……はぁ」
「いろは、どうかこの母を」
僕の溜息を諦めのそれと受け取ったのか、遥歌さんがいろはちゃんへの言葉を紡ぎ始めた。
こっちの手は一部読まれてたけど、それで済んで良かったって意味だったんだけどね。
あるいは、転ばぬ先の杖。
あるいは、こんなこともあろうかと。
「……え?」
遥歌さんと、彼女を囲む六枚、いや六基の開いた氷棺を前方に見る僕。
手には……アズサ。
あの棺を砕くには僕の魔術では力不足だと理解していたから。
時間稼ぎをしながら、アレらを“射抜いた”イメージを構築する際に識った。
僕がここにいる事か、それとも僕が弓を構えている事か、その両方か。
彼女との間に開いた距離はほんの十メートル程。
遥歌さんの顔は驚きに満ちていた。
瞳が大きく見開かれている。
種は簡単。
僕には転移の手段が二つある。
一つは魔術に拠る転移。
そしてもう一つが巴の霧に拠る転移だ。こっちは魔術ですらない。
どっちかといえばスキル寄りなんだろうけど、転移魔術の術式や詠唱を監視していた精霊には対応できる訳がない。
結果、僕は棺の包囲から脱出できた訳だ。
さて。まずは、精霊の力で作られた棺だ。
僕の手を離れた矢は次の瞬間、いかなる軌跡を描く事もなく六つの氷棺に突き刺さっていた。
三つの棺で肉体を、残る三つの棺で時を封じるおっそろしい代物は今度こそボロボロと崩れる様にその形を失っていき、やがて矢に貫かれた六匹の妖の姿で地に落ちていった。
「……」
「……」
このままアズサで、という考えが一瞬頭をよぎった。
きっと、それが彼女の二番目の望みでもあろうから。
だけどそれは今後のクズノハ商会にも、この街にも良い選択じゃない。
あくまで僕と彼女の間にだけ通用する自己満足に過ぎないんだろう。
だから。
僕は再び指に針を作る。
針と言うには少し長く、太く不格好ではあるけど、これは僕のイメージによる影響がでた所為だろうな。
右手を静かに振り上げて狙いをつける。
遥歌さんは、動かず。
僕は彼女に向けて手を振り下ろした。
「っ、あぁ……」
そんな、ほんの短い呻きを漏らし。
額を針に貫かれた遥歌さんが糸の切れた人形よろしく落ちていく。
仮死針を棒手裏剣として投擲する。
最初はアズサなんて使わず、これで全部終わらせる予定だったんだけどね。
思いのほか、彼女の執念に圧されたみたいだ。
「はぁ……熱い風呂に入りたいな……」
流石にこのまま地面に激突じゃあ、遥歌さんに悪い。
無性に風呂に入りたい気持ちがこみあげてくるのを抑えて、僕は彼女の落下地点に先回りして着地する。
「お帰りなさいませ、若」
「お疲れ様でした、若様」
「ただいま、二人とも。それから、ジン達も。全員無事なようで何より」
迎えてくれた巴と澪に返事をして、ほどなく上から落ちてくる遥歌さんをお姫様キャッチ。
その様子を見たいろはちゃんが、やはり悲痛な表情を浮かべる。
気丈にも目は逸らさなかったけど。
「大丈夫だよ、いろはちゃん。これでも峰打ちだから。他のお仲間同様復活できちゃうからね」
「頭にぶっとい針が刺さってるのにですか? からかわないで欲しいのです」
久々に会話して、ついでに彼女にとって嬉しい話をした筈なのに辛辣なお答えが返ってくる。
涙目でイズモの手をぎゅっと握って、無理をして精一杯姫として振る舞っているのが誰の目にも一目瞭然だ。
「本当だから。ねえ、ええと、コウゲツさん?」
「え、あ、ああ、はい! いろは姫、同じ状態にある他の者も仮死状態にあるだけとの事。であればおそらく遥歌、様も息はしておいでの筈」
巴に蘇生してもらって仮死状態の魅了組を確保してもらっていたコウゲツさんに助けを求めると、彼は即座に僕の意を汲んでかフォローしてくれた。
意外と良い人ですな。
「……ほんと、です。息してるです」
安堵の声。
しかし目元に大粒の涙が出来ていく。
駄目か、手遅れか。
まあ、思い切り泣くってのもいいよな。
こんな滅茶苦茶な夜だったんだ。
もういっぱいいっぱいだろう。
だから僕もとにかく風呂入りたい訳だし。
そして間もなくいろはちゃんの大泣きが始まった。
僕らといろはちゃん達とジン達とコウゲツさんと。
皆で連れだって歩き出したのは、それからもう少しだけ後の事。
ローレルの長い長い夜は、こうして終わりを告げた。
その殆どが自我を持たず自発的な行動も起こさない無害な存在である。彼らは多くのヒューマンからは認識さえされていない。
明確な自我が持たずとも個として存在し、本能による自発的行動を起こす存在がそれなりに。彼らは下位精霊と呼ばれている。
確固たる個体として存在し意思を疎通できる存在が少ないながらに在り、彼らは中位精霊と呼ばれている。
精霊魔術を扱う多くの術師にとってこの中位精霊と意思を交わし使役する事は人生の目標でもある。
その形状から実力に幅がある中位精霊の更に上、属性の頂点に君臨する唯一つの存在が上位精霊だ。
世界に上位精霊は六体のみ。火水風土光闇にそれぞれ一体のみが存在し、女神の使い、又は彼女に準ずる存在として畏敬の対象となっていた。
上位精霊を精霊魔術によって使役する事は不可能。
その意思に触れ、助力を得られるだけでもヒューマンにとっては偉業。
だからこそローレル連邦の巫女は代々、水の精霊と交信が出来る存在として尊敬を集めている。
急流河川が多いローレルでは治水において大きな恩恵を授かれる水の精霊との交信は国の維持と発展に欠かせないものだ。
火や風、土といった他属性は国を挙げて信仰されているという事はなく時折出現する英雄と個々に関わりを持つ程度という事を考えると、ローレル連邦と水の精霊の関係がいかに特殊なものかがわかる。
その成り立ちには符術の祖にして稀代の精霊使いでもあった初代の巫女、緋綱が大きく関わっているのだが……ともあれ現在のローレルにおいて水の精霊への信仰は絶大なものがある。
はっきりさせてしまうなら、女神よりもよほど熱心に拝まれていた。
女神は水の精霊の主人だからと、ついでに祈られている存在。
賢人を自ら望んで抱える事といい、異色な国家である。
されど大国の一角に名を連ね、変わらぬ在り方も貫く。
治水や数々の奇跡。
ローレルにおいて水の精霊がもたらす利益は小さなものから大きなものまで幅広い。
だが……では上位精霊としての力はどれほどのものなのか。
この世界において、大国一つ分の人々の信仰を一身に受ける水の上位精霊。彼女は女神に次ぐ存在といって過言ではない。
「一瞬女神の介入かと思うたが……精霊の方じゃったか」
やや面白くなさそうに呟いたのは巴。
上空の戦いを見上げつつ、嫌な奴に会ったような表情を浮かべていた。
先ほどまで妖怪大戦争を目をキラキラさせて時にテンションの上がり過ぎで地団駄を踏む程だった彼女とは随分な変わり様だ。
「巴さんと識が二人がかりで諦めざるを得なかった相手でしたっけ?」
「誤解を招く言い方はよさんか。あの女が若の魔力を吸収したのが気にくわんのはわかるがの」
「……ふん」
「この国への影響を考えると、どうやっても表沙汰になると判断したから一旦手を引いただけじゃよ。それだけローレル連邦と水の上位精霊の関係は旧く濃い」
「アレら精霊というモノは女神の使いですものね。上位竜とは違って信仰を得る事でも力を増す……」
「まったく。上位竜から見れば、奴らは我が物顔で好き勝手に振る舞う厄介な寄生虫のような存在、じゃろーなー。あくまで上位竜に立って考えてみたら、じゃがー」
「……上位竜から見れば、ですか。はいはい」
金色の光と、淡く澄んだ青光を纏った遥歌と真の戦い。
それは上空で展開され、時に街に破壊の光を降らせながら、今も継続中だ。
真は藍色を纏い、金と藍の光がたなびく尾を残しながら激突し合い、時に絡み合い。
出鱈目な魔力量から繰り出される高位魔術とスキルの入り乱れる様は、さながら博物館の様。
だがそんなとびっきりの戦いを目にしても巴と澪の様子は特に変わりない。
それ以前と同じこの場に残り、学生を保護し雑談をする程度。
「精霊様が、お母様に?」
「いくら巫女様がご不在だからといって、そんな事が……」
かすれ震える声で唖然と呟いたのはいろは。
疲労か精神的な要因かは不明だが未だ立ち上がれず横になっている彼女を支えるイズモもまた青い顔をしている。
無理もない。
彼らにとって水の上位精霊は信仰の対象。
神に等しい存在なのだから。
巫女としか交信しない神に等しい存在が今、その力の一端を遥歌に貸しているかもしれないと考えるだけで身が震えるのだ。
「で、どうみます、巴さん? アレの力の程を」
「儂らと同格、もしくはそれ以上じゃろ」
「対策なくぶつかれば分が悪いと。癪ですけど同感です」
「とはいえ儂らは若ではないしの。無策で上位精霊とエンカウントなんぞあり得ん。そして対策をしっかりした上でなら、負ける事はあるまいよ」
「ですわね」
『!?』
特に感慨もなく言い放った巴の言葉に澪は少しだけ瞳を細め、聞いていたジン達は一様に目を見開いた。
それは、超人や英雄そのものな戦いをやっている遥歌と巴、澪が互角であるかもしれないという事への驚き。
詳細には遥歌がそれくらいヤバイ存在だったという事への驚きと、巴と澪がこれほどの猛者だったのかという二つの驚きによる反応だった。
(という事はそのお二人を追い回すらしい先生は……一体……)
ただ一人、ジンだけはその先にいる人物、ライドウへの畏怖も一足先に心に刻んでいたが。
最早首の疲れも気にする事なく起こっている事全てを目に焼き付けておこうとする学生達。
回復してもらい体の負傷は治っても気力まで満ち溢れるものではない。
それでも、横になって休みたいという気持ちよりも、全てを見届けたいと思う気持ちの方が全員一致で勝っていた。
「巴、殿」
「ん? ……おお、コウゲツ殿か。貴殿が見えられたという事は乱心した者どもの回収も粗方終わったとみても?」
弱弱しいながら、低くはっきりした声で名を呼ばれた巴が振り返る。
そこには遥歌の奇襲に対応して出動したカンナオイの部隊をまとめていた男、コウゲツの姿があった。
「ああ。アレを除いては、だが。水色と金色のが……遥歌なのだろう?」
「うむ」
「で相対するのが君たちの主、ライドウ、殿という訳か」
「御推察の通り」
「彩律め、あんなモノを一体どうやって……。いや、最早詮無き事か。ともあれ巴殿。この老い先短い命と未来を担う若い命を救ってくださった事、改めてお礼申し上げる」
「構わんよ」
「事もなげに仰る。あのような奇跡――」
「儂も自分の力に馴染んでおく必要があった。若の命令もあった。故に貴殿らはただ、そう運が良かったのだと思えばいい。それに一度死んだ身なら、そこから数多の教訓を得てもいよう。これより先、存分にそれを伝えていけば良いさ」
巴は蘇生を行なった事への礼をさもどうでもよい事の様に流す。
ただその経験を大事にして次に活かせと、それだけ伝えた。
教訓。
今回のソレがどんなモノになるのかは、コウゲツらの想像力にもよるが、巴からの巧妙な恩の押し売りでもある。
恐怖の刷り込みともいう。
遥歌に惨殺された彼らだけに、トラウマを抱え今後兵士という職を辞する者も出てくるだろう。
「あれさえも、巴殿には造作もない事と?」
「まさか。随分と手間のかかる面倒な仕事であったよ。若の命でなければ二度と御免じゃな」
「……」
あれだけの行い。
コウゲツが口にしたそれは、ただの死者蘇生ではない。
無論死者の蘇生自体も凄まじい高等魔術であり、おいそれと扱えるものではない。
しかし巴がやったそれは、遥歌によってミンチにされたり、文字通り赤い飛沫にされて絶命した者、それに炎と熱で焼かれて影だけしかこの世に残っていなかった者までを全て五体満足の状態で復活させるというもの。
土くれからの再生。最早それは奇跡と呼んで遜色ない御業だった。
片足だけ残っている状態から最初にこの世に呼び戻されたコウゲツはその奇跡の全てを目の当たりにしたのだ。
あー、いきすぎじゃー! とか。
そこは違うじゃろ!? とか。
どうしていきなりそっちに繋がるかー! とか。
そんな緊張感のない言葉で奇跡が為されるのを見ていたコウゲツに、既にクズノハ商会へのわだかまりはなかった。
ずぶずぶと土から人の体が成っていき、その肉に生気が宿り目が開き、そして自分を見て隊長と呟く。
まるで神話だ。
コウゲツは野心より何よりこの事態の収束を望んだ。
自分の焦りが生んだこの悲劇から街を救いたいと切に願った。
だから、彼は奇跡を終えた巴から協力を求められた時、内容が襲撃者の保護だったとしても即断で了承した。
その決意は上空の光景を見ても変わらない。
彼とて敬虔とは言えないが人なみに精霊への信心はある。
遥歌に精霊が力を貸しているのかもしれないと考えはしても、一度死を経験し、復活を遂げた彼はどこか冷めた目で事実を受け入れていた。
第一その遥歌と少なくとも互角に戦いをしている者がいる。
ただの遥歌とでさえ驚異的なのに、精霊が力を貸しているらしい彼女と。
だからこの両方の事実をきちんと自身の天秤に置き、戦いの推移を気にしながらコウゲツは巴と澪、いろはがいる場に足を運んだ。
恩人と戦いの結末と、以後の自らの身の振り方を決める為に。
「あの女の人、どんどん……強くなってる。今攻撃を受けたらジュウキが一撃で粉々にされそう」
「正解です。流石若様の生徒、中々良い目をしてますね。もっと精進しなさいな、上手に扱えるならその内マークツーをあげますから」
「ええ!?」
ユーノの悔しさを通り越した諦めの言葉に、澪が予想外の言葉を掛ける。
「それにミスラ、ですか。お前も中々どうして。もう英雄の領域に片足突っ込んでますね。潔いまでの防御特化。とことんまでパーティ主義。気に入りました」
「え、ええ!?」
「巴さんが食いつくのもわかる気がします。ユーノとの連携も実戦の中で主導し構築していく防御の鬼。ふふ、一点特化に惹かれるのは若様の影響かしら」
楽し気にユーノとミスラを撫でる澪。
巴一人でも十分な地獄を見ているというのに、この上もう一人増えたら身が持たないと恐怖に震えるミスラ。
一方ユーノはマークツーという響きに目を輝かせつつ、先の戦いでのミスラを振り返り、うんうんと何度も頷いていた。
(そうだった。ミスラ先輩からの指示で連携するようになって凄く動きやすかった。思えばパーティの盾としての心構えなんて、私全然出来てなかったもん。本当に、凄かったな……今日のミスラ先輩……)
しかも火力としてスキルを使う時にはきっちりユーノを前線に送り届ける。
彼はまさに防御職人だった。その技量の高さを彼女は肌で感じ取ったのだった。
澪からはお褒めの言葉を、ユーノからは微かに熱い視線を送られつつミスラは直立不動で上を見上げていた。
「確かに凄い。凄いけど……何か違う。あれは初めて目にする濃さの精霊の力だけど……何か……」
シフが上を見ながらブツブツと呟いている。
巴から精霊の存在を教えられ、納得できたようで出来ていない。
精霊の力を借りる魔術師である彼女からみて、今の遥歌の状態はよくわからないものだった。
精霊を自身の身体に降臨させているようでそうではない。
そもそも上位精霊を身に宿そうなどとすれば大抵の場合人の器が消し飛ぶ。
ローレルでも巫女の数人が降臨の儀を行ない大きな奇跡を起こしてはいるものの、例外なく数分で命を落としている。
生命力と精神力が焼き切れての死。まだ五体満足な遺体が残るだけ巫女は凄い。
しかし遥歌はまだ生きている。もう数分などとうに過ぎ去ったというのに。
では上位精霊の力を貸与されているのか。
それにしては場に何者かの意思が濃密に存在している。
今の遥歌はまるで、精霊とヒューマンが一体となって戦っているような、精霊単体での顕現と人の器をかりての降臨の良いとこどりをしている、そんな奇妙な様子だった。
現実にはそんな虫の良い状況など作り出せる筈がなく、もしも顕現にせよ降臨にせよこれほどに効率の良い方法があるのなら誰もが飛びつくであろう。
シフとてその一人だ。
遥歌のこの在り様を頭に焼き付ける。
いずれ大地の精霊を召喚、顕現させ自らの力とする時に参考にする為に。
今はまだ叶わない目標ではあるけれど、未来の為に現状唯一出来る事はこの戦いを見て考える事と彼女は結論付けた。
(とはいえこのローレルで水の精霊が巫女以外にこれ程力を貸した戦いなんてものは、すぐに箝口令が敷かれるとみて間違いないけれど、ね)
他言は出来なくとも、価値は色褪せない。
「あの高みに……識さんがいる」
アベリアは学ぶ、考えるというよりも胸に秘めた一つの決意を確かめるように上を見ていた。
クズノハ商会との関わり方が少し前に変わった彼女にとって、目指す人の背中があそこにあるとわかる光景は貴重だった。
遥歌の姿は今はまだ遥か彼方。
一合も叶わず斬り捨てられる。
肩を並べる事はない、三歩後ろで良いんだと考えてみたところでやはり目標と現在の自分の距離はあまりにも遠い。
ライドウとぶつかり合う遥歌の姿は、しかし、アベリアをさほど絶望させる事はなかった。
(でも識さんは私の手をとって引っ張ってくれている。今は無理でも、いつか、絶対に。ライドウ先生にも私を見てもらう。そうしたら、先生の事、若様って呼んでもいいよね)
別に今のままでも真は乞われれば諦めたように頷いてくれるであろう。
しかし、アベリアは少しだけずれた自分の目標を胸に力強く導いてくれる識の為にも、自分ではなく識を信じて力を尽くそうと改めて覚悟を決めた。
ちらりと横目でその様子を見ていた巴が呆れたような、少し楽しそうにも見える表情で小さく溜息をついていた。
「……すげえよな」
『?』
ぼそりとダエナが口を開いた。
短くそれだけ口にした彼に学生たちの視線が集まる。
「あの遥歌って女性、滅茶苦茶強かった。本気を出してなくても俺らなんかとは格が違った」
『……』
「なのに先生はそんな人を相手にしても、やり返してくれてる。追い詰めて、引き出しを開けさせて全力を出させて。その上で一歩も引かないどころか……押してる。世界って、こんなに広いもんなのか? こんな……途方もないもんなのか?」
『……』
「冒険者でも騎士でも魔術師でもさ。生え抜きだのアカデミーだの学園卒だの……本当にくだらねえレベルの争いなんだな。外の世界はこんなだぜ。絶対の存在に見えてもそれを押し潰す絶対がいる。終わりがねえ……」
返ってくる言葉は無かった。
上空の戦いは確かに、レベルが違っていたから。
自らの糧にする事は出来ても、将来そこに自分が参加できるかといえばその答えは否、だろう。
選ばれた者の戦い。
実際にそれがあると受け止めた時に、自分のやってきた事が虚しくなる経験は誰にでもある。
しかし如何に虚しく思えようと、無駄ではない。
ダエナの言葉には自棄をうかがわせる悔しさを超えた諦めがあったが、誰もそれを否定してやる事が出来ずにいた。
「……ぷ、はは、っあはははは! なるほどなるほど、中々どうして。ひよっこはひよっこなりに思い悩むという事か!」
「っ?」
唐突に噴きだした巴の姿を見てダエナが言葉を詰まらせる。
見れば澪も扇を口元に当て、笑いをこらえている様子だった。
ダエナから見て選ばれた者の側にいる二人の反応に、彼はおおいに戸惑った。
「と、巴さん。いち、一応、ふふ、この子どもとて、己を、ぷふ、儚んでの思いの丈と……うふっ」
フォローらしき澪の言葉も今一つ意味を成していない。
ダエナの自虐を含んだ告白が如き独白が、どういう訳か巴と澪のツボに入ったらしかった。
「あー……子持ちのカトンボ。ダエナじゃったか。まず、一言良いかの?」
ひとしきり笑った後、わざわざダエナの正面まで出向き巴は彼の肩に手を置いて瞳を真正面から見つめて口を開いた。
一方のダエナはただ頷くのみ。
「思いあがるな」
「っ!!」
「お前たちは確かに若と識の指導と好奇心の結果、学生にあるまじき力を手にし、今己の持つ可能性に夢も見ていよう。それは良い。大いに突っ走れ。じゃがな、思いあがるな」
「思いあがっているつもりなんて、ありませんけど」
「良いか? ここには若がおらんで、まあ言葉を選ばず分かりやすく言ってやるが。今あそこでやりあっとるのはな?」
「……」
「片方は天才じゃ。それも儂の見る限りたった一つしか弱点がないような、御伽噺に出てくる英雄クラスの天賦の極み」
「……なら、もう片方は……」
「その英雄サマでも手も足もでん大魔王、化け物じゃよ。そんな戦いに未だ凡人に片足つけとるお前らが挑戦できる訳ないじゃろう? あの中に飛び込めば儂とて怪我をする」
「確かに、私も着物だけじゃ済みそうにありません。怪我もそこそこするでしょうねぇ」
巴の言葉に澪が頷く。
笑いのツボからはどうにか脱出できたようだ。揺り返しへの油断は禁物だが。
「良いか? 今日この戦いを頭に刻み込んでおいてな、いつか自分の力が最盛期にあると感じた時、あの女の方をイメージして戦ってみよ。一分も持てば立派なもんじゃ。その力で守れぬようなモノを抱えていたなら、それは分不相応というものじゃろうよ」
「一分……ですか」
「そうじゃ。あれはそういう戦いじゃよ。お主らにとってはな。これ以上ない程の物差しになろう」
「でも巴さん。天賦の極みと仰いましたけど、先生は圧倒的じゃないですか。ああなった遥歌という女性ですら必死で……」
「ジンか。馬鹿者、若と比較してどうする? それこそ全くの無意味。ほれ、やつの動きをよく見てみい」
「え?」
ダエナが口を一文字に結び思考モードに入ったタイミングで、今度はジンが巴に尋ねた。
巴が英雄と化け物の戦いと評した事に違和感を覚えたからだろう。
問われた巴は馬鹿者とジンをたしなめ、そして戦いの様子を指さした。
「限界まで高められた肉体、そして技。更に水の精霊の力を駆使した数々の回復魔術に五十を超えるスキルの駆使。これが天才でなくて一体何を才と呼べば良い?」
「……」
遥歌が揮う必殺の一撃の連発。
力と技と経験を駆使した攻め、受け、守り、回避。
空中という特殊な地形でありながらまるで地上を駆けるかのように縦横無尽に動く様は、生まれた時から空の住人だったかに思えてならない程。
一振りの隙をもう一振りで消し、両手の武器を叩きつけた隙は術で消す。
真の反撃を正確に把握し、回避しきれない攻撃は予め回復魔術を仕込んで対応、攻め手を緩める事は一切ない。
例え真が人の反応を逆手に取り、防御回避はおろか反応さえ難しい攻撃を仕掛けてもスキルの強制動作で避けてみせる。
更にはスキルを次のスキルで上書きして隙を無くす。
そんな行動に加えて精霊の力によるトラップや攻撃魔術まで活用する。
確かに、注目してみればどれもが凄まじい技術ばかり。
攻撃力や防御力などはもとより、遥歌の行動全てが誰かにとっての糧になるような。
まさに戦闘の天才というべき戦いぶりだった。
ただ大魔王がその全てに笑うしかない切り返しをしているだけ。
そう、大魔王は倒せない。理不尽の塊。
「ほれ、迎撃でそこを撃ち抜かれるとわかっておりながら事後発動の魔術を仕込んで加速、若の首を狙いにいきおった。いや、それだけでは飽き足らず斬り抜き様に背から心の臓を一突き、叶わず反撃に晒されても……更に上に逃げおった。最後のアレは上に跳んで斬りかかるスキルの初動かのう」
「……凄い」
「じゃろ? あの女が見せておるのはヒューマンとして、ある意味で最善の戦い。ソフィアや響とは違う目線からの戦い。故に……アレも今を好機と見てあの女に乗ったんじゃろうが……そこは早計よな」
ならどうして、自分はどこかで遥歌を大した事がないと感じてしまったのか。
ジンが抱いた疑問への答えは単純だ。
彼の先生という立場にいる人物が、彼女を圧倒しているから。
だから……ジンは遥歌を、精々が自分たちの延長線上にいる存在なんだと過小評価してしまっていた。
「いやはや、見惚れる程の高等技術のオンパレード。対等な相手がいないからと戦いを厭うておった女がブランク明けの実戦でこれじゃからな。人とは恐ろしいものよ」
その高等技術も全て受けられ、もしくは撃ち落とされてしまっては若い目には正当な評価が下せなくとも無理はない。
「ええ、本当に。やはりヒューマン、人という種こそが本当に恐ろしいのでしょうね……」
どこか哀れむような声音の澪。
「む……」
「巧妙に隠していますけど、気勢が変わりましたね。これは、仕掛けますか」
『え!?』
巴と澪が感じた微かな変化は、ジン達の目には全く見て取れなかった。
変わらずぶつかり合うライドウと遥歌の戦いを見守る事しか出来ない。
決着が近いのかもしれないと感じたいろはの手が、イズモの手を強く握る。
そして上の戦いを見つめたまま、彼は小さな手を握り返した。
「つまり決着か。フツからの頼まれ事など面倒の匂いしかせんかったが、得るモノも多い夜になったのう」
「お味噌もお醤油も守れましたし、夜更かし一回程度の価値は十分ありました」
遥歌の手から黒と白の薙刀が離れる。
束の間、戦いに静寂が差し込んだ。
◇◆◇◆◇◆◇◆
怯えた目だ。
遥歌さん。
この人は、戦いに向いてない。
技も体も信じられないレベルで身に付いた人だけど。
ただ一つ。
彼女には、心が備わっていない。
僕とは……違った意味でね。
同じレベルかそれ以上の相手がいれば戦いに意味を見出す?
遥歌さんに関して言うのなら、それは間違いだ。
ここまで……適度に追い詰めて、彼女の扱うスキルや術を晒させてみた。
閃きやその場での成長もあって結構な作業だったけど、もうそろそろ必殺の策くらいしか残っていないだろう。
怖いんだ、遥歌さんは。
負傷が怖い、敗北が怖い、死が怖い。
そんな恐怖を全く克服できてない。
というか、これまでの人生で彼女はその恐怖を感じる事なく圧倒的な才能で生きてこられたのだろう。
戦場に出る事を強いられながらも。
そっちは正直驚異的だし、なんという勝ち組と驚くばかりだ。
巫女でもないのに上位精霊をその身に受け入れて自我も失わず戦えているというのも滅茶苦茶。
無駄な仮定だけどタイマンまで持ち込めるなら、ゼフさんでさえ生まれ持ったものだけでミンチにしかねない。
……そういう意味では智樹と直接接触してなかったのは良かったというべきなんだろうか。
ん。
不意に肩を荒々しく上下させていた遥歌さんが手から薙刀を二本とも手放した。
黒と白の彼女の得物は下に落下していく事なく、主の左右に浮遊してる。
「終わりにする覚悟は出来ました?」
「……そう簡単に終わりにする気はありません。お前に、一矢報いる事さえ叶わぬ今は、特に」
「確かに。戦いというものを教えてくれる、筈でしたっけ」
「!」
「今のところ、立場が逆みたいですけどね。遥歌さん、確かに貴女は才能溢れる人だ。素直に凄い。その貴女が持てる力の全てで僕にぶつかる。なるほど、水の上位精霊がその身に降臨するなんて博打に出る気持ちもわからんでもないです」
「……そう、気付いていたの」
「ええ、まあ。ただ……そこについては全部が計画通りって訳じゃなく、期せずしてこれ以上を望めない状況が揃って勝負に出た、って感じがするんですけどね。後で聞くのも悪くないかな。って、今はそんな事はどうでもよくて」
「……っ」
「……怖いんでしょ、遥歌さん」
「!?」
「わかりますよ。バレバレです。もう必死で、本当に必死で僕に食らいついてきたその瞳。かつてない位苛烈で独創的で強力で……なのに全く戦士の闘志は感じなかった。戦いへの渇望? 貴女にはそんなものはありませんよ。何かを感じたのだとしたら、それはきっとこ――」
おっと。
子どもを授かるか産むかして母性をこじらせた時期じゃないんですか。
そんな事を言おうとして何とか言いとどまる。
わざわざ指摘する事もない。
女性として、ただ幸せに、愛する男性と子どもと家族を作って生きていく事に一番の幸せを感じるのが本性なのだと。
既に血に塗れここにいる彼女には、もう余りに遅過ぎるだろう。
「う……」
「智樹の魅了も解いて、精霊の意思さえ不完全ながら支配下に置きながら、貴女は僕とじゃなく恐怖と戦ってた。心だけが伴わない。ふふっ、なんというか……僕と似てる」
「化け物に似てると言われて喜ぶ者などいませんよ」
「認めますか。もうアイツの魅了の影響下にないって事は」
「っ」
なら投降すればいい。
それで戦いは終わる。
でも彼女は己と精霊の力をもって僕に挑んできた。
全能感への慢心、僕を排そうとする精霊の意思の影響?
確かにそれもあるかもしれない。
「……死ぬ心算ですか?」
恐怖と戦いながら。
死にたくないと全力を尽くしながら。
この女性は、ここで死のうとしている。
「心を読むのは下衆な行いとしりなさい」
「読んだ訳じゃありませんよ。ただ、貴女がそう心で叫びながら僕に攻撃をし続けていただけだ。嫌でも伝わる」
「……私は」
「最良の結末は、僕を殺して死ぬか、僕と一緒に死ぬか。そういう最後を貴方は望んでる」
「……」
「魅了が解けた所で、過去は変わらない。智樹への愛慕を理由に奪った命も、本当に大切にすべき人達に対してとり続けた態度も行いも、無かった事になりはしない。ただ、その記憶を持ったまま正気に戻った者だけが、残される」
あまりにも残酷だ。
魅了の影響下にあった期間やしでかした事にもよるだろうけど、生きていく事に絶望する程。
いっそ、そのまま命を摘み取ってやった方が慈悲である程。
といいながら、今回の僕については……。
遥歌さんから返事は無かった。
代わりに彼女の中にある圧倒的なまでの水の力の塊が圧縮され、練り込まれながら体の外に出てくるのを感じた。
僅かな水の精霊の抵抗の意思も。
けれど、今あの体にある全ての力の優先権は遥歌さんの方が持ってる。
僕への敵意や遥歌さんへのアドバイスなど、意思はあるようだけど力の行使は出来ないみたいだな。
もっともその方が上手く力を扱えている辺り、人の才の行き着く果てへの畏敬を感じるところだ。
元々百鬼夜行のスキルで召喚に関連する力の扱いは慣れていたってのもあるかもなあ。
しかし……つくづく召喚って凄い可能性がある魔術分野だな。
アズさんといい遥歌さんといい、人外クラスばかりを目にしているからというのもあるけど……うん、終わったら識と相談してジン達や下の生徒への講義に加えられないか検討。
「嘘ぉ、精霊の力の創ぞ、いや、これは百鬼夜行との……コラボ的な?」
新しい講義に意識が向いている間に遥歌さんと僕の間に奇妙な形をした六枚の氷の盾らしきものが出現した。
一瞬精霊の魔力を利用して創造をやってのけたかと思ったけど、違った。
水か氷と相性が良い妖を同時に呼び出して核にし、濃密な精霊の力を武具の形に映した。
ぼ、僕の魔力体よりも高度な気がする。
いや今だって重宝してますよ? かけた時間に後悔もありませんとも。
でもさ、僕はひと夏かけたのに……今?
ここまでもやたらとセンス溢れるスキルと魔術の連携を見せつけてくれたのに、そうかー……今かー今出来ちゃうのかー。
「もう、語るべき事もない。ただ、砕けるのみ!」
泣きそうな目でそう言われても!
六枚の盾、二本の薙刀。
近接戦闘のエキスパートが八刀流で遠距離型の僕を詰めにかかるとか、死にたくない癖に死ぬって決めてる人は迷いが無い! 意味が分からん!
どう考えてもあの盾はただの盾じゃないし。
服を赤に変えて一気に後退するも、遥歌さんはお構いなしの考えなしってな風に追ってきた。
右手の人差し指と中指を伸ばした先に作った仮死針はそのまま、とりあえず様子見のブリッドを六枚の盾全部に当ててみる。
はい、軌跡が曲げられた。
盾に当たる事もなく、六つのブリッドが遥歌さんを避ける様に明後日の方向に消えていく。
なら次だ。
意識を遥歌さんと盾の一つに合わせ、必中を確信して再度ブリッドを放つ。
威力は月の術よりも少し強め。
当たれば相応に痛い、筈。
さて……。
「マジか、おい」
結論から言えばどっちも失敗した。
盾に命中したブリッドは一瞬で砕かれてキラキラした塵になった。
凍らされて砕かれた? ってとこだろうか。
まあ、そっちはとりあえずいい。
問題は本体を狙った方だ。
こともあろうに……外れた。
正確には、今回は狙ってなかった盾の一つが一瞬遥歌さんの姿になってブリッドが、それ目指して逸れた。
もちろん、その後はもう一つと一緒。
砕けてキラキラになった。
……ちっ。
「っ」
「……」
上の僕と下の遥歌さん。
このまま次を仕掛けると、下手に逸らされるとブリッドじゃ街に被害が出るかもしれない。
だけど他の手で終わらせるのは……面白くない。
確かに中る絵は見えてたのに、外れたってのが、面白くない!
あの盾、舐めくさってくれる!
手の位置に魔力を固めて姿勢を反転。
そのまま下に向けてその足場を思い切り蹴る。
即座に距離を詰めてくる僕に対応して遥歌さんが六枚の盾を僕を囲む様に展開しつつ薙刀を操って斬撃から刺突のコンビを仕掛けてくるも、何とか彼女を通り過ぎる事に成功。
位置関係は逆、上の遥歌さんと下の僕に変わった。
これなら思い切り、試せる。
「ほんの数秒だろうけど、やらせてもらう」
威力は高く保ったまま属性を入り乱れさせ、遥歌さんと盾のあらゆる場所に狙いを定め、撃ち抜く。
カラフルなブリッドのガトリングが僕を追う彼女と盾の間を埋めつくす。
「あれ? 時間稼ぎと考証材料のつもりだったのに……」
遥歌さんの盾が前進に連れて一枚ずつ、崩れていく。
速度こそさした減衰はないけど、この分だとここに来るまでに彼女の切り札らしい盾は全部なくなる。
どういう事だ?
「これでっ!!」
最後の一枚を失って元の武装に戻った彼女が薙刀で既に見せた技を放ってきた。
ただ、これじゃ僕の魔力体を一撃じゃ砕けない。
それどころか……。
「……砕けましたね、武器」
「ええ、よくやってくれたわ」
「今度は何を思いつ――っ!!」
体が動かない!
これはっ、マリコさんのあの奥義を受けた時みたいなっ!
呼吸は出来るけど、一体?
「七、枚目?」
視界の右端近く。
さっきまで、ほんの数秒死角になっていた場所にあの盾があった。
薄めに展開していた魔力体に触れている。
ああ。
そうか。
この盾に触れたブリッドは凍って砕け散った。
だが本来、ブリットは凍らない。
だって魔力で構成された術なんだから。
実体がある訳じゃない。
それを、凍らせたんだ。
なら魔力体にだって何らかの干渉が出来ても不思議じゃない。
「いいえ、一枚目よ」
っ。
ああ、そういう。
つまりソフィアの時と反対の事をされたのか。
あの盾は、容易く、かどうかはわからないけどごく短時間で再生が可能。
もしくは破壊そのものが巧妙なフェイクだった。
「つまり、距離を詰め、一瞬でも反応できない死角を作る。その為にあの薙刀を見切った。玉砕覚悟、そのままの、特攻」
僕の推論を裏付けするように、二枚目、三枚目、と氷の盾が復活し今やクロスレンジになった僕と遥歌さんをごく近い距離で囲んでいく。
「ええ。更に言えば、これを盾の様に扱ったのも貴方の誤解を誘う為。初めて見るものでも問答無用で破壊しかねないライドウにはやり過ぎて困る事などないと感じたもの」
「……?」
盾だと……思わせる?
その時、噛み合った。
僕の方の時間稼ぎも、どうやら終わりみたいだ。
「私では、いいえ、きっとこの世の誰にだってお前は殺せない。ならば、ライドウという存在を終わらせる手段はただ一つだけ」
「これは、盾じゃなく……棺か」
「一時とはいえ、私自身と水の精霊様が持つ力の全てを見渡したこの身で見出した最善手。さあライドウ、共に朽ちましょう」
「封印が貴女の!」
「氷の六棺よ。開け!!」
幸い魔術が封じられた訳じゃない。
魔力体は動かす事も解除もできず、僕の動きを封印する働きをしているけれど。
残念。
僕にはまだ転移魔術がある。
ブリッドと同じくらい慣れ親しんだ魔術で僕は遥歌さんの後方に座標を定め、転移を発動させる。
「……おいおい」
しかし馴染みの術は発動してくれなかった。
「転移魔術なら、水の精霊様が術式を見張って完全に封印しています。無駄ですよ」
いつの間に。
遥歌さんの中から水の精霊の意識が消え去っていた。
出し抜かれたね、こりゃ。
「……はぁ」
「いろは、どうかこの母を」
僕の溜息を諦めのそれと受け取ったのか、遥歌さんがいろはちゃんへの言葉を紡ぎ始めた。
こっちの手は一部読まれてたけど、それで済んで良かったって意味だったんだけどね。
あるいは、転ばぬ先の杖。
あるいは、こんなこともあろうかと。
「……え?」
遥歌さんと、彼女を囲む六枚、いや六基の開いた氷棺を前方に見る僕。
手には……アズサ。
あの棺を砕くには僕の魔術では力不足だと理解していたから。
時間稼ぎをしながら、アレらを“射抜いた”イメージを構築する際に識った。
僕がここにいる事か、それとも僕が弓を構えている事か、その両方か。
彼女との間に開いた距離はほんの十メートル程。
遥歌さんの顔は驚きに満ちていた。
瞳が大きく見開かれている。
種は簡単。
僕には転移の手段が二つある。
一つは魔術に拠る転移。
そしてもう一つが巴の霧に拠る転移だ。こっちは魔術ですらない。
どっちかといえばスキル寄りなんだろうけど、転移魔術の術式や詠唱を監視していた精霊には対応できる訳がない。
結果、僕は棺の包囲から脱出できた訳だ。
さて。まずは、精霊の力で作られた棺だ。
僕の手を離れた矢は次の瞬間、いかなる軌跡を描く事もなく六つの氷棺に突き刺さっていた。
三つの棺で肉体を、残る三つの棺で時を封じるおっそろしい代物は今度こそボロボロと崩れる様にその形を失っていき、やがて矢に貫かれた六匹の妖の姿で地に落ちていった。
「……」
「……」
このままアズサで、という考えが一瞬頭をよぎった。
きっと、それが彼女の二番目の望みでもあろうから。
だけどそれは今後のクズノハ商会にも、この街にも良い選択じゃない。
あくまで僕と彼女の間にだけ通用する自己満足に過ぎないんだろう。
だから。
僕は再び指に針を作る。
針と言うには少し長く、太く不格好ではあるけど、これは僕のイメージによる影響がでた所為だろうな。
右手を静かに振り上げて狙いをつける。
遥歌さんは、動かず。
僕は彼女に向けて手を振り下ろした。
「っ、あぁ……」
そんな、ほんの短い呻きを漏らし。
額を針に貫かれた遥歌さんが糸の切れた人形よろしく落ちていく。
仮死針を棒手裏剣として投擲する。
最初はアズサなんて使わず、これで全部終わらせる予定だったんだけどね。
思いのほか、彼女の執念に圧されたみたいだ。
「はぁ……熱い風呂に入りたいな……」
流石にこのまま地面に激突じゃあ、遥歌さんに悪い。
無性に風呂に入りたい気持ちがこみあげてくるのを抑えて、僕は彼女の落下地点に先回りして着地する。
「お帰りなさいませ、若」
「お疲れ様でした、若様」
「ただいま、二人とも。それから、ジン達も。全員無事なようで何より」
迎えてくれた巴と澪に返事をして、ほどなく上から落ちてくる遥歌さんをお姫様キャッチ。
その様子を見たいろはちゃんが、やはり悲痛な表情を浮かべる。
気丈にも目は逸らさなかったけど。
「大丈夫だよ、いろはちゃん。これでも峰打ちだから。他のお仲間同様復活できちゃうからね」
「頭にぶっとい針が刺さってるのにですか? からかわないで欲しいのです」
久々に会話して、ついでに彼女にとって嬉しい話をした筈なのに辛辣なお答えが返ってくる。
涙目でイズモの手をぎゅっと握って、無理をして精一杯姫として振る舞っているのが誰の目にも一目瞭然だ。
「本当だから。ねえ、ええと、コウゲツさん?」
「え、あ、ああ、はい! いろは姫、同じ状態にある他の者も仮死状態にあるだけとの事。であればおそらく遥歌、様も息はしておいでの筈」
巴に蘇生してもらって仮死状態の魅了組を確保してもらっていたコウゲツさんに助けを求めると、彼は即座に僕の意を汲んでかフォローしてくれた。
意外と良い人ですな。
「……ほんと、です。息してるです」
安堵の声。
しかし目元に大粒の涙が出来ていく。
駄目か、手遅れか。
まあ、思い切り泣くってのもいいよな。
こんな滅茶苦茶な夜だったんだ。
もういっぱいいっぱいだろう。
だから僕もとにかく風呂入りたい訳だし。
そして間もなくいろはちゃんの大泣きが始まった。
僕らといろはちゃん達とジン達とコウゲツさんと。
皆で連れだって歩き出したのは、それからもう少しだけ後の事。
ローレルの長い長い夜は、こうして終わりを告げた。
1,958
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

月が導く異世界道中extra
あずみ 圭
ファンタジー
月読尊とある女神の手によって癖のある異世界に送られた高校生、深澄真。
真は商売をしながら少しずつ世界を見聞していく。
彼の他に召喚された二人の勇者、竜や亜人、そしてヒューマンと魔族の戦争、次々に真は事件に関わっていく。
これはそんな真と、彼を慕う(基本人外の)者達の異世界道中物語。
こちらは月が導く異世界道中番外編になります。

魔王を倒した手柄を横取りされたけど、俺を処刑するのは無理じゃないかな
七辻ゆゆ
ファンタジー
「では罪人よ。おまえはあくまで自分が勇者であり、魔王を倒したと言うのだな?」
「そうそう」
茶番にも飽きてきた。処刑できるというのなら、ぜひやってみてほしい。
無理だと思うけど。

親子丼(45歳の母親と20歳の娘) 連載開始
蔵屋
大衆娯楽
この物語は、私と母元子(45歳)、母の友人である友美(45歳)とその娘さゆり(20 歳)との物語である。親子の歳の差は25歳である。
私が大学に合格し、大阪で暮らすことになるので、母と私は大阪の高石に住んでいる友美夫婦とその娘さゆりに挨拶をするために高石に行ったのだ。
この物語の始まりである。
私たち親子と友美親子との実体験に基づく物語である。
私の脚色を加えてあるので、登場人物については、すべて仮称とした。
夕食が終わり、私と母は一緒にお風呂
に入った。広島にいる時から、いつも
母と私は一緒に風呂に入っていた。
それは親子という絆を確かめ合うこと
であった。
それと同時に、母は、過去の秘め事を
私に見られたことに対する恥じらいの
気持ちがあったのかもしれない。
「隆義、お母さんが体を洗ってあげる
ね」
「はい。」
私は母に体を洗ってもらった。
今度は、私が母の体を洗う番である。
このようにして、私と母は親子の絆を
深めているのであった。

友人(勇者)に恋人も幼馴染も取られたけど悔しくない。 だって俺は転生者だから。
石のやっさん
ファンタジー
パーティでお荷物扱いされていた魔法戦士のセレスは、とうとう勇者でありパーティーリーダーのリヒトにクビを宣告されてしまう。幼馴染も恋人も全部リヒトの物で、居場所がどこにもない状態だった。
だが、此の状態は彼にとっては『本当の幸せ』を掴む事に必要だった
何故なら、彼は『転生者』だから…
今度は違う切り口からのアプローチ。
追放の話しの一話は、前作とかなり似ていますが2話からは、かなり変わります。
こうご期待。



勇者の隣に住んでいただけの村人の話。
カモミール
ファンタジー
とある村に住んでいた英雄にあこがれて勇者を目指すレオという少年がいた。
だが、勇者に選ばれたのはレオの幼馴染である少女ソフィだった。
その事実にレオは打ちのめされ、自堕落な生活を送ることになる。
だがそんなある日、勇者となったソフィが死んだという知らせが届き…?
才能のない村びとである少年が、幼馴染で、好きな人でもあった勇者の少女を救うために勇気を出す物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。