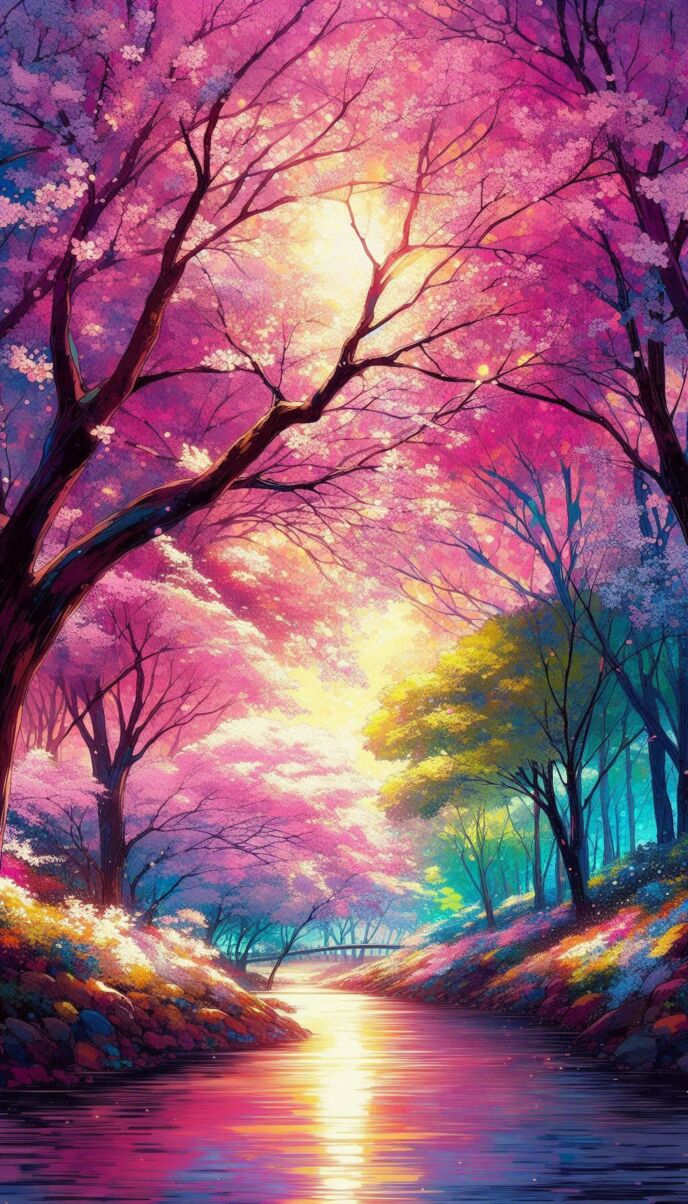10 / 189
第一章 愛と家族
9. 罪と罰と、ちいさな聖母の無垢なる祈り。Crime and Punishment with Prayer of the Very Lit
しおりを挟む
ひまりのことばは確かにアイのこころに触れた。こころのいちばん深いところに。埃をかぶって凍りついていたところに。しかし、ひまりが企図したこととは真逆の温度でもって。
アイの最後の言い訳を、アイが生きていていい言い訳を、やさしい陽だまりのなかでゆっくりと溶かしていた。
◇◆◇
それから3人はおしゃべりして、お菓子を食べ楽しく過ごした。楽しく笑いあいながら、アイはこんな事を考えた。きっと、このひまりは愛されて育ってきたんだ。
愛されて育ってきたから、愛情に飢え喘いでいる人のことなど理解できないのだ、と。こうしてまた新しい言い訳を拵えて、アイは醜く延命するのだった。
でも、今日はじめて会った自分に、わが子のように――決してわが子と同等にではないが――それでもわが子のようにやさしくしてくれる人を侮辱してまで作った生きていてもいい理由に、意味なんぞあるのかと。やさしい人を踏み台にして生きながらえる自分がいつもよりもっと、もっとずっと……醜く感じられるのだった。そしてきっと、それは間違いではないのだろう。自分の母親に対して罪悪を感じたあとは、友の母に対して罪悪感を覚える。
アイの人生とはそういうものだった。罪悪と罪悪感があざなえる縄のように交互に訪れる。そして、その降り積もる罪悪の雪の重みを片時も忘れることなく生きている。そんな生だった。アイの敬愛する先生は、『恋は罪悪ですよ』と言っていたが、アイにとっては“生こそが罪悪”で、“罪悪こそが生”だった。
◇◆◇
はるひがお風呂に行ったのを見計らって、お風呂から上がったアイにひまりが声をかける。
「アイちゃんアイちゃん、こっちおいで。」
ひまりが右手を動かす。しっしと追い払われることしかない人生なので、最初はそうされているのかと思ったが、いつもと見る手の動きと、動作が逆なことに気がついた。おいでおいでと手招きしているのだった。
おっかなびっくり控えめに、けれども着実に、ひまりの居る方へハイハイで近づいていく。その膝に吸い寄せられたのだった。怪我をしてニンゲンにおびえる子猫のようだった。向かい合ってひまりに抱っこされる。
「……?あの?」
「いや、なんとなくね?……なんとなく、今日は1日アイちゃんを眺めていたら、……ほんとうになんとはなしにね、抱きしめたくなったんだ。……今から手を上に上げるからね、怯えないでね。」
そうして、アイを怯えさせないようにだろう、とても徐ろに手を上げる。そうして、アイの黒髪を右手で撫で始める。アイにはひまりがなんでそうするのかが分からなかった。なんでなんの役にも立ってないのに、なにもあげられてないのに、抱きしめてくれて、撫でてくれるのか、ほんとうにわからなかった。
でも何も聞かなかった。もし理由を問うたらこの時間が終わってしまう気がして。今はただ何も考えずに、この陽だまりを享受していたかった。ほかには何もいらなかった。さっき感じた罪悪感が溶けていくようだった、でも罪悪の方は決して溶けてはくれないのだろうと、そう悟った。
◇◆◇
暫く2人とも無言だった。心地良いい静寂の中で、お互いの心臓の音だけを聞いていた。御言葉なんぞはこの場所には要らないのだった。溶けて、体温が混ざって、自分と相手との境界が分からなくなった。でもそれも心地よいのだった。
「……アイちゃんさ……。」
ピタリとくっついているから、声がひまりの身体から振動して直接聞こえてくる。その声につつまれるような感があった。
「……うん……。」
幼子に戻ったようだった。今でも幼子だが、もっと昔。まだ、世界をそのまま受け入れて、信じて疑わなかったときよような心地。世界にまだお母さんしかいなかった時代。チョコレートとジャムしかなかった世界。なんにも心配なことなんて、なんにもむずかしいことなんかなかった頃。
「さっきアイちゃんのお母さんと話したんだけどね?アイちゃんをうちにお泊りさせてもいいですか?って。」
「……うん。」
「もし……つらいことがあるなら。……アイちゃんのおうちに、かなしいことがあるなら、いつでもうちにきていいんだからね?」
「……うん……。」
「それに、もしアイちゃんとはるひが聖別の儀の勢いのまま結婚でもしたら、私たち、家族になるんだしね!アイちゃんの……お義母さん……楽しいだろうね。」
「……おかあさん。」
アイははっとした、自分のお母様に不義理を働いているような気がしたのだ。誰かを母と慕うということは、自分の母を傷つけはしないかと。万に一つもおかあさまは悲しまないと知っているのに、悲しんでくれないと。
でも、アイにとっては十分だった、万に一つで十分だった。どんなに小さくても、自分のせいでおかあさまをかなしませる可能性があるのなら、それを排除したいと思うのだった。おかあさまのしわあせを切に願うのだった。それほどアイは母を愛しているのだ。
理由なんてなかった。おかあさまがアイのおかあさまだから、愛している。たといおかあさまがアイをこどもだからという理由で、無条件には愛してくれないと知っていても。アイは愛してしまうのだった。さっき“母親は子を愛するのだ”と聞かされて、虫唾が走ったのに。アイは“子は無条件に母を愛するのだ”と思ってしまうのだった。おかあさまがアイのおかあさまだから、どんなにきらわれても、なぐられても、あいすることはやめられないのだった。
◇◆◇
「ただいま~、おかーさんとアイくん、すっかり仲良しだねぇ。」
はるひが湯気の立つ頭を拭きながら帰ってきた。その言葉は少しの嫉妬をはらんでいた。
「あら~!はるひ妬いてるの?ねえねえ!大丈夫よ!わたしははるひのお母さんなんだから!」
「おかーさん!うっとおしいっ!」
「っ……かっ帰ります!」
――これ以上ここにいてはいけない、自分は2人にとって邪魔な存在だし、またしあわせな家族の不純物になるところだった。それに、ここにいると、自分のお母様への愛情を疑ってしまいそうになる。
「えっ!泊まっていこうよ~!」
「そうねぇ、それ外を見て、雪が降っているわ、それも大雪よ。こんなに降り積もって。今から帰るのは危ないわよ?……お父さん大丈夫かしら?」
――雪?しかもこんな大雪が。雪が降る気配なんてなかったのに、この国でこの季節に雪があんなふうに積もったりするか?
「あっ……ご、ごめんなさい……。ごめんなさいぃ……。」
雪を目に捉えた瞬間に、突然蹲って謝り始めたアイに2人ともぎょっとしてしまう。
「ど、どうしたの?アイくん?ただの雪だよ?アイくんがなんで謝るのさ。」
「確かにこんな大雪は見たことないけど、アイちゃんのせいじゃないでしょ?」
ふるふるとアイは首を振る。
「いいえ、違うんです。これはわたくしのせいなのです。きっと。帰らないとって思っているのに、迷惑だと分かっているのに。わたくしの、このおうちを、ひまりさんと離れがたいと言う気持ちが、雪となって降り積もっているのです。遣らずの雨のように。しんしんと、ここにいたいという気持ちが降り積もっているのです。」
「……確かにアイちゃんはこころをもつものだけど……ここまでのことができるのかしら?」
「そうだよ!ただのいじょーきしょーだよ!アイくんのせいじゃないよ!」
◇◆◇
2人の言葉にゆっくりと面を上げたアイの、その顔をみたはるひは感じた。その、自責の念と申し訳なさに彩られた、震えるまつげの上目遣いみた時に、たった一度だけアイの涙をみたときと、同じ気持ちになった。熱を帯び、ピリッと電気が走る身体。前髪の影に隠れたはるひの眼光が温度を増す。無意識に上がった口角を右手で覆い隠す。
――あぁ、これがみたかったのだと。
――でも、どうしてだろう?すきなひとの悲しい顔がみたいなんて、ふつうはえがおがみたくなるっておかーさんもさっきいっていのにな。わたしってふつうじゃないのかな?
◇◆◇
「はるひが彼氏を連れてきた?!は!?まだ早いだろう!家の娘はまだ性別も決まってないんだぞ!!……うちに泊まった?!なんでお前は許したんだ!」
「まあまあアナタ、お似合いのかわいいカップルよ?」
「そんな問題じゃない!父親に挨拶もせずにはるひと付き合うなんて!うちに泊まるなんて!!その男をここに連れてこい!とっちめてやる!!」
「だってーアイちゃんー!こっちにきてくれるー?」
「……ん?あい……?」
◇◆◇
隣の部屋に敷かれた布団の上で、アイは震えていた。聞こえてくる春日春日の性格像が、自分の父親と一緒だったからだ。
春日春日の父親である、春日春日は、所謂昔気質の強い男だった。
生まれたときからやんごとなき身分であったアイの父オイディプスと、生い立ちは決して似通ってはいないが、通づるところがあった。家父長制の気質の強い家で育てられたのだ。
といってもしゅんじつは父から教えられる悪しき風習――と彼が判断したもの――は決して受け継がなかった。そして自らの心が善いと認めたものだけを、父から受け継ぎ――少なくとも彼そうできたと信じている――決して母や妹たちを蔑ろにする父を真似ようとはしなかった。
彼が父から真似た――もしくは彼の性癖だったのかもしれないが――ことは、男子たるもの女子供をよく守り、自分の事を犠牲にしてでも家族を守り抜くという一言に尽きた。彼の父親も妻と娘に対しては差別的ではあったが、いつもそれらを守ることに躊躇はなかった。この点で言えばオイディプスとしゅんじつに重なるところもあった。彼も家父長制的な家で育ったが、今は妻と娘たちを溺愛しているし、男子たるもの強くあれと言う精神を持っている。
違うのはしゅんじつはそれを自ら選び取り、オイディプスはそうなるしかなった、という点だ。また、おおよそ対極にも思える、庶民生まれのしゅんじつと高位貴族であるオイディプスの人生が数奇にも交わったことがあった。彼らは若かりし頃同じ女性を愛したのだ。
◇◆◇
その娘の名はサクラ。サクラ・マグダレーナ、貧民の生まれのため家名はなく――“マグダラのサクラ”――つまり“マグダラ生まれのサクラ”という意味であった。サクラは生まれたときからその美しさで周囲の人々を畏れさせていた。
しかし、サクラにとってはどうでもよかった。別の関心事があったのだ。サクラには幼なじみの男の子がいた。その子といつまでも繕いまみれの服や明日の飯もないことを笑いあいながら生きていたかった。山のなかで、貧しいその日暮らしをしていた。2人はそれでも幸せだった。
でも、サクラはある日それじゃあ足りなくなってしまった。この世でいちばんうつくしいとまで噂のサクラを、その時分まだただの平民の子であったしゅんじつが一目見ようとやってきたのだった。そしてその一目で恋に落ちた。一番下まで落ちたのだ。そしてすぐに求婚した。この恋が陽炎と消えてしまわぬように。
それがいけなかった、それがこの片田舎の美少女を傾国の美女へと変えるきっかけだった。彼女に気づかせてしまった。自分の美貌に価値があると。幼なじみと二人で花冠を作るよりも、この美しさを利用して純金の冠を手にしてやろうと。
それからは早かった。サクラは2人だけのユートピアであった山から降り、俗世の人塵の蔓延る街に降りていってしまった。思うにこの時がサクラと幼なじみとの決定的な別れの時であった。
サクラは貧民から平民となるために、春日と恋をし、平民から貴族となるために、オイディプスと逢瀬を重ねたのである。それから自らの美しさでもって春をひさぎ、地位を高めてきた。
外見ではなく、自分の能力1つでのし上がってきた――と少なくとも本人は自負している――エレクトラにはその点も気に食わないのであった。真にサクラとエレクトラは対照的だった。そして、その生き様は決してお互いを解さぬ平行線であった。アイが生まれるまでは。アイという子の2人の母親として、アイという存在によって、アイという点において、2つの線は交わったのである。
◇◆◇
――どんなやつだ?どんな男だ。まだちいさい、かわいいウチの娘を誑かしたやつは。どうせ碌なやつじゃねぇ。春日家の一人娘に手を出そうなんてやつは。いい度胸だ。どんな高位の貴族でも許しちゃおけねぇ。一発殴って分からせてやらねぇと。……来やがった、ふてぇ野郎だ……のこのこと――。
拳に力を込めたしゅんじつの前に、アイが怯えた眼をしながらおずおずと姿を現す。
「……サクラ……?」
――なんでここに?いや、ありえない、だってサクラは……。いや、それに……あの頃のサクラだ。この髪、顔、なんで――。
形をなしていない疑問が次々とこぼれ出る。
「……サクラ……、どうしてだ……?、いやありえない、サクラ……、どうしてここに、その姿は――?」
普段狼狽する姿を決して家族に見せようとしない夫がしどろもどろになっている姿を見て、ひまりは驚いてしまう。
「あ、アナタ?どうしたの……?それに、さくらって……?」
「……あ、あの……?」
困惑するアイの表情をとらえたしゅんじつがハッとする。
――いや、違う確かにあの頃のサクラの生き写しだと思ったが、違う、サクラはこんな表情はしない、こんな態度は取らない。それにこの娘とは髪の色も、眼の色だって違う。サクラはルビーの眼をしているが、この子はサファイアだ。
神に跪くように屈み込み、問う。
「キミは……?」
「!……申し遅れました!大変申し訳ありません!お初にお目にかかります……わたくしの名は、アイ、と申します。アイ・ミルヒシュトラーセでございます。春日春日様。お、お会いできたこと、恐悦至極の念に堪えません。」
「あい……アイ?アイ・ミルヒシュトラーセ?……それじゃあ、君が。」
「は、はい。はるひちゃんの友……いえ、はるひさんの聖別の儀の相手役を務めさせて頂きます。アイでございます。」
「そうか、そういうことか。道理でアイツ……俺に君の姿を見せてくれない……君と会わせてくれないわけだ。」
しゅんじつは何かずっと不可解だったことが氷解したように。ひとり納得する。
「……あいつ?と申しますと?」
「いや、いいんだ。はじめまして、もう知ってると思うが、俺は春日家の家長、春日春日の父親、春日春日だ。……アイ様?」
「様などと!どうかおやめください!……わたくしなどは、ただのアイと、そうお呼びください。」
アイが深く頭を下げ、しゅんじつの眼が大きく見開かれる。
「なるほど、アイツとは正反対だ。似ても似つかない。そんなに怯えないでくれ、俺は君の敵じゃあない。それに、君はミルヒシュトラーセだろう?上の立場の者が軽々しく頭を下げるものじゃないよ。春日家なんぞ、君からしたら末端も末端だろう――」
今はまだ、と心のなかで付け足す。
「いえ、わたくしなんぞは比することも烏滸がましい者です。どうかご容赦下さい。」
――なるほど、これがほんとうにアイツの息子か?いや、アイツらが母親だからこう育ったのか?
「では、どうだろう。こうしようじゃないか。君はウチのはるひの友達で、俺は友達の父親だ。だからまぁ、既に親しいとも言えるし、お互い気楽に行こうじゃないか。それに、親しい者たちの間では慇懃は、むしろ無礼というものだ。君も礼を欠きたくはないだろう。」
しゅんじつはこの一瞬でアイが礼を欠くことを最も恐れているのだと、その慧眼でもって見抜き、即座にそれを逆手に取った提案をする。こう言われてはアイも失礼を働かない為には、慇懃な態度をやめざるを得ない。
「分かりました。では、しゅんじつさん……と。」
「おお、よろしくアイ君、まぁ、とりあえず座ってくれよ。獲って食ったりしないからよ。」
アイに座布団を指し示す。
「失礼致します。」
――しっかし、この美しさ、完璧にサクラの生き写しだな。サクラより美しいものなんてこの先お目にかかれるもんじゃねぇと思っていたが、生きてると、あるもんだなぁ。
「…………。」
「……?」
無言で見つめられアイはもじもじと身を揺らす。
「あなた!アイちゃんが怖がってるでしょ!やめなさい!」
ペシッと肩をはたくひまり。
「い、いや……威嚇してるわけじゃないぞ?ただどんなふてぇ野郎がくるかと思ってたら、こんなに綺麗な子が来て、驚いているだけだ。」
「そんなこと言って、さっきは拳握って、『とっちめてやるぅ!』って言ってたじゃない。」
「!ひうっ……!……。」
ただでさえちいさい体躯をさらに縮こまらせるアイ。
「あ、アイくん!違うんだ。怯えないでくれ!ひまりも!この子を怖がらせるようなことを言うな!俺だってこんなにかわいい子を殴ったりはしねぇよ!」
「……ほんとう、ですか……?」
アイが震える瞳で尋ねる。
「あ、ああ!本当だ!安心してくれ!」
はるひとひまりには、アイに怖がられないよう必死な父が、初めて見る小動物に狼狽える大型犬のようで、声を上げて笑ってしまう。
「「あはははっ!」」
「お前ら!笑うんじゃねぇ!」
◇◆◇
ひと通り騒いだあと、しゅんじつが家長らしくまとめる。
「ふぅ……ときにアイくんよ、よく来てくれたな。俺も君には聖別の儀の前に一度は会っておきたかったんだ。だが、エレクトラは会わせてはくれないし、君はいつも来客があると別宅に隠れているからな。今回はちょうどよかった。」
アイは驚いていた。自分なんぞに会いたがる人がいるという奇妙もそうだが、なによりも母を呼び捨てにするしゅんじつに対してだ。貴族のなかで母を呼び捨てにするなんて、それこそ、父ぐらいしかいないのに。
「お母様と、親しいのですね?」
「ん?ああ、そうだな。親しいというより、腐れ縁といったほうが正しいが。春日春日と、エレクトラ、オイディプス、あと……サクラ、それとファントムもか、この5人はまぁ昔からの仲でな。まぁ、君とはるひ、陽炎陽炎のような仲だと思ってくれたらいい。……まぁ、君たちほど仲が良かったわけではないが。」
――まぁ、この子たち3人も本質的な意味でお互いの仲間か、といわれると怪しいがな。そもそも、政治に絡み、立場ある家に生まれた時点で、真実の友など望むべくもないことだ……はるひには悪いことをしたが……。
「へぇ~、知らなかったわ。アナタそんな話してくれたことないじゃない。」
「誰にでも知られたくない過去はあるだろう……それにアイ君にはその権利があると思ったから、教えただけだ。」
「お母さまとお父さま……さくら?さまと……ファントム先生も?」
「おや、サクラのことは知らないのに、ファントムのことは知っているのか……ふむ。」
――何者かの作為を感じるな。すこし、対話をすることで、こころを視てみるか。
「アイ君、少し俺とサシで腹を割って話をしないか?」
「おはなし……ですか?」
「ああ、人と心を通わせるには、心で闘うのが手っ取り早いという野蛮なやつもいるが、俺はそんなやつらとは違う。俺は膝を突き合わせて、胸襟を開いて、同じ飯を食って話す。これこそが心を通わせるものだと思っている。」
「それは……素敵な考えですね。」
たおやかな白い指を包む袖口を口元に添えてはにかむアイ。春日は、その薄氷の生色にまだ宵のない時代に恋恋た、解語の徒桜の匂いを垣間見るのだった。
「……君は――。」
◇◆◇
2人は暫くたいせつなことや、どうでもいいことを徒然に話した。
――この子の生き方は、他人の策謀に裏打ちされている。哀れだな……この子は自分で何事をも選んではいない。自分で選んだつもりが、悉く他人に選ばされているだけだ。つまり、自分の人生を生きていないのだ。人生とは、自分で何事かを選び抜くことなのだから。
まぁ、俺もこの子供を搾取する大人の1人なのだが。サクラの面影の射すこの子を利用するのは忍びないが、何物をも持たない人間が夢を持つにはそうするしかないのだ。悪びれはしない、許してくれとも思わない。金持ちから奪うことが、悪いことなのか?持たざる者が、持つ者から奪うことが。いいや、ありえない。罪にはなりえない。
◇◆◇
「君は、罪悪とは何だと思う?そもそも罪悪とはこの世に存在すると思うか?」
「罪悪……ですか。わたくしの短い生で得た言葉で語るには、少々荷が重いので、友の言葉をわたくしなりに解釈したものでお答えしてもよろしいでしょうか?」
「そこに君の思想が介在しているのなら。」
「ありがとうございます。」
「しかし友というと、陽炎陽炎か?それとも、まさかはるひが?」
「いいえ、確かにかげろうとはるひさんが、わたくしをお二人の友達にしてくれるまで、わたくしには友の1人もおりませんでした。生まれてこのかた孤独な一日一日に引きずられるように生きていました。勿論兄姉はやさしくしてくれましたが、それは友とは違います。
彼らはわたしくしがわたくしだから愛してくれるのではありません。わたくしが彼らの弟だからです。きっと他人として生まれていたら、彼らの視界にも入らずに一生を終えましょう。
そのように川に流る2枚の葉がたまたま重なったような縁なのです。その人がその人だから愛している、というのがほんとうの愛だとわたくしは思っています。だから、むしろ師や友との間にこそ見出すものなのかもしれません。」
「しかし、君も兄姉たちを愛しているのだろう?」
「もちろんです!そのことが卑しいわたくしの唯一の誇りであります。わたくしは兄姉のためなら何物も惜しくはないのです。ですが、わたくしは彼らに何事をも与えられてはいません。ですから、友や師に抱く愛とは違うのです。……わたくしの場合は友にも何も与えられてはおりませんが。
話がそれましたね。孤独だったわたくしは、書物の中に友を見出したのです。ええ、地獄の書物の中にです。文学書であっても、学術書であってもそこには必ずそれを記した者の思想が宿ります。そして書物を読むことは対話です。双方向的な対話では決してありませんが。そうしてわたくしは文学や哲学書、宗教書を読み漁り、一方的にその著者を友としてきたのです。わたくしの思想を形作ったのは主にその友たちとの“対話”です。」
「なるほど、それが君の言う友か……了解した。して、そうやって定義づけられた君の答えとは――?」
◇◆◇
「罪悪のお話でしたね。わたくしは罪悪は確かにこの世に存すると思います。そしてそれには罰が伴うものだと思います。たとい必ずしも罰が与えられなかったとしても。そして何を罪悪と思うか、ですよね。そうですね……まず、恋は罪悪だと思います――」
「ふむ、例えば持たざる者が持つ者から奪うことは?……君はどう考える?」
「それは例えば、“苦学生が高利貸しの老婆を斧で殺す”ような場合ですね。友の1人フョードルが論じていました。わたくしはそれも罰を与えられるべき罪だと考えます。
しかし、わたくしが考える罰とは救いです。罪を犯したのに、罰を与えてもらえないというのは、恐ろしいことです。許されないからです。許しを得たいというのは、人間の根源的な欲求です。なぜなら罰を与えられるまでは、自分が犯した罪が発覚しないか、責め咎められることがないか、なによりその罪を犯したおかげで得た幸福を、その罪自体が打ち砕きはしないか、ということを朝起きるたびに、愛しい人と過ごしているときにふと、または夜の安らかな安息のなかで、一生怯えて暮らすことになるのです。
だからこそ、罪を犯してもいないのに罰を求める人が現れたりするのだと思います。罰を得ることで自分の中の罪悪を消したいと願うのです。もっともそれで消えるのは罪悪ではなく、罪悪感だけかもしれませんが。」
「つまり、罪を犯したのに罰を与えられないのは不幸だと。なぜなら罰を受け入れて初めて人間は許され、安寧を得られるからと……ふむ。」
――俺もいつか罰を受けるのか?いや、俺は罪を犯してはいない、嫁と娘をより幸せなところに連れていきたいだけだ。それに、そもそも俺は罰を求めているのか?だがこのサファイアの瞳に見つめられると、オイディプスが理想を語る眼を思い出す。
◇◆◇
「君はどうしたい?何百もの深い見識のある友たちとの対話で、君の思想はどう変わったのだ?」
「わたくしがしたい事と、わたくしがするべき事は違います。書物の中の友たちや先生は、わたくしが“変えられるものと変えられぬものを見分ける洞察”を授けてくれました。“変えるべきものを変える胆力”も。そしてなにより、“変えられぬものを受け入れる勇気”も。友はわたくしがするべき事を教えてくれました。
しかし、わたくしがこれからの人生で行うのは、わたくしがしたいことでございます。友の意見とは関係がありません。……かなしいですが。友の、先生の忠告に従わない路を往くことを選んだのです。わたくしが選び取るのはわたくしがしたいことでございます。」
「……して、それは?」
「おかあさまの望みを叶えることです。お父様のお役に立つことです。そして、その見返りとして、わたくしを愛して頂くことです。それがわたくし、アイ・ミルヒシュトラーセの唯一手ずから選んだことです。生きる道です。」
アイの全てを貫くような、だか何物も見えてはいないサファイアの眼が、何よりも雄弁にしゅんじつに伝えた。
「……それではさっき君の言った、ほんとうの愛とは自家撞着しているように聞こえるが。」
――この子は、自分で唯一選んだことだと言っているが、それさえ実を言うと他人に選ばされているということに、気がついていない。
「そのとおりです。わたくしの思想、信念、信仰、哲学、世界観、その全てと対立する生き方です。わたくしは自身の信仰に背いているのです。わたくしは独りの背教者なのです。」
「……何故だ?自ら背信者となってまで、何故に父母に棹さして生きることを選ぶ?それは自分が1番つらい道だと知っているだろう?自分に嘘をついて生きるなど。」
――この子がエレクトラの思惑通りに動いてくれたら、我が家にとっても利益となる。だのに何故俺はこんな……それをやめさせるような言葉を吐いている。感心だな、と褒めて臆病な自尊心を慰めてやればいいではないか。なぜおれは――
今まで流れる水が如く理路整然と論理を並び立てていたアイが、初めてその言葉を詰まらせる。まるで言葉を愛しているように。わが子のように、言葉を――。
「……はい……そのとおりです。……ですが、わたくしにはこの道しかないのです……。……わたくしには、わたくしには……。わたくしの唯一の師、本の中の師、ルシウスは、彼の母を愛していました。たといコルシカ島に流されても、自分を慰めることなく、自己憐憫にふけることもなく、その地で研究を続け、母に手紙を書いたのです。わたくしは師から、自分がどんな目に遭っても、母を思う心、そして家族を愛することを学びました。」
「しかし、聖別の儀だって、君をさらに軍事的に利用できるしようと、エレクトラが考えたものだぞ?君を愛してのことじゃない。そんな母を何故愛する?」
――やめろ、儀式の相手をはるひにするのだって骨を折ったのに。俺もエレクトラの片棒を担いだのに。俺もこの子を利用しているのに、何故こんな事を聞く?俺は何がしたいんだ?
「おかあさまが……そして、おとうさまも、わたくしを愛して下さっていないのは重々承知です。そんなことは物心つく前に、身体に教え込まれました。
でも、それがなんだと言うのです?愛情とは愛してくれるという確信が持てる相手だけを愛することでしょうか?この人は私に与えてくれる、だから返してやってもいいだろうなんてものは愛情ではあり得ません。
愛情とは、ほんとうの愛とは――相手に憎まれていても、嫌われていても、愛してくれているかどうか分からなくても、それでも愛することです。The Art of Loving〈愛するということ〉はそういうことです。条件なんぞ愛の前には存し得ないのです。わたくしは、ただわたくしがおかあさまの子だから、おかあさまを愛するのです。」
◇◆◇
「それは、あまりにも、つらい……。」
「……!哀しんで下さるのですね。こんなわたくしのために。貴方はお優しいかたです。ひまりさんやはるひさんがやさしい人なのも、得心がいきます。」
――ちがう、やめてくれ、俺はこの子の母親と一緒になってこの子供利用しているだけだ。やさしい人なんかじゃない。
「ですから、わたくしはたとえ条件付きの愛情でも、ほんとうの愛とは呼べないものでも、おとうさまとおかあさまからそれが、一滴でもいいからそれが、ほしいと願わずにはいられないのです。この渇望は全てに優越します。其処には合理は必要ありません。
わたくしはただ、おとうさまとおかあさまの子供だから、お二人を愛するのです。このこころの前には、道理なんぞ露と消えてしまいます。子はその親の子供だから、親を愛するのです。それが全てなんです。それがわたくしの全てで。わたくしの世界の全てなのです。」
――親を愛していない子供なんぞいくらでもいる、俺もそんなことは知っている。だが、この子にはそんなことは、ひとえに風の前の塵と同じなのだろう。
この子はこんな俺を、この俺をつらまえて、やさしいひとだと、そう、言った。この子の最愛の母と共に、この子の地獄への道を、この両の手で舗装し、背中を押し、あちらへ行けと指を差す、この俺を。家族を守るためなら何だってしてきた。家族にさえ分かってもらえれば、それでいいと思っていた。
だか――この子は俺に罰を与えてはくれないだろう、こころやさしいこの子は。こころかなしいこの子は。だが――この子は、――この子は俺を赦してくれるだろうか?俺の罪を――。
◇◆◇
「アイ、おれは春日、春日春日だ。いつか、この俺のことも、祈ってはくれないか。何にでもいい、君が信じるものなら、君が奉じるものなであるのならば、『あなたの僕、春日』と。……それだけでいいのだから。」
アイには彼が赦しを求めているのだと分かった。それは、アイがずっと求めているものでもあったからだ。それが自分に与えられるのなら、与えないわけはない、とアイは勢い込んだ。
「わたくし、この先ずっとあなたのことを、お祈りします。」
少年は熱っぽい調子でそういうと、ふいに笑いだし、彼に近づき、低く垂れた彼の頭を、しっかり胸に抱きしめた。
――その姿はまるで、孤児に抱擁を与える、聖母のようであった――
◇◆◇
アイの耳は孤児の声を聞いた。
「ああ……サクラ――」
――さくら――?
アイの最後の言い訳を、アイが生きていていい言い訳を、やさしい陽だまりのなかでゆっくりと溶かしていた。
◇◆◇
それから3人はおしゃべりして、お菓子を食べ楽しく過ごした。楽しく笑いあいながら、アイはこんな事を考えた。きっと、このひまりは愛されて育ってきたんだ。
愛されて育ってきたから、愛情に飢え喘いでいる人のことなど理解できないのだ、と。こうしてまた新しい言い訳を拵えて、アイは醜く延命するのだった。
でも、今日はじめて会った自分に、わが子のように――決してわが子と同等にではないが――それでもわが子のようにやさしくしてくれる人を侮辱してまで作った生きていてもいい理由に、意味なんぞあるのかと。やさしい人を踏み台にして生きながらえる自分がいつもよりもっと、もっとずっと……醜く感じられるのだった。そしてきっと、それは間違いではないのだろう。自分の母親に対して罪悪を感じたあとは、友の母に対して罪悪感を覚える。
アイの人生とはそういうものだった。罪悪と罪悪感があざなえる縄のように交互に訪れる。そして、その降り積もる罪悪の雪の重みを片時も忘れることなく生きている。そんな生だった。アイの敬愛する先生は、『恋は罪悪ですよ』と言っていたが、アイにとっては“生こそが罪悪”で、“罪悪こそが生”だった。
◇◆◇
はるひがお風呂に行ったのを見計らって、お風呂から上がったアイにひまりが声をかける。
「アイちゃんアイちゃん、こっちおいで。」
ひまりが右手を動かす。しっしと追い払われることしかない人生なので、最初はそうされているのかと思ったが、いつもと見る手の動きと、動作が逆なことに気がついた。おいでおいでと手招きしているのだった。
おっかなびっくり控えめに、けれども着実に、ひまりの居る方へハイハイで近づいていく。その膝に吸い寄せられたのだった。怪我をしてニンゲンにおびえる子猫のようだった。向かい合ってひまりに抱っこされる。
「……?あの?」
「いや、なんとなくね?……なんとなく、今日は1日アイちゃんを眺めていたら、……ほんとうになんとはなしにね、抱きしめたくなったんだ。……今から手を上に上げるからね、怯えないでね。」
そうして、アイを怯えさせないようにだろう、とても徐ろに手を上げる。そうして、アイの黒髪を右手で撫で始める。アイにはひまりがなんでそうするのかが分からなかった。なんでなんの役にも立ってないのに、なにもあげられてないのに、抱きしめてくれて、撫でてくれるのか、ほんとうにわからなかった。
でも何も聞かなかった。もし理由を問うたらこの時間が終わってしまう気がして。今はただ何も考えずに、この陽だまりを享受していたかった。ほかには何もいらなかった。さっき感じた罪悪感が溶けていくようだった、でも罪悪の方は決して溶けてはくれないのだろうと、そう悟った。
◇◆◇
暫く2人とも無言だった。心地良いい静寂の中で、お互いの心臓の音だけを聞いていた。御言葉なんぞはこの場所には要らないのだった。溶けて、体温が混ざって、自分と相手との境界が分からなくなった。でもそれも心地よいのだった。
「……アイちゃんさ……。」
ピタリとくっついているから、声がひまりの身体から振動して直接聞こえてくる。その声につつまれるような感があった。
「……うん……。」
幼子に戻ったようだった。今でも幼子だが、もっと昔。まだ、世界をそのまま受け入れて、信じて疑わなかったときよような心地。世界にまだお母さんしかいなかった時代。チョコレートとジャムしかなかった世界。なんにも心配なことなんて、なんにもむずかしいことなんかなかった頃。
「さっきアイちゃんのお母さんと話したんだけどね?アイちゃんをうちにお泊りさせてもいいですか?って。」
「……うん。」
「もし……つらいことがあるなら。……アイちゃんのおうちに、かなしいことがあるなら、いつでもうちにきていいんだからね?」
「……うん……。」
「それに、もしアイちゃんとはるひが聖別の儀の勢いのまま結婚でもしたら、私たち、家族になるんだしね!アイちゃんの……お義母さん……楽しいだろうね。」
「……おかあさん。」
アイははっとした、自分のお母様に不義理を働いているような気がしたのだ。誰かを母と慕うということは、自分の母を傷つけはしないかと。万に一つもおかあさまは悲しまないと知っているのに、悲しんでくれないと。
でも、アイにとっては十分だった、万に一つで十分だった。どんなに小さくても、自分のせいでおかあさまをかなしませる可能性があるのなら、それを排除したいと思うのだった。おかあさまのしわあせを切に願うのだった。それほどアイは母を愛しているのだ。
理由なんてなかった。おかあさまがアイのおかあさまだから、愛している。たといおかあさまがアイをこどもだからという理由で、無条件には愛してくれないと知っていても。アイは愛してしまうのだった。さっき“母親は子を愛するのだ”と聞かされて、虫唾が走ったのに。アイは“子は無条件に母を愛するのだ”と思ってしまうのだった。おかあさまがアイのおかあさまだから、どんなにきらわれても、なぐられても、あいすることはやめられないのだった。
◇◆◇
「ただいま~、おかーさんとアイくん、すっかり仲良しだねぇ。」
はるひが湯気の立つ頭を拭きながら帰ってきた。その言葉は少しの嫉妬をはらんでいた。
「あら~!はるひ妬いてるの?ねえねえ!大丈夫よ!わたしははるひのお母さんなんだから!」
「おかーさん!うっとおしいっ!」
「っ……かっ帰ります!」
――これ以上ここにいてはいけない、自分は2人にとって邪魔な存在だし、またしあわせな家族の不純物になるところだった。それに、ここにいると、自分のお母様への愛情を疑ってしまいそうになる。
「えっ!泊まっていこうよ~!」
「そうねぇ、それ外を見て、雪が降っているわ、それも大雪よ。こんなに降り積もって。今から帰るのは危ないわよ?……お父さん大丈夫かしら?」
――雪?しかもこんな大雪が。雪が降る気配なんてなかったのに、この国でこの季節に雪があんなふうに積もったりするか?
「あっ……ご、ごめんなさい……。ごめんなさいぃ……。」
雪を目に捉えた瞬間に、突然蹲って謝り始めたアイに2人ともぎょっとしてしまう。
「ど、どうしたの?アイくん?ただの雪だよ?アイくんがなんで謝るのさ。」
「確かにこんな大雪は見たことないけど、アイちゃんのせいじゃないでしょ?」
ふるふるとアイは首を振る。
「いいえ、違うんです。これはわたくしのせいなのです。きっと。帰らないとって思っているのに、迷惑だと分かっているのに。わたくしの、このおうちを、ひまりさんと離れがたいと言う気持ちが、雪となって降り積もっているのです。遣らずの雨のように。しんしんと、ここにいたいという気持ちが降り積もっているのです。」
「……確かにアイちゃんはこころをもつものだけど……ここまでのことができるのかしら?」
「そうだよ!ただのいじょーきしょーだよ!アイくんのせいじゃないよ!」
◇◆◇
2人の言葉にゆっくりと面を上げたアイの、その顔をみたはるひは感じた。その、自責の念と申し訳なさに彩られた、震えるまつげの上目遣いみた時に、たった一度だけアイの涙をみたときと、同じ気持ちになった。熱を帯び、ピリッと電気が走る身体。前髪の影に隠れたはるひの眼光が温度を増す。無意識に上がった口角を右手で覆い隠す。
――あぁ、これがみたかったのだと。
――でも、どうしてだろう?すきなひとの悲しい顔がみたいなんて、ふつうはえがおがみたくなるっておかーさんもさっきいっていのにな。わたしってふつうじゃないのかな?
◇◆◇
「はるひが彼氏を連れてきた?!は!?まだ早いだろう!家の娘はまだ性別も決まってないんだぞ!!……うちに泊まった?!なんでお前は許したんだ!」
「まあまあアナタ、お似合いのかわいいカップルよ?」
「そんな問題じゃない!父親に挨拶もせずにはるひと付き合うなんて!うちに泊まるなんて!!その男をここに連れてこい!とっちめてやる!!」
「だってーアイちゃんー!こっちにきてくれるー?」
「……ん?あい……?」
◇◆◇
隣の部屋に敷かれた布団の上で、アイは震えていた。聞こえてくる春日春日の性格像が、自分の父親と一緒だったからだ。
春日春日の父親である、春日春日は、所謂昔気質の強い男だった。
生まれたときからやんごとなき身分であったアイの父オイディプスと、生い立ちは決して似通ってはいないが、通づるところがあった。家父長制の気質の強い家で育てられたのだ。
といってもしゅんじつは父から教えられる悪しき風習――と彼が判断したもの――は決して受け継がなかった。そして自らの心が善いと認めたものだけを、父から受け継ぎ――少なくとも彼そうできたと信じている――決して母や妹たちを蔑ろにする父を真似ようとはしなかった。
彼が父から真似た――もしくは彼の性癖だったのかもしれないが――ことは、男子たるもの女子供をよく守り、自分の事を犠牲にしてでも家族を守り抜くという一言に尽きた。彼の父親も妻と娘に対しては差別的ではあったが、いつもそれらを守ることに躊躇はなかった。この点で言えばオイディプスとしゅんじつに重なるところもあった。彼も家父長制的な家で育ったが、今は妻と娘たちを溺愛しているし、男子たるもの強くあれと言う精神を持っている。
違うのはしゅんじつはそれを自ら選び取り、オイディプスはそうなるしかなった、という点だ。また、おおよそ対極にも思える、庶民生まれのしゅんじつと高位貴族であるオイディプスの人生が数奇にも交わったことがあった。彼らは若かりし頃同じ女性を愛したのだ。
◇◆◇
その娘の名はサクラ。サクラ・マグダレーナ、貧民の生まれのため家名はなく――“マグダラのサクラ”――つまり“マグダラ生まれのサクラ”という意味であった。サクラは生まれたときからその美しさで周囲の人々を畏れさせていた。
しかし、サクラにとってはどうでもよかった。別の関心事があったのだ。サクラには幼なじみの男の子がいた。その子といつまでも繕いまみれの服や明日の飯もないことを笑いあいながら生きていたかった。山のなかで、貧しいその日暮らしをしていた。2人はそれでも幸せだった。
でも、サクラはある日それじゃあ足りなくなってしまった。この世でいちばんうつくしいとまで噂のサクラを、その時分まだただの平民の子であったしゅんじつが一目見ようとやってきたのだった。そしてその一目で恋に落ちた。一番下まで落ちたのだ。そしてすぐに求婚した。この恋が陽炎と消えてしまわぬように。
それがいけなかった、それがこの片田舎の美少女を傾国の美女へと変えるきっかけだった。彼女に気づかせてしまった。自分の美貌に価値があると。幼なじみと二人で花冠を作るよりも、この美しさを利用して純金の冠を手にしてやろうと。
それからは早かった。サクラは2人だけのユートピアであった山から降り、俗世の人塵の蔓延る街に降りていってしまった。思うにこの時がサクラと幼なじみとの決定的な別れの時であった。
サクラは貧民から平民となるために、春日と恋をし、平民から貴族となるために、オイディプスと逢瀬を重ねたのである。それから自らの美しさでもって春をひさぎ、地位を高めてきた。
外見ではなく、自分の能力1つでのし上がってきた――と少なくとも本人は自負している――エレクトラにはその点も気に食わないのであった。真にサクラとエレクトラは対照的だった。そして、その生き様は決してお互いを解さぬ平行線であった。アイが生まれるまでは。アイという子の2人の母親として、アイという存在によって、アイという点において、2つの線は交わったのである。
◇◆◇
――どんなやつだ?どんな男だ。まだちいさい、かわいいウチの娘を誑かしたやつは。どうせ碌なやつじゃねぇ。春日家の一人娘に手を出そうなんてやつは。いい度胸だ。どんな高位の貴族でも許しちゃおけねぇ。一発殴って分からせてやらねぇと。……来やがった、ふてぇ野郎だ……のこのこと――。
拳に力を込めたしゅんじつの前に、アイが怯えた眼をしながらおずおずと姿を現す。
「……サクラ……?」
――なんでここに?いや、ありえない、だってサクラは……。いや、それに……あの頃のサクラだ。この髪、顔、なんで――。
形をなしていない疑問が次々とこぼれ出る。
「……サクラ……、どうしてだ……?、いやありえない、サクラ……、どうしてここに、その姿は――?」
普段狼狽する姿を決して家族に見せようとしない夫がしどろもどろになっている姿を見て、ひまりは驚いてしまう。
「あ、アナタ?どうしたの……?それに、さくらって……?」
「……あ、あの……?」
困惑するアイの表情をとらえたしゅんじつがハッとする。
――いや、違う確かにあの頃のサクラの生き写しだと思ったが、違う、サクラはこんな表情はしない、こんな態度は取らない。それにこの娘とは髪の色も、眼の色だって違う。サクラはルビーの眼をしているが、この子はサファイアだ。
神に跪くように屈み込み、問う。
「キミは……?」
「!……申し遅れました!大変申し訳ありません!お初にお目にかかります……わたくしの名は、アイ、と申します。アイ・ミルヒシュトラーセでございます。春日春日様。お、お会いできたこと、恐悦至極の念に堪えません。」
「あい……アイ?アイ・ミルヒシュトラーセ?……それじゃあ、君が。」
「は、はい。はるひちゃんの友……いえ、はるひさんの聖別の儀の相手役を務めさせて頂きます。アイでございます。」
「そうか、そういうことか。道理でアイツ……俺に君の姿を見せてくれない……君と会わせてくれないわけだ。」
しゅんじつは何かずっと不可解だったことが氷解したように。ひとり納得する。
「……あいつ?と申しますと?」
「いや、いいんだ。はじめまして、もう知ってると思うが、俺は春日家の家長、春日春日の父親、春日春日だ。……アイ様?」
「様などと!どうかおやめください!……わたくしなどは、ただのアイと、そうお呼びください。」
アイが深く頭を下げ、しゅんじつの眼が大きく見開かれる。
「なるほど、アイツとは正反対だ。似ても似つかない。そんなに怯えないでくれ、俺は君の敵じゃあない。それに、君はミルヒシュトラーセだろう?上の立場の者が軽々しく頭を下げるものじゃないよ。春日家なんぞ、君からしたら末端も末端だろう――」
今はまだ、と心のなかで付け足す。
「いえ、わたくしなんぞは比することも烏滸がましい者です。どうかご容赦下さい。」
――なるほど、これがほんとうにアイツの息子か?いや、アイツらが母親だからこう育ったのか?
「では、どうだろう。こうしようじゃないか。君はウチのはるひの友達で、俺は友達の父親だ。だからまぁ、既に親しいとも言えるし、お互い気楽に行こうじゃないか。それに、親しい者たちの間では慇懃は、むしろ無礼というものだ。君も礼を欠きたくはないだろう。」
しゅんじつはこの一瞬でアイが礼を欠くことを最も恐れているのだと、その慧眼でもって見抜き、即座にそれを逆手に取った提案をする。こう言われてはアイも失礼を働かない為には、慇懃な態度をやめざるを得ない。
「分かりました。では、しゅんじつさん……と。」
「おお、よろしくアイ君、まぁ、とりあえず座ってくれよ。獲って食ったりしないからよ。」
アイに座布団を指し示す。
「失礼致します。」
――しっかし、この美しさ、完璧にサクラの生き写しだな。サクラより美しいものなんてこの先お目にかかれるもんじゃねぇと思っていたが、生きてると、あるもんだなぁ。
「…………。」
「……?」
無言で見つめられアイはもじもじと身を揺らす。
「あなた!アイちゃんが怖がってるでしょ!やめなさい!」
ペシッと肩をはたくひまり。
「い、いや……威嚇してるわけじゃないぞ?ただどんなふてぇ野郎がくるかと思ってたら、こんなに綺麗な子が来て、驚いているだけだ。」
「そんなこと言って、さっきは拳握って、『とっちめてやるぅ!』って言ってたじゃない。」
「!ひうっ……!……。」
ただでさえちいさい体躯をさらに縮こまらせるアイ。
「あ、アイくん!違うんだ。怯えないでくれ!ひまりも!この子を怖がらせるようなことを言うな!俺だってこんなにかわいい子を殴ったりはしねぇよ!」
「……ほんとう、ですか……?」
アイが震える瞳で尋ねる。
「あ、ああ!本当だ!安心してくれ!」
はるひとひまりには、アイに怖がられないよう必死な父が、初めて見る小動物に狼狽える大型犬のようで、声を上げて笑ってしまう。
「「あはははっ!」」
「お前ら!笑うんじゃねぇ!」
◇◆◇
ひと通り騒いだあと、しゅんじつが家長らしくまとめる。
「ふぅ……ときにアイくんよ、よく来てくれたな。俺も君には聖別の儀の前に一度は会っておきたかったんだ。だが、エレクトラは会わせてはくれないし、君はいつも来客があると別宅に隠れているからな。今回はちょうどよかった。」
アイは驚いていた。自分なんぞに会いたがる人がいるという奇妙もそうだが、なによりも母を呼び捨てにするしゅんじつに対してだ。貴族のなかで母を呼び捨てにするなんて、それこそ、父ぐらいしかいないのに。
「お母様と、親しいのですね?」
「ん?ああ、そうだな。親しいというより、腐れ縁といったほうが正しいが。春日春日と、エレクトラ、オイディプス、あと……サクラ、それとファントムもか、この5人はまぁ昔からの仲でな。まぁ、君とはるひ、陽炎陽炎のような仲だと思ってくれたらいい。……まぁ、君たちほど仲が良かったわけではないが。」
――まぁ、この子たち3人も本質的な意味でお互いの仲間か、といわれると怪しいがな。そもそも、政治に絡み、立場ある家に生まれた時点で、真実の友など望むべくもないことだ……はるひには悪いことをしたが……。
「へぇ~、知らなかったわ。アナタそんな話してくれたことないじゃない。」
「誰にでも知られたくない過去はあるだろう……それにアイ君にはその権利があると思ったから、教えただけだ。」
「お母さまとお父さま……さくら?さまと……ファントム先生も?」
「おや、サクラのことは知らないのに、ファントムのことは知っているのか……ふむ。」
――何者かの作為を感じるな。すこし、対話をすることで、こころを視てみるか。
「アイ君、少し俺とサシで腹を割って話をしないか?」
「おはなし……ですか?」
「ああ、人と心を通わせるには、心で闘うのが手っ取り早いという野蛮なやつもいるが、俺はそんなやつらとは違う。俺は膝を突き合わせて、胸襟を開いて、同じ飯を食って話す。これこそが心を通わせるものだと思っている。」
「それは……素敵な考えですね。」
たおやかな白い指を包む袖口を口元に添えてはにかむアイ。春日は、その薄氷の生色にまだ宵のない時代に恋恋た、解語の徒桜の匂いを垣間見るのだった。
「……君は――。」
◇◆◇
2人は暫くたいせつなことや、どうでもいいことを徒然に話した。
――この子の生き方は、他人の策謀に裏打ちされている。哀れだな……この子は自分で何事をも選んではいない。自分で選んだつもりが、悉く他人に選ばされているだけだ。つまり、自分の人生を生きていないのだ。人生とは、自分で何事かを選び抜くことなのだから。
まぁ、俺もこの子供を搾取する大人の1人なのだが。サクラの面影の射すこの子を利用するのは忍びないが、何物をも持たない人間が夢を持つにはそうするしかないのだ。悪びれはしない、許してくれとも思わない。金持ちから奪うことが、悪いことなのか?持たざる者が、持つ者から奪うことが。いいや、ありえない。罪にはなりえない。
◇◆◇
「君は、罪悪とは何だと思う?そもそも罪悪とはこの世に存在すると思うか?」
「罪悪……ですか。わたくしの短い生で得た言葉で語るには、少々荷が重いので、友の言葉をわたくしなりに解釈したものでお答えしてもよろしいでしょうか?」
「そこに君の思想が介在しているのなら。」
「ありがとうございます。」
「しかし友というと、陽炎陽炎か?それとも、まさかはるひが?」
「いいえ、確かにかげろうとはるひさんが、わたくしをお二人の友達にしてくれるまで、わたくしには友の1人もおりませんでした。生まれてこのかた孤独な一日一日に引きずられるように生きていました。勿論兄姉はやさしくしてくれましたが、それは友とは違います。
彼らはわたしくしがわたくしだから愛してくれるのではありません。わたくしが彼らの弟だからです。きっと他人として生まれていたら、彼らの視界にも入らずに一生を終えましょう。
そのように川に流る2枚の葉がたまたま重なったような縁なのです。その人がその人だから愛している、というのがほんとうの愛だとわたくしは思っています。だから、むしろ師や友との間にこそ見出すものなのかもしれません。」
「しかし、君も兄姉たちを愛しているのだろう?」
「もちろんです!そのことが卑しいわたくしの唯一の誇りであります。わたくしは兄姉のためなら何物も惜しくはないのです。ですが、わたくしは彼らに何事をも与えられてはいません。ですから、友や師に抱く愛とは違うのです。……わたくしの場合は友にも何も与えられてはおりませんが。
話がそれましたね。孤独だったわたくしは、書物の中に友を見出したのです。ええ、地獄の書物の中にです。文学書であっても、学術書であってもそこには必ずそれを記した者の思想が宿ります。そして書物を読むことは対話です。双方向的な対話では決してありませんが。そうしてわたくしは文学や哲学書、宗教書を読み漁り、一方的にその著者を友としてきたのです。わたくしの思想を形作ったのは主にその友たちとの“対話”です。」
「なるほど、それが君の言う友か……了解した。して、そうやって定義づけられた君の答えとは――?」
◇◆◇
「罪悪のお話でしたね。わたくしは罪悪は確かにこの世に存すると思います。そしてそれには罰が伴うものだと思います。たとい必ずしも罰が与えられなかったとしても。そして何を罪悪と思うか、ですよね。そうですね……まず、恋は罪悪だと思います――」
「ふむ、例えば持たざる者が持つ者から奪うことは?……君はどう考える?」
「それは例えば、“苦学生が高利貸しの老婆を斧で殺す”ような場合ですね。友の1人フョードルが論じていました。わたくしはそれも罰を与えられるべき罪だと考えます。
しかし、わたくしが考える罰とは救いです。罪を犯したのに、罰を与えてもらえないというのは、恐ろしいことです。許されないからです。許しを得たいというのは、人間の根源的な欲求です。なぜなら罰を与えられるまでは、自分が犯した罪が発覚しないか、責め咎められることがないか、なによりその罪を犯したおかげで得た幸福を、その罪自体が打ち砕きはしないか、ということを朝起きるたびに、愛しい人と過ごしているときにふと、または夜の安らかな安息のなかで、一生怯えて暮らすことになるのです。
だからこそ、罪を犯してもいないのに罰を求める人が現れたりするのだと思います。罰を得ることで自分の中の罪悪を消したいと願うのです。もっともそれで消えるのは罪悪ではなく、罪悪感だけかもしれませんが。」
「つまり、罪を犯したのに罰を与えられないのは不幸だと。なぜなら罰を受け入れて初めて人間は許され、安寧を得られるからと……ふむ。」
――俺もいつか罰を受けるのか?いや、俺は罪を犯してはいない、嫁と娘をより幸せなところに連れていきたいだけだ。それに、そもそも俺は罰を求めているのか?だがこのサファイアの瞳に見つめられると、オイディプスが理想を語る眼を思い出す。
◇◆◇
「君はどうしたい?何百もの深い見識のある友たちとの対話で、君の思想はどう変わったのだ?」
「わたくしがしたい事と、わたくしがするべき事は違います。書物の中の友たちや先生は、わたくしが“変えられるものと変えられぬものを見分ける洞察”を授けてくれました。“変えるべきものを変える胆力”も。そしてなにより、“変えられぬものを受け入れる勇気”も。友はわたくしがするべき事を教えてくれました。
しかし、わたくしがこれからの人生で行うのは、わたくしがしたいことでございます。友の意見とは関係がありません。……かなしいですが。友の、先生の忠告に従わない路を往くことを選んだのです。わたくしが選び取るのはわたくしがしたいことでございます。」
「……して、それは?」
「おかあさまの望みを叶えることです。お父様のお役に立つことです。そして、その見返りとして、わたくしを愛して頂くことです。それがわたくし、アイ・ミルヒシュトラーセの唯一手ずから選んだことです。生きる道です。」
アイの全てを貫くような、だか何物も見えてはいないサファイアの眼が、何よりも雄弁にしゅんじつに伝えた。
「……それではさっき君の言った、ほんとうの愛とは自家撞着しているように聞こえるが。」
――この子は、自分で唯一選んだことだと言っているが、それさえ実を言うと他人に選ばされているということに、気がついていない。
「そのとおりです。わたくしの思想、信念、信仰、哲学、世界観、その全てと対立する生き方です。わたくしは自身の信仰に背いているのです。わたくしは独りの背教者なのです。」
「……何故だ?自ら背信者となってまで、何故に父母に棹さして生きることを選ぶ?それは自分が1番つらい道だと知っているだろう?自分に嘘をついて生きるなど。」
――この子がエレクトラの思惑通りに動いてくれたら、我が家にとっても利益となる。だのに何故俺はこんな……それをやめさせるような言葉を吐いている。感心だな、と褒めて臆病な自尊心を慰めてやればいいではないか。なぜおれは――
今まで流れる水が如く理路整然と論理を並び立てていたアイが、初めてその言葉を詰まらせる。まるで言葉を愛しているように。わが子のように、言葉を――。
「……はい……そのとおりです。……ですが、わたくしにはこの道しかないのです……。……わたくしには、わたくしには……。わたくしの唯一の師、本の中の師、ルシウスは、彼の母を愛していました。たといコルシカ島に流されても、自分を慰めることなく、自己憐憫にふけることもなく、その地で研究を続け、母に手紙を書いたのです。わたくしは師から、自分がどんな目に遭っても、母を思う心、そして家族を愛することを学びました。」
「しかし、聖別の儀だって、君をさらに軍事的に利用できるしようと、エレクトラが考えたものだぞ?君を愛してのことじゃない。そんな母を何故愛する?」
――やめろ、儀式の相手をはるひにするのだって骨を折ったのに。俺もエレクトラの片棒を担いだのに。俺もこの子を利用しているのに、何故こんな事を聞く?俺は何がしたいんだ?
「おかあさまが……そして、おとうさまも、わたくしを愛して下さっていないのは重々承知です。そんなことは物心つく前に、身体に教え込まれました。
でも、それがなんだと言うのです?愛情とは愛してくれるという確信が持てる相手だけを愛することでしょうか?この人は私に与えてくれる、だから返してやってもいいだろうなんてものは愛情ではあり得ません。
愛情とは、ほんとうの愛とは――相手に憎まれていても、嫌われていても、愛してくれているかどうか分からなくても、それでも愛することです。The Art of Loving〈愛するということ〉はそういうことです。条件なんぞ愛の前には存し得ないのです。わたくしは、ただわたくしがおかあさまの子だから、おかあさまを愛するのです。」
◇◆◇
「それは、あまりにも、つらい……。」
「……!哀しんで下さるのですね。こんなわたくしのために。貴方はお優しいかたです。ひまりさんやはるひさんがやさしい人なのも、得心がいきます。」
――ちがう、やめてくれ、俺はこの子の母親と一緒になってこの子供利用しているだけだ。やさしい人なんかじゃない。
「ですから、わたくしはたとえ条件付きの愛情でも、ほんとうの愛とは呼べないものでも、おとうさまとおかあさまからそれが、一滴でもいいからそれが、ほしいと願わずにはいられないのです。この渇望は全てに優越します。其処には合理は必要ありません。
わたくしはただ、おとうさまとおかあさまの子供だから、お二人を愛するのです。このこころの前には、道理なんぞ露と消えてしまいます。子はその親の子供だから、親を愛するのです。それが全てなんです。それがわたくしの全てで。わたくしの世界の全てなのです。」
――親を愛していない子供なんぞいくらでもいる、俺もそんなことは知っている。だが、この子にはそんなことは、ひとえに風の前の塵と同じなのだろう。
この子はこんな俺を、この俺をつらまえて、やさしいひとだと、そう、言った。この子の最愛の母と共に、この子の地獄への道を、この両の手で舗装し、背中を押し、あちらへ行けと指を差す、この俺を。家族を守るためなら何だってしてきた。家族にさえ分かってもらえれば、それでいいと思っていた。
だか――この子は俺に罰を与えてはくれないだろう、こころやさしいこの子は。こころかなしいこの子は。だが――この子は、――この子は俺を赦してくれるだろうか?俺の罪を――。
◇◆◇
「アイ、おれは春日、春日春日だ。いつか、この俺のことも、祈ってはくれないか。何にでもいい、君が信じるものなら、君が奉じるものなであるのならば、『あなたの僕、春日』と。……それだけでいいのだから。」
アイには彼が赦しを求めているのだと分かった。それは、アイがずっと求めているものでもあったからだ。それが自分に与えられるのなら、与えないわけはない、とアイは勢い込んだ。
「わたくし、この先ずっとあなたのことを、お祈りします。」
少年は熱っぽい調子でそういうと、ふいに笑いだし、彼に近づき、低く垂れた彼の頭を、しっかり胸に抱きしめた。
――その姿はまるで、孤児に抱擁を与える、聖母のようであった――
◇◆◇
アイの耳は孤児の声を聞いた。
「ああ……サクラ――」
――さくら――?
30
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

旧校舎の地下室
守 秀斗
恋愛
高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。

【もうダメだ!】貧乏大学生、絶望から一気に成り上がる〜もし、無属性でFランクの俺が異文明の魔道兵器を担いでダンジョンに潜ったら〜
KEINO
ファンタジー
貧乏大学生の探索者はダンジョンに潜り、全てを覆す。
~あらすじ~
世界に突如出現した異次元空間「ダンジョン」。
そこから産出される魔石は人類に無限のエネルギーをもたらし、アーティファクトは魔法の力を授けた。
しかし、その恩恵は平等ではなかった。
富と力はダンジョン利権を牛耳る企業と、「属性適性」という特別な才能を持つ「選ばれし者」たちに独占され、世界は新たな格差社会へと変貌していた。
そんな歪んだ現代日本で、及川翔は「無属性」という最底辺の烙印を押された青年だった。
彼には魔法の才能も、富も、未来への希望もない。
あるのは、両親を失った二年前のダンジョン氾濫で、原因不明の昏睡状態に陥った最愛の妹、美咲を救うという、ただ一つの願いだけだった。
妹を治すため、彼は最先端の「魔力生体学」を学ぶが、学費と治療費という冷酷な現実が彼の行く手を阻む。
希望と絶望の狭間で、翔に残された道はただ一つ――危険なダンジョンに潜り、泥臭く魔石を稼ぐこと。
英雄とも呼べるようなSランク探索者が脚光を浴びる華やかな世界とは裏腹に、翔は今日も一人、薄暗いダンジョンの奥へと足を踏み入れる。
これは、神に選ばれなかった「持たざる者」が、絶望的な現実にもがきながら、たった一つの希望を掴むために抗い、やがて世界の真実と向き合う、戦いの物語。
彼の「無属性」の力が、世界を揺るがす光となることを、彼はまだ知らない。
テンプレのダンジョン物を書いてみたくなり、手を出しました。
SF味が増してくるのは結構先の予定です。
スローペースですが、しっかりと世界観を楽しんでもらえる作品になってると思います。
良かったら読んでください!

戦場帰りの俺が隠居しようとしたら、最強の美少女たちに囲まれて逃げ場がなくなった件
さん
ファンタジー
戦場で命を削り、帝国最強部隊を率いた男――ラル。
数々の激戦を生き抜き、任務を終えた彼は、
今は辺境の地に建てられた静かな屋敷で、
わずかな安寧を求めて暮らしている……はずだった。
彼のそばには、かつて命を懸けて彼を支えた、最強の少女たち。
それぞれの立場で戦い、支え、尽くしてきた――ただ、すべてはラルのために。
今では彼の屋敷に集い、仕え、そして溺愛している。
「ラルさまさえいれば、わたくしは他に何もいりませんわ!」
「ラル様…私だけを見ていてください。誰よりも、ずっとずっと……」
「ねぇラル君、その人の名前……まだ覚えてるの?」
「ラル、そんなに気にしなくていいよ!ミアがいるから大丈夫だよねっ!」
命がけの戦場より、ヒロインたちの“甘くて圧が強い愛情”のほうが数倍キケン!?
順番待ちの寝床争奪戦、過去の恋の追及、圧バトル修羅場――
ラルの平穏な日常は、最強で一途な彼女たちに包囲されて崩壊寸前。
これは――
【過去の傷を背負い静かに生きようとする男】と
【彼を神のように慕う最強少女たち】が織りなす、
“甘くて逃げ場のない生活”の物語。
――戦場よりも生き延びるのが難しいのは、愛されすぎる日常だった。
※表紙のキャラはエリスのイメージ画です。

最強無敗の少年は影を従え全てを制す
ユースケ
ファンタジー
不慮の事故により死んでしまった大学生のカズトは、異世界に転生した。
産まれ落ちた家は田舎に位置する辺境伯。
カズトもといリュートはその家系の長男として、日々貴族としての教養と常識を身に付けていく。
しかし彼の力は生まれながらにして最強。
そんな彼が巻き起こす騒動は、常識を越えたものばかりで……。

男女比がおかしい世界の貴族に転生してしまった件
美鈴
ファンタジー
転生したのは男性が少ない世界!?貴族に生まれたのはいいけど、どういう風に生きていこう…?
最新章の第五章も夕方18時に更新予定です!
☆の話は苦手な人は飛ばしても問題無い様に物語を紡いでおります。
※ホットランキング1位、ファンタジーランキング3位ありがとうございます!
※カクヨム様にも投稿しております。内容が大幅に異なり改稿しております。
※各種ランキング1位を頂いた事がある作品です!

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。
MP
ファンタジー
高校2年の夏。
高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。
地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。
しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる