3 / 20
第3話「王太子の金庫」
しおりを挟む夜の王都は、砂糖衣の下に刃を隠したお菓子みたいだ。光は甘く、音は軽く、けれど踏み割れば中から硬いものが覗く。
その夜、王太子主催の慈善舞踏会。広間の天井には金の蔓が星座のように絡み、床は磨かれた黒の鏡。貴族たちの笑い声は弦楽の上を滑り、杯の縁で小さな月が揺れている。
私は黒に近い群青のドレスを選んだ。光を飲み込む布。悪役令嬢は、夜になるほど輪郭がはっきりする。髪は緩く上げ、耳もとに小さなカメリア。ベラが最後のピンを留めながら、鏡越しに私の目の奥を覗いた。
「レティシア様、少し眠ってません?」
「眠ってないわ。狩りの前は、目が冴えて仕方ないの」
「狩り、ですか」
「ええ。言葉と数字の、ね」
ベラは笑い、私の肩を軽く押す。「行ってらっしゃいませ」。その掌の熱で、今夜の筋書きに印がつく。
扉の向こう、広間の端に楽団の席がある。指揮者の合図でワルツが流れる。私は人波の端を滑り、壁際の柱陰に立つ。獲物を見つける前に、匂いを嗅ぐ。寄付箱には銀貨が煌めき、受付の帳場には新しい帳簿。太い革紐で綴じられたその本は、まだ手垢が薄い。
――穴がある。
帳場の後ろに控える文官の袖口、金糸がほどけている。慣れていない。寄付を扱う手が、新しい。王太子府の代官は交代したばかり――ベラが昼のうちに拾ってきた噂が、ここで実体を持つ。
「レティシア・ヴァルン嬢。おひとり?」
背後から、絹を裂くような柔らかい声。振り返れば、燕尾服の青年。髪は煤のように黒く、瞳は琥珀。手には小さな握り皮の楽譜ケース。肩からかけた細い鞄は楽器の形ではない。
「ええ。あなたは?」
「作曲家の端くれ。酒場では“パルマ”と呼ばれている。——今夜、あなたが探しているのは、金の流れだ」
喉の奥で、笑いがひとつ跳ねた。あからさま。けれど、舞踏会の雑音の中では、こういう直球が一番早い。
「作曲家が、金の話?」
「音楽家は常に金の話をしているよ、ヴァルン嬢。貴族は音楽を愛すると言うが、楽譜には愛ではなく貨幣が必要だ」
「詩人ね」
「商人だよ」
彼は軽く頭を下げ、鞄から折り畳まれた紙束を覗かせた。封蝋はないが、端に王太子府の印影が薄く写る。薄いのは、複写。炭粉で写した痕跡だ。
「代官のミスか、意図か。どちらでも、あなたの“狩り”の餌になる」
「対価は?」
「簡単だ。王太子の演説の場で、あなたの口から“音楽家の地位向上”のための一言を。名指しは不要。風向きだけ変えてくれればいい」
私は一秒だけ迷って、うなずいた。正しい取引だ。善き提案の衣と、私の狙いは喧嘩しない。
「名は?」
「パルマで十分」
「いいわ、パルマ。口は固い?」
「鍵穴みたいにね。正しい鍵しか通らない」
「本当に詩人じゃないの?」
「詩人はもっと貧しい」
彼が紙束を渡す。私は手袋越しに受け取り、人混みの陰で最初のページをめくった。寄付金の出入り。王太子府への集金→代官室→“沿岸孤児救済会”へ送金の記録。だが救済会の銀行印が三度消える。消印が重なっているのではない。押すべき箇所に押されていない。送金が“書類の上で”だけ往復している。
もう一枚。搬送証書。封緘印の蝋が二箇所で二度押し。異なる刻印角度。偽造の癖。私は紙端をなぞり、薄く息を吐く。
「いい仕事」
「あなたも」
パルマの視線が、舞台側へすべる。王太子が登壇する気配。広間の照明が一段明るくなる。ざわめきが、意図的に落とされる。私は紙束を折りたたみ、胸元の内ポケットへ滑り込ませた。
「あとで、曲を捧げるよ。音は記憶を運ぶ。あなたに有利な旋律で」
「私の人生、BPMは早めでお願い」
「承知」
彼は人混みに溶けた。私は深呼吸をひとつ。胸の内側で言葉を並べ替える。演説を乗っ取るには、露骨すぎない楔が必要だ。善意の顔をした鋭利な一文。
鏡の前――控室の小さな姿見の前で、私は台詞稽古を始める。口角の角度、顎の引き、眉の開閉、息の深さ。校閲者の癖は、最終稿まで手を入れる手のしつこさだ。
「殿下の高邁な志を、私も支えたいと思いますの。ひとつだけ、提案がございます。寄付の可視化とともに、音楽家や職人といった“声なき才”の待遇を、国として底上げできませんか。志は、音と技に支えられて初めて届きますわ」
もう一案。
「殿下のご演説、胸を打たれました。寄付金の流れを明らかにする委員会に、どうか音楽家や書記官も加えて。数字に生命を与えるのは、彼らの手です」
言い回しを変え、主語を小さくしたり大きくしたりする。善き提案は、善いふりをして刃を隠す。刃は、数字の透明化。委員会。監査。職人の名誉。王太子の“美しい物語”の中に、現実の検算をねじ込む。
深呼吸。唇に薄く色を足し、扉を開く。広間に戻ると、エドワードが壇上。光の中心。蜂蜜色の髪。拍手が海のように寄せては返す。
「皆、今夜もよく集まってくれた。我々は恵まれている。だからこそ、恵まれない者に手を差し伸べる――」
完璧な言葉の連なり。内容は薄いが、言い方がうまい。人は言い方に救われるものだ。私は彼の声の波に合わせ、ひと呼吸早く前へ出る。タイミングは、拍手が高まる直前、息継ぎの隙。
「殿下。お言葉に、心から賛同いたしますわ」
声を広げる。視線が集まる。エドワードの笑顔が、そのまま私に向く。
「ヴァルン嬢。嬉しいよ。君の賛同は、ひときわ心強い」
「光栄です。ひとつだけ――小さな、でも確かな提案を」
私は両手を胸の前で合わせ、わずかに目線を下げる。攻撃ではなく献言。形だけ“下から”。
「寄付の流れを、誰の目にも見える形にしていただけませんか。委員会に音楽家や書記官、職人代表も加えて。志は、音と技によって遠くまで届きます。今夜のこの美しい音楽を、奏でる人たちにも、相応の席を」
一瞬、広間が呼吸を忘れた。音楽家の席で、指揮者の目が見開かれる。壁際の若い作曲家が、口を押さえて笑った。——パルマだ。王太子の頬に、薄い影が走る。笑顔は崩さない。崩せない立場の顔。
「もちろんだとも。私も常々、透明性の——」
彼は滑らかに受け止める。が、声の奥のテンポが半拍ずれる。言い淀みのない男が半拍ずらすとき、それは“想定外”。
「音楽家の地位向上も、私の願いだ。委員会の設置、前向きに……検討しよう」
検討。魔法の言葉。私は微笑んだ。検討と言ったとき、彼はすでに記録を残した。後で突くための杭。周囲の拍手は、先ほどよりも少し固い。人々は言葉に酔うが、数字の気配には覚める。
演説後、私は礼をして下がる。最前列で、エミリアがぱちぱちと嬉しそうに拍手している。聖騎士アランは腕を組み、目だけで王太子の顔色を読む。宮廷魔導士ルシアンは、退屈そうに爪を眺めて笑っていた。
その間に、私は壁際へ回り込む。今の一文で、何人の心拍が上がったか。王太子府の代官、帳場の文官、楽団の若者、そして——
「ノア」
影から影へ移る灰色が、私の横に立った。彼はいつものように、見ないふりをしている。けれど声は、私だけに向いている。
「文官の一人と話しました。封緘印の蝋、代官室で使っている印の“癖”が変わっています」
「印の癖?」
「角度。新しい代官は、封をする際にいつも時計回りに一二度傾ける。旧代官は無意識に反時計回り四度。両方の封が同じ日付の書類に共存している」
「つまり、同じ日に“別人の封”が押されている」
「はい。あるいは偽造」
素晴らしい。私は横顔の彼をまじまじと見た。灰の瞳は、どこか遠くを見る訓練をされた目。感情の波を表に出さないように、海面を静かに保つ習慣のある目。
「あなた、ただの侍従じゃないわね」
ノアは少しだけ口角を動かした。笑いとも、否ともつかないタッチ。
「私の職務は、主の安全と体面を守ることです」
「それは、王太子の?」
「今は、ヴァルン家の依頼に従っています」
「返事になってない」
「質問が鋭い」
「褒め言葉と受け取っておく」
言葉の刃を合わせる感触は、緊張ではなく安心に近い。隣に立つ者が、鈍い剣ではなくよく研がれた刃であるとき、人は背中を預けられる。
壇上では、王太子が笑顔のまま退場し、側近に低い声で何かを囁いた。代官の顔から血の気が引くのが、ここからでも見えた。圧がかかった。“誰かのせい”にする準備。美しい物語の汚れを、目に見えない場所へ押し込める手。
私は小さく息を吐く。舞踏会の中心では、円が描かれ、人々がすべるように踊る。音楽は軽やか。だからこそ、下に沈む音がよく聞こえる。
「パルマ」
柱陰から彼が現れた。指には白い粉がついている。チョークだ。楽譜に印をつけていたのだろう。
「一言、見事だったよ。僕の仲間が泣いてる」
「泣かせるのは趣味じゃないけれど」
「泣くのも仕事さ。音楽家は涙で塩分を補給する」
「やっぱり詩人じゃない」
「ほめ言葉として受け取る」
パルマは胸に手を当て、わずかに頭を下げた。「君は舞台の使い方を知っている。あとは裏口の鍵。——渡した紙の続きがある。場所を移そう」
私はノアを見た。彼は頷き、半歩後ろにつく。三人で広間から出て、音の薄い廊下へ。冷えた石壁が、熱を吸う。パルマは鞄の底からさらに薄い紙片を取り出した。指に唾をつけないのがいい。丁寧に扱われた紙は、人間の品のよさを映す。
「代官室の受領書。ここ、受け取り印の“受”の文字。一本、横画が長い。偽造の職人は、縦画より横画でミスをする。急ぐと、横に力が流れるから」
私は紙を目に近づける。確かに、一本の横画が他より長い。前世で見慣れた“癖”。人の手は、本当によく喋る。私は頷き、紙片を返す。
「十分。ありがとう、パルマ」
「僕の条件、忘れないで」
「忘れない。今夜の“検討”は、明日の“設置”に変わる。そう運ぶ」
「運べるのかい?」
「運ぶのよ。私が」
パルマは笑い、肩をすくめ、再び群衆へ消えた。彼の背中に、ささやかな尊敬を送る。情報屋が自分の分の正義を持つとき、世界は少しだけ良くなる。
ノアが口を開く。「ヴァルン嬢」
「なに?」
「あなたの言葉は、慈善の仮面を剥がす。味方も増えるが、敵も増える」
「敵は、増やさないと狩り甲斐がないわ」
「それは、危険だ」
「危険は、前に置いたほうが足を取られない」
ノアは目を伏せ、短く息を吐いた。吐息の温度が、廊下の石に溶ける。
「……なら、私の刃はあなたの前に。あなたが見落とした隙を斬る」
「心強いわね」
「職務です」
彼はそれしか言わない。けれど、その“しか”の中に、含みがいくつも畳まれている。灰色の瞳は、他人の秘密を守る色。自分の秘密も。
舞踏会は終盤に向けて熱を上げる。王太子は愛想よく笑い続け、代官は汗を拭き続ける。聖騎士は群衆の中の脅威を探し、魔導士は退屈をいじるように指先で虚空を弾く。エミリアは慈善の顔で子どもたちの話をして、周囲を柔らかく包む。舞台は、よくできた嘘の上で滑らかに進む。
私はその嘘に、針を一本ずつ刺していく。見えない針。明日の朝、必ず疼く針。
帰りの馬車で、私は紙束を膝に広げる。ベラが向かいに座り、毛布を私の膝にかけた。
「お疲れさまです」
「楽しかったわ」
「やっぱり寝てない」
「寝るのは、山場が過ぎてから」
「じゃあ、ずっと寝られませんね」
ベラの小さな皮肉に笑う。彼女は真面目だが、時々こういう塩をひとつまみ投げてくる。私は紙面を指で追い、封緘印の角度を確かめ、偽の横画を数え、日付の並びに歪みを探す。数字は正直だ。人間より。
「ベラ。明朝、王都の新聞に“委員会設置の検討”を載せさせて。王太子の演説の引用付きで」
「もう記事に?」
「検討、という言葉は、活字にした瞬間に半分現実になる」
「了解しました」
「それと、王太子府の文官で“左利き”を探して。封蝋の流れ癖、左の可能性がある」
「ノア様に?」
「ええ。彼、仕事が早い」
ベラの目がきらりと笑う。「レティシア様、ノア様のこと、気に入ってます?」
「刃物として優秀よ」
「人としては?」
「――まだ、研いでみないと」
馬車の窓に、夜の王都が逆さに映る。石畳に灯が揺れ、川面に星が落ちる。私はその光景を見ながら、胸の奥の言葉を確かめる。
――我慢しない。
我慢しないという旗を、今夜は高く掲げた。善き提案という衣で。音楽家の地位向上という、誰にも責められない理由で。けれど実のところ、私が求めているのは“透明”だ。透明な数字。透明な責任。透明な顔。
ベラが居心地よさそうに毛布にくるまり、小さな欠伸をする。私の肩の力が少し抜ける。人が傍で眠たくなるのは、世界が一瞬だけ平和になる証だ。
王城の尖塔が遠ざかる。今夜、王太子は眠れない。代官はなおさら。音楽家は笑って少し泣いて、酒場で歌うだろう。パルマはたぶん、新しい旋律を書き始める。ノアは影の中で何かの地図を描く。私は――紙束に挟んだ偽の横画の上に、しおりを置く。
扉はまだ閉まっていない。金庫は、まだ鳴っている。硬貨が重なり合う、鈍い音。そこに手を入れるのは、今日じゃない。明日でもない。けれど、近い。
「ベラ」
「はい……ふぁい」
「寝ていいわよ」
「ねてません……」
「可愛い嘘」
「ふぁ……」
彼女の頭がコトリと揺れ、眠りの音が静かに広がる。私は窓の外に目を戻し、夜の街の呼吸を聞いた。甘い匂いの下に、鉄の匂い。舞踏会の残香の下に、油の匂い。生きている匂い。
――悪役は舞台の主役を喰える。まずは、主役が立つ床に穴を開けるところから。
馬車は石畳の上を滑り、私の部屋へ向かう。鏡の中の私は、また少しだけ笑い方を覚えた気がした。いい。今夜の笑いは、刃じゃない。勝ち筋を舐める舌の笑い。
窓の外で、夜更けの鐘がひとつ、落ちた。次の合図は、もうすぐ。
10
あなたにおすすめの小説

笑顔が苦手な元公爵令嬢ですが、路地裏のパン屋さんで人生やり直し中です。~「悪役」なんて、もう言わせない!~
虹湖🌈
ファンタジー
不器用だっていいじゃない。焼きたてのパンがあればきっと明日は笑えるから
「悪役令嬢」と蔑まれ、婚約者にも捨てられた公爵令嬢フィオナ。彼女の唯一の慰めは、前世でパン職人だった頃の淡い記憶。居場所を失くした彼女が選んだのは、華やかな貴族社会とは無縁の、小さなパン屋を開くことだった。
人付き合いは苦手、笑顔もぎこちない。おまけにパン作りは素人も同然。
「私に、できるのだろうか……」
それでも、彼女が心を込めて焼き上げるパンは、なぜか人の心を惹きつける。幼馴染のツッコミ、忠実な執事のサポート、そしてパンの師匠との出会い。少しずつ開いていくフィオナの心と、広がっていく温かい人の輪。
これは、どん底から立ち上がり、自分の「好き」を信じて一歩ずつ前に進む少女の物語。彼女の焼くパンのように、優しくて、ちょっぴり切なくて、心がじんわり温かくなるお話です。読後、きっとあなたも誰かのために何かを作りたくなるはず。

義姉をいびり倒してましたが、前世の記憶が戻ったので全力で推します
一路(いちろ)
ファンタジー
アリシアは父の再婚により義姉ができる。義姉・セリーヌは気品と美貌を兼ね備え、家族や使用人たちに愛される存在。嫉妬心と劣等感から、アリシアは義姉に冷たい態度を取り、陰口や嫌がらせを繰り返す。しかし、アリシアが前世の記憶を思い出し……推し活開始します!

竜の国のカイラ~前世は、精霊王の愛し子だったんですが、異世界に転生して聖女の騎士になりました~
トモモト ヨシユキ
ファンタジー
辺境で暮らす孤児のカイラは、人には見えないものが見えるために悪魔つき(カイラ)と呼ばれている。
同じ日に拾われた孤児の美少女ルイーズといつも比較されていた。
16歳のとき、神見の儀で炎の神の守護を持つと言われたルイーズに比べて、なんの神の守護も持たないカイラは、ますます肩身が狭くなる。
そんなある日、魔物の住む森に使いに出されたカイラは、魔物の群れに教われている人々に遭遇する。
カイラは、命がけで人々を助けるが重傷を負う。
死に瀕してカイラは、自分が前世で異世界の精霊王の姫であったことを思い出す。
エブリスタにも掲載しています。

令和日本では五十代、異世界では十代、この二つの人生を生きていきます。
越路遼介
ファンタジー
篠永俊樹、五十四歳は三十年以上務めた消防士を早期退職し、日本一周の旅に出た。失敗の人生を振り返っていた彼は東尋坊で不思議な老爺と出会い、歳の離れた友人となる。老爺はその後に他界するも、俊樹に手紙を残してあった。老爺は言った。『儂はセイラシアという世界で魔王で、勇者に討たれたあと魔王の記憶を持ったまま日本に転生した』と。信じがたい思いを秘めつつ俊樹は手紙にあった通り、老爺の自宅物置の扉に合言葉と同時に開けると、そこには見たこともない大草原が広がっていた。

悪徳領主の息子に転生しました
アルト
ファンタジー
悪徳領主。その息子として現代っ子であった一人の青年が転生を果たす。
領民からは嫌われ、私腹を肥やす為にと過分過ぎる税を搾り取った結果、家の外に出た瞬間にその息子である『ナガレ』が領民にデカイ石を投げつけられ、意識不明の重体に。
そんな折に転生を果たすという不遇っぷり。
「ちょ、ま、死亡フラグ立ち過ぎだろおおおおお?!」
こんな状態ではいつ死ぬか分かったもんじゃない。
一刻も早い改善を……!と四苦八苦するも、転生前の人格からは末期過ぎる口調だけは受け継いでる始末。
これなんて無理ゲー??

政治家の娘が悪役令嬢転生 ~前パパの教えで異世界政治をぶっ壊させていただきますわ~
巫叶月良成
ファンタジー
政治家の娘として生まれ、父から様々なことを学んだ少女が異世界の悪徳政治をぶった切る!?
////////////////////////////////////////////////////
悪役令嬢に転生させられた琴音は政治家の娘。
しかしテンプレも何もわからないまま放り出された悪役令嬢の世界で、しかもすでに婚約破棄から令嬢が暗殺された後のお話。
琴音は前世の父親の教えをもとに、口先と策謀で相手を騙し、男を篭絡しながら自分を陥れた相手に復讐し、歪んだ王国の政治ゲームを支配しようという一大謀略劇!
※魔法とかゲーム的要素はありません。恋愛要素、バトル要素も薄め……?
※注意:作者が悪役令嬢知識ほぼゼロで書いてます。こんなの悪役令嬢ものじゃねぇという内容かもしれませんが、ご留意ください。
※あくまでこの物語はフィクションです。政治家が全部そういう思考回路とかいうわけではないのでこちらもご留意を。
隔日くらいに更新出来たらいいな、の更新です。のんびりお楽しみください。
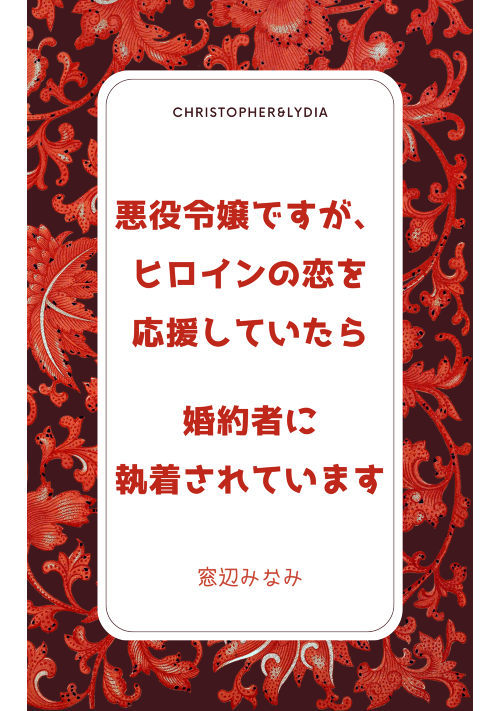
悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています
窓辺ミナミ
ファンタジー
悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。
シナリオ通りなら、死ぬ運命。
だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!
騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!
というわけで、私、悪役やりません!
来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。
あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!
気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。
悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

ぽっちゃり令嬢の異世界カフェ巡り~太っているからと婚約破棄されましたが番のモフモフ獣人がいるので貴方のことはどうでもいいです~
翡翠蓮
ファンタジー
幼い頃から王太子殿下の婚約者であることが決められ、厳しい教育を施されていたアイリス。王太子のアルヴィーンに初めて会ったとき、この世界が自分の読んでいた恋愛小説の中で、自分は主人公をいじめる悪役令嬢だということに気づく。自分が追放されないようにアルヴィーンと愛を育もうとするが、殿下のことを好きになれず、さらに自宅の料理長が作る料理が大量で、残さず食べろと両親に言われているうちにぶくぶくと太ってしまう。その上、両親はアルヴィーン以外の情報をアイリスに入れてほしくないがために、アイリスが学園以外の外を歩くことを禁止していた。そして十八歳の冬、小説と同じ時期に婚約破棄される。婚約破棄の理由は、アルヴィーンの『運命の番』である兎獣人、ミリアと出会ったから、そして……豚のように太っているから。「豚のような女と婚約するつもりはない」そう言われ学園を追い出され家も追い出されたが、アイリスは内心大喜びだった。これで……一人で外に出ることができて、異世界のカフェを巡ることができる!?しかも、泣きながらやっていた王太子妃教育もない!?カフェ巡りを繰り返しているうちに、『運命の番』である狼獣人の騎士団副団長に出会って……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















