16 / 105
ブルースターの色彩
バレンタインの贈り物 -3-
しおりを挟む
「こんにちは、アトリエ花音です。お花のお届けに上がりました」
花音が声をかけると、ほどなく玄関の扉が開き、四〇代くらいの女性が顔を覗かせた。彼女が小峰夫人なのだろう。
「旦那さんからご注文頂いたお花のお届けに上がりました」と花音は抱えていた花束を差し出した。
「お花?」とつぶやいた小峰夫人の目が、花音の抱える花束に行き当たり、「綺麗っ」と頬を綻ばせる。彼女は嬉々として花束を受け取った。
「いい香り」
小峰夫人は満足げな笑みを浮かべた。風に乗ったバラの香りは咲の元まで届き、鼻先をくすぐる。
──本当に素敵な香りだ。
「お気に召して頂き、大変光栄です」
花音が妙に畏まった言い方をし、胸に手を当て、お辞儀をする。それにクスリと小峰夫人が微笑んだ。
「今回使用したその濃いピンク色のバラは『イブピアッチェ』という香りの強い品種なんです」
「イブピアッチェ?」
「はい。イブピアッチェの香りは、『ダスク・モダン』というタイプに分類されています」
「ダスク・モダン?」
小峰夫人は小首を傾げた。
「ええ。日本のバラの香りは化学分析によって、七つのタイプに分類されることがわかっているのです。──その中の一つがダスク・モダンなんです」
へぇ、と花音の花に関する知識の豊富さに、咲は感心する。
「ダスク・モダンは甘くて、情熱的で、濃厚な香りと評されています。バレンタインの贈り物にはピッタリかと」
片目を瞑った花音に、「そうかもね」と小峰夫人は小さく笑い返した。
それから、でも、と困ったように眉尻を下げる。
「こんなに大きな花束を頂いても、家にはこれに見合うような花瓶はないわね」とため息を零した。
それなら、と花音は咲が持っていた花器を受け取った。
「こちらの花瓶をお使い下さい」と小峰夫人に差し出す。
「いいんですか?」
「ええ。お花も、私のほうで生けさせて頂きますよ」
花音の提案に、小峰夫人は「それは助かります」と安堵の表情を浮かべた。
「あまりに大きな花束だったので、少し戸惑ってしまって。お花屋さんが生けて下さるなら、安心です」と微笑む。
それから花束を上り框に置き、花音から花器を受け取った。そうして玄関のドアを大きく開き、「どうぞ」と二人を招き入れた。
「お邪魔します」
花音と二人、玄関を潜ると、かなり広めの空間が現れる。
向かって右側には開放的なシューズクロークが備えられ、靴のほかにガーデニング用品や自転車などが整然と収納されていた。
反対側には咲の肩くらいの高さの靴箱が据えられ、その上に可愛らしいフラワーアレンジメントが置かれていた。
薄いピンク色の陶器の器の上に、黄色い丸みを帯びたバラを主役に、コロコロとした同系色の花がこんもりと乗ったアレンジである。アイビーと小さな五片の花びらの青い花が引き立て役のようにチラリと顔を見せていた。
「素敵な空間ですね」
咲はつい感嘆の声を漏らしてしまった。
「そう言って頂けると嬉しいわ」と微笑んで、玄関のドア閉めた小峰夫人は、「お水を汲んできますね」と花器と共に家の奥へと消えていった。
その背中を見送り、「配達って、花も生けるんですね」と花音を見上げた。
ううん、と花音は首を振る。
「普段は花生けまではやらないよ」
「そうなんですか?」
「うん。さっきも言ったけど、張り切りすぎて花束が大きくなっちゃったの。お花を習ってない人がこのボリュームの花束を貰ったら、処理に困るかなって思って」
たしかに、困るかも。咲はこの前の体験教室での花生けを思い出して、苦笑した。
「ちなみに花生けまで行うのは、『生け込み』っていうんだ」
「生け込み?」
「うん。場所の雰囲気に合わせて、その場で花を生けるの。ホテルやお店からの依頼が多いかな」
「そんなこともやってるんですね」
感心する咲に、まぁね、と花音は頷いた。
「教室だけじゃ、食べていけないから」
切ない事情を聞いてしまう。咲は曖昧な笑みを浮かべた。
「ちなみに花束ってラッピングを外したら、そのまま花器に入れるだけでいいように組んであるんだ」
「え、そうなんですか?」
「うん。だから、わざわざ生ける必要はないの。でも、小峰さん、戸惑っていたみたいだから」と家の奥に目を向ける。
ちょうど小峰夫人が花瓶を抱え、戻ってくるのが見えた。
「お待たせしました」
小峰夫人は水の入った花器を花音の前に置いた。
ありがとうございます、と花音は笑顔で礼を述べる。それからグルリと室内を見渡した。
「そちらの姿見の横に生けさせて頂いてもよろしいですか?」
靴箱の横に大きな姿見があり、その右隣りを花音は手のひらで指し示す。
はい、と小峰夫人は花器を姿見の横へと移動させた。
「では、少しお邪魔させて頂きますね」
「お願いします」
花音は靴を脱ぎ、上り框へと上がった。
花音は姿見の前で手際よく花束のラッピングを外した。次いで、花束を結えていたリボンを手で巻き取り、何かの形を作る。そして、腰にぶら下げたシザーバッグから細い針金を取り出し、それを結えた。
「これ、『フレンチボウ』っていうんです」
二人を振り返り、花音がそれを掲げる。プレゼントによくついている花の形をしたリボンに似ていた。
あれって、手作りできるんだ。
「旦那さんはよくお花を贈られる方なのですか?」
後片付けついでに花音は世間話を始める。
「以前は全然だったんですよ」
小峰夫人は顔の前で手を振り、ケラケラと笑った。
「──でも、アメリカに赴任してからは記念日にお花を贈ってくるようになりました」
「あちらでは記念日にお花を贈る習慣がありますからね」
「そうみたいですね。先月の誕生日には、お花とペンダントを贈ってくれました」
そう言って首元のペンダントを触る。丸い三つのダイヤモンドが縦に連なったデザインのものだ。
「そちらが誕生日プレゼントのペンダントですか?」
「ええ」
「とても素敵なデザインですね」
花音はニコリと笑った。
「でも、いつもは別のペンダントをお着けになられているのでは?」
「え?」
花音の問いに、小峰夫人の目が大きく見開いた。
「……どうして?」
驚きで声がかすかに掠れる。
「いえ、ペンダントに触れる動作が、少しぎこちなかったので」
「ぎこちない?」
ええ、と花音は人差し指を唇に当てた。
「いつも着けているペンダントは、そちらとチェーンの長さが違うのだと思います。だから、ペンダントトップを触ろうとしたとき、一度で触れることができなかった」
「それで……」と小峰夫人は目を大きく見開いた。
「お花屋さんのおっしゃるとおりです。──いつもは結婚前に主人が贈ってくれたペンダントを着けているんですけど……」
小峰夫人の顔が僅かに曇る。
「そのペンダントトップをなくしてしまって」と眉根を寄せた。
花音が声をかけると、ほどなく玄関の扉が開き、四〇代くらいの女性が顔を覗かせた。彼女が小峰夫人なのだろう。
「旦那さんからご注文頂いたお花のお届けに上がりました」と花音は抱えていた花束を差し出した。
「お花?」とつぶやいた小峰夫人の目が、花音の抱える花束に行き当たり、「綺麗っ」と頬を綻ばせる。彼女は嬉々として花束を受け取った。
「いい香り」
小峰夫人は満足げな笑みを浮かべた。風に乗ったバラの香りは咲の元まで届き、鼻先をくすぐる。
──本当に素敵な香りだ。
「お気に召して頂き、大変光栄です」
花音が妙に畏まった言い方をし、胸に手を当て、お辞儀をする。それにクスリと小峰夫人が微笑んだ。
「今回使用したその濃いピンク色のバラは『イブピアッチェ』という香りの強い品種なんです」
「イブピアッチェ?」
「はい。イブピアッチェの香りは、『ダスク・モダン』というタイプに分類されています」
「ダスク・モダン?」
小峰夫人は小首を傾げた。
「ええ。日本のバラの香りは化学分析によって、七つのタイプに分類されることがわかっているのです。──その中の一つがダスク・モダンなんです」
へぇ、と花音の花に関する知識の豊富さに、咲は感心する。
「ダスク・モダンは甘くて、情熱的で、濃厚な香りと評されています。バレンタインの贈り物にはピッタリかと」
片目を瞑った花音に、「そうかもね」と小峰夫人は小さく笑い返した。
それから、でも、と困ったように眉尻を下げる。
「こんなに大きな花束を頂いても、家にはこれに見合うような花瓶はないわね」とため息を零した。
それなら、と花音は咲が持っていた花器を受け取った。
「こちらの花瓶をお使い下さい」と小峰夫人に差し出す。
「いいんですか?」
「ええ。お花も、私のほうで生けさせて頂きますよ」
花音の提案に、小峰夫人は「それは助かります」と安堵の表情を浮かべた。
「あまりに大きな花束だったので、少し戸惑ってしまって。お花屋さんが生けて下さるなら、安心です」と微笑む。
それから花束を上り框に置き、花音から花器を受け取った。そうして玄関のドアを大きく開き、「どうぞ」と二人を招き入れた。
「お邪魔します」
花音と二人、玄関を潜ると、かなり広めの空間が現れる。
向かって右側には開放的なシューズクロークが備えられ、靴のほかにガーデニング用品や自転車などが整然と収納されていた。
反対側には咲の肩くらいの高さの靴箱が据えられ、その上に可愛らしいフラワーアレンジメントが置かれていた。
薄いピンク色の陶器の器の上に、黄色い丸みを帯びたバラを主役に、コロコロとした同系色の花がこんもりと乗ったアレンジである。アイビーと小さな五片の花びらの青い花が引き立て役のようにチラリと顔を見せていた。
「素敵な空間ですね」
咲はつい感嘆の声を漏らしてしまった。
「そう言って頂けると嬉しいわ」と微笑んで、玄関のドア閉めた小峰夫人は、「お水を汲んできますね」と花器と共に家の奥へと消えていった。
その背中を見送り、「配達って、花も生けるんですね」と花音を見上げた。
ううん、と花音は首を振る。
「普段は花生けまではやらないよ」
「そうなんですか?」
「うん。さっきも言ったけど、張り切りすぎて花束が大きくなっちゃったの。お花を習ってない人がこのボリュームの花束を貰ったら、処理に困るかなって思って」
たしかに、困るかも。咲はこの前の体験教室での花生けを思い出して、苦笑した。
「ちなみに花生けまで行うのは、『生け込み』っていうんだ」
「生け込み?」
「うん。場所の雰囲気に合わせて、その場で花を生けるの。ホテルやお店からの依頼が多いかな」
「そんなこともやってるんですね」
感心する咲に、まぁね、と花音は頷いた。
「教室だけじゃ、食べていけないから」
切ない事情を聞いてしまう。咲は曖昧な笑みを浮かべた。
「ちなみに花束ってラッピングを外したら、そのまま花器に入れるだけでいいように組んであるんだ」
「え、そうなんですか?」
「うん。だから、わざわざ生ける必要はないの。でも、小峰さん、戸惑っていたみたいだから」と家の奥に目を向ける。
ちょうど小峰夫人が花瓶を抱え、戻ってくるのが見えた。
「お待たせしました」
小峰夫人は水の入った花器を花音の前に置いた。
ありがとうございます、と花音は笑顔で礼を述べる。それからグルリと室内を見渡した。
「そちらの姿見の横に生けさせて頂いてもよろしいですか?」
靴箱の横に大きな姿見があり、その右隣りを花音は手のひらで指し示す。
はい、と小峰夫人は花器を姿見の横へと移動させた。
「では、少しお邪魔させて頂きますね」
「お願いします」
花音は靴を脱ぎ、上り框へと上がった。
花音は姿見の前で手際よく花束のラッピングを外した。次いで、花束を結えていたリボンを手で巻き取り、何かの形を作る。そして、腰にぶら下げたシザーバッグから細い針金を取り出し、それを結えた。
「これ、『フレンチボウ』っていうんです」
二人を振り返り、花音がそれを掲げる。プレゼントによくついている花の形をしたリボンに似ていた。
あれって、手作りできるんだ。
「旦那さんはよくお花を贈られる方なのですか?」
後片付けついでに花音は世間話を始める。
「以前は全然だったんですよ」
小峰夫人は顔の前で手を振り、ケラケラと笑った。
「──でも、アメリカに赴任してからは記念日にお花を贈ってくるようになりました」
「あちらでは記念日にお花を贈る習慣がありますからね」
「そうみたいですね。先月の誕生日には、お花とペンダントを贈ってくれました」
そう言って首元のペンダントを触る。丸い三つのダイヤモンドが縦に連なったデザインのものだ。
「そちらが誕生日プレゼントのペンダントですか?」
「ええ」
「とても素敵なデザインですね」
花音はニコリと笑った。
「でも、いつもは別のペンダントをお着けになられているのでは?」
「え?」
花音の問いに、小峰夫人の目が大きく見開いた。
「……どうして?」
驚きで声がかすかに掠れる。
「いえ、ペンダントに触れる動作が、少しぎこちなかったので」
「ぎこちない?」
ええ、と花音は人差し指を唇に当てた。
「いつも着けているペンダントは、そちらとチェーンの長さが違うのだと思います。だから、ペンダントトップを触ろうとしたとき、一度で触れることができなかった」
「それで……」と小峰夫人は目を大きく見開いた。
「お花屋さんのおっしゃるとおりです。──いつもは結婚前に主人が贈ってくれたペンダントを着けているんですけど……」
小峰夫人の顔が僅かに曇る。
「そのペンダントトップをなくしてしまって」と眉根を寄せた。
1
あなたにおすすめの小説

【完結済】25億で極道に売られた女。姐になります!
satomi
恋愛
昼夜問わずに働く18才の主人公南ユキ。
働けども働けどもその収入は両親に搾取されるだけ…。睡眠時間だって2時間程度しかないのに、それでもまだ働き口を増やせと言う両親。
早朝のバイトで頭は朦朧としていたけれど、そんな時にうちにやってきたのは白虎商事CEOの白川大雄さん。ポーンっと25億で私を買っていった。
そんな大雄さん、白虎商事のCEOとは別に白虎組組長の顔を持っていて、私に『姐』になれとのこと。
大丈夫なのかなぁ?

『冷徹社長の秘書をしていたら、いつの間にか専属の妻に選ばれました』
鍛高譚
恋愛
秘書課に異動してきた相沢結衣は、
仕事一筋で冷徹と噂される社長・西園寺蓮の専属秘書を務めることになる。
厳しい指示、膨大な業務、容赦のない会議――
最初はただ必死に食らいつくだけの日々だった。
だが、誰よりも真剣に仕事と向き合う蓮の姿に触れるうち、
結衣は秘書としての誇りを胸に、確かな成長を遂げていく。
そして、蓮もまた陰で彼女を支える姿勢と誠実な仕事ぶりに心を動かされ、
次第に結衣は“ただの秘書”ではなく、唯一無二の存在になっていく。
同期の嫉妬による妨害、ライバル会社の不正、社内の疑惑。
数々の試練が二人を襲うが――
蓮は揺るがない意志で結衣を守り抜き、
結衣もまた社長としてではなく、一人の男性として蓮を信じ続けた。
そしてある夜、蓮がようやく口にした言葉は、
秘書と社長の関係を静かに越えていく。
「これからの人生も、そばで支えてほしい。」
それは、彼が初めて見せた弱さであり、
結衣だけに向けた真剣な想いだった。
秘書として。
一人の女性として。
結衣は蓮の差し伸べた未来を、涙と共に受け取る――。
仕事も恋も全力で駆け抜ける、
“冷徹社長×秘書”のじれ甘オフィスラブストーリー、ここに完結。

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。

皇太后(おかあ)様におまかせ!〜皇帝陛下の純愛探し〜
菰野るり
キャラ文芸
皇帝陛下はお年頃。
まわりは縁談を持ってくるが、どんな美人にもなびかない。
なんでも、3年前に一度だけ出逢った忘れられない女性がいるのだとか。手がかりはなし。そんな中、皇太后は自ら街に出て息子の嫁探しをすることに!
この物語の皇太后の名は雲泪(ユンレイ)、皇帝の名は堯舜(ヤオシュン)です。つまり【後宮物語〜身代わり宮女は皇帝陛下に溺愛されます⁉︎〜】の続編です。しかし、こちらから読んでも楽しめます‼︎どちらから読んでも違う感覚で楽しめる⁉︎こちらはポジティブなラブコメです。

10年引きこもりの私が外に出たら、御曹司の妻になりました
専業プウタ
恋愛
25歳の桜田未来は中学生から10年以上引きこもりだったが、2人暮らしの母親の死により外に出なくてはならなくなる。城ヶ崎冬馬は女遊びの激しい大手アパレルブランドの副社長。彼をストーカーから身を張って助けた事で未来は一時的に記憶喪失に陥る。冬馬はちょっとした興味から、未来は自分の恋人だったと偽る。冬馬は未来の純粋さと直向きさに惹かれていき、嘘が明らかになる日を恐れながらも未来の為に自分を変えていく。そして、未来は恐れもなくし、愛する人の胸に飛び込み夢を叶える扉を自ら開くのだった。

それは、ホントに不可抗力で。
樹沙都
恋愛
これ以上他人に振り回されるのはまっぴらごめんと一大決意。人生における全ての無駄を排除し、おひとりさまを謳歌する歩夢の前に、ひとりの男が立ちはだかった。
「まさか、夫の顔……を、忘れたとは言わないだろうな? 奥さん」
その婚姻は、天の啓示か、はたまた……ついうっかり、か。
恋に仕事に人間関係にと翻弄されるお人好しオンナ関口歩夢と腹黒大魔王小林尊の攻防戦。
まさにいま、開始のゴングが鳴った。
まあね、所詮、人生は不可抗力でできている。わけよ。とほほっ。

イケメン警視、アルバイトで雇った恋人役を溺愛する。
楠ノ木雫
恋愛
蒸発した母の借金を擦り付けられた主人公瑠奈は、お見合い代行のアルバイトを受けた。だが、そのお見合い相手、矢野湊に借金の事を見破られ3ヶ月間恋人役を務めるアルバイトを提案された。瑠奈はその報酬に飛びついたが……
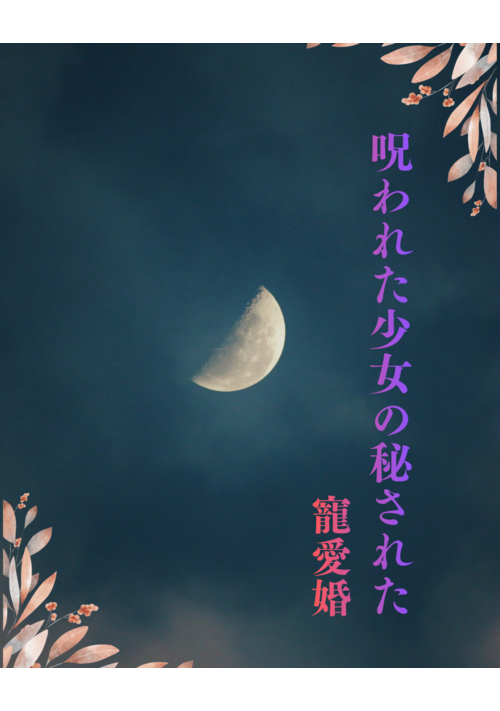
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















