42 / 84
4.魔王城の闇医者
10話
しおりを挟む
心の内側に手を突っ込まれ、かき混ぜられたような心地悪さを伴ったまま、シオンは宿への帰路についていた。
帰り道で簡単に昼食を済ませたが、頭の中がエリオルの言葉で埋め尽くされ、まるで味がしなかった。
とぼとぼと交互に出される自分の足先を見つめるように俯いて、ただ歩く。
午後にはシンシアの館に向かう予定だ。
レヴィアスは、もう宿に戻っているだろうか。
実のところ、今朝レヴィアスと顔を合わせずに済んだのはシオンにとって有難いことだった。
昨夜レヴィアスに対する特別な感情にはっきりと気付いてしまったために、正面から顔を見る事が出来るか不安だったのだ。
けれど、足取り重く宿に向かう今、心の中は全く違う感情で支配されていた。
「私の知らない、レヴィアスさん……」
もちろん、ぽっと出の自分が知らないことなんて山ほどある。
だからこそ、向き合って、会話をして、分かり合うことを大切にしてきたつもりだ。
けれど……。
得体の知れない恐怖が、シオンの背後から体を包むように襲ってくる。
今まで積み重ねてきた彼に対する信頼が崩れることは無い。
それでも、ぬかるみに足を取られるように、じわじわとエリオルの言葉が心を侵食するのだ。
(……駄目、今はシンシアさんのことを考えるのが先)
無理やり頭を仕事モードに引き戻し、気づけば目の前には宿の扉が佇んでいた。
ひとつ大きく深呼吸をして、その扉を押し開ける。
ふわりと漂うコーヒーの香り。
窓から差し込む日の光が淡く照らす先に、レヴィアスの姿があった。
いつもと変わらないその姿に、シオンはほっと息をつく。
エリオルの言葉一つで、目の前のレヴィアスが変貌するはずもない。
……大切なものを、見誤ってはいけない。
パチン!とシオンは両手で頬を叩いて、レヴィアスに向かって微笑んだ。
「お待たせしました!」
「いえ……大丈夫ですか?」
「気合を!入れました!」
そうですか、と呟くレヴィアスの表情が僅かに曇る。
あまりにも不審な行動だっただろうか?
(全部の気持ちを飲み込もう。……とにかく、今は)
シオンはもう一度、笑顔を顔に貼り付ける。
じん、と頬が痛んだ。
◇
「それは何ですか?」
馬に二人乗りしながら、再びシンシアの館への道のりを進む。
シオンの手には、風船がひとつ。
「町のお祭りで、この風船を飛ばしていたんです。ほら、紐の根元にお花が結ばれているんですよ」
さあ出発、というタイミングで木に引っかかっていたのを発見し、シオンが救出したものだ。
手土産にもならないけれど、話のタネになればと持ってきた。
「この花、オリヴィエさんゆかりのものだそうで。シンシアさんにも馴染があるのかなって」
先ほど、宿で出発の準備をしながら、オリヴィエとシンシアの関係性についてかいつまんでレヴィアスに共有した。
エリオルと遭遇したことについては、話すべきか悩んだが今のところは伏せている。
レヴィアスの古い友人と名乗っていたが、好意的な態度とは思えなかったからだ。
それに、何の話をしたのか尋ねられた時に、エリオルの口から出た『同族殺し』という言葉をうまく濁せる自信がなかった。
(何も、レヴィアスさんのことをそう言ったと決まったわけでもないのに)
再び渦を巻きそうになる思考を断ち切るように、シオンは周囲の景色に目をやる。
森はどんどん深くなり、もう少しでシンシアの館の門扉の前というところで、ふとシオンは気が付いた。
「あ……ここにも、同じ花が咲いていますね」
錆びた門の傍らに、ひとかたまりの紫の花。
まるで誰かがそこを選んで植えたような、不自然な華やかさを感じる。
馬を降り、昨日のように姿を隠す魔法を施した。
見るからにおどろおどろしいヴァンパイアの館に踏み込もうという時に、シオンの隣にはぷかぷかと風船が浮かんでいる。
(私、もしかして凄い間抜けなことしてる?)
改めて不安に駆られるが、レヴィアスが何かを言う様子も特にない。
思いつきで持ってきてしまったが、何となく引っ込みもつかずそのまま手に紐をもって向かうことにした。
「……シンシアさん、開けてください!」
扉の前でシオンが叫ぶ。
しん、とした森に、その呼び声がじわりと溶ける。
さわさわと耳をくすぐるような、風に揺れる枝の音。
時折聞こえる獲物を狙うカラスたちの声。
それらのただ中に、シオンとレヴィアスは立ち尽くしていた。
やがて。
ガチャ、という重い金属が動く音が響き、閉ざされていたドアが微かに動いた。
「開けてくれました……!」
それは対話の意志なのか、改めて追い返そうとされているだけなのか、まだ分からない。
それでも、細く空いたそのドアの向こうに、何とかして希望を見出さなければいけないのだ。
レヴィアスはいつものごとく、つかつかとそのドアをくぐって暗闇の中へと進んでいく。
よしっ、とシオンは頷いて、遅れずその背を追いかけた。
「……あなたたちも、懲りないわね」
昨日よりも僅かにリラックスした装いで、シンシアが二人の前に現れた。
片手に携えたグラスには、深紅の液体が揺らめいている。
(血っ!?)
シオンは一瞬身構えるが、ゆらゆらと軽やかに揺れるその液体に、血液のような粘度はないようだった。
近くのテーブルに、数本のワインボトルが置かれている。
それを見て、シオンは小さく息をついた。
「お嬢さん、それは何?」
「あっ……手土産です!」
おずおずと風船を差し出す。
その姿に、シンシアは氷のように冷たく笑った。
(うっ……やっぱり変だったよね)
焦る心をごまかすように、シオンはへらりと笑った。
シンシアの緩やかな動きにあわせて、ふわっと酒の匂いが漂う。
一体、どれだけ飲んでいたのだろう?
「レヴィアス、あなたどういう教育してるのよ」
「彼女は私の部下ではありません」
(うう、それはそうなんですけど、どういう意味ですか、レヴィアスさん……)
シンシアは呆れたような目をしながら、興味なさげに手を伸ばした。
風船の紐を手繰るシンシアの指が、シオンの手に微かに触れる。
酔いが回っているのだろうか。
思いのほか、その手は温かい。
風船の紐を指先でつまむと、その先の部分にシンシアの目が留まった。
「……これは」
「お祭りで、風船を空に飛ばす時に、この花を結わい付けるのだそうで……その、オリヴィエさんにゆかりのある花だとか」
そう、とシンシアは小さく呟く。
いつもの強気で冷たい声とは異なる、僅かに震えるような声。
思わずちらりとシンシアの顔を盗み見るが、彼女の長い金髪に遮られてその表情を読み取ることはできなかった。
「ねえ、オリヴィエは……どうしているの?」
シンシアの問いに、一瞬シオンの喉が詰まる。
事実をありのままに伝える。
それだけのことのはずなのに、なぜか言葉に出すのがひどくためらわれた。
それは、シオンが二人の間になにかの特別な関係性を想像してしまっているからなのだろう。
「すでに亡くなって、今は彼の子と孫が家業を継いでいる」
レヴィアスが淡々とシンシアに向けて語る。
「そう」
それを聞いて呟いたシンシアの声に、動揺は見られなかった。
まるで、何度もこれをシミュレーションしてきたかのような、自然な呟き。
「あの……シンシアさんとオリヴィエさんは、長年一緒にここで研究をされていたんですよね?」
一歩踏み込んで、シオンが尋ねる。
その瞬間、シンシアの表情がぴしりと凍り付いたように見えた。
「あら、誰から聞いたのか知らないけれど、あなたが想像するような甘~い関係じゃないわよ」
くい、とグラスに残ったワインをあおり、シンシアが再び冷たい笑みを浮かべる。
ワインに似たルージュの赤が艶めかしい。
「あの子は私のモルモット。私の研究に弄ばれただけの、可哀想な男よ」
「モルモット……?」
ぞく、とシオンの体に悪寒が走る。
シンシアの研究とは、いったいなんだっただろうか。
魔王城から追放されるほど、恐れられ、忌避された研究。
不意に、シオンの足元を何かが走り抜けるような気配がした。
「きゃっ……!」
驚いて僅かに飛びのくと、そこには大きな黒猫の姿があった。
ニャー、とあくびをしながら鳴くその姿に、シオンは安堵の息を吐く。
が、その腹部に異様なものを見つけて戦慄した。
猫の腹部には切り裂かれたような傷が走り、まるでその傷を埋めるように蛇の鱗状の皮膚が張り巡らされている。
それは飾りではなく、猫の鼓動に合わせて確かに脈打っているようだった。
息を飲んで、シオンは数歩後ずさりする。
とん、と背中にレヴィアスの腕が振れた。
驚きに震えるシオンの体を、そっと支えてくれているようだった。
気付けば薄ぼんやりとランプに照らされている館のあちこちに、どこか違和感のある動物たちのはく製が飾られている。
竜のたてがみのような背びれを持った大きな魚。
不自然な骨の継ぎ目から蝙蝠の羽根の骨格が伸びる、狼の標本。
「何……これ……」
一瞬、呆けたように言葉が漏れる。
それから、おぞましいものに囲まれていることを一瞬にして理解し、シオンはぎゅっと目を閉じた。
――オリヴィエは、シンシアの研究に弄ばれた――
その言葉の意味を理解することを、脳が激しく拒絶している。
「恐ろしさがわかったかい?オリヴィエの子供たちだか知らないが、その子らに決して伝えちゃいけないよ」
オリヴィエがどんな目にあったか……なんてね。
妖しさをまとう唇を歪ませて、シンシアがそう忠告した。
その不気味さが館の空気を一瞬にして凍り付かせる。
漂うはずのない血の匂いすら感じさせるかのように、彼女のその言葉がずしりとシオンの心にのしかかった。
帰り道で簡単に昼食を済ませたが、頭の中がエリオルの言葉で埋め尽くされ、まるで味がしなかった。
とぼとぼと交互に出される自分の足先を見つめるように俯いて、ただ歩く。
午後にはシンシアの館に向かう予定だ。
レヴィアスは、もう宿に戻っているだろうか。
実のところ、今朝レヴィアスと顔を合わせずに済んだのはシオンにとって有難いことだった。
昨夜レヴィアスに対する特別な感情にはっきりと気付いてしまったために、正面から顔を見る事が出来るか不安だったのだ。
けれど、足取り重く宿に向かう今、心の中は全く違う感情で支配されていた。
「私の知らない、レヴィアスさん……」
もちろん、ぽっと出の自分が知らないことなんて山ほどある。
だからこそ、向き合って、会話をして、分かり合うことを大切にしてきたつもりだ。
けれど……。
得体の知れない恐怖が、シオンの背後から体を包むように襲ってくる。
今まで積み重ねてきた彼に対する信頼が崩れることは無い。
それでも、ぬかるみに足を取られるように、じわじわとエリオルの言葉が心を侵食するのだ。
(……駄目、今はシンシアさんのことを考えるのが先)
無理やり頭を仕事モードに引き戻し、気づけば目の前には宿の扉が佇んでいた。
ひとつ大きく深呼吸をして、その扉を押し開ける。
ふわりと漂うコーヒーの香り。
窓から差し込む日の光が淡く照らす先に、レヴィアスの姿があった。
いつもと変わらないその姿に、シオンはほっと息をつく。
エリオルの言葉一つで、目の前のレヴィアスが変貌するはずもない。
……大切なものを、見誤ってはいけない。
パチン!とシオンは両手で頬を叩いて、レヴィアスに向かって微笑んだ。
「お待たせしました!」
「いえ……大丈夫ですか?」
「気合を!入れました!」
そうですか、と呟くレヴィアスの表情が僅かに曇る。
あまりにも不審な行動だっただろうか?
(全部の気持ちを飲み込もう。……とにかく、今は)
シオンはもう一度、笑顔を顔に貼り付ける。
じん、と頬が痛んだ。
◇
「それは何ですか?」
馬に二人乗りしながら、再びシンシアの館への道のりを進む。
シオンの手には、風船がひとつ。
「町のお祭りで、この風船を飛ばしていたんです。ほら、紐の根元にお花が結ばれているんですよ」
さあ出発、というタイミングで木に引っかかっていたのを発見し、シオンが救出したものだ。
手土産にもならないけれど、話のタネになればと持ってきた。
「この花、オリヴィエさんゆかりのものだそうで。シンシアさんにも馴染があるのかなって」
先ほど、宿で出発の準備をしながら、オリヴィエとシンシアの関係性についてかいつまんでレヴィアスに共有した。
エリオルと遭遇したことについては、話すべきか悩んだが今のところは伏せている。
レヴィアスの古い友人と名乗っていたが、好意的な態度とは思えなかったからだ。
それに、何の話をしたのか尋ねられた時に、エリオルの口から出た『同族殺し』という言葉をうまく濁せる自信がなかった。
(何も、レヴィアスさんのことをそう言ったと決まったわけでもないのに)
再び渦を巻きそうになる思考を断ち切るように、シオンは周囲の景色に目をやる。
森はどんどん深くなり、もう少しでシンシアの館の門扉の前というところで、ふとシオンは気が付いた。
「あ……ここにも、同じ花が咲いていますね」
錆びた門の傍らに、ひとかたまりの紫の花。
まるで誰かがそこを選んで植えたような、不自然な華やかさを感じる。
馬を降り、昨日のように姿を隠す魔法を施した。
見るからにおどろおどろしいヴァンパイアの館に踏み込もうという時に、シオンの隣にはぷかぷかと風船が浮かんでいる。
(私、もしかして凄い間抜けなことしてる?)
改めて不安に駆られるが、レヴィアスが何かを言う様子も特にない。
思いつきで持ってきてしまったが、何となく引っ込みもつかずそのまま手に紐をもって向かうことにした。
「……シンシアさん、開けてください!」
扉の前でシオンが叫ぶ。
しん、とした森に、その呼び声がじわりと溶ける。
さわさわと耳をくすぐるような、風に揺れる枝の音。
時折聞こえる獲物を狙うカラスたちの声。
それらのただ中に、シオンとレヴィアスは立ち尽くしていた。
やがて。
ガチャ、という重い金属が動く音が響き、閉ざされていたドアが微かに動いた。
「開けてくれました……!」
それは対話の意志なのか、改めて追い返そうとされているだけなのか、まだ分からない。
それでも、細く空いたそのドアの向こうに、何とかして希望を見出さなければいけないのだ。
レヴィアスはいつものごとく、つかつかとそのドアをくぐって暗闇の中へと進んでいく。
よしっ、とシオンは頷いて、遅れずその背を追いかけた。
「……あなたたちも、懲りないわね」
昨日よりも僅かにリラックスした装いで、シンシアが二人の前に現れた。
片手に携えたグラスには、深紅の液体が揺らめいている。
(血っ!?)
シオンは一瞬身構えるが、ゆらゆらと軽やかに揺れるその液体に、血液のような粘度はないようだった。
近くのテーブルに、数本のワインボトルが置かれている。
それを見て、シオンは小さく息をついた。
「お嬢さん、それは何?」
「あっ……手土産です!」
おずおずと風船を差し出す。
その姿に、シンシアは氷のように冷たく笑った。
(うっ……やっぱり変だったよね)
焦る心をごまかすように、シオンはへらりと笑った。
シンシアの緩やかな動きにあわせて、ふわっと酒の匂いが漂う。
一体、どれだけ飲んでいたのだろう?
「レヴィアス、あなたどういう教育してるのよ」
「彼女は私の部下ではありません」
(うう、それはそうなんですけど、どういう意味ですか、レヴィアスさん……)
シンシアは呆れたような目をしながら、興味なさげに手を伸ばした。
風船の紐を手繰るシンシアの指が、シオンの手に微かに触れる。
酔いが回っているのだろうか。
思いのほか、その手は温かい。
風船の紐を指先でつまむと、その先の部分にシンシアの目が留まった。
「……これは」
「お祭りで、風船を空に飛ばす時に、この花を結わい付けるのだそうで……その、オリヴィエさんにゆかりのある花だとか」
そう、とシンシアは小さく呟く。
いつもの強気で冷たい声とは異なる、僅かに震えるような声。
思わずちらりとシンシアの顔を盗み見るが、彼女の長い金髪に遮られてその表情を読み取ることはできなかった。
「ねえ、オリヴィエは……どうしているの?」
シンシアの問いに、一瞬シオンの喉が詰まる。
事実をありのままに伝える。
それだけのことのはずなのに、なぜか言葉に出すのがひどくためらわれた。
それは、シオンが二人の間になにかの特別な関係性を想像してしまっているからなのだろう。
「すでに亡くなって、今は彼の子と孫が家業を継いでいる」
レヴィアスが淡々とシンシアに向けて語る。
「そう」
それを聞いて呟いたシンシアの声に、動揺は見られなかった。
まるで、何度もこれをシミュレーションしてきたかのような、自然な呟き。
「あの……シンシアさんとオリヴィエさんは、長年一緒にここで研究をされていたんですよね?」
一歩踏み込んで、シオンが尋ねる。
その瞬間、シンシアの表情がぴしりと凍り付いたように見えた。
「あら、誰から聞いたのか知らないけれど、あなたが想像するような甘~い関係じゃないわよ」
くい、とグラスに残ったワインをあおり、シンシアが再び冷たい笑みを浮かべる。
ワインに似たルージュの赤が艶めかしい。
「あの子は私のモルモット。私の研究に弄ばれただけの、可哀想な男よ」
「モルモット……?」
ぞく、とシオンの体に悪寒が走る。
シンシアの研究とは、いったいなんだっただろうか。
魔王城から追放されるほど、恐れられ、忌避された研究。
不意に、シオンの足元を何かが走り抜けるような気配がした。
「きゃっ……!」
驚いて僅かに飛びのくと、そこには大きな黒猫の姿があった。
ニャー、とあくびをしながら鳴くその姿に、シオンは安堵の息を吐く。
が、その腹部に異様なものを見つけて戦慄した。
猫の腹部には切り裂かれたような傷が走り、まるでその傷を埋めるように蛇の鱗状の皮膚が張り巡らされている。
それは飾りではなく、猫の鼓動に合わせて確かに脈打っているようだった。
息を飲んで、シオンは数歩後ずさりする。
とん、と背中にレヴィアスの腕が振れた。
驚きに震えるシオンの体を、そっと支えてくれているようだった。
気付けば薄ぼんやりとランプに照らされている館のあちこちに、どこか違和感のある動物たちのはく製が飾られている。
竜のたてがみのような背びれを持った大きな魚。
不自然な骨の継ぎ目から蝙蝠の羽根の骨格が伸びる、狼の標本。
「何……これ……」
一瞬、呆けたように言葉が漏れる。
それから、おぞましいものに囲まれていることを一瞬にして理解し、シオンはぎゅっと目を閉じた。
――オリヴィエは、シンシアの研究に弄ばれた――
その言葉の意味を理解することを、脳が激しく拒絶している。
「恐ろしさがわかったかい?オリヴィエの子供たちだか知らないが、その子らに決して伝えちゃいけないよ」
オリヴィエがどんな目にあったか……なんてね。
妖しさをまとう唇を歪ませて、シンシアがそう忠告した。
その不気味さが館の空気を一瞬にして凍り付かせる。
漂うはずのない血の匂いすら感じさせるかのように、彼女のその言葉がずしりとシオンの心にのしかかった。
0
あなたにおすすめの小説

凡夫転生〜異世界行ったらあまりにも普通すぎた件〜
小林一咲
ファンタジー
「普通がいちばん」と教え込まれてきた佐藤啓二は、日本の平均寿命である81歳で平凡な一生を終えた。
死因は癌だった。
癌による全死亡者を占める割合は24.6パーセントと第一位である。
そんな彼にも唯一「普通では無いこと」が起きた。
死後の世界へ導かれ、女神の御前にやってくると突然異世界への転生を言い渡される。
それも生前の魂、記憶や未来の可能性すらも次の世界へと引き継ぐと言うのだ。
啓二は前世でもそれなりにアニメや漫画を嗜んでいたが、こんな展開には覚えがない。
挙げ句の果てには「質問は一切受け付けない」と言われる始末で、あれよあれよという間に異世界へと転生を果たしたのだった。
インヒター王国の外、漁業が盛んな街オームで平凡な家庭に産まれ落ちた啓二は『バルト・クラスト』という新しい名を受けた。
そうして、しばらく経った頃に自身の平凡すぎるステータスとおかしなスキルがある事に気がつく――。
これはある平凡すぎる男が異世界へ転生し、その普通で非凡な力で人生を謳歌する物語である。
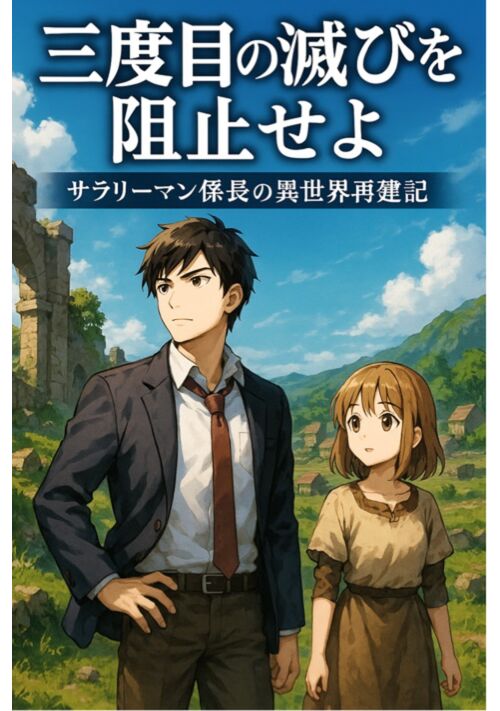
『三度目の滅びを阻止せよ ―サラリーマン係長の異世界再建記―』
KAORUwithAI
ファンタジー
45歳、胃薬が手放せない大手総合商社営業部係長・佐藤悠真。
ある日、横断歩道で子供を助け、トラックに轢かれて死んでしまう。
目を覚ますと、目の前に現れたのは“おじさんっぽい神”。
「この世界を何とかしてほしい」と頼まれるが、悠真は「ただのサラリーマンに何ができる」と拒否。
しかし神は、「ならこの世界は三度目の滅びで終わりだな」と冷徹に突き放す。
結局、悠真は渋々承諾。
与えられたのは“現実知識”と“ワールドサーチ”――地球の知識すら検索できる探索魔法。
さらに肉体は20歳に若返り、滅びかけの異世界に送り込まれた。
衛生観念もなく、食糧も乏しく、二度の滅びで人々は絶望の淵にある。
だが、係長として培った経験と知識を武器に、悠真は人々をまとめ、再び世界を立て直そうと奮闘する。
――これは、“三度目の滅び”を阻止するために挑む、ひとりの中年係長の異世界再建記である。

『規格外の薬師、追放されて辺境スローライフを始める。〜作ったポーションが国家機密級なのは秘密です〜』
雛月 らん
ファンタジー
俺、黒田 蓮(くろだ れん)35歳は前世でブラック企業の社畜だった。過労死寸前で倒れ、次に目覚めたとき、そこは剣と魔法の異世界。しかも、幼少期の俺は、とある大貴族の私生児、アレン・クロイツェルとして生まれ変わっていた。
前世の記憶と、この世界では「外れスキル」とされる『万物鑑定』と『薬草栽培(ハイレベル)』。そして、誰にも知られていない規格外の莫大な魔力を持っていた。
しかし、俺は決意する。「今世こそ、誰にも邪魔されない、のんびりしたスローライフを送る!」と。
これは、スローライフを死守したい天才薬師のアレンと、彼の作る規格外の薬に振り回される異世界の物語。
平穏を愛する(自称)凡人薬師の、のんびりだけど実は波乱万丈な辺境スローライフファンタジー。

異世界でゆるゆるスローライフ!~小さな波乱とチートを添えて~
イノナかノかワズ
ファンタジー
助けて、刺されて、死亡した主人公。神様に会ったりなんやかんやあったけど、社畜だった前世から一転、ゆるいスローライフを送る……筈であるが、そこは知識チートと能力チートを持った主人公。波乱に巻き込まれたりしそうになるが、そこはのんびり暮らしたいと持っている主人公。波乱に逆らい、世界に名が知れ渡ることはなくなり、知る人ぞ知る感じに収まる。まぁ、それは置いといて、主人公の新たな人生は、温かな家族とのんびりした自然、そしてちょっとした研究生活が彩りを与え、幸せに溢れています。
*話はとてもゆっくりに進みます。また、序盤はややこしい設定が多々あるので、流しても構いません。
*他の小説や漫画、ゲームの影響が見え隠れします。作者の願望も見え隠れします。ご了承下さい。
*頑張って週一で投稿しますが、基本不定期です。
*本作の無断転載、無断翻訳、無断利用を禁止します。
小説家になろうにて先行公開中です。主にそっちを優先して投稿します。
カクヨムにても公開しています。
更新は不定期です。

転生したみたいなので異世界生活を楽しみます
さっちさん
ファンタジー
又々、題名変更しました。
内容がどんどんかけ離れていくので…
沢山のコメントありがとうございます。対応出来なくてすいません。
誤字脱字申し訳ございません。気がついたら直していきます。
感傷的表現は無しでお願いしたいと思います😢
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ありきたりな転生ものの予定です。
主人公は30代後半で病死した、天涯孤独の女性が幼女になって冒険する。
一応、転生特典でスキルは貰ったけど、大丈夫か。私。
まっ、なんとかなるっしょ。

高校生の俺、異世界転移していきなり追放されるが、じつは最強魔法使い。可愛い看板娘がいる宿屋に拾われたのでもう戻りません
下昴しん
ファンタジー
高校生のタクトは部活帰りに突然異世界へ転移してしまう。
横柄な態度の王から、魔法使いはいらんわ、城から出ていけと言われ、いきなり無職になったタクト。
偶然会った宿屋の店長トロに仕事をもらい、看板娘のマロンと一緒に宿と食堂を手伝うことに。
すると突然、客の兵士が暴れだし宿はメチャクチャになる。
兵士に殴り飛ばされるトロとマロン。
この世界の魔法は、生活で利用する程度の威力しかなく、とても弱い。
しかし──タクトの魔法は人並み外れて、無法者も脳筋男もひれ伏すほど強かった。

転生魔竜~異世界ライフを謳歌してたら世界最強最悪の覇者となってた?~
アズドラ
ファンタジー
主人公タカトはテンプレ通り事故で死亡、運よく異世界転生できることになり神様にドラゴンになりたいとお願いした。 夢にまで見た異世界生活をドラゴンパワーと現代地球の知識で全力満喫! 仲間を増やして夢を叶える王道、テンプレ、モリモリファンタジー。

家庭菜園物語
コンビニ
ファンタジー
お人好しで動物好きな最上悠は肉親であった祖父が亡くなり、最後の家族であり姉のような存在でもある黒猫の杏も、寿命から静かに息を引き取ろうとする。
「助けたいなら異世界に来てくれない」と少し残念な神様と出会う。
転移先では半ば強引に、死にかけていた犬を助けたことで、能力を失いそのひっそりとスローライフを送ることになってしまうが
迷い込んだ、訪問者次々とやってきて異世界で新しい家族や友人を作り、本人としてはほのぼのと家庭菜園を営んでいるが、小さな畑が世界には大きな影響を与えることになっていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















