13 / 13
一章 ソフト勧誘編
四回裏 バスの車窓から
しおりを挟む
「で、どうだったよ?」
ソフトボール大会後の部活の練習終わり、私は今日の(監督いわく)トライアウトの結果を報告するために監督室にきていた。
「はい、最高の逸材がいました。一人だけですが……」
「そうか! その子は何組の誰だ?」
監督は嬉しそうに私から回収した青いファイルを広げた。
「B組の広瀬さんです」
「B組の……、広瀬、広瀬……、おっ! この子か! なんだ! 帰宅部じゃないか」
B組のページの広瀬さんを指差しながら、監督は満足そうに笑っている。
「これなら、上手く話に乗せれば入ってくれそうじゃないか? 例えば……、そうだ! ソフトボール用品一式支給とかな!」
がははと笑う監督。素直に入ってくださいと頼む選択肢は初めからこの人の中には存在しないのだろうか。と思いながら遠い目で監督を見つめる。
「どうかは分かりませんが、ただそう簡単にはいかないかもしれません」
対戦してみて、彼女のスキルが高いのは分かった。しかし、あの試合、最終回になるまで彼女の存在にすら気付かなかったのも事実だ。
あれほどの選手、大会序盤から活躍していてもおかしくなかった。どうして彼女はそこまで力を出さなかったのか? 私は試合の詳細を監督に話した。
◇
「なるほど……、確かに引っ掛かるな。何かやりたない理由があるとか……。どちらにせよ、彼女と話をしないことには始まらないな。案外、あっさりいったりしてな! しかし、すげぇな、七割とは言えお前の球をスタンドインさせるなんて! そんなパワーがあるようには見えねえけどな」
あ……、最後の打席だけ全力を出した事を伝え忘れていた。まぁそこに関してはそんなに重要でもないか……。
「実際、小柄ですしパワーはないと思います。でもそれを補うだけの体幹の強さスキルがあります。それに、私の球を見極める選球眼、動体視力もあるかと」
「それは是非とも欲しいな! 二番セカンド……、いや一番セカンドで使えれば初回から得点を狙える! ポジション的に少し問題はあるが……」
確かに、選手層の薄い今のチームだとトップバッターは重要になってくる。広瀬さんほどの選手が一人入るだけでそこは解消されるのは間違いない。ただ……。
「セカンドは二年の本間先輩ですか……」
監督の表情が一瞬曇る。
「あぁ、でもそれを今悩んでもしょうがない! そんなことは二の次だ! 氷山、早速で悪いんだが、この広瀬さんとやらに接触してくれ!」
「――えっ、私がですか?」
正直言って、私はコミュニケーションを取るのが好きではない。ソフトボールの試合、打者との駆け引きは別として、相手の様子を伺いながら話をすることが面倒で仕方ないのだ。
「監督が直に話した方が良いのではないでしょうか?」
「うーん……すまん! 俺は色々と忙しいんだ。だからこの件に関してはお前に任せる!」
自分の進退にも関わる大事なことのはずなのに、今の間、表情、おそらくだか監督も面倒くさいのだろう。しかし、私に拒否権はない。監督が頼むと言えば私はイエスとしか答えられない。それだけの忠誠心が私にはある。それは監督も分かっている。だからこうして私に言ってくるのだろう。
「はぁ……。分かりました」
私が気のない返事をしても監督は満足そうに笑っていた。監督も信頼してくれているのだろうが、私には面白がっているようにしか見えなかった。
「それじゃ、頼んだぞ!」
私は「はい」と返事をすると監督に一礼をして監督室を後にした。
◇
帰りのバスの中、私は考えていた。
試合で戦った相手だからといって、ほぼ初対面の相手。どうしたら自然に誘えるか? まずは仲良くなる必要があるのではないだろうか。でもクラスは違う……。
(困ったわ……)
こういうとき結菜みたいに気さくに話せる性格が羨ましくなる。
きっと結菜なら、いとも簡単にソフト部入らないっすか? なんて言ってしまうだろう。
(私には到底無理な話ね)
とりあえず今日出来ることは何もない。明日にでも結菜に頼んでみようかしら。そう思いながら外を眺めていた。
すると突然、夜道を歩く人影と目が合った。
(――えっ? 今のは……、広瀬さん?)
バスの中が明るいこともあって、はっきりと見えないが多分彼女だ。わたしの勘がそう言っている。
(なんで彼女がこんなところに?)
いや、今はそんな事を気にしている場合じゃない。監督に頼まれた以上私がやらなくてはならない。私は咄嗟に降車ボタンを押す。
バスは直ぐに停車した。ここから広瀬さんのいる場所は近い。走れば直ぐに追い付ける距離だ。
私はバスを降りると直ぐ様走り出した。
しかし、走りながらふと思う。あれは本当に広瀬さんだったのだろうか、一瞬しか見ていないが、昼間と印象が全然違った。
(違ったらどうしましょう……)
仮に広瀬さんだったとして、何て声をかければいい? こんばんわ? 今日は良い勝負だった? いや、まだお互いに自己紹介すらしていない。彼女が私を見て誰だか分かるかも疑問だ。私の不安は募る一方だった。
が、すぐにその不安や疑問を忘れてしまうくらい驚くべき光景が私の目に飛び込んできた。
(――えっ? どうして?)
なんと反対方向から広瀬さんと思われる人物がこちらに向かって来ていたのだ。しかも走って。
その光景を見た瞬間、私は思わず笑ってしまった。自分でも不思議だった。それでもなぜか笑ってしまった、無意識に、突発的に笑ってしまったのだ。
(あなたも“何か”を感じたようね)
“何か”が何かは分からない。でもお互いにその何かを感じたのは間違いないようだ。そう思うと私は嬉しかった。試合と呼べないような試合、七割でしか投げれない苦痛、そんな球すら打てない生徒たち、監督の指示だったとはいえ、正直何も面白くない、メリットのない大会だった。でも彼女との勝負だけは違った。だから、今、この瞬間、あのソフトボール大会は無駄ではなかったと心から思う。
(私は……、私はあなたとソフトがしたい!)
二人の距離はどんどん近づく。しかし、
(――えっ! なぜ?)
広瀬さんらしき人物は急に止まると、引き返し始めた。
もう目と鼻の先に彼女がいる。ここまできて声をかけないなんて私には……無理。
「(今まで誰かと一緒にソフトボールをしたいなんて思ったこともないのに……、そんな想いにまでさせといて、なぜあなたは背を向けるの? あなたは何も感じてなかったっていうの?)ちょっと、あなた! 広瀬さん、広瀬るいさんでしょ?」
私は咄嗟に声をかけた。声はかけたが、もし、この気持ちが私の独りよがりだったらと思うと不安でしょうがない。
「――えっ?」
私の呼び掛けに広瀬さんは振り返ってくれた。彼女は驚いているのか、なんともいえない表情をしている。
「そうですけど……」
もしかしたら、彼女も私と同じように不安だったのかもしれない。そう考えると少し楽になった。私は広瀬さんに微笑んだ。
「よかったわ。バスからあなたの姿が見えたから」
「わっ、わたしも!」
「そう、あなたも……。それは良かったわ」
やっぱり彼女は不安だったようだ。その証拠に、こんなにもおどおどしている。
(あら?)
そのとき私は気付いた。昼間と印象が違うと思っていた理由、それは誰でもわかるような単純なことだった。
「広瀬さんって化粧しないと子供みたいね」
「は?」
さすがに今のはまずかったかしら? すっぴんの広瀬さんは目を細め睨むように私を見つめている。別に悪気はないのだけど……。私としてはどちらかというと誉め言葉だ。私は昔から大きかったせいか年相応に見られなかった。だから同年代の子たちと遊んでいても、一人だけ浮いていた。
「あら、ごめんなさい。気にさわったかしら? 悪気はないのなよ」
「べっ、べつに、気にしてないですっ!」
明らかに気にした様子の広瀬さん。言葉とは反対で顔がもろにそう言っている。
(素のときは感情が顔に出るタイプなのね)
試合の時は何を考えているか分からなかったのに、素のときこんな分かりやすい子だったのには驚きだ。
「そんなことより、わたしに何か用事があるんじゃないんですか? というか……、何でわたしの名前知ってるんですか?」
同い年なのに敬語というのは気になるが、それはさておき、私は彼女の名前を知っている。でもそれはあの資料があったからだ。私からするとたいした問題ではないが、彼女からしたらただの個人情報の漏洩。私はもっともらしく言葉を並べる。
「あら? 知ってたらおかしいかしら? だつて今日あんなに気持ち良くホームランを打たれた相手よ? 誰かに聞いててもおかしくないわ。あなたも私の名前くらいは知っているでしょう?」
咄嗟の話にしては上出来だ。でもホームランを打たれたことは正直根に持っている。渾身のストレートをあそこまで運ばれたのだから気にしない訳がない。
本気の戦いをした相手、彼女も私を知っているに違いない。そう思った、だけど広瀬さんの口から出た言葉は私の予想とはかけ離れたものだった。
「ごめん、知らない……」
「(知らないですって? 私はこんなに意識していたのに? 冗談でしょ? 冗談よね?)本当に?」
「はい」
しかし、広瀬さんは私の願いを簡単にぶち壊した。驚きと悔しさで言葉がつまる。
彼女からしたら私は印象にも残らないようなダメなピッチャーだったのだろうか……。
「私の投げる球って魅力ないのかしら……」
私ははうつむき考えるようにボソッと呟いた。すると広瀬さんは、
「そんなことないです! 凄かったです! 間違いなく今まで対戦した相手をの中で一番だったです! はい!」
必死にそう言っているが、その必死さが逆に言い訳のように聞こえる。おそらく彼女の中には更に優れたピッチャーがいるのだろう。それを今言っても仕方はないが……、私は目をつぶって軽く息を吐いた。
「まぁいいわ。私はC組の氷山つらら、ソフトボール部の一年よ」
「よろしく」と言って私は手を差し出した。広瀬さんはその手を取ってくれた。握った彼女の手は冷たかった。その冷たさが私の心を刺激する。
(今はまだ広瀬さんの中で一番のピッチャーじゃなくても、私は必ず越えてみせる。一番のピッチャーになってみせる)そう心に誓った。
そして、お互いに笑い合った――。
変に噛みついてしまったが、とりあえず広瀬さんとの接触には成功した。後はどう勧誘するかだけど……。
その時、私はふとあることを思い出した。広瀬さんの手を離すと、迷わずバッグからスマホを取りだした。
「今何時かしら?」
取り出したスマホの画面には幼い頃の私と若い両親の姿が写っている。これは残っている最後の家族写真。携帯を変えてもずっとデータを移行して残している大切な画像だ。
その画像の上にある時計を確認する。時計は二十時五十五分と表示されていた。
それを目にした途端、私は焦った。
「いけない! もう九時前だわ! 早く帰らないと!」
さっきバスの中で下宿先の家主さんに『今から帰ります』とメールをしていたのだ。本来ならとっくに帰宅している時間だ。
「えっ! うそっ! もうそんな時間?」
時間が分かると広瀬さんも焦てだした。見たいテレビでもあるのだろうか。そんなことよりも私は早く帰らないと、そう思い広瀬さんに声をかけようとしたが先に口を開いたのは広瀬さんだった。
「じゃあね氷山さんっ!」
「――えっ! ええ、さようなら」
なんという瞬発力、声と同時に走り出した広瀬さんはもう数メートル先を行っている。
(速い! というか帰る方向一緒なのね)
私も急いで広瀬さんを追いかける。制服に部活バッグを持ってはいるが、身長の分私の方が手足は長い。
私はすかさず広瀬さんに並ぶ。
「あなたもこっちが家なのね!」
「そう! わたし下宿してるんだっ!」
「あら、そうなの?」
確かに前に下宿先の家主さんから聞いた事がある。私の下宿先に同じ高校の子がいると。私はまさかとは思ったが、それは胸の内にしまう。
「……奇遇ね! 私もよ!」
「そうなんだ! なんか、面白いねっ!」
「そうね!」
確かに面白すぎる。まだソフトボール部に入る確証もないが、広瀬さんと同じ下宿先かもしれない。これで本当に同じ下宿先で、ソフト部に入ったのならいったいどんな刺激的な毎日が私を待っているのだろう。そう考えるだけで自然と笑みがこぼれる。
「じゃあわたし、こっちだからっ! またね!」
広瀬さんは私の下宿先へと続く路地へと入っていく。
(――やっぱり!)
広瀬さんは走る勢いのまま下宿先の玄関ドアを開けた。私はそれにすかさず飛び込んだ。
「あらぁ、おかえり! あんたたち一緒やったとねぇ! 今から帰るって連絡きたとに、遅かったけん探しに行こうと思っとったとよ」
「陽子ママ、変なこと言わないでよ。わたし一人だよ」
「るいちゃんこそ、何ば言いよっとね。後ろにちゃんとおるやかね」
そんなに私は存在感がなかったのだろうか。言葉を発していないにせよこんなにも近くにいるのに、彼女は本当に気付いていないようだ。
(この子はバカなの? 天然なの?)
「陽子ママ! 祓ってっ! お願いっ! お願いだから、たずげでぇ~!」
しかも泣き出す始末。やれやれと私は存在を知らせるために肩を掴んだ。
「――ひぃっ!」
すると広瀬さんは声にならないような声をあげ竦み上がった。明らかに私を人だとは思っていない。
「ちょっと広瀬さん? それは失礼すぎやしないかしら?」
「えっ?」
広瀬さんはゆっくりとこちらを振り向く。それはもう本当にゆっくりと。
「えっ? ……ええぇぇぇ~っ!」
私の顔を見た広瀬さんは驚いたようで、突然大声をだした。私はその声に驚いた。今日一番の衝撃。ホームランを打たれたのとは違う衝撃。そんな失礼極まりない彼女の様子に私は少しイラッとした。
「驚きすぎよ。私だって、これでも驚いているのよ。あなたがそんなに驚いたら私は素直に驚けないじゃない」
「だって……、だっでぇ~~~」
広瀬さんは安心したのか膝から崩れ落ちた。子供のように泣く姿に私は苛立ちを押さえる。
「もう……、ほらしっかりしなさいよ。立てる?」
「たでない……」
泣きじゃくる広瀬さんを陽子さんと一緒に抱えながら、私たちは一旦リビングへ向かった。
その後、広瀬さんが落ち着くのを待って、私たちは各々の部屋に戻った。
そんなこんなで、私と広瀬さんの変な共同生活が始まるのであった。
(あ、勧誘するの忘れてたわ……)
ソフトボール大会後の部活の練習終わり、私は今日の(監督いわく)トライアウトの結果を報告するために監督室にきていた。
「はい、最高の逸材がいました。一人だけですが……」
「そうか! その子は何組の誰だ?」
監督は嬉しそうに私から回収した青いファイルを広げた。
「B組の広瀬さんです」
「B組の……、広瀬、広瀬……、おっ! この子か! なんだ! 帰宅部じゃないか」
B組のページの広瀬さんを指差しながら、監督は満足そうに笑っている。
「これなら、上手く話に乗せれば入ってくれそうじゃないか? 例えば……、そうだ! ソフトボール用品一式支給とかな!」
がははと笑う監督。素直に入ってくださいと頼む選択肢は初めからこの人の中には存在しないのだろうか。と思いながら遠い目で監督を見つめる。
「どうかは分かりませんが、ただそう簡単にはいかないかもしれません」
対戦してみて、彼女のスキルが高いのは分かった。しかし、あの試合、最終回になるまで彼女の存在にすら気付かなかったのも事実だ。
あれほどの選手、大会序盤から活躍していてもおかしくなかった。どうして彼女はそこまで力を出さなかったのか? 私は試合の詳細を監督に話した。
◇
「なるほど……、確かに引っ掛かるな。何かやりたない理由があるとか……。どちらにせよ、彼女と話をしないことには始まらないな。案外、あっさりいったりしてな! しかし、すげぇな、七割とは言えお前の球をスタンドインさせるなんて! そんなパワーがあるようには見えねえけどな」
あ……、最後の打席だけ全力を出した事を伝え忘れていた。まぁそこに関してはそんなに重要でもないか……。
「実際、小柄ですしパワーはないと思います。でもそれを補うだけの体幹の強さスキルがあります。それに、私の球を見極める選球眼、動体視力もあるかと」
「それは是非とも欲しいな! 二番セカンド……、いや一番セカンドで使えれば初回から得点を狙える! ポジション的に少し問題はあるが……」
確かに、選手層の薄い今のチームだとトップバッターは重要になってくる。広瀬さんほどの選手が一人入るだけでそこは解消されるのは間違いない。ただ……。
「セカンドは二年の本間先輩ですか……」
監督の表情が一瞬曇る。
「あぁ、でもそれを今悩んでもしょうがない! そんなことは二の次だ! 氷山、早速で悪いんだが、この広瀬さんとやらに接触してくれ!」
「――えっ、私がですか?」
正直言って、私はコミュニケーションを取るのが好きではない。ソフトボールの試合、打者との駆け引きは別として、相手の様子を伺いながら話をすることが面倒で仕方ないのだ。
「監督が直に話した方が良いのではないでしょうか?」
「うーん……すまん! 俺は色々と忙しいんだ。だからこの件に関してはお前に任せる!」
自分の進退にも関わる大事なことのはずなのに、今の間、表情、おそらくだか監督も面倒くさいのだろう。しかし、私に拒否権はない。監督が頼むと言えば私はイエスとしか答えられない。それだけの忠誠心が私にはある。それは監督も分かっている。だからこうして私に言ってくるのだろう。
「はぁ……。分かりました」
私が気のない返事をしても監督は満足そうに笑っていた。監督も信頼してくれているのだろうが、私には面白がっているようにしか見えなかった。
「それじゃ、頼んだぞ!」
私は「はい」と返事をすると監督に一礼をして監督室を後にした。
◇
帰りのバスの中、私は考えていた。
試合で戦った相手だからといって、ほぼ初対面の相手。どうしたら自然に誘えるか? まずは仲良くなる必要があるのではないだろうか。でもクラスは違う……。
(困ったわ……)
こういうとき結菜みたいに気さくに話せる性格が羨ましくなる。
きっと結菜なら、いとも簡単にソフト部入らないっすか? なんて言ってしまうだろう。
(私には到底無理な話ね)
とりあえず今日出来ることは何もない。明日にでも結菜に頼んでみようかしら。そう思いながら外を眺めていた。
すると突然、夜道を歩く人影と目が合った。
(――えっ? 今のは……、広瀬さん?)
バスの中が明るいこともあって、はっきりと見えないが多分彼女だ。わたしの勘がそう言っている。
(なんで彼女がこんなところに?)
いや、今はそんな事を気にしている場合じゃない。監督に頼まれた以上私がやらなくてはならない。私は咄嗟に降車ボタンを押す。
バスは直ぐに停車した。ここから広瀬さんのいる場所は近い。走れば直ぐに追い付ける距離だ。
私はバスを降りると直ぐ様走り出した。
しかし、走りながらふと思う。あれは本当に広瀬さんだったのだろうか、一瞬しか見ていないが、昼間と印象が全然違った。
(違ったらどうしましょう……)
仮に広瀬さんだったとして、何て声をかければいい? こんばんわ? 今日は良い勝負だった? いや、まだお互いに自己紹介すらしていない。彼女が私を見て誰だか分かるかも疑問だ。私の不安は募る一方だった。
が、すぐにその不安や疑問を忘れてしまうくらい驚くべき光景が私の目に飛び込んできた。
(――えっ? どうして?)
なんと反対方向から広瀬さんと思われる人物がこちらに向かって来ていたのだ。しかも走って。
その光景を見た瞬間、私は思わず笑ってしまった。自分でも不思議だった。それでもなぜか笑ってしまった、無意識に、突発的に笑ってしまったのだ。
(あなたも“何か”を感じたようね)
“何か”が何かは分からない。でもお互いにその何かを感じたのは間違いないようだ。そう思うと私は嬉しかった。試合と呼べないような試合、七割でしか投げれない苦痛、そんな球すら打てない生徒たち、監督の指示だったとはいえ、正直何も面白くない、メリットのない大会だった。でも彼女との勝負だけは違った。だから、今、この瞬間、あのソフトボール大会は無駄ではなかったと心から思う。
(私は……、私はあなたとソフトがしたい!)
二人の距離はどんどん近づく。しかし、
(――えっ! なぜ?)
広瀬さんらしき人物は急に止まると、引き返し始めた。
もう目と鼻の先に彼女がいる。ここまできて声をかけないなんて私には……無理。
「(今まで誰かと一緒にソフトボールをしたいなんて思ったこともないのに……、そんな想いにまでさせといて、なぜあなたは背を向けるの? あなたは何も感じてなかったっていうの?)ちょっと、あなた! 広瀬さん、広瀬るいさんでしょ?」
私は咄嗟に声をかけた。声はかけたが、もし、この気持ちが私の独りよがりだったらと思うと不安でしょうがない。
「――えっ?」
私の呼び掛けに広瀬さんは振り返ってくれた。彼女は驚いているのか、なんともいえない表情をしている。
「そうですけど……」
もしかしたら、彼女も私と同じように不安だったのかもしれない。そう考えると少し楽になった。私は広瀬さんに微笑んだ。
「よかったわ。バスからあなたの姿が見えたから」
「わっ、わたしも!」
「そう、あなたも……。それは良かったわ」
やっぱり彼女は不安だったようだ。その証拠に、こんなにもおどおどしている。
(あら?)
そのとき私は気付いた。昼間と印象が違うと思っていた理由、それは誰でもわかるような単純なことだった。
「広瀬さんって化粧しないと子供みたいね」
「は?」
さすがに今のはまずかったかしら? すっぴんの広瀬さんは目を細め睨むように私を見つめている。別に悪気はないのだけど……。私としてはどちらかというと誉め言葉だ。私は昔から大きかったせいか年相応に見られなかった。だから同年代の子たちと遊んでいても、一人だけ浮いていた。
「あら、ごめんなさい。気にさわったかしら? 悪気はないのなよ」
「べっ、べつに、気にしてないですっ!」
明らかに気にした様子の広瀬さん。言葉とは反対で顔がもろにそう言っている。
(素のときは感情が顔に出るタイプなのね)
試合の時は何を考えているか分からなかったのに、素のときこんな分かりやすい子だったのには驚きだ。
「そんなことより、わたしに何か用事があるんじゃないんですか? というか……、何でわたしの名前知ってるんですか?」
同い年なのに敬語というのは気になるが、それはさておき、私は彼女の名前を知っている。でもそれはあの資料があったからだ。私からするとたいした問題ではないが、彼女からしたらただの個人情報の漏洩。私はもっともらしく言葉を並べる。
「あら? 知ってたらおかしいかしら? だつて今日あんなに気持ち良くホームランを打たれた相手よ? 誰かに聞いててもおかしくないわ。あなたも私の名前くらいは知っているでしょう?」
咄嗟の話にしては上出来だ。でもホームランを打たれたことは正直根に持っている。渾身のストレートをあそこまで運ばれたのだから気にしない訳がない。
本気の戦いをした相手、彼女も私を知っているに違いない。そう思った、だけど広瀬さんの口から出た言葉は私の予想とはかけ離れたものだった。
「ごめん、知らない……」
「(知らないですって? 私はこんなに意識していたのに? 冗談でしょ? 冗談よね?)本当に?」
「はい」
しかし、広瀬さんは私の願いを簡単にぶち壊した。驚きと悔しさで言葉がつまる。
彼女からしたら私は印象にも残らないようなダメなピッチャーだったのだろうか……。
「私の投げる球って魅力ないのかしら……」
私ははうつむき考えるようにボソッと呟いた。すると広瀬さんは、
「そんなことないです! 凄かったです! 間違いなく今まで対戦した相手をの中で一番だったです! はい!」
必死にそう言っているが、その必死さが逆に言い訳のように聞こえる。おそらく彼女の中には更に優れたピッチャーがいるのだろう。それを今言っても仕方はないが……、私は目をつぶって軽く息を吐いた。
「まぁいいわ。私はC組の氷山つらら、ソフトボール部の一年よ」
「よろしく」と言って私は手を差し出した。広瀬さんはその手を取ってくれた。握った彼女の手は冷たかった。その冷たさが私の心を刺激する。
(今はまだ広瀬さんの中で一番のピッチャーじゃなくても、私は必ず越えてみせる。一番のピッチャーになってみせる)そう心に誓った。
そして、お互いに笑い合った――。
変に噛みついてしまったが、とりあえず広瀬さんとの接触には成功した。後はどう勧誘するかだけど……。
その時、私はふとあることを思い出した。広瀬さんの手を離すと、迷わずバッグからスマホを取りだした。
「今何時かしら?」
取り出したスマホの画面には幼い頃の私と若い両親の姿が写っている。これは残っている最後の家族写真。携帯を変えてもずっとデータを移行して残している大切な画像だ。
その画像の上にある時計を確認する。時計は二十時五十五分と表示されていた。
それを目にした途端、私は焦った。
「いけない! もう九時前だわ! 早く帰らないと!」
さっきバスの中で下宿先の家主さんに『今から帰ります』とメールをしていたのだ。本来ならとっくに帰宅している時間だ。
「えっ! うそっ! もうそんな時間?」
時間が分かると広瀬さんも焦てだした。見たいテレビでもあるのだろうか。そんなことよりも私は早く帰らないと、そう思い広瀬さんに声をかけようとしたが先に口を開いたのは広瀬さんだった。
「じゃあね氷山さんっ!」
「――えっ! ええ、さようなら」
なんという瞬発力、声と同時に走り出した広瀬さんはもう数メートル先を行っている。
(速い! というか帰る方向一緒なのね)
私も急いで広瀬さんを追いかける。制服に部活バッグを持ってはいるが、身長の分私の方が手足は長い。
私はすかさず広瀬さんに並ぶ。
「あなたもこっちが家なのね!」
「そう! わたし下宿してるんだっ!」
「あら、そうなの?」
確かに前に下宿先の家主さんから聞いた事がある。私の下宿先に同じ高校の子がいると。私はまさかとは思ったが、それは胸の内にしまう。
「……奇遇ね! 私もよ!」
「そうなんだ! なんか、面白いねっ!」
「そうね!」
確かに面白すぎる。まだソフトボール部に入る確証もないが、広瀬さんと同じ下宿先かもしれない。これで本当に同じ下宿先で、ソフト部に入ったのならいったいどんな刺激的な毎日が私を待っているのだろう。そう考えるだけで自然と笑みがこぼれる。
「じゃあわたし、こっちだからっ! またね!」
広瀬さんは私の下宿先へと続く路地へと入っていく。
(――やっぱり!)
広瀬さんは走る勢いのまま下宿先の玄関ドアを開けた。私はそれにすかさず飛び込んだ。
「あらぁ、おかえり! あんたたち一緒やったとねぇ! 今から帰るって連絡きたとに、遅かったけん探しに行こうと思っとったとよ」
「陽子ママ、変なこと言わないでよ。わたし一人だよ」
「るいちゃんこそ、何ば言いよっとね。後ろにちゃんとおるやかね」
そんなに私は存在感がなかったのだろうか。言葉を発していないにせよこんなにも近くにいるのに、彼女は本当に気付いていないようだ。
(この子はバカなの? 天然なの?)
「陽子ママ! 祓ってっ! お願いっ! お願いだから、たずげでぇ~!」
しかも泣き出す始末。やれやれと私は存在を知らせるために肩を掴んだ。
「――ひぃっ!」
すると広瀬さんは声にならないような声をあげ竦み上がった。明らかに私を人だとは思っていない。
「ちょっと広瀬さん? それは失礼すぎやしないかしら?」
「えっ?」
広瀬さんはゆっくりとこちらを振り向く。それはもう本当にゆっくりと。
「えっ? ……ええぇぇぇ~っ!」
私の顔を見た広瀬さんは驚いたようで、突然大声をだした。私はその声に驚いた。今日一番の衝撃。ホームランを打たれたのとは違う衝撃。そんな失礼極まりない彼女の様子に私は少しイラッとした。
「驚きすぎよ。私だって、これでも驚いているのよ。あなたがそんなに驚いたら私は素直に驚けないじゃない」
「だって……、だっでぇ~~~」
広瀬さんは安心したのか膝から崩れ落ちた。子供のように泣く姿に私は苛立ちを押さえる。
「もう……、ほらしっかりしなさいよ。立てる?」
「たでない……」
泣きじゃくる広瀬さんを陽子さんと一緒に抱えながら、私たちは一旦リビングへ向かった。
その後、広瀬さんが落ち着くのを待って、私たちは各々の部屋に戻った。
そんなこんなで、私と広瀬さんの変な共同生活が始まるのであった。
(あ、勧誘するの忘れてたわ……)
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。


甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。
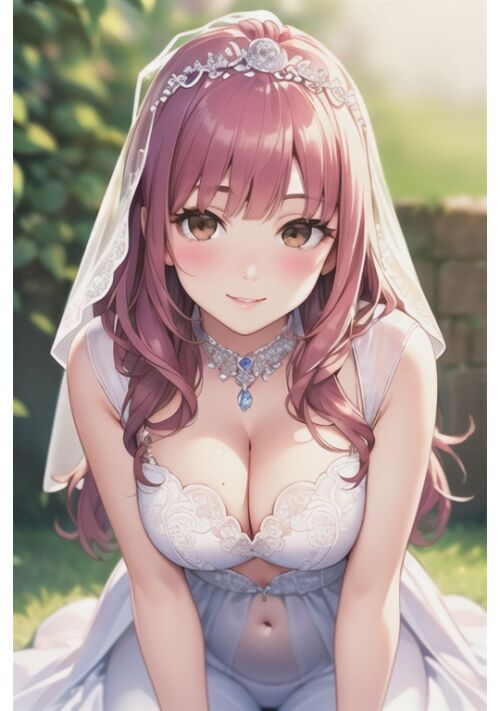
兄貴のお嫁さんは異世界のセクシー・エルフ! 巨乳の兄嫁にひと目惚れ!!
オズ研究所《横須賀ストーリー紅白へ》
ファンタジー
夏休み前、友朗は祖父の屋敷の留守を預かっていた。
その屋敷に兄貴と共に兄嫁が現れた。シェリーと言う名の巨乳の美少女エルフだった。
友朗はシェリーにひと目惚れしたが、もちろん兄嫁だ。好きだと告白する事は出来ない。
兄貴とシェリーが仲良くしているのを見ると友朗は嫉妬心が芽生えた。
そして兄貴が事故に遭い、両足を骨折し入院してしまった。
当分の間、友朗はセクシー・エルフのシェリーとふたりっきりで暮らすことになった。


お兄ちゃんはお兄ちゃんだけど、お兄ちゃんなのにお兄ちゃんじゃない!?
すずなり。
恋愛
幼いころ、母に施設に預けられた鈴(すず)。
お母さん「病気を治して迎えにくるから待ってて?」
その母は・・迎えにくることは無かった。
代わりに迎えに来た『父』と『兄』。
私の引き取り先は『本当の家』だった。
お父さん「鈴の家だよ?」
鈴「私・・一緒に暮らしていいんでしょうか・・。」
新しい家で始まる生活。
でも私は・・・お母さんの病気の遺伝子を受け継いでる・・・。
鈴「うぁ・・・・。」
兄「鈴!?」
倒れることが多くなっていく日々・・・。
そんな中でも『恋』は私の都合なんて考えてくれない。
『もう・・妹にみれない・・・。』
『お兄ちゃん・・・。』
「お前のこと、施設にいたころから好きだった・・・!」
「ーーーーっ!」
※本編には病名や治療法、薬などいろいろ出てきますが、全て想像の世界のお話です。現実世界とは一切関係ありません。
※コメントや感想などは受け付けることはできません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
※孤児、脱字などチェックはしてますが漏れもあります。ご容赦ください。
※表現不足なども重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけたら幸いです。(それはもう『へぇー・・』ぐらいに。)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















