21 / 31
相談
しおりを挟む
翌日、昼まで寝ていた俺たちをアリアンナさんが起こしに来てくれた。柔らかな寝具に包まれてぐっすり、最高の目覚めだ。
「さあ、あたたかいパン粥ですよ。召し上がれ」
「ありがとうございます」
湯気がふわりと立ち上がり、ほのかに甘い麦の香りが鼻をくすぐる。
器を受け取ったアシェルは当然のように俺の分も手に取り、自然な流れでスプーンを構えてくる。
「フィル、はい」
差し出されたパン粥をニコニコ顔で当たり前のようにぱくぱく食べる俺を見て、アシェルも楽しそうに笑う。
「あらまぁ、ほんと、仲良しなのね」
アリアンナさんが飲み物を準備しながらそう言って笑っていた。
食後にのんびりしていると、ラーシュが医者を連れて部屋にやって来た。
服を脱いで色んなところを検査したり、問診をしていく。
「ふむ……この子は完全に栄養失調ですな。かわいそうに、かなり酷い環境にいたようだ。しばらくは絶対安静にすることです」
痩せた身体には切り傷や、注射針の跡。青黒い痣が所々にあってとても痛々しい。
アシェルは視線を落として、居づらそうに小さく肩を縮めている。
(子供相手によくこんなこと出来る……)
逃げてくる時、ついでにあの場の全員を一発ずつくらい殴ってくれば良かった、と今更ながら思う。
大人たちのアシェルへの扱いを思い出して怒りが湧いてきた。
次に俺の番。
「なるほど、ハーピーの幼体ですか……。魔獣を診るのは初めてなんですがね、ふむ……羽が多少傷んでるようですが、目立った怪我はなさそうです。まぁ問題ないでしょう」
まじまじと羽や脚の他、喉の奥まで覗かれたり、目をグイっと開かれたり……色々されたけど、結果は健康そのもの。
ここ二日くらいゆっくり休めたし、墜落時のダメージも、もうほとんど感じない。
魔獣と言われるくらいだし、普通の人間よりもその辺は頑丈に出来てたりするんだろうか?
続いて魔力量の測定も行われた。
いかにもといった感じの水晶玉が差し出され、表面に両の翼をくっつけるように促される。
熱を感じたかと思うと、水晶が白く光を放った。これが俺の魔力、ということらしい。
次はアシェルの番だ。
不安そうな表情のアシェルは両手を出すのを躊躇している。
医者が優しく声をかけるが、アシェルは床を見たまま動かない。
(あ……そりゃ、怖いよな)
アシェルの過去の記憶を一瞬だけ覗き見てしまった俺には、なんとなく察しがついた。
アシェルが貴族の家にいた頃も、彼を取り巻く環境は最悪ではあったけど。魔力測定をしてからの扱いはモノ同然だ。
痛みと恐怖の中で、ずっと魔力を搾取される日々。
設定の魔王アシェルは、世界最強なんて言われていた。それほどにアシェルの魔力は特別なものなんだろう。
水晶玉に触れるというその行為だけで、魔力を、人生を、また奪われるんじゃないか。
そう思ってしまっているのかもしれない。
肩をこわばらせて、指先が白くなるほど手を握るアシェルを安心させようと、俺はそっと寄り添って羽根でふわふわと撫でてやる。
戸惑う様子の医者が、ラーシュに視線を投げた。
ラーシュは静かにアシェルと目線を合わせるようにしゃがみ込んだ。
「無理をさせるつもりはない。お前にもなにか事情があるんだろう。ただ、これはお前を守るために必要なことなんだと理解して欲しい。」
低く、穏やかな、落ち着いた声で続けた。
「魔力っていうのは俺たちの体の一部だ。上手く扱えば便利なものだが、危険もある。魔力量が少ないと、どんなに体を休めても元気にはなれないんだぞ?異常があれば、病気になったりもする」
ラーシュはそっと手を伸ばし、アシェルの肩にそっと触れた。
顔を上げたアシェルを安心させるように微笑む。
「どうしても駄目ならすぐ止める。少しだけ、頑張ってみないか?」
肩に置かれた手は、押さえつけるのではなく、支えるように軽く、確かな安心感を覚える大人の大きな手だ。
アシェルがおそるおそる俺の方を見る。
魔力云々については俺もさっぱりなので、しっかりと診断してもらうのが良いと思う。
元は周囲を燃やし尽くす程のほどの暴走をする設定だったし、ラーシュの話した内容を聞けば、魔王化を阻止したとはいえ、体に悪い影響が無いとも限らないのかもしれない。
ここまで世話になったラーシュは、信用出来る、と思っている。アシェルに危害が及ぶことはないだろう。
俺は励ます様に大きく一つ頷いた。
アシェルの握りしめていた指先がかすかに緩んだ。
まだ体はこわばっているが、少しずつ前に体が傾いていく。
ラーシュが俺に離れるよう手で制してきた。
アシェルは深く息をつくと、意を決したように水晶玉の前へそっと両手を伸ばした。
触れた瞬間、水晶玉の内部で爆ぜるように黒い閃光が渦を巻き、周囲にあふれ出す。
その場にいた俺たちは息をのみ、身じろぎせずただ静かにたたずむアシェルを見つめていた。
――――
書斎の窓から差す光が、机に並べられた書簡を静かに照らしていた。
この屋敷の主である、カール・マスラーク伯爵が眉を寄せながらその内容を確認している。
「この診断結果は……すさまじいね」
「医者の先生も驚いていた。身体はボロボロなのに、魔力が異様に濃くて多い。子供どころか、常人の器に収まるもんじゃねぇって」
報告に来たラーシュは続ける。
「栄養失調と慢性的な暴行で、本来なら死んでしまっていてもおかしくない状態だったのを、あふれる魔力で無意識に体の負担を補っていたんだろうって言ってたぜ。今日まで生きてこられたのは奇跡だってな」
話を聞いて、カール伯爵は眉を寄せた。
幼い頃からの友人である彼は、本気で嫌悪感を持った時に、決まってこの顔になる事をラーシュは知っていた。
「子供を私利私欲で傷つける不届き者がいるとは……」
「まだ本人から詳しい話は聞けていない。アルソレイユの貴族の生まれらしいが、自分がどこから来たのかよく覚えていないみたいだったぜ」
森で出会ったときにアシェルから聞いた内容だった。
帝国のマスラーク領は、人類未踏の広大な魔の森という不可侵地域を挟んで、アルソレイユ王国と隣接している。
断片的な情報からだが、おそらくは王国で酷い扱いを受け、魔の森を抜けて帝国領まで逃げてきたのだろうと予想された。
アシェルの様子から、せめてもう少し体の回復を待ってから、改めて話を聞いた方が良いだろうという事で2人は合意した。
「魔力量もそうだが、性質も随分珍しいようだね。黒い光か」
「先生が言うには複数の属性に適性があるらしい。難しいが、上手く鍛えれば色んな属性の魔法が扱えるようになるかもしれないってな」
魔力には適性があり、それは色や形で、ある程度診断することが出来る。
実際に魔術が使えるようになるかは、本人が内包する魔力の多さで判断がされる。
アシェルの場合、元の適性属性が判別できないほど様々な魔力が混ざり合い、さらに天賦の魔力量を誇る。
まさに逸材と言っていい。
「今のうちに正しい魔力の制御方法を訓練しないと、子供の体には負担が大きすぎるそうだ。今はまだ体の回復にエネルギーを割いてる状態なんだろうが、元気になったら行き場をなくした魔力が暴発して、事故が起きるかもしれねぇってよ」
カールは深く椅子に背を預ける。
「しかしな、うちがアルソレイユ王国の貴族を匿うのは筋が悪い。ましてこれほどの才能ある子だ。よくよく揉め事になるぞ」
「分かってる。だが……」
ラーシュは森で2人と出会ったときの様子、往診の際に見たアシェルの体を思い返し、硬く拳を握る。
「俺には見過ごすなんて出来ん。拾ってきたのは俺だ、責任は取る。なんとか……頼めないか」
神妙に目線を下げるラーシュ。
沈黙するその場に、ふっと短く笑う声が漏れた。
「そう言うと思ったよ」
真剣な様子で自分に頼みごとをする旧友に微笑むカールは、手元の書簡を数枚めくり、机に置いた。
「帰還したお前から報告を聞いてすぐ、調べさせた。王国の貴族台帳に“アシェル”という名の子はいない。過去に遡って年頃の子供はすべて洗い出したが、どれも該当無しだ」
「つまり?」
「身寄りのない子供という判断で良いだろう。そもそもあんな扱いを受けている子だ、保護者が親権を主張したとして、まともな効力を発揮するとは思えない。万が一、何かあっても面倒事はこちらに任せてくれれば良い」
カールはいたずらっ子のように笑いかける。
「お前の家で育ててやれ。子がいないのを奥方も気にしていただろう?必要なものがあれば遠慮なく頼って欲しい。私は、お前たちが良い養い親になると信じているよ」
ラーシュは少し息を呑んだ。
「……ありがとう。悪いな」
「恩の1つくらい返させてくれ。孤児だったお前が父に拾われてから、領地のため今日まで尽力してくれた事への、ほんの感謝だ。お前が居なきゃ領地経営なんてやってられないと投げ出すところだったんだからな」
「ははは、ガキの頃の話だろ?また今度、酒でも飲みながらしようや」
そう言って表情を崩したラーシュ。大柄な体に似合わず、目の奥がじんと熱くなっていた。
問題はまだあった。
「さて、こっちはハーピーの子か……」
「フィルだな」
書類を一枚取り、視線を落とす。
カールは深く息を吐き、どうしたものかと顎に手を当てた。
「魔獣だというだけで、民衆は騒ぐだろう。まして人型魔獣が人間の子供に懐くなんて前代未聞だ」
ラーシュも頷く。
「人間の言葉が通じているみたいでな、会話はかわせないが、意思疎通に問題はない。どういうわけかアシェルに懐いてるみたいで、ただの魔獣として扱うわけにもいかない」
「見た目は鳥の雛ようなのだろう?生まれた時にアシェルを見て親だと思ってる、というのは考えられないのかい?」
「俺もそう思ってな。魔獣に詳しい団員に聞いてみたが、ハーピーは見た目こそ鳥と人間を合わせたような魔獣だが、生態が鳥と近いのかまでは判断できないそうだ。ただ、フィルという名前はアシェルが名づけたんだと」
「今は幼体だから良いものの、相手は魔獣だ。成長して制御できない存在にならないとも限らない。今のうちに引き離して逃がすか、駆除の選択肢もあるだろうか」
ラーシュは即座に首を振った。
「無理だ。あいつは身を挺してアシェルを守ろうとしてた。あれは魔獣の本能じゃなく、明確な意思を持ってないと出来ない行動だ。理由なく引き離せるとは思えない。アシェルも今はフィルにずっとくっ付いてる。無理に奴をどうこうして精神的な負荷をかけたくはない」
ふむ、と息をついてカールはゆっくりと立ち上がった。
「なら、まずは二人に話をしてみた方が良い。意思の疎通は出来るのだろう?ある程度知性があるのなら、状況を伝えて、これからどうするか本人たちの意思を確認してみることだ」
「そう、だよな……わかった」
ラーシュは、ゆっくりと頷いた。
「さあ、あたたかいパン粥ですよ。召し上がれ」
「ありがとうございます」
湯気がふわりと立ち上がり、ほのかに甘い麦の香りが鼻をくすぐる。
器を受け取ったアシェルは当然のように俺の分も手に取り、自然な流れでスプーンを構えてくる。
「フィル、はい」
差し出されたパン粥をニコニコ顔で当たり前のようにぱくぱく食べる俺を見て、アシェルも楽しそうに笑う。
「あらまぁ、ほんと、仲良しなのね」
アリアンナさんが飲み物を準備しながらそう言って笑っていた。
食後にのんびりしていると、ラーシュが医者を連れて部屋にやって来た。
服を脱いで色んなところを検査したり、問診をしていく。
「ふむ……この子は完全に栄養失調ですな。かわいそうに、かなり酷い環境にいたようだ。しばらくは絶対安静にすることです」
痩せた身体には切り傷や、注射針の跡。青黒い痣が所々にあってとても痛々しい。
アシェルは視線を落として、居づらそうに小さく肩を縮めている。
(子供相手によくこんなこと出来る……)
逃げてくる時、ついでにあの場の全員を一発ずつくらい殴ってくれば良かった、と今更ながら思う。
大人たちのアシェルへの扱いを思い出して怒りが湧いてきた。
次に俺の番。
「なるほど、ハーピーの幼体ですか……。魔獣を診るのは初めてなんですがね、ふむ……羽が多少傷んでるようですが、目立った怪我はなさそうです。まぁ問題ないでしょう」
まじまじと羽や脚の他、喉の奥まで覗かれたり、目をグイっと開かれたり……色々されたけど、結果は健康そのもの。
ここ二日くらいゆっくり休めたし、墜落時のダメージも、もうほとんど感じない。
魔獣と言われるくらいだし、普通の人間よりもその辺は頑丈に出来てたりするんだろうか?
続いて魔力量の測定も行われた。
いかにもといった感じの水晶玉が差し出され、表面に両の翼をくっつけるように促される。
熱を感じたかと思うと、水晶が白く光を放った。これが俺の魔力、ということらしい。
次はアシェルの番だ。
不安そうな表情のアシェルは両手を出すのを躊躇している。
医者が優しく声をかけるが、アシェルは床を見たまま動かない。
(あ……そりゃ、怖いよな)
アシェルの過去の記憶を一瞬だけ覗き見てしまった俺には、なんとなく察しがついた。
アシェルが貴族の家にいた頃も、彼を取り巻く環境は最悪ではあったけど。魔力測定をしてからの扱いはモノ同然だ。
痛みと恐怖の中で、ずっと魔力を搾取される日々。
設定の魔王アシェルは、世界最強なんて言われていた。それほどにアシェルの魔力は特別なものなんだろう。
水晶玉に触れるというその行為だけで、魔力を、人生を、また奪われるんじゃないか。
そう思ってしまっているのかもしれない。
肩をこわばらせて、指先が白くなるほど手を握るアシェルを安心させようと、俺はそっと寄り添って羽根でふわふわと撫でてやる。
戸惑う様子の医者が、ラーシュに視線を投げた。
ラーシュは静かにアシェルと目線を合わせるようにしゃがみ込んだ。
「無理をさせるつもりはない。お前にもなにか事情があるんだろう。ただ、これはお前を守るために必要なことなんだと理解して欲しい。」
低く、穏やかな、落ち着いた声で続けた。
「魔力っていうのは俺たちの体の一部だ。上手く扱えば便利なものだが、危険もある。魔力量が少ないと、どんなに体を休めても元気にはなれないんだぞ?異常があれば、病気になったりもする」
ラーシュはそっと手を伸ばし、アシェルの肩にそっと触れた。
顔を上げたアシェルを安心させるように微笑む。
「どうしても駄目ならすぐ止める。少しだけ、頑張ってみないか?」
肩に置かれた手は、押さえつけるのではなく、支えるように軽く、確かな安心感を覚える大人の大きな手だ。
アシェルがおそるおそる俺の方を見る。
魔力云々については俺もさっぱりなので、しっかりと診断してもらうのが良いと思う。
元は周囲を燃やし尽くす程のほどの暴走をする設定だったし、ラーシュの話した内容を聞けば、魔王化を阻止したとはいえ、体に悪い影響が無いとも限らないのかもしれない。
ここまで世話になったラーシュは、信用出来る、と思っている。アシェルに危害が及ぶことはないだろう。
俺は励ます様に大きく一つ頷いた。
アシェルの握りしめていた指先がかすかに緩んだ。
まだ体はこわばっているが、少しずつ前に体が傾いていく。
ラーシュが俺に離れるよう手で制してきた。
アシェルは深く息をつくと、意を決したように水晶玉の前へそっと両手を伸ばした。
触れた瞬間、水晶玉の内部で爆ぜるように黒い閃光が渦を巻き、周囲にあふれ出す。
その場にいた俺たちは息をのみ、身じろぎせずただ静かにたたずむアシェルを見つめていた。
――――
書斎の窓から差す光が、机に並べられた書簡を静かに照らしていた。
この屋敷の主である、カール・マスラーク伯爵が眉を寄せながらその内容を確認している。
「この診断結果は……すさまじいね」
「医者の先生も驚いていた。身体はボロボロなのに、魔力が異様に濃くて多い。子供どころか、常人の器に収まるもんじゃねぇって」
報告に来たラーシュは続ける。
「栄養失調と慢性的な暴行で、本来なら死んでしまっていてもおかしくない状態だったのを、あふれる魔力で無意識に体の負担を補っていたんだろうって言ってたぜ。今日まで生きてこられたのは奇跡だってな」
話を聞いて、カール伯爵は眉を寄せた。
幼い頃からの友人である彼は、本気で嫌悪感を持った時に、決まってこの顔になる事をラーシュは知っていた。
「子供を私利私欲で傷つける不届き者がいるとは……」
「まだ本人から詳しい話は聞けていない。アルソレイユの貴族の生まれらしいが、自分がどこから来たのかよく覚えていないみたいだったぜ」
森で出会ったときにアシェルから聞いた内容だった。
帝国のマスラーク領は、人類未踏の広大な魔の森という不可侵地域を挟んで、アルソレイユ王国と隣接している。
断片的な情報からだが、おそらくは王国で酷い扱いを受け、魔の森を抜けて帝国領まで逃げてきたのだろうと予想された。
アシェルの様子から、せめてもう少し体の回復を待ってから、改めて話を聞いた方が良いだろうという事で2人は合意した。
「魔力量もそうだが、性質も随分珍しいようだね。黒い光か」
「先生が言うには複数の属性に適性があるらしい。難しいが、上手く鍛えれば色んな属性の魔法が扱えるようになるかもしれないってな」
魔力には適性があり、それは色や形で、ある程度診断することが出来る。
実際に魔術が使えるようになるかは、本人が内包する魔力の多さで判断がされる。
アシェルの場合、元の適性属性が判別できないほど様々な魔力が混ざり合い、さらに天賦の魔力量を誇る。
まさに逸材と言っていい。
「今のうちに正しい魔力の制御方法を訓練しないと、子供の体には負担が大きすぎるそうだ。今はまだ体の回復にエネルギーを割いてる状態なんだろうが、元気になったら行き場をなくした魔力が暴発して、事故が起きるかもしれねぇってよ」
カールは深く椅子に背を預ける。
「しかしな、うちがアルソレイユ王国の貴族を匿うのは筋が悪い。ましてこれほどの才能ある子だ。よくよく揉め事になるぞ」
「分かってる。だが……」
ラーシュは森で2人と出会ったときの様子、往診の際に見たアシェルの体を思い返し、硬く拳を握る。
「俺には見過ごすなんて出来ん。拾ってきたのは俺だ、責任は取る。なんとか……頼めないか」
神妙に目線を下げるラーシュ。
沈黙するその場に、ふっと短く笑う声が漏れた。
「そう言うと思ったよ」
真剣な様子で自分に頼みごとをする旧友に微笑むカールは、手元の書簡を数枚めくり、机に置いた。
「帰還したお前から報告を聞いてすぐ、調べさせた。王国の貴族台帳に“アシェル”という名の子はいない。過去に遡って年頃の子供はすべて洗い出したが、どれも該当無しだ」
「つまり?」
「身寄りのない子供という判断で良いだろう。そもそもあんな扱いを受けている子だ、保護者が親権を主張したとして、まともな効力を発揮するとは思えない。万が一、何かあっても面倒事はこちらに任せてくれれば良い」
カールはいたずらっ子のように笑いかける。
「お前の家で育ててやれ。子がいないのを奥方も気にしていただろう?必要なものがあれば遠慮なく頼って欲しい。私は、お前たちが良い養い親になると信じているよ」
ラーシュは少し息を呑んだ。
「……ありがとう。悪いな」
「恩の1つくらい返させてくれ。孤児だったお前が父に拾われてから、領地のため今日まで尽力してくれた事への、ほんの感謝だ。お前が居なきゃ領地経営なんてやってられないと投げ出すところだったんだからな」
「ははは、ガキの頃の話だろ?また今度、酒でも飲みながらしようや」
そう言って表情を崩したラーシュ。大柄な体に似合わず、目の奥がじんと熱くなっていた。
問題はまだあった。
「さて、こっちはハーピーの子か……」
「フィルだな」
書類を一枚取り、視線を落とす。
カールは深く息を吐き、どうしたものかと顎に手を当てた。
「魔獣だというだけで、民衆は騒ぐだろう。まして人型魔獣が人間の子供に懐くなんて前代未聞だ」
ラーシュも頷く。
「人間の言葉が通じているみたいでな、会話はかわせないが、意思疎通に問題はない。どういうわけかアシェルに懐いてるみたいで、ただの魔獣として扱うわけにもいかない」
「見た目は鳥の雛ようなのだろう?生まれた時にアシェルを見て親だと思ってる、というのは考えられないのかい?」
「俺もそう思ってな。魔獣に詳しい団員に聞いてみたが、ハーピーは見た目こそ鳥と人間を合わせたような魔獣だが、生態が鳥と近いのかまでは判断できないそうだ。ただ、フィルという名前はアシェルが名づけたんだと」
「今は幼体だから良いものの、相手は魔獣だ。成長して制御できない存在にならないとも限らない。今のうちに引き離して逃がすか、駆除の選択肢もあるだろうか」
ラーシュは即座に首を振った。
「無理だ。あいつは身を挺してアシェルを守ろうとしてた。あれは魔獣の本能じゃなく、明確な意思を持ってないと出来ない行動だ。理由なく引き離せるとは思えない。アシェルも今はフィルにずっとくっ付いてる。無理に奴をどうこうして精神的な負荷をかけたくはない」
ふむ、と息をついてカールはゆっくりと立ち上がった。
「なら、まずは二人に話をしてみた方が良い。意思の疎通は出来るのだろう?ある程度知性があるのなら、状況を伝えて、これからどうするか本人たちの意思を確認してみることだ」
「そう、だよな……わかった」
ラーシュは、ゆっくりと頷いた。
288
あなたにおすすめの小説

人族は一人で生きられないらしい――獣人公爵に拾われ、溺愛されて家族になりました
よっちゃん
BL
人族がほとんど存在しない世界に、
前世の記憶を持ったまま転生した少年・レオン。
獣人が支配する貴族社会。
魔力こそが価値とされ、
「弱い人族」は守られるべき存在として扱われる世界で、
レオンは常識の違いに戸惑いながらも必死に生きようとする。
そんな彼を拾ったのは、
辺境を治める獣人公爵アルト。
寡黙で冷静、しかし一度守ると決めたものは決して手放さない男だった。
溺愛され、守られ、育てられる日々。
だが、レオンはただ守られるだけの存在で終わることを選ばない。
学院での出会い。
貴族社会に潜む差別と陰謀。
そして「番」という、深く重い絆。
レオンは学び、考え、
自分にしかできない魔法理論を武器に、
少しずつ“並び立つ覚悟”を身につけていく。
獣人と人族。
価値観も、立場も、すべてが違う二人が、
それでも選び合い、家族になるまでの物語。
溺愛×成長×異世界BL。
読後に残るのは、
「ここに居場所があっていい」と思える、あたたかな幸福。

ハッピーライフのために地味で根暗な僕がチャラ男会計になるために
ミカン
BL
地味で根暗な北斗が上手く生きていくために王道学園でチャラ男会計になる話
※主人公へのいじめ描写ありのため苦手な方は閲覧ご注意下さい。

僕、天使に転生したようです!
神代天音
BL
トラックに轢かれそうだった猫……ではなく鳥を助けたら、転生をしていたアンジュ。新しい家族は最低で、世話は最低限。そんなある日、自分が売られることを知って……。
天使のような羽を持って生まれてしまったアンジュが、周りのみんなに愛されるお話です。

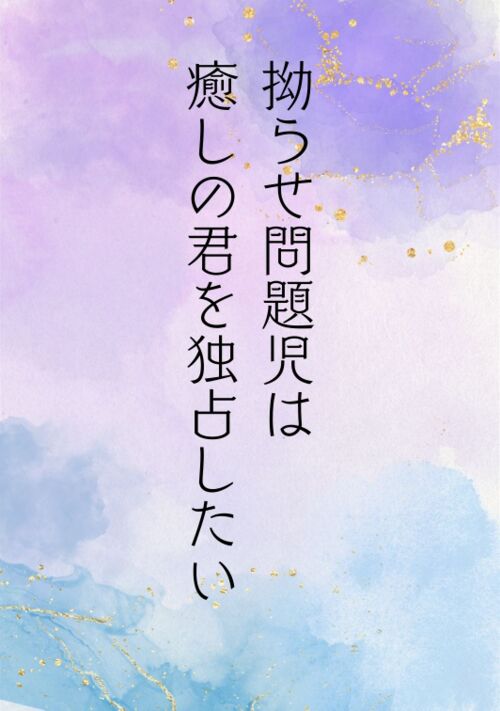
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

異世界転移をした俺は文通相手の家にお世話になることになりました
陽花紫
BL
異世界転移をしたハルトには、週に一度の楽しみがあった。
それは、文通であった。ハルトの身を受け入れてくれた老人ハンスが、文字の練習のためにと勧めたのだ。
文通相手は、年上のセラ。
手紙の上では”ハル”と名乗り、多くのやりとりを重ねていた。
ある日、ハンスが亡くなってしまう。見知らぬ世界で一人となったハルトの唯一の心の支えは、セラだけであった。
シリアスほのぼの、最終的にはハッピーエンドになる予定です。
ハルトとセラ、視点が交互に変わって話が進んでいきます。
小説家になろうにも掲載中です。


異世界転生してBL漫画描いてたら幼馴染に迫られた
はちも
BL
異世界転生した元腐男子の伯爵家三男。
病弱設定をうまく使って、半引きこもり生活を満喫中。
趣味と実益を兼ねて、こっそりBL漫画を描いていたら──
なぜか誠実一直線な爽やか騎士の幼馴染にバレた!?
「……おまえ、俺にこうされたいのか?」
そんなわけあるかーーーっ!!
描く側だったはずの自分が、
誤解と好意と立場の違いにじわじわ追い詰められていく。
引きこもり腐男子貴族のオタ活ライフは、
王子と騎士に目をつけられ、
いつの間にか“逃げ場のない現実”へ発展中!?
誠実一直線騎士 × 流され系オタク
異世界・身分差・勘違いから始まる
リアル発展型BLコメディ。
*基本的に水・土の20時更新予定です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















