34 / 115
34話 いろいろ珍しいものが手に入ったぞ
しおりを挟む
ヌーの隊商が帰ったあと、分けてもらったモノの品評会が始まった。
銅の斧、ヒエ酒、塩塊、染料(苔)だ。
少し無理をして色々交換したが、渡したのはここで生産できるものばかりだ。
なんとでもなるだろう。
女子供が喜ぶようなものまで手が回らなかったと思っていたが、意外と皆が興味津々らしい。
繊維の生産をするコナンが少量の染料をすりつぶし、水につけると黒っぽい色が出た。
これに繊維をつけると緑色に染まるというのだから不思議な話だ。
エルフの染料は樹皮を用いるもので茶色系統の色ばかり、これとは趣が異なる。
「これは……色々と試していくしかないな」
「別の色に染めた繊維を混ぜてもいいかもしれませんね」
コナンとフローラが熱心に繊維や糸を染料に浸けている。
この2人は理屈っぽくて試行錯誤が好きだ。
意外と仲がいいのである。
(まあ、本人同士がよければいいんだけど、長命種と短命種は難しいよなあ)
長命種は繁殖力の強い短命種を交配のために妾にすることはあっても、妻にすることは稀だ。
できればコナンやバーンにも嫁を迎えてやりたいが……ヌー隊商にそのあたりも頼んでみてもいいかもしれない。
コナンの隣ではウシカの子供たちが染料を手につけ、乾燥している窯入れ前の陶器にペタペタと落書きをしている。
「うむうむ、うまいぞ。これは虫だな、兄ウシカは絵心がある。弟ウシカはよく見るのだ、アシュリンには尻尾はないぞ」
「あはは、ひどいな! これはこうして――ゆ、弓にすればいい」
スケサンとアシュリンまで一緒になって遊んでいるが、あの皿を焼いたらどんな感じになるのだろう?
想像もつかない。
銅の斧頭はウシカとケハヤが柄をとりつけていた。
斧頭の穴に堅い木を突っ込み、逆からくさびを入れる。
「おっ、柄をつけてくれたのか?」
「ああ、我らの故郷は銅の道具はあまり使わぬゆえ珍しい、興味深い」
銅というやつは産地によって強度がかなり違う(※注)。
黄金に近い色の銅は磨かないと緑青が湧いて青っぽくなるから青銅と呼ばれる。
青銅が使えればよいのだが、この森の銅はかなり赤い。
つまり、赤銅だ。
赤銅はさほど強度がある金属ではないが、それは鍛鉄や青銅と比べればの話である。
十分に刃物になるし、武器としても使えるだろう。
「でも日常使いには少しもったいないよな?」
「ああ、貴重なものだからな。客を迎える礼装や戦のとき使うのがいいだろう」
ウシカたちの里では銅器は実用品ではなく祭具であったらしい。
光輝く金属を神聖視する文化はわりとある。
「うん、余裕があれば銅の鼎(足つきの鍋)も発注してみるか。便利だし」
かまどでは女ウシカが煮物を作り、モリーとピーターがお手伝いで塩塊を削っている。
慎ましく気が利く女ウシカは酒が来たことで宴になると思ったのだろう。
せっせと火を起こし、割った獣骨を煮込んでいる。
獣骨を煮込んだ汁に塩は抜群に合う。
干し魚やイモもあるし、今晩はごちそうである。
「女ウシカ、助かるよ。モリーとピーターも精が出るな」
「へへ、僕は食べ物を煮炊きするのが好きなんだよね」
ピーターがはにかみながら返事をした。
彼はまだまだ子供で体も小さいが、積極的に皆の手伝いをする働き者だ。
叔父のパーシーが家畜を連れてきたら一緒に世話をさせるのがよいかもしれない。
「お塩がたくさんあると色々できますよね。私たちの家族は肉を塩漬けにしてましたよ」
「姉ちゃんは煮物に幼虫が入るのが嫌だからね」
どうやらヤギ人には昆虫食の習慣がないらしい。
モリーとフローラは露骨に嫌がるが、ここに来たときに幼かったピーターは慣れたようだ。
こうして姉をからかう程度には虫も食べる。
「痛てっ! やめろよ!」
「アンタがケンカ売ってきたんでしょ! いい加減オネショやめなさいよっ!」
この姉弟は本当に仲がいい。
モリーは最近、角も伸びてきており徐々に大人になってきたようだ。
(モリーやフローラにもよい婿を探してやらねばなあ)
ヤギ人は大抵の場合、婚姻は家長が決めていたらしい。
だが、モリーたちの一族は壊滅しているし、この辺は臨機応変にやるしかないだろう。
(パーシーとかいうのは頼りないしな……本人同士が望むならまだしも、ちょっとオススメはできんな)
いつの間にか、ヤギ人の娘らにも情が移ってしまった。
(今のサイズじゃちょいと難しいが、大きくなってから俺が妾にしたら――アシュリンが嫌がるだろうな。やめとこう)
俺だって男だ。
女をはべらすような生活をしてみたいが……アシュリンはベルが寄ってきただけで目を三角にするのだ。
俺には妾をむかえて家庭の平和を保つ自信がない。
ぼんやりとしているうちに、いつの間にか日が暮れ食事のために皆が集まってきた。
今日は仕事にならなかったが、こんな日があってもいいだろう。
塩気の利いた食事に皆が舌鼓を打っている。
「塩か……魚を塩漬けにしたものを熟成させると我らが魚醤と呼ぶ調味液になる」
「生魚をか? どのくらい熟成させるんだ?」
ウシカによると、リザードマンは魚醤と呼ぶ調味液を作るらしい。
だが、1年以上塩漬けにした生魚から出た汁とは……挑戦に勇気が必要だ。
いつものようにモリーたちヤギ人が聖霊へのお供えとして、食事を少し取り分ける。
それをモリーがスケサンに供えると、スケサンは「いつもすまんな」と礼をいい、ウシカの子供らに与える。
よく分からないが、いつの間にか始まった光景だ。
誰も嫌がってないし、食事をしないスケサンも少し楽しそうだ。
皆で食事を終えるとお楽しみの酒である。
「ヒエ酒は飲んだことがない。楽しみだな」
ちいさな甕の蓋を外すと、独特の香りの濁った液体がなみなみと入っている。
よく見ると、液体にはぷちぷちと小さな泡がたっているようだ。
「では、早速」
俺は小さなお椀を甕に浸し、直接酒をくむ。
森に来てはじめての酒だ。
少し緊張しながら口に含むと、なんともいえない酸味と酒精の熱さを舌に感じた。
「たしかに酒だ。皆も飲んでくれ」
俺が促すと、皆がわらわらと甕に群がる。
酒は貴重品、滅多にないごちそうなのだ。
「……悪くないが、酸味が強いか?」
「噛み酒かも? 酒精は弱いな」
コナンとバーンが酒を飲みながらうんちくを垂れている。
面倒くさいやつらだ。
ウシカとケハヤは無言で飲んでいるが、これはリザードマンの嗜みらしい。
酒を飲んで言葉を放つと争いの種を撒くから無言で飲むのだそうだ。
理解できるし立派なことだとは思うが……少し素っ気ない気もする。
「さ、酒か、うちでも作れないかな?」
「ん? エルフは酒を作ってたのか?」
アシュリンが漏らした一言は聞き逃せないものがある。
酒作りが可能ならわざわざ買う必要もないし、量によっては売り物になりそうだ。
「うーん、エルフの里では作ってたぞ。で、でも長老たちの仕事で私たちはよく分からないんだ」
「どんな酒なんだ?」
アシュリンがいうにはハチミツを使った酒とブドウの実を使った酒を作っていたそうだ。
そういえば、かつてエルフの貢ぎ物に酒があったような気もする。
「作るとこは見たけど……ハチミツと祈りを捧げた清水を混ぜて、かまどの側に置いておくんだ。だ、だけどお祈りの言葉が分からないし……」
「ふうん、たしかにそれだけで酒ができるなら祈りが大切なんだろうな」
酒作りは神秘の技とされる。
祈りが秘技だとしても不思議はない。
「ブドウの実はどうだ?」
「うーん、ブドウの実をたくさん集めなきゃいけないから、これは滅多につくらないな。ぶ、ブドウをそのまま潰して甕に入れるんだけど、これもそれだけしか分からない」
いきなり酒が作れるようになる――そんなに甘い話はないということだろう。
みんなで小さな甕の酒を舐めると、すぐに空になってしまった。
モリーやフローラは耳を真っ赤にしているが、他はケロッとしている。
弱い酒だし、酔っぱらうほど量がないのだ。
「皆がこれだけ酒が好きなら作れるようになるといいな」
「う、うん。祈りの言葉をしっかり思い出せればいいんだけど……」
酒造はワイルドエルフの秘事だったらしく、族長の一族だったアシュリンしか見た記憶がないらしい。
コナンやバーンはまったく分からないのだそうだ。
「ふむ、リザードマンの嗜みではないが酒は理性を弱める働きがある。ワイルドエルフは皆が勝手に作りはじめ、酒浸りになるのを恐れたのだろう」
「なるほど。たしかに今日はなにも手につかなかった。こんな日ばかりでは困ってしまうな」
スケサンの言葉には皆が笑ってしまった。
たしかに酒は理性を弱めるかもしれないが、こうして楽しむぶんには構わないだろう。
「ヤギ人はお葬式のとき、近親者は酩酊するまでお酒を飲むんです。死者の言葉が聞こえるから」
フローラがポツリと呟いた。
「でも、お酒を飲んでも私には声が聞こえません。家族は生きてる」
「そうか、そうだな」
酒は日常の楽しみであり、身を持ち崩す毒であり、大切な祭具なのだ。
なんとかして酒作りをはじめたい。
俺は密かに決意をした。
■■■■
銅器
そのまま、銅でできた道具。
銅は柔らかくて武具などには使い物にならないという人もいるが、そんなことはない。
人類史において銅器を用いた時代を銅器時代といい、ちゃんと実用品として使われていたのだ。
アルプスで発見された青銅器時代以前の遺体(アイスマン)は純度の高い銅の斧と石のナイフを所持していたことでも知られている。
(※注)もちろん、青銅とは銅と錫の合金のこと。
しかし、冶金の知識がないベルクは銅の産地の問題だと思い込んでいるらしい。
どこかの銅鉱山で不純物量の錫やアンチモンなどが含まれていた可能性も捨てきれないが、冶金は秘中の秘であるから嘘を教えられた可能性は大いにある。
銅の斧、ヒエ酒、塩塊、染料(苔)だ。
少し無理をして色々交換したが、渡したのはここで生産できるものばかりだ。
なんとでもなるだろう。
女子供が喜ぶようなものまで手が回らなかったと思っていたが、意外と皆が興味津々らしい。
繊維の生産をするコナンが少量の染料をすりつぶし、水につけると黒っぽい色が出た。
これに繊維をつけると緑色に染まるというのだから不思議な話だ。
エルフの染料は樹皮を用いるもので茶色系統の色ばかり、これとは趣が異なる。
「これは……色々と試していくしかないな」
「別の色に染めた繊維を混ぜてもいいかもしれませんね」
コナンとフローラが熱心に繊維や糸を染料に浸けている。
この2人は理屈っぽくて試行錯誤が好きだ。
意外と仲がいいのである。
(まあ、本人同士がよければいいんだけど、長命種と短命種は難しいよなあ)
長命種は繁殖力の強い短命種を交配のために妾にすることはあっても、妻にすることは稀だ。
できればコナンやバーンにも嫁を迎えてやりたいが……ヌー隊商にそのあたりも頼んでみてもいいかもしれない。
コナンの隣ではウシカの子供たちが染料を手につけ、乾燥している窯入れ前の陶器にペタペタと落書きをしている。
「うむうむ、うまいぞ。これは虫だな、兄ウシカは絵心がある。弟ウシカはよく見るのだ、アシュリンには尻尾はないぞ」
「あはは、ひどいな! これはこうして――ゆ、弓にすればいい」
スケサンとアシュリンまで一緒になって遊んでいるが、あの皿を焼いたらどんな感じになるのだろう?
想像もつかない。
銅の斧頭はウシカとケハヤが柄をとりつけていた。
斧頭の穴に堅い木を突っ込み、逆からくさびを入れる。
「おっ、柄をつけてくれたのか?」
「ああ、我らの故郷は銅の道具はあまり使わぬゆえ珍しい、興味深い」
銅というやつは産地によって強度がかなり違う(※注)。
黄金に近い色の銅は磨かないと緑青が湧いて青っぽくなるから青銅と呼ばれる。
青銅が使えればよいのだが、この森の銅はかなり赤い。
つまり、赤銅だ。
赤銅はさほど強度がある金属ではないが、それは鍛鉄や青銅と比べればの話である。
十分に刃物になるし、武器としても使えるだろう。
「でも日常使いには少しもったいないよな?」
「ああ、貴重なものだからな。客を迎える礼装や戦のとき使うのがいいだろう」
ウシカたちの里では銅器は実用品ではなく祭具であったらしい。
光輝く金属を神聖視する文化はわりとある。
「うん、余裕があれば銅の鼎(足つきの鍋)も発注してみるか。便利だし」
かまどでは女ウシカが煮物を作り、モリーとピーターがお手伝いで塩塊を削っている。
慎ましく気が利く女ウシカは酒が来たことで宴になると思ったのだろう。
せっせと火を起こし、割った獣骨を煮込んでいる。
獣骨を煮込んだ汁に塩は抜群に合う。
干し魚やイモもあるし、今晩はごちそうである。
「女ウシカ、助かるよ。モリーとピーターも精が出るな」
「へへ、僕は食べ物を煮炊きするのが好きなんだよね」
ピーターがはにかみながら返事をした。
彼はまだまだ子供で体も小さいが、積極的に皆の手伝いをする働き者だ。
叔父のパーシーが家畜を連れてきたら一緒に世話をさせるのがよいかもしれない。
「お塩がたくさんあると色々できますよね。私たちの家族は肉を塩漬けにしてましたよ」
「姉ちゃんは煮物に幼虫が入るのが嫌だからね」
どうやらヤギ人には昆虫食の習慣がないらしい。
モリーとフローラは露骨に嫌がるが、ここに来たときに幼かったピーターは慣れたようだ。
こうして姉をからかう程度には虫も食べる。
「痛てっ! やめろよ!」
「アンタがケンカ売ってきたんでしょ! いい加減オネショやめなさいよっ!」
この姉弟は本当に仲がいい。
モリーは最近、角も伸びてきており徐々に大人になってきたようだ。
(モリーやフローラにもよい婿を探してやらねばなあ)
ヤギ人は大抵の場合、婚姻は家長が決めていたらしい。
だが、モリーたちの一族は壊滅しているし、この辺は臨機応変にやるしかないだろう。
(パーシーとかいうのは頼りないしな……本人同士が望むならまだしも、ちょっとオススメはできんな)
いつの間にか、ヤギ人の娘らにも情が移ってしまった。
(今のサイズじゃちょいと難しいが、大きくなってから俺が妾にしたら――アシュリンが嫌がるだろうな。やめとこう)
俺だって男だ。
女をはべらすような生活をしてみたいが……アシュリンはベルが寄ってきただけで目を三角にするのだ。
俺には妾をむかえて家庭の平和を保つ自信がない。
ぼんやりとしているうちに、いつの間にか日が暮れ食事のために皆が集まってきた。
今日は仕事にならなかったが、こんな日があってもいいだろう。
塩気の利いた食事に皆が舌鼓を打っている。
「塩か……魚を塩漬けにしたものを熟成させると我らが魚醤と呼ぶ調味液になる」
「生魚をか? どのくらい熟成させるんだ?」
ウシカによると、リザードマンは魚醤と呼ぶ調味液を作るらしい。
だが、1年以上塩漬けにした生魚から出た汁とは……挑戦に勇気が必要だ。
いつものようにモリーたちヤギ人が聖霊へのお供えとして、食事を少し取り分ける。
それをモリーがスケサンに供えると、スケサンは「いつもすまんな」と礼をいい、ウシカの子供らに与える。
よく分からないが、いつの間にか始まった光景だ。
誰も嫌がってないし、食事をしないスケサンも少し楽しそうだ。
皆で食事を終えるとお楽しみの酒である。
「ヒエ酒は飲んだことがない。楽しみだな」
ちいさな甕の蓋を外すと、独特の香りの濁った液体がなみなみと入っている。
よく見ると、液体にはぷちぷちと小さな泡がたっているようだ。
「では、早速」
俺は小さなお椀を甕に浸し、直接酒をくむ。
森に来てはじめての酒だ。
少し緊張しながら口に含むと、なんともいえない酸味と酒精の熱さを舌に感じた。
「たしかに酒だ。皆も飲んでくれ」
俺が促すと、皆がわらわらと甕に群がる。
酒は貴重品、滅多にないごちそうなのだ。
「……悪くないが、酸味が強いか?」
「噛み酒かも? 酒精は弱いな」
コナンとバーンが酒を飲みながらうんちくを垂れている。
面倒くさいやつらだ。
ウシカとケハヤは無言で飲んでいるが、これはリザードマンの嗜みらしい。
酒を飲んで言葉を放つと争いの種を撒くから無言で飲むのだそうだ。
理解できるし立派なことだとは思うが……少し素っ気ない気もする。
「さ、酒か、うちでも作れないかな?」
「ん? エルフは酒を作ってたのか?」
アシュリンが漏らした一言は聞き逃せないものがある。
酒作りが可能ならわざわざ買う必要もないし、量によっては売り物になりそうだ。
「うーん、エルフの里では作ってたぞ。で、でも長老たちの仕事で私たちはよく分からないんだ」
「どんな酒なんだ?」
アシュリンがいうにはハチミツを使った酒とブドウの実を使った酒を作っていたそうだ。
そういえば、かつてエルフの貢ぎ物に酒があったような気もする。
「作るとこは見たけど……ハチミツと祈りを捧げた清水を混ぜて、かまどの側に置いておくんだ。だ、だけどお祈りの言葉が分からないし……」
「ふうん、たしかにそれだけで酒ができるなら祈りが大切なんだろうな」
酒作りは神秘の技とされる。
祈りが秘技だとしても不思議はない。
「ブドウの実はどうだ?」
「うーん、ブドウの実をたくさん集めなきゃいけないから、これは滅多につくらないな。ぶ、ブドウをそのまま潰して甕に入れるんだけど、これもそれだけしか分からない」
いきなり酒が作れるようになる――そんなに甘い話はないということだろう。
みんなで小さな甕の酒を舐めると、すぐに空になってしまった。
モリーやフローラは耳を真っ赤にしているが、他はケロッとしている。
弱い酒だし、酔っぱらうほど量がないのだ。
「皆がこれだけ酒が好きなら作れるようになるといいな」
「う、うん。祈りの言葉をしっかり思い出せればいいんだけど……」
酒造はワイルドエルフの秘事だったらしく、族長の一族だったアシュリンしか見た記憶がないらしい。
コナンやバーンはまったく分からないのだそうだ。
「ふむ、リザードマンの嗜みではないが酒は理性を弱める働きがある。ワイルドエルフは皆が勝手に作りはじめ、酒浸りになるのを恐れたのだろう」
「なるほど。たしかに今日はなにも手につかなかった。こんな日ばかりでは困ってしまうな」
スケサンの言葉には皆が笑ってしまった。
たしかに酒は理性を弱めるかもしれないが、こうして楽しむぶんには構わないだろう。
「ヤギ人はお葬式のとき、近親者は酩酊するまでお酒を飲むんです。死者の言葉が聞こえるから」
フローラがポツリと呟いた。
「でも、お酒を飲んでも私には声が聞こえません。家族は生きてる」
「そうか、そうだな」
酒は日常の楽しみであり、身を持ち崩す毒であり、大切な祭具なのだ。
なんとかして酒作りをはじめたい。
俺は密かに決意をした。
■■■■
銅器
そのまま、銅でできた道具。
銅は柔らかくて武具などには使い物にならないという人もいるが、そんなことはない。
人類史において銅器を用いた時代を銅器時代といい、ちゃんと実用品として使われていたのだ。
アルプスで発見された青銅器時代以前の遺体(アイスマン)は純度の高い銅の斧と石のナイフを所持していたことでも知られている。
(※注)もちろん、青銅とは銅と錫の合金のこと。
しかし、冶金の知識がないベルクは銅の産地の問題だと思い込んでいるらしい。
どこかの銅鉱山で不純物量の錫やアンチモンなどが含まれていた可能性も捨てきれないが、冶金は秘中の秘であるから嘘を教えられた可能性は大いにある。
0
あなたにおすすめの小説

家族転生 ~父、勇者 母、大魔導師 兄、宰相 姉、公爵夫人 弟、S級暗殺者 妹、宮廷薬師 ……俺、門番~
北条新九郎
ファンタジー
三好家は一家揃って全滅し、そして一家揃って異世界転生を果たしていた。
父は勇者として、母は大魔導師として異世界で名声を博し、現地人の期待に応えて魔王討伐に旅立つ。またその子供たちも兄は宰相、姉は公爵夫人、弟はS級暗殺者、妹は宮廷薬師として異世界を謳歌していた。
ただ、三好家第三子の神太郎だけは異世界において冴えない立場だった。
彼の職業は………………ただの門番である。
そして、そんな彼の目的はスローライフを送りつつ、異世界ハーレムを作ることだった。
お気に入り・感想、宜しくお願いします。

異世界に転移したら、孤児院でごはん係になりました
雪月夜狐
ファンタジー
ある日突然、異世界に転移してしまったユウ。
気がつけば、そこは辺境にある小さな孤児院だった。
剣も魔法も使えないユウにできるのは、
子供たちのごはんを作り、洗濯をして、寝かしつけをすることだけ。
……のはずが、なぜか料理や家事といった
日常のことだけが、やたらとうまくいく。
無口な男の子、甘えん坊の女の子、元気いっぱいな年長組。
個性豊かな子供たちに囲まれて、
ユウは孤児院の「ごはん係」として、毎日を過ごしていく。
やがて、かつてこの孤児院で育った冒険者や商人たちも顔を出し、
孤児院は少しずつ、人が集まる場所になっていく。
戦わない、争わない。
ただ、ごはんを作って、今日をちゃんと暮らすだけ。
ほんわか天然な世話係と子供たちの日常を描く、
やさしい異世界孤児院ファンタジー。

スーパーの店長・結城偉介 〜異世界でスーパーの売れ残りを在庫処分〜
かの
ファンタジー
世界一周旅行を夢見てコツコツ貯金してきたスーパーの店長、結城偉介32歳。
スーパーのバックヤードで、うたた寝をしていた偉介は、何故か異世界に転移してしまう。
偉介が転移したのは、スーパーでバイトするハル君こと、青柳ハル26歳が書いたファンタジー小説の世界の中。
スーパーの過剰商品(売れ残り)を捌きながら、微妙にズレた世界線で、偉介の異世界一周旅行が始まる!
冒険者じゃない! 勇者じゃない! 俺は商人だーーー! だからハル君、お願い! 俺を戦わせないでください!
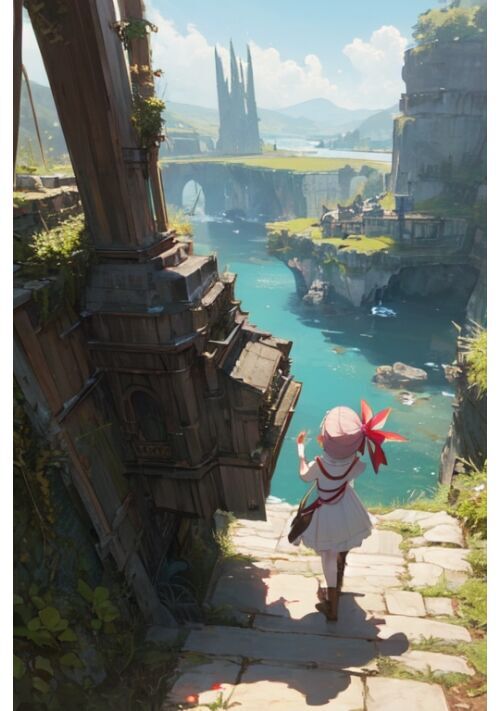
竜の子と灰かぶりの配達屋
さばちゃそ
ファンタジー
世にも珍しい『竜の子』であるボロを相棒にする少女エラは、激務に悩まされる日々を過ごしている。
彼女は、危険地帯(ダンジョン)や危険な生物が各地に跋扈(ばっこ)している世界の中で、最も必要とされている仕事についていた。
それが、配達屋(フェアリーズ)である。
危険な猛獣や魔物が至るところに蔓延(はびこ)っているグリモ大陸では、国と国の間で物流が滞ってしまう。そんな世界で、人から人へ配達物を繋ぐ架け橋となっているのが、配達屋という者達だった。
指定された時間を厳守し、可能であればどのような荷物でも届けることが出来る彼らは、毎日大量の配達物の山に翻弄(ほんろう)されていた。
そして、エラもその一員だった。
とある日、ようやく見習いから一人前と認められ、配達屋として世界を飛び回ることができるようになったエラは、この危険で広大な世界で色んな出会い、そして別れを繰り返し、相棒のボロと共に一歩ずつ成長していくことになる――。

七億円当たったので異世界買ってみた!
コンビニ
ファンタジー
三十四歳、独身、家電量販店勤務の平凡な俺。
ある日、スポーツくじで7億円を当てた──と思ったら、突如現れた“自称・神様”に言われた。
「異世界を買ってみないか?」
そんなわけで購入した異世界は、荒れ果てて疫病まみれ、赤字経営まっしぐら。
でも天使の助けを借りて、街づくり・人材スカウト・ダンジョン建設に挑む日々が始まった。
一方、現実世界でもスローライフと東北の田舎に引っ越してみたが、近所の小学生に絡まれたり、ドタバタに巻き込まれていく。
異世界と現実を往復しながら、癒やされて、ときどき婚活。
チートはないけど、地に足つけたスローライフ(たまに労働)を始めます。

固有スキルガチャで最底辺からの大逆転だモ~モンスターのスキルを使えるようになった俺のお気楽ダンジョンライフ~
うみ
ファンタジー
恵まれない固有スキルを持って生まれたクラウディオだったが、一人、ダンジョンの一階層で宝箱を漁ることで生計を立てていた。
いつものように一階層を探索していたところ、弱い癖に探索者を続けている彼の態度が気に入らない探索者によって深層に飛ばされてしまう。
モンスターに襲われ絶体絶命のピンチに機転を利かせて切り抜けるも、ただの雑魚モンスター一匹を倒したに過ぎなかった。
そこで、クラウディオは固有スキルを入れ替えるアイテムを手に入れ、大逆転。
モンスターの力を吸収できるようになった彼は深層から無事帰還することができた。
その後、彼と同じように深層に転移した探索者の手助けをしたり、彼を深層に飛ばした探索者にお灸をすえたり、と彼の生活が一変する。
稼いだ金で郊外で隠居生活を送ることを目標に今日もまたダンジョンに挑むクラウディオなのであった。
『箱を開けるモ』
「餌は待てと言ってるだろうに」
とあるイベントでくっついてくることになった生意気なマーモットと共に。

無属性魔法使いの下剋上~現代日本の知識を持つ魔導書と契約したら、俺だけが使える「科学魔法」で学園の英雄に成り上がりました~
黒崎隼人
ファンタジー
「お前は今日から、俺の主(マスター)だ」――魔力を持たない“無能”と蔑まれる落ちこぼれ貴族、ユキナリ。彼が手にした一冊の古びた魔導書。そこに宿っていたのは、異世界日本の知識を持つ生意気な魂、カイだった!
「俺の知識とお前の魔力があれば、最強だって夢じゃない」
主従契約から始まる、二人の秘密の特訓。科学的知識で魔法の常識を覆し、落ちこぼれが天才たちに成り上がる! 無自覚に甘い主従関係と、胸がすくような下剋上劇が今、幕を開ける!

異世界召喚された俺の料理が美味すぎて魔王軍が侵略やめた件
さかーん
ファンタジー
魔王様、世界征服より晩ご飯ですよ!
食品メーカー勤務の平凡な社会人・橘陽人(たちばな はると)は、ある日突然異世界に召喚されてしまった。剣も魔法もない陽人が頼れるのは唯一の特技――料理の腕だけ。
侵略の真っ最中だった魔王ゼファーとその部下たちに、試しに料理を振る舞ったところ、まさかの大絶賛。
「なにこれ美味い!」「もう戦争どころじゃない!」
気づけば魔王軍は侵略作戦を完全放棄。陽人の料理に夢中になり、次々と餌付けされてしまった。
いつの間にか『魔王専属料理人』として雇われてしまった陽人は、料理の腕一本で人間世界と魔族の架け橋となってしまう――。
料理と異世界が織りなす、ほのぼのグルメ・ファンタジー開幕!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















