11 / 15
第11話 【ボロのロボ】
しおりを挟む
「うわわわわわわわわわわわわわわわわ!!」
誰かの絶叫が空間を引き裂くように響いた。
マリンはその声に反応して、ぱっと目を開けた。
「きゃああああああああああああああああああ!!」
気づけば自分も叫んでいた。というよりも、叫ばずにはいられなかった。
――落ちている。
一面に灰色の空が広がり、浮かぶ雲がつかめそうな上空から真っ逆さまに、速度を増しながら、三人は落ちていた。
耳元をかすめる風のようなもの。上下の感覚すら狂ってしまいそうな視界。夢か現実か、境目が曖昧なまま、身を任せることしか出来なかった。
そして――
ドッシーーーン!!!
衝撃と共に、大地が彼女たちを受け止めた。
だが、その“着地”は意外にも柔らかく、何かが砕け、崩れるような音もしたが、全身に広がったのは激痛ではなく、スポンジの中にうずもれるような妙にふわりとした感触だった。
「‥‥いたっ、く‥‥ない?」
最初に声を出したのはチハルだった。
恐る恐る目を開けると、目の前には紙くず木くず、茶色く錆びた塊、何かの破片、折れ曲がったパイプ、粗大な物々といった――ごみとしか言いようのないもので埋め尽くされた景色が広がっていた。
三人は巨大なゴミの山の上に落ちてきたのだ。クッションになりそうにないものばかりだが、なぜクッションになったのだろうか不思議に思いつつも、とにかく助かったことに安堵の息を吐く。
「マリンちゃん‥‥? 大丈夫? 無事? 生きてる?」
チハルが慌てて隣を覗き込むと、マリンはその場に座り込んで、まばたきを繰り返していた。
「‥‥うん。生きてる。たぶん、大丈夫」
マリンもまた不思議そうに自分の手や足を触り、擦り傷ひとつないことを確認した。
二人はゆっくりと立ち上がり、辺りを見渡す。
まるで巨大な廃棄場の中に放り込まれたようだった。今自分たちがいるゴミの山がいくつもあり、無秩序に無造作に積まれたゴミたちの中で、風も音も生気もなく、ただ“捨てられたもの”だけがこの世界を満たしているようだった。
「で、チハル。ここはどういう作品の世界なんだ?」
きっとここも何かの小説の世界だと、レンは慣れた感じで訊いてくる。
「えっと‥‥」
チハルは眉をひそめ、心当たりを探すように記憶を巡らせるが――
「‥‥この物語は、知らないかも」
「え?!」
チハルが知らない――それは、これまでの冒険では一度もなかったことだった。レンは心底驚いた表情を見せる。
チハルもまた、これまで沢山の本を読んできたはずなのに思い当たらないなんてと人知れずにショックを受けていた。
「それじゃ、どうすればいいんだよ?」
不安で思わず声に出してしまった。
これまで話を知っているからどういう行動を取れば良いのか解っていたから、多少の安心はあったが道しるべが無いようなものだった。
しかし、
「‥‥わたし、知ってるかもしれない」
ぽつりと、マリンが静かに呟いた。二人の視線が彼女に集中する。
マリンはゆっくりとチハルの方を向いて言った。
「ここは『ボロのロボ』の世界だと思う」
「ボロの‥‥ロボ?」
聞き慣れないタイトルに、チハルが目を丸くする。するとマリンは、どこか懐かしさの混じった神妙な表情で語り始めた。
「ママが、わたしにだけ作ってくれた物語なの。まだ、ママが生きていた頃に‥‥私に読み聞かせてくれてた。わたしのためだけの物語」
「マリンちゃんの‥‥お母さんが?」
「うん。物語の中にね、ゴミの山を一人で片付けているボロボロのロボットが出てくるの。‥‥ほら、あそこ」
マリンが指をさした先には、確かにそれらしいモノが居た。
ゴミの山の麓で、錆びた鉄の体をきしませながら、せっせとゴミを片付けるロボット。外装ははがれ、中の部品がむき出し、脚は引きずるようにして動いている。
その姿を見た瞬間、マリンの胸がぎゅっと締めつけられた。
「‥‥あのロボットが物語の主人公の一人で。少女と出会って、一緒に少女の家を探す為の冒険の旅をするの」
「冒険の旅? どこにだ?」
レンが身を乗り出し、興味津々で尋ねる。
「‥‥あそこ」
今度は遠く、空の向こうを指さした。
遥か彼方にそびえる塔。よく見れば、霞んでいて揺らめくように形が歪んでいる。
「『蜃気楼の塔』って呼ばれてるの。あそこに住む『灰色の魔女』が、どんな願いでも一つだけ叶えてくれて、少女の家に戻してくれるの」
「うわ、すごく面白そうな話!」
チハルが目を輝かせる。その素直な反応が、マリンには嬉しかった。
母の物語を誰かが「面白い」と言ってくれる――それだけで、心が少し温かくなった気がした。
「あ、ありがとう」
照れくささと嬉しさがないまぜになって、マリンは少しだけ視線をそらしながらも、素直に礼を言った。
「ねえねえ、マリンちゃん。その“ボロのロボ”って物語、できれば最後まで教えてくれない?」
「あ‥‥」
マリンは一瞬、言葉を詰まらせた。
ほんのわずかの沈黙のあと、目を伏せて小さく首を横に振った。
「実は‥‥ママ、最後まで書き上げられなかったの。病気で亡くなっちゃって‥‥私も、当時はまだ小さかったから、内容もよく覚えてなくて‥‥」
チハルの表情が、はっと曇る。
「そうなんだ‥‥ご、ごめん。気が回らなくて‥‥」
チハルがしゅんとしたようにうつむき、申し訳なさそうに唇を噛む。
マリンは慌てて首を横に振った。
「ううん、謝らなくて大丈夫だよ。私が覚えているのは‥‥さっき言った程度で‥‥」
そこで一度、マリンは言葉を切った。少しだけ遠くを見るような目になって、ゆっくりと思い出を探るように語り出す。
誰かの絶叫が空間を引き裂くように響いた。
マリンはその声に反応して、ぱっと目を開けた。
「きゃああああああああああああああああああ!!」
気づけば自分も叫んでいた。というよりも、叫ばずにはいられなかった。
――落ちている。
一面に灰色の空が広がり、浮かぶ雲がつかめそうな上空から真っ逆さまに、速度を増しながら、三人は落ちていた。
耳元をかすめる風のようなもの。上下の感覚すら狂ってしまいそうな視界。夢か現実か、境目が曖昧なまま、身を任せることしか出来なかった。
そして――
ドッシーーーン!!!
衝撃と共に、大地が彼女たちを受け止めた。
だが、その“着地”は意外にも柔らかく、何かが砕け、崩れるような音もしたが、全身に広がったのは激痛ではなく、スポンジの中にうずもれるような妙にふわりとした感触だった。
「‥‥いたっ、く‥‥ない?」
最初に声を出したのはチハルだった。
恐る恐る目を開けると、目の前には紙くず木くず、茶色く錆びた塊、何かの破片、折れ曲がったパイプ、粗大な物々といった――ごみとしか言いようのないもので埋め尽くされた景色が広がっていた。
三人は巨大なゴミの山の上に落ちてきたのだ。クッションになりそうにないものばかりだが、なぜクッションになったのだろうか不思議に思いつつも、とにかく助かったことに安堵の息を吐く。
「マリンちゃん‥‥? 大丈夫? 無事? 生きてる?」
チハルが慌てて隣を覗き込むと、マリンはその場に座り込んで、まばたきを繰り返していた。
「‥‥うん。生きてる。たぶん、大丈夫」
マリンもまた不思議そうに自分の手や足を触り、擦り傷ひとつないことを確認した。
二人はゆっくりと立ち上がり、辺りを見渡す。
まるで巨大な廃棄場の中に放り込まれたようだった。今自分たちがいるゴミの山がいくつもあり、無秩序に無造作に積まれたゴミたちの中で、風も音も生気もなく、ただ“捨てられたもの”だけがこの世界を満たしているようだった。
「で、チハル。ここはどういう作品の世界なんだ?」
きっとここも何かの小説の世界だと、レンは慣れた感じで訊いてくる。
「えっと‥‥」
チハルは眉をひそめ、心当たりを探すように記憶を巡らせるが――
「‥‥この物語は、知らないかも」
「え?!」
チハルが知らない――それは、これまでの冒険では一度もなかったことだった。レンは心底驚いた表情を見せる。
チハルもまた、これまで沢山の本を読んできたはずなのに思い当たらないなんてと人知れずにショックを受けていた。
「それじゃ、どうすればいいんだよ?」
不安で思わず声に出してしまった。
これまで話を知っているからどういう行動を取れば良いのか解っていたから、多少の安心はあったが道しるべが無いようなものだった。
しかし、
「‥‥わたし、知ってるかもしれない」
ぽつりと、マリンが静かに呟いた。二人の視線が彼女に集中する。
マリンはゆっくりとチハルの方を向いて言った。
「ここは『ボロのロボ』の世界だと思う」
「ボロの‥‥ロボ?」
聞き慣れないタイトルに、チハルが目を丸くする。するとマリンは、どこか懐かしさの混じった神妙な表情で語り始めた。
「ママが、わたしにだけ作ってくれた物語なの。まだ、ママが生きていた頃に‥‥私に読み聞かせてくれてた。わたしのためだけの物語」
「マリンちゃんの‥‥お母さんが?」
「うん。物語の中にね、ゴミの山を一人で片付けているボロボロのロボットが出てくるの。‥‥ほら、あそこ」
マリンが指をさした先には、確かにそれらしいモノが居た。
ゴミの山の麓で、錆びた鉄の体をきしませながら、せっせとゴミを片付けるロボット。外装ははがれ、中の部品がむき出し、脚は引きずるようにして動いている。
その姿を見た瞬間、マリンの胸がぎゅっと締めつけられた。
「‥‥あのロボットが物語の主人公の一人で。少女と出会って、一緒に少女の家を探す為の冒険の旅をするの」
「冒険の旅? どこにだ?」
レンが身を乗り出し、興味津々で尋ねる。
「‥‥あそこ」
今度は遠く、空の向こうを指さした。
遥か彼方にそびえる塔。よく見れば、霞んでいて揺らめくように形が歪んでいる。
「『蜃気楼の塔』って呼ばれてるの。あそこに住む『灰色の魔女』が、どんな願いでも一つだけ叶えてくれて、少女の家に戻してくれるの」
「うわ、すごく面白そうな話!」
チハルが目を輝かせる。その素直な反応が、マリンには嬉しかった。
母の物語を誰かが「面白い」と言ってくれる――それだけで、心が少し温かくなった気がした。
「あ、ありがとう」
照れくささと嬉しさがないまぜになって、マリンは少しだけ視線をそらしながらも、素直に礼を言った。
「ねえねえ、マリンちゃん。その“ボロのロボ”って物語、できれば最後まで教えてくれない?」
「あ‥‥」
マリンは一瞬、言葉を詰まらせた。
ほんのわずかの沈黙のあと、目を伏せて小さく首を横に振った。
「実は‥‥ママ、最後まで書き上げられなかったの。病気で亡くなっちゃって‥‥私も、当時はまだ小さかったから、内容もよく覚えてなくて‥‥」
チハルの表情が、はっと曇る。
「そうなんだ‥‥ご、ごめん。気が回らなくて‥‥」
チハルがしゅんとしたようにうつむき、申し訳なさそうに唇を噛む。
マリンは慌てて首を横に振った。
「ううん、謝らなくて大丈夫だよ。私が覚えているのは‥‥さっき言った程度で‥‥」
そこで一度、マリンは言葉を切った。少しだけ遠くを見るような目になって、ゆっくりと思い出を探るように語り出す。
0
あなたにおすすめの小説

僕らの無人島漂流記
ましゅまろ
児童書・童話
夏休み、仲良しの小学4年男子5人組が出かけたキャンプは、突然の嵐で思わぬ大冒険に!
目を覚ますと、そこは見たこともない無人島だった。
地図もない。電波もない。食べ物も、水も、家もない。
頼れるのは、友だちと、自分の力だけ。
ケンカして、笑って、泣いて、助け合って——。
子どもだけの“1ヶ月サバイバル生活”が、いま始まる!


14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。
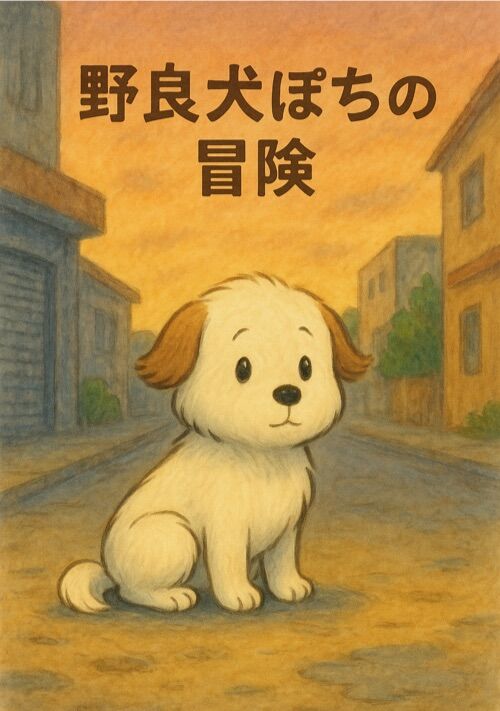
野良犬ぽちの冒険
KAORUwithAI
児童書・童話
――ぼくの名前、まだおぼえてる?
ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。
だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、
気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。
やさしい人もいれば、こわい人もいる。
あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。
それでも、ぽちは 思っている。
──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。
すこし さみしくて、すこし あたたかい、
のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

カリンカの子メルヴェ
田原更
児童書・童話
地下に掘り進めた穴の中で、黒い油という可燃性の液体を採掘して生きる、カリンカという民がいた。
かつて迫害により追われたカリンカたちは、地下都市「ユヴァーシ」を作り上げ、豊かに暮らしていた。
彼らは合言葉を用いていた。それは……「ともに生き、ともに生かす」
十三歳の少女メルヴェは、不在の父や病弱な母に代わって、一家の父親役を務めていた。仕事に従事し、弟妹のまとめ役となり、時には厳しく叱ることもあった。そのせいで妹たちとの間に亀裂が走ったことに、メルヴェは気づいていなかった。
幼なじみのタリクはメルヴェを気遣い、きらきら輝く白い石をメルヴェに贈った。メルヴェは幼い頃のように喜んだ。タリクは次はもっと大きな石を掘り当てると約束した。
年に一度の祭にあわせ、父が帰郷した。祭当日、男だけが踊る舞台に妹の一人が上がった。メルヴェは妹を叱った。しかし、メルヴェも、最近みせた傲慢な態度を父から叱られてしまう。
そんな折に地下都市ユヴァーシで起きた事件により、メルヴェは生まれてはじめて外の世界に飛び出していく……。
※本作はトルコのカッパドキアにある地下都市から着想を得ました。

少年騎士
克全
児童書・童話
「第1回きずな児童書大賞参加作」ポーウィス王国という辺境の小国には、12歳になるとダンジョンか魔境で一定の強さになるまで自分を鍛えなければいけないと言う全国民に対する法律があった。周囲の小国群の中で生き残るため、小国を狙う大国から自国を守るために作られた法律、義務だった。領地持ち騎士家の嫡男ハリー・グリフィスも、その義務に従い1人王都にあるダンジョンに向かって村をでた。だが、両親祖父母の計らいで平民の幼馴染2人も一緒に12歳の義務に同行する事になった。将来救国の英雄となるハリーの物語が始まった。

不幸でしあわせな子どもたち 「しあわせのふうせん」
山口かずなり
絵本
小説 不幸でしあわせな子どもたち
スピンオフ作品
・
ウルが友だちのメロウからもらったのは、
緑色のふうせん
だけどウルにとっては、いらないもの
いらないものは、誰かにとっては、
ほしいもの。
だけど、気づいて
ふうせんの正体に‥。
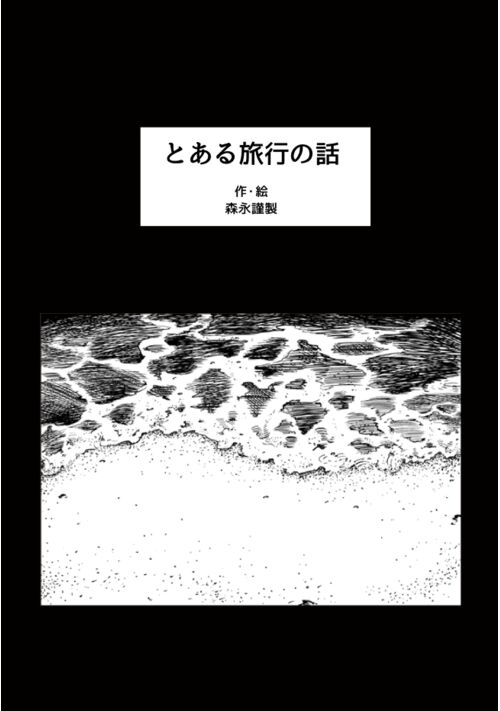
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















