14 / 15
第14話 【約束】
しおりを挟む
あの日、あの時、マリンの手を握りしめながら、リサは微笑んでそう言ってくれた。
その言葉を、マリンはずっと胸の奥に仕舞い込んでいた。苦しくて、思い出すたびに心が引き裂かれるようで、封じ込めていた。
だけど今、その封が解かれ、思い出が堰を切ったように溢れ出してきた。
涙がとめどなく流れ、マリンはその場に崩れ落ちた。
嗚咽がこぼれ、胸の奥がぎゅっと締め付けられる。
「‥‥ママぁ‥‥ママぁ‥‥!」
母を思い出すと、胸が痛かった。苦しかった。だから、思い出すことを止めて、やがて忘れてしまった。
けれど、母の温もり、母の声、母の愛しさ、母の“約束”。それはたしかに、マリンの中に生きていた。
そう、母は、もういない。けれど――いなくなっても、完全に失われたわけではない。
マリンは大粒の涙を流しながら、口を両手で覆い、嗚咽をこらえた。
リサの姿をした“何か”は、無表情のままマリンをじっと見つめ続けていた。
マリンの嘆きをよそに、灰色の魔女は冷ややかに微笑み、関心を示さないまま静かに視線をチハルへと移した。ただ自分の使命を果たす為に、事務的な口調で言葉を告げる。
「――さて。今度はアナタの番よ。どんな願いを叶えて欲しいの?」
チハルは今にも崩れそうなほど泣きじゃくるマリンを見つめたまま、魔女に言い放つ。
「‥‥私が、マリンちゃんのお母さんを、ちゃんと‥‥マリンちゃんと一緒に過ごしていた頃と同じように‥‥生き返らせて、と願ったら‥‥叶えてくれるんですか?」
声は震えていたが、意志の強さが滲んでいた。
魔女は表情を変えず、ふっと小さく息を吐いた。
「‥‥さっきも言ったでしょう? それは“ちゃんと”生き返らせているわよ」
抑揚のない声だった。
「だけど‥‥」
チハルの言葉は途中で詰まった。
“だけど、あれはマリンちゃんのママじゃない”。――喉元まで出かけたその言葉を、どうしても言えなかった。
願いを叶えたはずなのに、マリンはあんなにも泣いている。あれが良かったなんて、到底思えなかったのに。
灰色の魔女はもう、興味を失ったように軽く肩をすくめた。
「‥‥願いがないなら、ここでお開きかしらね。どんな物語にも必ず終わりはやってくる。その終わりは、読者が望まない終わりだってある。この物語はここまでね。さようなら」
「‥‥あっ! 待って――!」
チハルが声を上げた瞬間には、もう遅かった。
魔女とリサの姿は、煙のようにふっと薄れ、揺らめく幻影のように消えていった。まるで最初からそこにいなかったかのように。
「あ、マ‥‥」
マリンは言葉を途中で飲み込んだ。母に似た存在にママと呼ぶのを拒んだのだ。
けれど、深く息を吸い、胸の奥で震える感情をそっと整えてから、マリンは小さく口を開く。
「ありがとう‥‥ママを思い出せてくれて」
それは感謝の言葉だった。
忘れていた母との日々、母との大切な約束。
愛しさが悲しみを上塗りしてくれた。
そして――塔が鳴動した。
床が低く唸りを上げ、空間がわずかに震える。空気が急に淡くなり、視界の端がぼやけ始める。
高くそびえていた石の壁が、まるで霧が晴れるように薄れ、崩れ、静かに形を失っていく。
「えっ‥‥なに‥‥!? 塔が‥‥!」
三人は突然、足元の感覚を失い、糸の切れた凧のように、ゴミの大地へと急降下を始めた。
「きゃあっ!?」
「うわっ、落ちる――っ!」
三人の叫び声が虚空に消える。目を閉じたその一瞬、チハルは念じた。
そのときだった。
空の果て、はるか彼方から目眩く虹色の光が現れた。
それは残光を引きながら、一直線にこちらへ向かってくる。
次の瞬間、巨大な青い翼が広がり、空気を切り裂く音と共に三人の体をやさしく包み込んだ。
不思議な感触。まるで空そのものに抱きとめられたような心地だった。
その正体は――
「えっ‥‥あれ、ポータ‥‥?」
チハルが恐る恐るつぶやくと、巨鳥は「そうだよ」とでも言いたげに、低く優しく「クルルン」と鳴いた。
その声にレンが素っ頓狂な声をあげる。
「マジで!? あのポータ!? あの――あの、むっくりとしたポータが、こんなカッコよくてデカい鳥になっているんだよ!?」
金色に縁取られた大きな瞳、七色に輝く巨大な翼、神話に登場する神獣のような威厳と美しさを併せ持った姿。それが幸せの青い鳥ポータの真の姿であった。
そう、ネタバレになるのだが、ポータは実は神獣の子供であり、見たものを幸運を招くと呼ばれる瑞鳥なのだ。
普段の“鶏のようなずんぐりむっくり姿”からは到底想像もつかない、気高く堂々とした姿であった。
「‥‥ところでなんで、ポータが助けにやってきたんだ?」
レンが震える声で尋ねると、チハルは意味深な表情を浮かべて答えた。
「‥‥たぶん、これが私の願いごとだったから、かな」
「願いごと?」
「うん。さっき心の中で“私たちを現実の世界に戻してください”って願ったんだよ。きっとそれでも届いてたんだと思う。そう思うことにしたわ、私は‥‥」
レンとマリンは驚きの表情を見せた後、自分たちも無理やり納得したように頷いた。
助かったのだから、それで良いやと。
ポータは三人を乗せたまま、かつて蜃気楼の塔がそびえていた場所を一度大きく旋回した。その眼下には、もはや塔の姿はなく、ただ白く濁った霧が名残のように漂っていた。
三人はそれぞれの胸の内に去来する思い出を巡らせていた。
光る本、冒険、出会い、大切な約束。
チハルは感慨にふけ、レンはSwitch2が手元にないことに気づき、マリンはそっと目を閉じた。
ポータは巨大な翼を力強くはためかせた。
風が巻き起こり、雲が吹き飛び、空が開ける。
高度とスピードを上げていき、一直線に天へと駆け上がるように飛翔し、やがて光のような速さとなり“天を突き破った”。
それは比喩ではなかった。世界の境界すら超えて、チハルたちを現実の世界へと導く光が天空を裂いたのだ。
その頃、かつて塔がそびえていた中心部には、まだわずかに霧が立ち込めていた。
その中に、灰色の魔女と、マリンの母――リサの姿があった。
魔女とリサは空の彼方へと消えていくポータの姿を目で追いながら、静かにリサに言葉をかけた。
リサは微笑んだ。静かに、柔らかく、どこまでも温かく。
そしてリサの瞳からとめどなく涙が溢れた。彼女の表情は、まぎれもなく母のものであった。
やがて、ふたりの姿は霧の中にゆっくりと溶けていった。
舞台の幕が静かに下りるように。
その言葉を、マリンはずっと胸の奥に仕舞い込んでいた。苦しくて、思い出すたびに心が引き裂かれるようで、封じ込めていた。
だけど今、その封が解かれ、思い出が堰を切ったように溢れ出してきた。
涙がとめどなく流れ、マリンはその場に崩れ落ちた。
嗚咽がこぼれ、胸の奥がぎゅっと締め付けられる。
「‥‥ママぁ‥‥ママぁ‥‥!」
母を思い出すと、胸が痛かった。苦しかった。だから、思い出すことを止めて、やがて忘れてしまった。
けれど、母の温もり、母の声、母の愛しさ、母の“約束”。それはたしかに、マリンの中に生きていた。
そう、母は、もういない。けれど――いなくなっても、完全に失われたわけではない。
マリンは大粒の涙を流しながら、口を両手で覆い、嗚咽をこらえた。
リサの姿をした“何か”は、無表情のままマリンをじっと見つめ続けていた。
マリンの嘆きをよそに、灰色の魔女は冷ややかに微笑み、関心を示さないまま静かに視線をチハルへと移した。ただ自分の使命を果たす為に、事務的な口調で言葉を告げる。
「――さて。今度はアナタの番よ。どんな願いを叶えて欲しいの?」
チハルは今にも崩れそうなほど泣きじゃくるマリンを見つめたまま、魔女に言い放つ。
「‥‥私が、マリンちゃんのお母さんを、ちゃんと‥‥マリンちゃんと一緒に過ごしていた頃と同じように‥‥生き返らせて、と願ったら‥‥叶えてくれるんですか?」
声は震えていたが、意志の強さが滲んでいた。
魔女は表情を変えず、ふっと小さく息を吐いた。
「‥‥さっきも言ったでしょう? それは“ちゃんと”生き返らせているわよ」
抑揚のない声だった。
「だけど‥‥」
チハルの言葉は途中で詰まった。
“だけど、あれはマリンちゃんのママじゃない”。――喉元まで出かけたその言葉を、どうしても言えなかった。
願いを叶えたはずなのに、マリンはあんなにも泣いている。あれが良かったなんて、到底思えなかったのに。
灰色の魔女はもう、興味を失ったように軽く肩をすくめた。
「‥‥願いがないなら、ここでお開きかしらね。どんな物語にも必ず終わりはやってくる。その終わりは、読者が望まない終わりだってある。この物語はここまでね。さようなら」
「‥‥あっ! 待って――!」
チハルが声を上げた瞬間には、もう遅かった。
魔女とリサの姿は、煙のようにふっと薄れ、揺らめく幻影のように消えていった。まるで最初からそこにいなかったかのように。
「あ、マ‥‥」
マリンは言葉を途中で飲み込んだ。母に似た存在にママと呼ぶのを拒んだのだ。
けれど、深く息を吸い、胸の奥で震える感情をそっと整えてから、マリンは小さく口を開く。
「ありがとう‥‥ママを思い出せてくれて」
それは感謝の言葉だった。
忘れていた母との日々、母との大切な約束。
愛しさが悲しみを上塗りしてくれた。
そして――塔が鳴動した。
床が低く唸りを上げ、空間がわずかに震える。空気が急に淡くなり、視界の端がぼやけ始める。
高くそびえていた石の壁が、まるで霧が晴れるように薄れ、崩れ、静かに形を失っていく。
「えっ‥‥なに‥‥!? 塔が‥‥!」
三人は突然、足元の感覚を失い、糸の切れた凧のように、ゴミの大地へと急降下を始めた。
「きゃあっ!?」
「うわっ、落ちる――っ!」
三人の叫び声が虚空に消える。目を閉じたその一瞬、チハルは念じた。
そのときだった。
空の果て、はるか彼方から目眩く虹色の光が現れた。
それは残光を引きながら、一直線にこちらへ向かってくる。
次の瞬間、巨大な青い翼が広がり、空気を切り裂く音と共に三人の体をやさしく包み込んだ。
不思議な感触。まるで空そのものに抱きとめられたような心地だった。
その正体は――
「えっ‥‥あれ、ポータ‥‥?」
チハルが恐る恐るつぶやくと、巨鳥は「そうだよ」とでも言いたげに、低く優しく「クルルン」と鳴いた。
その声にレンが素っ頓狂な声をあげる。
「マジで!? あのポータ!? あの――あの、むっくりとしたポータが、こんなカッコよくてデカい鳥になっているんだよ!?」
金色に縁取られた大きな瞳、七色に輝く巨大な翼、神話に登場する神獣のような威厳と美しさを併せ持った姿。それが幸せの青い鳥ポータの真の姿であった。
そう、ネタバレになるのだが、ポータは実は神獣の子供であり、見たものを幸運を招くと呼ばれる瑞鳥なのだ。
普段の“鶏のようなずんぐりむっくり姿”からは到底想像もつかない、気高く堂々とした姿であった。
「‥‥ところでなんで、ポータが助けにやってきたんだ?」
レンが震える声で尋ねると、チハルは意味深な表情を浮かべて答えた。
「‥‥たぶん、これが私の願いごとだったから、かな」
「願いごと?」
「うん。さっき心の中で“私たちを現実の世界に戻してください”って願ったんだよ。きっとそれでも届いてたんだと思う。そう思うことにしたわ、私は‥‥」
レンとマリンは驚きの表情を見せた後、自分たちも無理やり納得したように頷いた。
助かったのだから、それで良いやと。
ポータは三人を乗せたまま、かつて蜃気楼の塔がそびえていた場所を一度大きく旋回した。その眼下には、もはや塔の姿はなく、ただ白く濁った霧が名残のように漂っていた。
三人はそれぞれの胸の内に去来する思い出を巡らせていた。
光る本、冒険、出会い、大切な約束。
チハルは感慨にふけ、レンはSwitch2が手元にないことに気づき、マリンはそっと目を閉じた。
ポータは巨大な翼を力強くはためかせた。
風が巻き起こり、雲が吹き飛び、空が開ける。
高度とスピードを上げていき、一直線に天へと駆け上がるように飛翔し、やがて光のような速さとなり“天を突き破った”。
それは比喩ではなかった。世界の境界すら超えて、チハルたちを現実の世界へと導く光が天空を裂いたのだ。
その頃、かつて塔がそびえていた中心部には、まだわずかに霧が立ち込めていた。
その中に、灰色の魔女と、マリンの母――リサの姿があった。
魔女とリサは空の彼方へと消えていくポータの姿を目で追いながら、静かにリサに言葉をかけた。
リサは微笑んだ。静かに、柔らかく、どこまでも温かく。
そしてリサの瞳からとめどなく涙が溢れた。彼女の表情は、まぎれもなく母のものであった。
やがて、ふたりの姿は霧の中にゆっくりと溶けていった。
舞台の幕が静かに下りるように。
0
あなたにおすすめの小説

僕らの無人島漂流記
ましゅまろ
児童書・童話
夏休み、仲良しの小学4年男子5人組が出かけたキャンプは、突然の嵐で思わぬ大冒険に!
目を覚ますと、そこは見たこともない無人島だった。
地図もない。電波もない。食べ物も、水も、家もない。
頼れるのは、友だちと、自分の力だけ。
ケンカして、笑って、泣いて、助け合って——。
子どもだけの“1ヶ月サバイバル生活”が、いま始まる!


14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。
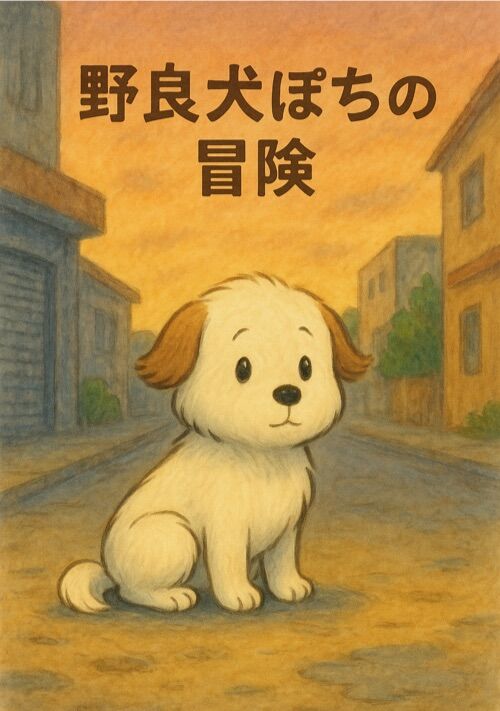
野良犬ぽちの冒険
KAORUwithAI
児童書・童話
――ぼくの名前、まだおぼえてる?
ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。
だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、
気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。
やさしい人もいれば、こわい人もいる。
あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。
それでも、ぽちは 思っている。
──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。
すこし さみしくて、すこし あたたかい、
のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

カリンカの子メルヴェ
田原更
児童書・童話
地下に掘り進めた穴の中で、黒い油という可燃性の液体を採掘して生きる、カリンカという民がいた。
かつて迫害により追われたカリンカたちは、地下都市「ユヴァーシ」を作り上げ、豊かに暮らしていた。
彼らは合言葉を用いていた。それは……「ともに生き、ともに生かす」
十三歳の少女メルヴェは、不在の父や病弱な母に代わって、一家の父親役を務めていた。仕事に従事し、弟妹のまとめ役となり、時には厳しく叱ることもあった。そのせいで妹たちとの間に亀裂が走ったことに、メルヴェは気づいていなかった。
幼なじみのタリクはメルヴェを気遣い、きらきら輝く白い石をメルヴェに贈った。メルヴェは幼い頃のように喜んだ。タリクは次はもっと大きな石を掘り当てると約束した。
年に一度の祭にあわせ、父が帰郷した。祭当日、男だけが踊る舞台に妹の一人が上がった。メルヴェは妹を叱った。しかし、メルヴェも、最近みせた傲慢な態度を父から叱られてしまう。
そんな折に地下都市ユヴァーシで起きた事件により、メルヴェは生まれてはじめて外の世界に飛び出していく……。
※本作はトルコのカッパドキアにある地下都市から着想を得ました。

少年騎士
克全
児童書・童話
「第1回きずな児童書大賞参加作」ポーウィス王国という辺境の小国には、12歳になるとダンジョンか魔境で一定の強さになるまで自分を鍛えなければいけないと言う全国民に対する法律があった。周囲の小国群の中で生き残るため、小国を狙う大国から自国を守るために作られた法律、義務だった。領地持ち騎士家の嫡男ハリー・グリフィスも、その義務に従い1人王都にあるダンジョンに向かって村をでた。だが、両親祖父母の計らいで平民の幼馴染2人も一緒に12歳の義務に同行する事になった。将来救国の英雄となるハリーの物語が始まった。

不幸でしあわせな子どもたち 「しあわせのふうせん」
山口かずなり
絵本
小説 不幸でしあわせな子どもたち
スピンオフ作品
・
ウルが友だちのメロウからもらったのは、
緑色のふうせん
だけどウルにとっては、いらないもの
いらないものは、誰かにとっては、
ほしいもの。
だけど、気づいて
ふうせんの正体に‥。
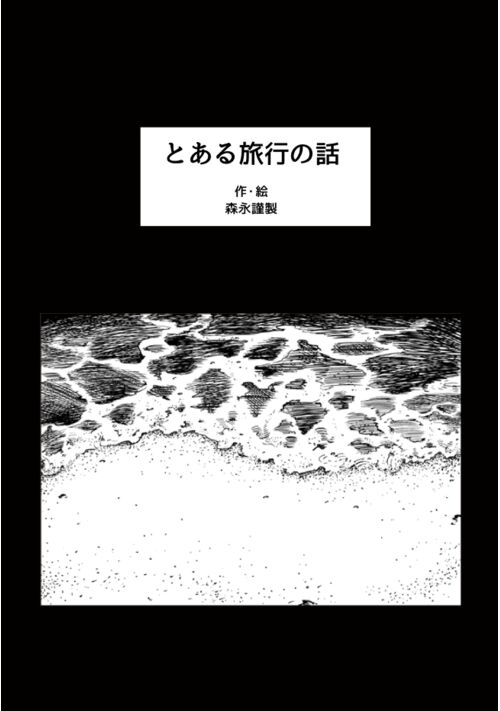
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















