6 / 15
第5話 余韻
しおりを挟む
眩しい朝陽が、寝台に横たわる王子の瞼を刺した。
ゆるりと目を開けた瞬間、全身に広がる気怠い感覚が押し寄せる。
「……っ……」
喉は乾き、身体は火照りの名残を残している。
まるで長い熱病に冒された後のような倦怠感。
けれど、それだけではなかった。
昨夜の記憶が、断片的に蘇る。
火照りに翻弄され、呼吸すら乱れていた自分。
その身を支え、抱きとめた温もり。
──低く、囁くような声。
『殿下……見てはなりません』
耳に残るその響きも息遣いも、夢のようであるのに現実の深みを持っていた。
「……影……」
思わず名を呼ぶ。
昨夜の触感が消えないのだ。
指先に残る、強く掴まれた跡。
背を支えられたときの硬質な体温。
目隠しをされたまま、熱を鎮められていったこの一夜。
夢であれば、これほど身体に残るはずがない。
だが、現実であるなら──。
「……私は……影に……」
言葉にするだけで、胸が焼ける。
もし現実ならば、それは掟を破ったことになるのか……?
──なのに、あの夜は確かに自分を包み、慰めてくれた。
頭では“職務として”だと理解している。
媚薬に苦しむ王子を救うため、それ以上の意味などないと。
けれど心は、どうしても違うと叫んでしまう。
(もし……あれがただの義務であったとしても……)
(私は……嬉しかった。救われたのだ……)
熱が引いたはずの胸の奥が、再び疼く。
あの時の腕の感触を思い出すたび、心臓は早鐘を打ち、呼吸が乱れる。
「……どうして、こんなにも……」
吐き出した声は震えていた。
叶わぬと知りながら、渇望は膨らむばかり。
もし、もう一度同じ状況に陥れば、抗える自信などない。
むしろ、心のどこかでそれを願ってしまっている。
「……苦しい……」
しばらく王子は動けなかった。昨夜の熱に囚われたまま──。
それは政務が始まっても変わらなかった。
昨夜から続く身体の重さ、肩に纏わりつく倦怠感が、
政務の合間にもあの熱を思い出させる。
「……」
頭を上げ、静まり返った執務室を見渡す。
見えるはずのない存在に向かって、王子は囁くように口を開いた。
「影……お前は、そこにいるのだろう」
もちろん返事はない。
だが、気配は確かにそこにあった。
夜も昼も、常に自分を見守り続ける沈黙の存在。
昨夜──熱に浮かされ、慰められた記憶。
夢にしてはあまりに鮮烈で、現実にしてはあまりに信じ難い。
影は確かにそこにいるのに、答えを聞くことは出来ない。
王子は拳を握り、さらに言葉を重ねる。
「もし現であったなら──なぜ、私に触れた?」
「なぜ……あのように、私を包んでくれたのだ?」
返答は沈黙。
だが、ほんの刹那、影の気配が揺れた気がした。
気配が揺らめき、王子の問いかけに触れたかのように。
そして──低く抑えた声が、確かに響いた。
『……私はただ、王家に仕える影。誰に対しても変わらず、
その務めを果たすのみでございます』
「……誰に対しても……」
その言葉は、刃のように胸に突き刺さった。
夢ではなかった──そう悟ると同時に、王子の心は締め付けられる。
それはつまり、自分だけが特別ではないということ。
昨夜の熱を鎮めた抱擁も、慰めも──任務の一環に過ぎなかったのだ。
「……そう、か」
(……なら、あの夜の熱も)
わかっている。影は掟に従う。王家の誰に対しても、同じ距離、同じ沈黙、同じ守り。
そうでなければならない存在だ。
けれど、理解と納得は別だ。理解しても、痛みは消えない。
王子は微笑んだ。
完璧な仮面を再びかぶり直すように。
けれどその笑みの裏で、胸は燃えるように痛んでいた。
◆
午後の政務。
重厚な書類を前に、臣下たちが次々と意見を述べる。
王子は表情を崩さず頷き、議論を導く。
その姿に誰も疑念を抱かない。
──だが心は、別のことに囚われていた。
(今も、いるのだろうか……)
臣下の言葉を聞き流しながら、気配を探してしまう。
視線を逸らし、柱の陰、天井の梁、背後の空気へ。
目には映らぬ存在を、意識の奥で追ってしまう。
(ここに……傍に……私だけを見てほしい……)
他の誰にではなく、自分だけに向けられたのだと。
──特別でありたい。
ただひとり、お前に選ばれたい。
そう願えば願うほど、理性の枷は音を立てて崩れていく。
王子は政務の場で堂々と微笑みながら、心の奥では影に縛られ、逃れられなくなっていた。
ゆるりと目を開けた瞬間、全身に広がる気怠い感覚が押し寄せる。
「……っ……」
喉は乾き、身体は火照りの名残を残している。
まるで長い熱病に冒された後のような倦怠感。
けれど、それだけではなかった。
昨夜の記憶が、断片的に蘇る。
火照りに翻弄され、呼吸すら乱れていた自分。
その身を支え、抱きとめた温もり。
──低く、囁くような声。
『殿下……見てはなりません』
耳に残るその響きも息遣いも、夢のようであるのに現実の深みを持っていた。
「……影……」
思わず名を呼ぶ。
昨夜の触感が消えないのだ。
指先に残る、強く掴まれた跡。
背を支えられたときの硬質な体温。
目隠しをされたまま、熱を鎮められていったこの一夜。
夢であれば、これほど身体に残るはずがない。
だが、現実であるなら──。
「……私は……影に……」
言葉にするだけで、胸が焼ける。
もし現実ならば、それは掟を破ったことになるのか……?
──なのに、あの夜は確かに自分を包み、慰めてくれた。
頭では“職務として”だと理解している。
媚薬に苦しむ王子を救うため、それ以上の意味などないと。
けれど心は、どうしても違うと叫んでしまう。
(もし……あれがただの義務であったとしても……)
(私は……嬉しかった。救われたのだ……)
熱が引いたはずの胸の奥が、再び疼く。
あの時の腕の感触を思い出すたび、心臓は早鐘を打ち、呼吸が乱れる。
「……どうして、こんなにも……」
吐き出した声は震えていた。
叶わぬと知りながら、渇望は膨らむばかり。
もし、もう一度同じ状況に陥れば、抗える自信などない。
むしろ、心のどこかでそれを願ってしまっている。
「……苦しい……」
しばらく王子は動けなかった。昨夜の熱に囚われたまま──。
それは政務が始まっても変わらなかった。
昨夜から続く身体の重さ、肩に纏わりつく倦怠感が、
政務の合間にもあの熱を思い出させる。
「……」
頭を上げ、静まり返った執務室を見渡す。
見えるはずのない存在に向かって、王子は囁くように口を開いた。
「影……お前は、そこにいるのだろう」
もちろん返事はない。
だが、気配は確かにそこにあった。
夜も昼も、常に自分を見守り続ける沈黙の存在。
昨夜──熱に浮かされ、慰められた記憶。
夢にしてはあまりに鮮烈で、現実にしてはあまりに信じ難い。
影は確かにそこにいるのに、答えを聞くことは出来ない。
王子は拳を握り、さらに言葉を重ねる。
「もし現であったなら──なぜ、私に触れた?」
「なぜ……あのように、私を包んでくれたのだ?」
返答は沈黙。
だが、ほんの刹那、影の気配が揺れた気がした。
気配が揺らめき、王子の問いかけに触れたかのように。
そして──低く抑えた声が、確かに響いた。
『……私はただ、王家に仕える影。誰に対しても変わらず、
その務めを果たすのみでございます』
「……誰に対しても……」
その言葉は、刃のように胸に突き刺さった。
夢ではなかった──そう悟ると同時に、王子の心は締め付けられる。
それはつまり、自分だけが特別ではないということ。
昨夜の熱を鎮めた抱擁も、慰めも──任務の一環に過ぎなかったのだ。
「……そう、か」
(……なら、あの夜の熱も)
わかっている。影は掟に従う。王家の誰に対しても、同じ距離、同じ沈黙、同じ守り。
そうでなければならない存在だ。
けれど、理解と納得は別だ。理解しても、痛みは消えない。
王子は微笑んだ。
完璧な仮面を再びかぶり直すように。
けれどその笑みの裏で、胸は燃えるように痛んでいた。
◆
午後の政務。
重厚な書類を前に、臣下たちが次々と意見を述べる。
王子は表情を崩さず頷き、議論を導く。
その姿に誰も疑念を抱かない。
──だが心は、別のことに囚われていた。
(今も、いるのだろうか……)
臣下の言葉を聞き流しながら、気配を探してしまう。
視線を逸らし、柱の陰、天井の梁、背後の空気へ。
目には映らぬ存在を、意識の奥で追ってしまう。
(ここに……傍に……私だけを見てほしい……)
他の誰にではなく、自分だけに向けられたのだと。
──特別でありたい。
ただひとり、お前に選ばれたい。
そう願えば願うほど、理性の枷は音を立てて崩れていく。
王子は政務の場で堂々と微笑みながら、心の奥では影に縛られ、逃れられなくなっていた。
2
あなたにおすすめの小説


沈黙のΩ、冷血宰相に拾われて溺愛されました
ホワイトヴァイス
BL
声を奪われ、競売にかけられたΩ《オメガ》――ノア。
落札したのは、冷血と呼ばれる宰相アルマン・ヴァルナティス。
“番契約”を偽装した取引から始まったふたりの関係は、
やがて国を揺るがす“真実”へとつながっていく。
喋れぬΩと、血を信じない宰相。
ただの契約だったはずの絆が、
互いの傷と孤独を少しずつ融かしていく。
だが、王都の夜に潜む副宰相ルシアンの影が、
彼らの「嘘」を暴こうとしていた――。
沈黙が祈りに変わるとき、
血の支配が終わりを告げ、
“番”の意味が書き換えられる。
冷血宰相×沈黙のΩ、
偽りの契約から始まる救済と革命の物語。

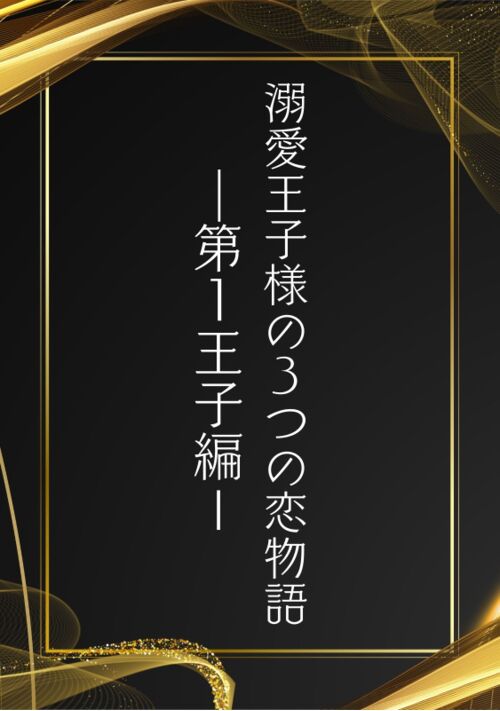
溺愛王子様の3つの恋物語~第1王子編~
結衣可
BL
生徒会副会長を務めるセオドア・ラインハルトは、冷静沈着で実直な青年。
学園の裏方として生徒会長クリストフを支える彼は、常に「縁の下の力持ち」として立場を確立していた。
そんなセオドアが王城へ同行した折、王国の次期国王と目される 第一王子レオナード・フォン・グランツ に出会う。
堂々たる風格と鋭い眼差し――その中に、一瞬だけ垣間見えた寂しさに、セオドアの胸は強く揺さぶられる。
一方のレオナードは、弟クリストフを支える副会長の聡明さと誠実さに興味を抱く。
「弟を支える柱」として出会ったセオドアに、いつしか彼自身にとっても特別な存在となっていく。

次元を歪めるほど愛してる
モカ
BL
白い世界で、俺は一人だった。
そこに新しい色を与えてくれたあの人。感謝してるし、大好きだった。俺に優しさをくれた優しい人たち。
それに報いたいと思っていた。けど、俺には何もなかったから…
「さぁ、我が贄よ。選ぶがいい」
でも見つけた。あの人たちに報いる方法を。俺の、存在の意味を。

抑制剤の効かない薬師オメガは森に隠れる。最強騎士団長に見つかり、聖なるフェロモンで理性を溶かされ、国を捨てた逃避行の果てに番となる
水凪しおん
BL
「この香りを嗅いだ瞬間、俺の本能は二つに引き裂かれた」
人里離れた森で暮らす薬師のエリアルは、抑制剤が効かない特異体質のオメガ。彼から放たれるフェロモンは万病を癒やす聖なる力を持つが、同時に理性を失わせる劇薬でもあった。
ある日、流行り病の特効薬を求めて森を訪れた最強の騎士団長・ジークフリートに見つかってしまう。エリアルの香りに強烈に反応しながらも、鋼の理性で耐え抜くジークフリート。
「俺が、貴方の剣となり盾となる」
国を救うための道具として狙われるエリアルを守るため、最強の騎士は地位も名誉も投げ捨て、国を敵に回す逃避行へと旅立つ。
シリアスから始まり、最後は辺境での幸せなスローライフへ。一途な騎士と健気な薬師の、運命のBLファンタジー。

捨てられた生贄オメガ、魔王城で極上の『巣作り』始めます!~不眠症の魔王様、私のクッションで爆睡して溺愛モードに突入~
水凪しおん
BL
「役立たずのオメガ」として冷遇され、血も涙もない魔王への生贄として捨てられたリノ。
死を覚悟して連れてこられた魔王城は、寒くて硬くて、居住性最悪のブラック環境だった!?
「こんなところで寝られるか!」
極限状態で発動したオメガ特有の『巣作り本能』と、神業レベルの裁縫スキルが火を噴く!
ゴミ同然の布切れをフカフカのクッションに、冷たい石床を極上のラグマットにリフォーム。
すると、不眠症で常にイライラしていた魔王ザルドリスが、リノの作った「巣」のあまりの快適さに陥落してしまい……?
「……貴様、私を堕落させる気か」
(※いいえ、ただ快適に寝たいだけです)
殺されるどころか、魔王様に気に入られ、気付けば城中がリノの虜に。
捨てられた生贄オメガが、裁縫一つで魔王城を「世界一のマイホーム」に変える、ほのぼの逆転溺愛ファンタジー!

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















