12 / 15
第11話 雨
しおりを挟む
午後の空は、灰色の雲に覆われていた。
王城の庭園を渡る風は冷たく、白百合の花弁がかすかに震える。
殿下が歩を進めると、すぐ傍で外套がふわりと広がり、
アルディスが寄り添っているのがわかる。
(もう、隠れていない。堂々と傍にいる――それだけのことで、どうして胸がこんなに安らぐのだろう)
ぽつ、ぽつ――やがて固い空から雨粒が落ち始め、白百合に重たい雫が宿った。
「……雨に降られるとはな」
殿下は苦笑し、外套の裾をつまむ。湿り気を含んだ布が指に重く絡み、石畳は急に滑りやすくなった。
ほんの一瞬の傾き。
靴底が濡れた面を滑り、視界が傾ぐ。
「――殿下!」
反射で伸びた腕。
片眼で測る距離はわずかに狂う――だからこそ、余計に強く抱き寄せた。
外套ごと殿下の身体が胸に収まり、冷えた雨と、内側から立ちのぼる体温がぶつかり合う。
「……大丈夫ですか」
声が掠れた。思った以上に震えてもいた。
殿下は腕の中で息を整え、ゆっくり顔を上げる。
濡れた睫毛からひとしずくが落ち、紅の瞳がまっすぐ刺し込む。
雨音の幕の向こうで、時間が少し滞る。
「大丈夫だ。……それより」
「それより……?」
「お前に守られるのは……心地よい」
胸の奥で、何かが一気に脈打った。
理性が「手を放せ」と命じるのに、身体は言うことを聞かない。
「……殿下」
呼ぶ声が低く沈む。そこから先が喉につかえたように続かない。
雨は容赦なく二人を濡らしてゆく。
だがアルディスの胸の中で震える微かな体温が、冷たさをかき消してしまう。
「私は……お前の腕は、安心する」
殿下の声が、雨と同じくらい静かに落ちる。
「アルディス、お前の傍は心地よい」
噛み殺していた何かが、そこで音を立てた。
腕の力を緩められない――むしろ、無意識に強く抱き締めてしまう。
「……殿下、そんなこと言われては離すことができません」
心の声が、ついに唇を越えた。
殿下はぱちりと瞬き、次の瞬間、ふっと頬を緩める。
「アルディス、しばらくこのままで」
雨音が、世界の輪郭をやさしくぼかす。
庭園には二人だけ。
アルディスは初めて知る――守るという行いが、自分自身の心に甘い痕を刻んでゆくことを。
(いけない。もっと距離を――
……いや、もう)
理性は後退し、欲望は確かに前へ出る。
外套の内側で、二つの鼓動が重なっていた。
◆
その夜、殿下は熱に伏した。
雨に濡れた身体を温める間もなく政務へ戻ったせいだ。
寝台の上、白い額が薄紅に染まり、呼吸は浅い。
「……殿下」
額に触れた指先に、明確な熱。
アルディスの眉間に自然と皺が寄る。
「側近である私が……申し訳ございません」
椅子を寝台の傍へ引き寄せ、夜着の襟元を整える。
押し上げられた喉の線がかすかに震え、胸板の上下に合わせて寝具がわずかに鳴った。
半ば夢の底から、紅の瞳が揺れる。
「……アルディス……」
「はい」
「……お前は、大丈夫なのか」
「はい、殿下」
「そうか……手を」
熱に浮かされた声は、とたんに幼い。
頼ることを学ばなかった王子が、ようやく掴めた細い綱のように差し出している。
「……アルディス……手を。このまま傍に」
震える指が縋る。汗ばむ掌が、必死に何かを確かめようとしている。
その体温が、皮膚越しに胸まで上ってくる。
(殿下……)
アルディスはそっと手を重ねた。
指と指を絡めるのは、線を一つ越えることに思えた――だから、掌を包み込む。
それでも十分すぎるほど、心が鳴った。
「……お傍におります」
自分の声が、思った以上に掠れている。
殿下は微笑み、安心の吐息とともに瞼を下ろした。
「……ありがとう……アルディス」
その微笑が「自分に向けられている」事実だけで、胸の内側が灼けるように疼く。
理性が慌てて鎮火に走る。だが火は、もう静かに、広く燃え移っていた。
◆
夜半。
殿下は浅い眠りの中で何度も寝返りを打ち、そのたびに指がきゅっと強まる。
離すまいとするその仕草に、アルディスは一睡もできなかった。
窓外の雲がきれ、薄い月が部屋の隅を照らす。
白い光が寝台の端に溜まり、殿下の髪に銀の縁を与えた。
額へ、頬へ、汗が細い道を描く。喉元に触れる空気は熱っぽく、時折、微かな喘ぎが混じる。
(苦しいのか、殿下……)
前髪が汗に張りついている。
アルディスは躊躇い、そしてそっと指先でそれを払った。
触れた瞬間、胸の奥で雷のような明滅。
理性が警鐘を鳴らす――これ以上は。
欲望は囁く――これくらいは。
「……殿下」
答えはない。
握られた手が小さく握り返す。
意識の底から、それでも掴みたいと願うように。
「私は、今まで影として殿下のお傍におりました。
今は騎士として、側近として傍に仕えております。
けれど――この身を、生涯、貴方の隣に置いてほしいと願わずにいられません」
言ってしまった。
月影が胸を過ぎ、沈黙が降りる。
寝台の端で、殿下の指がまた小さく動いた。まるで返事のように。
唇を噛む。
掌で包んだ熱が、ゆっくりとこちらへ移ってくる。
夜気は冷たいのに、腕の内側がじんわり汗ばむ。
喉が渇き、水ではないものを欲していた。
(守ることと、求めることは違う。
私は守るためにここにいる。
――しかし、これからきっと求めてしまうだろう)
影の頃にはなかった震えが、指先に宿る。
それを見ているのは自分だけ。
殿下は眠りの底で、安堵に頬を緩めた。
夜は更け、雨上がりの匂いが窓から忍び込む。
絡めないはずのもの――義務と願い、理性と渇望――が、静かに、確かに結び付き始めていた。
二人の手は、離れなかった。
月が傾き、鳥が鳴くまで。
そして心のどこかで、二人とも気づいている――
この手は、もう簡単には離せない、ということに。
王城の庭園を渡る風は冷たく、白百合の花弁がかすかに震える。
殿下が歩を進めると、すぐ傍で外套がふわりと広がり、
アルディスが寄り添っているのがわかる。
(もう、隠れていない。堂々と傍にいる――それだけのことで、どうして胸がこんなに安らぐのだろう)
ぽつ、ぽつ――やがて固い空から雨粒が落ち始め、白百合に重たい雫が宿った。
「……雨に降られるとはな」
殿下は苦笑し、外套の裾をつまむ。湿り気を含んだ布が指に重く絡み、石畳は急に滑りやすくなった。
ほんの一瞬の傾き。
靴底が濡れた面を滑り、視界が傾ぐ。
「――殿下!」
反射で伸びた腕。
片眼で測る距離はわずかに狂う――だからこそ、余計に強く抱き寄せた。
外套ごと殿下の身体が胸に収まり、冷えた雨と、内側から立ちのぼる体温がぶつかり合う。
「……大丈夫ですか」
声が掠れた。思った以上に震えてもいた。
殿下は腕の中で息を整え、ゆっくり顔を上げる。
濡れた睫毛からひとしずくが落ち、紅の瞳がまっすぐ刺し込む。
雨音の幕の向こうで、時間が少し滞る。
「大丈夫だ。……それより」
「それより……?」
「お前に守られるのは……心地よい」
胸の奥で、何かが一気に脈打った。
理性が「手を放せ」と命じるのに、身体は言うことを聞かない。
「……殿下」
呼ぶ声が低く沈む。そこから先が喉につかえたように続かない。
雨は容赦なく二人を濡らしてゆく。
だがアルディスの胸の中で震える微かな体温が、冷たさをかき消してしまう。
「私は……お前の腕は、安心する」
殿下の声が、雨と同じくらい静かに落ちる。
「アルディス、お前の傍は心地よい」
噛み殺していた何かが、そこで音を立てた。
腕の力を緩められない――むしろ、無意識に強く抱き締めてしまう。
「……殿下、そんなこと言われては離すことができません」
心の声が、ついに唇を越えた。
殿下はぱちりと瞬き、次の瞬間、ふっと頬を緩める。
「アルディス、しばらくこのままで」
雨音が、世界の輪郭をやさしくぼかす。
庭園には二人だけ。
アルディスは初めて知る――守るという行いが、自分自身の心に甘い痕を刻んでゆくことを。
(いけない。もっと距離を――
……いや、もう)
理性は後退し、欲望は確かに前へ出る。
外套の内側で、二つの鼓動が重なっていた。
◆
その夜、殿下は熱に伏した。
雨に濡れた身体を温める間もなく政務へ戻ったせいだ。
寝台の上、白い額が薄紅に染まり、呼吸は浅い。
「……殿下」
額に触れた指先に、明確な熱。
アルディスの眉間に自然と皺が寄る。
「側近である私が……申し訳ございません」
椅子を寝台の傍へ引き寄せ、夜着の襟元を整える。
押し上げられた喉の線がかすかに震え、胸板の上下に合わせて寝具がわずかに鳴った。
半ば夢の底から、紅の瞳が揺れる。
「……アルディス……」
「はい」
「……お前は、大丈夫なのか」
「はい、殿下」
「そうか……手を」
熱に浮かされた声は、とたんに幼い。
頼ることを学ばなかった王子が、ようやく掴めた細い綱のように差し出している。
「……アルディス……手を。このまま傍に」
震える指が縋る。汗ばむ掌が、必死に何かを確かめようとしている。
その体温が、皮膚越しに胸まで上ってくる。
(殿下……)
アルディスはそっと手を重ねた。
指と指を絡めるのは、線を一つ越えることに思えた――だから、掌を包み込む。
それでも十分すぎるほど、心が鳴った。
「……お傍におります」
自分の声が、思った以上に掠れている。
殿下は微笑み、安心の吐息とともに瞼を下ろした。
「……ありがとう……アルディス」
その微笑が「自分に向けられている」事実だけで、胸の内側が灼けるように疼く。
理性が慌てて鎮火に走る。だが火は、もう静かに、広く燃え移っていた。
◆
夜半。
殿下は浅い眠りの中で何度も寝返りを打ち、そのたびに指がきゅっと強まる。
離すまいとするその仕草に、アルディスは一睡もできなかった。
窓外の雲がきれ、薄い月が部屋の隅を照らす。
白い光が寝台の端に溜まり、殿下の髪に銀の縁を与えた。
額へ、頬へ、汗が細い道を描く。喉元に触れる空気は熱っぽく、時折、微かな喘ぎが混じる。
(苦しいのか、殿下……)
前髪が汗に張りついている。
アルディスは躊躇い、そしてそっと指先でそれを払った。
触れた瞬間、胸の奥で雷のような明滅。
理性が警鐘を鳴らす――これ以上は。
欲望は囁く――これくらいは。
「……殿下」
答えはない。
握られた手が小さく握り返す。
意識の底から、それでも掴みたいと願うように。
「私は、今まで影として殿下のお傍におりました。
今は騎士として、側近として傍に仕えております。
けれど――この身を、生涯、貴方の隣に置いてほしいと願わずにいられません」
言ってしまった。
月影が胸を過ぎ、沈黙が降りる。
寝台の端で、殿下の指がまた小さく動いた。まるで返事のように。
唇を噛む。
掌で包んだ熱が、ゆっくりとこちらへ移ってくる。
夜気は冷たいのに、腕の内側がじんわり汗ばむ。
喉が渇き、水ではないものを欲していた。
(守ることと、求めることは違う。
私は守るためにここにいる。
――しかし、これからきっと求めてしまうだろう)
影の頃にはなかった震えが、指先に宿る。
それを見ているのは自分だけ。
殿下は眠りの底で、安堵に頬を緩めた。
夜は更け、雨上がりの匂いが窓から忍び込む。
絡めないはずのもの――義務と願い、理性と渇望――が、静かに、確かに結び付き始めていた。
二人の手は、離れなかった。
月が傾き、鳥が鳴くまで。
そして心のどこかで、二人とも気づいている――
この手は、もう簡単には離せない、ということに。
3
あなたにおすすめの小説

次元を歪めるほど愛してる
モカ
BL
白い世界で、俺は一人だった。
そこに新しい色を与えてくれたあの人。感謝してるし、大好きだった。俺に優しさをくれた優しい人たち。
それに報いたいと思っていた。けど、俺には何もなかったから…
「さぁ、我が贄よ。選ぶがいい」
でも見つけた。あの人たちに報いる方法を。俺の、存在の意味を。


沈黙のΩ、冷血宰相に拾われて溺愛されました
ホワイトヴァイス
BL
声を奪われ、競売にかけられたΩ《オメガ》――ノア。
落札したのは、冷血と呼ばれる宰相アルマン・ヴァルナティス。
“番契約”を偽装した取引から始まったふたりの関係は、
やがて国を揺るがす“真実”へとつながっていく。
喋れぬΩと、血を信じない宰相。
ただの契約だったはずの絆が、
互いの傷と孤独を少しずつ融かしていく。
だが、王都の夜に潜む副宰相ルシアンの影が、
彼らの「嘘」を暴こうとしていた――。
沈黙が祈りに変わるとき、
血の支配が終わりを告げ、
“番”の意味が書き換えられる。
冷血宰相×沈黙のΩ、
偽りの契約から始まる救済と革命の物語。
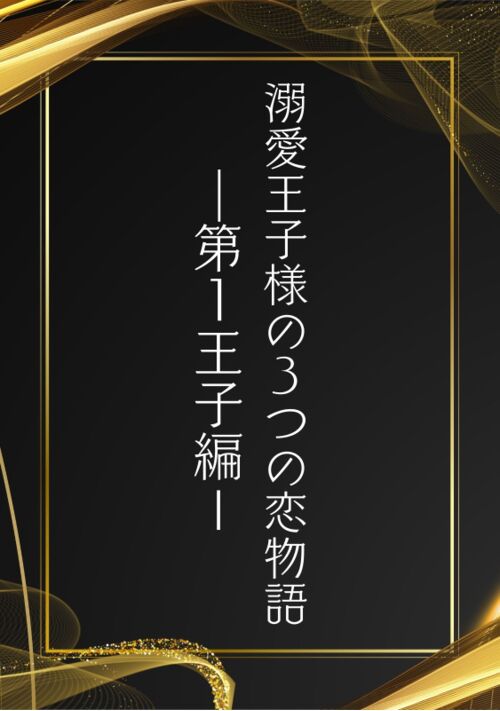
溺愛王子様の3つの恋物語~第1王子編~
結衣可
BL
生徒会副会長を務めるセオドア・ラインハルトは、冷静沈着で実直な青年。
学園の裏方として生徒会長クリストフを支える彼は、常に「縁の下の力持ち」として立場を確立していた。
そんなセオドアが王城へ同行した折、王国の次期国王と目される 第一王子レオナード・フォン・グランツ に出会う。
堂々たる風格と鋭い眼差し――その中に、一瞬だけ垣間見えた寂しさに、セオドアの胸は強く揺さぶられる。
一方のレオナードは、弟クリストフを支える副会長の聡明さと誠実さに興味を抱く。
「弟を支える柱」として出会ったセオドアに、いつしか彼自身にとっても特別な存在となっていく。


抑制剤の効かない薬師オメガは森に隠れる。最強騎士団長に見つかり、聖なるフェロモンで理性を溶かされ、国を捨てた逃避行の果てに番となる
水凪しおん
BL
「この香りを嗅いだ瞬間、俺の本能は二つに引き裂かれた」
人里離れた森で暮らす薬師のエリアルは、抑制剤が効かない特異体質のオメガ。彼から放たれるフェロモンは万病を癒やす聖なる力を持つが、同時に理性を失わせる劇薬でもあった。
ある日、流行り病の特効薬を求めて森を訪れた最強の騎士団長・ジークフリートに見つかってしまう。エリアルの香りに強烈に反応しながらも、鋼の理性で耐え抜くジークフリート。
「俺が、貴方の剣となり盾となる」
国を救うための道具として狙われるエリアルを守るため、最強の騎士は地位も名誉も投げ捨て、国を敵に回す逃避行へと旅立つ。
シリアスから始まり、最後は辺境での幸せなスローライフへ。一途な騎士と健気な薬師の、運命のBLファンタジー。

捨てられた生贄オメガ、魔王城で極上の『巣作り』始めます!~不眠症の魔王様、私のクッションで爆睡して溺愛モードに突入~
水凪しおん
BL
「役立たずのオメガ」として冷遇され、血も涙もない魔王への生贄として捨てられたリノ。
死を覚悟して連れてこられた魔王城は、寒くて硬くて、居住性最悪のブラック環境だった!?
「こんなところで寝られるか!」
極限状態で発動したオメガ特有の『巣作り本能』と、神業レベルの裁縫スキルが火を噴く!
ゴミ同然の布切れをフカフカのクッションに、冷たい石床を極上のラグマットにリフォーム。
すると、不眠症で常にイライラしていた魔王ザルドリスが、リノの作った「巣」のあまりの快適さに陥落してしまい……?
「……貴様、私を堕落させる気か」
(※いいえ、ただ快適に寝たいだけです)
殺されるどころか、魔王様に気に入られ、気付けば城中がリノの虜に。
捨てられた生贄オメガが、裁縫一つで魔王城を「世界一のマイホーム」に変える、ほのぼの逆転溺愛ファンタジー!

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















