8 / 17
8話 魔法を解かれて
しおりを挟む
ゆっくりと目を開くと、窓から差し込む優しい光が、私の視界を柔らかく照らし出した。
微睡みのような感覚から覚醒するにつれ、ぼやけた視界が徐々にクリアになっていく。
「ふぁ……っ!!!!!!」
のんきに伸びをしようとした私は、目の前の光景に気付き、声にならぬ悲鳴を漏らした。
見開いた目に映った鮮明な視界の中に、酷く顔色を悪くしたリアスの顔が飛び込んできたのだ。
あまりに具合が悪そうで、心臓が縮み上がった。
すると、何を勘違いしたのだろうか。
目覚めた私の反応を見るなり、リアスはただでさえ血の気を失ったような顔に、絶望の影を落として口を開いた。
「ちゃんと、魔法が解けたみたいだね……。本当に今までごめん。すぐに離婚の手続きをするから――」
「待って、リアス」
サッとベッドから起き上がり、私はぎこちなく口を動かす顔面蒼白になった彼の手を掴んだ。
そして告げた。
「私、あなたのことが好きよ」
「え?」
「私、ちゃんとあなたのことが好き……。魅了魔法にかかっていなかったみたいっ……!」
心の曇空が一気に晴れ上がるようだった。
私がリアスを愛する気持ちは、目覚めてもなお健在だったのだ。
リアスを見るだけで愛おしく感じるし、彼の戸惑う姿すら可愛く思える。
抱き締めたりキスしたりすることだって、厭わず彼にしてあげたいと思える。
――これで好きじゃないなんて、ありえないわ。
嬉しさが込み上げた私はその想いが伝わればと、はしゃぎながら彼の首に腕を回して頬に口付けた。
「リアス、私たち離婚せずに済むわね!」
そう言ったところ、なぜかリアスは私の腕を掴んでするりとその頭を抜いた。
「リアス?」
予想外の行動に戸惑い彼を見つめると、真顔のまま目だけを見開き、顔を真っ赤に染め上げた彼の姿が映った。
また、彼は見つめる私と目が合うなり、キスした頬にパッと手の甲を添え、信じ難いものでも見るような視線をこちらに向けた。
リアスのこの挙動に、私は思わず首を傾げた。
魔法は解けて一件落着のはずなのに、どうしてこのような反応をするのか分からないのだ。
すると、リアスが突然後ろに振り返った。
「どうなってる!? 魔法を解くのに失敗したのかっ?」
リアスが驚きの籠った声を発した方を見ると、そこにはアルチーナがいた。
彼女はリアスにかけられた言葉がよほど心外だったのだろう。軽く眉をひそめ、肘を覆うように腕を組み直した。
「そんなわけないじゃない。ちゃんと魔法は解けているはずよ」
非常に落ち着き払った声だった。
だが、リアスはどうにも納得できないらしく、再び口を開いた。
「じゃあ、どうしてエリーゼはこんなことを言うんだ?」
「それは……奥様があなたを好きだからじゃない?」
よく言ったわ、アルチーナ。
私は彼女の返しに、心の中で鳴り止まぬ拍手を送りながら賛同した。
まさにその通りだもの。
しかし、リアスは懲りなかった。
「そんなわけない。きっと魅了魔法が残っているから、こんなことを言うんだ」
そう言い張るリアスの言葉に、私は自身の耳を疑った。
――アルチーナは分かるのに、どうして夫のリアスが分かってくれないの?
私にかけられていた魅了魔法が解けたと、リアスがあまりに信じてくれない。
そのため、私は辛抱たまらず彼に声をかけた。
「ねえ、リアス」
名前を呼ぶと、背を向けていた彼が私の方に反射的な速さで向き直った。
「私にかけられた魔法はちゃんと解けたわよ。どうして頑なに否定するの?」
「っ……」
リアスは根拠もなしに、誰かを疑うような人ではない。二年も夫婦をしていれば、それくらい分かる。
「ねえ、リアス。教えてちょうだい。何かそう思う理由があるんでしょう?」
彼の本音を聞き出そうと、あえて優しく声をかけた。
すると途端に、リアスは言いようのない悔しさを滲ませるように顔を歪ませた。
「……ロベルト・ウィンクラー」
「え?」
「君が本当に好きなのは、ロベルト・ウィンクラーのはずだからだ」
あまりに想定外過ぎる。そんな人物の名前を出されて、私は思わず動揺した。
「どうして、そこでロビンが出てくるの?」
まるで意味が分からなかった。
だが、リアスにはそう考えた彼なりの理由があるのだろう。
記憶の片端から疑われそうなことを懸命に思い出していると、彼の方が先に口を開いた。
「君がロベルト卿に、二十歳までに婚約者ができなかったら結婚しようと言われて、いいよって答えていたじゃないか」
リアスの言葉を聞き、背後のアルチーナが「あらやだ、奥様!」なんて声を漏らす。
一方、リアスはこれまでのとめどない思いを溢れさせるように、早口で言葉を続けた。
「俺が魅了魔法をかけたきっかけは、間違いなく彼の存在があったからだ。エリーゼを他の誰のものにもしたくなかったっ……」
彼はそこまで言うと、深呼吸のようなため息をついた。続けて、弱り切ったか弱い声を零した。
「あのとき君は、あと半年もすれば二十歳だった。だから……焦ったんだ」
……まさか、リアスがロビンのことをこんなにも気にしていたとは。
これまで一度たりとも、そう考えたことは無かった。
思ってもみなかった。
ロビンこと、ロベルト・ウィンクラー。
彼は確かに、当時十九歳の私に結婚しようと言った。私も間違いなく、その話に乗った。
ただ私の場合、ベルガー公爵家が行き遅れの娘がいる家門だと泥を塗られないようにする、という目的ありきで成立したもの。
つまり、貴族としての義務を果たしつつ、双方の社会的地位を保証するための結婚話だったのだ。
だから、私は彼に恋情という思いは欠片も抱いていなかったし、今も抱いていない。
それは彼も同じはずだ。
だって、そもそもの私とロビンの関係は、実質姉弟だったから。
微睡みのような感覚から覚醒するにつれ、ぼやけた視界が徐々にクリアになっていく。
「ふぁ……っ!!!!!!」
のんきに伸びをしようとした私は、目の前の光景に気付き、声にならぬ悲鳴を漏らした。
見開いた目に映った鮮明な視界の中に、酷く顔色を悪くしたリアスの顔が飛び込んできたのだ。
あまりに具合が悪そうで、心臓が縮み上がった。
すると、何を勘違いしたのだろうか。
目覚めた私の反応を見るなり、リアスはただでさえ血の気を失ったような顔に、絶望の影を落として口を開いた。
「ちゃんと、魔法が解けたみたいだね……。本当に今までごめん。すぐに離婚の手続きをするから――」
「待って、リアス」
サッとベッドから起き上がり、私はぎこちなく口を動かす顔面蒼白になった彼の手を掴んだ。
そして告げた。
「私、あなたのことが好きよ」
「え?」
「私、ちゃんとあなたのことが好き……。魅了魔法にかかっていなかったみたいっ……!」
心の曇空が一気に晴れ上がるようだった。
私がリアスを愛する気持ちは、目覚めてもなお健在だったのだ。
リアスを見るだけで愛おしく感じるし、彼の戸惑う姿すら可愛く思える。
抱き締めたりキスしたりすることだって、厭わず彼にしてあげたいと思える。
――これで好きじゃないなんて、ありえないわ。
嬉しさが込み上げた私はその想いが伝わればと、はしゃぎながら彼の首に腕を回して頬に口付けた。
「リアス、私たち離婚せずに済むわね!」
そう言ったところ、なぜかリアスは私の腕を掴んでするりとその頭を抜いた。
「リアス?」
予想外の行動に戸惑い彼を見つめると、真顔のまま目だけを見開き、顔を真っ赤に染め上げた彼の姿が映った。
また、彼は見つめる私と目が合うなり、キスした頬にパッと手の甲を添え、信じ難いものでも見るような視線をこちらに向けた。
リアスのこの挙動に、私は思わず首を傾げた。
魔法は解けて一件落着のはずなのに、どうしてこのような反応をするのか分からないのだ。
すると、リアスが突然後ろに振り返った。
「どうなってる!? 魔法を解くのに失敗したのかっ?」
リアスが驚きの籠った声を発した方を見ると、そこにはアルチーナがいた。
彼女はリアスにかけられた言葉がよほど心外だったのだろう。軽く眉をひそめ、肘を覆うように腕を組み直した。
「そんなわけないじゃない。ちゃんと魔法は解けているはずよ」
非常に落ち着き払った声だった。
だが、リアスはどうにも納得できないらしく、再び口を開いた。
「じゃあ、どうしてエリーゼはこんなことを言うんだ?」
「それは……奥様があなたを好きだからじゃない?」
よく言ったわ、アルチーナ。
私は彼女の返しに、心の中で鳴り止まぬ拍手を送りながら賛同した。
まさにその通りだもの。
しかし、リアスは懲りなかった。
「そんなわけない。きっと魅了魔法が残っているから、こんなことを言うんだ」
そう言い張るリアスの言葉に、私は自身の耳を疑った。
――アルチーナは分かるのに、どうして夫のリアスが分かってくれないの?
私にかけられていた魅了魔法が解けたと、リアスがあまりに信じてくれない。
そのため、私は辛抱たまらず彼に声をかけた。
「ねえ、リアス」
名前を呼ぶと、背を向けていた彼が私の方に反射的な速さで向き直った。
「私にかけられた魔法はちゃんと解けたわよ。どうして頑なに否定するの?」
「っ……」
リアスは根拠もなしに、誰かを疑うような人ではない。二年も夫婦をしていれば、それくらい分かる。
「ねえ、リアス。教えてちょうだい。何かそう思う理由があるんでしょう?」
彼の本音を聞き出そうと、あえて優しく声をかけた。
すると途端に、リアスは言いようのない悔しさを滲ませるように顔を歪ませた。
「……ロベルト・ウィンクラー」
「え?」
「君が本当に好きなのは、ロベルト・ウィンクラーのはずだからだ」
あまりに想定外過ぎる。そんな人物の名前を出されて、私は思わず動揺した。
「どうして、そこでロビンが出てくるの?」
まるで意味が分からなかった。
だが、リアスにはそう考えた彼なりの理由があるのだろう。
記憶の片端から疑われそうなことを懸命に思い出していると、彼の方が先に口を開いた。
「君がロベルト卿に、二十歳までに婚約者ができなかったら結婚しようと言われて、いいよって答えていたじゃないか」
リアスの言葉を聞き、背後のアルチーナが「あらやだ、奥様!」なんて声を漏らす。
一方、リアスはこれまでのとめどない思いを溢れさせるように、早口で言葉を続けた。
「俺が魅了魔法をかけたきっかけは、間違いなく彼の存在があったからだ。エリーゼを他の誰のものにもしたくなかったっ……」
彼はそこまで言うと、深呼吸のようなため息をついた。続けて、弱り切ったか弱い声を零した。
「あのとき君は、あと半年もすれば二十歳だった。だから……焦ったんだ」
……まさか、リアスがロビンのことをこんなにも気にしていたとは。
これまで一度たりとも、そう考えたことは無かった。
思ってもみなかった。
ロビンこと、ロベルト・ウィンクラー。
彼は確かに、当時十九歳の私に結婚しようと言った。私も間違いなく、その話に乗った。
ただ私の場合、ベルガー公爵家が行き遅れの娘がいる家門だと泥を塗られないようにする、という目的ありきで成立したもの。
つまり、貴族としての義務を果たしつつ、双方の社会的地位を保証するための結婚話だったのだ。
だから、私は彼に恋情という思いは欠片も抱いていなかったし、今も抱いていない。
それは彼も同じはずだ。
だって、そもそもの私とロビンの関係は、実質姉弟だったから。
411
あなたにおすすめの小説

『恋心を凍らせる薬を飲みました』 - 残りの学園生活、どうぞご自由にお遊びください、婚約者様
恋せよ恋
恋愛
愛されることを諦めた。だから、私は心を凍らせた。
不誠実な婚約者・ユリアンの冷遇に耐えかねたヤスミンは、
伝説の魔女の元を訪れ、恋心を消し去る「氷の薬」を飲む。
感情を捨て、完璧な「人形」となった彼女を前に、
ユリアンは初めて己の罪と執着に狂い始める。
「お願いだ、前のように僕を愛して泣いてくれ!」
足元に跪き、涙を流して乞う男に、ヤスミンは冷酷に微笑む。
「愛?……あいにく、そのような無駄な感情は捨てましたわ」
一度凍りついた心は、二度と溶けない。
後悔にのたうち回る男と、心を凍らせた冷徹な公爵夫人の、
終わりのない贖罪の記録。
🔶登場人物・設定は筆者の創作によるものです。
🔶不快に感じられる表現がありましたらお詫び申し上げます。
🔶誤字脱字・文の調整は、投稿後にも随時行います。
🔶今後もこの世界観で物語を続けてまいります。
🔶 『エール📣』『いいね❤️』励みになります!

今夜で忘れる。
豆狸
恋愛
「……今夜で忘れます」
そう言って、私はジョアキン殿下を見つめました。
黄金の髪に緑色の瞳、鼻筋の通った端正な顔を持つ、我がソアレス王国の第二王子。大陸最大の図書館がそびえる学術都市として名高いソアレスの王都にある大学を卒業するまでは、侯爵令嬢の私の婚約者だった方です。
今はお互いに別の方と婚約しています。
「忘れると誓います。ですから、幼いころからの想いに決着をつけるため、どうか私にジョアキン殿下との一夜をくださいませ」
なろう様でも公開中です。

裏切りの街 ~すれ違う心~
緑谷めい
恋愛
エマは裏切られた。付き合って1年になる恋人リュカにだ。ある日、リュカとのデート中、街の裏通りに突然一人置き去りにされたエマ。リュカはエマを囮にした。彼は騎士としての手柄欲しさにエマを利用したのだ。※ 全5話完結予定
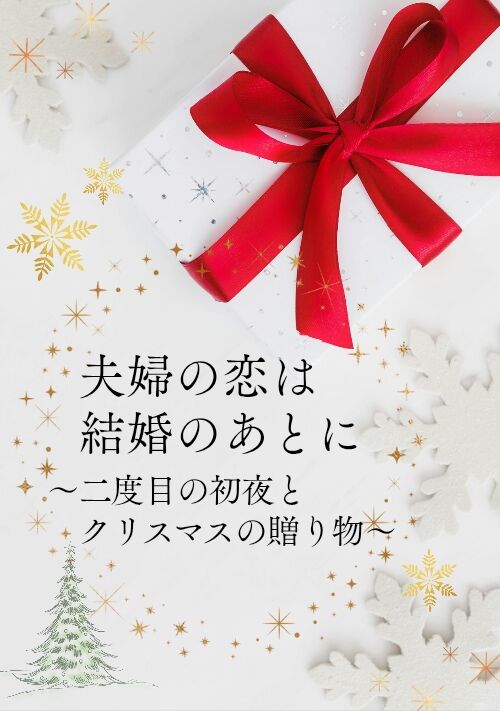
夫婦の恋は結婚のあとに 〜二度目の初夜とクリスマスの贈り物〜
出 万璃玲
恋愛
「エーミル、今年はサンタさんに何をお願いするの?」
「あのね、僕、弟か妹が欲しい!」
四歳の息子の純真無垢な願いを聞いて、アマーリアは固まった。愛のない結婚をした夫と関係を持ったのは、初夜の一度きり。弟か妹が生まれる可能性は皆無。だが、彼女は息子を何よりも愛していた。
「愛するエーミルの願いを無下にするなんてできない」。そう決意したアマーリアは、サンタ……もとい、夫ヴィンフリートに直談判する。
仕事人間でほとんど家にいない無愛想な夫ヴィンフリート、はじめから結婚に期待のなかった妻アマーリア。
不器用な夫婦それぞれの想いの行方は、果たして……?
――政略結婚からすれ違い続けた夫婦の、静かな「恋のやり直し」。
しっとりとした大人の恋愛と、あたたかな家族愛の物語です。
(おまけSS含め、約10000字の短編です。他サイト掲載あり。表紙はcanvaを使用。)

【完結】旦那に愛人がいると知ってから
よどら文鳥
恋愛
私(ジュリアーナ)は旦那のことをヒーローだと思っている。だからこそどんなに性格が変わってしまっても、いつの日か優しかった旦那に戻ることを願って今もなお愛している。
だが、私の気持ちなどお構いなく、旦那からの容赦ない暴言は絶えない。当然だが、私のことを愛してはくれていないのだろう。
それでも好きでいられる思い出があったから耐えてきた。
だが、偶然にも旦那が他の女と腕を組んでいる姿を目撃してしまった。
「……あの女、誰……!?」
この事件がきっかけで、私の大事にしていた思い出までもが崩れていく。
だが、今までの苦しい日々から解放される試練でもあった。
※前半が暗すぎるので、明るくなってくるところまで一気に更新しました。


セレナの居場所 ~下賜された側妃~
緑谷めい
恋愛
後宮が廃され、国王エドガルドの側妃だったセレナは、ルーベン・アルファーロ侯爵に下賜された。自らの新たな居場所を作ろうと努力するセレナだったが、夫ルーベンの幼馴染だという伯爵家令嬢クラーラが頻繁に屋敷を訪れることに違和感を覚える。

悪役令嬢として、愛し合う二人の邪魔をしてきた報いは受けましょう──ですが、少々しつこすぎやしませんか。
ふまさ
恋愛
「──いい加減、ぼくにつきまとうのはやめろ!」
ぱんっ。
愛する人にはじめて頬を打たれたマイナの心臓が、どくん、と大きく跳ねた。
甘やかされて育ってきたマイナにとって、それはとてつもない衝撃だったのだろう。そのショックからか。前世のものであろう記憶が、マイナの頭の中を一気にぐるぐると駆け巡った。
──え?
打たれた衝撃で横を向いていた顔を、真正面に向ける。王立学園の廊下には大勢の生徒が集まり、その中心には、三つの人影があった。一人は、マイナ。目の前には、この国の第一王子──ローランドがいて、その隣では、ローランドの愛する婚約者、伯爵令嬢のリリアンが怒りで目を吊り上げていた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















