10 / 17
10話 信じていいのに
しおりを挟む
私は誤解を解くべく、リアスに慌てて声をかけた。
「リアス、心配かけてごめんなさい。でも、私たちはそんな深い意味なく約束をしただけなの」
何だか私が浮気の弁明をしているかのような気持ちになってくる。
本当にそう言うんじゃないのに。
私がそう思う一方、リアスは納得できない様子で口を開いた。
「そんなはずないよ。だって、夜会のときに君たち仲睦まじそうだったじゃないか」
「例えば?」
「エリーゼがロベルト卿の髪をバルコニーで結んでいただろう?」
気付いている人は誰もいないと思っていたけれど、まさかリアスが見ていただなんて。
「あれはアクシデントよ」
きっと、リアスはあのときのことを言っているのだろう。
ある王城主催の夜会に招待されたとき、一緒に出席していたロビンの髪紐が千切れてしまったことがあった。
ロビンは癖毛が悩みで、いつも髪を伸ばして三つ編みにしていた。そのため、何かあったとき用に、彼は常に髪紐の替えを携帯していた。
だが、その日はあいにくロビンは替えを持ち合わせていなかったのだ。
普段なら、こっそりその場から居なくなって、自分で括り直して戻ってくる。しかし、そのときばかりはそうともいかなかった。
幸いなことに、その日の私はリボンを二つ使って、髪をセットしていた。
そのため、ロビンをバルコニーに連れて行き、応急処置として私のリボンでロビンの髪を括り直してあげたのだ。
時間をかけて結い上げたセットが崩れたと、ロビンが心底申し訳なさそうにしていたことをよく覚えている。
ハーフアップになっただけなのに、崩れたも何もないんだけど。
ロビンは一通り私に謝る終わると、リボンを見て恥ずかしそうに顔を赤らめていた。
女もののリボンだから、そりゃあ恥ずかしいわよね。そう思いながら、私は気を紛らわせるために、ロビンに「お揃いね?」と声をかけた。
そのとき、ハッと顔を晴らし嬉しそうに微笑み返してくれたロビンは、本当に可愛らしかった。
「ただの可愛い思い出じゃない。ロビンの髪紐が千切れたから、応急処置をしただけよ?」
「か、かわいいだって? そんなわけっ……」
リアスは戸惑ったように口をわなわなと震わせる。その姿があまりに不思議で、私は素直に訊ねた。
「どうしてそんなに驚くの?」
「どうしてって……ロベルト卿は180cmは優に超えた筋骨隆々の大男だぞ!? ロベルト卿を可愛いという人なんて、エリーゼ以外見たことも聞いたことも無い!」
「えっ!? ちょっとその男性私に紹介してよ!」
アルチーナの戯言が聞こえたような気がする。
しかしそんなことはどうでも良くて、私はますます頭を抱えたリアスに困惑していた。
時折こちらをチラッと見る彼の視線には、滾った嫉妬の情が滲んでいることに気付いたのだ。
知らないうちに、リアスのことをここまで思い詰めさせていたのね。人のことを言えないじゃない。
――ちゃんと彼の憂いを晴らさないと。
私はベッドから降りて、内省しながらリアスに告げた。
「リアス、私とロビンに特別なこと本当に何もないわ。だって、私が愛しているのはリアスだけなのよ?」
彼の顔を見上げると、リアスは難しい顔をして言葉を返した。
「そんなっ……。きっと魅了魔法が強すぎて、まだ魔法が消えずに残ってるんだよ」
「魅了魔法じゃないわ! あなたが好きで愛してるって、何度も言っているじゃないっ……」
あまりにも信じないリアスに、さすがにつらくなってきた。こうなったら、もう最終兵器を使うしかない。
「リアス」
私は彼の名を呼び、正面から彼の両手を握った。そして、目に涙を溜めて背の高い彼を見上げて言った。
「信じてくれないの?」
リアスはこの仕草に弱いのだ。
恥ずかしながら涙は嘘泣きではなく、本当に出て来てしまったものだが……。
私はこれ以上涙が溢れないよう気を付けながら、リアスをウルウルとした目で見つめ続けた。
すると、リアスは耳まで真っ赤にして、それは弱った声を漏らした。
「信じたくなるから……。そんな顔で見られたら困るよ。どうしてそんなに可愛いんだっ。酷いよ……」
彼はそう言ってぎこちなく私から顔を背けた。私はそんな彼に、間髪入れず声をかけた。
「信じていいのよ。だって、本当のことだもの」
そう言うと、リアスは困った様子で「うぅ」と唸った。
――もっと決め手になることが必要だわ。
少しでもリアスを安心させてあげたい。その方法を見つけないと。
私は一生懸命頭をフル回転させた。
――あっ!
逆転の発想を使えばいいんじゃっ……!
これしか方法はないのかもしれない。
私は今思いついたその方法を、さっそくリアスに伝えることにした。
「リアス。そんなに信じられないなら、明日ロビンに来てもらいましょう!」
「ロ、ロベルト卿にっ……?」
「ええ、それで証明してあげる。リアスと結婚する前の私が、ロビンに恋愛感情を抱いていなかったって!」
絶対的な自信があった。
ぐうの音も出ないくらい、リアスに証明して見せる。
私はそうと決まったらと、さっそくロビンに手紙を書いて出した。
すると早馬が互いに早かったのか、同じく王都に滞在しているロビンから三時間後に手紙が返ってきた。
《明日、ヴィルナー公爵家にお伺いいたします》
そう書かれた返信に、私はホッと胸を撫で下ろした。
これで、きっとすべてが解決して終わるはず。
このときの私はそうと信じて、勝手にスッキリとした気持ちで明日が来るのを待っていた。
「リアス、心配かけてごめんなさい。でも、私たちはそんな深い意味なく約束をしただけなの」
何だか私が浮気の弁明をしているかのような気持ちになってくる。
本当にそう言うんじゃないのに。
私がそう思う一方、リアスは納得できない様子で口を開いた。
「そんなはずないよ。だって、夜会のときに君たち仲睦まじそうだったじゃないか」
「例えば?」
「エリーゼがロベルト卿の髪をバルコニーで結んでいただろう?」
気付いている人は誰もいないと思っていたけれど、まさかリアスが見ていただなんて。
「あれはアクシデントよ」
きっと、リアスはあのときのことを言っているのだろう。
ある王城主催の夜会に招待されたとき、一緒に出席していたロビンの髪紐が千切れてしまったことがあった。
ロビンは癖毛が悩みで、いつも髪を伸ばして三つ編みにしていた。そのため、何かあったとき用に、彼は常に髪紐の替えを携帯していた。
だが、その日はあいにくロビンは替えを持ち合わせていなかったのだ。
普段なら、こっそりその場から居なくなって、自分で括り直して戻ってくる。しかし、そのときばかりはそうともいかなかった。
幸いなことに、その日の私はリボンを二つ使って、髪をセットしていた。
そのため、ロビンをバルコニーに連れて行き、応急処置として私のリボンでロビンの髪を括り直してあげたのだ。
時間をかけて結い上げたセットが崩れたと、ロビンが心底申し訳なさそうにしていたことをよく覚えている。
ハーフアップになっただけなのに、崩れたも何もないんだけど。
ロビンは一通り私に謝る終わると、リボンを見て恥ずかしそうに顔を赤らめていた。
女もののリボンだから、そりゃあ恥ずかしいわよね。そう思いながら、私は気を紛らわせるために、ロビンに「お揃いね?」と声をかけた。
そのとき、ハッと顔を晴らし嬉しそうに微笑み返してくれたロビンは、本当に可愛らしかった。
「ただの可愛い思い出じゃない。ロビンの髪紐が千切れたから、応急処置をしただけよ?」
「か、かわいいだって? そんなわけっ……」
リアスは戸惑ったように口をわなわなと震わせる。その姿があまりに不思議で、私は素直に訊ねた。
「どうしてそんなに驚くの?」
「どうしてって……ロベルト卿は180cmは優に超えた筋骨隆々の大男だぞ!? ロベルト卿を可愛いという人なんて、エリーゼ以外見たことも聞いたことも無い!」
「えっ!? ちょっとその男性私に紹介してよ!」
アルチーナの戯言が聞こえたような気がする。
しかしそんなことはどうでも良くて、私はますます頭を抱えたリアスに困惑していた。
時折こちらをチラッと見る彼の視線には、滾った嫉妬の情が滲んでいることに気付いたのだ。
知らないうちに、リアスのことをここまで思い詰めさせていたのね。人のことを言えないじゃない。
――ちゃんと彼の憂いを晴らさないと。
私はベッドから降りて、内省しながらリアスに告げた。
「リアス、私とロビンに特別なこと本当に何もないわ。だって、私が愛しているのはリアスだけなのよ?」
彼の顔を見上げると、リアスは難しい顔をして言葉を返した。
「そんなっ……。きっと魅了魔法が強すぎて、まだ魔法が消えずに残ってるんだよ」
「魅了魔法じゃないわ! あなたが好きで愛してるって、何度も言っているじゃないっ……」
あまりにも信じないリアスに、さすがにつらくなってきた。こうなったら、もう最終兵器を使うしかない。
「リアス」
私は彼の名を呼び、正面から彼の両手を握った。そして、目に涙を溜めて背の高い彼を見上げて言った。
「信じてくれないの?」
リアスはこの仕草に弱いのだ。
恥ずかしながら涙は嘘泣きではなく、本当に出て来てしまったものだが……。
私はこれ以上涙が溢れないよう気を付けながら、リアスをウルウルとした目で見つめ続けた。
すると、リアスは耳まで真っ赤にして、それは弱った声を漏らした。
「信じたくなるから……。そんな顔で見られたら困るよ。どうしてそんなに可愛いんだっ。酷いよ……」
彼はそう言ってぎこちなく私から顔を背けた。私はそんな彼に、間髪入れず声をかけた。
「信じていいのよ。だって、本当のことだもの」
そう言うと、リアスは困った様子で「うぅ」と唸った。
――もっと決め手になることが必要だわ。
少しでもリアスを安心させてあげたい。その方法を見つけないと。
私は一生懸命頭をフル回転させた。
――あっ!
逆転の発想を使えばいいんじゃっ……!
これしか方法はないのかもしれない。
私は今思いついたその方法を、さっそくリアスに伝えることにした。
「リアス。そんなに信じられないなら、明日ロビンに来てもらいましょう!」
「ロ、ロベルト卿にっ……?」
「ええ、それで証明してあげる。リアスと結婚する前の私が、ロビンに恋愛感情を抱いていなかったって!」
絶対的な自信があった。
ぐうの音も出ないくらい、リアスに証明して見せる。
私はそうと決まったらと、さっそくロビンに手紙を書いて出した。
すると早馬が互いに早かったのか、同じく王都に滞在しているロビンから三時間後に手紙が返ってきた。
《明日、ヴィルナー公爵家にお伺いいたします》
そう書かれた返信に、私はホッと胸を撫で下ろした。
これで、きっとすべてが解決して終わるはず。
このときの私はそうと信じて、勝手にスッキリとした気持ちで明日が来るのを待っていた。
417
あなたにおすすめの小説

『恋心を凍らせる薬を飲みました』 - 残りの学園生活、どうぞご自由にお遊びください、婚約者様
恋せよ恋
恋愛
愛されることを諦めた。だから、私は心を凍らせた。
不誠実な婚約者・ユリアンの冷遇に耐えかねたヤスミンは、
伝説の魔女の元を訪れ、恋心を消し去る「氷の薬」を飲む。
感情を捨て、完璧な「人形」となった彼女を前に、
ユリアンは初めて己の罪と執着に狂い始める。
「お願いだ、前のように僕を愛して泣いてくれ!」
足元に跪き、涙を流して乞う男に、ヤスミンは冷酷に微笑む。
「愛?……あいにく、そのような無駄な感情は捨てましたわ」
一度凍りついた心は、二度と溶けない。
後悔にのたうち回る男と、心を凍らせた冷徹な公爵夫人の、
終わりのない贖罪の記録。
🔶登場人物・設定は筆者の創作によるものです。
🔶不快に感じられる表現がありましたらお詫び申し上げます。
🔶誤字脱字・文の調整は、投稿後にも随時行います。
🔶今後もこの世界観で物語を続けてまいります。
🔶 『エール📣』『いいね❤️』励みになります!

今夜で忘れる。
豆狸
恋愛
「……今夜で忘れます」
そう言って、私はジョアキン殿下を見つめました。
黄金の髪に緑色の瞳、鼻筋の通った端正な顔を持つ、我がソアレス王国の第二王子。大陸最大の図書館がそびえる学術都市として名高いソアレスの王都にある大学を卒業するまでは、侯爵令嬢の私の婚約者だった方です。
今はお互いに別の方と婚約しています。
「忘れると誓います。ですから、幼いころからの想いに決着をつけるため、どうか私にジョアキン殿下との一夜をくださいませ」
なろう様でも公開中です。

裏切りの街 ~すれ違う心~
緑谷めい
恋愛
エマは裏切られた。付き合って1年になる恋人リュカにだ。ある日、リュカとのデート中、街の裏通りに突然一人置き去りにされたエマ。リュカはエマを囮にした。彼は騎士としての手柄欲しさにエマを利用したのだ。※ 全5話完結予定
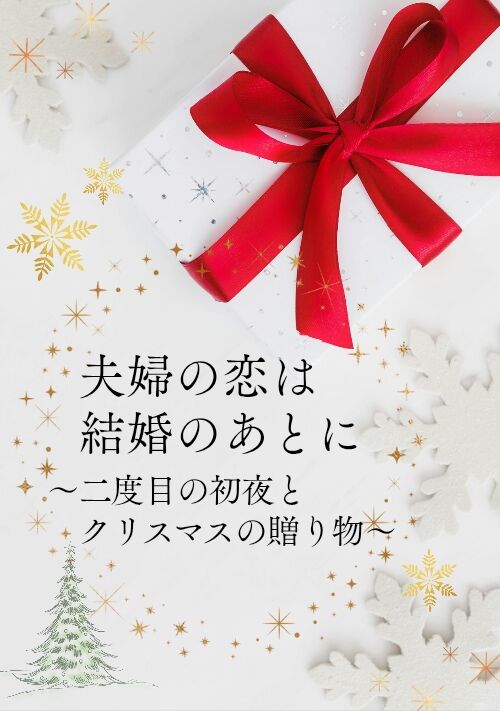
夫婦の恋は結婚のあとに 〜二度目の初夜とクリスマスの贈り物〜
出 万璃玲
恋愛
「エーミル、今年はサンタさんに何をお願いするの?」
「あのね、僕、弟か妹が欲しい!」
四歳の息子の純真無垢な願いを聞いて、アマーリアは固まった。愛のない結婚をした夫と関係を持ったのは、初夜の一度きり。弟か妹が生まれる可能性は皆無。だが、彼女は息子を何よりも愛していた。
「愛するエーミルの願いを無下にするなんてできない」。そう決意したアマーリアは、サンタ……もとい、夫ヴィンフリートに直談判する。
仕事人間でほとんど家にいない無愛想な夫ヴィンフリート、はじめから結婚に期待のなかった妻アマーリア。
不器用な夫婦それぞれの想いの行方は、果たして……?
――政略結婚からすれ違い続けた夫婦の、静かな「恋のやり直し」。
しっとりとした大人の恋愛と、あたたかな家族愛の物語です。
(おまけSS含め、約10000字の短編です。他サイト掲載あり。表紙はcanvaを使用。)

【完結】旦那に愛人がいると知ってから
よどら文鳥
恋愛
私(ジュリアーナ)は旦那のことをヒーローだと思っている。だからこそどんなに性格が変わってしまっても、いつの日か優しかった旦那に戻ることを願って今もなお愛している。
だが、私の気持ちなどお構いなく、旦那からの容赦ない暴言は絶えない。当然だが、私のことを愛してはくれていないのだろう。
それでも好きでいられる思い出があったから耐えてきた。
だが、偶然にも旦那が他の女と腕を組んでいる姿を目撃してしまった。
「……あの女、誰……!?」
この事件がきっかけで、私の大事にしていた思い出までもが崩れていく。
だが、今までの苦しい日々から解放される試練でもあった。
※前半が暗すぎるので、明るくなってくるところまで一気に更新しました。


セレナの居場所 ~下賜された側妃~
緑谷めい
恋愛
後宮が廃され、国王エドガルドの側妃だったセレナは、ルーベン・アルファーロ侯爵に下賜された。自らの新たな居場所を作ろうと努力するセレナだったが、夫ルーベンの幼馴染だという伯爵家令嬢クラーラが頻繁に屋敷を訪れることに違和感を覚える。

悪役令嬢として、愛し合う二人の邪魔をしてきた報いは受けましょう──ですが、少々しつこすぎやしませんか。
ふまさ
恋愛
「──いい加減、ぼくにつきまとうのはやめろ!」
ぱんっ。
愛する人にはじめて頬を打たれたマイナの心臓が、どくん、と大きく跳ねた。
甘やかされて育ってきたマイナにとって、それはとてつもない衝撃だったのだろう。そのショックからか。前世のものであろう記憶が、マイナの頭の中を一気にぐるぐると駆け巡った。
──え?
打たれた衝撃で横を向いていた顔を、真正面に向ける。王立学園の廊下には大勢の生徒が集まり、その中心には、三つの人影があった。一人は、マイナ。目の前には、この国の第一王子──ローランドがいて、その隣では、ローランドの愛する婚約者、伯爵令嬢のリリアンが怒りで目を吊り上げていた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















