61 / 66
第五章 フィオレンツァは王宮に舞い戻る。そして…
09 イリーナ・ナジェインの邁進
しおりを挟むイリーナがルーズヴェルト王国に赴く手配はすぐに整えられた。
そんな中、イリーナは父に掛け合って公爵家の諜報員を借り受けた。右も左も分からない隣国で少しでも有利に動きたいからだと言えば、父は特に不審に思うこともなく頷いてくれた。こちらの情報が父に筒抜けになるというデメリットがあるが、父は隣国ではイリーナの言うことに絶対に従えと命じてくれたし、人数も絞ったので上手く使えばこれ以上ない手足になることだろう。
早速イリーナは、諜報員を先行させてルーズヴェルト王国の王都の様子と、アレクシス元王子の同行を探らせた。
まず分かったのは、アレクシス元王子…現在のオルティス公爵と夫人のフィオレンツァは有名なおしどり夫婦だということだった。
アレクシスは女官となるべく城に上がった貧乏伯爵の娘だった年上のフィオレンツァを見初め、あの手この手で外堀を埋めて結婚にこぎつけたらしい。幼い娘が二人いるが溺愛ぶりは止まらず、現在夫人は三人目を身ごもっているという。
なんてこった、もしかしなくともこれはイリーナがお邪魔虫ではないか。絶対知っていただろう、あのクソ親父め…イリーナは『ニコライ君21号』の(『22号』だったかもしれない)首をぎりぎりと締めあげた。
次にルーズヴェルト王室だ。
王太子だったユージーンの廃嫡理由はなんと、宰相の家に招かれた際に十代のメイドを暴行し、さらに止めに入った宰相を刺して重傷を負わせたということだった。うちの馬鹿王子以上のクズがいるとは…気づけば『ニコライ君』は綿をぶちまけて跡形もなかった…南無。
このとんでもない醜態に、ルーズヴェルト王国の重臣たちはアレクシス元王子を王位に据えて現国王夫妻を排除しようという方向に動いているようだ。無理なからぬことだろう…どうやらアレクザンドラ王太后が病に倒れてから、国王夫妻は公務をおろそかにしていたらしい。加えて今回の王太子の暴挙とあっては、ガドフリー国王とグラフィーラ王妃に国を束ねる資質がないと思われても仕方がなかった。
一方の国王夫妻もそんな空気を感じ取り、アレクシスの正妃にバザロヴァ王国の王族の娘を迎えたいと思い立ったようだ。このままでは王位を追われるだけでなく、幽閉もありうる。しかし勢いのあるバザロヴァ王国の後ろ盾があれば、ルーズヴェルト王国の重臣たちも自分たちを無下にはできないと思ったのだろう。
売国ともとられかねないガドフリー国王の心理が理解できなかったのだが、これでようやくイリーナも得心がいった。
さて、ここまでの情報でどう動きべきか…。
イリーナが頭を悩ませていると、後ろに侍っていたルスランが侍女を話が聞こえない距離まで遠ざけた。
「お嬢様、確かテルフォード女公爵はフィオレンツァ夫人の友人だったはずです。彼女に接触するのはどうでしょうか?」
「テルフォード女公爵?あのスカーレット様よね?そんな大物と夫人は知り合いなの?」
スカーレット・テルフォード女公爵…かつてのスカーレット・ティンバーレイク公爵令嬢の名前はバザロヴァ王国でも有名だ。というのも、第二王子との婚約破棄にまつわる騒動が大衆向け小説となり、彼女は第二王子と彼を誑かした悪女からの冤罪をはねのけ、子爵令息との純愛を叶えたヒロインになっているのだ。派生作品もいくつか出て、バザロヴァ王国の民衆はもちろん、ロマンを愛する貴族令嬢の間でもひそかなブームになっている。
「女公爵が王妃教育を受けた際、ともに学んだのが当時女官見習いだったフィオレンツァ夫人だったようです。もともとフィオレンツァ夫人は王妃教育を施す教師の遠縁で、後継者となるべく王宮に入ったとか。結局アレクシス元王子に見初められて女官を二年勤めただけで嫁いだということですが」
報告書を見直せば、確かに結婚当初はテルフォード女公爵がオルティス領を訪れた記録があった。流石に手紙のやり取りまでは調べきれなかったが、この分ではずっと続いているのだろう。
イリーナは主にアレクシス元王子の周辺を調べさせていたが、今度は王宮に勤めていた時代のフィオレンツァの交友関係を詳しく調べるように密偵に命じた。そうして情報を得るためにルーズヴェルト王国内を駆け回った密偵たちが帰ってきたのは、イリーナがルーズヴェルト王国に赴く当日の朝のことだった。
イリーナがルーズヴェルト王国の王宮に到着したのは国を出立してから10日後だ。
夕方に到着したため、その日は国王夫妻に謁見せず、用意された部屋に通される。
『ニコライ君』は多めに持ってきた。この国にいる間…少なくとも、グラフィーラ王妃の目的をくじくまでは猫を被っておかなくてはならないとルスランが気を利かせてくれたのだ。さすがはできる従者である。
さて、そんなイリーナの部屋には一人の訪問者があった。
「お初にお目にかかります、ナジェイン公爵令嬢。カルロッタ・バーンスタインでございます」
「よろしくね、バーンスタイン夫人。なんでもスカーレット様とお知り合いなのだとか」
「はい、スカーレット様のことはよくよく存じ上げております」
イリーナはにっこりと笑うと人払いをした。侍女はもちろんルスランもだ。
ルスランが部屋を立ち去り際、僅かにうなずいたのを確認した。
完全に二人きりになり、イリーナはバーンスタイン夫人に椅子をすすめる。
「もう大丈夫よ。潜んでいた父の手の者も去ったみたい」
「間違いないのですか?」
「それは私と私のルスランを信じてもらうしかないわね」
イリーナ自身も監視されている身だ。しかし前々からの仕込みで、密偵たちはバーンスタイン夫人との会話を聞くに及ばないと判断したのだ。
「すごく恥ずかしかったのよ?スカーレット様に『私、ファンなんですぅ』っていうミーハーな手紙を送ったのは。あ、あの手紙消去してくださったのかしら?」
「そこまでは…。御父上の密偵たちはそのみーはーな手紙を見て、ナジェイン公爵令嬢がスカーレット様の熱狂的なファンだと勘違いしたと?」
「あいつらに五、六通は送らせたもの。最初は全部中身を確認していたでしょうけど、一番最後の手紙は見ていないはずよ」
「全て公爵家の紋章で封がしてあったそうですからね。…そう何度もこっそり開封できないでしょう」
スカーレットと連絡を取るためにイリーナがした方法は、ファンのふりをして手紙を送りつけることだった。
ずっと前からファンだった。
今度そちらに向かうのでぜひ会いたい。
直接例の婚約破棄騒動のお話を伺いたい。
現在のご主人との馴れ初めは?…等々。
見返したら顔から火を噴きそうなお花畑な手紙をしたためて、ナジェイン公爵家の立派な封蝋を押してスカーレットに二、三日に一回送り付けたのだ。その間も密偵たちにはルーズヴェルト王国での情報を集めさせていたので、イリーナが送ったミーハーな手紙の確認は手が足りず、最後の方はおざなりになっていたことだろう…もちろんすべて計画通りだ。
そうして最後の手紙には、イリーナがアレクシスの正妃になるべく祖国から送り込まれること、自分はアレクシスとも自国の王子でもない想い人がいること、グラフィーラ王妃はフィオレンツァ夫人を排除する可能性があるので阻止すべく協力するつもりであること、全てをしたためた。
それをスカーレットが見てくれるかどうかは賭けだったが、イリーナが留学という名目でルーズヴェルト王国に来ることは、王宮の女官でもある彼女は知っていたはず…彼女が聞いている通り優秀な人物ならば、イリーナに関することはすべて確認してくれるはずだった。
そうして、スカーレットが手配してくれたのがバーンスタイン夫人だったということだ。
「協力者は?」
「テルフォード女公爵と夫君のブレイク様、アレクザンドラ王太后、そしてスピネット卿です」
「…あら、スピネット卿って今の宰相よね?」
「さすがに今回のことで国王夫妻に失望したようです。それにご息女のロージー様もフィオレンツァ夫人の友人ですし」
国王夫妻は爵位を戻すことを餌にスピネット卿を完全に取り込んだつもりのようだったが、彼はかつての権力に取りつかれた男ではない。歳をとって丸くなった彼の関心は、今や手元に残ったロージーの幸せだけなのだ。
それでも臨時の宰相を引き受けた時は国王を裏切ることなど想像もしていなかっただろう。しかし自分たちの都合のためだけにアレクシスたちを、イリーナ公女を利用しようとし、さらに売国ともとれる行為をしようとしていることで完全に彼らに見切りをつけたようだった。
「フィオレンツァ夫人のことは少し調べたわ。派手な社交はしていないのに、色んな方に好かれているようね」
「大叔母として、鼻が高いですわ」
「まだオルティス夫妻は王都に着いていないの?」
「つい先日出立するという書状が王宮に届きましたので、数日かかるでしょう」
「国王と王妃はどう動くつもり?」
「それが…どうやら『竜の道』を使うつもりのようなのです」
「『竜の道』?」
「本来正門を潜った後、西館を通って本館、さらに東館に行くのが正規のルートです。しかし『竜の道』という、正門から本館へ直接向かうことができる特別な道が存在するのです。…王族ですら、自由に行き来できるものではありません。特別な儀式でしか使われないそれを、両陛下はこの混乱のなかで使うつもりなのです」
「…それを勝手に使えば国王夫妻は失脚もありうるということかしら?」
「さようです」
「でも止めないのね」
スピネット卿を通して国王夫妻の思惑は筒抜けていた。
議会の裏をかくように『竜の道』を使うことを命じられ、スピネット卿はこのままでは売国の手伝いをさせられてしまうことに危機感を抱いた。それでもこのまま議会に持ち込むことはためらわれ、まずはアレクザンドラ王太后の指示を仰ぐことにしたという。
彼はすぐに娘のロージーを使ってバーンスタイン夫人に連絡を取ってきた。
エステル妃の王妃教育を続けており、尚且つ王太后に目をかけられているバーンスタイン夫人は、未だに本館と東館を行き来する権限を有していた。ちなみに療養中のアレクザンドラ王太后は最近特に弱っており、以前は助言も求めに来ていた臣下たちも遠慮してあまり訪れることがなくなっていた。なので国王夫妻は南東の離宮に見張りは付けていたものの、世話をする女官の一人であるバーンスタイン夫人の訪問を制限していなかったのだ。
バーンスタイン夫人がスピネット卿から得た情報を告げると、最初はシーツに埋もれるようにして話を聞いていたアレクザンドラ王太后は、みる間に様子が変わった。目は見開かれらんらんとし、体は一気に膨れ上がったように活力を取り戻し、介添えもなく上半身が起き上がった。バーンスタイン夫人は何かが乗り移りでもしたのかと部屋を逃げ出しかけたそうだ。
「…病は気からという言葉を目の当たりにしましたわ」
「それは…ご愁傷さまです」
確かにそんな様子を見せつけられてはトラウマレベルだろう。
ともあれアレクザンドラ王太后の一時的な復活は、国王夫妻への激しい憤りによるものだ。未だに病気を装い離宮に籠ってはいるが、今のようにバーンスタイン夫人をイリーナに接触させるなど秘密裏に国王夫妻を追いつめようとしている。
「王太后様は国王夫妻にあえて失態を犯させ、それを理由に幽閉に持ち込もうとなさっているのね」
「さようでございます」
「ならばその計画をオルティス夫妻に伝えたのでしょうね?」
「それが…」
「伝えていないの?…伝えられないではなく?」
「王太后様は、これくらいのことを切り抜けられねばフィオレンツァを正妃にはできないと。…もちろん、彼女が王妃の手にかからないように色々取り計らうとおっしゃられていましたが」
「悠長なことね。暗殺なんてしようと思えばいくらでも手はあるのよ。本当にそれを全部防げるのかしら」
「…」
バーンスタイン夫人は苦い顔をしている。彼女も大姪のフィオレンツァを危険にさらすことは避けたいのだろう…今回の計画を何とかして伝えたいと思っているはずだ。
恐らくだが、アレクザンドラ王太后はフィオレンツァが王太子妃になる事態を歓迎していないのではないか。後ろ盾が弱いということだから、正妃の座を巡って国が荒れる心配をしているのかもしれない。ここまで国王夫妻の動きを把握しているというのにオルティス夫妻に情報を流さないのは、彼女が害されることを期待しているような気がした。
…とはいえさすがにこれ以上は他国の問題なのでイリーナも口を出すことはできない。
それにこれはチャンスだと思った。
アレクシスにアレクザンドラ王太后がフィオレンツァを見捨てようとしていたことを匂わせつつ、自分たちが彼女を無事に確保して引き渡したらどうなるだろう。愛妻家のアレクシスにかなり恩が売れる…交渉次第で、イリーナの最終目標を達成するために手を貸してくれる可能性が高い。
イリーナは凶悪になりそうな表情筋を必死で宥め、そのままバーンスタイン夫人と当日の打ち合わせをして別れた。
「…あとはそちらもご存じの通りです。当日の面会を私はすっぽかして王妃の計画を狂わせ、ルスランを動かして夫人を確保しました」
これまでの経緯を話し終えたイリーナは、一気に紅茶を飲み干した。
「ルスラン様は王太后様のお部屋にいらしたとか」
「王妃も大胆よね。王太后様の寝室の真下にあなたを呼び出して毒を飲ませようとするのだから。…何かあれば王太后様に罪を擦り付けるつもりだったのでしょうけど」
まあフィオレンツァをあえて危険にさらしたようなものだから、王太后も白とは言い切れないだろう。
イリーナがルスランをちらりと見た。ルスランは僅かにうなずくと、一歩前に出て口を開く。
「私はまず、王妃の侍女に近づきました。フィオレンツァ夫人を害するために王妃が用意した毒は、入手経路と種類を王太后様があらかじめ調べられていましたから、似たような香りがする香料に強い睡眠薬を混ぜたものを作っていました。王妃は毒を直前まで侍女の一人に持たせていたので、口説くふりをして気を逸らして毒と睡眠薬をすり替えました」
「…はあ」
随分と簡単に「すり替えた」などというものだ。いくら色仕掛けで気を逸らしたところで、そんな手品みたいなこと誰でもできるとは思えないのだが…。
主人があれなので、仕える方もハイスペックになっていくのだろうか。
「そしてイリーナお嬢様と引き離された後、昨晩のうちに南東の離宮に潜り込みました。フィオレンツァ夫人を南東の離宮に連れてくる直前、王妃は侍女に王太后様の部屋を確認させていましたが、私は簡単に隠れていられましたよ。メラニアという侍女も王太后様のご様子こそ念入りに観察していましたが、まさか人が潜んでいるとは思わなかったようです」
グラフィーラ王妃はアレクザンドラ王太后を利用するつもりで、しかし完全に相手に裏をかかれていた。
「そして公爵夫人をお救いすべく待機していたというのに、まさか夫人が自力で彼らを躱し湖に逃れるとは…王太后様も驚いておられましたよ」
それまでずっと黙っていたアレクシスが目を剥いた。
「フィオレンツァ!本当に自分から湖に飛び込んだのか!!?」
「すみません」
「なんて無茶を…」
無理なからぬことだろう。
この国の貴族に取って、川も湖も海も泳ぐものではなく眺めるものだ。海のある地域は国のごく一部であるため、平民ですら泳ぐという概念を持つ者は少ない。
ドレスをまとったまま湖に入れば沈むのみだ。
「黙っていてごめんなさい。実は泳げたんです」
「…どうして?ホワイトリー領には川も湖もないよね?」
「すみません、その話はあとにしていただけませんでしょうか」
ルスランは淡々と夫婦の会話に割って入る。
「フィオレンツァ夫人が無事でオルティス公爵のもとに戻ってきたのは、我が主の功績だということはご理解いただけたでしょうか?」
「…」
アレクシスとフィオレンツァは気を引き締めた。
どうやらイリーナが最初に言っていた、「褒賞」の話に戻ったようだ。
「とりあえず望みを聞こうか。…あなたたちのことだから、僕たちがぎりぎり叶えられる程度の要求を用意しているんだろう?」
42
あなたにおすすめの小説

過労死コンサル、貧乏貴族に転生す~現代農業知識と魔法で荒地を開拓していたら、いつの間にか世界を救う食糧大国になっていました~
黒崎隼人
ファンタジー
農業コンサルタントとして過労死した杉本健一は、異世界の貧乏貴族ローレンツ家の当主として目覚めた。
待っていたのは、荒れた土地、飢える領民、そして莫大な借金!
チートスキルも戦闘能力もない彼に残された武器は、前世で培った「農業知識」だけだった。
「貴族が土を耕すだと?」と笑われても構わない!
輪作、堆肥、品種改良! 現代知識と異世界の魔法を組み合わせた独自農法で、俺は自らクワを握る「耕作貴族」となる!
元Sランク冒険者のクールなメイドや、義理堅い元騎士を仲間に迎え、荒れ果てた領地を最強の農業大国へと変えていく、異色の領地経営ファンタジー!

虚弱体質?の脇役令嬢に転生したので、食事療法を始めました
たくわん
恋愛
「跡継ぎを産めない貴女とは結婚できない」婚約者である公爵嫡男アレクシスから、冷酷に告げられた婚約破棄。その場で新しい婚約者まで紹介される屈辱。病弱な侯爵令嬢セラフィーナは、社交界の哀れみと嘲笑の的となった。

【完結】辺境に飛ばされた子爵令嬢、前世の経営知識で大商会を作ったら王都がひれ伏したし、隣国のハイスペ王子とも結婚できました
いっぺいちゃん
ファンタジー
婚約破棄、そして辺境送り――。
子爵令嬢マリエールの運命は、結婚式直前に無惨にも断ち切られた。
「辺境の館で余生を送れ。もうお前は必要ない」
冷酷に告げた婚約者により、社交界から追放された彼女。
しかし、マリエールには秘密があった。
――前世の彼女は、一流企業で辣腕を振るった経営コンサルタント。
未開拓の農産物、眠る鉱山資源、誠実で働き者の人々。
「必要ない」と切り捨てられた辺境には、未来を切り拓く力があった。
物流網を整え、作物をブランド化し、やがて「大商会」を設立!
数年で辺境は“商業帝国”と呼ばれるまでに発展していく。
さらに隣国の完璧王子から熱烈な求婚を受け、愛も手に入れるマリエール。
一方で、税収激減に苦しむ王都は彼女に救いを求めて――
「必要ないとおっしゃったのは、そちらでしょう?」
これは、追放令嬢が“経営知識”で国を動かし、
ざまぁと恋と繁栄を手に入れる逆転サクセスストーリー!
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

積みかけアラフォーOL、公爵令嬢に転生したのでやりたいことをやって好きに生きる!
ぽらいと
ファンタジー
アラフォー、バツ2派遣OLが公爵令嬢に転生したので、やりたいことを好きなようにやって過ごす、というほのぼの系の話。
悪役等は一切出てこない、優しい世界のお話です。

追放令嬢、辺境王国で無双して王宮を揺るがす
yukataka
ファンタジー
王国随一の名門ハーランド公爵家の令嬢エリシアは、第一王子の婚約者でありながら、王宮の陰謀により突然追放される。濡れ衣を着せられ、全てを奪われた彼女は極寒の辺境国家ノルディアへと流される。しかしエリシアには秘密があった――前世の記憶と現代日本の経営知識を持つ転生者だったのだ。荒廃した辺境で、彼女は持ち前の戦略眼と人心掌握術で奇跡の復興を成し遂げる。やがて彼女の手腕は王国全土を震撼させ、自らを追放した者たちに復讐の刃を向ける。だが辺境王ルシアンとの運命的な出会いが、彼女の心に新たな感情を芽生えさせていく。これは、理不尽に奪われた女性が、知略と情熱で世界を変える物語――。

異世界転生目立ちたく無いから冒険者を目指します
桂崇
ファンタジー
小さな町で酒場の手伝いをする母親と2人で住む少年イールスに転生覚醒する、チートする方法も無く、母親の死により、実の父親の家に引き取られる。イールスは、冒険者になろうと目指すが、周囲はその才能を惜しんでいる

貴族令嬢、転生十秒で家出します。目指せ、おひとり様スローライフ
凜
ファンタジー
第18回ファンタジー小説大賞にて奨励賞を頂きました。ありがとうございます!
貴族令嬢に転生したリルは、前世の記憶に混乱しつつも今世で恵まれていない環境なことに気が付き、突発で家出してしまう。
前世の社畜生活で疲れていたため、山奥で魔法の才能を生かしスローライフを目指すことにした。しかししょっぱなから魔物に襲われ、元王宮魔法士と出会ったり、はては皇子までやってきてと、なんだかスローライフとは違う毎日で……?
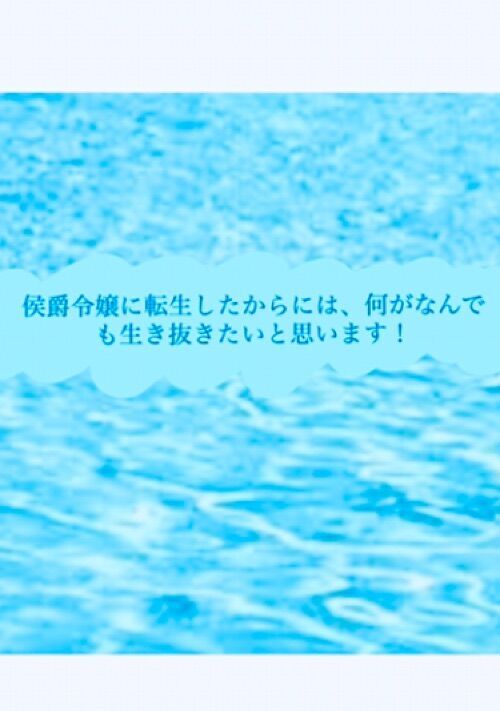
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















