6 / 7
3
しおりを挟む
「ねぇ。祐樹さん。今度映画見に行きませんか?」
夜ご飯のハンバーグを食べ終わり、課題だという難しそうな英文に目を通していたユイくんが、手を止めてこちらを見る。
「映画?別に良いけど。なんてやつ?」
「前からずっと見たいと思ってた映画なんですけど、近日リバイバル上映するみたいで。これ、知ってますか?」
すいっと、ユイくんから差し出された映画の題名に、僕は思わず目を見開く。
「…………あ」
「数年前に流行ったやつなんですけど、俺一作目だけしか見れてなくて。ずっと続きが気になってたんですよね」
「…………」
「サブスクに無いし、レンタルするのも面倒でずっと放ったらかしてたんですけど、映画館で見られるなら見たいなと思って」
見覚えのあるその映画は、確か無名の小説家が低予算で作った映画だったはずだ。智紀がゲームにハマるほんの少し前に二人で見に行ったことを覚えている。一緒に行こうと言っていた続編を、終に見に行くことはなかったけれど。
「いいよ。見に行こう。その映画、僕もちょうど一作目しか見れてないんだよね」
「え、本当ですか?すごい偶然。一応今週末の二日間だけ上映されるんですけど、どちらがいいです?」
「うーん、じゃあ土曜日がいいかなぁ」
「分かりました。じゃあとりあえず土曜日ってことで。時間と場所はまた今度連絡しますね」
ユイくんは普段かけないメガネをぐいっと押し上げて一瞬小さく笑みを作ると、すぐに難しい英文に目線を戻した。その表情がすぐに真剣なものに変わったから、僕も目の前の家事へと戻ることにする。
会話がなくなった後、空間は静寂に包まれる。テレビも音楽もつけず、何を喋るわけでもない。聞こえてくる音は二人から出るわずかな生活音だけ。
智紀と別れてから、僕は静かな空間が嫌いだった。ひとりぼっちな感じがして寂しかったからだ。だけどこのひとときは嫌いじゃない。耳を澄ませば時計の秒針が聞こえてくるほど静かだけど、寂しいわけじゃないから。
この時間をユイくんも好きでいてくれたらいいのに。
そしてこの時間が続けばいいのに。
……そんなことを思うのは、多分、僕が募る罪悪感に気付かないフリをしているから。
ユイくんは高熱を出したあの日から、ちょっとずつ、だけど確実に変わっていった。その中でも一番の変化といえば、それはユイくんが僕の家へご飯を食べに来るようになったことだろう。彼は食材がパンパンに詰められたスーパーの袋を片手にふらっと現れ、当たり前のように僕が作ったご飯を食べるようになった。最近では結構な頻度で訪れるものだから、僕の家の冷蔵庫はいつもパンパンだ。
そうやって軟化する彼の態度に、僕はもしかしたらなんて思ってしまっている。不毛な恋愛ごっこをやめるだなんて、やっぱり僕には無理だった。あの時から僕は止まったまま。期待しないと決めていたはずなのに、最初はそれで良かったのに、ユイくんへの思いはむくむくと成長する。
この思いは、まるで玄関前にポツンと佇む朝出し忘れたゴミ袋だ。早く捨てなきゃいけないのに、放置したらどんどん汚れてしまうのに、今更捨てに行くのが面倒でずっと放置されている。
何も成せぬまま、時間だけが過ぎていく。
だんだん近づいてくる終わりが、僕は怖くてたまらない。
⭐︎
「あぁ、どうしたらいいんだろう」その光景を見た時、僕が真っ先に思ったことはそれだ。
ユイくんと映画の約束をした日。他の予定の都合で待ち合わせ場所に早く着いてしまった僕は、暇を持て余していた。約束の時間まではあと二時間。一旦家に帰ってもよかったのだが、映画館は駅近くの大きなショッピングモールの中に入っているし、いくらでも時間は潰せるだろう、そう思ってとりあえず来てみた。……のだけど、久しぶりに訪れたショッピングモールは、何というかこう、ちょっと異世界のようだった。本屋は人がごった返していてゆっくり見る事ができなかったし、お菓子屋さんは売り切ればっかり。やっと購入できるものが見つかったと思えばレジまでの列が異様に長く、結局焼き菓子を二つ買うために二十分も並んだ。休日だからってのもあるかもしれないけれど、あまりにも人が多すぎる。デートはこれからだというのに、この時点で僕はもうクタクタだった。
こんなに時間をかけてまで焼き菓子を買った理由は、ユイくんが好きだから。彼は意外にも甘党で、ごはんの後にはデザートが食べたくなるらしい。だけど、もし今日映画を見た後に僕の家に来ることになったら、デザートがない。どうせ食べてもらうなら、ちゃんとした菓子店のものを食べさせてあげたい。そんな思いからのことだった。
……だけど、このデザートはいらなかったかもしれない。
僕は数メートル先にある人影に、進めていた足をぴたっと止める。
「――…………」
僕の目に映るのは、通路の壁の前に立ってスマホを見ているユイくん、……と、その腰に抱きつくようにしている女の子。遠くて声は聞こえないが、二人は何かを話しているようだった。
「――…………」
こういう時、どうしたらいいんだろう?怒る?笑う?それとも見て見ぬふり?怒るはないな、そんなことしたら僕たちは本当に終わりだ。笑うって、この状況でそれも無い。じゃあ見て見ぬふり……それが一番しっくりくる。だけど、僕の足は縫い付けられたみたいに動かない。この期に及んでまだユイくんにすがろうとしている自分が本当に情けない。
ユイくんはノンケだ。つまり女の子が好き。今はどうか分からないけれど、昔は色んな女の子を取っ替え引っ替えしていたらしい。そこで思い出すのが、ユイくんのスマホに頻繁にかかってくるあの電話。朝も夜も関係なく無遠慮にかかってくるその電話を、ユイくんは僕の前で出たことがない。「大した用事じゃない」そう言っていつも出ないのだ。
この二人を見てこみ上げてくる感情は、別に悲しみでも怒りでもなかった。そこにあったのは、凄まじいほどの羨望。僕は女の子が羨ましかった。僕は男だからユイくんにそんな顔はさせられない。いや、男とか女とかじゃなく、僕っていうのがダメなのかもしれない。十分理解していたはずなのに、改めて目の当たりにするとやっぱり応える自分に嫌気がさす。なんで愛されないって分かっているのに期待しちゃうんだろう。寂しさを埋めるために新しい寂しさを用意して、僕は何をしているんだろう。
ユイくんとまだ一緒にいたい。僕はまだ、終わらせたくない。そんなことばかりが頭をよぎり、僕の目からは、ぽつん、と涙が落ちる。
こんな公共の場で、と思うのに、一度こぼれてしまえば、僕の目からは涙が溢れて止まらない。突然ポロポロと涙をこぼす僕に、周りの人はギョッとした顔をした。そりゃそうだ。大の大人が、しかも男が、こんなたくさんの人がいる場所で大泣きするなんて恥ずかしいったらない。目立ちたくなんかないのに、僕はどんどん目立っていく。そしてそのギョッは数メートル先にいるユイくんにも伝わり。
「……祐樹さん……?」
ついにユイくんにバレた。泣きじゃくる僕を、ユイくんは信じられないものを見たかのような目で見ている。
「っ…………」
「ち、ちょっと待って!」
やっと動いた足を動かし、咄嗟に逃げようとした僕の腕を、ユイくんが掴む。数メートルも差があったのに、ユイくんはすぐに追いついてこれるらしい。僕がとろいのか、ユイくんが素早いのか。尚も逃げようもがく僕を、ユイくんは腕の中に閉じ込める。
「祐樹さん逃げないで」
「っやだ!……っふ……ぐすっ」
「裕樹さん誤解してる」
「くっ……っふ……ぐすっ」
ユイくんの腕が、更に僕をぎゅうっと抱きしめる。
「あの子の方が大事なら、わざわざこうやって祐樹さんのところに来たりしない」
「……っぐす……っ」
「すみません。全部俺が悪い」
「っふぐっ……」
ユイくんは目立つのにも関わらず、ショッピングモールの通路の真ん中で泣きじゃくる僕を抱きしめ続ける。そうしてどのくらい時間が経っただろうか。少し落ち着いてきた僕の体を、ユイくんの腕がそっと離す。
「……祐樹さん」
「…………」
「ちょっと話そう」
「…………」
「俺の気持ちを聞いてほしい」
いつになく真剣な表情のユイくんに、僕は小さく頷いた。
「どこから話そうか」
僕の家のリビングで椅子に座ったユイくんは、そんな言葉から話を始めた。
「まず第一に、俺はクズだ。それは間違いない」
「…………」
「祐樹さんに俺がどう映ってるかは分からないけど、俺は碌な人間じゃない」
それからユイくんは、ぽつり、ぽつりと自分のことを話し始めた。親のこと、大学のこと、遊び歩いていたこと、勘当されたこと、ヒモだったこと。僕の知らないユイくんが彼の口から次々と明かされる。
「祐樹さんのことも、本気で金づるだって思ってた。多分祐樹さんも気付いてたと思う。それでも何も言わないアンタに、俺は甘えた。甘えまくった。だけどそんな日々を過ごすうちに、今度は祐樹さんが何も言わないことにイライラし始めた。ただの都合のいい金づるとして扱っていたのは自分の筈なのに、我ながら自分勝手だと思う」
「………………」
「そして俺は熱を出したあの日確信した。あぁ、俺は祐樹さんに惚れてると。散々酷いことしておいて何を今更って感じだけど、やっと自分の気持ちに気付いたんだ」
「………………」
「それで、気付いたら祐樹さんの家に飯を食いに行くようになった。だけど祐樹さんと過ごすうちに自分のクズさが浮き彫りになってきて、まずいと思った。俺今まで酷いところしか祐樹さんに見せてなかったから。それで、親に頭を下げて大学費を払ってもらって復学した」
「…………」
「今までの分返すために、バイトだって始めた。さっきの子はバイトの子なんだ。確かに好きって言われたけど、ちゃんと断った。信じてもらえないかもしれないけど、本当にそれだけ。それで、寝る間もないほど真剣に働いて、金を貯めて。今日はこれを買った」
そう言ってユイくんが持っていた袋から取り出したのは、シンプルなデザインのふたつの腕時計だった。
「アクセサリーは祐樹さんつけないかなって思って。俺もなんか恥ずかしいし。だから腕時計。対になっててちゃんとお互いの名前が彫ってある」
「…………僕に?」
ユイくんはこくりと頷き、黒い円盤のすっきりとしたデザインの腕時計を僕の腕につける。
「こんなことで許してもらえるとは思わない。それだけ酷いことをした。だけど、俺の気持ちをちゃんと伝えたかった。俺は祐樹さんが好きだから」
色素が薄く茶色がかった真剣な瞳が、僕を真っ直ぐ射抜く。これは現実なのだろうか。夢かもしれない。だけど、それなら僕も謝らなきゃだめだ。僕もユイくんにずっと言えなかったことがある。
「……運命だって思ってたんだよね」
「……え?」
「時が変われば、人も変わるのにね。僕はそんな事に全然気が付かなかった。僕はユイくんと未来があるなんて考えてなかった。確実に別れると思ってた」
「それは俺が……」
「ううん。違う。最初から諦めて何も頑張らなかったんだ。考えることを放棄して、いつも受け身で、不貞腐れてたんだよ」
智紀と離れるときは、智紀がいなくなることよりも、今後一人で愛されないまま生きていかなければならないという恐怖のほうが強かったように思う。だけど、ユイくんは違う。僕はユイくんと離れたくない。だからちゃんと伝えないといけない。
「僕、ちゃんとユイくんの恋人になりたい」
――――大切なのは相手をちゃんと大事にすることでしょ。それさえ伝わればそれで良いんですよ。むしろ伝わらないやり方じゃ意味がない――――
田口さんの言った通りだ。
未来を変えるのは時代じゃない。人の意思だ。
未来は意外とどうにでもなるのだから。
突然だが、僕には前世の記憶がある。
だけど、前世というものは意外と今世に影響しないらしい。時代も前世も関係ない。いつの時代も大切なのは目の前にいる大事な人をちゃんと大事に扱うことだ。
僕とユイくんは前世で恋人同士では……なかった。
だけど二人はお互いの命が尽きるまで、ずっと幸せに暮らした。
夜ご飯のハンバーグを食べ終わり、課題だという難しそうな英文に目を通していたユイくんが、手を止めてこちらを見る。
「映画?別に良いけど。なんてやつ?」
「前からずっと見たいと思ってた映画なんですけど、近日リバイバル上映するみたいで。これ、知ってますか?」
すいっと、ユイくんから差し出された映画の題名に、僕は思わず目を見開く。
「…………あ」
「数年前に流行ったやつなんですけど、俺一作目だけしか見れてなくて。ずっと続きが気になってたんですよね」
「…………」
「サブスクに無いし、レンタルするのも面倒でずっと放ったらかしてたんですけど、映画館で見られるなら見たいなと思って」
見覚えのあるその映画は、確か無名の小説家が低予算で作った映画だったはずだ。智紀がゲームにハマるほんの少し前に二人で見に行ったことを覚えている。一緒に行こうと言っていた続編を、終に見に行くことはなかったけれど。
「いいよ。見に行こう。その映画、僕もちょうど一作目しか見れてないんだよね」
「え、本当ですか?すごい偶然。一応今週末の二日間だけ上映されるんですけど、どちらがいいです?」
「うーん、じゃあ土曜日がいいかなぁ」
「分かりました。じゃあとりあえず土曜日ってことで。時間と場所はまた今度連絡しますね」
ユイくんは普段かけないメガネをぐいっと押し上げて一瞬小さく笑みを作ると、すぐに難しい英文に目線を戻した。その表情がすぐに真剣なものに変わったから、僕も目の前の家事へと戻ることにする。
会話がなくなった後、空間は静寂に包まれる。テレビも音楽もつけず、何を喋るわけでもない。聞こえてくる音は二人から出るわずかな生活音だけ。
智紀と別れてから、僕は静かな空間が嫌いだった。ひとりぼっちな感じがして寂しかったからだ。だけどこのひとときは嫌いじゃない。耳を澄ませば時計の秒針が聞こえてくるほど静かだけど、寂しいわけじゃないから。
この時間をユイくんも好きでいてくれたらいいのに。
そしてこの時間が続けばいいのに。
……そんなことを思うのは、多分、僕が募る罪悪感に気付かないフリをしているから。
ユイくんは高熱を出したあの日から、ちょっとずつ、だけど確実に変わっていった。その中でも一番の変化といえば、それはユイくんが僕の家へご飯を食べに来るようになったことだろう。彼は食材がパンパンに詰められたスーパーの袋を片手にふらっと現れ、当たり前のように僕が作ったご飯を食べるようになった。最近では結構な頻度で訪れるものだから、僕の家の冷蔵庫はいつもパンパンだ。
そうやって軟化する彼の態度に、僕はもしかしたらなんて思ってしまっている。不毛な恋愛ごっこをやめるだなんて、やっぱり僕には無理だった。あの時から僕は止まったまま。期待しないと決めていたはずなのに、最初はそれで良かったのに、ユイくんへの思いはむくむくと成長する。
この思いは、まるで玄関前にポツンと佇む朝出し忘れたゴミ袋だ。早く捨てなきゃいけないのに、放置したらどんどん汚れてしまうのに、今更捨てに行くのが面倒でずっと放置されている。
何も成せぬまま、時間だけが過ぎていく。
だんだん近づいてくる終わりが、僕は怖くてたまらない。
⭐︎
「あぁ、どうしたらいいんだろう」その光景を見た時、僕が真っ先に思ったことはそれだ。
ユイくんと映画の約束をした日。他の予定の都合で待ち合わせ場所に早く着いてしまった僕は、暇を持て余していた。約束の時間まではあと二時間。一旦家に帰ってもよかったのだが、映画館は駅近くの大きなショッピングモールの中に入っているし、いくらでも時間は潰せるだろう、そう思ってとりあえず来てみた。……のだけど、久しぶりに訪れたショッピングモールは、何というかこう、ちょっと異世界のようだった。本屋は人がごった返していてゆっくり見る事ができなかったし、お菓子屋さんは売り切ればっかり。やっと購入できるものが見つかったと思えばレジまでの列が異様に長く、結局焼き菓子を二つ買うために二十分も並んだ。休日だからってのもあるかもしれないけれど、あまりにも人が多すぎる。デートはこれからだというのに、この時点で僕はもうクタクタだった。
こんなに時間をかけてまで焼き菓子を買った理由は、ユイくんが好きだから。彼は意外にも甘党で、ごはんの後にはデザートが食べたくなるらしい。だけど、もし今日映画を見た後に僕の家に来ることになったら、デザートがない。どうせ食べてもらうなら、ちゃんとした菓子店のものを食べさせてあげたい。そんな思いからのことだった。
……だけど、このデザートはいらなかったかもしれない。
僕は数メートル先にある人影に、進めていた足をぴたっと止める。
「――…………」
僕の目に映るのは、通路の壁の前に立ってスマホを見ているユイくん、……と、その腰に抱きつくようにしている女の子。遠くて声は聞こえないが、二人は何かを話しているようだった。
「――…………」
こういう時、どうしたらいいんだろう?怒る?笑う?それとも見て見ぬふり?怒るはないな、そんなことしたら僕たちは本当に終わりだ。笑うって、この状況でそれも無い。じゃあ見て見ぬふり……それが一番しっくりくる。だけど、僕の足は縫い付けられたみたいに動かない。この期に及んでまだユイくんにすがろうとしている自分が本当に情けない。
ユイくんはノンケだ。つまり女の子が好き。今はどうか分からないけれど、昔は色んな女の子を取っ替え引っ替えしていたらしい。そこで思い出すのが、ユイくんのスマホに頻繁にかかってくるあの電話。朝も夜も関係なく無遠慮にかかってくるその電話を、ユイくんは僕の前で出たことがない。「大した用事じゃない」そう言っていつも出ないのだ。
この二人を見てこみ上げてくる感情は、別に悲しみでも怒りでもなかった。そこにあったのは、凄まじいほどの羨望。僕は女の子が羨ましかった。僕は男だからユイくんにそんな顔はさせられない。いや、男とか女とかじゃなく、僕っていうのがダメなのかもしれない。十分理解していたはずなのに、改めて目の当たりにするとやっぱり応える自分に嫌気がさす。なんで愛されないって分かっているのに期待しちゃうんだろう。寂しさを埋めるために新しい寂しさを用意して、僕は何をしているんだろう。
ユイくんとまだ一緒にいたい。僕はまだ、終わらせたくない。そんなことばかりが頭をよぎり、僕の目からは、ぽつん、と涙が落ちる。
こんな公共の場で、と思うのに、一度こぼれてしまえば、僕の目からは涙が溢れて止まらない。突然ポロポロと涙をこぼす僕に、周りの人はギョッとした顔をした。そりゃそうだ。大の大人が、しかも男が、こんなたくさんの人がいる場所で大泣きするなんて恥ずかしいったらない。目立ちたくなんかないのに、僕はどんどん目立っていく。そしてそのギョッは数メートル先にいるユイくんにも伝わり。
「……祐樹さん……?」
ついにユイくんにバレた。泣きじゃくる僕を、ユイくんは信じられないものを見たかのような目で見ている。
「っ…………」
「ち、ちょっと待って!」
やっと動いた足を動かし、咄嗟に逃げようとした僕の腕を、ユイくんが掴む。数メートルも差があったのに、ユイくんはすぐに追いついてこれるらしい。僕がとろいのか、ユイくんが素早いのか。尚も逃げようもがく僕を、ユイくんは腕の中に閉じ込める。
「祐樹さん逃げないで」
「っやだ!……っふ……ぐすっ」
「裕樹さん誤解してる」
「くっ……っふ……ぐすっ」
ユイくんの腕が、更に僕をぎゅうっと抱きしめる。
「あの子の方が大事なら、わざわざこうやって祐樹さんのところに来たりしない」
「……っぐす……っ」
「すみません。全部俺が悪い」
「っふぐっ……」
ユイくんは目立つのにも関わらず、ショッピングモールの通路の真ん中で泣きじゃくる僕を抱きしめ続ける。そうしてどのくらい時間が経っただろうか。少し落ち着いてきた僕の体を、ユイくんの腕がそっと離す。
「……祐樹さん」
「…………」
「ちょっと話そう」
「…………」
「俺の気持ちを聞いてほしい」
いつになく真剣な表情のユイくんに、僕は小さく頷いた。
「どこから話そうか」
僕の家のリビングで椅子に座ったユイくんは、そんな言葉から話を始めた。
「まず第一に、俺はクズだ。それは間違いない」
「…………」
「祐樹さんに俺がどう映ってるかは分からないけど、俺は碌な人間じゃない」
それからユイくんは、ぽつり、ぽつりと自分のことを話し始めた。親のこと、大学のこと、遊び歩いていたこと、勘当されたこと、ヒモだったこと。僕の知らないユイくんが彼の口から次々と明かされる。
「祐樹さんのことも、本気で金づるだって思ってた。多分祐樹さんも気付いてたと思う。それでも何も言わないアンタに、俺は甘えた。甘えまくった。だけどそんな日々を過ごすうちに、今度は祐樹さんが何も言わないことにイライラし始めた。ただの都合のいい金づるとして扱っていたのは自分の筈なのに、我ながら自分勝手だと思う」
「………………」
「そして俺は熱を出したあの日確信した。あぁ、俺は祐樹さんに惚れてると。散々酷いことしておいて何を今更って感じだけど、やっと自分の気持ちに気付いたんだ」
「………………」
「それで、気付いたら祐樹さんの家に飯を食いに行くようになった。だけど祐樹さんと過ごすうちに自分のクズさが浮き彫りになってきて、まずいと思った。俺今まで酷いところしか祐樹さんに見せてなかったから。それで、親に頭を下げて大学費を払ってもらって復学した」
「…………」
「今までの分返すために、バイトだって始めた。さっきの子はバイトの子なんだ。確かに好きって言われたけど、ちゃんと断った。信じてもらえないかもしれないけど、本当にそれだけ。それで、寝る間もないほど真剣に働いて、金を貯めて。今日はこれを買った」
そう言ってユイくんが持っていた袋から取り出したのは、シンプルなデザインのふたつの腕時計だった。
「アクセサリーは祐樹さんつけないかなって思って。俺もなんか恥ずかしいし。だから腕時計。対になっててちゃんとお互いの名前が彫ってある」
「…………僕に?」
ユイくんはこくりと頷き、黒い円盤のすっきりとしたデザインの腕時計を僕の腕につける。
「こんなことで許してもらえるとは思わない。それだけ酷いことをした。だけど、俺の気持ちをちゃんと伝えたかった。俺は祐樹さんが好きだから」
色素が薄く茶色がかった真剣な瞳が、僕を真っ直ぐ射抜く。これは現実なのだろうか。夢かもしれない。だけど、それなら僕も謝らなきゃだめだ。僕もユイくんにずっと言えなかったことがある。
「……運命だって思ってたんだよね」
「……え?」
「時が変われば、人も変わるのにね。僕はそんな事に全然気が付かなかった。僕はユイくんと未来があるなんて考えてなかった。確実に別れると思ってた」
「それは俺が……」
「ううん。違う。最初から諦めて何も頑張らなかったんだ。考えることを放棄して、いつも受け身で、不貞腐れてたんだよ」
智紀と離れるときは、智紀がいなくなることよりも、今後一人で愛されないまま生きていかなければならないという恐怖のほうが強かったように思う。だけど、ユイくんは違う。僕はユイくんと離れたくない。だからちゃんと伝えないといけない。
「僕、ちゃんとユイくんの恋人になりたい」
――――大切なのは相手をちゃんと大事にすることでしょ。それさえ伝わればそれで良いんですよ。むしろ伝わらないやり方じゃ意味がない――――
田口さんの言った通りだ。
未来を変えるのは時代じゃない。人の意思だ。
未来は意外とどうにでもなるのだから。
突然だが、僕には前世の記憶がある。
だけど、前世というものは意外と今世に影響しないらしい。時代も前世も関係ない。いつの時代も大切なのは目の前にいる大事な人をちゃんと大事に扱うことだ。
僕とユイくんは前世で恋人同士では……なかった。
だけど二人はお互いの命が尽きるまで、ずっと幸せに暮らした。
25
あなたにおすすめの小説

完結|好きから一番遠いはずだった
七角@書籍化進行中!
BL
大学生の石田陽は、石ころみたいな自分に自信がない。酒の力を借りて恋愛のきっかけをつかもうと意気込む。
しかしサークル歴代最高イケメン・星川叶斗が邪魔してくる。恋愛なんて簡単そうなこの後輩、ずるいし、好きじゃない。
なのにあれこれ世話を焼かれる。いや利用されてるだけだ。恋愛相手として最も遠い後輩に、勘違いしない。
…はずだった。


平凡な僕が優しい彼氏と別れる方法
あと
BL
「よし!別れよう!」
元遊び人の現爽やか風受けには激重執着男×ちょっとネガティブな鈍感天然アホの子
昔チャラかった癖に手を出してくれない攻めに憤った受けが、もしかしたら他に好きな人がいる!?と思い込み、別れようとする……?みたいな話です。
攻めの女性関係匂わせや攻めフェラがあり、苦手な人はブラウザバックで。
……これはメンヘラなのではないか?という説もあります。
pixivでも投稿しています。
攻め:九條隼人
受け:田辺光希
友人:石川優希
ひよったら消します。
誤字脱字はサイレント修正します。
また、内容もサイレント修正する時もあります。
定期的にタグ整理します。ご了承ください。
批判・中傷コメントはお控えください。
見つけ次第削除いたします。
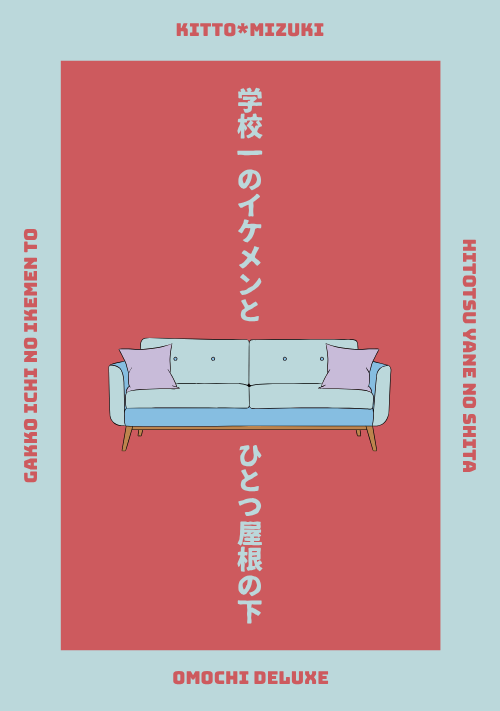
学校一のイケメンとひとつ屋根の下
おもちDX
BL
高校二年生の瑞は、母親の再婚で連れ子の同級生と家族になるらしい。顔合わせの時、そこにいたのはボソボソと喋る陰気な男の子。しかしよくよく名前を聞いてみれば、学校一のイケメンと名高い逢坂だった!
学校との激しいギャップに驚きつつも距離を縮めようとする瑞だが、逢坂からの印象は最悪なようで……?
キラキライケメンなのに家ではジメジメ!?なギャップ男子 × 地味グループ所属の能天気な男の子
立場の全く違う二人が家族となり、やがて特別な感情が芽生えるラブストーリー。
全年齢

久しぶりの発情期に大好きな番と一緒にいるΩ
いち
BL
Ωの丞(たすく)は、自分の番であるαの かじとのことが大好き。
いつものように晩御飯を作りながら、かじとを待っていたある日、丞にヒートの症状が…周期をかじとに把握されているため、万全の用意をされるが恥ずかしさから否定的にな。しかし丞の症状は止まらなくなってしまう。Ωがよしよしされる短編です。
※pixivにも同様の作品を掲載しています

【完結】後悔は再会の果てへ
関鷹親
BL
日々仕事で疲労困憊の松沢月人は、通勤中に倒れてしまう。
その時に助けてくれたのは、自らが縁を切ったはずの青柳晃成だった。
数年ぶりの再会に戸惑いながらも、変わらず接してくれる晃成に強く惹かれてしまう。
小さい頃から育ててきた独占欲は、縁を切ったくらいではなくなりはしない。
そうして再び始まった交流の中で、二人は一つの答えに辿り着く。
末っ子気質の甘ん坊大型犬×しっかり者の男前

君の恋人
risashy
BL
朝賀千尋(あさか ちひろ)は一番の親友である茅野怜(かやの れい)に片思いをしていた。
伝えるつもりもなかった気持ちを思い余って告げてしまった朝賀。
もう終わりだ、友達でさえいられない、と思っていたのに、茅野は「付き合おう」と答えてくれて——。
不器用な二人がすれ違いながら心を通わせていくお話。

自分の気持ちを素直に伝えたかったのに相手の心の声を聞いてしまう事になった話
よしゆき
BL
素直になれない受けが自分の気持ちを素直に伝えようとして「心を曝け出す薬」を飲んだら攻めの心の声が聞こえるようになった話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















