1 / 1
魚の反乱
しおりを挟む
メダカのメダちゃんは激怒した。
必ずや、あの暴虐無人の猫を許してはならぬと。
水槽の中で、メダカはぐるりを一回転して怒りを露わにした。
「いや、そうは言ってもさ。相手は猫だぞ?」
グッピーのぐっちゃんは、諦めるのが早い。
南国の気質のせいか、グッピーたちは、何かにつけて我慢が効かないとメダちゃんは思う。
残念な話だ。
一般家庭にしては、少々大きめのこの水槽世界で育んだ友情はある。
グッピーのぐっちゃんは、メダちゃんの親友だ。
だが、せっかくメダちゃんが怒りに立ち上がって、猫に怒りを向けたというのに、出鼻を挫く発言は聞き捨てならない。
「その蛍光色のひれは節穴か!」
メダちゃんは、すぐに言い返す。
「いや、別に蛍光色は、特に関係ないだろ。なんだよ、ひれが節穴って!」
ぐっちゃんの反論は、かなり正論だ。
目が節穴かどうかなら分かるが、ひれが節穴という概念は、さすがに魚界といえども……ない。
「かの英雄、大きな魚に群れで立ち向かった『僕が目になるよ!』君のように、猫を駆逐することは、きっとできるはずだ!」
メダちゃんが、怒りでひれを震わす。
気持ちはぐっちゃんも分かる。
二十五匹の魚たち、皆、猫には困っているのだ。
穏やかに水槽ライフを楽しむ魚たちを、じっと見つめる大きな瞳には、威圧感がある。
猫は、水槽の蓋を開けはしない。
ただ、じっと見ているだけなのだが、魚たちにとっては、たまったものではない。
遺伝子レベルで刻み込まれた恐怖が蘇り、ストレス絶大になるのだ。
「じゃあさ、皆で編隊を組んで……大きな魚のふりして猫を威圧する?」
「ぐっちゃんよ。それでは、意味がない。大きな魚になったとて、猫が怖がるか?」
きっとメダちゃんがぐっちゃんを睨む。
吐き出す泡も、ブクブクと激しく、メダちゃんの興奮を現わしている。
「いや、喜ぶだろうな」
だって、猫にとって魚は獲物。
それは、猫が普段食べている餌の絵柄を見れば分かる。
お魚ミックスだの、カツオ風味だの、おぞましい猫の食べ物の名前。
ご飯の袋にプリントされた生気を失った魚の絵柄。
それは、全身の毛も……全身の鱗もよだつ光景だ。
だから、猫にとって魚は獲物。
獲物が大きくなったとすれば、それは、猫には喜びしかないだろう。
何だったら、我慢できずについに手を出してくるかもしれない。
最悪だ。
だって、猫にとって魚は獲物。
進撃の猫に城壁を破られて、猫の口に母が収まる光景なんて、ぐっちゃんは見たくない。
「だろう。だから、俺達が大きな魚に擬態したところで、何の効果もないんだ!」
「だったら、どうするって言うんだよ」
ぐっちゃんは、もうそろそろ、この不毛な会話に飽きてきていた。
もうすぐ、飼い主の人間が、餌をまいてくれる時間だ。
早く水面に上がって、美味しい餌にありつきたいと思うのが、正しい魚情ではないか。
そうに違いない。
「待て、ぐっちゃん!」
水面に浮上しようとするぐっちゃんをメダちゃんが引き留める。
「なんだよ。お前も早くしないと、食いっぱぐれるぞ?」
何せこの水槽には、二十五匹も魚がいるのだ。
メダカが十匹。
グッピーが十五匹。
お魚天国を形成している。
みんな、腹ペコ。ご飯は、有限。
うかうかしていると、食事はなくなってしまうのだ。
「我ら一匹一匹は小さくとも、二十五匹の力を合わせれば、必ずや猫に一泡吹かせることができるのだ!」
「いや、だからどうするんだよ」
「それを考えているのではないか」
おい、ここまで会話を引っ張って、考えなしとは、酷くないか?
もうちょっと目処を立ててから提案するのが社会人のマナーではないか。
そろそろ本気でぐっちゃんは嫌になる。
「ぐっちゃん、頼むから一緒に考えてくれ」
「メダちゃん……そう言われても……」
ぐっちゃんだって、猫の嫌いな物なんて考えたことなんて、ないのだ。
巨大な体のモフモフの猫。
大きな瞳で、じっとこちらを見て、ゴロゴロと喉を鳴らしている。
赤い口をパカリと開けて、手をサリサリと舐める様は、思い返してもゾッとする。
あの口に吸いこまれたら、辞世の句を詠むまでもなく魚生が終わるのだ。
ぐっちゃんは、想像しただけで震えあがる。
「ほーら! ご飯だよ!」
人間の声がする。
メダちゃんとぐっちゃんの腹が鳴る。
「仕方ない。今は休憩といこう」
二匹は、仲間の後を追って水面に浮上する。
ご飯は、パラパラと天から降ってくる。
乾燥プランクトンを頬張って、二人ともご機嫌だった。
「今日のプランクトンはあれだで。フレッシュで美味しいで」
「うん、うめえ。これは、開封したての新しいプランクトンでい」
「人間は、この絶品プランクトンを、自分では食べないらしいぜよ」
「何ともそれは人生の半分損している話でごわす」
「口に入れた途端に広がるこおばしいフレーバーも、コクのある喉越しも知らずに一生を終える。なんとも憐れな生き物でおじゃる」
二十五匹の魚たちは、口々に勝手なことを言いながら、ご飯を食べる。
人間は、水槽に魚たちのご飯を落とすと、そのままどこかへ行ってしまった。
魚たちが、夢中でご飯を食べていると、部屋からけたたましい音をする。
ブオオオオオオオ。
「びっくりした。掃除機か」
メダちゃんは、ホッとする。
やめてほしい。
いつも何の予告もなしに、人間は掃除機をかける。
腹が立つ。
せめて、「掃除機をかけてもよろしいでしょうか?」と、お伺いをたててほしい。
メダちゃんは、イラっとする。
「おい、あれ……」
ぐっちゃんが、水槽の外をひれ指す。
「ああ……本当だ」
ぐっちゃんのひれの指した先には、猫がいた。
◇ ◇ ◇
その日、猫は不思議な光景を見た。
いつも覗いている水槽の様子が違うのだ。
魚たちが、群れ成して、何かを形作っている。
「なんだろ……?」
何かに似ている。
見たことのある形……。
ええっと……。
「猫じゃらし!」
猫が答えると、水槽の中の魚たちが一斉に×の形を創り出す。
違うらしい。
丸くって、長い棒がくっついていて……。
「ええっと、たわし?」
また、すぐ×の形に魚たちが、編隊を変える。
また、違うらしい。
困った。
猫は、頭を前足で擦って、悩む。
「どうやら、掃除機とは通じていないが、困っているようだぞ」
メダちゃんは嬉しそうにほくそ笑む。
そもそも、掃除機とは、何なのかが分からないメダちゃん達。
編隊で形を真似してみるが、その再現精度は極めて低い。
猫に分かるわけがないのだ。
あの日、猫が掃除機を怖がって逃げていた。
それを目撃したから、再現しただけのことなのだ。
「あ、諦めて逃げた! メダちゃん! やったよ!」
ぐっちゃんが言う通り、猫が撤退して、爪とぎでバリバリと爪を研いでいる。
「はっは! 悔しがっている!」
最初とは趣旨は違うが、何とか、猫撃退という目的は果たしたようだ。
魚たちは、歓喜の泡を一斉に上げた。
ここは、水槽の中の世界。
クラムボンもぷかぷか浮かばない、小さな世界。
二十五匹の魚たちは、本日も平和である。
「こ、今度こそ当ててやる!」
決意に燃える猫が、時々挑戦にくる以外は、とても平和である。
必ずや、あの暴虐無人の猫を許してはならぬと。
水槽の中で、メダカはぐるりを一回転して怒りを露わにした。
「いや、そうは言ってもさ。相手は猫だぞ?」
グッピーのぐっちゃんは、諦めるのが早い。
南国の気質のせいか、グッピーたちは、何かにつけて我慢が効かないとメダちゃんは思う。
残念な話だ。
一般家庭にしては、少々大きめのこの水槽世界で育んだ友情はある。
グッピーのぐっちゃんは、メダちゃんの親友だ。
だが、せっかくメダちゃんが怒りに立ち上がって、猫に怒りを向けたというのに、出鼻を挫く発言は聞き捨てならない。
「その蛍光色のひれは節穴か!」
メダちゃんは、すぐに言い返す。
「いや、別に蛍光色は、特に関係ないだろ。なんだよ、ひれが節穴って!」
ぐっちゃんの反論は、かなり正論だ。
目が節穴かどうかなら分かるが、ひれが節穴という概念は、さすがに魚界といえども……ない。
「かの英雄、大きな魚に群れで立ち向かった『僕が目になるよ!』君のように、猫を駆逐することは、きっとできるはずだ!」
メダちゃんが、怒りでひれを震わす。
気持ちはぐっちゃんも分かる。
二十五匹の魚たち、皆、猫には困っているのだ。
穏やかに水槽ライフを楽しむ魚たちを、じっと見つめる大きな瞳には、威圧感がある。
猫は、水槽の蓋を開けはしない。
ただ、じっと見ているだけなのだが、魚たちにとっては、たまったものではない。
遺伝子レベルで刻み込まれた恐怖が蘇り、ストレス絶大になるのだ。
「じゃあさ、皆で編隊を組んで……大きな魚のふりして猫を威圧する?」
「ぐっちゃんよ。それでは、意味がない。大きな魚になったとて、猫が怖がるか?」
きっとメダちゃんがぐっちゃんを睨む。
吐き出す泡も、ブクブクと激しく、メダちゃんの興奮を現わしている。
「いや、喜ぶだろうな」
だって、猫にとって魚は獲物。
それは、猫が普段食べている餌の絵柄を見れば分かる。
お魚ミックスだの、カツオ風味だの、おぞましい猫の食べ物の名前。
ご飯の袋にプリントされた生気を失った魚の絵柄。
それは、全身の毛も……全身の鱗もよだつ光景だ。
だから、猫にとって魚は獲物。
獲物が大きくなったとすれば、それは、猫には喜びしかないだろう。
何だったら、我慢できずについに手を出してくるかもしれない。
最悪だ。
だって、猫にとって魚は獲物。
進撃の猫に城壁を破られて、猫の口に母が収まる光景なんて、ぐっちゃんは見たくない。
「だろう。だから、俺達が大きな魚に擬態したところで、何の効果もないんだ!」
「だったら、どうするって言うんだよ」
ぐっちゃんは、もうそろそろ、この不毛な会話に飽きてきていた。
もうすぐ、飼い主の人間が、餌をまいてくれる時間だ。
早く水面に上がって、美味しい餌にありつきたいと思うのが、正しい魚情ではないか。
そうに違いない。
「待て、ぐっちゃん!」
水面に浮上しようとするぐっちゃんをメダちゃんが引き留める。
「なんだよ。お前も早くしないと、食いっぱぐれるぞ?」
何せこの水槽には、二十五匹も魚がいるのだ。
メダカが十匹。
グッピーが十五匹。
お魚天国を形成している。
みんな、腹ペコ。ご飯は、有限。
うかうかしていると、食事はなくなってしまうのだ。
「我ら一匹一匹は小さくとも、二十五匹の力を合わせれば、必ずや猫に一泡吹かせることができるのだ!」
「いや、だからどうするんだよ」
「それを考えているのではないか」
おい、ここまで会話を引っ張って、考えなしとは、酷くないか?
もうちょっと目処を立ててから提案するのが社会人のマナーではないか。
そろそろ本気でぐっちゃんは嫌になる。
「ぐっちゃん、頼むから一緒に考えてくれ」
「メダちゃん……そう言われても……」
ぐっちゃんだって、猫の嫌いな物なんて考えたことなんて、ないのだ。
巨大な体のモフモフの猫。
大きな瞳で、じっとこちらを見て、ゴロゴロと喉を鳴らしている。
赤い口をパカリと開けて、手をサリサリと舐める様は、思い返してもゾッとする。
あの口に吸いこまれたら、辞世の句を詠むまでもなく魚生が終わるのだ。
ぐっちゃんは、想像しただけで震えあがる。
「ほーら! ご飯だよ!」
人間の声がする。
メダちゃんとぐっちゃんの腹が鳴る。
「仕方ない。今は休憩といこう」
二匹は、仲間の後を追って水面に浮上する。
ご飯は、パラパラと天から降ってくる。
乾燥プランクトンを頬張って、二人ともご機嫌だった。
「今日のプランクトンはあれだで。フレッシュで美味しいで」
「うん、うめえ。これは、開封したての新しいプランクトンでい」
「人間は、この絶品プランクトンを、自分では食べないらしいぜよ」
「何ともそれは人生の半分損している話でごわす」
「口に入れた途端に広がるこおばしいフレーバーも、コクのある喉越しも知らずに一生を終える。なんとも憐れな生き物でおじゃる」
二十五匹の魚たちは、口々に勝手なことを言いながら、ご飯を食べる。
人間は、水槽に魚たちのご飯を落とすと、そのままどこかへ行ってしまった。
魚たちが、夢中でご飯を食べていると、部屋からけたたましい音をする。
ブオオオオオオオ。
「びっくりした。掃除機か」
メダちゃんは、ホッとする。
やめてほしい。
いつも何の予告もなしに、人間は掃除機をかける。
腹が立つ。
せめて、「掃除機をかけてもよろしいでしょうか?」と、お伺いをたててほしい。
メダちゃんは、イラっとする。
「おい、あれ……」
ぐっちゃんが、水槽の外をひれ指す。
「ああ……本当だ」
ぐっちゃんのひれの指した先には、猫がいた。
◇ ◇ ◇
その日、猫は不思議な光景を見た。
いつも覗いている水槽の様子が違うのだ。
魚たちが、群れ成して、何かを形作っている。
「なんだろ……?」
何かに似ている。
見たことのある形……。
ええっと……。
「猫じゃらし!」
猫が答えると、水槽の中の魚たちが一斉に×の形を創り出す。
違うらしい。
丸くって、長い棒がくっついていて……。
「ええっと、たわし?」
また、すぐ×の形に魚たちが、編隊を変える。
また、違うらしい。
困った。
猫は、頭を前足で擦って、悩む。
「どうやら、掃除機とは通じていないが、困っているようだぞ」
メダちゃんは嬉しそうにほくそ笑む。
そもそも、掃除機とは、何なのかが分からないメダちゃん達。
編隊で形を真似してみるが、その再現精度は極めて低い。
猫に分かるわけがないのだ。
あの日、猫が掃除機を怖がって逃げていた。
それを目撃したから、再現しただけのことなのだ。
「あ、諦めて逃げた! メダちゃん! やったよ!」
ぐっちゃんが言う通り、猫が撤退して、爪とぎでバリバリと爪を研いでいる。
「はっは! 悔しがっている!」
最初とは趣旨は違うが、何とか、猫撃退という目的は果たしたようだ。
魚たちは、歓喜の泡を一斉に上げた。
ここは、水槽の中の世界。
クラムボンもぷかぷか浮かばない、小さな世界。
二十五匹の魚たちは、本日も平和である。
「こ、今度こそ当ててやる!」
決意に燃える猫が、時々挑戦にくる以外は、とても平和である。
102
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

こわがり先生とまっくら森の大運動会
蓮澄
絵本
こわいは、おもしろい。
こわい噂のたくさんあるまっくら森には誰も近づきません。
入ったら大人も子供も、みんな出てこられないからです。
そんなまっくら森のある町に、一人の新しい先生がやってきました。
その先生は、とっても怖がりだったのです。
絵本で見たいお話を書いてみました。私には絵はかけないので文字だけで失礼いたします。
楽しんでいただければ嬉しいです。
まんじゅうは怖いかもしれない。


笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

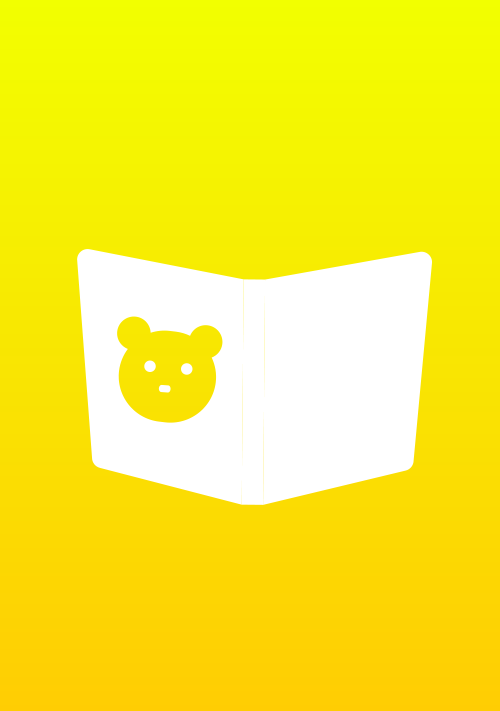
風船タコさん会えるかな?
いもり〜ぬ(いもいもぶーにゃん)
絵本
おととの左手は、おいしいソースいいにおい、ホカホカたこ焼きの入った袋。
ボクの右手は、タコさん風船のひも。
タコさん風船、タコ焼き屋さんでくれはった。
タコさん風船、ボクの頭の上をぷっかぷっか気持ちよさそう。
風船タコさんがボクをちらっ、ちらっ。
そしてボクをじーっと見る。
ボクも風船タコさんを見る。
そして「タコさん、わかったで」とうなずく。

児童絵本館のオオカミ
火隆丸
児童書・童話
閉鎖した児童絵本館に放置されたオオカミの着ぐるみが語る、数々の思い出。ボロボロの着ぐるみの中には、たくさんの人の想いが詰まっています。着ぐるみと人との間に生まれた、切なくも美しい物語です。


合言葉はサンタクロース~小さな街の小さな奇跡
辻堂安古市
絵本
一人の少女が募金箱に入れた小さな善意が、次々と人から人へと繋がっていきます。
仕事仲間、家族、孤独な老人、そして子供たち。手渡された優しさは街中に広がり、いつしか一つの合言葉が生まれました。
雪の降る寒い街で、人々の心に温かな奇跡が降り積もっていく、優しさの連鎖の物語です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















