35 / 35
第九章 皇妃候補から外れた公爵令嬢の再生
第三十五話 東雲の空を行け
しおりを挟む満月の夜から二度の朝を越え、月はすでに欠け始めている。
日没頃に東の空から登り始めたそれが、もう間もなく南の空の天辺に辿り着こうという頃、ソフィリアは皇帝執務室でも私室でもない場所にいた。
広い王宮のあちこちには主のいない部屋がいくつも存在するが、ふいの来客や会議などに使用されることもあるため常に手入れがされている。
皇帝やその一族だけではなく、各大臣や貴族、ある程度の地位にある城仕えの者ならば、当日の申請でも利用が可能。
ソフィリアもこれまで、ルドヴィークをはじめとするお馴染みスミレ会の面々で集まったり、同期の文官の結婚を祝うパーティなどで何度か使用したことがある。
この時ソフィリアがいたのは、そんな空き部屋のうち、後宮にほど近い場所にある一室だった。
部屋の規模は、皇帝執務室よりは狭いものの、ソフィリアの私室に比べれば格段に広い。
調度は、壁際にワイングラスが並んだ大きなキャビネットと、部屋の中央にソファセットがあるだけだが、ソファはごろ寝ができるくらい座面が広くゆったりとしたものが置かれていた。
掃き出し窓の向こうには広いバルコニーがあり、月を映した池が見下ろせる。
北からやってきて三ヶ月ほど過ごしていた渡り鳥達も、ここで孵った子らを連れてそろそろ南に向かう頃合いだろうか。
窓辺に立ったソフィリアがそんなことを考えていた時だった。
コンコン、というノックの音がしたかと思ったら、返事も待たずに扉が開く。
ソフィリアは振り返って、勝手知ったる相手に微笑みを向けた。
「お呼び立てして申し訳ありません――陛下」
現れたのは、この城の――それどころか、このグラディアトリアの現在の最高権力者、皇帝ルドヴィーク。
ソフィリア同様、今朝方パトラーシュとコンラートの宰相一行を見送った後は休暇となっていた彼は、片手にワインボトルを携えている。
シャツとズボンという砕けた格好をし、ほんのりと髪が濡れているところを見ると、湯浴みも済ませてきたようだ。
かく言うソフィリアも入浴を済ませ、淡い色合いのゆったりとしたワンピースに身を包んでいた。
扉を振り返った拍子に肩口を掠めて揺れた彼女の短い髪に、ルドヴィークが目を細める。
「ソフィに呼び立てられるのは一向に構わないが……まさか、こいつが呼びにくるとは思わなかったぞ」
苦笑いを浮かべてそう言う彼の腕には、黄緑色をした植物の蔓が絡み付いていた。
一昨日の夜、騒動の最中に庭園で月光を浴びて急激な成長を遂げたプチセバスである。
誕生日に贈られ、立派に育って主人であるソフィリアに幸せを運ぶよう、スミレに命じられていた光景さえもう懐かしい。
ソフィリアが手を差し伸べると、ルドヴィークの腕から彼女の腕へとぴょんと飛び移り、褒めて褒めてとばかりに柔らかな葉を擦り寄せた。
「お使いご苦労様でした、プチセバス。どうもありがとう。大変ではなかったかしら?」
「いや、大変だったのはそのお使いを目撃した者達だろう。何しろこいつ、廊下をぺたぺた歩いてやってきたんだからな」
他にもレイスウェイク大公爵家の蔦執事セバスチャンから分かたれた株は存在するが、そんな中でもプチセバスは一味違う。
なんと彼は、水を張ったガラス容器から根ごと這い出て、まるで動物みたいに自由に移動するようになったのだ。
そんな摩訶不思議な植物の出現に、王城の一角は騒然となった。
「おかげで、ソフィに会いに行くのがクロヴィスに知れてな。こいつを持たされた」
「年代物のワインでございますね。あら……これ、私達が生まれた年に作られたものではありませんか」
ソフィリアは壁際のキャビネットからワイングラスを二つ取り出す。
一方、ソファに腰を下ろしたルドヴィークは、早速次兄に進呈されたワインを開けた。
二十六年ものの赤ワインだ。
栓を開けたとたん、閉じ込められていた芳醇な香りが解放される。
ルドヴィークはそれにスンと鼻を鳴らしたが、グラスを携えたソフィリアが隣に座ったとたんに首を傾げた。
「ソフィ……何か、新しい香を使っているか?」
「あら、お気づきになりました? 昼間、スミレが届けてくれた香油を髪に付けてみたんです」
ソフィリアは二つのグラスにワインを注ぎながら、さらりと髪を揺らして続ける。
「イランイランという名の植物の花から採ったもので……なんでも、えっちな気分になる香だとか」
「ふむ、えっち。……えっち、とは何だ?」
「さあ? 大公閣下は、それをお聞になったとたんに噎せていらっしゃいましたけれど」
「いや……それ、絶対碌でもないやつだろう?」
ルドヴィークはたちまち警戒するような素振りをする。
しかしながら、濃厚な甘い香りは決して不快なものではなく、むしろ彼の興味を引いた。
まるで花に誘われたかのように、香りの元に顔を寄せる。
香っているのはソフィリアの髪であるから、必然的に二人の顔が近付いた。
――それこそ、もう少しで唇が触れ合いそうなくらいに。
「……」
互いに無言のまま、視線だけが絡み合う。
沈黙を破ったのは、ルドヴィークだった。
彼はソフィリアから視線を外さないまま、ワインが注がれたグラスを持ち上げて呟く。
「私達はともにこのワインと同じ年に生まれ……実質、婚約者のような立場にあったな」
「……そうでございますね。私も……ずっと漠然と、将来は陛下と結婚するのだと思って生きておりました」
ソフィリアもルドヴィークに倣ってグラスを手に取った。
けれども二人とも、ワインに口を付けることなく会話を続ける。
「とはいえ、かつて私達はお互いのことを何も知らなかった……いや、知ろうとしなかった。ソフィは、私自身になど興味はなかったのだろう?」
「あら、それは陛下も同じでございましょう? 私のことはどうせ、父の付属品くらいの認識だったのではありませんか?」
ソフィリアはツンと澄まして言い返したが、しかし今宵はいつものように軽口の掛け合いに発展することはなかった。
ルドヴィークが、あまりにも優しい笑みを浮かべて言うからだ。
「それなのに、不思議だな――今は、ソフィ自身への興味が尽きない。お前の、何もかもを知りたいと思う」
ソフィリアの頬がぱっと色づいた。
それを見たルドヴィークは、笑みを深めて続ける。
「――ソフィが、好きだ」
改めて告げられた想いが、ソフィリアの胸に深く染み入った。
今こそ、彼女もルドヴィークに気持ちを伝える時だ。
「わ、私も、陛下が……」
ところが、いざとなるとうまく言葉が出てこない。
これが仕事上の議論の場だったのなら、相手がルドヴィークだって、父だって、それこそ泣く子も黙ると恐れられる宰相閣下にだって、堂々と意見を述べられるというのに。
自分の心のうちをさらけ出すのは何とも難しいことだとソフィリアは思い知る。
それでも今、どうしても、ルドヴィークにこの想いを伝えたかった。
いつの間にか、見て見ぬふりなどできないくらいに大きく成長してしまった、彼への想いを――。
ルドヴィークもまた、ソフィリアの言葉をじっと待ってくれている。
ソフィリアはドキドキと煩い胸を片手で押さえつつ――
「私も、陛下が……ルドヴィーク様が――好きです」
喘ぐように言葉を紡いだ。
たちまち、ルドヴィークが溢れんばかりの笑顔になる。
「それをお伝えしたくて……今宵こうしてお呼び立てしました」
「ああ……そうであってほしいと期待して、私もここに来た」
心の底から嬉しくてたまらないと言わんばかりの彼の全てが、ソフィリアもまた、たまらなく愛おしい。
二人は、ここでようやくワインに口を付ける。
彼らと同じだけの年月熟成されてきたワインは、渋みが取れてまろやかな味わいになっていた。
クロヴィスが何を思ってこのワインを用意し、どういう気持ちで今宵ルドヴィークに渡したのか。
弟への、そしておそらく、自らの手で一端の文官へと育て上げたソフィリアへの、宰相閣下の愛情の深さが感じられた。
ソフィリアはそれを感慨深い思いで味わいながら、この日の昼間に父ロートリアス公爵と話したことを打ち明ける。
ルドヴィークはそれに相槌を打ちながら真摯に耳を傾けてくれたが、母のことに話が及んだとたん、ほうっと大きく息を吐き出した。
「そうか、母上が……。それでは、母上の思いはスカーフに託されて、いつもソフィに寄り添ってくれていたんだな」
「はい……」
ルドヴィークは、ソフィリアが母親と疎遠になっていることを心配していたらしい。
彼は、それにしても、と苦笑いを浮かべて続けた。
「八年経ってもまだ素直になれないとは……ソフィと母上は、意地っ張りなところがそっくりだな」
「まあ、陛下。心外ですわ。意地っ張りなのは母だけで、私は違いますもの」
「よく言う。お前だって文官の試験に合格して以来、一度も家に帰っていないだろう。母上が謝る機会を奪っていたソフィにも、反省すべきところはあるのではないか?」
「それは……」
ソフィリアはぐっと口を噤む。ルドヴィークの言う通りだった。
確かに八年前、母から心無い言葉をかけられて傷付いたが、ソフィリアはそれ以来ずっと彼女から逃げて背中を向けたままだった。
母が自分に見向きもしてくれなくなったなんて嘆きつつ、その実、ソフィリアだって母と分かり合う努力を怠ってきたのだ。
痛いところを突かれて言い返すこともできず、ソフィリアは俯く。
そんな彼女の前髪を優しく指先で梳きながら、ルドヴィークが笑って言った。
「この意地っ張りな家出娘の手を引いて、私も一度、母上にご挨拶に伺わねばならないな」
その言葉にソフィリアははっとして顔を上げる。
好きだ、と子供みたいに純粋な気持ちを伝え合ったが、ソフィリアもルドヴィークも、もう子供ではない。
両思いとなった大人の男女、しかも、相手が次代のグラディアトリアを担う跡継ぎが必要な皇帝ともなれば、二人が目指す先は……
「ソフィ、お前の二十七歳の誕生日――私は、夫として祝いたいと思っている」
先日のソフィリアの二十六歳の誕生日の夜、お互いこの年になっても独り身でますます風当たりが強くなりそうだ、と冗談を言い合ったルドヴィークは、ソフィリアをまっすぐに見つめてそう告げた。
「かつて、私達が婚約者のような関係にあったのは、兄上やロートリアス公爵の意向だった。だが今は、私自身の意思によってソフィを皇妃に望む――ソフィ、私との結婚を考えてほしい」
「陛下、私は……」
ところがこの期に及んで、ソフィリアは言い淀んだ。
娘が皇妃になると知れば、母は喜んでくれるかもしれない。
しかし彼女はきっと、ソフィリアも理想の母親像そのものだと敬愛する母后陛下みたいな、優しく包み込むような国母となることを望むだろう。
そしておそらく母以外にも多くの者が、ソフィリアにそうあるよう期待するに違いない。
後宮に入り、皇帝の子供を産み育て、たおやかに国民を愛することにこそ人生を捧げよ、と。
かつての、ただのロートリアス公爵令嬢でしかなかったソフィリアならば、その枠にうまく収まれたかもしれない。
けれども、ソフィリアはもう、それ以外の生き方を知ってしまった。
「私は……皇妃となっても、今の仕事をやめたくありませんわ。もっと文官として働きたいですし、何より……」
ソフィリアはワインの残ったグラスをテーブルに戻し、おずおずとルドヴィークを見上げて続ける。
「陛下の、一の部下の座を……まだ誰にも譲りたくありません」
とたん、ルドヴィークが破顔した。
「うん、私もだ。ソフィ以外を補佐官として置くことは、まったくもって想像できないな」
「私は母后陛下のように、全てを癒し包み込むような素敵な国母にはきっとなれないでしょう。それでも……?」
「何の問題もない。母は母、ソフィはソフィだ。私は、そんなソフィが好きなんだ」
「陛下……」
不安も何もかも払拭するように、ルドヴィークが力強く笑う。
その笑顔に背を押され、ソフィリアは彼を真っ直ぐに見つめて告げた。
「私は、陛下の補佐官でありたいし、友人でもありたいし、その上、あなたの愛情までほしいと思う欲張りなんです」
「はは、奇遇だな。私もまったく同じだ」
ぐいっとワインを飲み干したルドヴィークが、空になったそれをテーブルに置く。
そうして、自由になった手でソフィリアの肩を抱いた。
「補佐官としてのソフィも、友人としてのソフィも、そして伴侶としてのソフィも――私は全部ほしい」
彼の胸にそっと手を添え、ソフィリアは瞼を閉じた。
さらりと頬をくすぐるのは、ルドヴィークの髪だろう。
やがて、唇が重なる。
二人の心が、ぴったりと重なった瞬間でもあった。
「陛下」
「うん?」
「ルドヴィーク様」
「ん?」
ルドヴィークが、ソフィリアの髪に鼻先を埋めながらキスをする。
イランイランの甘い香りを堪能するみたいにスンと鼻を鳴らす彼に、実は、とソフィリアは続けた。
「えっち、とは何か……本当は、スミレに教えてもらったので知っておりますの」
「ほう? それで、結局どういう意味なんだ?」
かつてのような、世間知らずなロートリアス公爵令嬢はもうどこにもいない。
泣く子も黙ると恐れられる宰相閣下とさえ渡り合える、強かな女性へと成長を遂げたのだ。
それを証拠に、想いが通じ合ってご満悦の様子の皇帝陛下を見上げ、ソフィリアは悪戯っぽい笑みを浮かべて言った。
「えっちとは、〝淫ら〟とか〝いやらしい〟とか、いわゆる性的ないことを意味するんですって」
「……っん、な!?」
「いかがですか、陛下? 〝えっちな気分〟になりまして?」
「は……!?」
あまりの不意打ちに、ルドヴィークはただただぽかんとする。
そんな彼から目を逸らし、ソフィリアが密やかな声で呟く。
その頬は、薔薇色に染まっていた。
「私は……少し、そういう気分になっております」
「……っ、ソフィ……」
ルドヴィークの喉が、さっきワインを飲み干した時よりもずっと大きく、ごくりと鳴った。
窓辺ではプチセバスが、ガラス容器に張られた水に根を浸しつつ、薄く開いたカーテンの隙間から漏れる月の光を浴びている。
主人であるソフィリアのために役目を全うしたその姿は、実に誇らしげであった。
夜が、深まる。
この夜を境に、ソフィリアの世界はまた、生まれ変わった。
「……?」
何かに誘われるように、ソフィリアの意識が深い眠りの淵から浮上する。
のろのろと瞼を開くも、辺りはまだ随分と暗かった。
そんな中でまず気づいたのは、昨夜髪に塗り込んだイランイランの甘い香り。
けれども、それよりも顕著に感じるのは、隣に横たわる愛しい人の香りだ。
すぐ側のテーブルには、ワインボトルとグラスが二つ、影を落としていた。
ふいに外が騒がしいのに気付いたソフィリアは、気怠い身体を起こして窓に向かって腕を伸ばす。
ソフィリアとは反対に、これから眠りに就こうとしているプチセバスを気遣いつつ、薄くカーテンを開いた。
その時だった。
「あっ……」
バサバサと羽音を響かせて、鳥達の影が一気に空へと舞い上がった。
グラディアトリア城の池で繁殖を終えた渡り鳥達が、ついに南を目指して旅立つらしい。
ソフィリアにとって人生の大きな節目となるこの朝、ここで生まれた渡り鳥の雛達もまた、新たな世界へと飛び立つ。
窓の外もまだ薄暗かった。
しかし、東の空はすでに白み始めている。
その空の色を一言で表現するのは難しい。
少し紫がかった雲に、黄色やピンク、青を混ぜたような神秘的な情景の中を、黒い影となった渡り鳥の群れが行く。
しばし言葉も忘れてそれを眺めていたソフィリアだったが、ふと、この光景を独り占めするのが惜しくなった。
「ねえ、起きてくださいまし」
「……ん……」
美しい光景も、それに覚えた感動も、分かち合いたいと思う相手がいる。
ソフィリアはその人と一緒に、この先の人生を歩んでいくと決めたのだ。
「陛下――ルドヴィーク様、朝ですよ」
「うん……おはよう、ソフィ」
やがて開いたルドヴィークの青い瞳――そこに映った東雲の空を、ソフィリアは一生忘れることはない。
次に渡り鳥達がグラディアトリアに戻ってくる時。
彼女は補佐官として、友人として――
そして、妻として、彼の隣にあるだろう。
終
34
この作品の感想を投稿する
みんなの感想(19件)
あなたにおすすめの小説

虐げられ続けてきたお嬢様、全てを踏み台に幸せになることにしました。
ラディ
恋愛
一つ違いの姉と比べられる為に、愚かであることを強制され矯正されて育った妹。
家族からだけではなく、侍女や使用人からも虐げられ弄ばれ続けてきた。
劣悪こそが彼女と標準となっていたある日。
一人の男が現れる。
彼女の人生は彼の登場により一変する。
この機を逃さぬよう、彼女は。
幸せになることに、決めた。
■完結しました! 現在はルビ振りを調整中です!
■第14回恋愛小説大賞99位でした! 応援ありがとうございました!
■感想や御要望などお気軽にどうぞ!
■エールやいいねも励みになります!
■こちらの他にいくつか話を書いてますのでよろしければ、登録コンテンツから是非に。
※一部サブタイトルが文字化けで表示されているのは演出上の仕様です。お使いの端末、表示されているページは正常です。

愛する旦那様が妻(わたし)の嫁ぎ先を探しています。でも、離縁なんてしてあげません。
秘密 (秘翠ミツキ)
恋愛
【清い関係のまま結婚して十年……彼は私を別の男へと引き渡す】
幼い頃、大国の国王へ献上品として連れて来られリゼット。だが余りに幼く扱いに困った国王は末の弟のクロヴィスに下賜した。その為、王弟クロヴィスと結婚をする事になったリゼット。歳の差が9歳とあり、旦那のクロヴィスとは夫婦と言うよりは歳の離れた仲の良い兄妹の様に過ごして来た。
そんな中、結婚から10年が経ちリゼットが15歳という結婚適齢期に差し掛かると、クロヴィスはリゼットの嫁ぎ先を探し始めた。すると社交界は、その噂で持ちきりとなり必然的にリゼットの耳にも入る事となった。噂を聞いたリゼットはショックを受ける。
クロヴィスはリゼットの幸せの為だと話すが、リゼットは大好きなクロヴィスと離れたくなくて……。

【完結】婚約破棄された令嬢の毒はいかがでしょうか
まさかの
恋愛
皇太子の未来の王妃だったカナリアは突如として、父親の罪によって婚約破棄をされてしまった。
己の命が助かる方法は、友好国の悪評のある第二王子と婚約すること。
カナリアはその提案をのんだが、最初の夜会で毒を盛られてしまった。
誰も味方がいない状況で心がすり減っていくが、婚約者のシリウスだけは他の者たちとは違った。
ある時、シリウスの悪評の原因に気付いたカナリアの手でシリウスは穏やかな性格を取り戻したのだった。
シリウスはカナリアへ愛を囁き、カナリアもまた少しずつ彼の愛を受け入れていく。
そんな時に、義姉のヒルダがカナリアへ多くの嫌がらせを行い、女の戦いが始まる。
嫁いできただけの女と甘く見ている者たちに分からせよう。
カナリア・ノートメアシュトラーセがどんな女かを──。
小説家になろう、エブリスタ、アルファポリス、カクヨムで投稿しています。

今宵、薔薇の園で
天海月
恋愛
早世した母の代わりに妹たちの世話に励み、婚期を逃しかけていた伯爵家の長女・シャーロットは、これが最後のチャンスだと思い、唐突に持ち込まれた気の進まない婚約話を承諾する。
しかし、一か月も経たないうちに、その話は先方からの一方的な申し出によって破談になってしまう。
彼女は藁にもすがる思いで、幼馴染の公爵アルバート・グレアムに相談を持ち掛けるが、新たな婚約者候補として紹介されたのは彼の弟のキースだった。
キースは長年、シャーロットに思いを寄せていたが、遠慮して距離を縮めることが出来ないでいた。
そんな弟を見かねた兄が一計を図ったのだった。
彼女はキースのことを弟のようにしか思っていなかったが、次第に彼の情熱に絆されていく・・・。
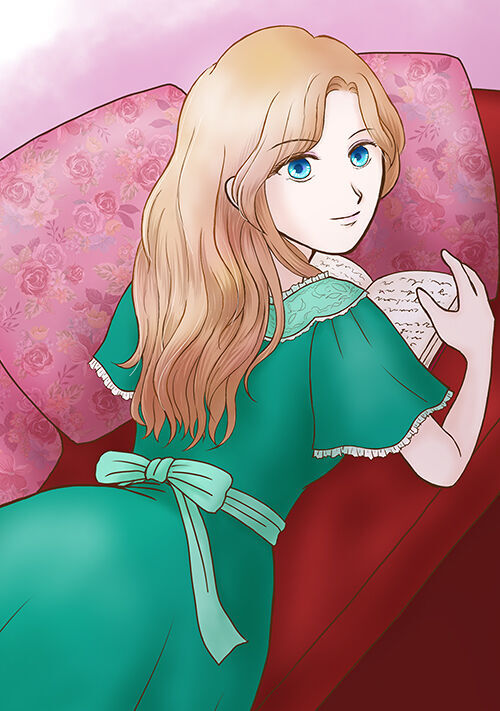
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

婚約者を妹に譲ったら、婚約者の兄に溺愛された
みみぢあん
恋愛
結婚式がまじかに迫ったジュリーは、幼馴染の婚約者ジョナサンと妹が裏庭で抱き合う姿を目撃する。 それがきっかけで婚約は解消され、妹と元婚約者が結婚することとなった。 落ち込むジュリーのもとへ元婚約者の兄、ファゼリー伯爵エドガーが謝罪をしに訪れた。 もう1人の幼馴染と再会し、ジュリーは子供の頃の初恋を思い出す。
大人になった2人は……

P.S. 推し活に夢中ですので、返信は不要ですわ
汐瀬うに
恋愛
アルカナ学院に通う伯爵令嬢クラリスは、幼い頃から婚約者である第一王子アルベルトと共に過ごしてきた。しかし彼は言葉を尽くさず、想いはすれ違っていく。噂、距離、役割に心を閉ざしながらも、クラリスは自分の居場所を見つけて前へ進む。迎えたプロムの夜、ようやく言葉を選び、追いかけてきたアルベルトが告げたのは――遅すぎる本心だった。
※こちらの作品はカクヨム・アルファポリス・小説家になろうに並行掲載しています。

愛する人は、貴方だけ
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
下町で暮らすケイトは母と二人暮らし。ところが母は病に倒れ、ついに亡くなってしまう。亡くなる直前に母はケイトの父親がアークライト公爵だと告白した。
天涯孤独になったケイトの元にアークライト公爵家から使者がやって来て、ケイトは公爵家に引き取られた。
公爵家には三歳年上のブライアンがいた。跡継ぎがいないため遠縁から引き取られたというブライアン。彼はケイトに冷たい態度を取る。
平民上がりゆえに令嬢たちからは無視されているがケイトは気にしない。最初は冷たかったブライアン、第二王子アーサー、公爵令嬢ミレーヌ、幼馴染カイルとの交友を深めていく。
やがて戦争の足音が聞こえ、若者の青春を奪っていく。ケイトも無関係ではいられなかった……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。





















一話から最終話まで二時間で読破してしまうほど面白すぎて夢中になりました( ◍•㉦•◍ )♡
蔦王購入します❤️✨
蔦王時代から読んでます!
質問なんですが、トマトの研究は今現在どうなってるのですか?
ソフィもルドも、本当に幸せそうで良かったです😍
先生、ありがとうございました❣️
また、ソフィとルドの番外編で お会いしたいです💕