1 / 7
1.出会い
しおりを挟む
「リネー、わかっているな」
「ええ、勿論です。お父様」
「お前の美しさはこの時の為にある」
心の中では『くだらない』、と思いながらもそんな事はおくびにも出さない。
躾けられた通り頭を下げて貴族の礼をして、躾けられた通りの笑顔で笑う。
「私たちの狙いは、このシェーンフェルト家の更なる繁栄だ。たかが一介の子爵家との縁談なんぞ、何にもならん。いいか、お前はお前の与えられた役目を果たせ」
一度もリネーの顔を見ずに、強い口調で必要な事だけを言って父親は部屋から出て行った。
扉が完全に閉じるのを確認してから、どっかりと背後のチェアに身体を投げ出すように座った。
「リネー様……」
「ラニ、紅茶でも入れてくれないか」
「すぐにご用意致します」
ラニは幼い頃よりリネーに仕える世話係だ。褐色の肌に、黒い髪を背まで伸ばした姿勢の良い姿が、湯を沸かしに部屋の外へと出ていく。心配させただろうか。ラニはいつだってリネーを気遣っている。
少し開いた窓の隙間から心地の良い風が流れ込んできて、柔らかくリネーの髪を撫でていく。ダークブラウンの髪が風に揺れる。
リネーの生い立ちは少々複雑だ。
この、誰もが美しいと褒める顔立ちのおかげで、酷い目にだけは合わないでここまで生きて来られた。
(けど、それもここまでかもな)
この国一番の美人だと言われていた母親は、リネーが産まれてすぐに死んでしまった。産後の肥立ちが悪かったらしい。生まれてからすぐの頃はまだ、母の生き写しだと言って父にも愛されていた。その父親の態度がすっかり変わってしまったのは、リネーがオメガだとわかったその瞬間からだ。
それまではきっと、リネーがアルファになると信じて疑わなかったのだろう。医師が告げた検査結果を父親はその場で破り捨てた。
新しく来た継母も、リネーがオメガだとわかるなり露骨に態度を変えるようになった。この国ではオメガが当主になる事はないからだ。それまではリネーが当主になる可能性もあったからこそ、優しくしてくれていたのだろう。リネーが当主にならないのであれば、継母の産んだ子が当主になる。
元よりそれほど親しくしていたわけでもなかったが、家族として信頼できる相手は物心つくころにはいなくなっていた。
そして、先日、継母の産んだ子が十六歳になると同時に、次期当主になる事が正式に決まった。
そうとなれば、直系の子と言えどオメガのリネーはこの家ではお役御免だ。この国でのオメガの地位は低い。卑しい性別だと言われて、大抵が酷い扱いを受ける。運良く優秀なアルファに見初められれば救いの道はあるのかもしれないが、貴族同士の結婚は家同士の結婚だ。親が縁談を取り持ってくれない限りは、縁が出来る事は無い。オメガが歩き回って結婚相手を探す事など言語道断だ。
おとぎ話にあるような運命の相手など見つけられるはずもないのだから、貴族の家のオメガに産まれた子は、せめて家に利のある優秀なアルファになんとか見初めて貰おうと品評会とでも言うべきダンスパーティーへ出席する。リネーも偶発的な発情を避ける為に薬を飲まされて、パーティーへ出席させられていた時期もあった。
パーティーへの参加している間だけは、リネーは自由に振舞えた。
見目の良さも手伝って、いろんなアルファから言い寄られて、その度に気を持たせるような事を言って、相手とも何度かのパーティーで良い関係を築けていた事もあった。けれどどれだけ良い関係を築いたとしても、何度目かのパーティーで、相手に縁談がまとまったという噂を聞くことになる。それはただ自分の不運のせいだと思っていたのだが、当時持ち掛けられた縁談の、どれもが父親に断られてしまっていた事を知ったのは、随分と後の事だ。
ただ、オメガだったというだけで、それほど父親に憎まれる事をしたのだろうか。
オメガとして、家に良縁を齎そうとしていた事すら、無かった事にされるような、それほどであるのならいっそのことパーティーへなんか送り出さなければいいのに。
(家としての体面もあったんだろうな)
オメガが家にいるのにパーティーに出さないとなると、悪い病気を持っているなどと噂話を立てられてしまう。それを嫌がったのだろう。
両家の子息の縁談は断る事は無かったとは思うのだが、それでも父親からすれば、母親とうり二つの美しい顔を持ちながら卑しいオメガとして産まれた息子を許せなかったのかもしれない。
継母の子が優秀に育ち、次期当主となれそうだと判断されてからはパーティーの招待状も届かなくなってしまった。父親の元へは届いていたのかもしれないが、リネーにそれが手渡される事は無かった。
顔を合わせることも、ダンスパーティーへの参加を促されることもなくなり、家族との交流も随分と途絶えてしまっていた。オメガと判断されてすぐに、リネーは屋敷の別邸で暮らすようになっていた。それは表向きは、リネーをアルファから守るための措置だったが、少し考えればそれが、ただ疎まれた末の事なのだとわかる。
だから先ほど突然部屋を訪ねて来た父親とは、久しぶりの邂逅だった。何年も顔を合わせていなかったのだ。
突然の来訪だけでも驚いたのに、更に驚いた事に父親が持ってきたのは、ヴェクテル子爵家とリネーの縁談だった。
あれほどリネーへの縁談を断っていた癖に、とは思えど、口にすることなど許されない。
縁談相手のヴェクテル子爵家のアルベルト・リンデホルムは、年若くして最近爵位を継いだと聞いたばかりだ。齢の頃は二十四歳くらいだったはずだ。貴族にしては遅い縁談だろう。つい最近、爵位を継いだ話を聞いた時に、随分と遅い発表だと思ったのだ。家を継ぐこと自体は大抵十六の歳を迎える頃に発表になる。
それから大抵が成人する前には縁談も結んでしまうものだ。
その事を不思議に思って尋ねれば、アルベルトは長い間他国に留学していたのだという。
リネーは二十六歳で、2つ年上になる。この齢になると縁談などもう来ないのだと思っていた。互いに縁談の遅い者同士、と言う事なのかもしれない。
この家の別邸で、生涯一人で、誰からも忘れ去られて、この生を終えるのだと思っていた。
「リネー様、お持ち致しました」
甘い香りの菓子を添えて、目の前のテーブルに置かれたのはリネーの好む紅茶だった。テキパキとティーセットを並べていくラニは、幼い頃にリネーが奴隷市で拾って来た。それ以来の付き合いだがよく懐いて仕えてくれている。少女だったラニを引き取った時は、ただ自分のように哀れな身分の子どもが一人でもいなくなればいいと思っての事だったが、今ではただ一人、信頼のおける家族だった。
「…………ラニ、お前はついて来なくても」
「いいえ、リネー様。どこまでもお供致します。この家に残るなど、望んでいません」
「ラニ、話は聞いていただろう」
「だからこそ、です」
お側にいさせてください、と床に膝をついて、リネーの手を取り、その手の甲に額を押し付ける最上位の礼をされてしまえばもう断れない。
「茨の道だぞ」
「承知の上です」
あの父親の持ってくる縁談が、ただリネーを思っての縁組であるはずがなかった。
政略結婚。それだけなら、まだ、良かった。
『アルベルト・リンデホルムの弱みを握って醜聞を晒せ』
『…………アルベルト様には、何か、そのような疑惑が?』
『無いから作れと言っている。相変わらず物分かりの悪いやつだな』
シェーンフェルトは伯爵家だ。その伯爵家からオメガとは言え、直系男子との縁談を結ぶのであれば、アルベルトの家からすれば随分な格上との結婚という事になる。ヴェクテル子爵家からすれば望んだ以上の縁談だろう。
それが、なぜ、格上であるはずのこちらからそんな工作が必要なのか。
『ヴェクテル子爵はどうやら隣国の王家との繋がりがあるらしい。定かではないがな。ここの所、他の伯爵家からの覚えもめでたい。諸外国を渡り歩いたお陰で、各国の権力者とも縁がある。潰しておくに越したことはない』
『………………承知しました』
つまりは、リネーに醜聞を偽装させて、アルベルトを告発し、家もろとも取り潰したいのだろう。
上手くやれば、告発をしたシェーンフェルトの家は家名を上げる事になり、有力な貴族をねじ伏せる事になる。一方で、きっと醜聞を偽装したリネーはアルベルトと共に消されるに違いない。真実を知る者は少なければ少ないほどいいからだ。
リネーの側にいれば、ラニもきっと関わる事になる。
(…………ラニは、どこかで逃がしてやろう)
どこかの家に嫁がせてもいい。早い内に手放してしまわなければ。
せめて一人くらいは、自分に関わった人間を幸せにしたいと願ったって罰は当たらないはずだ。
父親の命令が、自分に害を為すものだったとして断れるわけもない。
結局自分はあの父親の子で、シェーンフェルトの家のオメガだ。政略結婚で嫁ぐのだから、自分の役割を果たすことくらいしかリネーに出来ることはない。
いくら父親に言われた事が不条理だったとしても、リネーに逆らう事は許されない。
「ごきげんよう、ヴェクテル子爵」
「お目にかかれて光栄です。リネー様」
初めて屋敷を訪ねて来たアルベルトは、すぐにリネーの前に跪いて、その手の甲に額を付けた。
金色の透き通るような髪に、淡いサファイアの瞳、スラっとした長身に柔らかな笑顔。リネーの側にいた、悪だくみばかりの狸たちとは似ても似つかず、思わず息を呑んでしまう。背後から光が溢れてまるで天使のようなあどけなさだ。二歳しか違わないというのに、この無邪気さというか、毒気の無さは、何を食べたらそうなるのかと問い正したくなる。
(…………こんな男のどこに醜聞なんて立てられるんだよ)
どこをどう見ても清廉潔白だ。誰がどう見ても、何かあったとして、指摘した人間の勘違いだろうと言われるに違いない。
その見た目の爽やかさが、何もかもを正当化してしまいそうだ。
「リネー、とお呼びください。敬語も不要です」
「では、俺の事もアルとお呼びください。是非、敬語も無しで。俺の方が年下ですから」
想像以上の好青年ぶりに拍子抜けしてしまう。
本当にこの相手が父が警戒するほどの相手なのだろうか。今まで見た貴族の誰よりも毒気が無く、清々しく、それから少し、おっとりしてる。
これからこの男をまずは骨抜きにしなければならない。
ダンスパーティーに出ていた頃は、リネーが少し微笑めば何人もの男が頬を染めていたが、果たしてこの純朴そうな男にその手が通じるだろうか。
「……実は、恥ずかしながら、一目惚れで。リネー……は覚えてないと思いますが、一度俺に声を掛けてくれたことがあるんです」
「え」
「随分と昔の事なので……王家の主催ダンスパーティーで一緒に踊らないかと声を掛けてくれて、それですっかり」
そう言えばそんな事もあったかもしれない。
けれどあのような場では、誘われれば誰の誘いでも断らないし、相手がいなければその辺にいる相手に声を掛けるしで、正直アルベルトと踊った記憶は無い。沢山踊ったその中の一人だったのだろう。王家の主催のダンスパーティーは貴族であり、招待されれば参加は必須となる。
「すまない、覚えてない」
「仕方ないですよ。あの頃は皆あなたと踊りたくてたまらなかった。沢山の人と踊っていたでしょう? 俺もその一人です。最近は社交界には出られていなかったようですが、皆美しいあなたの姿を探していました」
「それは……」
「だからリネー様、俺のところへ来て頂いてありがとうございます」
まずはアルベルトの意識を引いて、リネーに好意を抱いてくれればと思っていたのに、その思惑は出会い頭に良い方向に打ち砕かれてしまった。一目惚れだという言葉通り、リネーへの好意を隠さないアルベルトは、リネーがこの家に来てから、常に気に掛けてくれている。家の使用人たちにも微笑ましい目で見守られて居心地が悪い。
仕事も忙しいだろうに、帰宅すれば一番にリネーの元へと来て、出掛ける時も必ず声を掛けていく。ずっと独りで暮らしていたリネーにとってはそれだけで新鮮な日々だった。恋人や夫が出来たと言うよりは、なんだか大型犬のペットデモで来たかのような気分だ。
夫婦としての初夜は、次にリネーの発情期が来た時にと言われていた。
だからまだ、同じ部屋で眠る事はしていないせいかもしれない。
眠る前のわずかな時間、アルベルトは必ずリネーの部屋を訪ねる。行きましょう、と言って手を取り、植物が多く飾られたテラスに連れて行く。そうして二人きりでとりとめのない話をするのがこの家に来てからの日課になっていた。ラニが紅茶を用意して下がってしまえば、あとはずっと二人きりで、側に執事すら控えていない。
「ご不便はありませんか? すみません、日中はなかなか家にいられなくて」
「……いや、いい。あまり気にするな」
想像以上に良くしてくれている。正直ここまでの好待遇は想像していなかった。
別邸にいたときは使用人でさえ、オメガであるリネーを毛嫌いしていた。ラニだけが唯一の心の安寧だったのだ。
けれど子爵邸では、当然ながら本邸のアルベルトの部屋の隣にリネーの部屋がある。夫婦の寝室は二人の部屋の間だ。
使用人たちは朝から晩までリネーの側に待機しており、「困った」の「こ」が発せられる前に「どうしましたか、リネー様」と気の良い従者が駆けつける。家から連れてきたラニが基本的に身の回りの世話はしてくれているが、この家に来てからはマグヌスという従者が更に側についてくれていた。
実質的にはリネーの執事のようなもので、対外的な仕事のサポートや、家での仕事についてはマグヌスが管理してくれている。どうやら母親が、アルベルトの乳母だったようで、アルベルトのことについてもよく教えてくれた。
『貴方が来て下さって良かった。あの方は貴方と踊ったあの日から夢中でしたから』
そんな風に言われれば、悪い気はしない。
マグヌス以外にも屋敷には使用人が多くいるが、皆、誰もがリネーに好意的だった。
「良かったですね、リネー様」
「……そうだな」
共についてきたラニは嬉しそうにしている。
主人がまともな扱いを受けて喜んでいるなど、可哀想でしかない。
当然の扱いすら受けられていなかった主人によくもまぁついて来てくれたものだと思う。
「アルベルト、もし良ければ父上に少しこの領地の果物を送ってもいいだろうか」
「はい、もちろん。素敵ですね、リネー。貴方の優しさと慈愛を感じます」
「アル、あの…」
「ああ、あの件ですね。マグヌスから聞いてます。いいですよ。領地の教会への貢献は、私たちの責務ですが、リネーの心遣いに感謝します。私が考えるより、より現実的で、温かみのある提案でした。きっと子供たちも喜びます」
「先日の御礼に、ヴォルトラーク卿へこれを贈ろうと思うんだが」
「リネー、こちらへ。良く見せて。ああ、さすがです。センスがあるし、これは良い品だ。以前ヴォルトラーク卿はこのような物が好きだと伺ってました。きっと喜ばれるでしょう」
リネーが一言言葉を発せば、その何倍もの言葉と、称賛と、全肯定の返事が来て戸惑ってしまう。
そうでなくとも、いつだってアルベルトは顔を合わせればリネーを褒める。
容姿も性格も、資質も、考え方も何もかも全肯定だ。
「アルベルト、もう少し……その、……控えたほうがいいのでは? 会う度に褒められても……私たちは出会って間もないのだし、その……お前の言う、その通りの人間とはわからないだろう」
ある日あまりにも褒められることに耐えられなくなって、暗に褒めるのは控えて欲しいと伝えると、アルベルトはリネーの両手をそっと取って、指先に口づけた。
「その時はその時で、例えば貴方が私の思う通りの人間じゃなくても、理想を裏切られたなんて思わないですよ。今、この瞬間、目の前にいる貴方を信頼して、愛して、それで貴方の望むことを叶えたいと思ってる俺の欲望に従ってるだけです。例えば裏切られたとして、それはその時の俺が考えます」
だから心配しなくて大丈夫です。存分に俺に褒められてください、と言われて、苦笑して返すしかなかった。
こんなにも清廉潔白な人間がいるのか。こんなにも優しい人間がいるのかと、日々困惑するばかりだ。
褒められて嬉しくないわけがない。
アルベルトが部屋を訪ねてくるのを楽しみにするほどには、多少心を動かされている。
けれどどれだけアルベルトに優しくされたって、この家がどんなに心地が良くたって、リネーはここで、心地よく過ごすだけでは生きていけない。
「アル、少し頼み事が」
「リネー、ちょっと待って。それなら外で、お茶でも入れて話しましょう」
敬語は不要だと言ったのに、やはり慣れないからとアルベルトは敬語を使う。
そのうち仲が深まれば、そうじゃなくなるはずだと言っていたが、この家に来て一カ月が経つのにまだ敬語は外れなかった。
「それで、頼み事とは?」
「…………商人を呼んで欲しい。服や、装飾を買い足したい」
(そんなもの、欲しいとも思わないけど)
父親が望む『醜聞』がどのようなものかはわからないが、おそらく今後もう二度と貴族界で生きていけないような醜聞を期待されているのだろう。何をするかは具体的には決めていなかったが、父親の望みを叶える為には、ある程度リネーの思う通りにアルベルトが行動するようにならなければならない。
例えば、薬の売人と接触をさせるとか、夫のいる貴族の夫人と二人きりで会わせるとか、それを第三者に目撃させるとか、思いつくことはいくつかあるが、リネーの計画通りにアルベルトを動かすには、まずは二人の信頼関係を作るところから必要だった。
その第一歩だ。小さな我が儘を聞いてもらう。それを繰り返す。
そうして、少しずつ、『我が儘』の規模を大きくしていくのだ。自然に、何を頼んでも不自然じゃないように。
幸いにもリネーのヒートはまだ来ていない。元々、リネーのヒートは来るタイミングが安定しない、不安定なヒートだ。
できればヒートが来る前に、番になる前に終わらせたい。そうでなければ、醜聞が発覚した後のアルベルトについていかなくてはならなくなる。
オメガは一人では生きていけない。アルファの庇護下でしか、生きていけないのだ。
アルベルトと番ってしまえば、例えばアルベルトが国外追放になったとしても、リネーは側を離れられない。アルファから離れたオメガは、そのうち狂って精神異常を来す。定期的にアルファのフェロモンを浴びる事が必要なのだ。
(……急がないと、次のヒートがいつ来るかわからない)
もしかしたら父親としては、アルベルトと番ったリネー自身もいなくなることが望みなのかもしれない。
「すみません。私の気が回らず、商人ですね。すぐに呼びましょう。とっておきの商人がいますから」
「……ありがとう」
大した仕事もしていないリネーに理由もなく強請られても嫌な顔ひとつしない。リネーの望むことならなんでも叶えたいと言った言葉の通りだ。
ほどなくして商人が大量の商品を屋敷へと持ち込んだ。衣服も、宝飾品も、用意された物はどれも一級品だった。宝飾品もこの国では手に入らない高価なものだった。ひとつ、紫にも青色にも見える美しい石を選べば、美しい宝飾品にして届けましょうかと提案された。けれどそれはやんわりと断った。
オーダーメイドの一点物はダメだ。そのままでは売れない。この世に一点しかない物など、売れば足がついてしまうかもしれない。
定期的に父親がリネーの元を訪れるようになっていた。
別邸に住んでいた頃には声を聞くことすらなかったのに。
先日、経過報告の為に屋敷へ戻って父親と面会した際、首から掛けていたネックレスが父親の目に留まった。子爵邸で、アルベルトに買わせた商品がどれも高価で希少価値の高い物だと気付いたらしい。
『ちょうどいい。お前、アルベルトに買わせた宝飾品はこちらへ渡しなさい』
『…………物の数が減れば、バレます』
『ああ、安心しろ。すぐに別物を用意する』
つまり、アルベルトに買わせた宝石をそのままどこかへ売りさばく代わりに、ダミーの安物と入れ替えようと言うのだ。宝石商人が見れば違い目がわかるかもしれないが、素人目には遠目からではわかるものではないだろう。
『ああ、いいな。美しい。高く売れるぞ』
そうして、その日、身に着けていたネックレスは父親の手に渡り、数日後、少しくすんだ色の石が嵌められたネックレスが『忘れ物』として届けられた。
売りさばくなら、足がつかない方が良い。だから一点物はダメだ。そう言ったのは、忘れ物を届けに来た父親だ。
次に商人を呼んだ時には、宝石は宝石のままで飾りたいのだと丁寧に伝えた。不自然になるかと思ったが、その宝石を飾る為のガラスのケースも一緒に欲しいと言えば、喜んで用意してくれた。
それからもリネーは、今までの人生で目にした事もないほどの品物を手に入れた。
全てリネーが欲しいと強請ったものだ。
ダイヤモンド、サファイア、ルビーの装飾品に、真珠、金細工のブローチ、絹やベルベットの服、手編みのレース、羽飾りに刺しゅう入りのガウン、ビーズと金糸を織り込んだ手袋、ミンクのファーなど、贅沢品と呼ばれる何もかもを欲しいと言ったのに、アルベルトは嫌な顔ひとつせずに手配してくれる。
執務用に机がひとつと簡素なベッドが一つあっただけのリネーの私室は、あっという間に大量の高価な物で溢れてしまった。
そのどれもが、リネーの望んだ物ではない。
けれど父親は大層喜んでいた。どれもこの国では手に入らない、上質で高価な物だ。
アルベルトの手配した商人は国外から来ていて、この国では手に入らないような物が多くある。あまりこの国には訪ねて来ない商人だという。それもアルベルトが気を利かせて他国から知り合いの商人を呼びよせてくれたらしい。知り合いだから融通が利くのだと言っていたが、おそらく多少無理をしてくれたのだろう。
確かに求める以上のものを持ってくる商人は、それからも定期的にこの国を訪れてくれるようになった。
それでもまずこの国にくれば最初にアルベルトを訪ねてくるあたり、二人の縁は長いものなのだろう。珍しい物があれば、他者に求められても、まずはアルベルトとリネーに欲しいかどうかを聞いてくれる。いつだったか、どうしてそこまで良くしてくれるのかと尋ねれば「アルベルト様にはちょっとした御縁で、良くして頂いたので、恩返しです」と言っていた。
アルベルトの側にはそう言った人物がよく訪ねてくる。皆、アルベルトに恩があると言う。本人は何もしてないと言っているが、それでもきっと、意識せずにしている行動が人を助けているのだろう。
(ああ、でもそういう男だ。困ってる人間を助けるのに、躊躇しない)
おかげでここのところ随分と、居心地が悪い。
ここのところ、一度に求める金額がかなり大きくなってきたにも関わらず、アルベルトは何も言わない。
それどころか「気に入る物はありますか?他にも見てみますか?」と言って新たな商人を連れてくる始末だ。
寝る前の小さな茶会も変わらずに行われていて、二日に一度はふたりきりで話す。いつだって穏やかなアルベルトが持ってくる話題は日常の些細な話だ。幼馴染が結婚した話、部下が飼っていた猫が逃げ出したのに、結局宿舎にいた話。上司の靴下の左右が違っていた話。
こんな男が、醜聞など晒すはずがない。
リネーの父親こそ、叩けばいくらでも出てくるだろう。
「……それで、カーティス子爵が紹介してくださったんですが、良ければ今度一緒に行きませんか。珍しい宝石もあるようで、貴方が欲しければその場で譲って下さるそうです」
「……………………もう十分貰ってるだろう、商人も屋敷に呼んでもらってる」
「ああ、ただの口実です。欲しい物が無ければないでいいんですよ。これはデートなので」
「デート」
「俺が、貴方と一緒にいたいだけです」
何もかもが想定外だった。
最初は、当然ながらアルベルトがどういう男か知らなかった。
父親が縁談を持ってきたとき、異国にいてこの齢になるまで縁談を結んで来なかった男と聞いて、それだけで自己主張の激しい、頑固な相手だろうかと勝手に予想していた。
貴族であれば、ある程度リネーにも噂話は入って来るものだが、誰からもアルベルトの噂を聞いた事が無かったので大した男ではないのだろうと思っていた。父親が注視している相手ならば、それなりの遣り手なのかもしれないとは考えたが、けれどそれほどの警戒が必要な相手ではないと舐めていたのが本当のところだ。
だから、最初はとにかく尽くして、親切にして、リネーに興味がない男だとしても寄り添って、例えばリネーが一目惚れしたのだとでも言えばそのうち絆されてくれるだろうと考えていた。『惚れた弱み』という言葉があるように、リネーを好きにさえなってくれればどうとでもなると思っていた。
『リネー様』
リネーに会う度、嬉しそうにするアルベルトに戸惑う。
リネーの望むものを何もかも与えようとするアルベルトに困惑してしまう。
思い通りになったはずなのに、アルベルトの信頼が、信用がリネーの心の奥底にあるざらついた罪悪感優しく撫でていく。
あとはどうやってアルベルトを陥れるか、だった。
父親が用意した男爵家に嫁いだ女と密会をさせ、それを誰かに目撃させるというのが一番手っ取り早い。男爵家に嫁いだマリアンヌと言う女は、大層な男好きで、その屋敷に務める執事から下男、果ては夫の親友にまで手を出しているらしい。性的に奔放な彼女であれば、アルベルトのような清廉潔癖な男を落とすのも楽しめるだろう。
(マリアンヌは、アルベルトの好みでは無さそうだが、目の前に魅惑的な身体があれば……)
ふと、アルベルトの好みはどんな相手だろうかと考える。どこかで好きな容姿の話をしていただろうか、誰か好みの相手がいただろうかと思い起こしていると、ふと、出会ったその日に言われた言葉を思い出した。
『リネーと踊りたかったんですよ、ずっと』
アルベルトの愛情表現はストレートだ。
リネーの事を、心から大切にしたいのだと、そういう気持ちが伝わってくる。
「……でも……あれは……」
社交辞令かもしれない。
誰にでも優しい男なので、政略結婚のような形で迎え入れたリネーへの心遣いからかもしれない。
けれど、それだけであんなにも優しいものだろうか。忙しいのに小まめにリネーに言葉をかけて、不自由が無いか考えて、欲しがる物をすべて与えて、あれは本物の愛ではないのだろうか。
――――もしかしたらアルベルトは、本気でリネーを好きなのかもしれない。
(いや、そんなわけがない)
アルベルトは、飛びぬけて親切なだけだ。リネーの父親に目を付けられてしまったのはたまたま、事故にあったようなものだ。
誰がどう見たって、アルベルトは親切で、好青年だ。いくら父親が策略を練ったところで、誰もがアルベルトの事を疑わないだろう。それだけの信頼と実績を、丁寧に積み重ねているようで、この所貴族の噂話はあれほどの将来有望な好青年をどうして今まで放っといたのかと言う話題で持ちきりらしい。それが父親の心証を更に悪くしているようだが、妬み、僻みを恥ずかし気もなく露にするその姿に、リネーは驚いていた。リネーの知る父親は、もう少し理性的な男だったはずだが、年を取って随分と抑制が効かなくなったのだろうか。
きっとそんな父親の立てた計画など失敗するに違いない。そうは思ってもリネーは逆らえない。
策略通りアルベルトが密会が出来るような場所へ誘い出して、マリアンヌと面会させる。そこへ彼女の夫を仕向けるだけでいい。
マリアンヌは美丈夫が相手をしたいと言っていると言えばどこへでも行くだろうし、アルベルトは……リネーの言うことを疑わない。用事があるからそこで待っててほしいとでも言えば、その通りにするだろう。貴族の不貞行為などはよくある事で、それ自体はきっと大きな醜聞にはならないだろう。信用は多少落ちるが、それで家の格が堕ちるようなものでもない。
マリーとアルベルトを会わせる段取りを整理していた時、急に父親がひらめいたとばかりに机を叩いた。マリーとの不貞の疑惑に加えて、アルベルトが敵国と内通していた疑惑を捏造すると言い出したのだ。異国に住んでいたアルベルトであればあり得ないこともない。マリーとの醜聞に続いて、敵国との内通がわかれば、さすがに貴族院も動かざるを得ない。
子爵家であるからこそ、少しでも不穏分子は取り除いた方がいいだろうと早い処分が下されるかもしれない。子爵邸が一つ潰れたことで大きな影響はないからだ。
(そうなれば……アルベルトは本当に終わりだ)
「そうだ……、その前にラニを自由にしてやらないと」
何もかもを始める前にラニを自由にしてやりたい。父親に頼めばきっと家の為に利用されてしまう。
けれど他に宛てがあるわけでもない。結局考えた末に、アルベルトに頼むことにした。ラニになるべく早く結婚相手を見つけてやりたいのだと言えば、アルベルトは喜んで相手を探すと言ってくれた。
これで安心だ。これから何かがあってもラニを傷つけることはない。
「リネー」
アルベルトに呼ばれて顔をあげると、小さな箱が手渡された。
美しいグレージュに白いリボンのかかった箱は、一目見て上等なものが入っているとわかるものだった。
「開けてみてください」
丁寧にリボンを解いていくと、開けた箱に収められていたのは美しい金細工の施された懐中時計だった。時計の文字盤には天然の貝殻が用いられており、角度を変えるたびに違う表情を見せる。繊細な針に美しいケースを見れば、それは全て手作業で作られているのだとわかる。時計の蓋にはよく見れば、花や植物の装飾の中に紛れて、リネーの名前が彫られていた。
「これ……」
「俺からの贈り物です、貴方に似合うと思って」
美しい意匠はリネーの好みのものだった。繊細な細工は、見惚れているだけで時間が経ってしまう。
気が付くと随分と長い時間時計を見ていて、御礼も言えていない事に気が付いた。
「あ、あの……ありがとう」
「どういたしまして」
慌てて顔をあげると、いつもより嬉しそうな顔をしたアルベルトがこちらを見ていた。
眠ろうとして、眠れなくて、枕元の棚を開けて箱を取り出す。
箱を開けると美しい懐中時計が月明りに照らされていた。
(きれいだ……)
よく見ると日中は目立たなかった小さな宝石が月明りを受けてキラキラと輝いている。金細工の飾りが懐中時計を彩る。文字盤のシェルも美しい。いつまでも見ていられる美しさだ。きっと、今までに買って貰った物の中でもかなり高価な物だろう。リネーと名前が彫られている部分をそっと撫でる。これはリネーが、初めてちゃんとリネーの物として受け取った贈り物だった。
『貴方に似合うと思って』
こんなにもきれいな物が、似合うと言われてもよくわからない。本当にそうだろうか。似合うと言われても、これほどきれいなものに似合うような人間ではないと思う。
アルベルトの誉め言葉はいつだって過剰だ。
この懐中時計だっていずれ父親に渡さなければならないのだろう。それをアルベルトが知れば、とてもじゃないがこれがリネーに似合う代物だなんて言わないだろう。
(……でも、名前が入ってるし……売れないって言われるか)
乾いた布でそっと拭いて、箱に戻して、そっとベッドサイドの棚へと戻した。
その日から眠る前に、箱から時計を取り出すのが日課になった。
カチコチ、カチコチ、と整った音を立てるそれが、ちょうど眠るのに心地が良いのだ。
自分に似合うと言われたあの言葉を何度も思い出す。
こんなにきれいな物が似合うと言われるのはどこか心苦しいのに、それでも時計を見るたびにあの声がよみがえった。
「ええ、勿論です。お父様」
「お前の美しさはこの時の為にある」
心の中では『くだらない』、と思いながらもそんな事はおくびにも出さない。
躾けられた通り頭を下げて貴族の礼をして、躾けられた通りの笑顔で笑う。
「私たちの狙いは、このシェーンフェルト家の更なる繁栄だ。たかが一介の子爵家との縁談なんぞ、何にもならん。いいか、お前はお前の与えられた役目を果たせ」
一度もリネーの顔を見ずに、強い口調で必要な事だけを言って父親は部屋から出て行った。
扉が完全に閉じるのを確認してから、どっかりと背後のチェアに身体を投げ出すように座った。
「リネー様……」
「ラニ、紅茶でも入れてくれないか」
「すぐにご用意致します」
ラニは幼い頃よりリネーに仕える世話係だ。褐色の肌に、黒い髪を背まで伸ばした姿勢の良い姿が、湯を沸かしに部屋の外へと出ていく。心配させただろうか。ラニはいつだってリネーを気遣っている。
少し開いた窓の隙間から心地の良い風が流れ込んできて、柔らかくリネーの髪を撫でていく。ダークブラウンの髪が風に揺れる。
リネーの生い立ちは少々複雑だ。
この、誰もが美しいと褒める顔立ちのおかげで、酷い目にだけは合わないでここまで生きて来られた。
(けど、それもここまでかもな)
この国一番の美人だと言われていた母親は、リネーが産まれてすぐに死んでしまった。産後の肥立ちが悪かったらしい。生まれてからすぐの頃はまだ、母の生き写しだと言って父にも愛されていた。その父親の態度がすっかり変わってしまったのは、リネーがオメガだとわかったその瞬間からだ。
それまではきっと、リネーがアルファになると信じて疑わなかったのだろう。医師が告げた検査結果を父親はその場で破り捨てた。
新しく来た継母も、リネーがオメガだとわかるなり露骨に態度を変えるようになった。この国ではオメガが当主になる事はないからだ。それまではリネーが当主になる可能性もあったからこそ、優しくしてくれていたのだろう。リネーが当主にならないのであれば、継母の産んだ子が当主になる。
元よりそれほど親しくしていたわけでもなかったが、家族として信頼できる相手は物心つくころにはいなくなっていた。
そして、先日、継母の産んだ子が十六歳になると同時に、次期当主になる事が正式に決まった。
そうとなれば、直系の子と言えどオメガのリネーはこの家ではお役御免だ。この国でのオメガの地位は低い。卑しい性別だと言われて、大抵が酷い扱いを受ける。運良く優秀なアルファに見初められれば救いの道はあるのかもしれないが、貴族同士の結婚は家同士の結婚だ。親が縁談を取り持ってくれない限りは、縁が出来る事は無い。オメガが歩き回って結婚相手を探す事など言語道断だ。
おとぎ話にあるような運命の相手など見つけられるはずもないのだから、貴族の家のオメガに産まれた子は、せめて家に利のある優秀なアルファになんとか見初めて貰おうと品評会とでも言うべきダンスパーティーへ出席する。リネーも偶発的な発情を避ける為に薬を飲まされて、パーティーへ出席させられていた時期もあった。
パーティーへの参加している間だけは、リネーは自由に振舞えた。
見目の良さも手伝って、いろんなアルファから言い寄られて、その度に気を持たせるような事を言って、相手とも何度かのパーティーで良い関係を築けていた事もあった。けれどどれだけ良い関係を築いたとしても、何度目かのパーティーで、相手に縁談がまとまったという噂を聞くことになる。それはただ自分の不運のせいだと思っていたのだが、当時持ち掛けられた縁談の、どれもが父親に断られてしまっていた事を知ったのは、随分と後の事だ。
ただ、オメガだったというだけで、それほど父親に憎まれる事をしたのだろうか。
オメガとして、家に良縁を齎そうとしていた事すら、無かった事にされるような、それほどであるのならいっそのことパーティーへなんか送り出さなければいいのに。
(家としての体面もあったんだろうな)
オメガが家にいるのにパーティーに出さないとなると、悪い病気を持っているなどと噂話を立てられてしまう。それを嫌がったのだろう。
両家の子息の縁談は断る事は無かったとは思うのだが、それでも父親からすれば、母親とうり二つの美しい顔を持ちながら卑しいオメガとして産まれた息子を許せなかったのかもしれない。
継母の子が優秀に育ち、次期当主となれそうだと判断されてからはパーティーの招待状も届かなくなってしまった。父親の元へは届いていたのかもしれないが、リネーにそれが手渡される事は無かった。
顔を合わせることも、ダンスパーティーへの参加を促されることもなくなり、家族との交流も随分と途絶えてしまっていた。オメガと判断されてすぐに、リネーは屋敷の別邸で暮らすようになっていた。それは表向きは、リネーをアルファから守るための措置だったが、少し考えればそれが、ただ疎まれた末の事なのだとわかる。
だから先ほど突然部屋を訪ねて来た父親とは、久しぶりの邂逅だった。何年も顔を合わせていなかったのだ。
突然の来訪だけでも驚いたのに、更に驚いた事に父親が持ってきたのは、ヴェクテル子爵家とリネーの縁談だった。
あれほどリネーへの縁談を断っていた癖に、とは思えど、口にすることなど許されない。
縁談相手のヴェクテル子爵家のアルベルト・リンデホルムは、年若くして最近爵位を継いだと聞いたばかりだ。齢の頃は二十四歳くらいだったはずだ。貴族にしては遅い縁談だろう。つい最近、爵位を継いだ話を聞いた時に、随分と遅い発表だと思ったのだ。家を継ぐこと自体は大抵十六の歳を迎える頃に発表になる。
それから大抵が成人する前には縁談も結んでしまうものだ。
その事を不思議に思って尋ねれば、アルベルトは長い間他国に留学していたのだという。
リネーは二十六歳で、2つ年上になる。この齢になると縁談などもう来ないのだと思っていた。互いに縁談の遅い者同士、と言う事なのかもしれない。
この家の別邸で、生涯一人で、誰からも忘れ去られて、この生を終えるのだと思っていた。
「リネー様、お持ち致しました」
甘い香りの菓子を添えて、目の前のテーブルに置かれたのはリネーの好む紅茶だった。テキパキとティーセットを並べていくラニは、幼い頃にリネーが奴隷市で拾って来た。それ以来の付き合いだがよく懐いて仕えてくれている。少女だったラニを引き取った時は、ただ自分のように哀れな身分の子どもが一人でもいなくなればいいと思っての事だったが、今ではただ一人、信頼のおける家族だった。
「…………ラニ、お前はついて来なくても」
「いいえ、リネー様。どこまでもお供致します。この家に残るなど、望んでいません」
「ラニ、話は聞いていただろう」
「だからこそ、です」
お側にいさせてください、と床に膝をついて、リネーの手を取り、その手の甲に額を押し付ける最上位の礼をされてしまえばもう断れない。
「茨の道だぞ」
「承知の上です」
あの父親の持ってくる縁談が、ただリネーを思っての縁組であるはずがなかった。
政略結婚。それだけなら、まだ、良かった。
『アルベルト・リンデホルムの弱みを握って醜聞を晒せ』
『…………アルベルト様には、何か、そのような疑惑が?』
『無いから作れと言っている。相変わらず物分かりの悪いやつだな』
シェーンフェルトは伯爵家だ。その伯爵家からオメガとは言え、直系男子との縁談を結ぶのであれば、アルベルトの家からすれば随分な格上との結婚という事になる。ヴェクテル子爵家からすれば望んだ以上の縁談だろう。
それが、なぜ、格上であるはずのこちらからそんな工作が必要なのか。
『ヴェクテル子爵はどうやら隣国の王家との繋がりがあるらしい。定かではないがな。ここの所、他の伯爵家からの覚えもめでたい。諸外国を渡り歩いたお陰で、各国の権力者とも縁がある。潰しておくに越したことはない』
『………………承知しました』
つまりは、リネーに醜聞を偽装させて、アルベルトを告発し、家もろとも取り潰したいのだろう。
上手くやれば、告発をしたシェーンフェルトの家は家名を上げる事になり、有力な貴族をねじ伏せる事になる。一方で、きっと醜聞を偽装したリネーはアルベルトと共に消されるに違いない。真実を知る者は少なければ少ないほどいいからだ。
リネーの側にいれば、ラニもきっと関わる事になる。
(…………ラニは、どこかで逃がしてやろう)
どこかの家に嫁がせてもいい。早い内に手放してしまわなければ。
せめて一人くらいは、自分に関わった人間を幸せにしたいと願ったって罰は当たらないはずだ。
父親の命令が、自分に害を為すものだったとして断れるわけもない。
結局自分はあの父親の子で、シェーンフェルトの家のオメガだ。政略結婚で嫁ぐのだから、自分の役割を果たすことくらいしかリネーに出来ることはない。
いくら父親に言われた事が不条理だったとしても、リネーに逆らう事は許されない。
「ごきげんよう、ヴェクテル子爵」
「お目にかかれて光栄です。リネー様」
初めて屋敷を訪ねて来たアルベルトは、すぐにリネーの前に跪いて、その手の甲に額を付けた。
金色の透き通るような髪に、淡いサファイアの瞳、スラっとした長身に柔らかな笑顔。リネーの側にいた、悪だくみばかりの狸たちとは似ても似つかず、思わず息を呑んでしまう。背後から光が溢れてまるで天使のようなあどけなさだ。二歳しか違わないというのに、この無邪気さというか、毒気の無さは、何を食べたらそうなるのかと問い正したくなる。
(…………こんな男のどこに醜聞なんて立てられるんだよ)
どこをどう見ても清廉潔白だ。誰がどう見ても、何かあったとして、指摘した人間の勘違いだろうと言われるに違いない。
その見た目の爽やかさが、何もかもを正当化してしまいそうだ。
「リネー、とお呼びください。敬語も不要です」
「では、俺の事もアルとお呼びください。是非、敬語も無しで。俺の方が年下ですから」
想像以上の好青年ぶりに拍子抜けしてしまう。
本当にこの相手が父が警戒するほどの相手なのだろうか。今まで見た貴族の誰よりも毒気が無く、清々しく、それから少し、おっとりしてる。
これからこの男をまずは骨抜きにしなければならない。
ダンスパーティーに出ていた頃は、リネーが少し微笑めば何人もの男が頬を染めていたが、果たしてこの純朴そうな男にその手が通じるだろうか。
「……実は、恥ずかしながら、一目惚れで。リネー……は覚えてないと思いますが、一度俺に声を掛けてくれたことがあるんです」
「え」
「随分と昔の事なので……王家の主催ダンスパーティーで一緒に踊らないかと声を掛けてくれて、それですっかり」
そう言えばそんな事もあったかもしれない。
けれどあのような場では、誘われれば誰の誘いでも断らないし、相手がいなければその辺にいる相手に声を掛けるしで、正直アルベルトと踊った記憶は無い。沢山踊ったその中の一人だったのだろう。王家の主催のダンスパーティーは貴族であり、招待されれば参加は必須となる。
「すまない、覚えてない」
「仕方ないですよ。あの頃は皆あなたと踊りたくてたまらなかった。沢山の人と踊っていたでしょう? 俺もその一人です。最近は社交界には出られていなかったようですが、皆美しいあなたの姿を探していました」
「それは……」
「だからリネー様、俺のところへ来て頂いてありがとうございます」
まずはアルベルトの意識を引いて、リネーに好意を抱いてくれればと思っていたのに、その思惑は出会い頭に良い方向に打ち砕かれてしまった。一目惚れだという言葉通り、リネーへの好意を隠さないアルベルトは、リネーがこの家に来てから、常に気に掛けてくれている。家の使用人たちにも微笑ましい目で見守られて居心地が悪い。
仕事も忙しいだろうに、帰宅すれば一番にリネーの元へと来て、出掛ける時も必ず声を掛けていく。ずっと独りで暮らしていたリネーにとってはそれだけで新鮮な日々だった。恋人や夫が出来たと言うよりは、なんだか大型犬のペットデモで来たかのような気分だ。
夫婦としての初夜は、次にリネーの発情期が来た時にと言われていた。
だからまだ、同じ部屋で眠る事はしていないせいかもしれない。
眠る前のわずかな時間、アルベルトは必ずリネーの部屋を訪ねる。行きましょう、と言って手を取り、植物が多く飾られたテラスに連れて行く。そうして二人きりでとりとめのない話をするのがこの家に来てからの日課になっていた。ラニが紅茶を用意して下がってしまえば、あとはずっと二人きりで、側に執事すら控えていない。
「ご不便はありませんか? すみません、日中はなかなか家にいられなくて」
「……いや、いい。あまり気にするな」
想像以上に良くしてくれている。正直ここまでの好待遇は想像していなかった。
別邸にいたときは使用人でさえ、オメガであるリネーを毛嫌いしていた。ラニだけが唯一の心の安寧だったのだ。
けれど子爵邸では、当然ながら本邸のアルベルトの部屋の隣にリネーの部屋がある。夫婦の寝室は二人の部屋の間だ。
使用人たちは朝から晩までリネーの側に待機しており、「困った」の「こ」が発せられる前に「どうしましたか、リネー様」と気の良い従者が駆けつける。家から連れてきたラニが基本的に身の回りの世話はしてくれているが、この家に来てからはマグヌスという従者が更に側についてくれていた。
実質的にはリネーの執事のようなもので、対外的な仕事のサポートや、家での仕事についてはマグヌスが管理してくれている。どうやら母親が、アルベルトの乳母だったようで、アルベルトのことについてもよく教えてくれた。
『貴方が来て下さって良かった。あの方は貴方と踊ったあの日から夢中でしたから』
そんな風に言われれば、悪い気はしない。
マグヌス以外にも屋敷には使用人が多くいるが、皆、誰もがリネーに好意的だった。
「良かったですね、リネー様」
「……そうだな」
共についてきたラニは嬉しそうにしている。
主人がまともな扱いを受けて喜んでいるなど、可哀想でしかない。
当然の扱いすら受けられていなかった主人によくもまぁついて来てくれたものだと思う。
「アルベルト、もし良ければ父上に少しこの領地の果物を送ってもいいだろうか」
「はい、もちろん。素敵ですね、リネー。貴方の優しさと慈愛を感じます」
「アル、あの…」
「ああ、あの件ですね。マグヌスから聞いてます。いいですよ。領地の教会への貢献は、私たちの責務ですが、リネーの心遣いに感謝します。私が考えるより、より現実的で、温かみのある提案でした。きっと子供たちも喜びます」
「先日の御礼に、ヴォルトラーク卿へこれを贈ろうと思うんだが」
「リネー、こちらへ。良く見せて。ああ、さすがです。センスがあるし、これは良い品だ。以前ヴォルトラーク卿はこのような物が好きだと伺ってました。きっと喜ばれるでしょう」
リネーが一言言葉を発せば、その何倍もの言葉と、称賛と、全肯定の返事が来て戸惑ってしまう。
そうでなくとも、いつだってアルベルトは顔を合わせればリネーを褒める。
容姿も性格も、資質も、考え方も何もかも全肯定だ。
「アルベルト、もう少し……その、……控えたほうがいいのでは? 会う度に褒められても……私たちは出会って間もないのだし、その……お前の言う、その通りの人間とはわからないだろう」
ある日あまりにも褒められることに耐えられなくなって、暗に褒めるのは控えて欲しいと伝えると、アルベルトはリネーの両手をそっと取って、指先に口づけた。
「その時はその時で、例えば貴方が私の思う通りの人間じゃなくても、理想を裏切られたなんて思わないですよ。今、この瞬間、目の前にいる貴方を信頼して、愛して、それで貴方の望むことを叶えたいと思ってる俺の欲望に従ってるだけです。例えば裏切られたとして、それはその時の俺が考えます」
だから心配しなくて大丈夫です。存分に俺に褒められてください、と言われて、苦笑して返すしかなかった。
こんなにも清廉潔白な人間がいるのか。こんなにも優しい人間がいるのかと、日々困惑するばかりだ。
褒められて嬉しくないわけがない。
アルベルトが部屋を訪ねてくるのを楽しみにするほどには、多少心を動かされている。
けれどどれだけアルベルトに優しくされたって、この家がどんなに心地が良くたって、リネーはここで、心地よく過ごすだけでは生きていけない。
「アル、少し頼み事が」
「リネー、ちょっと待って。それなら外で、お茶でも入れて話しましょう」
敬語は不要だと言ったのに、やはり慣れないからとアルベルトは敬語を使う。
そのうち仲が深まれば、そうじゃなくなるはずだと言っていたが、この家に来て一カ月が経つのにまだ敬語は外れなかった。
「それで、頼み事とは?」
「…………商人を呼んで欲しい。服や、装飾を買い足したい」
(そんなもの、欲しいとも思わないけど)
父親が望む『醜聞』がどのようなものかはわからないが、おそらく今後もう二度と貴族界で生きていけないような醜聞を期待されているのだろう。何をするかは具体的には決めていなかったが、父親の望みを叶える為には、ある程度リネーの思う通りにアルベルトが行動するようにならなければならない。
例えば、薬の売人と接触をさせるとか、夫のいる貴族の夫人と二人きりで会わせるとか、それを第三者に目撃させるとか、思いつくことはいくつかあるが、リネーの計画通りにアルベルトを動かすには、まずは二人の信頼関係を作るところから必要だった。
その第一歩だ。小さな我が儘を聞いてもらう。それを繰り返す。
そうして、少しずつ、『我が儘』の規模を大きくしていくのだ。自然に、何を頼んでも不自然じゃないように。
幸いにもリネーのヒートはまだ来ていない。元々、リネーのヒートは来るタイミングが安定しない、不安定なヒートだ。
できればヒートが来る前に、番になる前に終わらせたい。そうでなければ、醜聞が発覚した後のアルベルトについていかなくてはならなくなる。
オメガは一人では生きていけない。アルファの庇護下でしか、生きていけないのだ。
アルベルトと番ってしまえば、例えばアルベルトが国外追放になったとしても、リネーは側を離れられない。アルファから離れたオメガは、そのうち狂って精神異常を来す。定期的にアルファのフェロモンを浴びる事が必要なのだ。
(……急がないと、次のヒートがいつ来るかわからない)
もしかしたら父親としては、アルベルトと番ったリネー自身もいなくなることが望みなのかもしれない。
「すみません。私の気が回らず、商人ですね。すぐに呼びましょう。とっておきの商人がいますから」
「……ありがとう」
大した仕事もしていないリネーに理由もなく強請られても嫌な顔ひとつしない。リネーの望むことならなんでも叶えたいと言った言葉の通りだ。
ほどなくして商人が大量の商品を屋敷へと持ち込んだ。衣服も、宝飾品も、用意された物はどれも一級品だった。宝飾品もこの国では手に入らない高価なものだった。ひとつ、紫にも青色にも見える美しい石を選べば、美しい宝飾品にして届けましょうかと提案された。けれどそれはやんわりと断った。
オーダーメイドの一点物はダメだ。そのままでは売れない。この世に一点しかない物など、売れば足がついてしまうかもしれない。
定期的に父親がリネーの元を訪れるようになっていた。
別邸に住んでいた頃には声を聞くことすらなかったのに。
先日、経過報告の為に屋敷へ戻って父親と面会した際、首から掛けていたネックレスが父親の目に留まった。子爵邸で、アルベルトに買わせた商品がどれも高価で希少価値の高い物だと気付いたらしい。
『ちょうどいい。お前、アルベルトに買わせた宝飾品はこちらへ渡しなさい』
『…………物の数が減れば、バレます』
『ああ、安心しろ。すぐに別物を用意する』
つまり、アルベルトに買わせた宝石をそのままどこかへ売りさばく代わりに、ダミーの安物と入れ替えようと言うのだ。宝石商人が見れば違い目がわかるかもしれないが、素人目には遠目からではわかるものではないだろう。
『ああ、いいな。美しい。高く売れるぞ』
そうして、その日、身に着けていたネックレスは父親の手に渡り、数日後、少しくすんだ色の石が嵌められたネックレスが『忘れ物』として届けられた。
売りさばくなら、足がつかない方が良い。だから一点物はダメだ。そう言ったのは、忘れ物を届けに来た父親だ。
次に商人を呼んだ時には、宝石は宝石のままで飾りたいのだと丁寧に伝えた。不自然になるかと思ったが、その宝石を飾る為のガラスのケースも一緒に欲しいと言えば、喜んで用意してくれた。
それからもリネーは、今までの人生で目にした事もないほどの品物を手に入れた。
全てリネーが欲しいと強請ったものだ。
ダイヤモンド、サファイア、ルビーの装飾品に、真珠、金細工のブローチ、絹やベルベットの服、手編みのレース、羽飾りに刺しゅう入りのガウン、ビーズと金糸を織り込んだ手袋、ミンクのファーなど、贅沢品と呼ばれる何もかもを欲しいと言ったのに、アルベルトは嫌な顔ひとつせずに手配してくれる。
執務用に机がひとつと簡素なベッドが一つあっただけのリネーの私室は、あっという間に大量の高価な物で溢れてしまった。
そのどれもが、リネーの望んだ物ではない。
けれど父親は大層喜んでいた。どれもこの国では手に入らない、上質で高価な物だ。
アルベルトの手配した商人は国外から来ていて、この国では手に入らないような物が多くある。あまりこの国には訪ねて来ない商人だという。それもアルベルトが気を利かせて他国から知り合いの商人を呼びよせてくれたらしい。知り合いだから融通が利くのだと言っていたが、おそらく多少無理をしてくれたのだろう。
確かに求める以上のものを持ってくる商人は、それからも定期的にこの国を訪れてくれるようになった。
それでもまずこの国にくれば最初にアルベルトを訪ねてくるあたり、二人の縁は長いものなのだろう。珍しい物があれば、他者に求められても、まずはアルベルトとリネーに欲しいかどうかを聞いてくれる。いつだったか、どうしてそこまで良くしてくれるのかと尋ねれば「アルベルト様にはちょっとした御縁で、良くして頂いたので、恩返しです」と言っていた。
アルベルトの側にはそう言った人物がよく訪ねてくる。皆、アルベルトに恩があると言う。本人は何もしてないと言っているが、それでもきっと、意識せずにしている行動が人を助けているのだろう。
(ああ、でもそういう男だ。困ってる人間を助けるのに、躊躇しない)
おかげでここのところ随分と、居心地が悪い。
ここのところ、一度に求める金額がかなり大きくなってきたにも関わらず、アルベルトは何も言わない。
それどころか「気に入る物はありますか?他にも見てみますか?」と言って新たな商人を連れてくる始末だ。
寝る前の小さな茶会も変わらずに行われていて、二日に一度はふたりきりで話す。いつだって穏やかなアルベルトが持ってくる話題は日常の些細な話だ。幼馴染が結婚した話、部下が飼っていた猫が逃げ出したのに、結局宿舎にいた話。上司の靴下の左右が違っていた話。
こんな男が、醜聞など晒すはずがない。
リネーの父親こそ、叩けばいくらでも出てくるだろう。
「……それで、カーティス子爵が紹介してくださったんですが、良ければ今度一緒に行きませんか。珍しい宝石もあるようで、貴方が欲しければその場で譲って下さるそうです」
「……………………もう十分貰ってるだろう、商人も屋敷に呼んでもらってる」
「ああ、ただの口実です。欲しい物が無ければないでいいんですよ。これはデートなので」
「デート」
「俺が、貴方と一緒にいたいだけです」
何もかもが想定外だった。
最初は、当然ながらアルベルトがどういう男か知らなかった。
父親が縁談を持ってきたとき、異国にいてこの齢になるまで縁談を結んで来なかった男と聞いて、それだけで自己主張の激しい、頑固な相手だろうかと勝手に予想していた。
貴族であれば、ある程度リネーにも噂話は入って来るものだが、誰からもアルベルトの噂を聞いた事が無かったので大した男ではないのだろうと思っていた。父親が注視している相手ならば、それなりの遣り手なのかもしれないとは考えたが、けれどそれほどの警戒が必要な相手ではないと舐めていたのが本当のところだ。
だから、最初はとにかく尽くして、親切にして、リネーに興味がない男だとしても寄り添って、例えばリネーが一目惚れしたのだとでも言えばそのうち絆されてくれるだろうと考えていた。『惚れた弱み』という言葉があるように、リネーを好きにさえなってくれればどうとでもなると思っていた。
『リネー様』
リネーに会う度、嬉しそうにするアルベルトに戸惑う。
リネーの望むものを何もかも与えようとするアルベルトに困惑してしまう。
思い通りになったはずなのに、アルベルトの信頼が、信用がリネーの心の奥底にあるざらついた罪悪感優しく撫でていく。
あとはどうやってアルベルトを陥れるか、だった。
父親が用意した男爵家に嫁いだ女と密会をさせ、それを誰かに目撃させるというのが一番手っ取り早い。男爵家に嫁いだマリアンヌと言う女は、大層な男好きで、その屋敷に務める執事から下男、果ては夫の親友にまで手を出しているらしい。性的に奔放な彼女であれば、アルベルトのような清廉潔癖な男を落とすのも楽しめるだろう。
(マリアンヌは、アルベルトの好みでは無さそうだが、目の前に魅惑的な身体があれば……)
ふと、アルベルトの好みはどんな相手だろうかと考える。どこかで好きな容姿の話をしていただろうか、誰か好みの相手がいただろうかと思い起こしていると、ふと、出会ったその日に言われた言葉を思い出した。
『リネーと踊りたかったんですよ、ずっと』
アルベルトの愛情表現はストレートだ。
リネーの事を、心から大切にしたいのだと、そういう気持ちが伝わってくる。
「……でも……あれは……」
社交辞令かもしれない。
誰にでも優しい男なので、政略結婚のような形で迎え入れたリネーへの心遣いからかもしれない。
けれど、それだけであんなにも優しいものだろうか。忙しいのに小まめにリネーに言葉をかけて、不自由が無いか考えて、欲しがる物をすべて与えて、あれは本物の愛ではないのだろうか。
――――もしかしたらアルベルトは、本気でリネーを好きなのかもしれない。
(いや、そんなわけがない)
アルベルトは、飛びぬけて親切なだけだ。リネーの父親に目を付けられてしまったのはたまたま、事故にあったようなものだ。
誰がどう見たって、アルベルトは親切で、好青年だ。いくら父親が策略を練ったところで、誰もがアルベルトの事を疑わないだろう。それだけの信頼と実績を、丁寧に積み重ねているようで、この所貴族の噂話はあれほどの将来有望な好青年をどうして今まで放っといたのかと言う話題で持ちきりらしい。それが父親の心証を更に悪くしているようだが、妬み、僻みを恥ずかし気もなく露にするその姿に、リネーは驚いていた。リネーの知る父親は、もう少し理性的な男だったはずだが、年を取って随分と抑制が効かなくなったのだろうか。
きっとそんな父親の立てた計画など失敗するに違いない。そうは思ってもリネーは逆らえない。
策略通りアルベルトが密会が出来るような場所へ誘い出して、マリアンヌと面会させる。そこへ彼女の夫を仕向けるだけでいい。
マリアンヌは美丈夫が相手をしたいと言っていると言えばどこへでも行くだろうし、アルベルトは……リネーの言うことを疑わない。用事があるからそこで待っててほしいとでも言えば、その通りにするだろう。貴族の不貞行為などはよくある事で、それ自体はきっと大きな醜聞にはならないだろう。信用は多少落ちるが、それで家の格が堕ちるようなものでもない。
マリーとアルベルトを会わせる段取りを整理していた時、急に父親がひらめいたとばかりに机を叩いた。マリーとの不貞の疑惑に加えて、アルベルトが敵国と内通していた疑惑を捏造すると言い出したのだ。異国に住んでいたアルベルトであればあり得ないこともない。マリーとの醜聞に続いて、敵国との内通がわかれば、さすがに貴族院も動かざるを得ない。
子爵家であるからこそ、少しでも不穏分子は取り除いた方がいいだろうと早い処分が下されるかもしれない。子爵邸が一つ潰れたことで大きな影響はないからだ。
(そうなれば……アルベルトは本当に終わりだ)
「そうだ……、その前にラニを自由にしてやらないと」
何もかもを始める前にラニを自由にしてやりたい。父親に頼めばきっと家の為に利用されてしまう。
けれど他に宛てがあるわけでもない。結局考えた末に、アルベルトに頼むことにした。ラニになるべく早く結婚相手を見つけてやりたいのだと言えば、アルベルトは喜んで相手を探すと言ってくれた。
これで安心だ。これから何かがあってもラニを傷つけることはない。
「リネー」
アルベルトに呼ばれて顔をあげると、小さな箱が手渡された。
美しいグレージュに白いリボンのかかった箱は、一目見て上等なものが入っているとわかるものだった。
「開けてみてください」
丁寧にリボンを解いていくと、開けた箱に収められていたのは美しい金細工の施された懐中時計だった。時計の文字盤には天然の貝殻が用いられており、角度を変えるたびに違う表情を見せる。繊細な針に美しいケースを見れば、それは全て手作業で作られているのだとわかる。時計の蓋にはよく見れば、花や植物の装飾の中に紛れて、リネーの名前が彫られていた。
「これ……」
「俺からの贈り物です、貴方に似合うと思って」
美しい意匠はリネーの好みのものだった。繊細な細工は、見惚れているだけで時間が経ってしまう。
気が付くと随分と長い時間時計を見ていて、御礼も言えていない事に気が付いた。
「あ、あの……ありがとう」
「どういたしまして」
慌てて顔をあげると、いつもより嬉しそうな顔をしたアルベルトがこちらを見ていた。
眠ろうとして、眠れなくて、枕元の棚を開けて箱を取り出す。
箱を開けると美しい懐中時計が月明りに照らされていた。
(きれいだ……)
よく見ると日中は目立たなかった小さな宝石が月明りを受けてキラキラと輝いている。金細工の飾りが懐中時計を彩る。文字盤のシェルも美しい。いつまでも見ていられる美しさだ。きっと、今までに買って貰った物の中でもかなり高価な物だろう。リネーと名前が彫られている部分をそっと撫でる。これはリネーが、初めてちゃんとリネーの物として受け取った贈り物だった。
『貴方に似合うと思って』
こんなにもきれいな物が、似合うと言われてもよくわからない。本当にそうだろうか。似合うと言われても、これほどきれいなものに似合うような人間ではないと思う。
アルベルトの誉め言葉はいつだって過剰だ。
この懐中時計だっていずれ父親に渡さなければならないのだろう。それをアルベルトが知れば、とてもじゃないがこれがリネーに似合う代物だなんて言わないだろう。
(……でも、名前が入ってるし……売れないって言われるか)
乾いた布でそっと拭いて、箱に戻して、そっとベッドサイドの棚へと戻した。
その日から眠る前に、箱から時計を取り出すのが日課になった。
カチコチ、カチコチ、と整った音を立てるそれが、ちょうど眠るのに心地が良いのだ。
自分に似合うと言われたあの言葉を何度も思い出す。
こんなにきれいな物が似合うと言われるのはどこか心苦しいのに、それでも時計を見るたびにあの声がよみがえった。
101
あなたにおすすめの小説

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

【完結】愛されたかった僕の人生
Kanade
BL
✯オメガバース
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。
今日も《夫》は帰らない。
《夫》には僕以外の『番』がいる。
ねぇ、どうしてなの?
一目惚れだって言ったじゃない。
愛してるって言ってくれたじゃないか。
ねぇ、僕はもう要らないの…?
独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。

捨てた筈の恋が追ってきて逃がしてくれない
Q矢(Q.➽)
BL
18歳の愛緒(まなお)は、ある男に出会った瞬間から身も心も奪われるような恋をした。
だがそれはリスクしかない刹那的なもの。
恋の最中に目が覚めてそれに気づいた時、愛緒は最愛の人の前から姿を消した。
それから、7年。
捨てたつもりで、とうに忘れたと思っていたその恋が、再び目の前に現れる。
※不倫表現が苦手な方はご注意ください。

悪役令息(Ω)に転生したので、破滅を避けてスローライフを目指します。だけどなぜか最強騎士団長(α)の運命の番に認定され、溺愛ルートに突入!
水凪しおん
BL
貧乏男爵家の三男リヒトには秘密があった。
それは、自分が乙女ゲームの「悪役令息」であり、現代日本から転生してきたという記憶だ。
家は没落寸前、自身の立場は断罪エンドへまっしぐら。
そんな破滅フラグを回避するため、前世の知識を活かして領地改革に奮闘するリヒトだったが、彼が生まれ持った「Ω」という性は、否応なく運命の渦へと彼を巻き込んでいく。
ある夜会で出会ったのは、氷のように冷徹で、王国最強と謳われる騎士団長のカイ。
誰もが恐れるαの彼に、なぜかリヒトは興味を持たれてしまう。
「関わってはいけない」――そう思えば思うほど、抗いがたいフェロモンと、カイの不器用な優しさがリヒトの心を揺さぶる。
これは、運命に翻弄される悪役令息が、最強騎士団長の激重な愛に包まれ、やがて国をも動かす存在へと成り上がっていく、甘くて刺激的な溺愛ラブストーリー。

オメガに説く幸福論
葉咲透織
BL
長寿ゆえに子孫問題を後回しにしていたエルフの国へ、オメガの国の第二王子・リッカは弟王子他数名を連れて行く。褐色のエルフである王弟・エドアールに惹かれつつも、彼との結婚を訳あってリッカは望めず……。
ダークエルフの王族×訳アリ平凡オメガ王子の嫁入りBL。
※ブログにもアップしています

孤独の王と後宮の青葉
秋月真鳥
BL
塔に閉じ込められた居場所のない妾腹の王子は、15歳になってもバース性が判明していなかった。美少女のような彼を、父親はオメガと決め付けて遠い異国の後宮に入れる。
異国の王は孤独だった。誰もが彼をアルファと信じているのに、本当はオメガでそのことを明かすことができない。
筋骨隆々としたアルファらしい孤独なオメガの王と、美少女のようなオメガらしいアルファの王子は、互いの孤独を埋め合い、愛し合う。
※ムーンライトノベルズ様にも投稿しています。
※完結まで予約投稿しています。
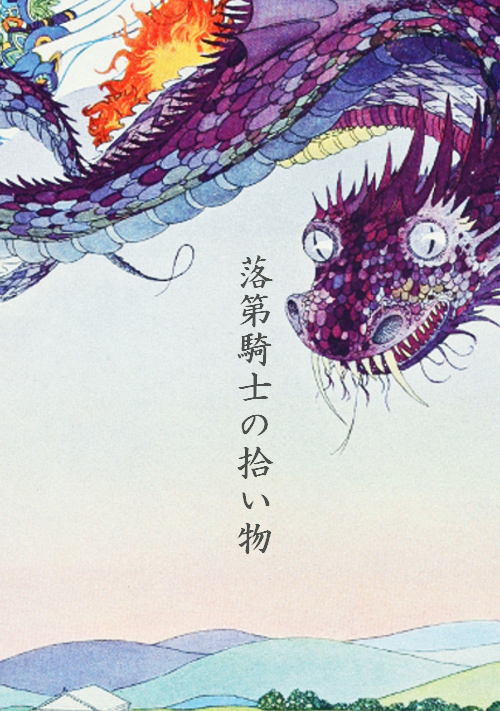
落第騎士の拾い物
深山恐竜
BL
「オメガでございます」
ひと月前、セレガは医者から第三の性別を告知された。将来は勇猛な騎士になることを夢見ていたセレガは、この診断に絶望した。
セレガは絶望の末に”ドラゴンの巣”へ向かう。そこで彼は騎士見習いとして最期の戦いをするつもりであった。しかし、巣にはドラゴンに育てられたという男がいた。男は純粋で、無垢で、彼と交流するうちに、セレガは未来への希望を取り戻す。
ところがある日、発情したセレガは男と関係を持ってしまって……?
オメガバースの設定をお借りしています。
ムーンライトノベルズにも掲載中

婚約解消されたネコミミ悪役令息はなぜか王子に溺愛される
日色
BL
大好きな王子に婚約解消されてしまった悪役令息ルジア=アンセルは、ネコミミの呪いをかけられると同時に前世の記憶を思い出した。最後の情けにと両親に与えられた猫カフェで、これからは猫とまったり生きていくことに決めた……はずなのに! なぜか婚約解消したはずの王子レオンが押しかけてきて!?
『悪役令息溺愛アンソロジー』に寄稿したお話です。全11話になる予定です。
*ムーンライトノベルズにも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















