2 / 6
2
しおりを挟む
ユリウス殿下──いえ、ユリウスの私室は、第一王子にふさわしく広く、それでいて無駄がなく、整然としていた。
大理石の床には手織りのカーペット、壁には歴代の王族の肖像画。窓辺からは王都の街並みが見渡せる。
だが、そんな景観も、彼の近くでは霞んで見える。
「……本当に、よく無事で帰ってきてくれたな。アリア」
椅子に腰かけた私の向かいで、ユリウスがワインを注ぎながら言った。
「一度は覚悟したよ。君が帰ってこない可能性も……」
「でも私は帰りました。あなたの“期待”に応えるために」
その言葉に、ユリウスは一瞬だけ動きを止めた。琥珀色のワインがグラスに静かに注がれ続ける。
「君は、いつも自分に厳しい」
ワインを手渡され、私は受け取る。
「でも、僕はね、アリア。君に“完璧”を求めたことなんて一度もない。君が生きていてくれる、それだけで十分だった」
「……嘘、です」
「嘘じゃない」
ユリウスは少し微笑んだ。
「君がこの国を救ったことを誰よりも誇りに思ってる。けれど、それ以上に……君が、僕の隣に戻ってきてくれたことが嬉しい」
その目は、ただの上司や同僚が向けるような視線ではなかった。
……ああ、だめだ。こんなに優しくされたら。
「ユリウス……」
「アリア」
そっと、ユリウスが私の手を取った。
その温もりに、私は一瞬だけ目を閉じる。戦場で何度も失いかけた心が、ようやく安堵に包まれる。
「お願いがあるんだ」
「……なんでしょう」
「君に、正式に近衛団長を任せたい。国王にかけあうつもりだ」
思わず、私は息を呑んだ。
「わたしが……団長?」
「ああ。戦場での采配、士気を維持し続けた統率力、そして剣の腕前。どれをとっても、今の騎士団では君以上の人材はいない」
私は、膝の上で拳をぎゅっと握る。
「でも……私は平民です。貴族社会に迎えられる保証など……」
「僕が保証する。君の出自ではなく、実力を見て判断する」
「それが通るほど、甘くはありませんよ。ユリウス、“殿下”」
わざと皮肉を込めてそう呼ぶと、ユリウスは困ったように笑った。
「君はいつも、自分を過小評価しすぎる」
「過小評価しているのではなく、現実を見ているだけです。レオナルド殿下のように」
その名前を出した瞬間、ユリウスの目が少しだけ細められた。
「……奴にまた何か言われたのか?」
「いえ。ただ、態度があまりにも……変わりすぎていて、呆れたというだけです」
「そうか」
ユリウスはグラスの中のワインを一口含み、言葉を選ぶようにしてから言った。
「アリア。……あいつにだけは、気を許さないでくれ。あいつは今、焦っている。君の存在が、あいつの立場を脅かしていると気づいたから」
「……王族としての立場を?」
「いや、男としても、かもしれないな」
冗談めいた調子だったけれど、彼の表情は真剣だった。
「奴は、君の価値を見誤った。手放したことを、今になって悔いているだろう」
「後悔しても、もう遅いです」
私はきっぱりとそう言い放ち、グラスを置く。
その時、扉の向こうで、控えの侍女の声がした。
「ユリウス殿下、第二王子レオナルド様がお見えです」
……来た。やっぱり来た。
ユリウスと目を合わせる。彼は微かに眉をひそめると、椅子から立ち上がった。
「通す必要はない。今は、私的な時間だ」
だが、扉が勢いよく開いた。
「兄上、少しだけ時間をいただけないか?」
堂々と入ってきたレオナルドの目が、まず私を捉え、次にユリウスを見た。
「……お邪魔だったかもしれないが、伝えたいことがあるんだ」
私は席を立ち、冷静に言葉を選ぶ。
「わたくしに、でしょうか」
「……ああ。君に」
レオナルドは一歩、私のほうに近づく。けれど、ユリウスがすっと私の前に出た。
「ここは、私の私室だ。来客の許可を出すのは、私だぞ、レオナルド」
その言葉にレオナルドは眉をひそめたが、言い返さなかった。
「……アリア。あの時のことを謝りたかった。君を、平民だからと侮ったこと……それは、間違いだった」
「ええ、間違いでしたね。でもそれを今になって言われても、何も変わりません」
「君は……昔のままじゃない」
「当たり前です。英雄と呼ばれてしまったので。平民のままの私では、国は救えませんでした」
皮肉混じりの言葉に、レオナルドはたじろぐ。
「……いや、本当に、俺は君を――」
「やめてください。昔の“恋人”に未練がましい言葉を投げかけるのは、貴族らしくありませんよ、レオナルド“殿下”」
私は、あえて冷たく、上から見下すように言った。
かつて私が見上げていた彼を、今は見下ろすことができる。地位ではなく、誇りによって。
レオナルドは何も言えなくなり、しばらく沈黙したのち、舌打ちをして部屋を出ていった。
扉が閉まる音が響いたあと、ユリウスがこちらを振り返った。
「……強くなったな、アリア」
「そう見えますか?」
「見えるよ。けど……無理は、してないか?」
その声は、今まででいちばん優しかった。
私は、少しだけ目を伏せた。
「……まだ、少しだけ怖いです。全部、夢なんじゃないかって。でも……あなたがいるから、なんとか、現実だと思える」
ユリウスの瞳が、ふわりと柔らかくなる。
次の瞬間、彼がそっと私の髪を撫でた。
「大丈夫。これは夢じゃない。……俺が、君の居場所になるから」
心が、ふっと軽くなる。
けれど、その夜。
王宮の奥深くで、一枚の密書が交わされていた。
『“英雄”アリアの存在は、国家の秩序を乱す――排除すべし』
その署名には、見覚えのある貴族の名が並んでいた。
アリアを巡る陰謀が、静かに幕を開けようとしていた。
大理石の床には手織りのカーペット、壁には歴代の王族の肖像画。窓辺からは王都の街並みが見渡せる。
だが、そんな景観も、彼の近くでは霞んで見える。
「……本当に、よく無事で帰ってきてくれたな。アリア」
椅子に腰かけた私の向かいで、ユリウスがワインを注ぎながら言った。
「一度は覚悟したよ。君が帰ってこない可能性も……」
「でも私は帰りました。あなたの“期待”に応えるために」
その言葉に、ユリウスは一瞬だけ動きを止めた。琥珀色のワインがグラスに静かに注がれ続ける。
「君は、いつも自分に厳しい」
ワインを手渡され、私は受け取る。
「でも、僕はね、アリア。君に“完璧”を求めたことなんて一度もない。君が生きていてくれる、それだけで十分だった」
「……嘘、です」
「嘘じゃない」
ユリウスは少し微笑んだ。
「君がこの国を救ったことを誰よりも誇りに思ってる。けれど、それ以上に……君が、僕の隣に戻ってきてくれたことが嬉しい」
その目は、ただの上司や同僚が向けるような視線ではなかった。
……ああ、だめだ。こんなに優しくされたら。
「ユリウス……」
「アリア」
そっと、ユリウスが私の手を取った。
その温もりに、私は一瞬だけ目を閉じる。戦場で何度も失いかけた心が、ようやく安堵に包まれる。
「お願いがあるんだ」
「……なんでしょう」
「君に、正式に近衛団長を任せたい。国王にかけあうつもりだ」
思わず、私は息を呑んだ。
「わたしが……団長?」
「ああ。戦場での采配、士気を維持し続けた統率力、そして剣の腕前。どれをとっても、今の騎士団では君以上の人材はいない」
私は、膝の上で拳をぎゅっと握る。
「でも……私は平民です。貴族社会に迎えられる保証など……」
「僕が保証する。君の出自ではなく、実力を見て判断する」
「それが通るほど、甘くはありませんよ。ユリウス、“殿下”」
わざと皮肉を込めてそう呼ぶと、ユリウスは困ったように笑った。
「君はいつも、自分を過小評価しすぎる」
「過小評価しているのではなく、現実を見ているだけです。レオナルド殿下のように」
その名前を出した瞬間、ユリウスの目が少しだけ細められた。
「……奴にまた何か言われたのか?」
「いえ。ただ、態度があまりにも……変わりすぎていて、呆れたというだけです」
「そうか」
ユリウスはグラスの中のワインを一口含み、言葉を選ぶようにしてから言った。
「アリア。……あいつにだけは、気を許さないでくれ。あいつは今、焦っている。君の存在が、あいつの立場を脅かしていると気づいたから」
「……王族としての立場を?」
「いや、男としても、かもしれないな」
冗談めいた調子だったけれど、彼の表情は真剣だった。
「奴は、君の価値を見誤った。手放したことを、今になって悔いているだろう」
「後悔しても、もう遅いです」
私はきっぱりとそう言い放ち、グラスを置く。
その時、扉の向こうで、控えの侍女の声がした。
「ユリウス殿下、第二王子レオナルド様がお見えです」
……来た。やっぱり来た。
ユリウスと目を合わせる。彼は微かに眉をひそめると、椅子から立ち上がった。
「通す必要はない。今は、私的な時間だ」
だが、扉が勢いよく開いた。
「兄上、少しだけ時間をいただけないか?」
堂々と入ってきたレオナルドの目が、まず私を捉え、次にユリウスを見た。
「……お邪魔だったかもしれないが、伝えたいことがあるんだ」
私は席を立ち、冷静に言葉を選ぶ。
「わたくしに、でしょうか」
「……ああ。君に」
レオナルドは一歩、私のほうに近づく。けれど、ユリウスがすっと私の前に出た。
「ここは、私の私室だ。来客の許可を出すのは、私だぞ、レオナルド」
その言葉にレオナルドは眉をひそめたが、言い返さなかった。
「……アリア。あの時のことを謝りたかった。君を、平民だからと侮ったこと……それは、間違いだった」
「ええ、間違いでしたね。でもそれを今になって言われても、何も変わりません」
「君は……昔のままじゃない」
「当たり前です。英雄と呼ばれてしまったので。平民のままの私では、国は救えませんでした」
皮肉混じりの言葉に、レオナルドはたじろぐ。
「……いや、本当に、俺は君を――」
「やめてください。昔の“恋人”に未練がましい言葉を投げかけるのは、貴族らしくありませんよ、レオナルド“殿下”」
私は、あえて冷たく、上から見下すように言った。
かつて私が見上げていた彼を、今は見下ろすことができる。地位ではなく、誇りによって。
レオナルドは何も言えなくなり、しばらく沈黙したのち、舌打ちをして部屋を出ていった。
扉が閉まる音が響いたあと、ユリウスがこちらを振り返った。
「……強くなったな、アリア」
「そう見えますか?」
「見えるよ。けど……無理は、してないか?」
その声は、今まででいちばん優しかった。
私は、少しだけ目を伏せた。
「……まだ、少しだけ怖いです。全部、夢なんじゃないかって。でも……あなたがいるから、なんとか、現実だと思える」
ユリウスの瞳が、ふわりと柔らかくなる。
次の瞬間、彼がそっと私の髪を撫でた。
「大丈夫。これは夢じゃない。……俺が、君の居場所になるから」
心が、ふっと軽くなる。
けれど、その夜。
王宮の奥深くで、一枚の密書が交わされていた。
『“英雄”アリアの存在は、国家の秩序を乱す――排除すべし』
その署名には、見覚えのある貴族の名が並んでいた。
アリアを巡る陰謀が、静かに幕を開けようとしていた。
106
あなたにおすすめの小説

私を捨てた婚約者へ――あなたのおかげで幸せです
有賀冬馬
恋愛
「役立たずは消えろ」
理不尽な理由で婚約を破棄された伯爵令嬢アンナ。
涙の底で彼女を救ったのは、かつて密かに想いを寄せてくれた完璧すぎる男性――
名門貴族、セシル・グラスフィット。
美しさ、強さ、優しさ、すべてを兼ね備えた彼に愛され、
アンナはようやく本当の幸せを手に入れる。
そんな中、落ちぶれた元婚約者が復縁を迫ってくるけれど――
心優しき令嬢が報われ、誰よりも愛される、ざまぁ&スカッと恋愛ファンタジー

婚約者に「愛することはない」と言われたその日にたまたま出会った隣国の皇帝から溺愛されることになります。~捨てる王あれば拾う王ありですわ。
松ノ木るな
恋愛
純真無垢な侯爵令嬢レヴィーナは、国の次期王であるフィリベールと固い絆で結ばれる未来を夢みていた。しかし王太子はそのような意思を持つ彼女を生意気だと疎み、気まぐれに婚約破棄を言い渡す。
伴侶と寄り添う幸せな未来を諦めた彼女は悲観し、井戸に身を投げたのだった。
あの世だと思って辿りついた先は、小さな貴族の家の、こじんまりとした食堂。そこには呑めもしないのに酒を舐め、身分社会に恨み節を唱える美しい青年がいた。
どこの家の出の、どの立場とも知らぬふたりが、一目で恋に落ちたなら。
たまたま出会って離れていてもその存在を支えとする、そんなふたりが再会して結ばれる初恋ストーリーです。

「華がない」と婚約破棄されたけど、冷徹宰相の恋人として帰ってきたら……
有賀冬馬
恋愛
「貴族の妻にはもっと華やかさが必要なんだ」
そんな言葉で、あっさり私を捨てたラウル。
涙でくしゃくしゃの毎日……だけど、そんな私に声をかけてくれたのは、誰もが恐れる冷徹宰相ゼノ様だった。
気がつけば、彼の側近として活躍し、やがては恋人に――!
数年後、舞踏会で土下座してきたラウルに、私は静かに言う。
「あなたが捨てたのは、私じゃなくて未来だったのね」

婚約破棄されたはずなのに、元婚約者が溺愛してくるのですが
ルイス
恋愛
「シルヴィア、私が好きなのは幼馴染のライナだ! お前とは婚約破棄をする!」
「そんな! アルヴィド様、酷過ぎます……!」
伯爵令嬢のシルヴィアは、侯爵のアルヴィドに一方的に婚約破棄をされてしまった。
一生を仕える心構えを一蹴されたシルヴィアは、精神的に大きなダメージを負ってしまった。
しかし、時が流れたある日、アルヴィドは180度態度を変え、シルヴィアを溺愛し再び婚約をして欲しいと言ってくるのだった。
シルヴィアはその時、侯爵以上の権力を持つ辺境伯のバルクと良い関係になっていた。今更もう遅いと、彼女の示した行動は……。

見捨ててくれてありがとうございます。あとはご勝手に。
有賀冬馬
恋愛
「君のような女は俺の格を下げる」――そう言って、侯爵家嫡男の婚約者は、わたしを社交界で公然と捨てた。
選んだのは、華やかで高慢な伯爵令嬢。
涙に暮れるわたしを慰めてくれたのは、王国最強の騎士団副団長だった。
彼に守られ、真実の愛を知ったとき、地味で陰気だったわたしは、もういなかった。
やがて、彼は新妻の悪行によって失脚。復縁を求めて縋りつく元婚約者に、わたしは冷たく告げる。

「輝きがない」と言って婚約破棄した元婚約者様へ、私は隣国の皇后になりました
有賀冬馬
恋愛
「君のような輝きのない女性を、妻にするわけにはいかない」――そう言って、近衛騎士カイルは私との婚約を一方的に破棄した。
私は傷つき、絶望の淵に落ちたけれど、森で出会った傷だらけの青年を助けたことが、私の人生を大きく変えることになる。
彼こそ、隣国の若き皇子、ルイス様だった。
彼の心優しさに触れ、皇后として迎え入れられた私は、見違えるほど美しく、そして強く生まれ変わる。
数年後、権力を失い、みすぼらしい姿になったカイルが、私の目の前に現れる。
「お久しぶりですわ、カイル様。私を見捨てたあなたが、今さら縋るなんて滑稽ですわね」。

私の物をなんでも欲しがる義妹が、奪った下着に顔を埋めていた
ばぅ
恋愛
公爵令嬢フィオナは、義母と義妹シャルロッテがやってきて以来、屋敷での居場所を失っていた。
義母は冷たく、妹は何かとフィオナの物を欲しがる。ドレスに髪飾り、果ては流行りのコルセットまで――。
学園でも孤立し、ただ一人で過ごす日々。
しかも、妹から 「婚約者と別れて!」 と突然言い渡される。
……いったい、どうして?
そんな疑問を抱く中、 フィオナは偶然、妹が自分のコルセットに顔を埋めている衝撃の光景を目撃してしまい――!?
すべての誤解が解けたとき、孤独だった令嬢の人生は思わぬ方向へ動き出す!
誤解と愛が入り乱れる、波乱の姉妹ストーリー!
(※百合要素はありますが、完全な百合ではありません)
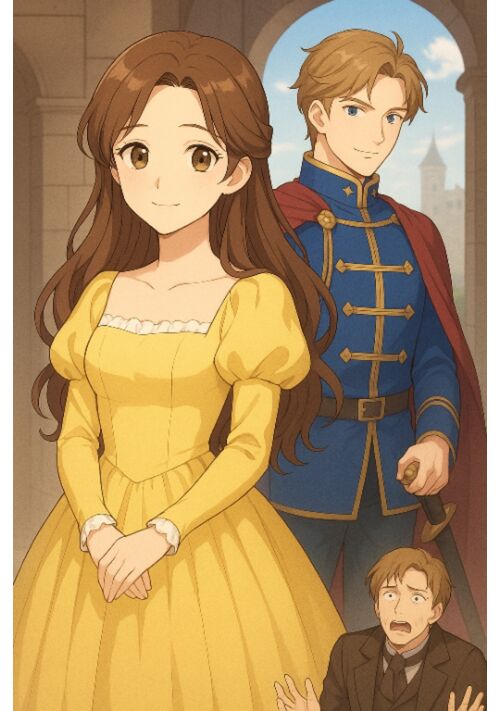
地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします
有賀冬馬
恋愛
子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。
唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。
もう二度と恋なんてしない。
そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。
彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。
彼は、この国の王太子だったのだ。
「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。
一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。
私に助けを求めてきた彼に、私は……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















