135 / 140
九頁 愛憎のヒガンバナ
126話 一筋縄ではいかない子息
しおりを挟む
アウルはアラグリアの横暴に関して即座に学園へ戻り、アクナイト公爵とエヴェイユへ連絡を入れた。すぐに折り返しがあり、事情聴取が行われることになって、アウルはエヴェイユのいる生徒会長室へと呼ばれた。
「さて……随分と大変な目に遭いましたね」
「俺はいい。だがまさかアラグリアが直接乗り込んでくるとは……」
「それもですが貴方の知らせにあった魅了の力についてです。アラグリア・リコリスが魅了の力を使ったというのは事実ですか?」
「……ああ。間違いない」
「彼女は無属性持ちではなかったと思いますが、一体どうやって使ったというのですか? しかもアクナイト公爵邸全体に掛けられるほどの魅了魔法とは……いえ、この場合は魔術と呼ぶべきでしょうか?」
「いや、詠唱はしていなかったから魔術のほうだろう。信じ難いのは俺も同じだ。だがあの不愉快な魔力と使用人たちの行動はそれ以外に説明がつかない」
「まあお話を聞く限り、魅了というよりは洗脳と言った方が正しいのでしょうけど……彼女が何らかの方法でその力を手に入れたのだとしたら、アマラ・リコリスの状態にも納得がいきますね」
「……アマラ・リコリスとはたしか元・アクナイト公爵夫人だったか? なぜ彼女の名前がここで出る?」
「ああ……実はですね——」
深いため息とともにエヴェイユから齎された情報は衝撃的なものだった。
アラグリアがアクナイト邸に襲来したのと同じ時刻にアクナイト公爵のもとへは元・公爵夫人が訪れていたらしい。最初は追い返そうとした公爵だが彼女は姪であるアラグリアを止めてほしいと涙ながらに訴えていたという。しかしそもそもは元・夫人が原因での離縁である。加害者側が被害者側に助けを求めるというのは厚顔無恥にもほどがある。ましてやアクナイト家はリコリス家よりも身分が上なのだ。そんな相手に『お願い』などできるはずもない。にも拘らず平然と自分の前に現れた女を公爵は冷めた目で見ていた。そこへアラグリアによるアクナイト邸襲撃の知らせを受け、アクナイト公爵はその場で元夫人であるアマラ・リコリスを拘束。現在黒光騎士団による取り調べが行われている。
「……それはどう考えても」
「ええ。十中八九アラグリア・リコリスの指示でしょうね。公爵子息だけでなく公爵家の敷地をも害したとしてすでに重要指名手配となっております。しかしリコリスの所有する別荘なども当たっておりますがいまだどこへ向かったかが掴めません」
「暗部のほうは?」
「そちらも使っておりますが……もし目くらましの類の魔術を使用しているのだとしたら捜索には時間がかかるでしょうね」
「そうか……エヴェイユ」
「なんです?」
「……これ、なんだと思う?」
「……?」
この状況におおよそ似つかわしくない問いにエヴェイユは怪訝な顔をしながらアウルが置いたものを見下ろす。それは一冊の本と丸薬が入った小瓶だった。小瓶についてはこの際置いておいて問題は本のほうである。一見するとただの本だが違和感が強い。それが意味するところにも気づいてしまったエヴェイユは思わず額に手を当てて深いため息をついた。
「シュヴァリエ公子は本当に…………大方アラグリア・リコリスを欺くため、というのは理解できますが……納得できませんね」
「それについては同意だ。だがおかげで同盟関係にひびが入りかねないことをしでかした馬鹿を処理できるというのから何とも言えないな」
「…………そんなことを他国の人間に言われるこちらの身にもなってください」
「…………すまない。だがアウィスもこの国の王族を巻き込んでいるのだからお互い様だろう」
「あの愚弟は自ら首を突っ込んでいるんですよ……」
「今の俺だって似たようなものだ」
「……本当に勘弁してください。じゃじゃ馬は弟二人で十分ですよ」
「何を言っている? 君だって相当なじゃじゃ馬だろう。王太子殿下から弟たちがやりたい放題だと聞いているが?」
「他国の人間に何を話しているんですかあの人は……」
「心配するな、ただの世間話だ」
すっかり頭を抱えてしまったエヴェイユをしばらく楽しそうに見つめていたアウルだが、すっと机に置かれた本へ視線を移すと険しい表情で表紙をなぞる。『愛に堕ちた魔女』と書かれたタイトルにアウルは真っ先にアラグリア・リコリスを想像した。この本は読んだことがなかったが、わざわざシュヴァリエが選んだのだ。何かしら意味があるのだろう。
「エヴェイユ、これを読んだことはあるか?」
「……一度だけですが。しかしおそらく本の中身は別のお話かもしれませんね」
「なぜだ?」
「まず本の表紙がところどころ違います。次に本自体が薄すぎるのですよ」
「……ならエヴェイユが読んだという正規のものとは違うということか。何のためにそんな真似を」
「わかりません。そもそも開けないかと」
「どういうことだ?」
「この本にこんな金具はついていません」
「……はあ、シュヴァリエがここまで手の込んだことをするとはよっぽど警戒していたんだろうな」
「……そのようですね。彼はどのように処するつもりなのでしょう」
「こういう状況で意味のないことはしないだろう。これを開ける鍵はすでに俺たちが持っているのかもしれない」
「……鍵、ですか? そんなものもらった記憶はありませんが」
「こういった本には通常鍵穴があるがこれにはそれが見当たらない。だから鍵自体が特殊な形をしている可能性がある」
「なるほど……魔術で封じてあるという可能性もありますがこの本から魔力は感じない。ゆえに特殊な形の鍵があるということですか」
「問題はそれが何か、だが……」
その時。
「ギュイ♪」
「うわ!?」
突然アウルの膝に乗ってきたのはご機嫌なフェイバースパイダーの子どもだった。この子蜘蛛はほかの人に見られることを防ぐため、荷物としてアウルのカバンに入っていることが多い。基本的には大人しいが時々抜け出してはどこかへと散歩に出かけてしまうやんちゃなところがあった。ここ最近はシュヴァリエのところへ行くことが多く、その場合は寮の部屋で留守番となっていたのだが……どうやらここへ来てしまったらしい。何かあった際はエヴェイユのいる場所に行くようにと事前に取り決めており、不用心にはなるが、エヴェイユがいるところの窓を開けるようにしていたため入ってこれたのだろう。そしてアウルがいるときは決まって彼の膝に乗っていた。
そんなフェイバースパイダーの子どもはアウルの膝に乗ったまま机の上に置いてある本をじっと見つめた後、何を思ったのかアウルの袖をずらし腕につけていたバングルを露わにした。そして下からアウルを見上げながら本の金具部分をつつく。
アウルははっとしてシュヴァリエからもらったバングルを見る。このバングルは中に入っている羽の一部分が浮き出るようにして凹凸になっていた。そしてこのバングルに使われている素材はフェイバースパイダーの糸である。だとすれば本についている金具部分もそれが使用されている可能性は高い。
アウルは腕からバングルを抜き取ると子蜘蛛が指し示すまま金具の凹凸にそっとバングルの凹凸を重ねた。それらは一切の隙間もなくかちりとはまった感触があり、ゆっくりと一周させるとカチャと鍵の開く音が響いた。
「本当に開いた……これが鍵だったとはな」
「考えましたね。これならなかなか気づきにくいでしょう」
「この金具もシュヴァリエが作ったのだとしたらバングルと合わせるなど造作もなかっただろう。なにせ製作者本人だ。いくらでも細工はできる」
「ええ。それに次期眷属様が反応したということはそのバングルどころかこの金具にもフェイバースパイダーの糸が使われているのでしょう」
その予想は正しいらしく子蜘蛛は満足げに足を上げた。
アウルは腕にバングルをはめ直し、エヴェイユと目を合わせて表紙を開く。
「な、なんだこれは……?!」
「……彼は一体なぜこんなことを?」
本を覗き込んだ二人の目に飛び込んできたのは何も書かれていない、ただひたすらに真っ白なページだけだった——
「さて……随分と大変な目に遭いましたね」
「俺はいい。だがまさかアラグリアが直接乗り込んでくるとは……」
「それもですが貴方の知らせにあった魅了の力についてです。アラグリア・リコリスが魅了の力を使ったというのは事実ですか?」
「……ああ。間違いない」
「彼女は無属性持ちではなかったと思いますが、一体どうやって使ったというのですか? しかもアクナイト公爵邸全体に掛けられるほどの魅了魔法とは……いえ、この場合は魔術と呼ぶべきでしょうか?」
「いや、詠唱はしていなかったから魔術のほうだろう。信じ難いのは俺も同じだ。だがあの不愉快な魔力と使用人たちの行動はそれ以外に説明がつかない」
「まあお話を聞く限り、魅了というよりは洗脳と言った方が正しいのでしょうけど……彼女が何らかの方法でその力を手に入れたのだとしたら、アマラ・リコリスの状態にも納得がいきますね」
「……アマラ・リコリスとはたしか元・アクナイト公爵夫人だったか? なぜ彼女の名前がここで出る?」
「ああ……実はですね——」
深いため息とともにエヴェイユから齎された情報は衝撃的なものだった。
アラグリアがアクナイト邸に襲来したのと同じ時刻にアクナイト公爵のもとへは元・公爵夫人が訪れていたらしい。最初は追い返そうとした公爵だが彼女は姪であるアラグリアを止めてほしいと涙ながらに訴えていたという。しかしそもそもは元・夫人が原因での離縁である。加害者側が被害者側に助けを求めるというのは厚顔無恥にもほどがある。ましてやアクナイト家はリコリス家よりも身分が上なのだ。そんな相手に『お願い』などできるはずもない。にも拘らず平然と自分の前に現れた女を公爵は冷めた目で見ていた。そこへアラグリアによるアクナイト邸襲撃の知らせを受け、アクナイト公爵はその場で元夫人であるアマラ・リコリスを拘束。現在黒光騎士団による取り調べが行われている。
「……それはどう考えても」
「ええ。十中八九アラグリア・リコリスの指示でしょうね。公爵子息だけでなく公爵家の敷地をも害したとしてすでに重要指名手配となっております。しかしリコリスの所有する別荘なども当たっておりますがいまだどこへ向かったかが掴めません」
「暗部のほうは?」
「そちらも使っておりますが……もし目くらましの類の魔術を使用しているのだとしたら捜索には時間がかかるでしょうね」
「そうか……エヴェイユ」
「なんです?」
「……これ、なんだと思う?」
「……?」
この状況におおよそ似つかわしくない問いにエヴェイユは怪訝な顔をしながらアウルが置いたものを見下ろす。それは一冊の本と丸薬が入った小瓶だった。小瓶についてはこの際置いておいて問題は本のほうである。一見するとただの本だが違和感が強い。それが意味するところにも気づいてしまったエヴェイユは思わず額に手を当てて深いため息をついた。
「シュヴァリエ公子は本当に…………大方アラグリア・リコリスを欺くため、というのは理解できますが……納得できませんね」
「それについては同意だ。だがおかげで同盟関係にひびが入りかねないことをしでかした馬鹿を処理できるというのから何とも言えないな」
「…………そんなことを他国の人間に言われるこちらの身にもなってください」
「…………すまない。だがアウィスもこの国の王族を巻き込んでいるのだからお互い様だろう」
「あの愚弟は自ら首を突っ込んでいるんですよ……」
「今の俺だって似たようなものだ」
「……本当に勘弁してください。じゃじゃ馬は弟二人で十分ですよ」
「何を言っている? 君だって相当なじゃじゃ馬だろう。王太子殿下から弟たちがやりたい放題だと聞いているが?」
「他国の人間に何を話しているんですかあの人は……」
「心配するな、ただの世間話だ」
すっかり頭を抱えてしまったエヴェイユをしばらく楽しそうに見つめていたアウルだが、すっと机に置かれた本へ視線を移すと険しい表情で表紙をなぞる。『愛に堕ちた魔女』と書かれたタイトルにアウルは真っ先にアラグリア・リコリスを想像した。この本は読んだことがなかったが、わざわざシュヴァリエが選んだのだ。何かしら意味があるのだろう。
「エヴェイユ、これを読んだことはあるか?」
「……一度だけですが。しかしおそらく本の中身は別のお話かもしれませんね」
「なぜだ?」
「まず本の表紙がところどころ違います。次に本自体が薄すぎるのですよ」
「……ならエヴェイユが読んだという正規のものとは違うということか。何のためにそんな真似を」
「わかりません。そもそも開けないかと」
「どういうことだ?」
「この本にこんな金具はついていません」
「……はあ、シュヴァリエがここまで手の込んだことをするとはよっぽど警戒していたんだろうな」
「……そのようですね。彼はどのように処するつもりなのでしょう」
「こういう状況で意味のないことはしないだろう。これを開ける鍵はすでに俺たちが持っているのかもしれない」
「……鍵、ですか? そんなものもらった記憶はありませんが」
「こういった本には通常鍵穴があるがこれにはそれが見当たらない。だから鍵自体が特殊な形をしている可能性がある」
「なるほど……魔術で封じてあるという可能性もありますがこの本から魔力は感じない。ゆえに特殊な形の鍵があるということですか」
「問題はそれが何か、だが……」
その時。
「ギュイ♪」
「うわ!?」
突然アウルの膝に乗ってきたのはご機嫌なフェイバースパイダーの子どもだった。この子蜘蛛はほかの人に見られることを防ぐため、荷物としてアウルのカバンに入っていることが多い。基本的には大人しいが時々抜け出してはどこかへと散歩に出かけてしまうやんちゃなところがあった。ここ最近はシュヴァリエのところへ行くことが多く、その場合は寮の部屋で留守番となっていたのだが……どうやらここへ来てしまったらしい。何かあった際はエヴェイユのいる場所に行くようにと事前に取り決めており、不用心にはなるが、エヴェイユがいるところの窓を開けるようにしていたため入ってこれたのだろう。そしてアウルがいるときは決まって彼の膝に乗っていた。
そんなフェイバースパイダーの子どもはアウルの膝に乗ったまま机の上に置いてある本をじっと見つめた後、何を思ったのかアウルの袖をずらし腕につけていたバングルを露わにした。そして下からアウルを見上げながら本の金具部分をつつく。
アウルははっとしてシュヴァリエからもらったバングルを見る。このバングルは中に入っている羽の一部分が浮き出るようにして凹凸になっていた。そしてこのバングルに使われている素材はフェイバースパイダーの糸である。だとすれば本についている金具部分もそれが使用されている可能性は高い。
アウルは腕からバングルを抜き取ると子蜘蛛が指し示すまま金具の凹凸にそっとバングルの凹凸を重ねた。それらは一切の隙間もなくかちりとはまった感触があり、ゆっくりと一周させるとカチャと鍵の開く音が響いた。
「本当に開いた……これが鍵だったとはな」
「考えましたね。これならなかなか気づきにくいでしょう」
「この金具もシュヴァリエが作ったのだとしたらバングルと合わせるなど造作もなかっただろう。なにせ製作者本人だ。いくらでも細工はできる」
「ええ。それに次期眷属様が反応したということはそのバングルどころかこの金具にもフェイバースパイダーの糸が使われているのでしょう」
その予想は正しいらしく子蜘蛛は満足げに足を上げた。
アウルは腕にバングルをはめ直し、エヴェイユと目を合わせて表紙を開く。
「な、なんだこれは……?!」
「……彼は一体なぜこんなことを?」
本を覗き込んだ二人の目に飛び込んできたのは何も書かれていない、ただひたすらに真っ白なページだけだった——
639
あなたにおすすめの小説


結婚十年目の夫から「結婚契約更新書」なるものが届いた。彼は「送り間違えた」というけれど、それはそれで問題なのでは?
ぽんた
恋愛
レミ・マカリスター侯爵夫人は、夫と政略結婚をして十年目。侯爵夫人として、義父母の介護や領地経営その他もろもろを完ぺきにこなしている。そんなある日、王都に住む夫から「結婚契約更新書」なるものが届いた。義弟を通じ、夫を追求するも夫は「送り間違えた。ほんとうは金を送れというメモを送りたかった」という。レミは、心から思った。「それはそれで問題なのでは?」、と。そして、彼女の夫にたいするざまぁがはじまる。
※ハッピーエンド確約。ざまぁあり。ご都合主義のゆるゆる設定はご容赦願います。

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。
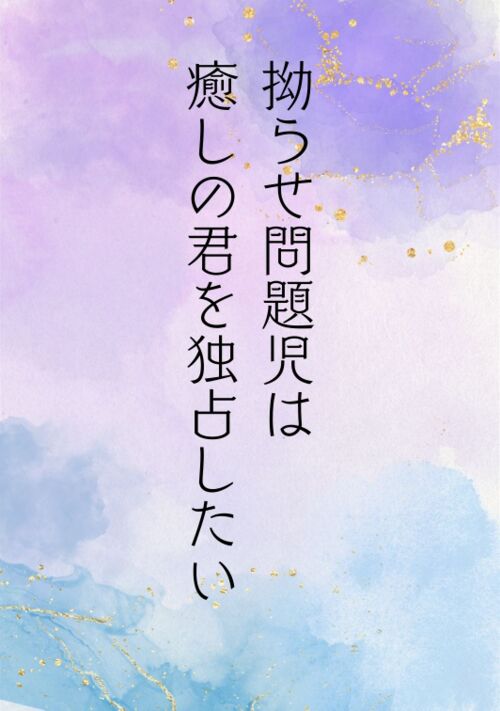
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
-----------------------------------------
0時,6時,12時,18時に2話ずつ更新

悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















