8 / 140
一頁 覚醒のロベリア
8話 事件の報告①
しおりを挟む
今、俺の前に公爵と夫人、それから夫人付き侍女のシエンナがいる。どいつもこいつも無駄に険しい顔しちゃって、そんなに俺からの呼び出しが嫌か。もっとも夫人と侍女を呼んだのは俺じゃなくて公爵なんだけど。公爵は体面を重んじるから夫人も交えて俺の今後の話をしたいと持ちかけたのだ。その際、以前夫人に不敬を働いたことを理由に夫人付きの筆頭侍女を彼女の護衛につけてくれと言ったがこちらもなんとか承諾させて、最初の面子が揃った。
「……それで? お前が私たちの時間を潰してまで話がしたいと言うからには、それなりの内容なのだろうな」
お前に費やす時間はない、とはっきり言う公爵にシュヴァリエとしての感情が一瞬だけチクリと疼く。こんな奴でも一時期は父と言っていた相手だ。しかし揺れ動いたのは本当に一瞬で、そのあとはいっそおかしくなるくらいになにも感じなくなった。それにいつも感じていた恐怖も驚くほどに掻き消えている。だからこそ、俺はまっすぐに公爵を見つめて躊躇うことなく言った。
「先日私が毒を盛られた件についての調査報告です」
途端に二人の眼差しがさらにキツくなる。もう若くないのにそんなに皺を寄せて大丈夫か?
「何を言い出すのかと思えばくだらん。毒を盛られたからなんだ。アクナイトの人間があの程度の毒でいちいち大袈裟に騒ぎ立てるな」
「その通りですわ。わざわざ私まで呼び立ててそんなこと……」
そんなこと、ねえ? 公爵家という王家に近い関係にある貴族の子息が毒殺されかけたのにその程度で済ます神経がわからんのだが。まあまともな神経していたらもう少しちゃんと動いているか。それにあの程度と言っているが、本当に毒の説明を受けていないのだろうか? それとも毒のことを分かった上で言っているのか? どっちにしてもまずいってわかれよ盆暗が。
「ひとまず報告を聞いていただけますか。本当にあの程度ですませて良いことなのかはそれからでも遅くはないかと」
「くだらない!」
そう言って公爵夫人はすぐに席を立とうとした。
「どこへ行かれるのです?」
「お前の戯言に付き合っていられないから刺繍の続きをしに行くに決まっているでしょう!」
「へえ……? 私はてっきり愛する公爵の前で悪女の素顔を暴かれるのが嫌なのかと思いましたが」
「……なんですって?」
いくらか低い声で言葉を発した夫人は確かな怒りを浮かべた瞳をこちらへ向けた。いや、怒りたいのはこっちだっつーの。
「今のはどういう意味かしら?」
「そのままの意味ですよ。というか公爵が席を立っていないのに怒りに任せて行動するのは公爵夫人という立場的によろしくないかと」
俺がはっきりと言うと夫人は一瞬で顔を赤くした。短気だな。というか公爵夫人という立場の人間がこんな感情的で大丈夫なのか。ほんと公爵もよく結婚したものだよ。
「お前……私を侮辱しているの!?」
「事実でしょう? この程度のことで声を荒げるなんてアクナイトの女主人としてどうかと思いますけどね」
にっこり微笑んでやると公爵夫人が耐えきれなくなったのか、持っていた扇子を振りかぶった。……そんな攻撃効くか。
「そのまま振り下ろしていただいても結構ですが、ここには公爵もおられることをお忘れなきよう」
俺の言葉にハッとなった夫人がチラリと公爵の顔色を伺う。その目にはほんの僅かに怯えが滲んでいて、よっぽど失望されるのが嫌らしい。当の公爵は夫人に目をくれることなく無言で俺を睨むばかり。
「……アマラ、少し静かにしなさい」
「……はい」
公爵に言われては夫人は従うほかなく、黙りこくった。それでも目だけは元気に動かして俺を捉えている。
「お前は自分が何を言っているのかわかっているのか?」
公爵が俺に対して口を開いた。その声は酷く冷たく、子供に向ける声ではない。少なくとも息子には向けない。こんなに態度に出されると逆に清々しいな。
まあそれでも公爵は俺の話を聞くことを選んだようだ。でなきゃこんな質問はしてこない。俺はまっすぐに公爵を見据えて、深く頷く。
「もちろんです。でなければわざわざお二人を呼びません」
「お前の内容に筋が通っていないと判断された場合どうなるのかも理解していると?」
「はい、その際はお好きなようになさってください。ですが、今から話すことは嘘偽りない証拠つきです。よほどのことがない限り覆りません」
「……そこまで言うのなら話だけは聞いてやろう。本来ならばお前の言葉を聞く筋合いはないが、我がアクナイトに関わることであるならば別だ。言うだけ言ってみろ」
「ありがとうございます」
うおぉっ……! よかったぁぁ! 正直話を聞いてくれるのか微妙だった。これで思う存分にやれる。公爵は利益のあることを重んじるし、これでも一応騎士団長だ。それなりに礼節や義も持っている。俺の話を聞くだけ聞くか無視するか、息子でないと言った人ではあるがアクナイト公爵家に属する人間として最善を選ぶことは予想できたけど、自信なかったからな。
さてこれで準備は整った。
「まずは先日私が倒れた毒物についてですが、サラダに盛られていました」
「ほう? 根拠は?」
「こちらです」
俺はサリクスが描いた数枚の絵を机に並べた。そこには厨房の様子が描かれており、見るだけでも忙しなく動いているのがわかる。
「この絵がなんだ?」
「こちらの絵に描かれている料理人、手に花を持っているでしょう?」
「ああ」
「この花がどのようなものか、公爵はご存じですか?」
「知らん。花は花だろう」
「……」
花は花って……まだ枯れるには少~し早い気がするんだが、大丈夫かよこの親父。
「……この花が毒物です」
「なに?」
「この花の名前は宿根ロベリア。別名サワギキョウともいい、全草にロベリンという毒が含まれています。摂取した場合は嘔吐、頭痛、呼吸困難などの症状を引き起こし、最悪の場合死に至ります」
そこまで説明すると公爵は思案顔になり、夫人の方は相変わらず俺を睨んでいた。説明中もずっとこうだったんだけど、黙っていてもうるさい奴って本当にいるんだな。
「その症状はお前の診断書に記載れていたものと同じだな」
「……ご覧になっていたんですね」
「この屋敷で起こったことだ。一応目は通す」
ほう……? 症状を知っていたのに『あの程度』とか言いやがったわけか。じゃああんたはロベリアを食っても平気とでも言いたいのかよ。……まあいいや。
「こちらを」
「なんだ?」
「アクナイト公爵家の所有するすべての場所に植えられている植物の一覧です。こちらを見てもらえればわかりますが、この花はこの屋敷には存在しない花なんです。温室、ガゼボ、中庭……植物が存在する場所にロベリアの花は置いておりません。そして他の場所にも」
唐突に出された書類に公爵が微かに目を見張る。気持ちはわかる。どうやって調べたのかってことだよな? それはカルに聞け。俺は最近の公爵家の人間が購入したものと公爵夫妻の調査しかお願いしていないのに届いた紙束の中に『これついでにあげる♡』とかふざけたメモとともにしれっと混ざっていたものだ。俺個人的にはすげえありがたいんだけど……後で追加請求されそうだ。
「これをどこで手に入れた?」
「さあ? 私にもそれなりにツテはあります」
「……まあいいだろう。続けよ」
へえ? 喋らせてくれるんだ。植物に関してはそれぞれの場所を管理している庭師やらに聞けば裏は取れるから詮索の必要なしと判断したんだろうな。それじゃ、お話を続けましょうかね。
「公爵家が所有していない花が私の食事に入っていた、ということは誰かが持ち込んだことは明白です。そしてその持ち込んだ、あるいは持ち込むように指示した人物こそ、私に毒を盛り死に至らしめようとした犯人です」
「そうなるな。ここに描かれている料理人はその犯人の手下か」
「はい。もちろん直接の下手人はこの料理人ですがただの料理人が独断で公爵家の人間に毒を盛るとは思えない。背後に指示した人物がいます。証拠の方もーー」
「ちょっと待ちなさいよ!」
公爵に言われ今まで口は閉じていた夫人が割り込んできた。このタイミングで突っ込んでくるか。なんか言いたいことでもあるんですかね。
「なんでしょうか?」
「お前はさっきからこの絵から毒花の話をしているけど、この絵は一体なんなの? こんな都合よく絵があるなんておかしいわ。卑しいお前のことだからどうせ事件にしたくてわざと偽りの絵を描いたんでしょう。ここに描かれているのが本当にアクナイト公爵家の料理人かも怪しいわよ」
うん、一理ある。前世みたいに防犯カメラがあるわけじゃないし、それに近しい魔道具ならあるけど、我が家の厨房には置かれていない。だとすれば過去のことなど記録しようがないから、でっち上げだと思うのは自然なことだ。しかしこの絵を持ってきた時点でその質問が飛んでくることは予想済みだった。でなければこんなもの危なっかしくて証拠には出せない。
「厨房には魔道具を置いていないから過去を記録することは不可能。だからこれは私が犯人を陥れるために描いたまやかしだと、夫人は仰りたいのですね」
「そうよ。わかっているじゃない。過去を知るには『写実の水晶』が必要よ。でもあそこにそんな水晶は置いていないわ。ならでっち上げだと考えるのが自然ではなくて? ねえ、あなたもそう思うでしょう?」
公爵を巻き込んだか。すぐ公爵に擦り寄ろうとするところ、何年経っても変わらないな。まるで虎の威を借る狐だ。だけど、夫人の言葉には納得できる要素しかない。これには公爵も頷いた。
「アマラの言う通りだな。そんなものは置いていないはずだ。それはどう説明する?」
「それに関しましては、本人に説明させるのが早いかと」
「どういう意味だ」
公爵が眉を顰めると同時に室内にノックが響き渡る。
「なんだ」
「お話中のところ失礼致します。サリクスでございます」
「……シュヴァリエの侍従がなんの用だ」
「御二方の疑問に対する答えですよ。どうか入れて差し上げてください」
「…………入れ」
しばしの間の後、許可が下り入ってきたのは俺の専属侍従のサリクスとあと二人。件の馬鹿、もといロベリアをサラダに入れた料理人のファボルとサリクスの上司でアクナイト公爵家の侍従長ダズルだった。
「ダズル? なぜお前がここにいる」
「私がお願いしたのです。我が専属侍従の証人になってもらいたいと。サリクスだけでは口裏を合わせていると言われかねなかったもので」
「一体なんの証人だ?」
「それは……」
一瞬サリクスに視線を向け、微かに目で頷いたことを確認する。本当はこんな初っ端に明かしたくなかったんだけど、必要なことだったし、公爵という立場上知っていても損はないだろう。それにサリクスの能力は使い勝手がいい。黙秘した罪人の尋問やら証拠探しやらにめちゃくちゃ便利だ。サリクスの雇い主は公爵であって俺じゃないから公爵という立場から命じられれば使用人であるサリクスには断りようがない。
「サリクスの魔法は無属性魔法で能力は実写です。彼は『写実の水晶』と同じ能力を持っています」
案の定公爵夫妻の表情がガラリと変わりサリクスへと驚愕の視線を向けた。ですよね! 何その反則の技。使いようによってめちゃくちゃ怖い能力を持つ人間がそばにいたことに今まで気づかなかったわけだ。そりゃ驚愕もするよな~……。驚愕の理由は公爵と夫人で違うみたいだけど。
「それは真実か?」
「嘘ではございません。そうだろダズル?」
俺は後ろに控えているダズルに視線を向けた。ダズルは一歩踏み出すと公爵と夫人に一礼をする。
「旦那様、発言をお許しいただけますか」
「ああ、申せ」
「ありがとうございます。サリクスの能力に関してですが、このダズル・グラジオスの名において保証いたします」
「お前は知っていたのだな」
「はい。申し訳ございません」
「よい。無属性持ちの場合、本人の了承なしに能力を明かすことは許されていない。よって不問とする」
「寛大なお言葉ありがとうございます」
今、公爵がサラッと言ったけど、この世界では無属性を持って生まれた人間はその能力を他人に秘さなければいけないという制約がある。本人の同意なしに能力を明かすことはタブーとされ、その場合は他人にバラした者には呪いがかけられるというよくわからないシステムがあるのだ。ちなみにその理由は明かされていない。ただゲームの設定資料集に記述があった。運営さん方はなんでこんな意味不明な設定作ったんだか。
「侍従長がお認めになったことで、納得していただけましたでしょうか」
「……ああ。そんな能力があると知っていればお前にはつけなかったんだが」
はいはい、言ってくれるじゃねえかよ。俺は便利に使わせてもらっていますけどね。それに能力なんか関係なく俺はサリクスを信頼している。そう簡単に手放しはしない。
「……ひとまず、この絵の信憑性も確立されたと思います。夫人もこれでよろしいでしょうか」
「……侍従長を出してくるなんて本当に腹立たしいわね」
今にも歯軋りをしそうなほど悔しげな顔で睨む夫人に俺は内心ニヤリと笑う。まだまだこれからなのに今からそんな調子で大丈夫かな~?
「……さて、役者が揃ったことで、続きを始めましょうか」
「……それで? お前が私たちの時間を潰してまで話がしたいと言うからには、それなりの内容なのだろうな」
お前に費やす時間はない、とはっきり言う公爵にシュヴァリエとしての感情が一瞬だけチクリと疼く。こんな奴でも一時期は父と言っていた相手だ。しかし揺れ動いたのは本当に一瞬で、そのあとはいっそおかしくなるくらいになにも感じなくなった。それにいつも感じていた恐怖も驚くほどに掻き消えている。だからこそ、俺はまっすぐに公爵を見つめて躊躇うことなく言った。
「先日私が毒を盛られた件についての調査報告です」
途端に二人の眼差しがさらにキツくなる。もう若くないのにそんなに皺を寄せて大丈夫か?
「何を言い出すのかと思えばくだらん。毒を盛られたからなんだ。アクナイトの人間があの程度の毒でいちいち大袈裟に騒ぎ立てるな」
「その通りですわ。わざわざ私まで呼び立ててそんなこと……」
そんなこと、ねえ? 公爵家という王家に近い関係にある貴族の子息が毒殺されかけたのにその程度で済ます神経がわからんのだが。まあまともな神経していたらもう少しちゃんと動いているか。それにあの程度と言っているが、本当に毒の説明を受けていないのだろうか? それとも毒のことを分かった上で言っているのか? どっちにしてもまずいってわかれよ盆暗が。
「ひとまず報告を聞いていただけますか。本当にあの程度ですませて良いことなのかはそれからでも遅くはないかと」
「くだらない!」
そう言って公爵夫人はすぐに席を立とうとした。
「どこへ行かれるのです?」
「お前の戯言に付き合っていられないから刺繍の続きをしに行くに決まっているでしょう!」
「へえ……? 私はてっきり愛する公爵の前で悪女の素顔を暴かれるのが嫌なのかと思いましたが」
「……なんですって?」
いくらか低い声で言葉を発した夫人は確かな怒りを浮かべた瞳をこちらへ向けた。いや、怒りたいのはこっちだっつーの。
「今のはどういう意味かしら?」
「そのままの意味ですよ。というか公爵が席を立っていないのに怒りに任せて行動するのは公爵夫人という立場的によろしくないかと」
俺がはっきりと言うと夫人は一瞬で顔を赤くした。短気だな。というか公爵夫人という立場の人間がこんな感情的で大丈夫なのか。ほんと公爵もよく結婚したものだよ。
「お前……私を侮辱しているの!?」
「事実でしょう? この程度のことで声を荒げるなんてアクナイトの女主人としてどうかと思いますけどね」
にっこり微笑んでやると公爵夫人が耐えきれなくなったのか、持っていた扇子を振りかぶった。……そんな攻撃効くか。
「そのまま振り下ろしていただいても結構ですが、ここには公爵もおられることをお忘れなきよう」
俺の言葉にハッとなった夫人がチラリと公爵の顔色を伺う。その目にはほんの僅かに怯えが滲んでいて、よっぽど失望されるのが嫌らしい。当の公爵は夫人に目をくれることなく無言で俺を睨むばかり。
「……アマラ、少し静かにしなさい」
「……はい」
公爵に言われては夫人は従うほかなく、黙りこくった。それでも目だけは元気に動かして俺を捉えている。
「お前は自分が何を言っているのかわかっているのか?」
公爵が俺に対して口を開いた。その声は酷く冷たく、子供に向ける声ではない。少なくとも息子には向けない。こんなに態度に出されると逆に清々しいな。
まあそれでも公爵は俺の話を聞くことを選んだようだ。でなきゃこんな質問はしてこない。俺はまっすぐに公爵を見据えて、深く頷く。
「もちろんです。でなければわざわざお二人を呼びません」
「お前の内容に筋が通っていないと判断された場合どうなるのかも理解していると?」
「はい、その際はお好きなようになさってください。ですが、今から話すことは嘘偽りない証拠つきです。よほどのことがない限り覆りません」
「……そこまで言うのなら話だけは聞いてやろう。本来ならばお前の言葉を聞く筋合いはないが、我がアクナイトに関わることであるならば別だ。言うだけ言ってみろ」
「ありがとうございます」
うおぉっ……! よかったぁぁ! 正直話を聞いてくれるのか微妙だった。これで思う存分にやれる。公爵は利益のあることを重んじるし、これでも一応騎士団長だ。それなりに礼節や義も持っている。俺の話を聞くだけ聞くか無視するか、息子でないと言った人ではあるがアクナイト公爵家に属する人間として最善を選ぶことは予想できたけど、自信なかったからな。
さてこれで準備は整った。
「まずは先日私が倒れた毒物についてですが、サラダに盛られていました」
「ほう? 根拠は?」
「こちらです」
俺はサリクスが描いた数枚の絵を机に並べた。そこには厨房の様子が描かれており、見るだけでも忙しなく動いているのがわかる。
「この絵がなんだ?」
「こちらの絵に描かれている料理人、手に花を持っているでしょう?」
「ああ」
「この花がどのようなものか、公爵はご存じですか?」
「知らん。花は花だろう」
「……」
花は花って……まだ枯れるには少~し早い気がするんだが、大丈夫かよこの親父。
「……この花が毒物です」
「なに?」
「この花の名前は宿根ロベリア。別名サワギキョウともいい、全草にロベリンという毒が含まれています。摂取した場合は嘔吐、頭痛、呼吸困難などの症状を引き起こし、最悪の場合死に至ります」
そこまで説明すると公爵は思案顔になり、夫人の方は相変わらず俺を睨んでいた。説明中もずっとこうだったんだけど、黙っていてもうるさい奴って本当にいるんだな。
「その症状はお前の診断書に記載れていたものと同じだな」
「……ご覧になっていたんですね」
「この屋敷で起こったことだ。一応目は通す」
ほう……? 症状を知っていたのに『あの程度』とか言いやがったわけか。じゃああんたはロベリアを食っても平気とでも言いたいのかよ。……まあいいや。
「こちらを」
「なんだ?」
「アクナイト公爵家の所有するすべての場所に植えられている植物の一覧です。こちらを見てもらえればわかりますが、この花はこの屋敷には存在しない花なんです。温室、ガゼボ、中庭……植物が存在する場所にロベリアの花は置いておりません。そして他の場所にも」
唐突に出された書類に公爵が微かに目を見張る。気持ちはわかる。どうやって調べたのかってことだよな? それはカルに聞け。俺は最近の公爵家の人間が購入したものと公爵夫妻の調査しかお願いしていないのに届いた紙束の中に『これついでにあげる♡』とかふざけたメモとともにしれっと混ざっていたものだ。俺個人的にはすげえありがたいんだけど……後で追加請求されそうだ。
「これをどこで手に入れた?」
「さあ? 私にもそれなりにツテはあります」
「……まあいいだろう。続けよ」
へえ? 喋らせてくれるんだ。植物に関してはそれぞれの場所を管理している庭師やらに聞けば裏は取れるから詮索の必要なしと判断したんだろうな。それじゃ、お話を続けましょうかね。
「公爵家が所有していない花が私の食事に入っていた、ということは誰かが持ち込んだことは明白です。そしてその持ち込んだ、あるいは持ち込むように指示した人物こそ、私に毒を盛り死に至らしめようとした犯人です」
「そうなるな。ここに描かれている料理人はその犯人の手下か」
「はい。もちろん直接の下手人はこの料理人ですがただの料理人が独断で公爵家の人間に毒を盛るとは思えない。背後に指示した人物がいます。証拠の方もーー」
「ちょっと待ちなさいよ!」
公爵に言われ今まで口は閉じていた夫人が割り込んできた。このタイミングで突っ込んでくるか。なんか言いたいことでもあるんですかね。
「なんでしょうか?」
「お前はさっきからこの絵から毒花の話をしているけど、この絵は一体なんなの? こんな都合よく絵があるなんておかしいわ。卑しいお前のことだからどうせ事件にしたくてわざと偽りの絵を描いたんでしょう。ここに描かれているのが本当にアクナイト公爵家の料理人かも怪しいわよ」
うん、一理ある。前世みたいに防犯カメラがあるわけじゃないし、それに近しい魔道具ならあるけど、我が家の厨房には置かれていない。だとすれば過去のことなど記録しようがないから、でっち上げだと思うのは自然なことだ。しかしこの絵を持ってきた時点でその質問が飛んでくることは予想済みだった。でなければこんなもの危なっかしくて証拠には出せない。
「厨房には魔道具を置いていないから過去を記録することは不可能。だからこれは私が犯人を陥れるために描いたまやかしだと、夫人は仰りたいのですね」
「そうよ。わかっているじゃない。過去を知るには『写実の水晶』が必要よ。でもあそこにそんな水晶は置いていないわ。ならでっち上げだと考えるのが自然ではなくて? ねえ、あなたもそう思うでしょう?」
公爵を巻き込んだか。すぐ公爵に擦り寄ろうとするところ、何年経っても変わらないな。まるで虎の威を借る狐だ。だけど、夫人の言葉には納得できる要素しかない。これには公爵も頷いた。
「アマラの言う通りだな。そんなものは置いていないはずだ。それはどう説明する?」
「それに関しましては、本人に説明させるのが早いかと」
「どういう意味だ」
公爵が眉を顰めると同時に室内にノックが響き渡る。
「なんだ」
「お話中のところ失礼致します。サリクスでございます」
「……シュヴァリエの侍従がなんの用だ」
「御二方の疑問に対する答えですよ。どうか入れて差し上げてください」
「…………入れ」
しばしの間の後、許可が下り入ってきたのは俺の専属侍従のサリクスとあと二人。件の馬鹿、もといロベリアをサラダに入れた料理人のファボルとサリクスの上司でアクナイト公爵家の侍従長ダズルだった。
「ダズル? なぜお前がここにいる」
「私がお願いしたのです。我が専属侍従の証人になってもらいたいと。サリクスだけでは口裏を合わせていると言われかねなかったもので」
「一体なんの証人だ?」
「それは……」
一瞬サリクスに視線を向け、微かに目で頷いたことを確認する。本当はこんな初っ端に明かしたくなかったんだけど、必要なことだったし、公爵という立場上知っていても損はないだろう。それにサリクスの能力は使い勝手がいい。黙秘した罪人の尋問やら証拠探しやらにめちゃくちゃ便利だ。サリクスの雇い主は公爵であって俺じゃないから公爵という立場から命じられれば使用人であるサリクスには断りようがない。
「サリクスの魔法は無属性魔法で能力は実写です。彼は『写実の水晶』と同じ能力を持っています」
案の定公爵夫妻の表情がガラリと変わりサリクスへと驚愕の視線を向けた。ですよね! 何その反則の技。使いようによってめちゃくちゃ怖い能力を持つ人間がそばにいたことに今まで気づかなかったわけだ。そりゃ驚愕もするよな~……。驚愕の理由は公爵と夫人で違うみたいだけど。
「それは真実か?」
「嘘ではございません。そうだろダズル?」
俺は後ろに控えているダズルに視線を向けた。ダズルは一歩踏み出すと公爵と夫人に一礼をする。
「旦那様、発言をお許しいただけますか」
「ああ、申せ」
「ありがとうございます。サリクスの能力に関してですが、このダズル・グラジオスの名において保証いたします」
「お前は知っていたのだな」
「はい。申し訳ございません」
「よい。無属性持ちの場合、本人の了承なしに能力を明かすことは許されていない。よって不問とする」
「寛大なお言葉ありがとうございます」
今、公爵がサラッと言ったけど、この世界では無属性を持って生まれた人間はその能力を他人に秘さなければいけないという制約がある。本人の同意なしに能力を明かすことはタブーとされ、その場合は他人にバラした者には呪いがかけられるというよくわからないシステムがあるのだ。ちなみにその理由は明かされていない。ただゲームの設定資料集に記述があった。運営さん方はなんでこんな意味不明な設定作ったんだか。
「侍従長がお認めになったことで、納得していただけましたでしょうか」
「……ああ。そんな能力があると知っていればお前にはつけなかったんだが」
はいはい、言ってくれるじゃねえかよ。俺は便利に使わせてもらっていますけどね。それに能力なんか関係なく俺はサリクスを信頼している。そう簡単に手放しはしない。
「……ひとまず、この絵の信憑性も確立されたと思います。夫人もこれでよろしいでしょうか」
「……侍従長を出してくるなんて本当に腹立たしいわね」
今にも歯軋りをしそうなほど悔しげな顔で睨む夫人に俺は内心ニヤリと笑う。まだまだこれからなのに今からそんな調子で大丈夫かな~?
「……さて、役者が揃ったことで、続きを始めましょうか」
723
あなたにおすすめの小説


結婚十年目の夫から「結婚契約更新書」なるものが届いた。彼は「送り間違えた」というけれど、それはそれで問題なのでは?
ぽんた
恋愛
レミ・マカリスター侯爵夫人は、夫と政略結婚をして十年目。侯爵夫人として、義父母の介護や領地経営その他もろもろを完ぺきにこなしている。そんなある日、王都に住む夫から「結婚契約更新書」なるものが届いた。義弟を通じ、夫を追求するも夫は「送り間違えた。ほんとうは金を送れというメモを送りたかった」という。レミは、心から思った。「それはそれで問題なのでは?」、と。そして、彼女の夫にたいするざまぁがはじまる。
※ハッピーエンド確約。ざまぁあり。ご都合主義のゆるゆる設定はご容赦願います。

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。
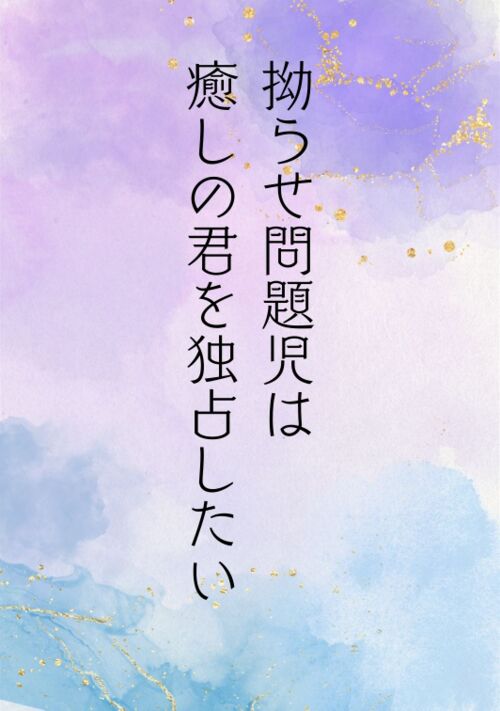
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
-----------------------------------------
0時,6時,12時,18時に2話ずつ更新
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















