16 / 140
一頁 覚醒のロベリア
シュヴァリエの本性(side アクナイト公爵)
しおりを挟む
書斎に戻った私はしばらく言葉が出なかった。先ほどのやり取りが頭にこびりついて離れない。
♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎
シュヴァリエは私がまだ爵位を継いで間もない頃に、ある貴族の夜会であてがわれた接待係の娘との間に生まれた。私はあの娘を抱くつもりは全くなく、名前すら知らない。しかし当時は国が少々ゴタついており、自然と貴族同士の関係強化の気風が高まっていた。もちろんそれはアクナイトも例外ではなかった。むしろ公爵家が筆頭となって各派閥内で動いていたのだ。公爵になりたてであった私の足場が不安定だったことと、相手の貴族がアクナイト公爵家と古くから付き合いのある家だったということもあり、断りきれずやむなく娘を抱いた。しかしまさか身籠るとは思わなかった。数年経った後でそのことを知り、悩んだ挙句に私は引き取ることにした。腐ってもアクナイトの血が入っている人間を他家に置いておくわけにもいくまい。
引き取ったばかりの頃のシュヴァリエは子どものくせにひどくつまらない存在で、私もさして興味は抱かなかった。すでにシエルを授かっていたこともあるが、何よりも好きで抱いたわけでもない女が勝手に孕んだ子をかわいいと思えるはずもなく、鬱陶しいとさえ感じていた私は極力関わらないよう過ごしていた。そのシュヴァリエはなんとか私に気に入られようとしていたようだが、私にはひどく浅はかで愚かなこととしか思わなかった。私がお前を気にいることなどないというのに……なんと滑稽な。
先日、シュヴァリエが毒に倒れたという報告を聞いた時、私は情けないという思いしか湧かなかった。アクナイトの直系の血を引く人間は生まれつき高い毒耐性を持って生まれてくる。どれほどの猛毒にあたろうともほとんど効かないためアクナイトの人間には毒殺という手が通用しない、というのは周知の事実だった。しかしごく稀にアクナイトの血の引くにも関わらず耐性の弱い子が生まれてくることがあり、シュヴァリエはまさにその稀な人間だった。ただでさえその出自は厄介だというのに、アクナイトの特徴も霞んでいるとは……。私はこの時、シュヴァリエを引き取ったことを後悔した。
……しかし、まさかこんなことになろうとは。
今日唐突にシュヴァリエが執務室を訪れ、アマラとその筆頭侍女を呼べと言い出した。いきなり何を言い出すのか、そもそもお前が私に何かを要求できるとでも思っているのか。身の程を弁えないその行動に蔑みが込み上げるが、なぜか私は了承してしまった。普段ならばあり得ないが、シュヴァリエに対していつもと違うと感じてしまったからだろうか。奇妙な心地を覚えながらも私はアマラとシエンナを呼び出した。
そこからはシュヴァリエの独壇場だった。淡々と紡がれる言葉といっそ不気味さを覚えるほどの詳細が記載された書類に私は自分の目の前で起こっていることを呑み込めずにいた。カルからの情報という話を聞けば納得はしたが、同時に私が知らないうちにカルと接点を持っていたとに動揺すら覚えてしまった。何よりも一番私を驚かせたのは私たちに対するシュヴァリエの態度だ。これまでずっと私たちの怒りに触れないよう、あるいは私に気に入られようと顔色を伺うような態度しか取ってこなかったはずだったが、報告を行うシュヴァリエは目に光を宿し、アマラを追い詰めていた。息子ではないと言った言葉は本心だったが、シュヴァリエも私への目つきが変わっていることに気づいた。
……だが、そんなことはどうでも良くなるような事態が私に起こった。
シュヴァリエが執務室でていく直前に、渡し忘れたと言って寄越した厚い茶封筒。まさかこんなものまで手に入れていたとは……! これが表に出ようものなら私は終わりだ。そう思った時にはもう体が動いていた。貴族としての矜持や気品などもはやどうでもいい。一刻も早くシュヴァリエの元へ行かなければ……!
焦燥に駆られる中、乱暴に部屋の扉を開けた先ではーーシュヴァリエとサリクスが碌でもない状況でソファの上にいた。一瞬自分の目的を忘れその場に固まってしまった。
ーー……何をやっているんだ。
どうにかそれだけ絞り出す。
ーー事故ですお気になさらず。
どういう事故だそれは。しれっとした顔で言うことかと思いながらも紅茶で濡れたテーブルと床が目に入り、状況を悟る。アクナイトの使用人ともあろう人間が何をやっているんだ。
サリクスにすぐさま片付けさせた部屋で私はシュヴァリエと向かい合った。憤りを覚える私にシュヴァリエは何の用かと厚かましくも聞いてきた。用事など判りきっているだろうに、さっきの出来事を思うとわざと言っているように思えてならん。しかもあろうことか贈り物とのたまった。毒にやられて随分と命知らずになったものだ。
……などと思ったのも束の間。シュヴァリエの言葉に私はもはや目上という立場を完全に封じられてしまった。アマラやシエル、ルアルにバラされるだけでも耐え難いというのに、よりにもよって国中にバラすと言ってきたのだ。カルとあっさり取引をしたことといい、すでに手筈も済んでいる可能性がある以上こちらにできるのはシュヴァリエに従うという道しかない。内臓どころか己の体全てが今にも燃え出してしまいそうなほどの怒りを覚えると同時に、あまりのシュヴァリエの変わりぶりにほんの少しの寒さを感じた。今目の前で私を脅しているのは一体誰なのだ、と。
不気味さが胸の奥に燻り始めた私に気づかずシュヴァリエは自分の望みを伝えてきた。だがその内容はいささか拍子抜けするものだった。私の最大の黒歴史を握ったのだからもう少し大それた願いかと思ったのだが。
しかしその理由を言われた時、私は身の程知らずだと心底思った。思いはしたが私の命運はシュヴァリエに握られてしまっている。聞き入れる以外の選択はない。……が。シュヴァリエの二つ目の願いに私は理解が追いつかなかった。
ーー私の趣味を妨害しないでください。むしろこっちが本命です。
何を言っているんだこいつは。自分の扱いのことよりも趣味の方が大事だと? 全くもって意味がわからん。しかもその趣味とやらが花集めときた。仮にもアクナイトの人間あろうものがそんなものに現を抜かすとは。など思って口にした言葉にシュヴァリエが少々声を荒げた。あまりの態度の変わりぶりに私は情けなくも少々たじろいでしまった。……そこまでその趣味が大事なのかお前は。
軽蔑は呆れへと変わり、渋々だが条件を受け入れることにしたのだが。
ーー夫人の部屋に置いているロベリアの花を私にください。
早速要求してきた内容に私は思考が停止した。命を奪いかけた花をよりにもよって欲しいとは、一体どういう思考回路をしていたらそんな言葉が出てくるのか。問えば趣味だと言う。
……。
こいつ実は相当の馬鹿ではなかろうか。しかも二回言った。シュヴァリエの発する奇妙な内容に私は先ほどの不気味さが確信に変わった。そして気づけば言葉が勝手に出ていた。お前本当にシュヴァリエか、と。そんな私の問いにシュヴァリエは心底楽しそうな笑顔で言った。いつもの私だと。
♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎
「はあ……」
少し頭を整理するために、私は椅子に深く腰掛け目を閉じる。
「いつもの私です、か……」
シュヴァリエの言葉を反芻する。私に気に入られようと顔色を窺う姿、怯えを滲ませた目。そしてつまらない言動。あれは全て偽りだったと、そう言う意味だろう。今日のシュヴァリエは光を宿した目でまっすぐ視線を合わせ、楽しそうにアマラを、そして私を追い詰める、あんな姿を私は知らない。…………いや、知らないのではなく知ろうとしなかった、が正しいか。アクナイトの特徴らしい特徴を受け継いでいない彼奴の気概はもしかしたら誰よりもアクナイトの血が濃いのではないだろうか。
そう思うと同時に私はシュヴァリエの一つ目の条件の理由に思い至る。
ーーアクナイトの姓を名乗ることを許したのにあの扱いは……はっきり言って矛盾しているかと。
…………なるほど、な。確かに私はシュヴァリエにアクナイトを名乗ることを許した。だが屋敷内での扱いがその姓に相応しいものだったかと考えれば微妙なところだ。部屋を与え金を与え学園にも通わせてやったにも関わらず、身の程も弁えずこれ以上何を望むのかと一種の軽蔑を抱いたが、それはすぐさま否定する。身の程知らずだと、強欲な奴だと思うのは私がシュヴァリエを使用人と同等に扱っているからではないか。アクナイトは公爵家。王家に次ぐ権力を有した家であり、王族との婚姻も度々行われる家だ。そんな家の姓を名乗っているのならば、扱いがそこらの使用人と同じでいいはずがない。使用人には不相応なものでもアクナイトの人間は持っていて当たり前のものだ。
思えば私はシュヴァリエを一度もパーティーなど社交の場に連れて行ったことがない。何かと理由をつけて参加させていなかった。社交の場に出させない。それだけで私のシュヴァリエに対する思いの現れだったのだ。……確かに矛盾している。シュヴァリエの出自がどれほど卑しくとも、それでも彼奴にアクナイトを与えたのは、他でもないこの私だ。
そこまで考えて私は自分がいかに愚かだったかを思い知った。私はアクナイト公爵家の体面を保つことしか考えていなかったが、そもそもが中途半端だったのだな。そのことを他でもないシュヴァリエに教えられるとは……なんと滑稽な。
だが、今更思い立ったところで何になるというのか。いくら反省し懺悔しようとも私のこれまでは変えられない。加えてシュヴァリエの口からはっきりと父ではないと言われたというのに。シュヴァリエのことをアクナイトの名を穢す存在と思っていたが、一番穢していたのは他でもないこの私だった。
父上、貴方はいつも私に言っておりましたね。お前は中途半端だ、アクナイトの信念を、心を何一つ理解していない、と。その言葉の意味が今ようやくわかった気がします。私はこれからシュヴァリエにどう接していけばよいのでしょう。
問いかけても意味のないことと思いながら、私は深くため息をついた。
……まずはシュヴァリエの望み通り、ダズルにロベリアの花を届けさせるか。彼奴の直近の願いはそこだからな。……今だ理解はできないが。
「ダズル」
「はい旦那様」
私の呼びかけにすぐさま反応し姿を見せたダズルにシュヴァリエの願いを伝える。
「アマラの部屋にあるらしいロベリアの花を今すぐにシュヴァリエの元へ届けろ」
「……承知しましたが、何故?」
「……シュヴァリエの希望だ」
「……失礼を承知で申し上げますが、あの花はシュヴァリエ坊っちゃまのお命を危険に晒した花だと思うのですが」
「アイツの思考回路など知らん。ただ欲しいと言っていた。どうせ捨てるのなら欲しがっている人間に持っていけ」
「かしこまりました。ですが、随分とシュヴァリエ様への態度が変わられましたな」
……ダズルは昔からアクナイトにいる古参中の古参だ。使用人でありながら父の歳離れた友人でもあったこの男には幼少期から何かと世話になり、今でも時折説教を食らうことがある。そんなダズルが、心底面白そうにこちらを見ていた。……此奴が笑っている様は実に気持ち悪い。
「あんなもので脅されてはな」
「おやおや、貴方が目を離している間にシュヴァリエ坊っちゃまは己の毒の調合を続けていらしたようですな。いやはや若者の成長というのは誠に早うございます」
「ニヤニヤするな、古狸が」
「古狸とは面白いですな」
相変わらず胡散臭い男だ。
だが、こんな男だからこそ聞いてみたいことがあった。
「……お前はシュヴァリエをどう思う?」
「……そうですね。綺麗な花には毒がある、を体現なさっている方と申しましょうか」
それは先ほどご自分で体験なさったかと思いますよ、と清々しい笑顔で言ってきたダズルに腹が立つが、実際その通りだった。
「いつからだ?」
「シュヴァリエ坊っちゃまのことにいつから気づいていたのか、というご質問でしたら、最初からでございますよ。伊達に歳を重ねておりません」
「……そうか」
「ですがずっと土の中にお隠れになっておりましたので、ようやっと芽を出してくださって非常に喜ばしく思います」
「ニヤニヤするな、古狸」
「これは失敬。今だ成長しておらぬどこかの甘えん坊も無事一皮剥けられて、二重の喜びが込み上げてしまいました」
……この男は本当に口が減らん。そろそろ引退してもいいと思うのだが。
「……それからアマラに何か見繕え。最後の土産くらいはくれてやる」
「それもシュヴァリエ坊っちゃまのご提案で?」
「……そうだ」
「なるほど。そういえば奥様は新しい靴が欲しいと仰っておりましたので、そちらでよろしいでしょうか」
「好きにしろ。靴にするなら色は赤だ」
「……この国における赤い靴の意味するものを承知の上でお送りなさるとは」
諌めるような言葉も何処か楽しげな古狸に私は顔を顰める。
「さっさと行け」
「はい旦那様」
一礼をしてさっさと書斎を後にした古狸に思わず舌打ちが出る。アクナイトの古狸は随分とご機嫌だった。アレにこき使われる使用人連中が哀れでならん。
しかしあのダズルがシュヴァリエのことを評価していたことに驚きを隠せない。古狸が評価しているということはシュヴァリエの能力が本物であり……相当の曲者だという証明だ。シュヴァリエにはダズルに気に入られる何かがあるということか。
……。
「………………嫌な予感がする」
私は己の予感が当たらないことを心の底から願った。
・・・・・・・・・・・
次回から『二頁 アジサイの涙』が始まります。お楽しみに♪
♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎
シュヴァリエは私がまだ爵位を継いで間もない頃に、ある貴族の夜会であてがわれた接待係の娘との間に生まれた。私はあの娘を抱くつもりは全くなく、名前すら知らない。しかし当時は国が少々ゴタついており、自然と貴族同士の関係強化の気風が高まっていた。もちろんそれはアクナイトも例外ではなかった。むしろ公爵家が筆頭となって各派閥内で動いていたのだ。公爵になりたてであった私の足場が不安定だったことと、相手の貴族がアクナイト公爵家と古くから付き合いのある家だったということもあり、断りきれずやむなく娘を抱いた。しかしまさか身籠るとは思わなかった。数年経った後でそのことを知り、悩んだ挙句に私は引き取ることにした。腐ってもアクナイトの血が入っている人間を他家に置いておくわけにもいくまい。
引き取ったばかりの頃のシュヴァリエは子どものくせにひどくつまらない存在で、私もさして興味は抱かなかった。すでにシエルを授かっていたこともあるが、何よりも好きで抱いたわけでもない女が勝手に孕んだ子をかわいいと思えるはずもなく、鬱陶しいとさえ感じていた私は極力関わらないよう過ごしていた。そのシュヴァリエはなんとか私に気に入られようとしていたようだが、私にはひどく浅はかで愚かなこととしか思わなかった。私がお前を気にいることなどないというのに……なんと滑稽な。
先日、シュヴァリエが毒に倒れたという報告を聞いた時、私は情けないという思いしか湧かなかった。アクナイトの直系の血を引く人間は生まれつき高い毒耐性を持って生まれてくる。どれほどの猛毒にあたろうともほとんど効かないためアクナイトの人間には毒殺という手が通用しない、というのは周知の事実だった。しかしごく稀にアクナイトの血の引くにも関わらず耐性の弱い子が生まれてくることがあり、シュヴァリエはまさにその稀な人間だった。ただでさえその出自は厄介だというのに、アクナイトの特徴も霞んでいるとは……。私はこの時、シュヴァリエを引き取ったことを後悔した。
……しかし、まさかこんなことになろうとは。
今日唐突にシュヴァリエが執務室を訪れ、アマラとその筆頭侍女を呼べと言い出した。いきなり何を言い出すのか、そもそもお前が私に何かを要求できるとでも思っているのか。身の程を弁えないその行動に蔑みが込み上げるが、なぜか私は了承してしまった。普段ならばあり得ないが、シュヴァリエに対していつもと違うと感じてしまったからだろうか。奇妙な心地を覚えながらも私はアマラとシエンナを呼び出した。
そこからはシュヴァリエの独壇場だった。淡々と紡がれる言葉といっそ不気味さを覚えるほどの詳細が記載された書類に私は自分の目の前で起こっていることを呑み込めずにいた。カルからの情報という話を聞けば納得はしたが、同時に私が知らないうちにカルと接点を持っていたとに動揺すら覚えてしまった。何よりも一番私を驚かせたのは私たちに対するシュヴァリエの態度だ。これまでずっと私たちの怒りに触れないよう、あるいは私に気に入られようと顔色を伺うような態度しか取ってこなかったはずだったが、報告を行うシュヴァリエは目に光を宿し、アマラを追い詰めていた。息子ではないと言った言葉は本心だったが、シュヴァリエも私への目つきが変わっていることに気づいた。
……だが、そんなことはどうでも良くなるような事態が私に起こった。
シュヴァリエが執務室でていく直前に、渡し忘れたと言って寄越した厚い茶封筒。まさかこんなものまで手に入れていたとは……! これが表に出ようものなら私は終わりだ。そう思った時にはもう体が動いていた。貴族としての矜持や気品などもはやどうでもいい。一刻も早くシュヴァリエの元へ行かなければ……!
焦燥に駆られる中、乱暴に部屋の扉を開けた先ではーーシュヴァリエとサリクスが碌でもない状況でソファの上にいた。一瞬自分の目的を忘れその場に固まってしまった。
ーー……何をやっているんだ。
どうにかそれだけ絞り出す。
ーー事故ですお気になさらず。
どういう事故だそれは。しれっとした顔で言うことかと思いながらも紅茶で濡れたテーブルと床が目に入り、状況を悟る。アクナイトの使用人ともあろう人間が何をやっているんだ。
サリクスにすぐさま片付けさせた部屋で私はシュヴァリエと向かい合った。憤りを覚える私にシュヴァリエは何の用かと厚かましくも聞いてきた。用事など判りきっているだろうに、さっきの出来事を思うとわざと言っているように思えてならん。しかもあろうことか贈り物とのたまった。毒にやられて随分と命知らずになったものだ。
……などと思ったのも束の間。シュヴァリエの言葉に私はもはや目上という立場を完全に封じられてしまった。アマラやシエル、ルアルにバラされるだけでも耐え難いというのに、よりにもよって国中にバラすと言ってきたのだ。カルとあっさり取引をしたことといい、すでに手筈も済んでいる可能性がある以上こちらにできるのはシュヴァリエに従うという道しかない。内臓どころか己の体全てが今にも燃え出してしまいそうなほどの怒りを覚えると同時に、あまりのシュヴァリエの変わりぶりにほんの少しの寒さを感じた。今目の前で私を脅しているのは一体誰なのだ、と。
不気味さが胸の奥に燻り始めた私に気づかずシュヴァリエは自分の望みを伝えてきた。だがその内容はいささか拍子抜けするものだった。私の最大の黒歴史を握ったのだからもう少し大それた願いかと思ったのだが。
しかしその理由を言われた時、私は身の程知らずだと心底思った。思いはしたが私の命運はシュヴァリエに握られてしまっている。聞き入れる以外の選択はない。……が。シュヴァリエの二つ目の願いに私は理解が追いつかなかった。
ーー私の趣味を妨害しないでください。むしろこっちが本命です。
何を言っているんだこいつは。自分の扱いのことよりも趣味の方が大事だと? 全くもって意味がわからん。しかもその趣味とやらが花集めときた。仮にもアクナイトの人間あろうものがそんなものに現を抜かすとは。など思って口にした言葉にシュヴァリエが少々声を荒げた。あまりの態度の変わりぶりに私は情けなくも少々たじろいでしまった。……そこまでその趣味が大事なのかお前は。
軽蔑は呆れへと変わり、渋々だが条件を受け入れることにしたのだが。
ーー夫人の部屋に置いているロベリアの花を私にください。
早速要求してきた内容に私は思考が停止した。命を奪いかけた花をよりにもよって欲しいとは、一体どういう思考回路をしていたらそんな言葉が出てくるのか。問えば趣味だと言う。
……。
こいつ実は相当の馬鹿ではなかろうか。しかも二回言った。シュヴァリエの発する奇妙な内容に私は先ほどの不気味さが確信に変わった。そして気づけば言葉が勝手に出ていた。お前本当にシュヴァリエか、と。そんな私の問いにシュヴァリエは心底楽しそうな笑顔で言った。いつもの私だと。
♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎
「はあ……」
少し頭を整理するために、私は椅子に深く腰掛け目を閉じる。
「いつもの私です、か……」
シュヴァリエの言葉を反芻する。私に気に入られようと顔色を窺う姿、怯えを滲ませた目。そしてつまらない言動。あれは全て偽りだったと、そう言う意味だろう。今日のシュヴァリエは光を宿した目でまっすぐ視線を合わせ、楽しそうにアマラを、そして私を追い詰める、あんな姿を私は知らない。…………いや、知らないのではなく知ろうとしなかった、が正しいか。アクナイトの特徴らしい特徴を受け継いでいない彼奴の気概はもしかしたら誰よりもアクナイトの血が濃いのではないだろうか。
そう思うと同時に私はシュヴァリエの一つ目の条件の理由に思い至る。
ーーアクナイトの姓を名乗ることを許したのにあの扱いは……はっきり言って矛盾しているかと。
…………なるほど、な。確かに私はシュヴァリエにアクナイトを名乗ることを許した。だが屋敷内での扱いがその姓に相応しいものだったかと考えれば微妙なところだ。部屋を与え金を与え学園にも通わせてやったにも関わらず、身の程も弁えずこれ以上何を望むのかと一種の軽蔑を抱いたが、それはすぐさま否定する。身の程知らずだと、強欲な奴だと思うのは私がシュヴァリエを使用人と同等に扱っているからではないか。アクナイトは公爵家。王家に次ぐ権力を有した家であり、王族との婚姻も度々行われる家だ。そんな家の姓を名乗っているのならば、扱いがそこらの使用人と同じでいいはずがない。使用人には不相応なものでもアクナイトの人間は持っていて当たり前のものだ。
思えば私はシュヴァリエを一度もパーティーなど社交の場に連れて行ったことがない。何かと理由をつけて参加させていなかった。社交の場に出させない。それだけで私のシュヴァリエに対する思いの現れだったのだ。……確かに矛盾している。シュヴァリエの出自がどれほど卑しくとも、それでも彼奴にアクナイトを与えたのは、他でもないこの私だ。
そこまで考えて私は自分がいかに愚かだったかを思い知った。私はアクナイト公爵家の体面を保つことしか考えていなかったが、そもそもが中途半端だったのだな。そのことを他でもないシュヴァリエに教えられるとは……なんと滑稽な。
だが、今更思い立ったところで何になるというのか。いくら反省し懺悔しようとも私のこれまでは変えられない。加えてシュヴァリエの口からはっきりと父ではないと言われたというのに。シュヴァリエのことをアクナイトの名を穢す存在と思っていたが、一番穢していたのは他でもないこの私だった。
父上、貴方はいつも私に言っておりましたね。お前は中途半端だ、アクナイトの信念を、心を何一つ理解していない、と。その言葉の意味が今ようやくわかった気がします。私はこれからシュヴァリエにどう接していけばよいのでしょう。
問いかけても意味のないことと思いながら、私は深くため息をついた。
……まずはシュヴァリエの望み通り、ダズルにロベリアの花を届けさせるか。彼奴の直近の願いはそこだからな。……今だ理解はできないが。
「ダズル」
「はい旦那様」
私の呼びかけにすぐさま反応し姿を見せたダズルにシュヴァリエの願いを伝える。
「アマラの部屋にあるらしいロベリアの花を今すぐにシュヴァリエの元へ届けろ」
「……承知しましたが、何故?」
「……シュヴァリエの希望だ」
「……失礼を承知で申し上げますが、あの花はシュヴァリエ坊っちゃまのお命を危険に晒した花だと思うのですが」
「アイツの思考回路など知らん。ただ欲しいと言っていた。どうせ捨てるのなら欲しがっている人間に持っていけ」
「かしこまりました。ですが、随分とシュヴァリエ様への態度が変わられましたな」
……ダズルは昔からアクナイトにいる古参中の古参だ。使用人でありながら父の歳離れた友人でもあったこの男には幼少期から何かと世話になり、今でも時折説教を食らうことがある。そんなダズルが、心底面白そうにこちらを見ていた。……此奴が笑っている様は実に気持ち悪い。
「あんなもので脅されてはな」
「おやおや、貴方が目を離している間にシュヴァリエ坊っちゃまは己の毒の調合を続けていらしたようですな。いやはや若者の成長というのは誠に早うございます」
「ニヤニヤするな、古狸が」
「古狸とは面白いですな」
相変わらず胡散臭い男だ。
だが、こんな男だからこそ聞いてみたいことがあった。
「……お前はシュヴァリエをどう思う?」
「……そうですね。綺麗な花には毒がある、を体現なさっている方と申しましょうか」
それは先ほどご自分で体験なさったかと思いますよ、と清々しい笑顔で言ってきたダズルに腹が立つが、実際その通りだった。
「いつからだ?」
「シュヴァリエ坊っちゃまのことにいつから気づいていたのか、というご質問でしたら、最初からでございますよ。伊達に歳を重ねておりません」
「……そうか」
「ですがずっと土の中にお隠れになっておりましたので、ようやっと芽を出してくださって非常に喜ばしく思います」
「ニヤニヤするな、古狸」
「これは失敬。今だ成長しておらぬどこかの甘えん坊も無事一皮剥けられて、二重の喜びが込み上げてしまいました」
……この男は本当に口が減らん。そろそろ引退してもいいと思うのだが。
「……それからアマラに何か見繕え。最後の土産くらいはくれてやる」
「それもシュヴァリエ坊っちゃまのご提案で?」
「……そうだ」
「なるほど。そういえば奥様は新しい靴が欲しいと仰っておりましたので、そちらでよろしいでしょうか」
「好きにしろ。靴にするなら色は赤だ」
「……この国における赤い靴の意味するものを承知の上でお送りなさるとは」
諌めるような言葉も何処か楽しげな古狸に私は顔を顰める。
「さっさと行け」
「はい旦那様」
一礼をしてさっさと書斎を後にした古狸に思わず舌打ちが出る。アクナイトの古狸は随分とご機嫌だった。アレにこき使われる使用人連中が哀れでならん。
しかしあのダズルがシュヴァリエのことを評価していたことに驚きを隠せない。古狸が評価しているということはシュヴァリエの能力が本物であり……相当の曲者だという証明だ。シュヴァリエにはダズルに気に入られる何かがあるということか。
……。
「………………嫌な予感がする」
私は己の予感が当たらないことを心の底から願った。
・・・・・・・・・・・
次回から『二頁 アジサイの涙』が始まります。お楽しみに♪
827
あなたにおすすめの小説

結婚十年目の夫から「結婚契約更新書」なるものが届いた。彼は「送り間違えた」というけれど、それはそれで問題なのでは?
ぽんた
恋愛
レミ・マカリスター侯爵夫人は、夫と政略結婚をして十年目。侯爵夫人として、義父母の介護や領地経営その他もろもろを完ぺきにこなしている。そんなある日、王都に住む夫から「結婚契約更新書」なるものが届いた。義弟を通じ、夫を追求するも夫は「送り間違えた。ほんとうは金を送れというメモを送りたかった」という。レミは、心から思った。「それはそれで問題なのでは?」、と。そして、彼女の夫にたいするざまぁがはじまる。
※ハッピーエンド確約。ざまぁあり。ご都合主義のゆるゆる設定はご容赦願います。

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。
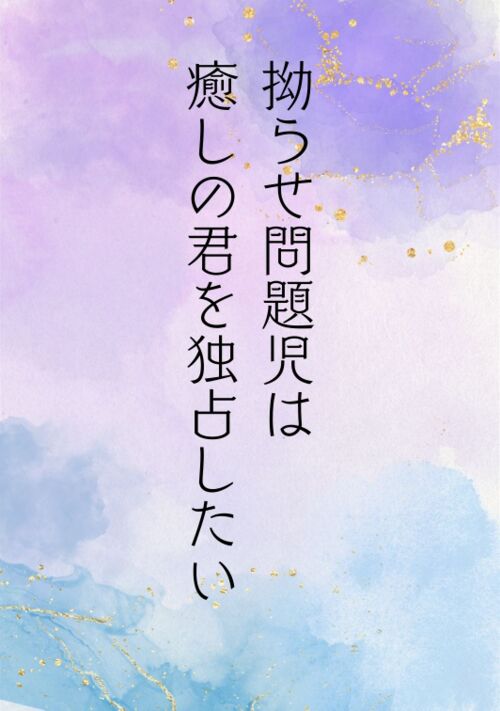
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

売れ残りオメガの従僕なる日々
灰鷹
BL
王弟騎士α(23才)× 地方貴族庶子Ω(18才)
※ 第12回BL大賞では、たくさんの応援をありがとうございました!
ユリウスが暮らすシャマラーン帝国では、平民のオメガは18才になると、宮廷で開かれる選定の儀に参加することが義務付けられている。王族の妾となるオメガを選ぶためのその儀式に参加し、誰にも選ばれずに売れ残ったユリウスは、国王陛下から「第3王弟に謀反の疑いがあるため、身辺を探るように」という密命を受け、オメガ嫌いと噂される第3王弟ラインハルトの従僕になった。
無口で無愛想な彼の優しい一面を知り、任務とは裏腹にラインハルトに惹かれていくユリウスであったが、働き始めて3カ月が過ぎたところで第3王弟殿下が辺境伯令嬢の婿養子になるという噂を聞き、従僕も解雇される。

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
-----------------------------------------
0時,6時,12時,18時に2話ずつ更新

『外見しか見なかったあなたへ。私はもう、選ぶ側です』
鷹 綾
恋愛
「お前のようなガキは嫌いだ」
幼く見える容姿を理由に、婚約者ライオネルから一方的に婚約を破棄された
公爵令嬢シルフィーネ・エルフィンベルク。
その夜、嫉妬に狂った伯爵令嬢に突き落とされ、
彼女は一年もの間、意識不明の重体に陥る――。
目を覚ました彼女は、大人びた美貌を手に入れていた。
だが、中身は何ひとつ変わっていない。
にもかかわらず、
かつて彼女を「幼すぎる」と切り捨てた元婚約者は態度を一変させ、
「やり直したい」とすり寄ってくる。
「見かけが変わっても、中身は同じです。
それでもあなたは、私の外見しか見ていなかったのですね?」
静かにそう告げ、シルフィーネは過去を見限る。
やがて彼女に興味を示したのは、
隣国ノルディアの王太子エドワルド。
彼が見ていたのは、美貌ではなく――
対話し、考え、異論を述べる彼女の“在り方”だった。
これは、
外見で価値を決められた令嬢が、
「選ばれる人生」をやめ、
自分の意思で未来を選び直す物語。
静かなざまぁと、
対等な関係から始まる大人の恋。
そして――
自分の人生を、自分の言葉で生きるための物語。
---
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















