5 / 6
第五話 癒しの処方箋
しおりを挟む
「……療養、食?」
白石さんは目を瞬かせ、手元の皿を見た。
「えっ……えっ!?これ、病人食なんですか!?うそーっ!」
プディングと亜嵐さんの顔を交互に見遣る彼女の発言に、俺も激しく同意する。
「だって病気の人の食事っていったら、『あれはダメ、これもダメ、これならギリ食べていい』って感じじゃないですか!こんな美味しいデザートを食べていいなんて……信じられないっ!」
確かにその通りだ。
臨床栄養学の献立作成でも、『使えない食材』を避けつついかに満足感を出すか――それが最大の難問だった。
糖尿病なら総カロリーと糖質の管理、腎臓病ならナトリウムとカリウムの制限。
どんな食事を作るにしても制限ばかりが先に立ち、食の楽しさは後回しになる。
「亜嵐さん。サマープディングって、どんな病態の患者さん向けなんですか?」
「ふむ。良いところに気づいたな、湊」
亜嵐さんは軽く頷き、ナプキンの端を指先で整えると、ゆっくり語り始めた。
「時代は十九世紀、ヴィクトリア朝のイギリスだ。
産業革命で豊かになった人々は、それまでにない『飽食の時代』を迎えた。バターやクリーム、砂糖をふんだんに使った高カロリーな料理を楽しめるようになった。
だが――やがて彼らは、その代償を支払うことになる。
肥満や消化器の不調に悩まされ、温泉地や保養地での長い療養を余儀なくされた。当然、彼らの楽しみだったデザートとも、距離を置かねばならなくなった」
亜嵐さんは少し間を置いて、静かに続ける。
「しかし節制ほど難しいものはない。少しくらいならと隠れて、つい甘いものを食べてしまう。だがそれでは本末転倒だ。
そこで考案されたのが、この『サマープディング』だ。
リッチなペストリー生地の代わりにパンを使い、旬のベリーで自然な甘みを引き出した。砂糖を減らしても、風味はむしろ豊かになった。そして何より――美味かった。
やがてこの料理は療養食というカテゴリーを超えて、夏の定番デザートとして親しまれるようになったのだ」
気付けば俺たちは、亜嵐さんの語りにすっかり引き込まれていた。
白石さんはごくりと喉を鳴らすと、震える声で呟いた。
「もし……もし私が何かの病気で入院して、食事制限がつらくて、療養生活を苦しいと感じるようになったら。こんな美味しいデザートが出てきたらすごく嬉しいし、治療を続ける力になると思う」
その言葉に、亜嵐さんは確信の笑みを浮かべた。
「そうだとも、ミス・美緒。患者にとって治療とは、特別な時間ではなく『日常』なのだ。暮らしの中に彩りを見出したいのは、健康な者だけではない。むしろ病と向き合い、つらい治療を続ける者にこそ――それは希望の光となる」
希望の光――。
その言葉が、胸の奥で何かを打ち破った。
俺が小学生の頃、母は腎臓病を患った。
治療を続けても病状は改善せず、結局俺が高校に上がる前に母は亡くなった。
腎臓病の治療に、食事療法は欠かせない。
母も例外ではなく、厳しい制限の中で、それまで好きだった食べ物を口にできなくなっていった。
『真っ赤なイチゴが食べたいな……』
普段は弱音を吐かない母が、最後にこぼした一言。
あのときの俺は何もできずに泣くだけだったけれど、今ならわかる。
『真っ赤なイチゴ』こそ、母にとっての希望の光だったんだ。
「母さんが言いたかったことは、元気になってまたイチゴを食べたい――そういう意味だったと思うんです」
視界が滲み、熱いものが頬を伝う。
「食べ物って、栄養とかカロリーとか、そういう理屈じゃなくて……人の命の源であり、希望なんです。人は、食べるから生きられる。だから俺は――命を支える『食』を学びたくて、栄養士を目指したんです」
涙を拭いながら、必死に言葉を紡ぐ。
亜嵐さんは、そっと俺の背に手を置いた。
「湊……そうだったのか。君はもう、十分すぎるほど頑張っているとも」
「……っ、亜嵐、さんっ……!」
小さな嗚咽が、店内の静けさに溶けていく。
この想いを誰かに打ち明けるのは、これが初めてだ。父にも話したことはない。
苦しいなんて思ったことはない――そのはずだったけれど、それはただの強がりだった。
ふと顔を上げると、白石さんがじっとこちらを見つめていた。
その瞳は驚きと、温かい光を湛えていた。
(……まずい。こんな話をするつもりじゃなかったのに……)
ばつが悪くなって、乱暴に涙を拭う。
そんな俺に、白石さんは静かに言った。
「藤宮くん……私、間違ってた。ううん、今もね、ドクターと看護師と栄養士、それぞれの専門分野でチームを作る――その考えの根っこは変わらないよ。でも気付いたの。私たち看護師は、誰よりも患者さんに近い存在だわ。その看護師が、患者さんにとっての希望のひとつ――『食べること』に疎いなんて、あってはならないよね」
「白石さん……」
その声音は凛として、反省のほかに喜びの色を含んでいた。
「なんていうかね、栄養学って、患者さんを縛る鎖みたいなイメージだったの。でも本質は全然違うんだね。どうしたって生まれる制約の中で、どう楽しみをみつけるか――まるで宝物を探すような、素敵な分野なんだね!」
白石さんは太陽のような笑顔を浮かべた。
その言葉に、思わずこちらも笑顔になる。
(……宝探しか……)
自分が学んでいるものが、輝いているように感じられた。
うれしくて誇らしい。喜びがふつふつと湧き上がってくる。
「そんなふうに言ってもらえて、すごくうれしいな。俺、一生懸命勉強して、立派な栄養士になるよ!」
へへっと笑うと、亜嵐さんも白石さんも頷いてくれた。
「湊ならなれるさ」
「うん、絶対なれる!私が保証する!」
「白石さんもね。素敵な看護師さんになるよ、きっと」
わかり合えた温かさが、ゆったりと漂う。
――と、そのタイミングで、翠さんが銀色の盆を手にやってきた。
「みんな、体が冷えてきた頃でしょう?温かい紅茶をお持ちしましたよ」
白い小花が描かれたかわいらしいカップに、やさしい琥珀色の紅茶が注がれる。
立ち上る湯気がふわっと香って、全てが溶けていくようだ。
カップに口をつけた白石さんは、「はぁ…」と息を吐いた。
「この紅茶も、すっごく美味しいです。――藤宮くん、西園寺さん、翠さん。今日は本当にありがとうございました。私、目から鱗が落ちました。食卓の上に、こんなにも素敵な世界が広がっているなんて」
そう語る表情は、清々しく輝いている。
けれどすぐ、残念そうにテーブルを見た。
「しまったなぁ……二十年間、損してた気分だわ」
「あら。気づいたのなら、これから楽しめばいいだけじゃない?」
優しい声音で、翠さんが微笑む。
「そうだとも。それに『同じ食卓』とは、何も顔を突き合わせることだけを言うのではない。忙しくてなかなか揃わないご両親と、たとえ一緒にではなくとも、同じものを美味しいと感じられたら――それは立派な食卓といえる」
白石さんは「……そっか」と呟いて、パッと顔を上げた。
「翠さん!ここのケーキって、テイクアウトもやってますか?」
「ええ、もちろんよ。今日は三種類ご用意していますよ」
「三種類……え、どれにしよう。西園寺さん、ちょっと見てきていいですか?」
返答を待たず白石さんは立ち上がり、翠さんと一緒にショーケースへ向かった。
静かになったテーブルを前に、俺は亜嵐さんに向かい合う。
「亜嵐さん、改めて今日はありがとうございました」
「……意地悪ではない証明になったかな?」
片目を眇めて唇の端を上げる亜嵐さんに、思わずぷっと吹き出した。
「あれは……!本当にガールハントなんかじゃないし、それに亜嵐さんが意地悪だなんて、俺、これっぽっちも思ってませんよ!」
「冗談さ。――まあ、礼も必要ない。素晴らしいホットケーキを焼いてもらったからな。これくらいは当然のことだ」
(まったく……どこまでが本気なんだか)
でも俺は、これまでの短い付き合いの中でも、しっかり感じ取っている。
この人の言動の底には、いつも温かな思い遣りがあるのだと――。
そこへ、ケーキを選び終えた白石さんが戻ってきた。
「も~っ!どのケーキもすごく美味しそうなんだもん、迷っちゃったよ!」
その顔には、満面の笑みが浮かんでいる。
「どのケーキを選んでも、最高のティータイムを保証するとも」
「ですよね!オレンジのケーキもいいなぁって思ったけど、旬だからチェリーパイにしました。……えへへ、お父さんもお母さんも、喜んでくれるといいな」
「きっと喜んでくれるよ」
そして俺たちは色々おしゃべりをしながら、サマープディングと紅茶を楽しんだ。
***
「……ふむ、面白い。実に湊らしい発想だ」
「でも、問題は中に何を入れるかで……」
後日。
ローズメリーでお茶を飲みながら、亜嵐さんと話に興じていると。
チリン、チリン!
軽やかなベルの音とともに、颯爽とした足取りで店内に入ってくる人の姿。
「いらっしゃいませ――あら、美緒ちゃん」
「翠さん、こんにちは!」
爽やかな風のように現れたのは、白石さんだった。
しかしその姿は、いつものパンツスタイルではない。
元気な印象だったポニーテールは下ろされ、首筋で緩くまとめられている。
水色の花柄スカートはふわりと揺れ、レースの肩口が涼やかだ。
「まぁ、美緒ちゃん……素敵よ。とてもよく似合ってるわ」
「えへへ、ありがとうございます。この間は藤宮くんに『ドレスコードはない』って言われて信じちゃったけど。このお店に来るんだったら、やっぱり少しはおしゃれしないと!って思って」
しれっと引き合いに出されたが、これは軽い非難だろうか?
「あっ、藤宮くんと西園寺さん!こんにちは、会えて良かった」
とことこと近付いてきた白石さんは、挨拶もそこそこに、ぺこりと頭を下げた。
「あの日――やっぱり一緒には食べられなかったけど、父も母もチェリーパイをすごく喜んでくれました。疲れが吹き飛ぶって。西園寺さんが言った通りでした。本当にありがとうございました!」
「頭を上げたまえ、ミス・美緒。ご両親が喜んだのは、そこに君の思い遣りがあったからだ」
優しく言葉を紡ぐ亜嵐さんを見て、俺の胸はほっこりと温かくなった。
頭を上げた白石さんは、キラキラと光る瞳で亜嵐さんを見つめ、口を開いた。
「それで、決めたんです!これからは私、西園寺さんのことを『師匠』って呼ばせてもらいます!」
「……は?」
「……へ?」
(まさかの師匠呼び……!?)
突然の宣言に、亜嵐さんも俺も二の句が継げない。
そんな俺たちなどお構いなしに、白石さんはどんどん言葉を発していく。
「藤宮くんと同じ並びだなんて、そんなおこがましいことは言いません。末席にちょこんと置いてもらえれば十分なんで。どうかよろしくお願いします!」
「えっと……亜嵐さん?」
向かいの男を見遣ると、こめかみに手を当てて、眉根をギュッと寄せていた。
「……頭が痛い……」
「あらあら、うふふ……」
けれど誰も「否」とは言わない。
(新しい仲間――そう思っていいんだよね?)
これから先は、賑やかになりそうだ。
でもきっと、とんでもなく愉快になるに違いない。
期待を胸に、俺はそっと紅茶を口に含んだ。
秘密はいつもティーカップの向こう側
サマープディングと癒しのレシピ / 完
◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側
本編もアルファポリスで連載中です☕
ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」
シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」
シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」
シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪
白石さんは目を瞬かせ、手元の皿を見た。
「えっ……えっ!?これ、病人食なんですか!?うそーっ!」
プディングと亜嵐さんの顔を交互に見遣る彼女の発言に、俺も激しく同意する。
「だって病気の人の食事っていったら、『あれはダメ、これもダメ、これならギリ食べていい』って感じじゃないですか!こんな美味しいデザートを食べていいなんて……信じられないっ!」
確かにその通りだ。
臨床栄養学の献立作成でも、『使えない食材』を避けつついかに満足感を出すか――それが最大の難問だった。
糖尿病なら総カロリーと糖質の管理、腎臓病ならナトリウムとカリウムの制限。
どんな食事を作るにしても制限ばかりが先に立ち、食の楽しさは後回しになる。
「亜嵐さん。サマープディングって、どんな病態の患者さん向けなんですか?」
「ふむ。良いところに気づいたな、湊」
亜嵐さんは軽く頷き、ナプキンの端を指先で整えると、ゆっくり語り始めた。
「時代は十九世紀、ヴィクトリア朝のイギリスだ。
産業革命で豊かになった人々は、それまでにない『飽食の時代』を迎えた。バターやクリーム、砂糖をふんだんに使った高カロリーな料理を楽しめるようになった。
だが――やがて彼らは、その代償を支払うことになる。
肥満や消化器の不調に悩まされ、温泉地や保養地での長い療養を余儀なくされた。当然、彼らの楽しみだったデザートとも、距離を置かねばならなくなった」
亜嵐さんは少し間を置いて、静かに続ける。
「しかし節制ほど難しいものはない。少しくらいならと隠れて、つい甘いものを食べてしまう。だがそれでは本末転倒だ。
そこで考案されたのが、この『サマープディング』だ。
リッチなペストリー生地の代わりにパンを使い、旬のベリーで自然な甘みを引き出した。砂糖を減らしても、風味はむしろ豊かになった。そして何より――美味かった。
やがてこの料理は療養食というカテゴリーを超えて、夏の定番デザートとして親しまれるようになったのだ」
気付けば俺たちは、亜嵐さんの語りにすっかり引き込まれていた。
白石さんはごくりと喉を鳴らすと、震える声で呟いた。
「もし……もし私が何かの病気で入院して、食事制限がつらくて、療養生活を苦しいと感じるようになったら。こんな美味しいデザートが出てきたらすごく嬉しいし、治療を続ける力になると思う」
その言葉に、亜嵐さんは確信の笑みを浮かべた。
「そうだとも、ミス・美緒。患者にとって治療とは、特別な時間ではなく『日常』なのだ。暮らしの中に彩りを見出したいのは、健康な者だけではない。むしろ病と向き合い、つらい治療を続ける者にこそ――それは希望の光となる」
希望の光――。
その言葉が、胸の奥で何かを打ち破った。
俺が小学生の頃、母は腎臓病を患った。
治療を続けても病状は改善せず、結局俺が高校に上がる前に母は亡くなった。
腎臓病の治療に、食事療法は欠かせない。
母も例外ではなく、厳しい制限の中で、それまで好きだった食べ物を口にできなくなっていった。
『真っ赤なイチゴが食べたいな……』
普段は弱音を吐かない母が、最後にこぼした一言。
あのときの俺は何もできずに泣くだけだったけれど、今ならわかる。
『真っ赤なイチゴ』こそ、母にとっての希望の光だったんだ。
「母さんが言いたかったことは、元気になってまたイチゴを食べたい――そういう意味だったと思うんです」
視界が滲み、熱いものが頬を伝う。
「食べ物って、栄養とかカロリーとか、そういう理屈じゃなくて……人の命の源であり、希望なんです。人は、食べるから生きられる。だから俺は――命を支える『食』を学びたくて、栄養士を目指したんです」
涙を拭いながら、必死に言葉を紡ぐ。
亜嵐さんは、そっと俺の背に手を置いた。
「湊……そうだったのか。君はもう、十分すぎるほど頑張っているとも」
「……っ、亜嵐、さんっ……!」
小さな嗚咽が、店内の静けさに溶けていく。
この想いを誰かに打ち明けるのは、これが初めてだ。父にも話したことはない。
苦しいなんて思ったことはない――そのはずだったけれど、それはただの強がりだった。
ふと顔を上げると、白石さんがじっとこちらを見つめていた。
その瞳は驚きと、温かい光を湛えていた。
(……まずい。こんな話をするつもりじゃなかったのに……)
ばつが悪くなって、乱暴に涙を拭う。
そんな俺に、白石さんは静かに言った。
「藤宮くん……私、間違ってた。ううん、今もね、ドクターと看護師と栄養士、それぞれの専門分野でチームを作る――その考えの根っこは変わらないよ。でも気付いたの。私たち看護師は、誰よりも患者さんに近い存在だわ。その看護師が、患者さんにとっての希望のひとつ――『食べること』に疎いなんて、あってはならないよね」
「白石さん……」
その声音は凛として、反省のほかに喜びの色を含んでいた。
「なんていうかね、栄養学って、患者さんを縛る鎖みたいなイメージだったの。でも本質は全然違うんだね。どうしたって生まれる制約の中で、どう楽しみをみつけるか――まるで宝物を探すような、素敵な分野なんだね!」
白石さんは太陽のような笑顔を浮かべた。
その言葉に、思わずこちらも笑顔になる。
(……宝探しか……)
自分が学んでいるものが、輝いているように感じられた。
うれしくて誇らしい。喜びがふつふつと湧き上がってくる。
「そんなふうに言ってもらえて、すごくうれしいな。俺、一生懸命勉強して、立派な栄養士になるよ!」
へへっと笑うと、亜嵐さんも白石さんも頷いてくれた。
「湊ならなれるさ」
「うん、絶対なれる!私が保証する!」
「白石さんもね。素敵な看護師さんになるよ、きっと」
わかり合えた温かさが、ゆったりと漂う。
――と、そのタイミングで、翠さんが銀色の盆を手にやってきた。
「みんな、体が冷えてきた頃でしょう?温かい紅茶をお持ちしましたよ」
白い小花が描かれたかわいらしいカップに、やさしい琥珀色の紅茶が注がれる。
立ち上る湯気がふわっと香って、全てが溶けていくようだ。
カップに口をつけた白石さんは、「はぁ…」と息を吐いた。
「この紅茶も、すっごく美味しいです。――藤宮くん、西園寺さん、翠さん。今日は本当にありがとうございました。私、目から鱗が落ちました。食卓の上に、こんなにも素敵な世界が広がっているなんて」
そう語る表情は、清々しく輝いている。
けれどすぐ、残念そうにテーブルを見た。
「しまったなぁ……二十年間、損してた気分だわ」
「あら。気づいたのなら、これから楽しめばいいだけじゃない?」
優しい声音で、翠さんが微笑む。
「そうだとも。それに『同じ食卓』とは、何も顔を突き合わせることだけを言うのではない。忙しくてなかなか揃わないご両親と、たとえ一緒にではなくとも、同じものを美味しいと感じられたら――それは立派な食卓といえる」
白石さんは「……そっか」と呟いて、パッと顔を上げた。
「翠さん!ここのケーキって、テイクアウトもやってますか?」
「ええ、もちろんよ。今日は三種類ご用意していますよ」
「三種類……え、どれにしよう。西園寺さん、ちょっと見てきていいですか?」
返答を待たず白石さんは立ち上がり、翠さんと一緒にショーケースへ向かった。
静かになったテーブルを前に、俺は亜嵐さんに向かい合う。
「亜嵐さん、改めて今日はありがとうございました」
「……意地悪ではない証明になったかな?」
片目を眇めて唇の端を上げる亜嵐さんに、思わずぷっと吹き出した。
「あれは……!本当にガールハントなんかじゃないし、それに亜嵐さんが意地悪だなんて、俺、これっぽっちも思ってませんよ!」
「冗談さ。――まあ、礼も必要ない。素晴らしいホットケーキを焼いてもらったからな。これくらいは当然のことだ」
(まったく……どこまでが本気なんだか)
でも俺は、これまでの短い付き合いの中でも、しっかり感じ取っている。
この人の言動の底には、いつも温かな思い遣りがあるのだと――。
そこへ、ケーキを選び終えた白石さんが戻ってきた。
「も~っ!どのケーキもすごく美味しそうなんだもん、迷っちゃったよ!」
その顔には、満面の笑みが浮かんでいる。
「どのケーキを選んでも、最高のティータイムを保証するとも」
「ですよね!オレンジのケーキもいいなぁって思ったけど、旬だからチェリーパイにしました。……えへへ、お父さんもお母さんも、喜んでくれるといいな」
「きっと喜んでくれるよ」
そして俺たちは色々おしゃべりをしながら、サマープディングと紅茶を楽しんだ。
***
「……ふむ、面白い。実に湊らしい発想だ」
「でも、問題は中に何を入れるかで……」
後日。
ローズメリーでお茶を飲みながら、亜嵐さんと話に興じていると。
チリン、チリン!
軽やかなベルの音とともに、颯爽とした足取りで店内に入ってくる人の姿。
「いらっしゃいませ――あら、美緒ちゃん」
「翠さん、こんにちは!」
爽やかな風のように現れたのは、白石さんだった。
しかしその姿は、いつものパンツスタイルではない。
元気な印象だったポニーテールは下ろされ、首筋で緩くまとめられている。
水色の花柄スカートはふわりと揺れ、レースの肩口が涼やかだ。
「まぁ、美緒ちゃん……素敵よ。とてもよく似合ってるわ」
「えへへ、ありがとうございます。この間は藤宮くんに『ドレスコードはない』って言われて信じちゃったけど。このお店に来るんだったら、やっぱり少しはおしゃれしないと!って思って」
しれっと引き合いに出されたが、これは軽い非難だろうか?
「あっ、藤宮くんと西園寺さん!こんにちは、会えて良かった」
とことこと近付いてきた白石さんは、挨拶もそこそこに、ぺこりと頭を下げた。
「あの日――やっぱり一緒には食べられなかったけど、父も母もチェリーパイをすごく喜んでくれました。疲れが吹き飛ぶって。西園寺さんが言った通りでした。本当にありがとうございました!」
「頭を上げたまえ、ミス・美緒。ご両親が喜んだのは、そこに君の思い遣りがあったからだ」
優しく言葉を紡ぐ亜嵐さんを見て、俺の胸はほっこりと温かくなった。
頭を上げた白石さんは、キラキラと光る瞳で亜嵐さんを見つめ、口を開いた。
「それで、決めたんです!これからは私、西園寺さんのことを『師匠』って呼ばせてもらいます!」
「……は?」
「……へ?」
(まさかの師匠呼び……!?)
突然の宣言に、亜嵐さんも俺も二の句が継げない。
そんな俺たちなどお構いなしに、白石さんはどんどん言葉を発していく。
「藤宮くんと同じ並びだなんて、そんなおこがましいことは言いません。末席にちょこんと置いてもらえれば十分なんで。どうかよろしくお願いします!」
「えっと……亜嵐さん?」
向かいの男を見遣ると、こめかみに手を当てて、眉根をギュッと寄せていた。
「……頭が痛い……」
「あらあら、うふふ……」
けれど誰も「否」とは言わない。
(新しい仲間――そう思っていいんだよね?)
これから先は、賑やかになりそうだ。
でもきっと、とんでもなく愉快になるに違いない。
期待を胸に、俺はそっと紅茶を口に含んだ。
秘密はいつもティーカップの向こう側
サマープディングと癒しのレシピ / 完
◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側
本編もアルファポリスで連載中です☕
ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」
シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」
シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」
シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪
1
あなたにおすすめの小説
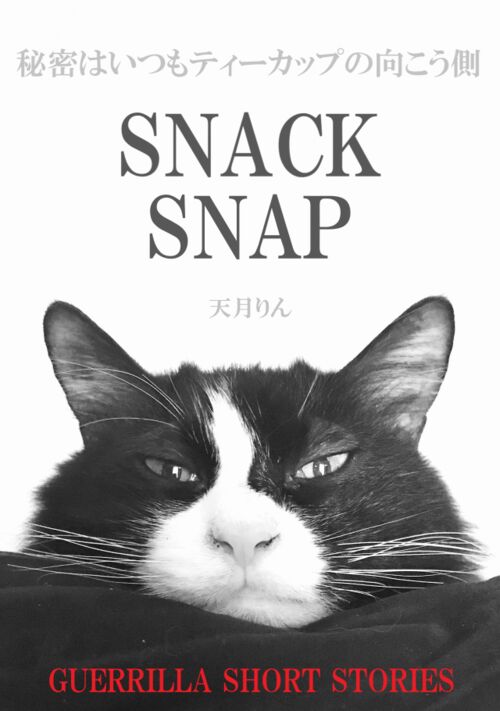
秘密はいつもティーカップの向こう側 ―SNACK SNAP―
天月りん
キャラ文芸
食べることは、生きること。
ティーハウス<ローズメリー>に集う面々に起きる、ほんの些細な出来事。
楽しかったり、ちょっぴり悲しかったり。
悔しかったり、ちょっぴり喜んだり。
彼らの日常をそっと覗き込んで、写し撮った一枚のスナップ――。
『秘密はいつもティーカップの向こう側』SNACK SNAPシリーズ。
気まぐれ更新。
ティーカップの紅茶に、ちょっとミルクを入れるようなSHORT STORYです☕
◆・◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側(本編) ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪

秘密はいつもティーカップの向こう側 ―BONUS TRACK―
天月りん
キャラ文芸
食べることは、生きること。
ティーハウス<ローズメリー>に集う面々の日常を、こっそり覗いてみませんか?
笑って、悩んで、ときにはすれ違いながら――それでも前を向く。
誰かの心がふと動く瞬間を描く短編集。
本編では語られない「その後」や「すき間」の物語をお届けする
『秘密はいつもティーカップの向こう側』BONUST RACKシリーズ。
気まぐれ更新。
あなたのタイミングで、そっと覗きにきてください☕
◆・◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側(本編) ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪

敗戦国の姫は、敵国将軍に掠奪される
clayclay
恋愛
架空の国アルバ国は、ブリタニア国に侵略され、国は壊滅状態となる。
状況を打破するため、アルバ国王は娘のソフィアに、ブリタニア国使者への「接待」を命じたが……。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

秘密はいつもティーカップの向こう側 ―TEACUP TALES―
天月りん
キャラ文芸
食べることは、生きること。
湊と亜嵐の目線を通して繰り広げられる、食と人を繋ぐ心の物語。
ティーカップの湯気の向こうに揺蕩う、誰かを想う心の機微。
ふわりと舞い上がる彼らの物語を、別角度からお届けします。
本編に近いサイドストーリーをお届けする
『秘密はいつもティーカップの向こう側』SHORT STORYシリーズ。
気まぐれ更新でお届けする、登場人物の本音の物語です
あなたのタイミングで、そっと覗きにきてください☕
◆・◆・◆・◆
秘密はいつもティーカップの向こう側(本編) ティーカップ越しの湊と亜嵐の物語はこちら。
秘密はいつもティーカップの向こう側の姉妹編
・本編番外編シリーズ「TEACUP TALES」シリーズ本編番外編
・番外編シリーズ「BONUS TRACK」シリーズSS番外編
・番外SSシリーズ「SNACK SNAP」シリーズのおやつ小話
よろしければ覗いてみてください♪

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















