45 / 84
4.魔王城の闇医者
13話
しおりを挟む
レヴィアスの片翼が、失われてしまった。
目の前で起きたことへのあまりのショックに、シオンは叫びそうになる。
しかし、吐息が頬に掛かるほどの距離で、血に濡れた顔を苦痛にゆがめるレヴィアスの姿を見て、ぐっと唇を嚙み締めた。
深々と突き刺さった鎌を地面から引き抜こうと、蜘蛛が体を左右に動かしている。
体を支える脚を失い、いっそうバランスが取れないのだろう。
距離をとれれば。
馬のいるところまで戻ることが出来れば、もしかしたら。
恐怖と焦りで焼き切れそうな思考を必死に回す。
強く噛んだ唇には血が滲み、泣きたくないのに涙がこぼれる。
「大丈夫です」
耳元で、囁くような声がする。
「レヴィアスさ……」
思わず声をあげて名前を呼ぶ。
血に濡れ、その多量の出血のせいで青ざめたレヴィアスと視線が絡んだ。
ぼろっ、とシオンの瞳から涙がこぼれる。
不安にさせまいとしているのだろうか。
レヴィアスの表情は、かえっていつもよりも柔らかい。
「少しだけ、力を貸してもらえますか」
「えっ……?」
そう言うと、レヴィアスはシオンの後頭部を一、二度撫でて目を閉じる。
それからレヴィアスの背に回していたシオンの手をとり、指をからませてぎゅっと握った。
ほんの数秒の出来事だ。
じわりと体が熱を持ち、その熱がレヴィアスの方へと流れていくような感覚。
ほんのわずかに、レヴィアスの顔に生気が戻る。
(なに…これ)
驚きを隠せない表情で、シオンはレヴィアスの顔を見る。
目が合ったその一瞬、レヴィアスは本当に僅かに、微笑んだようだった。
ぱっと体を離したレヴィアスは、足元の血だまりに転がった剣を拾い上げる。
片手に握りなおしたその刃先から、ぽたぽたと鮮血がしたたり落ちていた。
ふっと、一陣の風が、血と土の匂いをつれて吹き抜ける。
その瞬間。
翼を裂かれた大きな傷跡が残る彼の左の背から、まるで魔法のように新しい翼が現れた。
右に残る黒い翼とは異なる、純白の大きな翼。
付け根から滴る血を吸って、白い翼がじわじわと赤く染まっていく。
こちらを守るように剣を構えるレヴィアスの向こうに、ようやく体勢を立て直した蜘蛛が大きく振りかぶる鎌が見える。
白い翼に染みる血の色はだんだんと広がり、さらにそれを凌駕する速度で……
まるで、何かの呪いのように、あっという間に付け根から真っ黒に塗り上げられた。
(……っ!?)
天使の純白の翼が、そこに在ることを拒絶するかのように色を変えたのだ。
まるで、その翼の色が、彼の『なにかの罪』を象徴しているようで。
シオンはその光景に、射すくめられてしまった。
蜘蛛が鎌を掲げながらこちらに突き進んでくる、そのほんの一瞬。
レヴィアスは小さくシオンを振り返った。
シオンの表情を見た彼の目に浮かんだ感情は何だったのか、読み取れない。
――蜘蛛の断末魔が聞こえる。
蜘蛛の体を剣で裂き、溢れる血をその身に浴びるレヴィアスの姿は、禍々しくも、神々しくもあった。
◇
「……それで、これがその蜘蛛ってわけね」
巨大な蜘蛛が引き裂かれ、絶命したのち、騒ぎを感知したシンシアが現れた。
日光を避けるためだろうか。
ローブを着込み、目深にフードをかぶっている。
シオンの傍らには、あまりのショックで気を失ったリヴィオが横たわっていた。
さっと見る限り、体に傷は無いようだ。
シオンはほっと息をつく。
まだ温かい血を流している蜘蛛の亡骸を検分しながら、シンシアは苦い顔をした。
「まあ、自然に起きる変異じゃないわね。体の構造的にも無理がある……切って貼ったような、『誰か』が、『無理やり』引き起こした後天的な変異ね」
「調査したらどこまでわかる?」
「どの組織が何の変化をしたのかは分析できるでしょうけど、誰が、なぜ、は私の専門外」
淡々と会話が進むレヴィアスとシンシアの様子を後ろから眺める。
どうやら、シンシアは今回の件に興味を持ってくれたらしい。
その事実に、シオンは胸をなでおろした。
「まあ、解剖はじっくり後でやるとして」
シンシアはきっ、とレヴィアスを睨む。
「あなたはドクターストップ。それから……」
シオンの傍らに倒れるリヴィオに視線を向ける。
「その子も……置いてはいけないわね」
目を閉じたリヴィオの姿を見つめるシンシアの表情は、どこか切なげに見えた。
◇
シンシアの館で治療を受け、少し休ませてもらった後に町の宿屋へと戻っていた。
館の中で目を覚まされたくない、というシンシアの意向により、リヴィオは魔法で眠らせた状態で町へと運び、家族へと引き渡した。
森の中で、野生動物か何かに襲われて気絶しているところを保護した。
気を失いながらうわごとを言っていたので、何か怖い夢を見たのかもしれない、と。
そんなことを伝えると、リヴィオの家族はシオン達に何度も礼を言い、心配そうに彼を抱えて家の中へと入っていった。
リヴィオの様子を見ていればよくわかるが、彼は家族からも周囲からも真っ当に愛されて育っている。
(私たちが、関わるべきじゃない子だよね)
なぜリヴィオがあの森の中にいたのか、謎は残っている。
薬草を摘んでいるうちに、迷い込んでしまったのか。
そうでなければ……。
シオン達の後を、つけてきたのか。
疑問を振り払うようにして、シオン達は宿屋へと急いだ。
――明日には、この町を出るべきだろう。
ひとつ大きく深呼吸して、シオンは潮の香りを胸いっぱいに吸い込んだ。
それから宿の二階でレヴィアスと分かれ、自室のベッドに飛び込む。
シンシアの館で湯を借りて、蜘蛛の返り血やらで汚れた服もすっかり着替えた。
それでもまだ、体のどこかから、温かい血の匂いがするような気がする。
(レヴィアスさんの顔、うまく見れなかったな……)
さすがにレヴィアスにも疲労の色がにじんでいたこともあり、帰り道もお互いに言葉少なだった。
レヴィアスに伝えるべきことは沢山あったはずなのに、喉の奥に引っかかって出てこない。
シオンの心の中には、沢山の感情が渦巻いていた。
「はあ……」
情けなさに、思わず涙がこぼれる。
(私が勝手なことをしなければ、彼は傷つかずに済んだのかもしれない)
背中に負った大きな傷。
シンシアの館で手当てを受けたレヴィアスの姿を見て、彼が生きていることに感謝をした。
翼こそ再生したが、しばらくの間出血が続き、その傷の状態はあまりにも痛々しいものだったのだ。
シオンはぎゅっと手を握りしめた。
ただ逃げ惑うことしかできなかった自分を思い出して、悔しさがこみ上げる。
それに、体に負わせた傷だけではない。
彼の翼が漆黒に染め上げられる瞬間を目の当たりにしたとき。
(……私は、どんな顔をしていただろう)
シオンは、確かに恐怖を感じていた。
真っ白い雪に墨を垂らしたように、じわじわと黒い色が侵食していく様は、まさに呪いのように見えたのだ。
あのとき一瞬、レヴィアスはシオンの顔を見た。
彼の瞳に映った自分の顔は、恐怖に歪んでいたのだろうか。
「はあ……」
何度目かになるため息をついて、にじんだ涙を隠すように両手で顔を覆う。
命がけで守ってくれた彼を、一瞬でも『恐ろしい』と感じてしまった。
そのことに、シオンは激しい自己嫌悪を覚えていたのだ。
しばらくの間ベッドに寝転がり、ぼんやりと天井を見つめていた。
相変わらず軽やかな祭りの音楽が、窓を通して微かに聞こえる。
やがて、ぱっ、と窓の外で何かが輝いた。
「あ……花火」
すっかり忘れていたが、今夜は花火が上がると言っていた。
はしゃぐ気分でもなかったが、部屋の中で鬱々とした時間を過ごしていても仕方ない。
シオンは部屋を出て、バルコニーへと繰り出すことにした。
夜風に、潮の香りと微かに火薬の匂いが混ざっている。
バルコニーからは海を臨むことができ、ラタンのソファとテーブルが用意されていた。
ソファの端に腰かけて、シオンはぼんやりと空を見上げた。
ほとんど濃紺色をした夜空だが、水平線の近くには僅かにオレンジ色の夕日が溶け残る様に滲んでいる。
花火は夕焼けと夜空の境を突き抜けるように、真っすぐに空を駆けあがって見事な花を咲かせていた。
すると、きし……とバルコニーの床板がきしむ音がする。
振り向くと、そこにはレヴィアスの姿があった。
「起きていて大丈夫なんですか……?」
慌ててシオンがレヴィアスをソファへと導く。
見た目にはわからないが、服の下はシンシアが巻いた包帯でぐるぐる巻きだ。
「問題ありません。……シンシアが、大袈裟なだけです」
少し動きにくそうにしながら、レヴィアスが左肩のあたりをさする。
「大袈裟なんかじゃないですよ、本当に……」
横並びになる様にソファへゆっくりと腰かけたレヴィアスに、シオンは姿勢を正して向き合った。
「レヴィアスさん、ごめんなさい」
シオンの心の中はまだぐちゃぐちゃで、整理はついていない。
それでも、それはまず伝えなくていけない言葉だった。
「……あなたを巻き込んだのは私です」
レヴィアスは、真っすぐにシオンの目を見てそう言った。
時折夜空に打ちあがる花火の色が、レヴィアスの銀色の髪を微かに染める。
「レヴィアスさんが……死んでしまうかと思いました……」
シオンは、鼻の奥がツンとするのを感じた。
言葉にしなければならない感情が、沢山ある。
その前に、彼に伝えなくてはならないことも。
「私……この町で、エリオルさんという方に会いました」
レヴィアスが、一瞬息を飲んだ。
冬空のような青色をした瞳が、僅かに揺らぐ。
「好意的、とは言い難い様子だったので……お伝えするか悩んだんです」
「彼は……」
彼は、何と?
恐らく、そう尋ねようとしたのだろう。
しかし、レヴィアスはそれを飲み込むと、違う言葉を口にした。
夜風に彼の銀色の髪がふわりと揺れる。
「……あなたは、私のことが恐ろしいですか?」
そこに感情は無く、風に消えていきそうなほど儚い問いかけだった。
ずきん、とシオンの胸が痛む。
恐ろしくありません、と言い切ることが出来たならどんなに楽だろう。
それでも、一瞬浮かんでしまったあの恐怖心は、曖昧な嘘で塗り隠すことはできない。
彼は、そんな上辺の受容を望んでいない気がしたのだ。
パン、と花火が弾ける音を聞きながら、シオンは何度か視線を彷徨わせる。
「結局、あなたにも傷がついてしまいましたね」
レヴィアスが、シオンの膝に置かれた両手を見て呟いた。
シオンの手には何枚か、絆創膏が巻かれている。
全く気付いていなかったが、リヴィオを庇う中であちこち擦り傷や切り傷が出来てしまっていたのだ。
シオンの手に触れようと伸ばした手が、ぴたりと止まる。
そしてそのまま、レヴィアスはシオンから距離をとる様に、僅かに身を引いた。
それを見て、咄嗟にシオンはその手を掴む。
驚いたように顔を上げるレヴィアスに、シオンは真っすぐな視線を向けた。
「……離れていこうとしないで下さい」
それは、絞り出した願いだった。
じわりと胸を焼く恋心はとうに自覚していた。
それでも、感情のままに多くを望むことはしたくない。
その願いは、相手も、自分も傷つけるかもしれないからだ。
「勝手なことを言ってごめんなさい。怖いと思うことだって、本当は有ります。でも……」
シオンの目に、涙がにじみそうになる。
(泣いちゃ駄目。傷ついているのは、きっと彼の方なのに)
心の中で、シオンは自らを叱咤した。
「あなたが離れていってしまうことの方が、ずっと怖いことだと思います」
町の賑わいを空から包み込むように、花火の光が降り注ぐ。
夜空を照らす花火の影になって、レヴィアスの表情はうかがえない。
それでも、レヴィアスがシオンの手を振り払うことは無かった。
やがて、ゆっくりとレヴィアスがシオンの首元のネックレスに触れる。
チカ、チカと数回光が瞬くと、輝きを失っていた魔法石が息を吹き返したかのように明るく色づいた。
「あなたの身を守ってくれましたね」
穏やかな声でレヴィアスが言う。
「また、その石が光を失ったら私のところに来てください」
そういうと魔法石を長い指でひと撫でして、レヴィアスは部屋へと戻っていく。
クライマックスに差しかかった花火の華やかな光を浴びながら、シオンはそっと首元の魔法石を見る。
その石の色は、いつの間にかレヴィアスの瞳を思わせる冴えた青色の輝きを放っていた。
シオンは、ぎゅっとその石を握り込む。
夜風がそっとシオンの髪を揺らしていた。
目の前で起きたことへのあまりのショックに、シオンは叫びそうになる。
しかし、吐息が頬に掛かるほどの距離で、血に濡れた顔を苦痛にゆがめるレヴィアスの姿を見て、ぐっと唇を嚙み締めた。
深々と突き刺さった鎌を地面から引き抜こうと、蜘蛛が体を左右に動かしている。
体を支える脚を失い、いっそうバランスが取れないのだろう。
距離をとれれば。
馬のいるところまで戻ることが出来れば、もしかしたら。
恐怖と焦りで焼き切れそうな思考を必死に回す。
強く噛んだ唇には血が滲み、泣きたくないのに涙がこぼれる。
「大丈夫です」
耳元で、囁くような声がする。
「レヴィアスさ……」
思わず声をあげて名前を呼ぶ。
血に濡れ、その多量の出血のせいで青ざめたレヴィアスと視線が絡んだ。
ぼろっ、とシオンの瞳から涙がこぼれる。
不安にさせまいとしているのだろうか。
レヴィアスの表情は、かえっていつもよりも柔らかい。
「少しだけ、力を貸してもらえますか」
「えっ……?」
そう言うと、レヴィアスはシオンの後頭部を一、二度撫でて目を閉じる。
それからレヴィアスの背に回していたシオンの手をとり、指をからませてぎゅっと握った。
ほんの数秒の出来事だ。
じわりと体が熱を持ち、その熱がレヴィアスの方へと流れていくような感覚。
ほんのわずかに、レヴィアスの顔に生気が戻る。
(なに…これ)
驚きを隠せない表情で、シオンはレヴィアスの顔を見る。
目が合ったその一瞬、レヴィアスは本当に僅かに、微笑んだようだった。
ぱっと体を離したレヴィアスは、足元の血だまりに転がった剣を拾い上げる。
片手に握りなおしたその刃先から、ぽたぽたと鮮血がしたたり落ちていた。
ふっと、一陣の風が、血と土の匂いをつれて吹き抜ける。
その瞬間。
翼を裂かれた大きな傷跡が残る彼の左の背から、まるで魔法のように新しい翼が現れた。
右に残る黒い翼とは異なる、純白の大きな翼。
付け根から滴る血を吸って、白い翼がじわじわと赤く染まっていく。
こちらを守るように剣を構えるレヴィアスの向こうに、ようやく体勢を立て直した蜘蛛が大きく振りかぶる鎌が見える。
白い翼に染みる血の色はだんだんと広がり、さらにそれを凌駕する速度で……
まるで、何かの呪いのように、あっという間に付け根から真っ黒に塗り上げられた。
(……っ!?)
天使の純白の翼が、そこに在ることを拒絶するかのように色を変えたのだ。
まるで、その翼の色が、彼の『なにかの罪』を象徴しているようで。
シオンはその光景に、射すくめられてしまった。
蜘蛛が鎌を掲げながらこちらに突き進んでくる、そのほんの一瞬。
レヴィアスは小さくシオンを振り返った。
シオンの表情を見た彼の目に浮かんだ感情は何だったのか、読み取れない。
――蜘蛛の断末魔が聞こえる。
蜘蛛の体を剣で裂き、溢れる血をその身に浴びるレヴィアスの姿は、禍々しくも、神々しくもあった。
◇
「……それで、これがその蜘蛛ってわけね」
巨大な蜘蛛が引き裂かれ、絶命したのち、騒ぎを感知したシンシアが現れた。
日光を避けるためだろうか。
ローブを着込み、目深にフードをかぶっている。
シオンの傍らには、あまりのショックで気を失ったリヴィオが横たわっていた。
さっと見る限り、体に傷は無いようだ。
シオンはほっと息をつく。
まだ温かい血を流している蜘蛛の亡骸を検分しながら、シンシアは苦い顔をした。
「まあ、自然に起きる変異じゃないわね。体の構造的にも無理がある……切って貼ったような、『誰か』が、『無理やり』引き起こした後天的な変異ね」
「調査したらどこまでわかる?」
「どの組織が何の変化をしたのかは分析できるでしょうけど、誰が、なぜ、は私の専門外」
淡々と会話が進むレヴィアスとシンシアの様子を後ろから眺める。
どうやら、シンシアは今回の件に興味を持ってくれたらしい。
その事実に、シオンは胸をなでおろした。
「まあ、解剖はじっくり後でやるとして」
シンシアはきっ、とレヴィアスを睨む。
「あなたはドクターストップ。それから……」
シオンの傍らに倒れるリヴィオに視線を向ける。
「その子も……置いてはいけないわね」
目を閉じたリヴィオの姿を見つめるシンシアの表情は、どこか切なげに見えた。
◇
シンシアの館で治療を受け、少し休ませてもらった後に町の宿屋へと戻っていた。
館の中で目を覚まされたくない、というシンシアの意向により、リヴィオは魔法で眠らせた状態で町へと運び、家族へと引き渡した。
森の中で、野生動物か何かに襲われて気絶しているところを保護した。
気を失いながらうわごとを言っていたので、何か怖い夢を見たのかもしれない、と。
そんなことを伝えると、リヴィオの家族はシオン達に何度も礼を言い、心配そうに彼を抱えて家の中へと入っていった。
リヴィオの様子を見ていればよくわかるが、彼は家族からも周囲からも真っ当に愛されて育っている。
(私たちが、関わるべきじゃない子だよね)
なぜリヴィオがあの森の中にいたのか、謎は残っている。
薬草を摘んでいるうちに、迷い込んでしまったのか。
そうでなければ……。
シオン達の後を、つけてきたのか。
疑問を振り払うようにして、シオン達は宿屋へと急いだ。
――明日には、この町を出るべきだろう。
ひとつ大きく深呼吸して、シオンは潮の香りを胸いっぱいに吸い込んだ。
それから宿の二階でレヴィアスと分かれ、自室のベッドに飛び込む。
シンシアの館で湯を借りて、蜘蛛の返り血やらで汚れた服もすっかり着替えた。
それでもまだ、体のどこかから、温かい血の匂いがするような気がする。
(レヴィアスさんの顔、うまく見れなかったな……)
さすがにレヴィアスにも疲労の色がにじんでいたこともあり、帰り道もお互いに言葉少なだった。
レヴィアスに伝えるべきことは沢山あったはずなのに、喉の奥に引っかかって出てこない。
シオンの心の中には、沢山の感情が渦巻いていた。
「はあ……」
情けなさに、思わず涙がこぼれる。
(私が勝手なことをしなければ、彼は傷つかずに済んだのかもしれない)
背中に負った大きな傷。
シンシアの館で手当てを受けたレヴィアスの姿を見て、彼が生きていることに感謝をした。
翼こそ再生したが、しばらくの間出血が続き、その傷の状態はあまりにも痛々しいものだったのだ。
シオンはぎゅっと手を握りしめた。
ただ逃げ惑うことしかできなかった自分を思い出して、悔しさがこみ上げる。
それに、体に負わせた傷だけではない。
彼の翼が漆黒に染め上げられる瞬間を目の当たりにしたとき。
(……私は、どんな顔をしていただろう)
シオンは、確かに恐怖を感じていた。
真っ白い雪に墨を垂らしたように、じわじわと黒い色が侵食していく様は、まさに呪いのように見えたのだ。
あのとき一瞬、レヴィアスはシオンの顔を見た。
彼の瞳に映った自分の顔は、恐怖に歪んでいたのだろうか。
「はあ……」
何度目かになるため息をついて、にじんだ涙を隠すように両手で顔を覆う。
命がけで守ってくれた彼を、一瞬でも『恐ろしい』と感じてしまった。
そのことに、シオンは激しい自己嫌悪を覚えていたのだ。
しばらくの間ベッドに寝転がり、ぼんやりと天井を見つめていた。
相変わらず軽やかな祭りの音楽が、窓を通して微かに聞こえる。
やがて、ぱっ、と窓の外で何かが輝いた。
「あ……花火」
すっかり忘れていたが、今夜は花火が上がると言っていた。
はしゃぐ気分でもなかったが、部屋の中で鬱々とした時間を過ごしていても仕方ない。
シオンは部屋を出て、バルコニーへと繰り出すことにした。
夜風に、潮の香りと微かに火薬の匂いが混ざっている。
バルコニーからは海を臨むことができ、ラタンのソファとテーブルが用意されていた。
ソファの端に腰かけて、シオンはぼんやりと空を見上げた。
ほとんど濃紺色をした夜空だが、水平線の近くには僅かにオレンジ色の夕日が溶け残る様に滲んでいる。
花火は夕焼けと夜空の境を突き抜けるように、真っすぐに空を駆けあがって見事な花を咲かせていた。
すると、きし……とバルコニーの床板がきしむ音がする。
振り向くと、そこにはレヴィアスの姿があった。
「起きていて大丈夫なんですか……?」
慌ててシオンがレヴィアスをソファへと導く。
見た目にはわからないが、服の下はシンシアが巻いた包帯でぐるぐる巻きだ。
「問題ありません。……シンシアが、大袈裟なだけです」
少し動きにくそうにしながら、レヴィアスが左肩のあたりをさする。
「大袈裟なんかじゃないですよ、本当に……」
横並びになる様にソファへゆっくりと腰かけたレヴィアスに、シオンは姿勢を正して向き合った。
「レヴィアスさん、ごめんなさい」
シオンの心の中はまだぐちゃぐちゃで、整理はついていない。
それでも、それはまず伝えなくていけない言葉だった。
「……あなたを巻き込んだのは私です」
レヴィアスは、真っすぐにシオンの目を見てそう言った。
時折夜空に打ちあがる花火の色が、レヴィアスの銀色の髪を微かに染める。
「レヴィアスさんが……死んでしまうかと思いました……」
シオンは、鼻の奥がツンとするのを感じた。
言葉にしなければならない感情が、沢山ある。
その前に、彼に伝えなくてはならないことも。
「私……この町で、エリオルさんという方に会いました」
レヴィアスが、一瞬息を飲んだ。
冬空のような青色をした瞳が、僅かに揺らぐ。
「好意的、とは言い難い様子だったので……お伝えするか悩んだんです」
「彼は……」
彼は、何と?
恐らく、そう尋ねようとしたのだろう。
しかし、レヴィアスはそれを飲み込むと、違う言葉を口にした。
夜風に彼の銀色の髪がふわりと揺れる。
「……あなたは、私のことが恐ろしいですか?」
そこに感情は無く、風に消えていきそうなほど儚い問いかけだった。
ずきん、とシオンの胸が痛む。
恐ろしくありません、と言い切ることが出来たならどんなに楽だろう。
それでも、一瞬浮かんでしまったあの恐怖心は、曖昧な嘘で塗り隠すことはできない。
彼は、そんな上辺の受容を望んでいない気がしたのだ。
パン、と花火が弾ける音を聞きながら、シオンは何度か視線を彷徨わせる。
「結局、あなたにも傷がついてしまいましたね」
レヴィアスが、シオンの膝に置かれた両手を見て呟いた。
シオンの手には何枚か、絆創膏が巻かれている。
全く気付いていなかったが、リヴィオを庇う中であちこち擦り傷や切り傷が出来てしまっていたのだ。
シオンの手に触れようと伸ばした手が、ぴたりと止まる。
そしてそのまま、レヴィアスはシオンから距離をとる様に、僅かに身を引いた。
それを見て、咄嗟にシオンはその手を掴む。
驚いたように顔を上げるレヴィアスに、シオンは真っすぐな視線を向けた。
「……離れていこうとしないで下さい」
それは、絞り出した願いだった。
じわりと胸を焼く恋心はとうに自覚していた。
それでも、感情のままに多くを望むことはしたくない。
その願いは、相手も、自分も傷つけるかもしれないからだ。
「勝手なことを言ってごめんなさい。怖いと思うことだって、本当は有ります。でも……」
シオンの目に、涙がにじみそうになる。
(泣いちゃ駄目。傷ついているのは、きっと彼の方なのに)
心の中で、シオンは自らを叱咤した。
「あなたが離れていってしまうことの方が、ずっと怖いことだと思います」
町の賑わいを空から包み込むように、花火の光が降り注ぐ。
夜空を照らす花火の影になって、レヴィアスの表情はうかがえない。
それでも、レヴィアスがシオンの手を振り払うことは無かった。
やがて、ゆっくりとレヴィアスがシオンの首元のネックレスに触れる。
チカ、チカと数回光が瞬くと、輝きを失っていた魔法石が息を吹き返したかのように明るく色づいた。
「あなたの身を守ってくれましたね」
穏やかな声でレヴィアスが言う。
「また、その石が光を失ったら私のところに来てください」
そういうと魔法石を長い指でひと撫でして、レヴィアスは部屋へと戻っていく。
クライマックスに差しかかった花火の華やかな光を浴びながら、シオンはそっと首元の魔法石を見る。
その石の色は、いつの間にかレヴィアスの瞳を思わせる冴えた青色の輝きを放っていた。
シオンは、ぎゅっとその石を握り込む。
夜風がそっとシオンの髪を揺らしていた。
0
あなたにおすすめの小説

『規格外の薬師、追放されて辺境スローライフを始める。〜作ったポーションが国家機密級なのは秘密です〜』
雛月 らん
ファンタジー
俺、黒田 蓮(くろだ れん)35歳は前世でブラック企業の社畜だった。過労死寸前で倒れ、次に目覚めたとき、そこは剣と魔法の異世界。しかも、幼少期の俺は、とある大貴族の私生児、アレン・クロイツェルとして生まれ変わっていた。
前世の記憶と、この世界では「外れスキル」とされる『万物鑑定』と『薬草栽培(ハイレベル)』。そして、誰にも知られていない規格外の莫大な魔力を持っていた。
しかし、俺は決意する。「今世こそ、誰にも邪魔されない、のんびりしたスローライフを送る!」と。
これは、スローライフを死守したい天才薬師のアレンと、彼の作る規格外の薬に振り回される異世界の物語。
平穏を愛する(自称)凡人薬師の、のんびりだけど実は波乱万丈な辺境スローライフファンタジー。

異世界でゆるゆるスローライフ!~小さな波乱とチートを添えて~
イノナかノかワズ
ファンタジー
助けて、刺されて、死亡した主人公。神様に会ったりなんやかんやあったけど、社畜だった前世から一転、ゆるいスローライフを送る……筈であるが、そこは知識チートと能力チートを持った主人公。波乱に巻き込まれたりしそうになるが、そこはのんびり暮らしたいと持っている主人公。波乱に逆らい、世界に名が知れ渡ることはなくなり、知る人ぞ知る感じに収まる。まぁ、それは置いといて、主人公の新たな人生は、温かな家族とのんびりした自然、そしてちょっとした研究生活が彩りを与え、幸せに溢れています。
*話はとてもゆっくりに進みます。また、序盤はややこしい設定が多々あるので、流しても構いません。
*他の小説や漫画、ゲームの影響が見え隠れします。作者の願望も見え隠れします。ご了承下さい。
*頑張って週一で投稿しますが、基本不定期です。
*本作の無断転載、無断翻訳、無断利用を禁止します。
小説家になろうにて先行公開中です。主にそっちを優先して投稿します。
カクヨムにても公開しています。
更新は不定期です。

転生したみたいなので異世界生活を楽しみます
さっちさん
ファンタジー
又々、題名変更しました。
内容がどんどんかけ離れていくので…
沢山のコメントありがとうございます。対応出来なくてすいません。
誤字脱字申し訳ございません。気がついたら直していきます。
感傷的表現は無しでお願いしたいと思います😢
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ありきたりな転生ものの予定です。
主人公は30代後半で病死した、天涯孤独の女性が幼女になって冒険する。
一応、転生特典でスキルは貰ったけど、大丈夫か。私。
まっ、なんとかなるっしょ。

高校生の俺、異世界転移していきなり追放されるが、じつは最強魔法使い。可愛い看板娘がいる宿屋に拾われたのでもう戻りません
下昴しん
ファンタジー
高校生のタクトは部活帰りに突然異世界へ転移してしまう。
横柄な態度の王から、魔法使いはいらんわ、城から出ていけと言われ、いきなり無職になったタクト。
偶然会った宿屋の店長トロに仕事をもらい、看板娘のマロンと一緒に宿と食堂を手伝うことに。
すると突然、客の兵士が暴れだし宿はメチャクチャになる。
兵士に殴り飛ばされるトロとマロン。
この世界の魔法は、生活で利用する程度の威力しかなく、とても弱い。
しかし──タクトの魔法は人並み外れて、無法者も脳筋男もひれ伏すほど強かった。
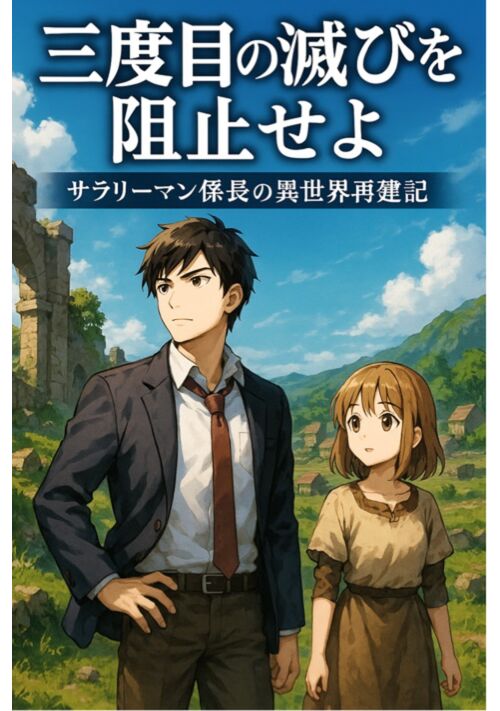
『三度目の滅びを阻止せよ ―サラリーマン係長の異世界再建記―』
KAORUwithAI
ファンタジー
45歳、胃薬が手放せない大手総合商社営業部係長・佐藤悠真。
ある日、横断歩道で子供を助け、トラックに轢かれて死んでしまう。
目を覚ますと、目の前に現れたのは“おじさんっぽい神”。
「この世界を何とかしてほしい」と頼まれるが、悠真は「ただのサラリーマンに何ができる」と拒否。
しかし神は、「ならこの世界は三度目の滅びで終わりだな」と冷徹に突き放す。
結局、悠真は渋々承諾。
与えられたのは“現実知識”と“ワールドサーチ”――地球の知識すら検索できる探索魔法。
さらに肉体は20歳に若返り、滅びかけの異世界に送り込まれた。
衛生観念もなく、食糧も乏しく、二度の滅びで人々は絶望の淵にある。
だが、係長として培った経験と知識を武器に、悠真は人々をまとめ、再び世界を立て直そうと奮闘する。
――これは、“三度目の滅び”を阻止するために挑む、ひとりの中年係長の異世界再建記である。

凡夫転生〜異世界行ったらあまりにも普通すぎた件〜
小林一咲
ファンタジー
「普通がいちばん」と教え込まれてきた佐藤啓二は、日本の平均寿命である81歳で平凡な一生を終えた。
死因は癌だった。
癌による全死亡者を占める割合は24.6パーセントと第一位である。
そんな彼にも唯一「普通では無いこと」が起きた。
死後の世界へ導かれ、女神の御前にやってくると突然異世界への転生を言い渡される。
それも生前の魂、記憶や未来の可能性すらも次の世界へと引き継ぐと言うのだ。
啓二は前世でもそれなりにアニメや漫画を嗜んでいたが、こんな展開には覚えがない。
挙げ句の果てには「質問は一切受け付けない」と言われる始末で、あれよあれよという間に異世界へと転生を果たしたのだった。
インヒター王国の外、漁業が盛んな街オームで平凡な家庭に産まれ落ちた啓二は『バルト・クラスト』という新しい名を受けた。
そうして、しばらく経った頃に自身の平凡すぎるステータスとおかしなスキルがある事に気がつく――。
これはある平凡すぎる男が異世界へ転生し、その普通で非凡な力で人生を謳歌する物語である。

家庭菜園物語
コンビニ
ファンタジー
お人好しで動物好きな最上悠は肉親であった祖父が亡くなり、最後の家族であり姉のような存在でもある黒猫の杏も、寿命から静かに息を引き取ろうとする。
「助けたいなら異世界に来てくれない」と少し残念な神様と出会う。
転移先では半ば強引に、死にかけていた犬を助けたことで、能力を失いそのひっそりとスローライフを送ることになってしまうが
迷い込んだ、訪問者次々とやってきて異世界で新しい家族や友人を作り、本人としてはほのぼのと家庭菜園を営んでいるが、小さな畑が世界には大きな影響を与えることになっていく。

異世界転生したので森の中で静かに暮らしたい
ボナペティ鈴木
ファンタジー
異世界に転生することになったが勇者や賢者、チート能力なんて必要ない。
強靭な肉体さえあれば生きていくことができるはず。
ただただ森の中で静かに暮らしていきたい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















