46 / 84
4.魔王城の闇医者
14話
しおりを挟む
◇
町中の路地で出店の片付けが進む中、シオンは市場へと繰り出していた。
漁を終えて街へ戻ってきた漁師たちが一斉に市場へ魚や貝なんかを運び込んでいる。
この数日ですっかり慣れ親しんだこの光景ともしばしお別れとなる。
今日の昼には町を後にする予定なのだ。
しかし魔王城へ戻るその前に、もうひと働きしておきたい。
今後、ドランが作る魔道具を交易に出すとしたら、どのくらいの価格が相場なのか、想像できるように。
生鮮食品や衣料品、日用品や、一般的な武器防具の類を見て回り、片っ端からノートに価格を記録して回る。
魔王城に出入りする商人たちを疑う意図は無いのだが、やはり市場の相場を目視確認することは大切だと思う。
時々、美味しそうなお菓子や可愛らしいワンピースを見つけてうきうきと買い物をしていると、あっという間に時間が過ぎた。
「ふう……楽しい」
次に人里に降りてこれるのはいつなのかわからない。
この町のように、商売も盛んで賑やかなところともなればなおさらだ。
いつか、カイレンと遊びにこられたら、と想像するが、彼女の立派な獣耳を隠すのには苦労しそうだ。
メインストリートにびっしりと張られていた出店のテントがあっという間にたたまれていく。
時折ほんのり炭の匂いが残っているようで、あの美味しかった串焼きの味を思い出して頬が緩んだ。
すっかり祭りの装飾が外され、元の姿に戻っていく町の様子をきょろきょろと眺めながら歩く。
ここ数日の疲労で重たくなっていた足取りが、自然と軽やかなものになっていた。
「良かった……まだ、町にいたんですね!」
突如かけられた声に、シオンはどきりとして足を止める。
息を切らして走ってきたのは、昨日眠ったまま町へと運ばれたリヴィオだった。
「リヴィオさん……」
一瞬、どう振る舞うべきか迷う。
彼はどこまで、何を見たのだろうか。
そして、なぜあのとき、あそこにいたのだろうか。
晴れない疑問は数多く残っているが、シオンに向けられるリヴィオの表情は安堵の笑顔そのもので、邪険にするのは気が引けた。
言葉を交わすことを選択した代わりに、シオンは両手に張られた絆創膏を隠すようにそっと服の袖を伸ばした。
「リヴィオさん、こんにちは。体調は大丈夫ですか?」
「はい、どこも悪くありません。あの……少しだけ時間、いいですか?」
すっと真剣な顔になったリヴィオに、シオンは僅かに身構える。
ただ、そこに悪意や敵意は読み取れず、少しだけならと大人しく付き合うことにした。
◇
シオンは、リヴィオに連れられて再び町の高台を訪れていた。
オリヴィエの墓の前には、先日エリオルが飾った花のほかに、グラスに注がれた琥珀色の酒が供えられている。
「……家族に、うまいこと言ってくださってありがとうございます」
墓の周りの草を軽くむしりながら、リヴィオはシオンに礼を言った。
「大きな蜘蛛がこっちを見たところまでの記憶しかなくて……あなたたちが助けてくれたんですよね?」
そう言って振り返るリヴィオに、シオンは、ああ……と言葉を濁して笑った。
蜘蛛と対峙するレヴィアスの姿も見ていたのなら、シオン達が何者なのか、薄々わかっているのだろう。
「怖くて、私にもすごく大きく見えたような気がします。でも、討伐できたからもう大丈夫ですよ。」
普通サイズの土蜘蛛もほとんど見たことがないだろうリヴィオに、あれは恐怖のせいでちょっと大きく見えただけ、と刷り込む。
「はい、恥ずかしいんですが、とても大きく見えて竦んでしまいました」
と、リヴィオもすんなりそれを受け入れたようで、シオンは内心ほっとする。
さて、こちらからも確かめなければいけないことがある。
「私たちの後をついてきていたんですね?」
偶然立ち入る場所ではないし、町の人間が立ち入った形跡もない場所だ。
責める口調ではなく、純粋に理由を知りたい思いでリヴィオに尋ねる。
「ごめんなさい、僕……どうしても、崖の上の館に行きたかったんです」
しょんぼりと、叱られた子供のようにリヴィオは項垂れた。
「あなたたちが館を訪れていることはなんとなくわかっていました。何度か、馬で森から降りてくる様子も見ていましたから」
なるほど、先日薬草摘みをしていたリヴィオと出くわしたのが初めてだと思っていたが、どうやらそうではなかったらしい。
それでも、リヴィオの人懐こさは健在で、こちらを不審に思っている様子もない。
言っては何だが、あれだけ怪しい館に頻繁に出入りしている相手だというのに、だ。
「崖の上の館が何なのか、知っているんですか?」
シオンが尋ねると、リヴィオは少し困ったような顔をする。
それから息を一つ吐き、意を決したように口を開く。
「長い間、ヴァンパイアが住んでいるのだと聞いています。見た者はいないですから、噂だけ」
「……恐ろしくはないんですか? なぜ館に行きたかったの?」
シオンの問いかけにリヴィオは曖昧に微笑んで、オリヴィエの墓をひと撫でした。
「祖父が、大切にしていた思い出の場所だから、ですかね」
シオンは驚愕した。
いや、薄々そうではないかと思ってはいたのだ。
リヴィオは、オリヴィエとシンシアの関係性を知っている。
「オリヴィエさんの、思い出の場所……彼がそう言っていたんですか?」
「はい、家族の中では僕だけに、よく昔話をしてくれました」
昔話。
その言葉にシオンの胸はつきんと痛む。
オリヴィエの話をする時のシンシアの表情は、昔話と呼ぶにはあまりに生々しいものだった。
それこそ、傷があるならばまだ僅かに血がにじんでいるのではないかという程に。
シオンはそっと胸元に手を寄せる。
魔物と人間の過ごす時間の違いを見せつけられたような心地がしたのだ。
「ご存知かもしれませんが、祖父は館の主人と共に長年研究をしていました。解剖学から、魔法薬づくりまで沢山のことを」
シオンの脳裏に、シンシアの館で見た異様な生き物たちの影が浮かび、背筋が凍った。
……しかし、リヴィオの表情はいたって穏やかだ。
まるで祖父が大切にしまっていた温かい思い出を、そっと取り出して語るような。
そんな様子に、シオンは強烈な違和感を覚えた。
「ある頃から、祖父が体調を崩して、なかなか館に向かうことができなくなってしまったそうで……そんなさなかに町では疫病が流行り出しました」
「オリヴィエさんが町で称えられるようになった出来事ですね」
リヴィオはこくりと頷く。
あまり、嬉しくはなさそうに見えた。
「疫病は海の外から持ち込まれたものでしたが、当時は大混乱で。呪いだとか、魔物が撒き散らした災いに違いないとか、有る事無い事叫ぶ人たちも多かったようです。それで、館の主に危害が及んだら、と思うと、とても出向くことができなかった、と」
これから、のめり込むようにオリヴィエは疫病の特効薬の研究に打ち込んだ。
それによって町は危機から脱することができたのだとリヴィオはぽつぽつ語った。
「祖父が急に育て始めた花も、もしかしたら館の主への贈り物なのかなって」
夢、見過ぎですかね?とリヴィオが笑う。
シオンには、それを肯定も否定もすることは出来なかった。
晩年のオリヴィエの心に残った、美しい上澄みの部分を、まるで童話のようにリヴィオに語って聞かせたのかもしれない。
それでも、故人が描いていた情景を、美しいままに信じたい自分もいたからだ。
リヴィオは、どこか熱に浮かされたような瞳をゆっくりと閉じる。
それからひと呼吸おいて、シオンに問いかけた。
「館の主に、会うことはできるでしょうか?」
ふわり、と潮の香りを纏った風が吹き抜けた。
「……残念だけど、館の主はとっくに去ったわよ」
突然、背後から響いた少し低い女性の声。
驚いて、シオンは勢いよく振り向いた。
ローブのフードを目深に被った、金髪の女性。
……シンシアが、そこに立っていた。
「あの、あなたは?」
リヴィオが怪訝な顔をして尋ねる。
風に揺れるフードの隙間から僅かにシンシアの瞳が見えたが、その表情までは窺い知れない。
「廃墟や洞窟なんかを巡っている冒険者よ。」
そう言いながら、シンシアは胸元から一本の万年筆を取り出して、オリヴィエの墓の前にことりと置いた。
リヴィオはその万年筆をじっくりと眺め、すっかり薄くなった名入れ部分を見て呟いた。
「これは……祖父の?」
「金目のものはあらかた頂戴したけど、これは名前が彫ってあったんでね」
シンシアはこともなげにそう言いながら、取り出したパイプに火をつけて、ゆっくりと煙を吐いた。
リヴィオは困惑した様子でシオンに視線を向けてくる。
突然現れたシンシアの意図が読めない。
それでも、彼女に話を合わせたほうが良いのだろうと、シオンはリヴィオの視線に応えた。
「この人の言う通り。私たちは館の主を何度か訪ねたのだけれど、もうあそこには誰もいなかったの」
リヴィオは目に見えて落胆した顔をして、そうですか、と呟いた。
青年の冒険の芽を摘んだようで心が痛んだが、先ほど一瞬チラリとこちらを見たシンシアの目は厳しく、覚悟の色すら滲んでいた。
シオンには、それを無碍にすることができなかったのだ。
「もう、何十年も前の話ですもんね。……祖父が亡くなる前に言ったんです。もらった命の礼を伝えられなかった、って」
ぴくりとシンシアのまつ毛が震える。
リヴィオはそれには気が付かなかった様子で勢いよく伸びをすると、シオンたちに笑顔を向けた。
「すみません、時間をとらせてしまって。諦めがつきました」
◇
礼を言って去っていったリヴィオの背中を眺めながら、シオンは言葉を探していた。
シンシアは、何も言わずにオリヴィエの墓前に佇んでいる。
「……その、良かったんですか? リヴィオさんはオリヴィエさんの研究を継ぎたかったんだと思います」
「あなた本当におめでたい子ね。忘れたの? 私は魔王城を追われるような研究してたんだって」
「う……それは、そうなんですけど」
館で見た光景を再び思い出し、ぶるりと身震いする。
そう言われてしまうと、研究に没頭していたオリヴィエの印象にも狂気が影を落とし、印象が大きく変わる。
にゃん、と小さな鳴き声と共に、シンシアのローブから黒猫が飛び出した。
「あら、あなたもいたの?」
シオンが恐る恐る黒猫に話しかける。
ちらりと見える腹毛の途切れ目からは、やはり蛇の鱗の輝きが感じ取れた。
ひとつの体から、ふたつの生命の息づかいが聞こえる気がする。
やはりその姿は異形のものに思えた。
黒猫の喉元を指先でころころとくすぐりながら、シンシアはぽつりと呟いた。
「もらった命の礼だなんて、本当に呑気な男」
何をされたのかも知らずにね。とシンシアは黒猫に語り掛けた。
猫はただ、にゃあと鳴く。
「シンシアさんが、オリヴィエさんを助けたってことですか?」
そう言いながら、シオンも黒猫にそっと手を伸ばす。
猫はピンクの舌を出して、シオンの指先をぺろりと舐めた。
「どうかしてたのよ。たまたま一緒に研究をしていた変わり者の人間が、目の前で病に倒れた。だからね」
シンシアの瞳に、ほの暗い色が宿る。
「つくってあげたの」
――決して壊れない、心臓。
そういう彼女の微笑みは、人間離れした美しさと、狂気を湛えていた。
それから、ひと匙の後悔も。
「ただそれだけ。オリヴィエは何も知らない。あの男の命は、ただ私に弄ばれたのよ」
シンシアは猫を胸に抱き、その鼻先にキスをする。
もしかしたらこの猫は、彼女たちの関係の生き証人なのだろうか。
猫の腹部を半分に切り付けるかのように、ばっくり裂けた傷状に走る蛇の肌。
仮にそれが猫の体を覆っていなかったならば、この猫は今生きてはいないのかもしれない。
「身内が化け物にされて喜んでる孫なんて、滑稽だわね」
ローブの裾を翻して数歩歩きだしてから、思い出したようにシンシアがこちらを振り返る。
「蜘蛛の死骸は魔王城で保管するように伝えて頂戴。私が切り刻んであげる」
そう言って、シンシアは高台からゆっくりと姿を消した。
後姿を見送りながら、シオンはそっと目を閉じる。
心臓をオリヴィエに与えた後、シンシアが館を閉ざして眠りについたのは何故だろう?
シオンが感じ取ることが出来たのは、彼女の罪悪感と絶望だった。
時を同じくして、彼女は魔王城で過激な研究を繰り返し、バルドラッドによって城を追われている。
クレバーな彼女が、なりふり構わず研究を重ねたのは、彼の命への執着がそうさせたのではないかと思えてならなかった。
オリヴィエは、本当に何も知らなかったのだろうか。
シンシアの館の前に植えられた、あの見事な紫色の花は、誰が手入れし続けていたのだろう。
長い眠りにつくシンシアのことを想いながら。
(勝手な、きれいな妄想だけれど……)
いつの間にかオリヴィエの墓前に供えられたワインのボトルに目を引かれる。
それはよく見れば半分飲みかけで、墓前に供えるにはふさわしくないようにも思える。
「素直じゃないなあ……」
一本のワインボトルを分け合ってグラスを傾けていた二人の姿が、深い赤色の液体の向こう側に見えた気がした。
町中の路地で出店の片付けが進む中、シオンは市場へと繰り出していた。
漁を終えて街へ戻ってきた漁師たちが一斉に市場へ魚や貝なんかを運び込んでいる。
この数日ですっかり慣れ親しんだこの光景ともしばしお別れとなる。
今日の昼には町を後にする予定なのだ。
しかし魔王城へ戻るその前に、もうひと働きしておきたい。
今後、ドランが作る魔道具を交易に出すとしたら、どのくらいの価格が相場なのか、想像できるように。
生鮮食品や衣料品、日用品や、一般的な武器防具の類を見て回り、片っ端からノートに価格を記録して回る。
魔王城に出入りする商人たちを疑う意図は無いのだが、やはり市場の相場を目視確認することは大切だと思う。
時々、美味しそうなお菓子や可愛らしいワンピースを見つけてうきうきと買い物をしていると、あっという間に時間が過ぎた。
「ふう……楽しい」
次に人里に降りてこれるのはいつなのかわからない。
この町のように、商売も盛んで賑やかなところともなればなおさらだ。
いつか、カイレンと遊びにこられたら、と想像するが、彼女の立派な獣耳を隠すのには苦労しそうだ。
メインストリートにびっしりと張られていた出店のテントがあっという間にたたまれていく。
時折ほんのり炭の匂いが残っているようで、あの美味しかった串焼きの味を思い出して頬が緩んだ。
すっかり祭りの装飾が外され、元の姿に戻っていく町の様子をきょろきょろと眺めながら歩く。
ここ数日の疲労で重たくなっていた足取りが、自然と軽やかなものになっていた。
「良かった……まだ、町にいたんですね!」
突如かけられた声に、シオンはどきりとして足を止める。
息を切らして走ってきたのは、昨日眠ったまま町へと運ばれたリヴィオだった。
「リヴィオさん……」
一瞬、どう振る舞うべきか迷う。
彼はどこまで、何を見たのだろうか。
そして、なぜあのとき、あそこにいたのだろうか。
晴れない疑問は数多く残っているが、シオンに向けられるリヴィオの表情は安堵の笑顔そのもので、邪険にするのは気が引けた。
言葉を交わすことを選択した代わりに、シオンは両手に張られた絆創膏を隠すようにそっと服の袖を伸ばした。
「リヴィオさん、こんにちは。体調は大丈夫ですか?」
「はい、どこも悪くありません。あの……少しだけ時間、いいですか?」
すっと真剣な顔になったリヴィオに、シオンは僅かに身構える。
ただ、そこに悪意や敵意は読み取れず、少しだけならと大人しく付き合うことにした。
◇
シオンは、リヴィオに連れられて再び町の高台を訪れていた。
オリヴィエの墓の前には、先日エリオルが飾った花のほかに、グラスに注がれた琥珀色の酒が供えられている。
「……家族に、うまいこと言ってくださってありがとうございます」
墓の周りの草を軽くむしりながら、リヴィオはシオンに礼を言った。
「大きな蜘蛛がこっちを見たところまでの記憶しかなくて……あなたたちが助けてくれたんですよね?」
そう言って振り返るリヴィオに、シオンは、ああ……と言葉を濁して笑った。
蜘蛛と対峙するレヴィアスの姿も見ていたのなら、シオン達が何者なのか、薄々わかっているのだろう。
「怖くて、私にもすごく大きく見えたような気がします。でも、討伐できたからもう大丈夫ですよ。」
普通サイズの土蜘蛛もほとんど見たことがないだろうリヴィオに、あれは恐怖のせいでちょっと大きく見えただけ、と刷り込む。
「はい、恥ずかしいんですが、とても大きく見えて竦んでしまいました」
と、リヴィオもすんなりそれを受け入れたようで、シオンは内心ほっとする。
さて、こちらからも確かめなければいけないことがある。
「私たちの後をついてきていたんですね?」
偶然立ち入る場所ではないし、町の人間が立ち入った形跡もない場所だ。
責める口調ではなく、純粋に理由を知りたい思いでリヴィオに尋ねる。
「ごめんなさい、僕……どうしても、崖の上の館に行きたかったんです」
しょんぼりと、叱られた子供のようにリヴィオは項垂れた。
「あなたたちが館を訪れていることはなんとなくわかっていました。何度か、馬で森から降りてくる様子も見ていましたから」
なるほど、先日薬草摘みをしていたリヴィオと出くわしたのが初めてだと思っていたが、どうやらそうではなかったらしい。
それでも、リヴィオの人懐こさは健在で、こちらを不審に思っている様子もない。
言っては何だが、あれだけ怪しい館に頻繁に出入りしている相手だというのに、だ。
「崖の上の館が何なのか、知っているんですか?」
シオンが尋ねると、リヴィオは少し困ったような顔をする。
それから息を一つ吐き、意を決したように口を開く。
「長い間、ヴァンパイアが住んでいるのだと聞いています。見た者はいないですから、噂だけ」
「……恐ろしくはないんですか? なぜ館に行きたかったの?」
シオンの問いかけにリヴィオは曖昧に微笑んで、オリヴィエの墓をひと撫でした。
「祖父が、大切にしていた思い出の場所だから、ですかね」
シオンは驚愕した。
いや、薄々そうではないかと思ってはいたのだ。
リヴィオは、オリヴィエとシンシアの関係性を知っている。
「オリヴィエさんの、思い出の場所……彼がそう言っていたんですか?」
「はい、家族の中では僕だけに、よく昔話をしてくれました」
昔話。
その言葉にシオンの胸はつきんと痛む。
オリヴィエの話をする時のシンシアの表情は、昔話と呼ぶにはあまりに生々しいものだった。
それこそ、傷があるならばまだ僅かに血がにじんでいるのではないかという程に。
シオンはそっと胸元に手を寄せる。
魔物と人間の過ごす時間の違いを見せつけられたような心地がしたのだ。
「ご存知かもしれませんが、祖父は館の主人と共に長年研究をしていました。解剖学から、魔法薬づくりまで沢山のことを」
シオンの脳裏に、シンシアの館で見た異様な生き物たちの影が浮かび、背筋が凍った。
……しかし、リヴィオの表情はいたって穏やかだ。
まるで祖父が大切にしまっていた温かい思い出を、そっと取り出して語るような。
そんな様子に、シオンは強烈な違和感を覚えた。
「ある頃から、祖父が体調を崩して、なかなか館に向かうことができなくなってしまったそうで……そんなさなかに町では疫病が流行り出しました」
「オリヴィエさんが町で称えられるようになった出来事ですね」
リヴィオはこくりと頷く。
あまり、嬉しくはなさそうに見えた。
「疫病は海の外から持ち込まれたものでしたが、当時は大混乱で。呪いだとか、魔物が撒き散らした災いに違いないとか、有る事無い事叫ぶ人たちも多かったようです。それで、館の主に危害が及んだら、と思うと、とても出向くことができなかった、と」
これから、のめり込むようにオリヴィエは疫病の特効薬の研究に打ち込んだ。
それによって町は危機から脱することができたのだとリヴィオはぽつぽつ語った。
「祖父が急に育て始めた花も、もしかしたら館の主への贈り物なのかなって」
夢、見過ぎですかね?とリヴィオが笑う。
シオンには、それを肯定も否定もすることは出来なかった。
晩年のオリヴィエの心に残った、美しい上澄みの部分を、まるで童話のようにリヴィオに語って聞かせたのかもしれない。
それでも、故人が描いていた情景を、美しいままに信じたい自分もいたからだ。
リヴィオは、どこか熱に浮かされたような瞳をゆっくりと閉じる。
それからひと呼吸おいて、シオンに問いかけた。
「館の主に、会うことはできるでしょうか?」
ふわり、と潮の香りを纏った風が吹き抜けた。
「……残念だけど、館の主はとっくに去ったわよ」
突然、背後から響いた少し低い女性の声。
驚いて、シオンは勢いよく振り向いた。
ローブのフードを目深に被った、金髪の女性。
……シンシアが、そこに立っていた。
「あの、あなたは?」
リヴィオが怪訝な顔をして尋ねる。
風に揺れるフードの隙間から僅かにシンシアの瞳が見えたが、その表情までは窺い知れない。
「廃墟や洞窟なんかを巡っている冒険者よ。」
そう言いながら、シンシアは胸元から一本の万年筆を取り出して、オリヴィエの墓の前にことりと置いた。
リヴィオはその万年筆をじっくりと眺め、すっかり薄くなった名入れ部分を見て呟いた。
「これは……祖父の?」
「金目のものはあらかた頂戴したけど、これは名前が彫ってあったんでね」
シンシアはこともなげにそう言いながら、取り出したパイプに火をつけて、ゆっくりと煙を吐いた。
リヴィオは困惑した様子でシオンに視線を向けてくる。
突然現れたシンシアの意図が読めない。
それでも、彼女に話を合わせたほうが良いのだろうと、シオンはリヴィオの視線に応えた。
「この人の言う通り。私たちは館の主を何度か訪ねたのだけれど、もうあそこには誰もいなかったの」
リヴィオは目に見えて落胆した顔をして、そうですか、と呟いた。
青年の冒険の芽を摘んだようで心が痛んだが、先ほど一瞬チラリとこちらを見たシンシアの目は厳しく、覚悟の色すら滲んでいた。
シオンには、それを無碍にすることができなかったのだ。
「もう、何十年も前の話ですもんね。……祖父が亡くなる前に言ったんです。もらった命の礼を伝えられなかった、って」
ぴくりとシンシアのまつ毛が震える。
リヴィオはそれには気が付かなかった様子で勢いよく伸びをすると、シオンたちに笑顔を向けた。
「すみません、時間をとらせてしまって。諦めがつきました」
◇
礼を言って去っていったリヴィオの背中を眺めながら、シオンは言葉を探していた。
シンシアは、何も言わずにオリヴィエの墓前に佇んでいる。
「……その、良かったんですか? リヴィオさんはオリヴィエさんの研究を継ぎたかったんだと思います」
「あなた本当におめでたい子ね。忘れたの? 私は魔王城を追われるような研究してたんだって」
「う……それは、そうなんですけど」
館で見た光景を再び思い出し、ぶるりと身震いする。
そう言われてしまうと、研究に没頭していたオリヴィエの印象にも狂気が影を落とし、印象が大きく変わる。
にゃん、と小さな鳴き声と共に、シンシアのローブから黒猫が飛び出した。
「あら、あなたもいたの?」
シオンが恐る恐る黒猫に話しかける。
ちらりと見える腹毛の途切れ目からは、やはり蛇の鱗の輝きが感じ取れた。
ひとつの体から、ふたつの生命の息づかいが聞こえる気がする。
やはりその姿は異形のものに思えた。
黒猫の喉元を指先でころころとくすぐりながら、シンシアはぽつりと呟いた。
「もらった命の礼だなんて、本当に呑気な男」
何をされたのかも知らずにね。とシンシアは黒猫に語り掛けた。
猫はただ、にゃあと鳴く。
「シンシアさんが、オリヴィエさんを助けたってことですか?」
そう言いながら、シオンも黒猫にそっと手を伸ばす。
猫はピンクの舌を出して、シオンの指先をぺろりと舐めた。
「どうかしてたのよ。たまたま一緒に研究をしていた変わり者の人間が、目の前で病に倒れた。だからね」
シンシアの瞳に、ほの暗い色が宿る。
「つくってあげたの」
――決して壊れない、心臓。
そういう彼女の微笑みは、人間離れした美しさと、狂気を湛えていた。
それから、ひと匙の後悔も。
「ただそれだけ。オリヴィエは何も知らない。あの男の命は、ただ私に弄ばれたのよ」
シンシアは猫を胸に抱き、その鼻先にキスをする。
もしかしたらこの猫は、彼女たちの関係の生き証人なのだろうか。
猫の腹部を半分に切り付けるかのように、ばっくり裂けた傷状に走る蛇の肌。
仮にそれが猫の体を覆っていなかったならば、この猫は今生きてはいないのかもしれない。
「身内が化け物にされて喜んでる孫なんて、滑稽だわね」
ローブの裾を翻して数歩歩きだしてから、思い出したようにシンシアがこちらを振り返る。
「蜘蛛の死骸は魔王城で保管するように伝えて頂戴。私が切り刻んであげる」
そう言って、シンシアは高台からゆっくりと姿を消した。
後姿を見送りながら、シオンはそっと目を閉じる。
心臓をオリヴィエに与えた後、シンシアが館を閉ざして眠りについたのは何故だろう?
シオンが感じ取ることが出来たのは、彼女の罪悪感と絶望だった。
時を同じくして、彼女は魔王城で過激な研究を繰り返し、バルドラッドによって城を追われている。
クレバーな彼女が、なりふり構わず研究を重ねたのは、彼の命への執着がそうさせたのではないかと思えてならなかった。
オリヴィエは、本当に何も知らなかったのだろうか。
シンシアの館の前に植えられた、あの見事な紫色の花は、誰が手入れし続けていたのだろう。
長い眠りにつくシンシアのことを想いながら。
(勝手な、きれいな妄想だけれど……)
いつの間にかオリヴィエの墓前に供えられたワインのボトルに目を引かれる。
それはよく見れば半分飲みかけで、墓前に供えるにはふさわしくないようにも思える。
「素直じゃないなあ……」
一本のワインボトルを分け合ってグラスを傾けていた二人の姿が、深い赤色の液体の向こう側に見えた気がした。
0
あなたにおすすめの小説

凡夫転生〜異世界行ったらあまりにも普通すぎた件〜
小林一咲
ファンタジー
「普通がいちばん」と教え込まれてきた佐藤啓二は、日本の平均寿命である81歳で平凡な一生を終えた。
死因は癌だった。
癌による全死亡者を占める割合は24.6パーセントと第一位である。
そんな彼にも唯一「普通では無いこと」が起きた。
死後の世界へ導かれ、女神の御前にやってくると突然異世界への転生を言い渡される。
それも生前の魂、記憶や未来の可能性すらも次の世界へと引き継ぐと言うのだ。
啓二は前世でもそれなりにアニメや漫画を嗜んでいたが、こんな展開には覚えがない。
挙げ句の果てには「質問は一切受け付けない」と言われる始末で、あれよあれよという間に異世界へと転生を果たしたのだった。
インヒター王国の外、漁業が盛んな街オームで平凡な家庭に産まれ落ちた啓二は『バルト・クラスト』という新しい名を受けた。
そうして、しばらく経った頃に自身の平凡すぎるステータスとおかしなスキルがある事に気がつく――。
これはある平凡すぎる男が異世界へ転生し、その普通で非凡な力で人生を謳歌する物語である。
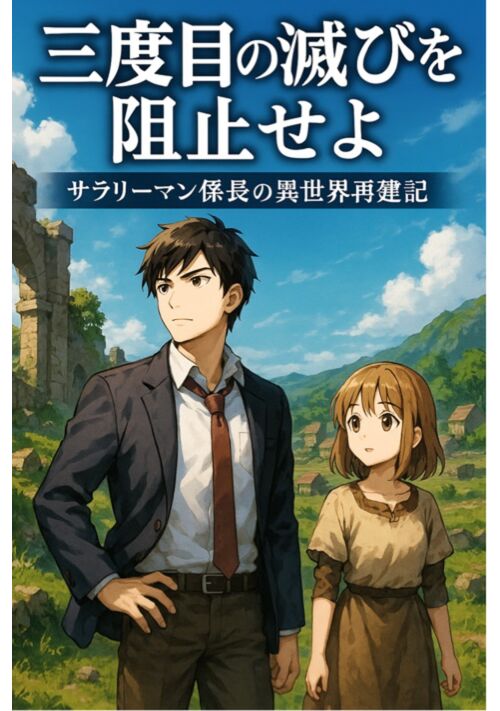
『三度目の滅びを阻止せよ ―サラリーマン係長の異世界再建記―』
KAORUwithAI
ファンタジー
45歳、胃薬が手放せない大手総合商社営業部係長・佐藤悠真。
ある日、横断歩道で子供を助け、トラックに轢かれて死んでしまう。
目を覚ますと、目の前に現れたのは“おじさんっぽい神”。
「この世界を何とかしてほしい」と頼まれるが、悠真は「ただのサラリーマンに何ができる」と拒否。
しかし神は、「ならこの世界は三度目の滅びで終わりだな」と冷徹に突き放す。
結局、悠真は渋々承諾。
与えられたのは“現実知識”と“ワールドサーチ”――地球の知識すら検索できる探索魔法。
さらに肉体は20歳に若返り、滅びかけの異世界に送り込まれた。
衛生観念もなく、食糧も乏しく、二度の滅びで人々は絶望の淵にある。
だが、係長として培った経験と知識を武器に、悠真は人々をまとめ、再び世界を立て直そうと奮闘する。
――これは、“三度目の滅び”を阻止するために挑む、ひとりの中年係長の異世界再建記である。

『規格外の薬師、追放されて辺境スローライフを始める。〜作ったポーションが国家機密級なのは秘密です〜』
雛月 らん
ファンタジー
俺、黒田 蓮(くろだ れん)35歳は前世でブラック企業の社畜だった。過労死寸前で倒れ、次に目覚めたとき、そこは剣と魔法の異世界。しかも、幼少期の俺は、とある大貴族の私生児、アレン・クロイツェルとして生まれ変わっていた。
前世の記憶と、この世界では「外れスキル」とされる『万物鑑定』と『薬草栽培(ハイレベル)』。そして、誰にも知られていない規格外の莫大な魔力を持っていた。
しかし、俺は決意する。「今世こそ、誰にも邪魔されない、のんびりしたスローライフを送る!」と。
これは、スローライフを死守したい天才薬師のアレンと、彼の作る規格外の薬に振り回される異世界の物語。
平穏を愛する(自称)凡人薬師の、のんびりだけど実は波乱万丈な辺境スローライフファンタジー。

異世界でゆるゆるスローライフ!~小さな波乱とチートを添えて~
イノナかノかワズ
ファンタジー
助けて、刺されて、死亡した主人公。神様に会ったりなんやかんやあったけど、社畜だった前世から一転、ゆるいスローライフを送る……筈であるが、そこは知識チートと能力チートを持った主人公。波乱に巻き込まれたりしそうになるが、そこはのんびり暮らしたいと持っている主人公。波乱に逆らい、世界に名が知れ渡ることはなくなり、知る人ぞ知る感じに収まる。まぁ、それは置いといて、主人公の新たな人生は、温かな家族とのんびりした自然、そしてちょっとした研究生活が彩りを与え、幸せに溢れています。
*話はとてもゆっくりに進みます。また、序盤はややこしい設定が多々あるので、流しても構いません。
*他の小説や漫画、ゲームの影響が見え隠れします。作者の願望も見え隠れします。ご了承下さい。
*頑張って週一で投稿しますが、基本不定期です。
*本作の無断転載、無断翻訳、無断利用を禁止します。
小説家になろうにて先行公開中です。主にそっちを優先して投稿します。
カクヨムにても公開しています。
更新は不定期です。

転生したみたいなので異世界生活を楽しみます
さっちさん
ファンタジー
又々、題名変更しました。
内容がどんどんかけ離れていくので…
沢山のコメントありがとうございます。対応出来なくてすいません。
誤字脱字申し訳ございません。気がついたら直していきます。
感傷的表現は無しでお願いしたいと思います😢
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ありきたりな転生ものの予定です。
主人公は30代後半で病死した、天涯孤独の女性が幼女になって冒険する。
一応、転生特典でスキルは貰ったけど、大丈夫か。私。
まっ、なんとかなるっしょ。

高校生の俺、異世界転移していきなり追放されるが、じつは最強魔法使い。可愛い看板娘がいる宿屋に拾われたのでもう戻りません
下昴しん
ファンタジー
高校生のタクトは部活帰りに突然異世界へ転移してしまう。
横柄な態度の王から、魔法使いはいらんわ、城から出ていけと言われ、いきなり無職になったタクト。
偶然会った宿屋の店長トロに仕事をもらい、看板娘のマロンと一緒に宿と食堂を手伝うことに。
すると突然、客の兵士が暴れだし宿はメチャクチャになる。
兵士に殴り飛ばされるトロとマロン。
この世界の魔法は、生活で利用する程度の威力しかなく、とても弱い。
しかし──タクトの魔法は人並み外れて、無法者も脳筋男もひれ伏すほど強かった。

転生魔竜~異世界ライフを謳歌してたら世界最強最悪の覇者となってた?~
アズドラ
ファンタジー
主人公タカトはテンプレ通り事故で死亡、運よく異世界転生できることになり神様にドラゴンになりたいとお願いした。 夢にまで見た異世界生活をドラゴンパワーと現代地球の知識で全力満喫! 仲間を増やして夢を叶える王道、テンプレ、モリモリファンタジー。

家庭菜園物語
コンビニ
ファンタジー
お人好しで動物好きな最上悠は肉親であった祖父が亡くなり、最後の家族であり姉のような存在でもある黒猫の杏も、寿命から静かに息を引き取ろうとする。
「助けたいなら異世界に来てくれない」と少し残念な神様と出会う。
転移先では半ば強引に、死にかけていた犬を助けたことで、能力を失いそのひっそりとスローライフを送ることになってしまうが
迷い込んだ、訪問者次々とやってきて異世界で新しい家族や友人を作り、本人としてはほのぼのと家庭菜園を営んでいるが、小さな畑が世界には大きな影響を与えることになっていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















