2 / 30
2
しおりを挟む
儀式によって降り始めた雨は、一時間ほどで止んだ。
後にはすっかり水で満たされた泉と、立ち尽くすアルフレッドが残された。
「お嬢様……今のは、いったい……?」
アルフレッドが、信じられないものを見るような目で私を見つめてくる。
彼の驚きも無理はない。何十年も枯れていた泉が、私の指示でよみがえったのだから。
「言ったでしょう?水が湧くかもしれないって」
私は、いたずらっぽく笑ってみせる。
本当の仕組みを説明したところで、彼には理解できないだろう。
化学反応や上昇気流なんて言っても、首をかしげられるだけだ。
「しかし……まるで、魔法のようでございました」
「そうね。古い時代の魔法、と言えるかもしれないわね」
私はそう言って、話をはぐらかした。
民俗学は、時に魔法と呼ばれる現象を解き明かす学問だ。
人々が奇跡や呪いと信じていたものが、実は合理的な知識に基づいていたことは珍しくない。
「さあ、冷えてしまうわ。小屋に戻って着替えましょう。アルフレッドも、風邪をひいてしまうわよ」
私たちは濡れた服のまま、小屋へと戻った。
幸い、持ってきていた荷物の中に着替えはあった。
乾いた服に着替えると、ようやく人心地がついた気がする。
アルフレッドは、火を起こして簡単なスープを作ってくれた。
干し肉と固いパンだけの夕食だったけれど、今日の成功を祝うには十分だった。
温かいスープが、冷えた体にじんわりとしみ渡っていく。
「お嬢様は、一体何者なのでございますか?」
スープを飲みながら、アルフレッドがぽつりと言った。
その表情は、おそれと好奇が入り混じったような複雑な色を浮かべている。
「何者って、私はリゼット・ヴァインベルクよ。あなたの知っている通りだわ」
「ですが、先ほどの御業はとても貴族の御令嬢がご存じのこととは思えません」
「うーん、昔から古い言い伝えとかに興味があって色々と本を読んでいただけよ」
もちろん、うそだ。
この世界の書物で、あんな古代技術について学べるはずがない。
だけど、前世の知識について話すわけにもいかなかった。
幸い、アルフレッドはそれ以上聞いてはこなかった。
彼はただ私の顔をじっと見つめ、やがて深々と頭を下げた。
「どのようなお力かは存じませんが、私はお嬢様にお仕えできて光栄にございます。このアルフレッド、生涯をかけてお嬢様をお守りいたします」
彼のまっすぐな言葉に、私は少しだけ胸が熱くなった。
王都の家では、誰も私を認めてくれなかった。
それがここでは、まだ初日なのにこんなにも忠誠を捧げてくれる人がいる。
「ありがとう、アルフレッド。これからもよろしくね」
その夜、私は久しぶりにぐっすりと眠ることができた。
王都の屋敷の豪華なベッドよりも、この固くて小さなベッドの方がずっと心地よかった。
翌朝、私は早速次の計画に取り掛かることにした。
水は確保できた。次は食料だ。
この痩せた土地で、どうやって作物を育てるか。
「アルフレッド、この辺りに村はあるのかしら?」
朝食をとりながら尋ねると、彼はうなずいた。
「はい。ここから東に半日ほど歩いた場所に、小さな村が一つございます。ですが、非常に貧しい村でして」
「そこに住んでいる人たちに、話を聞いてみたいの。この土地に伝わる古い話とか、変わった風習とか何でもいいから」
「言い伝え、でございますか」
「ええ。きっと、この土地を豊かにするヒントが隠されているはずよ」
私の言葉に、アルフレッドはまた不思議そうな顔をした。
しかし今度は何も言わずに、うなずいてくれた。
彼はもう、私の言うことには何か特別な意味があると信じ始めているようだった。
私たちは簡単な準備を済ませ、アルフレッドが言う村へと向かった。
道中は、昨日見たのと同じような荒れ地が続いている。
土は乾燥してひび割れ、生えている草もまばらだ。
これでは、まともな作物が育つはずもない。
半日ほど歩くと、前方に数軒の家が集まっているのが見えてきた。
あれが村だろう。しかし近づくにつれて、そのあまりの寂れ具合に言葉を失った。
家はどれも崩れかけており、畑らしき場所も石ころだらけで耕されていない。
村を歩いている人々の顔にも、生気がなかった。
痩せて汚れた服を着た彼らは、私たちのような人間が現れたことに驚き警戒しているようだった。
「こんにちは」
私が声をかけると、近くにいた老婆がびくりと肩を震わせ家の中に引っ込んでしまった。
他の村人たちも、遠巻きに私たちを見ているだけで誰も近づいてこようとしない。
「困ったわね……」
これでは、話を聞くどころではない。
どうしたものかと思っていると、一人の若者がおずおずとこちらに近づいてきた。
「あんたたち、役人か。もう、取るものなんて何もねえぞ」
若者は、私たちを税の取り立てに来た役人だと思っているらしい。
その目には、深い絶望と不信感が浮かんでいた。
「いいえ、違うわ。私はリゼット。今日から、この土地の管理を任されることになったの」
私の自己紹介に、若者は不思議な顔をした。
「管理だあ?こんな土地を、好きで管理する奴がいるのかよ」
「ええ。これから、この土地を少しでも住みやすくしたいと思っているの。だから、あなたたちの力を貸してほしい」
「力を貸す、だあ?冗談だろ。俺たちに何ができるってんだ」
若者は、吐き捨てるように言った。
彼の言う通りかもしれない。長年の貧しい生活が、彼らから希望を奪ってしまったのだろう。
言葉だけでは、彼らの心を開くことはできない。
必要なのは、目に見える結果だ。
「昨日の夕方、この辺りで雨が降らなかった?」
私は、話題を変えてみた。
若者は一瞬きょとんとした後、思い出したようにうなずいた。
「ああ、そういや降ったな。妙な雨だったぜ。空は晴れてんのに、あの丘の辺りだけいきなり土砂降りになったんだ」
「その雨を降らせたのが、私だと言ったら信じる?」
私の言葉に、若者だけでなく遠巻きに見ていた村人たちもざわめき始めた。
「何を言ってるんだこの女は」「頭がおかしいんじゃないのか」そんな声が聞こえてくる。
若者は、私を馬鹿にしたように鼻で笑った。
「あんたが?面白い冗談を言うじゃねえか。そんなことができるなら、今すぐこの畑に作物を実らせてみろよ」
彼はそう言って、足元の石ころだらけの畑を指差した。
その挑発するような態度に、隣にいたアルフレッドが何か言おうとした。
私は、それを手で制した。
「いいわ。ただし、少し時間がかかるしあなたたちの協力も必要よ」
「協力?」
「ええ。まず、この土地に伝わる古い話を聞かせてほしいの。昔の畑仕事のやり方とか、お祭りのこととか何でもいいわ」
私の提案に、若者はますます意味がわからないという顔をした。
しかし彼の後ろにいた村人の中から、一人の老人がゆっくりと前に出てきた。
「わしなら、少しは知っておるが……」
その老人は、村の長老らしかった。
深く刻まれたしわと、にごっているが鋭い光を宿したひとみが印象的だ。
「本当?ぜひ聞かせてちょうだい」
「あんた様は、本当にこの土地を豊かにしてくださるのか」
「ええ、約束するわ」
私は長老の目を真っ直ぐに見つめて、はっきりと答えた。
私のひとみに何かを見出したのか、長老はしばらく黙って私を見つめ返した。
そして、ゆっくりとうなずいた。
「……わかった。話せることは、話そう。ついてきなされ」
長老はそう言って、村で一番大きな家へ私たちを案内してくれた。
若者や他の村人たちも、興味を引かれたのかぞろぞろと後についてくる。
家の中は薄暗く、質素な木のテーブルと椅子があるだけだった。
長老は私たちに席をすすめ、自身もゆっくりと腰を下ろした。
「この土地にはな、昔から伝わる奇妙な言い伝えがあるんじゃ」
長老は、ゆっくりとした口調で語り始めた。
「『土を眠らせ、火で起こせ』。畑を耕す前に、必ずそう唱えるようにと先祖代々言い伝えられておる」
「土を眠らせ、火で起こせ……?」
私は、その言葉を繰り返した。
一見すると、意味のわからないおまじないのように聞こえる。
「はい。ですが、今ではただの形式じゃ。そんなことをしても、作物が育つわけでもないからのう」
長老は、自分を笑うように言った。
だが私の頭の中では、忘れられていた知識の断片がつながり始めていた。
「その『火で起こす』というのは、具体的に何をするの?」
「畑に、特定の草を燃やした灰をまくんじゃよ。『龍の髭』と呼ばれる、赤い穂先を持つ草じゃな」
龍の髭、という名前に私はピンときた。
昨日、泉の周りでも見かけた植物だ。
前世の知識によれば、あの植物は根に特殊なバクテリアを共生させている。
そして、空気中の窒素を土に固定する能力を持っていた。
その草を燃やしてできる灰は、カリウムをたくさん含んでいる。
窒素とカリウムは、どちらも植物の成長に欠かせない重要な栄養素だ。
「土を眠らせる」というのは、おそらく畑を休ませる期間のことだろう。
一定期間畑を休ませることで、土地の栄養が回復するのを待つ。
そして次の作付けの前に、龍の髭の灰つまり天然の化学肥料をまいて土の栄養をおぎなうのだ。
「なんて、合理的なんだ……」
私は、思わずつぶやいていた。
それは近代の農法にも通じる、非常に科学的な土の管理技術だった。
この世界の人はそれを「言い伝え」として、意味も分からず形式だけを受け継いできたのだ。
「長老、その『龍の髭』はどこに生えているの?」
「その辺りの荒れ地に、いくらでも生えておりますじゃろう。何の役にも立たん、ただの雑草じゃが」
「いいえ、それは宝の山よ」
私は立ち上がって、きっぱりと言い切った。
村人たちが、驚いたように私を見ている。
「今から、みんなでその草を集めるわよ。そしてその灰を使って、あなたたちの畑をよみがえらせてみせる」
私の宣言に、家の中は水を打ったように静かになった。
誰もが、信じられないという顔で私を見ている。
最初に動いたのは、あの若者だった。
彼は疑いの目を向けながらも、どこか期待するような響きを声に乗せて尋ねてきた。
「……本気で、言ってるのか?」
「もちろんよ。私を信じてみて」
私は、自信を持って微笑んだ。
水神の次は、大地母神の復活だ。
私の民俗学の知識が、この貧しい村を救うことになるだろう。
村人たちはしばらく顔を見合わせていたが、やがて長老が重々しくうなずいた。
「……わかった。あんた様の言う通りにしてみよう。どうせ、失うものなど我々には何もないんじゃからな」
その言葉をきっかけに、他の村人たちも一人また一人とうなずき始めた。
彼らの目に、ほんの少しだけれど希望の光がともったように見えた。
「ありがとう。それじゃあ、早速始めましょう!」
私は村人たちを連れて、家の外に出た。
まずは、みんなで「龍の髭」を集めることからだ。
アルフレッドが、少し心配そうな顔で私のそばに寄ってきた。
「お嬢様、本当に大丈夫なのでございますか?」
「ええ、問題ないわ。見ていてアルフレッド、ここでも小さな奇跡を起こしてみせるから」
私は彼にウィンクして、村人たちに指示を出し始めた。
痩せこけた村人たちの顔には、まだ疑いの色が濃い。
私はそんな彼らを先導し、龍の髭がたくさん生えている場所へと向かった。
乾いた大地に、私たちの足音が響き渡る。
村人たちは私の的確な指示と、時折見せる笑顔に少しずつ緊張が解けてきたようだった。
私たちは黙々と草を刈り取り、山のように積み上げていく。
太陽が西に傾き始め、空がオレンジ色に染まる頃にはたくさんの龍の髭が集まった。
私はそれをいくつかの山に分け、火をつける準備を始める。
後にはすっかり水で満たされた泉と、立ち尽くすアルフレッドが残された。
「お嬢様……今のは、いったい……?」
アルフレッドが、信じられないものを見るような目で私を見つめてくる。
彼の驚きも無理はない。何十年も枯れていた泉が、私の指示でよみがえったのだから。
「言ったでしょう?水が湧くかもしれないって」
私は、いたずらっぽく笑ってみせる。
本当の仕組みを説明したところで、彼には理解できないだろう。
化学反応や上昇気流なんて言っても、首をかしげられるだけだ。
「しかし……まるで、魔法のようでございました」
「そうね。古い時代の魔法、と言えるかもしれないわね」
私はそう言って、話をはぐらかした。
民俗学は、時に魔法と呼ばれる現象を解き明かす学問だ。
人々が奇跡や呪いと信じていたものが、実は合理的な知識に基づいていたことは珍しくない。
「さあ、冷えてしまうわ。小屋に戻って着替えましょう。アルフレッドも、風邪をひいてしまうわよ」
私たちは濡れた服のまま、小屋へと戻った。
幸い、持ってきていた荷物の中に着替えはあった。
乾いた服に着替えると、ようやく人心地がついた気がする。
アルフレッドは、火を起こして簡単なスープを作ってくれた。
干し肉と固いパンだけの夕食だったけれど、今日の成功を祝うには十分だった。
温かいスープが、冷えた体にじんわりとしみ渡っていく。
「お嬢様は、一体何者なのでございますか?」
スープを飲みながら、アルフレッドがぽつりと言った。
その表情は、おそれと好奇が入り混じったような複雑な色を浮かべている。
「何者って、私はリゼット・ヴァインベルクよ。あなたの知っている通りだわ」
「ですが、先ほどの御業はとても貴族の御令嬢がご存じのこととは思えません」
「うーん、昔から古い言い伝えとかに興味があって色々と本を読んでいただけよ」
もちろん、うそだ。
この世界の書物で、あんな古代技術について学べるはずがない。
だけど、前世の知識について話すわけにもいかなかった。
幸い、アルフレッドはそれ以上聞いてはこなかった。
彼はただ私の顔をじっと見つめ、やがて深々と頭を下げた。
「どのようなお力かは存じませんが、私はお嬢様にお仕えできて光栄にございます。このアルフレッド、生涯をかけてお嬢様をお守りいたします」
彼のまっすぐな言葉に、私は少しだけ胸が熱くなった。
王都の家では、誰も私を認めてくれなかった。
それがここでは、まだ初日なのにこんなにも忠誠を捧げてくれる人がいる。
「ありがとう、アルフレッド。これからもよろしくね」
その夜、私は久しぶりにぐっすりと眠ることができた。
王都の屋敷の豪華なベッドよりも、この固くて小さなベッドの方がずっと心地よかった。
翌朝、私は早速次の計画に取り掛かることにした。
水は確保できた。次は食料だ。
この痩せた土地で、どうやって作物を育てるか。
「アルフレッド、この辺りに村はあるのかしら?」
朝食をとりながら尋ねると、彼はうなずいた。
「はい。ここから東に半日ほど歩いた場所に、小さな村が一つございます。ですが、非常に貧しい村でして」
「そこに住んでいる人たちに、話を聞いてみたいの。この土地に伝わる古い話とか、変わった風習とか何でもいいから」
「言い伝え、でございますか」
「ええ。きっと、この土地を豊かにするヒントが隠されているはずよ」
私の言葉に、アルフレッドはまた不思議そうな顔をした。
しかし今度は何も言わずに、うなずいてくれた。
彼はもう、私の言うことには何か特別な意味があると信じ始めているようだった。
私たちは簡単な準備を済ませ、アルフレッドが言う村へと向かった。
道中は、昨日見たのと同じような荒れ地が続いている。
土は乾燥してひび割れ、生えている草もまばらだ。
これでは、まともな作物が育つはずもない。
半日ほど歩くと、前方に数軒の家が集まっているのが見えてきた。
あれが村だろう。しかし近づくにつれて、そのあまりの寂れ具合に言葉を失った。
家はどれも崩れかけており、畑らしき場所も石ころだらけで耕されていない。
村を歩いている人々の顔にも、生気がなかった。
痩せて汚れた服を着た彼らは、私たちのような人間が現れたことに驚き警戒しているようだった。
「こんにちは」
私が声をかけると、近くにいた老婆がびくりと肩を震わせ家の中に引っ込んでしまった。
他の村人たちも、遠巻きに私たちを見ているだけで誰も近づいてこようとしない。
「困ったわね……」
これでは、話を聞くどころではない。
どうしたものかと思っていると、一人の若者がおずおずとこちらに近づいてきた。
「あんたたち、役人か。もう、取るものなんて何もねえぞ」
若者は、私たちを税の取り立てに来た役人だと思っているらしい。
その目には、深い絶望と不信感が浮かんでいた。
「いいえ、違うわ。私はリゼット。今日から、この土地の管理を任されることになったの」
私の自己紹介に、若者は不思議な顔をした。
「管理だあ?こんな土地を、好きで管理する奴がいるのかよ」
「ええ。これから、この土地を少しでも住みやすくしたいと思っているの。だから、あなたたちの力を貸してほしい」
「力を貸す、だあ?冗談だろ。俺たちに何ができるってんだ」
若者は、吐き捨てるように言った。
彼の言う通りかもしれない。長年の貧しい生活が、彼らから希望を奪ってしまったのだろう。
言葉だけでは、彼らの心を開くことはできない。
必要なのは、目に見える結果だ。
「昨日の夕方、この辺りで雨が降らなかった?」
私は、話題を変えてみた。
若者は一瞬きょとんとした後、思い出したようにうなずいた。
「ああ、そういや降ったな。妙な雨だったぜ。空は晴れてんのに、あの丘の辺りだけいきなり土砂降りになったんだ」
「その雨を降らせたのが、私だと言ったら信じる?」
私の言葉に、若者だけでなく遠巻きに見ていた村人たちもざわめき始めた。
「何を言ってるんだこの女は」「頭がおかしいんじゃないのか」そんな声が聞こえてくる。
若者は、私を馬鹿にしたように鼻で笑った。
「あんたが?面白い冗談を言うじゃねえか。そんなことができるなら、今すぐこの畑に作物を実らせてみろよ」
彼はそう言って、足元の石ころだらけの畑を指差した。
その挑発するような態度に、隣にいたアルフレッドが何か言おうとした。
私は、それを手で制した。
「いいわ。ただし、少し時間がかかるしあなたたちの協力も必要よ」
「協力?」
「ええ。まず、この土地に伝わる古い話を聞かせてほしいの。昔の畑仕事のやり方とか、お祭りのこととか何でもいいわ」
私の提案に、若者はますます意味がわからないという顔をした。
しかし彼の後ろにいた村人の中から、一人の老人がゆっくりと前に出てきた。
「わしなら、少しは知っておるが……」
その老人は、村の長老らしかった。
深く刻まれたしわと、にごっているが鋭い光を宿したひとみが印象的だ。
「本当?ぜひ聞かせてちょうだい」
「あんた様は、本当にこの土地を豊かにしてくださるのか」
「ええ、約束するわ」
私は長老の目を真っ直ぐに見つめて、はっきりと答えた。
私のひとみに何かを見出したのか、長老はしばらく黙って私を見つめ返した。
そして、ゆっくりとうなずいた。
「……わかった。話せることは、話そう。ついてきなされ」
長老はそう言って、村で一番大きな家へ私たちを案内してくれた。
若者や他の村人たちも、興味を引かれたのかぞろぞろと後についてくる。
家の中は薄暗く、質素な木のテーブルと椅子があるだけだった。
長老は私たちに席をすすめ、自身もゆっくりと腰を下ろした。
「この土地にはな、昔から伝わる奇妙な言い伝えがあるんじゃ」
長老は、ゆっくりとした口調で語り始めた。
「『土を眠らせ、火で起こせ』。畑を耕す前に、必ずそう唱えるようにと先祖代々言い伝えられておる」
「土を眠らせ、火で起こせ……?」
私は、その言葉を繰り返した。
一見すると、意味のわからないおまじないのように聞こえる。
「はい。ですが、今ではただの形式じゃ。そんなことをしても、作物が育つわけでもないからのう」
長老は、自分を笑うように言った。
だが私の頭の中では、忘れられていた知識の断片がつながり始めていた。
「その『火で起こす』というのは、具体的に何をするの?」
「畑に、特定の草を燃やした灰をまくんじゃよ。『龍の髭』と呼ばれる、赤い穂先を持つ草じゃな」
龍の髭、という名前に私はピンときた。
昨日、泉の周りでも見かけた植物だ。
前世の知識によれば、あの植物は根に特殊なバクテリアを共生させている。
そして、空気中の窒素を土に固定する能力を持っていた。
その草を燃やしてできる灰は、カリウムをたくさん含んでいる。
窒素とカリウムは、どちらも植物の成長に欠かせない重要な栄養素だ。
「土を眠らせる」というのは、おそらく畑を休ませる期間のことだろう。
一定期間畑を休ませることで、土地の栄養が回復するのを待つ。
そして次の作付けの前に、龍の髭の灰つまり天然の化学肥料をまいて土の栄養をおぎなうのだ。
「なんて、合理的なんだ……」
私は、思わずつぶやいていた。
それは近代の農法にも通じる、非常に科学的な土の管理技術だった。
この世界の人はそれを「言い伝え」として、意味も分からず形式だけを受け継いできたのだ。
「長老、その『龍の髭』はどこに生えているの?」
「その辺りの荒れ地に、いくらでも生えておりますじゃろう。何の役にも立たん、ただの雑草じゃが」
「いいえ、それは宝の山よ」
私は立ち上がって、きっぱりと言い切った。
村人たちが、驚いたように私を見ている。
「今から、みんなでその草を集めるわよ。そしてその灰を使って、あなたたちの畑をよみがえらせてみせる」
私の宣言に、家の中は水を打ったように静かになった。
誰もが、信じられないという顔で私を見ている。
最初に動いたのは、あの若者だった。
彼は疑いの目を向けながらも、どこか期待するような響きを声に乗せて尋ねてきた。
「……本気で、言ってるのか?」
「もちろんよ。私を信じてみて」
私は、自信を持って微笑んだ。
水神の次は、大地母神の復活だ。
私の民俗学の知識が、この貧しい村を救うことになるだろう。
村人たちはしばらく顔を見合わせていたが、やがて長老が重々しくうなずいた。
「……わかった。あんた様の言う通りにしてみよう。どうせ、失うものなど我々には何もないんじゃからな」
その言葉をきっかけに、他の村人たちも一人また一人とうなずき始めた。
彼らの目に、ほんの少しだけれど希望の光がともったように見えた。
「ありがとう。それじゃあ、早速始めましょう!」
私は村人たちを連れて、家の外に出た。
まずは、みんなで「龍の髭」を集めることからだ。
アルフレッドが、少し心配そうな顔で私のそばに寄ってきた。
「お嬢様、本当に大丈夫なのでございますか?」
「ええ、問題ないわ。見ていてアルフレッド、ここでも小さな奇跡を起こしてみせるから」
私は彼にウィンクして、村人たちに指示を出し始めた。
痩せこけた村人たちの顔には、まだ疑いの色が濃い。
私はそんな彼らを先導し、龍の髭がたくさん生えている場所へと向かった。
乾いた大地に、私たちの足音が響き渡る。
村人たちは私の的確な指示と、時折見せる笑顔に少しずつ緊張が解けてきたようだった。
私たちは黙々と草を刈り取り、山のように積み上げていく。
太陽が西に傾き始め、空がオレンジ色に染まる頃にはたくさんの龍の髭が集まった。
私はそれをいくつかの山に分け、火をつける準備を始める。
170
あなたにおすすめの小説

役立たずと追放された聖女は、第二の人生で薬師として静かに輝く
腐ったバナナ
ファンタジー
「お前は役立たずだ」
――そう言われ、聖女カリナは宮廷から追放された。
癒やしの力は弱く、誰からも冷遇され続けた日々。
居場所を失った彼女は、静かな田舎の村へ向かう。
しかしそこで出会ったのは、病に苦しむ人々、薬草を必要とする生活、そして彼女をまっすぐ信じてくれる村人たちだった。
小さな治療を重ねるうちに、カリナは“ただの役立たず”ではなく「薬師」としての価値を見いだしていく。

刷り込みで竜の母親になった私は、国の運命を預かることになりました。繁栄も滅亡も、私の導き次第で決まるようです。
木山楽斗
ファンタジー
宿屋で働くフェリナは、ある日森で卵を見つけた。
その卵からかえったのは、彼女が見たことがない生物だった。その生物は、生まれて初めて見たフェリナのことを母親だと思ったらしく、彼女にとても懐いていた。
本物の母親も見当たらず、見捨てることも忍びないことから、フェリナは謎の生物を育てることにした。
リルフと名付けられた生物と、フェリナはしばらく平和な日常を過ごしていた。
しかし、ある日彼女達の元に国王から通達があった。
なんでも、リルフは竜という生物であり、国を繁栄にも破滅にも導く特別な存在であるようだ。
竜がどちらの道を辿るかは、その母親にかかっているらしい。知らない内に、フェリナは国の運命を握っていたのだ。
※この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「アルファポリス」にも掲載しています。
※2021/09/03 改題しました。(旧題:刷り込みで竜の母親になった私は、国の運命を預かることになりました。)

追放された回復術師は、なんでも『回復』できて万能でした
新緑あらた
ファンタジー
死闘の末、強敵の討伐クエストを達成した回復術師ヨシュアを待っていたのは、称賛の言葉ではなく、解雇通告だった。
「ヨシュア……てめえはクビだ」
ポーションを湯水のように使える最高位冒険者になった彼らは、今まで散々ポーションの代用品としてヨシュアを利用してきたのに、回復術師は不要だと考えて切り捨てることにしたのだ。
「ポーションの下位互換」とまで罵られて気落ちしていたヨシュアだったが、ブラックな労働をしいるあのパーティーから解放されて喜んでいる自分に気づく。
危機から救った辺境の地方領主の娘との出会いをきっかけに、彼の世界はどんどん広がっていく……。
一方、Sランク冒険者パーティーはクエストの未達成でどんどんランクを落としていく。
彼らは知らなかったのだ、ヨシュアが彼らの傷だけでなく、状態異常や武器の破損など、なんでも『回復』していたことを……。

タダ働きなので待遇改善を求めて抗議したら、精霊達から『破壊神』と怖れられています。
渡里あずま
ファンタジー
出来損ないの聖女・アガタ。
しかし、精霊の加護を持つ新たな聖女が現れて、王子から婚約破棄された時――彼女は、前世(現代)の記憶を取り戻した。
「それなら、今までの報酬を払って貰えますか?」
※※※
虐げられていた子が、モフモフしながらやりたいことを探す旅に出る話です。
※重複投稿作品※
表紙の使用画像は、AdobeStockのものです。

【完結】特別な力で国を守っていた〈防国姫〉の私、愚王と愚妹に王宮追放されたのでスパダリ従者と旅に出ます。一方で愚王と愚妹は破滅する模様
岡崎 剛柔
ファンタジー
◎第17回ファンタジー小説大賞に応募しています。投票していただけると嬉しいです
【あらすじ】
カスケード王国には魔力水晶石と呼ばれる特殊な鉱物が国中に存在しており、その魔力水晶石に特別な魔力を流すことで〈魔素〉による疫病などを防いでいた特別な聖女がいた。
聖女の名前はアメリア・フィンドラル。
国民から〈防国姫〉と呼ばれて尊敬されていた、フィンドラル男爵家の長女としてこの世に生を受けた凛々しい女性だった。
「アメリア・フィンドラル、ちょうどいい機会だからここでお前との婚約を破棄する! いいか、これは現国王である僕ことアントン・カスケードがずっと前から決めていたことだ! だから異議は認めない!」
そんなアメリアは婚約者だった若き国王――アントン・カスケードに公衆の面前で一方的に婚約破棄されてしまう。
婚約破棄された理由は、アメリアの妹であったミーシャの策略だった。
ミーシャはアメリアと同じ〈防国姫〉になれる特別な魔力を発現させたことで、アントンを口説き落としてアメリアとの婚約を破棄させてしまう。
そしてミーシャに骨抜きにされたアントンは、アメリアに王宮からの追放処分を言い渡した。
これにはアメリアもすっかり呆れ、無駄な言い訳をせずに大人しく王宮から出て行った。
やがてアメリアは天才騎士と呼ばれていたリヒト・ジークウォルトを連れて〈放浪医師〉となることを決意する。
〈防国姫〉の任を解かれても、国民たちを守るために自分が持つ医術の知識を活かそうと考えたのだ。
一方、本物の知識と実力を持っていたアメリアを王宮から追放したことで、主核の魔力水晶石が致命的な誤作動を起こしてカスケード王国は未曽有の大災害に陥ってしまう。
普通の女性ならば「私と婚約破棄して王宮から追放した報いよ。ざまあ」と喜ぶだろう。
だが、誰よりも優しい心と気高い信念を持っていたアメリアは違った。
カスケード王国全土を襲った未曽有の大災害を鎮めるべく、すべての原因だったミーシャとアントンのいる王宮に、アメリアはリヒトを始めとして旅先で出会った弟子の少女や伝説の魔獣フェンリルと向かう。
些細な恨みよりも、〈防国姫〉と呼ばれた聖女の力で国を救うために――。

召喚失敗!?いや、私聖女みたいなんですけど・・・まぁいっか。
SaToo
ファンタジー
聖女を召喚しておいてお前は聖女じゃないって、それはなくない?
その魔道具、私の力量りきれてないよ?まぁ聖女じゃないっていうならそれでもいいけど。
ってなんで地下牢に閉じ込められてるんだろ…。
せっかく異世界に来たんだから、世界中を旅したいよ。
こんなところさっさと抜け出して、旅に出ますか。

オネエ伯爵、幼女を拾う。~実はこの子、逃げてきた聖女らしい~
雪丸
ファンタジー
アタシ、アドルディ・レッドフォード伯爵。
突然だけど今の状況を説明するわ。幼女を拾ったの。
多分年齢は6~8歳くらいの子。屋敷の前にボロ雑巾が落ちてると思ったらびっくり!人だったの。
死んでる?と思ってその辺りに落ちている木で突いたら、息をしていたから屋敷に運んで手当てをしたのよ。
「道端で倒れていた私を助け、手当を施したその所業。賞賛に値します。(盛大なキャラ作り中)」
んま~~~尊大だし図々しいし可愛くないわ~~~!!
でも聖女様だから変な扱いもできないわ~~~!!
これからアタシ、どうなっちゃうのかしら…。
な、ラブコメ&ファンタジーです。恋の進展はスローペースです。
小説家になろう、カクヨムにも投稿しています。(敬称略)
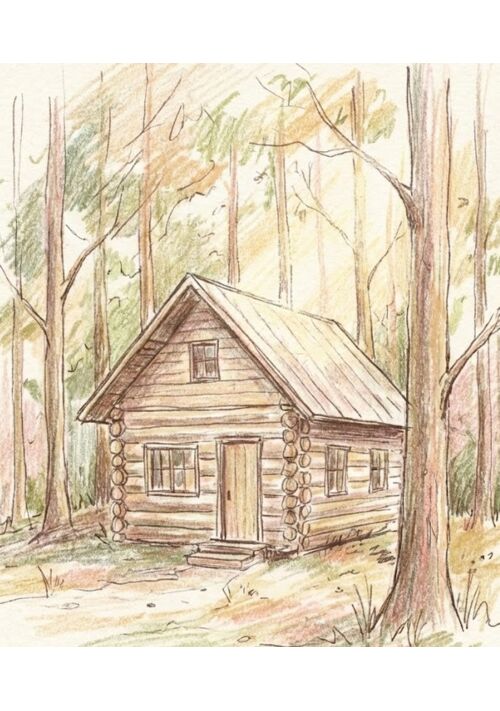
『捨てられシスターと傷ついた獣の修繕日誌』~「修理が遅い」と追放されたけど、DIY知識チートで壊れた家も心も直して、幸せな家庭を築きます
エリモコピコット
ファンタジー
【12/6 日間ランキング17位!】
「魔法で直せば一瞬だ。お前の手作業は時間の無駄なんだよ」
そう言われて勇者パーティを追放されたシスター、エリス。
彼女の魔法は弱く、派手な活躍はできない。 けれど彼女には、物の声を聞く『構造把握』の力と、前世から受け継いだ『DIY(日曜大工)』の知識があった。
傷心のまま辺境の村「ココン」に流れ着いた彼女は、一軒のボロ家と出会う。 隙間風だらけの壁、腐りかけた床。けれど、エリスは目を輝かせた。
「直せる。ここを、世界で一番温かい『帰る場所』にしよう!」
釘を使わない頑丈な家具、水汲み不要の自動ポンプ、冬でもポカポカの床暖房。
魔法文明が見落としていた「手間暇かけた技術」は、不便な辺境生活を快適な楽園へと変えていく。
やがてその温かい家には、 傷ついた銀髪の狼少女や、 素直になれないツンデレ黒猫、 人見知りな犬耳の鍛冶師が集まってきて――。
「エリス姉、あったか~い……」「……悔しいけど、この家から出られないわね」
これは、不器用なシスターが、壊れた家と、傷ついた心を修繕していく物語。 優しくて温かい、手作りのスローライフ・ファンタジー!
(※一方その頃、メンテナンス係を失った勇者パーティの装備はボロボロになり、冷たい野営で後悔の日々を送るのですが……それはまた別のお話)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















