3 / 15
第3話 【ポータの大冒険】
しおりを挟む
――ふわりと地面を踏んだ感覚とともに、三人は目を開けた。
そこは、小高い丘の上だった。
目の前には、どこまでも広がる緑の草原と、ゆるやかにうねる地平。空は高く、雲ひとつない青空が頭上を覆っていた。風にそよぐ草花は見たことのない色と形をしており、甘くて懐かしいような香りが鼻をくすぐる。
「ここって‥‥どこだ?」
レンがぽつりとつぶやいた。だが、誰も答えられなかった。
そのとき、丘草原の先から、青い影が転がるように走ってきた。
ずんぐりむっくりした鶏のような体形の青い鳥。
「青い鳥‥‥?」
その姿にどこかで見た覚えがあり、チハルとマリンが目を凝らしてその様子を眺めていると、青い鳥のすぐ背後――草原の影を切り裂くように、黒い何かが地を蹴って迫ってきた。
唸り声とともに現れたのは、狼のような、いやそれよりももっと凶悪で、虚ろな目をした異形の黒い獣だった。
「うわっ! やばっ! なんか後ろにヤバそうなの来てるぞ!」
レンが叫んだ瞬間、獣は大きな口を開けて青い鳥に飛びかかった。
「「「危ないっ!!」」」
三人は声をそろえて叫んだ。
だが青い鳥は、寸前でひらりと身を翻し、また逃げ出す。丘を中心に獣と鳥はぐるぐると回り続けていた。
まるで、逃げる者と追う者が、舞台装置の中で永遠に同じ演目を繰り返しているかのようだった。
「鳥なんだから、飛んで逃げればいいのに‥‥」
レンが眉をひそめつつ発した言葉に、チハルがハッとしたように目を見開いた。
「――あっ、これって‥‥」
彼女の脳裏に、過去に見たことがある情景が鮮やかに蘇る。青い鳥、丘、黒い怪物との逃走劇。
「もしかして『ポータの大冒険』?」
***
“ポータの大冒険”
かつて多くの子どもたちに親しまれ、今でも語り継がれている児童文学作品――それが『ポータの大冒険』。
その主人公は、飛ぶことが苦手な一羽の青い鳥、「ポータ」だった。
ポータは、丸みを帯びた体に小さな翼、どこか間の抜けたような愛嬌のある表情が特徴で、歩く姿はよちよちと不格好。だが、その見た目とは裏腹に芯の強さと優しさと運の良さを持った鳥である。
物語は、ポータが遠く離れた故郷を目指して旅をするという冒険譚。
旅の途中で出会う動物たちや人々との心温まる交流、数々の困難と試練を乗り越える中で「幸せを招く青い鳥」として成長していく。
読んだ人の心を温かく包みこみ、ときには涙を誘うその物語は、世代を超えて愛され、教室や図書館の棚に並んでいる。
***
少し昔にアニメ化されたことで、その名は一時的に全国区となり、ある世代にとってもなじみ深いキャラクターとなった。
チハルは幼い頃にテレビで流れていた草原を駆けるポータのオープニングアニメを思い出す。
そして今、まさに物語のシーン――ポータが黒い魔獣に追いかけられるシーンが、現実のものとして繰り広げられていた。
「ポータ‥‥ああ、昔アニメでやってたやつか」
レンもその名前に聞き覚えがあったようで眉を上げてつぶやき、マリンも同じ反応をしている。どうやらマリンも幼い頃に観ていたのだろう。
「たしか青い鳥が旅する話だったよな。それが、どうかしたのか?」
「ねえ、もしかしたらなんだけど――ここって、その『ポータの大冒険』の世界なんじゃないかな?」
チハルの言葉にレンとマリンは同時にきょとんとした顔で彼女を見つめた。あまりにも突拍子もない発言に、場の空気が一瞬凍りついたかのような静けさが流れた。
「‥‥なに言ってるんだ、チハル?」
レンが苦笑混じりに言う。
「いや、私だって自分で言ってて馬鹿みたいだと思ってるよ。でもさ、ほら、思い出してよ。図書室の地下室で、本が開いた瞬間、光に包まれて‥‥気がついたら、ここにいたでしょ? あれ、どう考えても普通じゃなかったじゃん」
チハルは言いながら、胸のあたりを押さえた。言葉の奥にある焦燥と困惑が、その仕草にもにじみ出ていた。
自分自身でもまだ信じ切れていない言葉を、どうにか必死に口にしていた。目の前で起きていることを否定できなかった。
「いや、チハル。これは夢なんだよ、きっと。こういうのはだいたい、俺たちが変なタイミングで同じ夢でも見てるってことだろ?」
レンが腕を組み、わざとらしく声をやや低くして言った。
「でも、それこそおかしくない? 三人とも同じタイミングで、同じ夢を見て、同じ場所にいる。そんな都合のいい偶然ってないでしょう。そもそも、この現実感が何よりの証明じゃない」
チハルの反論にレンは口をつぐんだ。
確かに夢だとするにはあまりにリアルすぎる。
風の匂い、草の感触、目下で繰り広げているずんぐりむっくりした青い鳥と黒い魔獣の追いかけっこ――とうてい「夢」とは思えない。
そのとき、ずっと黙って話を聞いていたマリンが、ぽつりと首をかしげながら言葉を落とした。
「‥‥それならさ。なんで、私たちがそのポータの世界なんかに居るの?」
何気ない問いだったが、言われて初めて、三人とも“なぜ自分たちが”という点を深く考えていなかったことに気づいた。
この不思議な出来事の原因――何が引き金になったのか。
チハルは目を伏せ、少し間を置いてからぽつりとつぶやいた。
「‥‥もしかしたら、私が、心のどこかで本の中に入ってみたいって思っていたからかも。特にポータは小さいころ何度も読み返してた本だったし、アニメも大好きで‥‥あの世界に行けたらなって思っていたことがあるんだよね」
本の中に入りたい――そんな想像は、きっと誰もが子どものころ一度は抱く夢だ。
だけどそれは、あくまでも「夢物語」で、現実に起きることではないと思っていた。
けれど今、こうして三人は実際に“体験している”。
「そうすると、あの本が‥‥図書室のあの地下室の光る本が、本当に“なんでも願いが叶う本”だったとしたら‥‥?」
マリンがゆっくりと言葉をつなぐ。
「‥‥それなら、こんな不思議な現象も説明がつくわよね」
その言葉に三人はしばらく沈黙し、ただ静かにその可能性を飲み込もうとしていた。
「じゃあ‥‥もしそうだとしたら、これからどうすればいいんだ?」
沈黙を破ったのはレンだった。明らかに自分は考える気がない他力本願な口調でそう言った。
ただレンに対して、最初からそれほどの期待を抱いていなかったチハルは視線を草原へと戻した。そこでは青い鳥――ポータが、相変わらず必死に黒い魔獣から逃げ回っている。
小さな翼をばたつかせながらも飛べず、必死に地面をよちよちと駆け回っているポータの様子は、かつてテレビ画面の中で見たあの冒険の第一幕と、まったく同じ。
延々と同じような追いかけっこを繰り返しているのを見れば、どこか“進行が止まった物語”のようにも思える。
まるで、読み手がページをめくってくれないまま、物語が止まってしまっているような、そんな感覚。
「たぶんだけど‥‥ポータの旅立ちの展開をなぞったり、物語を進めないといけないんじゃないかな」
チハルは右手を上げて、遠くに広がる森の方を指さした。
「このあとポータがあの森に逃げ込んで、黒い獣から逃れるの。その流れを私たちが手伝って進めていく必要があるんじゃないかって」
如何にもな説明にマリンとレンはチハルの提案に反対する理由はなかった。
そこは、小高い丘の上だった。
目の前には、どこまでも広がる緑の草原と、ゆるやかにうねる地平。空は高く、雲ひとつない青空が頭上を覆っていた。風にそよぐ草花は見たことのない色と形をしており、甘くて懐かしいような香りが鼻をくすぐる。
「ここって‥‥どこだ?」
レンがぽつりとつぶやいた。だが、誰も答えられなかった。
そのとき、丘草原の先から、青い影が転がるように走ってきた。
ずんぐりむっくりした鶏のような体形の青い鳥。
「青い鳥‥‥?」
その姿にどこかで見た覚えがあり、チハルとマリンが目を凝らしてその様子を眺めていると、青い鳥のすぐ背後――草原の影を切り裂くように、黒い何かが地を蹴って迫ってきた。
唸り声とともに現れたのは、狼のような、いやそれよりももっと凶悪で、虚ろな目をした異形の黒い獣だった。
「うわっ! やばっ! なんか後ろにヤバそうなの来てるぞ!」
レンが叫んだ瞬間、獣は大きな口を開けて青い鳥に飛びかかった。
「「「危ないっ!!」」」
三人は声をそろえて叫んだ。
だが青い鳥は、寸前でひらりと身を翻し、また逃げ出す。丘を中心に獣と鳥はぐるぐると回り続けていた。
まるで、逃げる者と追う者が、舞台装置の中で永遠に同じ演目を繰り返しているかのようだった。
「鳥なんだから、飛んで逃げればいいのに‥‥」
レンが眉をひそめつつ発した言葉に、チハルがハッとしたように目を見開いた。
「――あっ、これって‥‥」
彼女の脳裏に、過去に見たことがある情景が鮮やかに蘇る。青い鳥、丘、黒い怪物との逃走劇。
「もしかして『ポータの大冒険』?」
***
“ポータの大冒険”
かつて多くの子どもたちに親しまれ、今でも語り継がれている児童文学作品――それが『ポータの大冒険』。
その主人公は、飛ぶことが苦手な一羽の青い鳥、「ポータ」だった。
ポータは、丸みを帯びた体に小さな翼、どこか間の抜けたような愛嬌のある表情が特徴で、歩く姿はよちよちと不格好。だが、その見た目とは裏腹に芯の強さと優しさと運の良さを持った鳥である。
物語は、ポータが遠く離れた故郷を目指して旅をするという冒険譚。
旅の途中で出会う動物たちや人々との心温まる交流、数々の困難と試練を乗り越える中で「幸せを招く青い鳥」として成長していく。
読んだ人の心を温かく包みこみ、ときには涙を誘うその物語は、世代を超えて愛され、教室や図書館の棚に並んでいる。
***
少し昔にアニメ化されたことで、その名は一時的に全国区となり、ある世代にとってもなじみ深いキャラクターとなった。
チハルは幼い頃にテレビで流れていた草原を駆けるポータのオープニングアニメを思い出す。
そして今、まさに物語のシーン――ポータが黒い魔獣に追いかけられるシーンが、現実のものとして繰り広げられていた。
「ポータ‥‥ああ、昔アニメでやってたやつか」
レンもその名前に聞き覚えがあったようで眉を上げてつぶやき、マリンも同じ反応をしている。どうやらマリンも幼い頃に観ていたのだろう。
「たしか青い鳥が旅する話だったよな。それが、どうかしたのか?」
「ねえ、もしかしたらなんだけど――ここって、その『ポータの大冒険』の世界なんじゃないかな?」
チハルの言葉にレンとマリンは同時にきょとんとした顔で彼女を見つめた。あまりにも突拍子もない発言に、場の空気が一瞬凍りついたかのような静けさが流れた。
「‥‥なに言ってるんだ、チハル?」
レンが苦笑混じりに言う。
「いや、私だって自分で言ってて馬鹿みたいだと思ってるよ。でもさ、ほら、思い出してよ。図書室の地下室で、本が開いた瞬間、光に包まれて‥‥気がついたら、ここにいたでしょ? あれ、どう考えても普通じゃなかったじゃん」
チハルは言いながら、胸のあたりを押さえた。言葉の奥にある焦燥と困惑が、その仕草にもにじみ出ていた。
自分自身でもまだ信じ切れていない言葉を、どうにか必死に口にしていた。目の前で起きていることを否定できなかった。
「いや、チハル。これは夢なんだよ、きっと。こういうのはだいたい、俺たちが変なタイミングで同じ夢でも見てるってことだろ?」
レンが腕を組み、わざとらしく声をやや低くして言った。
「でも、それこそおかしくない? 三人とも同じタイミングで、同じ夢を見て、同じ場所にいる。そんな都合のいい偶然ってないでしょう。そもそも、この現実感が何よりの証明じゃない」
チハルの反論にレンは口をつぐんだ。
確かに夢だとするにはあまりにリアルすぎる。
風の匂い、草の感触、目下で繰り広げているずんぐりむっくりした青い鳥と黒い魔獣の追いかけっこ――とうてい「夢」とは思えない。
そのとき、ずっと黙って話を聞いていたマリンが、ぽつりと首をかしげながら言葉を落とした。
「‥‥それならさ。なんで、私たちがそのポータの世界なんかに居るの?」
何気ない問いだったが、言われて初めて、三人とも“なぜ自分たちが”という点を深く考えていなかったことに気づいた。
この不思議な出来事の原因――何が引き金になったのか。
チハルは目を伏せ、少し間を置いてからぽつりとつぶやいた。
「‥‥もしかしたら、私が、心のどこかで本の中に入ってみたいって思っていたからかも。特にポータは小さいころ何度も読み返してた本だったし、アニメも大好きで‥‥あの世界に行けたらなって思っていたことがあるんだよね」
本の中に入りたい――そんな想像は、きっと誰もが子どものころ一度は抱く夢だ。
だけどそれは、あくまでも「夢物語」で、現実に起きることではないと思っていた。
けれど今、こうして三人は実際に“体験している”。
「そうすると、あの本が‥‥図書室のあの地下室の光る本が、本当に“なんでも願いが叶う本”だったとしたら‥‥?」
マリンがゆっくりと言葉をつなぐ。
「‥‥それなら、こんな不思議な現象も説明がつくわよね」
その言葉に三人はしばらく沈黙し、ただ静かにその可能性を飲み込もうとしていた。
「じゃあ‥‥もしそうだとしたら、これからどうすればいいんだ?」
沈黙を破ったのはレンだった。明らかに自分は考える気がない他力本願な口調でそう言った。
ただレンに対して、最初からそれほどの期待を抱いていなかったチハルは視線を草原へと戻した。そこでは青い鳥――ポータが、相変わらず必死に黒い魔獣から逃げ回っている。
小さな翼をばたつかせながらも飛べず、必死に地面をよちよちと駆け回っているポータの様子は、かつてテレビ画面の中で見たあの冒険の第一幕と、まったく同じ。
延々と同じような追いかけっこを繰り返しているのを見れば、どこか“進行が止まった物語”のようにも思える。
まるで、読み手がページをめくってくれないまま、物語が止まってしまっているような、そんな感覚。
「たぶんだけど‥‥ポータの旅立ちの展開をなぞったり、物語を進めないといけないんじゃないかな」
チハルは右手を上げて、遠くに広がる森の方を指さした。
「このあとポータがあの森に逃げ込んで、黒い獣から逃れるの。その流れを私たちが手伝って進めていく必要があるんじゃないかって」
如何にもな説明にマリンとレンはチハルの提案に反対する理由はなかった。
0
あなたにおすすめの小説

僕らの無人島漂流記
ましゅまろ
児童書・童話
夏休み、仲良しの小学4年男子5人組が出かけたキャンプは、突然の嵐で思わぬ大冒険に!
目を覚ますと、そこは見たこともない無人島だった。
地図もない。電波もない。食べ物も、水も、家もない。
頼れるのは、友だちと、自分の力だけ。
ケンカして、笑って、泣いて、助け合って——。
子どもだけの“1ヶ月サバイバル生活”が、いま始まる!


14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。
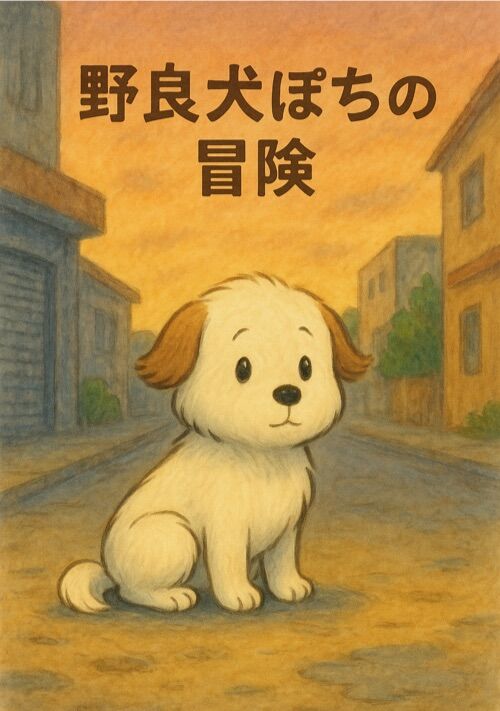
野良犬ぽちの冒険
KAORUwithAI
児童書・童話
――ぼくの名前、まだおぼえてる?
ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。
だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、
気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。
やさしい人もいれば、こわい人もいる。
あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。
それでも、ぽちは 思っている。
──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。
すこし さみしくて、すこし あたたかい、
のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

カリンカの子メルヴェ
田原更
児童書・童話
地下に掘り進めた穴の中で、黒い油という可燃性の液体を採掘して生きる、カリンカという民がいた。
かつて迫害により追われたカリンカたちは、地下都市「ユヴァーシ」を作り上げ、豊かに暮らしていた。
彼らは合言葉を用いていた。それは……「ともに生き、ともに生かす」
十三歳の少女メルヴェは、不在の父や病弱な母に代わって、一家の父親役を務めていた。仕事に従事し、弟妹のまとめ役となり、時には厳しく叱ることもあった。そのせいで妹たちとの間に亀裂が走ったことに、メルヴェは気づいていなかった。
幼なじみのタリクはメルヴェを気遣い、きらきら輝く白い石をメルヴェに贈った。メルヴェは幼い頃のように喜んだ。タリクは次はもっと大きな石を掘り当てると約束した。
年に一度の祭にあわせ、父が帰郷した。祭当日、男だけが踊る舞台に妹の一人が上がった。メルヴェは妹を叱った。しかし、メルヴェも、最近みせた傲慢な態度を父から叱られてしまう。
そんな折に地下都市ユヴァーシで起きた事件により、メルヴェは生まれてはじめて外の世界に飛び出していく……。
※本作はトルコのカッパドキアにある地下都市から着想を得ました。

少年騎士
克全
児童書・童話
「第1回きずな児童書大賞参加作」ポーウィス王国という辺境の小国には、12歳になるとダンジョンか魔境で一定の強さになるまで自分を鍛えなければいけないと言う全国民に対する法律があった。周囲の小国群の中で生き残るため、小国を狙う大国から自国を守るために作られた法律、義務だった。領地持ち騎士家の嫡男ハリー・グリフィスも、その義務に従い1人王都にあるダンジョンに向かって村をでた。だが、両親祖父母の計らいで平民の幼馴染2人も一緒に12歳の義務に同行する事になった。将来救国の英雄となるハリーの物語が始まった。

不幸でしあわせな子どもたち 「しあわせのふうせん」
山口かずなり
絵本
小説 不幸でしあわせな子どもたち
スピンオフ作品
・
ウルが友だちのメロウからもらったのは、
緑色のふうせん
だけどウルにとっては、いらないもの
いらないものは、誰かにとっては、
ほしいもの。
だけど、気づいて
ふうせんの正体に‥。
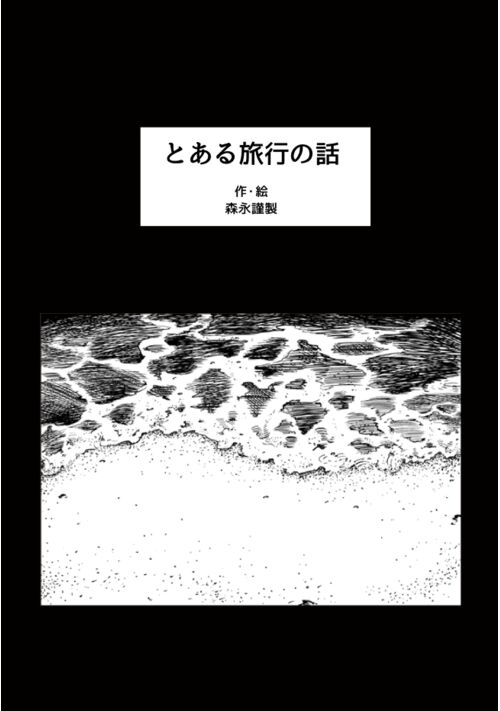
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















