13 / 26
社長と秘書の過去と本当の気持ち
しおりを挟む
さぁっと夜風に吹かれるように黄瀬さんは喋り出した。
「昔ね。ここは毎日綺麗なイルミネーションが点灯されていて、この場所でデートした恋人はずっと仲良しで居られるという、他愛のないジンクスがあった」
「へぇ。なんか可愛くていいですね」
「だろ。学生のとき。紗凪と一緒にここに来たかった」
ふっと笑って黄瀬さんは私を見た。
「!」
「覚えているかな。俺と紗凪は同級生。しかも俺は紗凪に告白したことがある。場所はベタに校舎の裏庭。放課後。死ぬほど緊張した」
「お、覚えていますよ! だって当時から黄瀬さんは凄い女子から人気があって。でも……何らかの理由で……あれは罰ゲームの告白だったんですよね?」
「──え?」
黄瀬さんの表情が硬まる。
先に私が核心をついてしまったかと慌てた。
「あ。大丈夫です。その気にしてませんから。ほらっ。私、当時太っていたし。一瞬だけでもいい夢見れたなぁって思っていたから」
だから、大人になって再会してもスルーしていた。仕事を優先したと、わたわたと伝えた。
けど、黄瀬さんは驚きの表情のままだった。
「ま、待ってくれ。罰ゲームの告白? 一体誰がそんなことを? むしろ紗凪は当時、他に付き合っていてる人がいて、俺を振ったんじゃないのか?」
黄瀬さんはばっと私に向きなおり、今まで見たことのない慌てようで私も焦ってしまう。
「えっ、だってあのギャル達が! 私、当時誰とも付き合ってませんよっ!? むしろ今まであんまり男性とお付き合いして来なかった、ぐらなんですけどっ」
お互いに混乱しあう。しかし、何か行き違いがあるのは確実だと思った。
なんでだろうと首を傾げると、黄瀬さんは私の顔をじっと見て。戸惑いながらも口を開いた。
「紗凪があまり男性と付き合ってない……こんなにも可愛いのに?」
「!!」
スーツ姿も凛々しく。今も昔もカッコいい男性にそんなことを言われたら、思考回路が完全に止まった。
風がしゃらんと耳元のタッセルを揺らして、言葉を紡げないでいると黄瀬さんが口元に手を置いて、もしかしてと言った。
「俺の告白が罰ゲームだと言ったのは、ギャル達と言ってたが……それは本当?」
こくりと頷く。
「俺もね。当時、ギャルみたいに化粧も香水もしっかりと纏った女子達から『青樹さんは、あぁ見えても付き合っている人がいる。だからやめといた方が良い』って言われた。ショックだった」
そんなことを言われていたなんて。
驚きで、怒りよりも胸が苦しくなる。
「実はそれが原因で香水のキツイ匂いが苦手になった」
あぁ。だから。黄瀬さんは香水の強い香りが苦手。
納得がいった。
そして、もっと気になること。
私が誰かと付き合っていると言うこと。
高校時代、そんな人はいない。
と言うことは──。
「それって、まさか」
「それを聞いて次の日、紗凪に本当かどうか訪ねようと思ったら避けられてしまい。思わず手を掴んだら『離して』って言われたから、あの女子達が言ったことは本当だと、思ってしまって──それで身を引いた」
口調も表情も寂しげに黄瀬さんは語った。そこに嘘を言ってる様子はない。まさかと思い当たったことを口にする。
「私は本当にお付き合いした人なんていません。多分ですが、黄瀬さんは当時から女子に凄く人気高かったから……ひょっとして告白をギャル達に知られしまって」
私が喉をこくっと鳴らしたあと。
「俺達を仲違いをさせた──と言うことか」
黄瀬さんが静かに言葉を繋いでくれた。
そのときぱちっと、頭の中で全てがのことが綺麗に収まったのを感じた。
ギャル達は私に罰ゲームだと言って、黄瀬さんを諦めさせた。黄瀬さんには私が付き合っている人がいると言って、私を諦めさせた。
──これが真実だと思った。
はぁと大きくため息をして空を見上げる。夜空やここから見える夜景が綺麗なだけ、ほんの少し救われた気分になった。
なんと単純な罠だろう。
それでも信じてしまったのは初恋だから。幼かったから。
今更当時の女子達に真意を聞いても仕方ない。悪意ある第三者に私達の初恋は邪魔をされたのだと、やっと腑に落ちた。
そして──ぽろりと涙が溢れた。慌てて涙をふく。
「っ、紗凪? どうした?」
一瞬、潮風が目に染みたと言おうかと思ったけど、素直に気持ちを伝えようと思った。
「すみません。なんだか安心したと言うか……私達、勘違いしてしまったけど。両思いだったんですね」
またぽろりと涙が溢れる。
「あの告白は罰ゲームじゃ無かったんだって思うと、やっぱり嬉しいなぁって……それにもっと素直に、黄瀬さんを信じてあげれば良かった。本当にごめんなさい」
「違うっ。謝るのは俺のほうだ。俺のほうこそ……!」
さらっと流して欲しいのに心配そうに私を見る、黄瀬さんに首を横に振る。
「ううん。違うんです。私、太っていて自分に自信がなかった。だから『罰ゲーム』って言う言葉を信じてしまったんです。本当は黄瀬さんみたいな、素敵な人に告白されて嬉しかったのに」
くすっと軽く笑うと、黄瀬さんがばっと私の手を掴んだ。
「俺は今でもっ──!」
指の先から感情が伝わるほどに暖かな手だった。
そして横を見てから、スッと立ち上がった。
なぜだろうと思っていると、向こうから男女のグループが歩いて来るのが見えた。
「──言いたいことがある。でも紗凪の泣き顔を他の人に見られたくない。あちらに行こう」
「……はい」
私も黄瀬さんに倣うように立ち上がり、手を引かれて歩きだした。
ここはイルミネーションなんか灯ってないのに、私の視界が滲んでしまっているから、目の前がキラキラして見えた。
なんだか──学生のとき。
こうして黄瀬さんと一緒に歩いていたら。
こんな風にイルミネーションは輝いていたんじゃないかと、今と昔が交錯した。
イルミネーション広場を離れつつ、黄瀬さんは私を見て呟いた。
「紗凪。太っているとか、いないとかそんなの関係ない。俺は紗凪だから好きになった。料理が得意で、美味しそうに食べているのが可愛いなって思った。俺の家はあまり家庭料理とか縁が無かったから……凄く魅力的に見えたんだ」
「黄瀬さん……」
夜の月明かりと同じぐらいに優しく、どこか切なく笑う黄瀬さん。その向こうにベイブリッジ、遊覧船が揺れてロマンチックだった。
広場からベイサイドエリアに移動して、すぐそばは海だった。波の音が穏やかで優しく、私の心を包んでくれるよう。
どこまでもこうして、優しい夜を二人で歩きたいと思えた。
黄瀬さんのご両親はきっと多忙だったのだろう。
その高校生という多感なときに、料理を披露していた私の存在が目立ったのだろう。
人を好きになるってそれで充分。
そんな初々しい気持ち忘れていたと思った。広大な海を前にしてそんな気分になれた。
「俺が女子達を信じてしまったのは、紗凪は当時から男子に人気があったからだ」
「うそ」
涙が思わず引っ込んだ。
「うそじゃない。紗凪は良く料理を作って皆にニコニコと差し入れしてただろ。それで胃袋を掴まれた男子が多くいた」
「う、うそ……」
「しかも、差し入れはどれも絶品。付き合うだけなら、他の女子が良いと言う男子も確かにいたけど、長く付き合うなら。青樹さんがいいって言う男子が結構いた」
「そんなっ。私、男子に告白されたことないし」
カツカツと共に歩く速度が速くなる。
「なんと言うか。見守りたくなる感じの女子と言うか。誰かが抜け駆けをして、手を出すのは卑怯みたいな。そんな雰囲気があった」
「……」
「でも、俺は受験前にどうしても気持ちを伝えたかったんだ」
ここまで聞いてしまったら否定しにくい。真実って本当に意地悪だ。こんなことを後から知るなんて、気持ちに置き場所がない。
当時の私はお母さんから教えて貰った料理を皆に知って貰うのが楽しくて、それを食べて貰うのが嬉しかっただけ。
今日作ったクッキーだってそうだ。
黄瀬さんに喜んで貰えたらそれでいい。
喜んで欲しいという、その気持ちは今も昔も思いは変わらない。
その精神の延長線に秘書と言う仕事を選んだのだから──と思えたら、涙は止まり。
笑うことが出来た。
私の手を握る黄瀬さんの手に、そっと指を絡ませた。
すると黄瀬さんの歩みが止まった。
ざあっと海風が私達の髪を揺らす。髪を抑えながら話す。
「そうだったんですね。今度お母さんに会ったら、お母さんの料理はモテモテだったって伝えておきます」
「──その笑顔。やっぱり紗凪は何も変わってない。いや、違う。綺麗になった。再び出会えたとき運命だと思った。もう二度と離すものかと感じた。本当はすぐにでも交際を申し込みたかったが、紗凪が仕事に向ける気持ちが分かったから我慢した」
黄瀬さんは私の心を射抜くように私を見つめる。
重ねていた手がつっと離れ。私の頬に触れてぐっと距離を詰めてきた。
それはキスをされてしまう距離。黄瀬さんに捉えられたと感じた。
こんな雰囲気ある場所で、そんな風に口説かれたら体も唇も動かせず。私も黄瀬さんを見つめ返すだけで精一杯。
「紗凪。あのときは引いたが、今はもう引かない」
「き、きせさんっ」
「紗凪、好きだ。俺と今度こそ、もう一度恋をしてくれ」
「……っ!」
返事を待たずにして、私達の唇は重なった。
それは私達が大人になった証拠だと感じた。
唇を軽く啄まれ。角度を変えてお互いの唇の感触が触れ合うと、ホテルで交わした情熱的なキスが蘇る。
黄瀬さんの手が私の腰へと回って、ぐいっと抱き寄せられると胸のトキメキは加速する。
唇から蕩けそうな甘いキスを授けられて。
息ってどうやってするんだったかなと、うっとりとしてしまうと唇は緩やかに離れて行った。
「……んっ」
キスの余韻でクラクラする。
その絶妙なタイミングに、男性としての魅力を意識せざるを得ない。
「紗凪。返事が聞きたい」
「私は──」
予期せぬ出来事だったとはいえホテルで触れ合い、こうしてキスを受け入れている。
黄瀬さんのことは好きだと心が訴える。
胸の高鳴りは恋を期待している。
なのに直ぐに『好きです』とは言えなかった。
頭が反発した。
その理由もちゃんとわかっている。
このまま過去のように口を閉ざして、過ちを繰り返さないように。今の素直な気持ちを伝える。
「私は今も昔も。黄瀬さんに惹かれてます。す、好きです。こうしてキスされて嬉しかった。でもっ」
「でも?」
僅かに私の腰を抱く黄瀬さんの手に力が籠る。
「私、秘書の仕事が好きなんです。akaiを辞めて、キセイ堂に再就職できて嬉しかった。パーティーでの出来事は驚いたけど……」
一瞬だけ俯き、また顔を上げて黄瀬さんにちゃんと伝える。
「それでも仕事が好きです。そうして頑張ってやっと一ヶ月が経った。でも、私はまだ恋も仕事も上手く出来る気がしないんです。それに、社長とデキてるから秘書になったんだって、思われたくなくて……そんな風に周りに言われないように、交際をする自信が今はまだ、持てないんです」
この一カ月間。
忙しさでなんとか恋心を誤魔化して来たことは認める。黄瀬さんにドキッとした場面は幾つもあった。
現状そんな状態で、これから恋心を自覚して仕事をちゃんとする自分のイメージが浮かばなかった。
他にも理由はある。
じっと黙って聞いてくれる黄瀬さんに、包み隠さず気持ちを吐き出す。
「キセイ堂の社長と秘書の私。私の家はごく普通のありふれた家庭です。そんな私が社長と釣り合うのかとか……もっと、美人な人が黄瀬さんとお似合いではとか。一瞬でもそんなことを考えてしまったり。好きだからこそ、いろんなことを考えてしまうんです」
口に出すと不安要素がポロポロと溢れた。
それは私と黄瀬さんには社会的立場の差があるからだ。そこを無視なんか出来なかった。
大人になったのに、ちっとも上手く恋も出来ない自分に歯痒さを感じてしまい。
「これが私の今の素直な気持ちです」と言ってから、次の言葉が出て来なかった。
波音と海風がゆっくりと通りすぎると──黄瀬さんの手が私の頬に触れた。
「本当の気持ちを言ってくれてありがとう。でも、紗凪がなんと言おうと俺の気持ちは変わらない」
「私……」
「紗凪の気持ちもわかった。だったら──紗凪が俺や仕事に慣れるまで。俺と居てもそんな風に思わなくても、いいようになるまで待とう」
「ま、待たせるなんて」
「大丈夫。ぼうっと待つつもりなんか一切ない」
「え」
「働いている時間はこれまで通り社長と秘書の一線を超えない。好きだからと言ってその感情を、仕事には持ち出さない」
ハキハキと喋るその姿に、私が好きなんだと言う気持ちがハッキリと見える。
恥ずかしいのにずっと、聞いてしまいたくなる気持ちになった。
「でも、仕事が終われば別だ。仕事が終わったら紗凪を口説く。俺には紗凪しかいないって、わかって貰えるまで口説き落とす」
「!」
挑むような強い視線に、口をパクパクさせてしまう。
「紗凪、俺は仕事も紗凪も手に入れる」
頬に触れられていた手が、するっと私の唇へと落ちればキスの余韻を思いだし。
黄瀬さんの情熱的な瞳に囚われて、気がつけば「はい」と返事をしてしまっていた。
「昔ね。ここは毎日綺麗なイルミネーションが点灯されていて、この場所でデートした恋人はずっと仲良しで居られるという、他愛のないジンクスがあった」
「へぇ。なんか可愛くていいですね」
「だろ。学生のとき。紗凪と一緒にここに来たかった」
ふっと笑って黄瀬さんは私を見た。
「!」
「覚えているかな。俺と紗凪は同級生。しかも俺は紗凪に告白したことがある。場所はベタに校舎の裏庭。放課後。死ぬほど緊張した」
「お、覚えていますよ! だって当時から黄瀬さんは凄い女子から人気があって。でも……何らかの理由で……あれは罰ゲームの告白だったんですよね?」
「──え?」
黄瀬さんの表情が硬まる。
先に私が核心をついてしまったかと慌てた。
「あ。大丈夫です。その気にしてませんから。ほらっ。私、当時太っていたし。一瞬だけでもいい夢見れたなぁって思っていたから」
だから、大人になって再会してもスルーしていた。仕事を優先したと、わたわたと伝えた。
けど、黄瀬さんは驚きの表情のままだった。
「ま、待ってくれ。罰ゲームの告白? 一体誰がそんなことを? むしろ紗凪は当時、他に付き合っていてる人がいて、俺を振ったんじゃないのか?」
黄瀬さんはばっと私に向きなおり、今まで見たことのない慌てようで私も焦ってしまう。
「えっ、だってあのギャル達が! 私、当時誰とも付き合ってませんよっ!? むしろ今まであんまり男性とお付き合いして来なかった、ぐらなんですけどっ」
お互いに混乱しあう。しかし、何か行き違いがあるのは確実だと思った。
なんでだろうと首を傾げると、黄瀬さんは私の顔をじっと見て。戸惑いながらも口を開いた。
「紗凪があまり男性と付き合ってない……こんなにも可愛いのに?」
「!!」
スーツ姿も凛々しく。今も昔もカッコいい男性にそんなことを言われたら、思考回路が完全に止まった。
風がしゃらんと耳元のタッセルを揺らして、言葉を紡げないでいると黄瀬さんが口元に手を置いて、もしかしてと言った。
「俺の告白が罰ゲームだと言ったのは、ギャル達と言ってたが……それは本当?」
こくりと頷く。
「俺もね。当時、ギャルみたいに化粧も香水もしっかりと纏った女子達から『青樹さんは、あぁ見えても付き合っている人がいる。だからやめといた方が良い』って言われた。ショックだった」
そんなことを言われていたなんて。
驚きで、怒りよりも胸が苦しくなる。
「実はそれが原因で香水のキツイ匂いが苦手になった」
あぁ。だから。黄瀬さんは香水の強い香りが苦手。
納得がいった。
そして、もっと気になること。
私が誰かと付き合っていると言うこと。
高校時代、そんな人はいない。
と言うことは──。
「それって、まさか」
「それを聞いて次の日、紗凪に本当かどうか訪ねようと思ったら避けられてしまい。思わず手を掴んだら『離して』って言われたから、あの女子達が言ったことは本当だと、思ってしまって──それで身を引いた」
口調も表情も寂しげに黄瀬さんは語った。そこに嘘を言ってる様子はない。まさかと思い当たったことを口にする。
「私は本当にお付き合いした人なんていません。多分ですが、黄瀬さんは当時から女子に凄く人気高かったから……ひょっとして告白をギャル達に知られしまって」
私が喉をこくっと鳴らしたあと。
「俺達を仲違いをさせた──と言うことか」
黄瀬さんが静かに言葉を繋いでくれた。
そのときぱちっと、頭の中で全てがのことが綺麗に収まったのを感じた。
ギャル達は私に罰ゲームだと言って、黄瀬さんを諦めさせた。黄瀬さんには私が付き合っている人がいると言って、私を諦めさせた。
──これが真実だと思った。
はぁと大きくため息をして空を見上げる。夜空やここから見える夜景が綺麗なだけ、ほんの少し救われた気分になった。
なんと単純な罠だろう。
それでも信じてしまったのは初恋だから。幼かったから。
今更当時の女子達に真意を聞いても仕方ない。悪意ある第三者に私達の初恋は邪魔をされたのだと、やっと腑に落ちた。
そして──ぽろりと涙が溢れた。慌てて涙をふく。
「っ、紗凪? どうした?」
一瞬、潮風が目に染みたと言おうかと思ったけど、素直に気持ちを伝えようと思った。
「すみません。なんだか安心したと言うか……私達、勘違いしてしまったけど。両思いだったんですね」
またぽろりと涙が溢れる。
「あの告白は罰ゲームじゃ無かったんだって思うと、やっぱり嬉しいなぁって……それにもっと素直に、黄瀬さんを信じてあげれば良かった。本当にごめんなさい」
「違うっ。謝るのは俺のほうだ。俺のほうこそ……!」
さらっと流して欲しいのに心配そうに私を見る、黄瀬さんに首を横に振る。
「ううん。違うんです。私、太っていて自分に自信がなかった。だから『罰ゲーム』って言う言葉を信じてしまったんです。本当は黄瀬さんみたいな、素敵な人に告白されて嬉しかったのに」
くすっと軽く笑うと、黄瀬さんがばっと私の手を掴んだ。
「俺は今でもっ──!」
指の先から感情が伝わるほどに暖かな手だった。
そして横を見てから、スッと立ち上がった。
なぜだろうと思っていると、向こうから男女のグループが歩いて来るのが見えた。
「──言いたいことがある。でも紗凪の泣き顔を他の人に見られたくない。あちらに行こう」
「……はい」
私も黄瀬さんに倣うように立ち上がり、手を引かれて歩きだした。
ここはイルミネーションなんか灯ってないのに、私の視界が滲んでしまっているから、目の前がキラキラして見えた。
なんだか──学生のとき。
こうして黄瀬さんと一緒に歩いていたら。
こんな風にイルミネーションは輝いていたんじゃないかと、今と昔が交錯した。
イルミネーション広場を離れつつ、黄瀬さんは私を見て呟いた。
「紗凪。太っているとか、いないとかそんなの関係ない。俺は紗凪だから好きになった。料理が得意で、美味しそうに食べているのが可愛いなって思った。俺の家はあまり家庭料理とか縁が無かったから……凄く魅力的に見えたんだ」
「黄瀬さん……」
夜の月明かりと同じぐらいに優しく、どこか切なく笑う黄瀬さん。その向こうにベイブリッジ、遊覧船が揺れてロマンチックだった。
広場からベイサイドエリアに移動して、すぐそばは海だった。波の音が穏やかで優しく、私の心を包んでくれるよう。
どこまでもこうして、優しい夜を二人で歩きたいと思えた。
黄瀬さんのご両親はきっと多忙だったのだろう。
その高校生という多感なときに、料理を披露していた私の存在が目立ったのだろう。
人を好きになるってそれで充分。
そんな初々しい気持ち忘れていたと思った。広大な海を前にしてそんな気分になれた。
「俺が女子達を信じてしまったのは、紗凪は当時から男子に人気があったからだ」
「うそ」
涙が思わず引っ込んだ。
「うそじゃない。紗凪は良く料理を作って皆にニコニコと差し入れしてただろ。それで胃袋を掴まれた男子が多くいた」
「う、うそ……」
「しかも、差し入れはどれも絶品。付き合うだけなら、他の女子が良いと言う男子も確かにいたけど、長く付き合うなら。青樹さんがいいって言う男子が結構いた」
「そんなっ。私、男子に告白されたことないし」
カツカツと共に歩く速度が速くなる。
「なんと言うか。見守りたくなる感じの女子と言うか。誰かが抜け駆けをして、手を出すのは卑怯みたいな。そんな雰囲気があった」
「……」
「でも、俺は受験前にどうしても気持ちを伝えたかったんだ」
ここまで聞いてしまったら否定しにくい。真実って本当に意地悪だ。こんなことを後から知るなんて、気持ちに置き場所がない。
当時の私はお母さんから教えて貰った料理を皆に知って貰うのが楽しくて、それを食べて貰うのが嬉しかっただけ。
今日作ったクッキーだってそうだ。
黄瀬さんに喜んで貰えたらそれでいい。
喜んで欲しいという、その気持ちは今も昔も思いは変わらない。
その精神の延長線に秘書と言う仕事を選んだのだから──と思えたら、涙は止まり。
笑うことが出来た。
私の手を握る黄瀬さんの手に、そっと指を絡ませた。
すると黄瀬さんの歩みが止まった。
ざあっと海風が私達の髪を揺らす。髪を抑えながら話す。
「そうだったんですね。今度お母さんに会ったら、お母さんの料理はモテモテだったって伝えておきます」
「──その笑顔。やっぱり紗凪は何も変わってない。いや、違う。綺麗になった。再び出会えたとき運命だと思った。もう二度と離すものかと感じた。本当はすぐにでも交際を申し込みたかったが、紗凪が仕事に向ける気持ちが分かったから我慢した」
黄瀬さんは私の心を射抜くように私を見つめる。
重ねていた手がつっと離れ。私の頬に触れてぐっと距離を詰めてきた。
それはキスをされてしまう距離。黄瀬さんに捉えられたと感じた。
こんな雰囲気ある場所で、そんな風に口説かれたら体も唇も動かせず。私も黄瀬さんを見つめ返すだけで精一杯。
「紗凪。あのときは引いたが、今はもう引かない」
「き、きせさんっ」
「紗凪、好きだ。俺と今度こそ、もう一度恋をしてくれ」
「……っ!」
返事を待たずにして、私達の唇は重なった。
それは私達が大人になった証拠だと感じた。
唇を軽く啄まれ。角度を変えてお互いの唇の感触が触れ合うと、ホテルで交わした情熱的なキスが蘇る。
黄瀬さんの手が私の腰へと回って、ぐいっと抱き寄せられると胸のトキメキは加速する。
唇から蕩けそうな甘いキスを授けられて。
息ってどうやってするんだったかなと、うっとりとしてしまうと唇は緩やかに離れて行った。
「……んっ」
キスの余韻でクラクラする。
その絶妙なタイミングに、男性としての魅力を意識せざるを得ない。
「紗凪。返事が聞きたい」
「私は──」
予期せぬ出来事だったとはいえホテルで触れ合い、こうしてキスを受け入れている。
黄瀬さんのことは好きだと心が訴える。
胸の高鳴りは恋を期待している。
なのに直ぐに『好きです』とは言えなかった。
頭が反発した。
その理由もちゃんとわかっている。
このまま過去のように口を閉ざして、過ちを繰り返さないように。今の素直な気持ちを伝える。
「私は今も昔も。黄瀬さんに惹かれてます。す、好きです。こうしてキスされて嬉しかった。でもっ」
「でも?」
僅かに私の腰を抱く黄瀬さんの手に力が籠る。
「私、秘書の仕事が好きなんです。akaiを辞めて、キセイ堂に再就職できて嬉しかった。パーティーでの出来事は驚いたけど……」
一瞬だけ俯き、また顔を上げて黄瀬さんにちゃんと伝える。
「それでも仕事が好きです。そうして頑張ってやっと一ヶ月が経った。でも、私はまだ恋も仕事も上手く出来る気がしないんです。それに、社長とデキてるから秘書になったんだって、思われたくなくて……そんな風に周りに言われないように、交際をする自信が今はまだ、持てないんです」
この一カ月間。
忙しさでなんとか恋心を誤魔化して来たことは認める。黄瀬さんにドキッとした場面は幾つもあった。
現状そんな状態で、これから恋心を自覚して仕事をちゃんとする自分のイメージが浮かばなかった。
他にも理由はある。
じっと黙って聞いてくれる黄瀬さんに、包み隠さず気持ちを吐き出す。
「キセイ堂の社長と秘書の私。私の家はごく普通のありふれた家庭です。そんな私が社長と釣り合うのかとか……もっと、美人な人が黄瀬さんとお似合いではとか。一瞬でもそんなことを考えてしまったり。好きだからこそ、いろんなことを考えてしまうんです」
口に出すと不安要素がポロポロと溢れた。
それは私と黄瀬さんには社会的立場の差があるからだ。そこを無視なんか出来なかった。
大人になったのに、ちっとも上手く恋も出来ない自分に歯痒さを感じてしまい。
「これが私の今の素直な気持ちです」と言ってから、次の言葉が出て来なかった。
波音と海風がゆっくりと通りすぎると──黄瀬さんの手が私の頬に触れた。
「本当の気持ちを言ってくれてありがとう。でも、紗凪がなんと言おうと俺の気持ちは変わらない」
「私……」
「紗凪の気持ちもわかった。だったら──紗凪が俺や仕事に慣れるまで。俺と居てもそんな風に思わなくても、いいようになるまで待とう」
「ま、待たせるなんて」
「大丈夫。ぼうっと待つつもりなんか一切ない」
「え」
「働いている時間はこれまで通り社長と秘書の一線を超えない。好きだからと言ってその感情を、仕事には持ち出さない」
ハキハキと喋るその姿に、私が好きなんだと言う気持ちがハッキリと見える。
恥ずかしいのにずっと、聞いてしまいたくなる気持ちになった。
「でも、仕事が終われば別だ。仕事が終わったら紗凪を口説く。俺には紗凪しかいないって、わかって貰えるまで口説き落とす」
「!」
挑むような強い視線に、口をパクパクさせてしまう。
「紗凪、俺は仕事も紗凪も手に入れる」
頬に触れられていた手が、するっと私の唇へと落ちればキスの余韻を思いだし。
黄瀬さんの情熱的な瞳に囚われて、気がつけば「はい」と返事をしてしまっていた。
1
あなたにおすすめの小説

腹黒外科医に唆された件~恋人(仮)のはずが迫られています~
有木珠乃
恋愛
両親を亡くし、二人だけの姉妹になった一ノ瀬栞と琴美。
ある日、栞は轢き逃げ事故に遭い、姉の琴美が務める病院に入院することになる。
そこで初めて知る、琴美の婚約者の存在。
彼らの逢引きを確保するために利用される栞と外科医の岡。
「二人で自由にならないか?」を囁かれて……。

【完結】あなた専属になります―借金OLは副社長の「専属」にされた―
七転び八起き
恋愛
『借金を返済する為に働いていたラウンジに現れたのは、勤務先の副社長だった。
彼から出された取引、それは『専属』になる事だった。』
実家の借金返済のため、昼は会社員、夜はラウンジ嬢として働く優美。
ある夜、一人でグラスを傾ける謎めいた男性客に指名される。
口数は少ないけれど、なぜか心に残る人だった。
「また来る」
そう言い残して去った彼。
しかし翌日、会社に現れたのは、なんと店に来た彼で、勤務先の副社長の河内だった。
「俺専属の嬢になって欲しい」
ラウンジで働いている事を秘密にする代わりに出された取引。
突然の取引提案に戸惑う優美。
しかし借金に追われる現状では、断る選択肢はなかった。
恋愛経験ゼロの優美と、完璧に見えて不器用な副社長。
立場も境遇も違う二人が紡ぐラブストーリー。
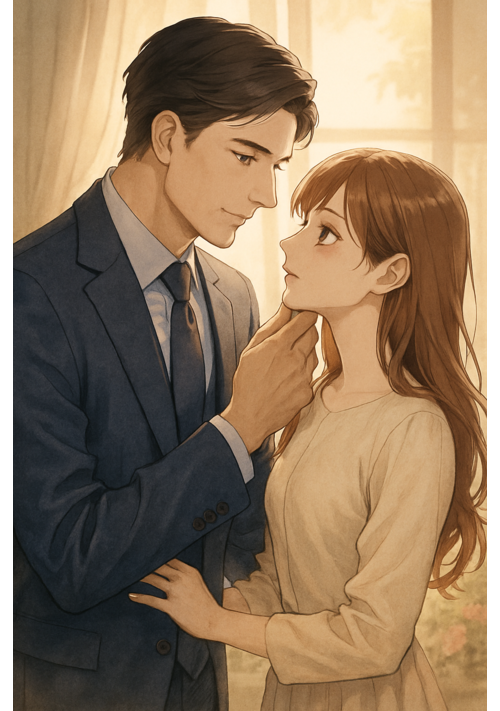
15歳差の御曹司に甘やかされています〜助けたはずがなぜか溺愛対象に〜 【完結】
日下奈緒
恋愛
雨の日の交差点。
車に轢かれそうになったスーツ姿の男性を、とっさに庇った大学生のひより。
そのまま病院へ運ばれ、しばらくの入院生活に。
目を覚ました彼女のもとに毎日現れたのは、助けたあの男性――そして、大手企業の御曹司・一ノ瀬玲央だった。
「俺にできることがあるなら、なんでもする」
花や差し入れを持って通い詰める彼に、戸惑いながらも心が惹かれていくひより。
けれど、退院の日に告げられたのは、彼のひとことだった。
「君、大学生だったんだ。……困ったな」
15歳という年の差、立場の違い、過去の恋。
簡単に踏み出せない距離があるのに、気づけばお互いを想う気持ちは止められなくなっていた――
「それでも俺は、君が欲しい」
助けたはずの御曹司から、溺れるほどに甘やかされる毎日が始まる。
これは、15歳差から始まる、不器用でまっすぐな恋の物語。

【完結】俺様御曹司の隠された溺愛野望 〜花嫁は蜜愛から逃れられない〜
椿かもめ
恋愛
「こはる、俺の妻になれ」その日、大女優を母に持つ2世女優の花宮こはるは自分の所属していた劇団の解散に絶望していた。そんなこはるに救いの手を差し伸べたのは年上の幼馴染で大企業の御曹司、月ノ島玲二だった。けれど代わりに妻になることを強要してきて──。花嫁となったこはるに対し、俺様な玲二は独占欲を露わにし始める。
【幼馴染の俺様御曹司×大物女優を母に持つ2世女優】
☆☆☆ベリーズカフェで日間4位いただきました☆☆☆
※ベリーズカフェでも掲載中
※推敲、校正前のものです。ご注意下さい

一目惚れ婚~美人すぎる御曹司に溺愛されてます~
椿蛍
恋愛
念願のデザイナーとして働き始めた私に、『家のためにお見合いしろ』と言い出した父と継母。
断りたかったけれど、病弱な妹を守るため、好きでもない相手と結婚することになってしまった……。
夢だったデザイナーの仕事を諦められない私――そんな私の前に現れたのは、有名な美女モデル、【リセ】だった。
パリで出会ったその美人モデル。
女性だと思っていたら――まさかの男!?
酔った勢いで一夜を共にしてしまう……。
けれど、彼の本当の姿はモデルではなく――
(モデル)御曹司×駆け出しデザイナー
【サクセスシンデレラストーリー!】
清中琉永(きよなかるな)新人デザイナー
麻王理世(あさおりせ)麻王グループ御曹司(モデル)
初出2021.11.26
改稿2023.10

美しき造船王は愛の海に彼女を誘う
花里 美佐
恋愛
★神崎 蓮 32歳 神崎造船副社長
『玲瓏皇子』の異名を持つ美しき御曹司。
ノースサイド出身のセレブリティ
×
☆清水 さくら 23歳 名取フラワーズ社員
名取フラワーズの社員だが、理由があって
伯父の花屋『ブラッサムフラワー』で今は働いている。
恋愛に不器用な仕事人間のセレブ男性が
花屋の女性の夢を応援し始めた。
最初は喧嘩をしながら、ふたりはお互いを認め合って惹かれていく。

恋愛禁止条項の火消し屋は、子会社社長を守る側に立つ
swingout777
恋愛
本社人事の“火消し屋”として働く私は、統合プロジェクトの責任者として子会社へ常駐するよう命じられた。スローガンは「雇用を守るための統合」。――けれど赴任初日、私が見つけたのは“片道三時間・期限二週間”の勤務地強制テンプレ。家庭持ちを狙い撃ちにして辞めさせる、実質退職の設計書だった。
現場では、共働きの夫婦が「私が辞める」と言い出し、夫が初めて怒って泣いていた。私は火消し屋だ。誰かを守るために、誰かを切る仕事もしてきた。だからこそ言った。「辞めないで済む道は作る。でも、あなた達にも戦ってほしい。声を上げないと、都合のいい数字にされるから」
そんな夜、子会社社長の不倫疑惑が週刊誌に出た。ホテル密会写真。火消しのため社長に張り付く私を、現場叩き上げの彼は冷たく突き放す。「本社の犬か?」――だが写真の裏にあったのは、不倫ではなく“保護”だった。社長が匿っていたのは、会社の闇を握る男性告発者。潰されかけ、経歴ごと消される寸前の人間を、彼は自分が汚れる覚悟で救っていた。
本社は告発者にパワハラの濡れ衣を着せ、部下の新人に「守秘義務違反で潰す」と脅して証言させる。匿名通報が量産され、「新人は告発者とつながっている」という空気が社内を支配する。さらには社内チャットが切り貼りされ、私まで“共犯”に仕立て上げられた――「あなたも同じ側ですよね」。孤立した私の前に届いた、切り貼りではない全文。「あなたも同じ側ですよね。――守る側に立つなら、これを見てください」添付されていたのは、あの勤務地強制テンプレだった。
恋愛禁止条項を運用してきた私が、守るためにルールを破る側へ回る。社員を守ろうとする社長と、ルールを武器に人を切る本社人事部長。雇用を守る顔をした統合の裏で、恋は噂になり、噂は刃になる。それでも私は決める。守る側に立つ。――守りながら恋をするために。

『冷徹社長の秘書をしていたら、いつの間にか専属の妻に選ばれました』
鍛高譚
恋愛
秘書課に異動してきた相沢結衣は、
仕事一筋で冷徹と噂される社長・西園寺蓮の専属秘書を務めることになる。
厳しい指示、膨大な業務、容赦のない会議――
最初はただ必死に食らいつくだけの日々だった。
だが、誰よりも真剣に仕事と向き合う蓮の姿に触れるうち、
結衣は秘書としての誇りを胸に、確かな成長を遂げていく。
そして、蓮もまた陰で彼女を支える姿勢と誠実な仕事ぶりに心を動かされ、
次第に結衣は“ただの秘書”ではなく、唯一無二の存在になっていく。
同期の嫉妬による妨害、ライバル会社の不正、社内の疑惑。
数々の試練が二人を襲うが――
蓮は揺るがない意志で結衣を守り抜き、
結衣もまた社長としてではなく、一人の男性として蓮を信じ続けた。
そしてある夜、蓮がようやく口にした言葉は、
秘書と社長の関係を静かに越えていく。
「これからの人生も、そばで支えてほしい。」
それは、彼が初めて見せた弱さであり、
結衣だけに向けた真剣な想いだった。
秘書として。
一人の女性として。
結衣は蓮の差し伸べた未来を、涙と共に受け取る――。
仕事も恋も全力で駆け抜ける、
“冷徹社長×秘書”のじれ甘オフィスラブストーリー、ここに完結。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















