25 / 100
第25話:穏やかな日々の終わり
しおりを挟む
公爵邸での日々は、まるで陽だまりの中で微睡んでいるかのように、穏やかに過ぎていった。
執事長のセバスチャンさんも、騎士団長のギルバート様も、今では私をアシュレイ様の対等なパートナーとして扱い、敬意を払ってくれる。使用人たちの笑顔も、マーサさんの温かい気遣いも、全てが私の心を優しく満たしてくれた。
そして何より、アシュレイ様の存在が、私の世界の中心にあった。
彼の呪いは、日々の『癒やしの時間』によって、薄皮を剥がすように少しずつ快方へと向かっていた。彼が本来の感情を取り戻していく過程を、一番近くで見守ることができる。それが、私にとって何よりの幸福だった。
かつて「出来損ない」と蔑まれ、息を潜めるように生きていた日々が、まるで遠い昔の悪夢のように感じられる。
私は、この幸せな日々が、永遠に続いていくのだと、何の疑いもなく信じていた。
その穏やかな日常が、終わりを告げる予兆もなく、唐突に破られることになるとも知らずに。
その日も、空はどこまでも青く澄み渡っていた。
私はアシュレイ様と共に、蘇った花壇の世話をしていた。二人で土に触れ、花に水をやり、他愛もない話をして笑い合う。そんな何気ない時間が、私には宝物のように思えた。
「この青い花、君の瞳の色によく似ている」
アシュレイ様が、お母様の形見の花を指さして言う。
「まあ。アシュレイ様の瞳の色は、この紫の花のようですわ」
私がそう返すと、彼は少し照れたように視線を逸らし、私の髪にそっと触れた。
そんな甘やかな空気が、私たちの間に流れていた、その時だった。
屋敷の正面玄関の方から、けたたましい蹄の音と、馬車の到着を告げる声が聞こえてきた。それは、来客を知らせるいつもの合図とは明らかに違う、どこか切迫した響きを持っていた。
アシュレイ様の表情が、すっと引き締まる。穏やかな恋人の顔から、一瞬にして『氷の公爵』の貌へと切り替わった。
「……何事だ」
彼が低く呟くと同時に、執事のセバスチャンさんが慌てた様子で庭園へと駆け込んできた。その完璧な執事の仮面が、わずかに崩れている。よほどのことなのだろう。
「アシュレイ様! 王宮より、勅使がお見えになりました!」
「王宮から? 事前の連絡はなかったはずだが」
アシュレイ様の問いに、セバスチャンさんは緊張した面持ちで首を横に振った。
「はい。国王陛下からの、緊急の勅命とのことでございます」
国王陛下からの、勅命。
その言葉の重みに、私の心臓がどきりと跳ねた。空気を読んだのか、私の隣にいたアシュレイ様が、私を安心させるように、そっと私の手を握ってくれた。その手は、いつもと変わらず温かかった。
私たちは、急いで応接室へと向かった。
壮麗な応接室の中央には、王家の使者である近衛騎士が二人、そして壮年の文官が一人、硬い表情で直立していた。彼らの前には、丁重に白い布で覆われた、一つの長細い桐の箱が置かれている。
アシュレイ様が部屋に入るなり、彼らは一斉に深々と頭を下げ、騎士の礼を取った。
「アイゼンベルク公爵閣下にはご壮健のこと、お慶び申し上げます」
文官が、仰々しい口調で口上を述べた。
アシュレイ様は、国王の椅子と対になるように置かれた、公爵専用の豪奢な椅子にゆったりと腰を下ろした。その姿には、先ほどまでの穏やかさは欠片もなく、王家に次ぐ権力者としての圧倒的な威厳が満ち溢れている。私も、彼の後ろに控えるように、静かに佇んだ。
「それで、勅命とは何だ。もったいぶらずに申せ」
アシュレイ様の低い声が、部屋の空気を震わせる。
文官は居住まいを正すと、恭しく一通の親書をアシュレイ様に差し出した。セバスチャンさんがそれを受け取り、アシュレイ様に手渡す。
アシュレイ様は封蝋を解くと、静かに書面に目を通し始めた。
最初は、いつもと変わらぬ無表情だった。だが、読み進めるうちに、その紫の瞳に、鋭く、そして冷たい光が宿っていくのが分かった。部屋の温度が、数度下がったかのような錯覚さえ覚える。
親書を読み終えた彼は、それを静かにテーブルの上に置いた。そして、凍てつくような声で、文官に問いかけた。
「……それで、その箱の中身は、親書に書かれている通りのものなのだろうな」
「はっ。相違ございません」
文官は、アシュレイ様の威圧感に気圧されたように、額に汗を浮かべている。彼は騎士たちに目配せをすると、二人掛かりで、その桐の箱をアシュレイ様の前のテーブルへと運んだ。
そして、ゆっくりと、白い布が取り払われる。
現れたのは、剣だった。
しかし、それはもはや剣と呼べる代物ではなかった。刀身は真ん中から無残にぽっきりと折れ、柄に繋がっている部分も、刃こぼれやひび割れが無数に入っている。鞘はなく、鈍い銀色の刀身は、長い年月の間にその輝きを失い、ただの鉄塊のように見えた。
唯一、柄の部分に嵌め込まれた大きな青い宝石だけが、その剣がかつては非凡なものであったことを物語っていた。
「これは……」
私が息をのむと、アシュレイ様が私の疑問に答えるように、静かに言った。
「我が国に伝わる、伝説の聖剣『エクシード』だ」
聖剣エクシード。
その名前は、私のような世間知らずの娘でも、物語の本で読んだことがあった。百年前、大陸を闇に陥れようとした魔王を、建国の英雄王が打ち破る際に用いたとされる、伝説の剣。
「英雄王が魔王に最後の一撃を加えた際、その強大な力に耐えきれず、聖剣もまた折れたと伝えられている。以来、百年もの間、王家の宝物庫の奥深くで眠っていたはずだが……」
アシュレイ様は、鋭い視線で文官を射抜いた。
「なぜ、今になって、このような形で私の元へ届けられた? 国王陛下の真意は何だ」
その問いに、文官はごくりと喉を鳴らした。
「親書にもございました通り、陛下は噂をお聞きになられたのです」
「噂?」
「はい。アイゼンベルク公爵閣下のお傍には、いかなる壊れたものでも元に戻すという、奇跡の力を持つ乙女がいる、と」
その言葉が向けられたのが、私であることは明らかだった。使者たちの視線が、好奇と不信の色をない交ぜにして、私へと突き刺さる。
私はたまらず、アシュレイ様の背後に身を隠した。
「陛下は、その力の真偽を確かめたいと仰せです。もしその力が本物であるならば、この折れたる聖剣を修復し、王家への揺るぎなき忠誠の証として示されたし、と。……それが、国王陛下からの勅命にございます」
部屋の中に、重い沈黙が落ちた。
私の力が、ついに王宮にまで知られてしまった。そして、国王陛下は、私の力を試そうとしている。
アシュレイ様は、何も言わなかった。ただ、その紫の瞳の奥で、静かで、しかし激しい怒りの炎が燃え上がっているのが、彼の隣にいる私には痛いほど分かった。
彼は、私が政治の道具として利用されることを、何よりも嫌悪している。
壊れた聖剣。国王の勅命。
それは、私たちの穏やかな日々の終わりを告げると共に、私の運命の歯車を、大きく、そして否応なく回し始める合図だった。
執事長のセバスチャンさんも、騎士団長のギルバート様も、今では私をアシュレイ様の対等なパートナーとして扱い、敬意を払ってくれる。使用人たちの笑顔も、マーサさんの温かい気遣いも、全てが私の心を優しく満たしてくれた。
そして何より、アシュレイ様の存在が、私の世界の中心にあった。
彼の呪いは、日々の『癒やしの時間』によって、薄皮を剥がすように少しずつ快方へと向かっていた。彼が本来の感情を取り戻していく過程を、一番近くで見守ることができる。それが、私にとって何よりの幸福だった。
かつて「出来損ない」と蔑まれ、息を潜めるように生きていた日々が、まるで遠い昔の悪夢のように感じられる。
私は、この幸せな日々が、永遠に続いていくのだと、何の疑いもなく信じていた。
その穏やかな日常が、終わりを告げる予兆もなく、唐突に破られることになるとも知らずに。
その日も、空はどこまでも青く澄み渡っていた。
私はアシュレイ様と共に、蘇った花壇の世話をしていた。二人で土に触れ、花に水をやり、他愛もない話をして笑い合う。そんな何気ない時間が、私には宝物のように思えた。
「この青い花、君の瞳の色によく似ている」
アシュレイ様が、お母様の形見の花を指さして言う。
「まあ。アシュレイ様の瞳の色は、この紫の花のようですわ」
私がそう返すと、彼は少し照れたように視線を逸らし、私の髪にそっと触れた。
そんな甘やかな空気が、私たちの間に流れていた、その時だった。
屋敷の正面玄関の方から、けたたましい蹄の音と、馬車の到着を告げる声が聞こえてきた。それは、来客を知らせるいつもの合図とは明らかに違う、どこか切迫した響きを持っていた。
アシュレイ様の表情が、すっと引き締まる。穏やかな恋人の顔から、一瞬にして『氷の公爵』の貌へと切り替わった。
「……何事だ」
彼が低く呟くと同時に、執事のセバスチャンさんが慌てた様子で庭園へと駆け込んできた。その完璧な執事の仮面が、わずかに崩れている。よほどのことなのだろう。
「アシュレイ様! 王宮より、勅使がお見えになりました!」
「王宮から? 事前の連絡はなかったはずだが」
アシュレイ様の問いに、セバスチャンさんは緊張した面持ちで首を横に振った。
「はい。国王陛下からの、緊急の勅命とのことでございます」
国王陛下からの、勅命。
その言葉の重みに、私の心臓がどきりと跳ねた。空気を読んだのか、私の隣にいたアシュレイ様が、私を安心させるように、そっと私の手を握ってくれた。その手は、いつもと変わらず温かかった。
私たちは、急いで応接室へと向かった。
壮麗な応接室の中央には、王家の使者である近衛騎士が二人、そして壮年の文官が一人、硬い表情で直立していた。彼らの前には、丁重に白い布で覆われた、一つの長細い桐の箱が置かれている。
アシュレイ様が部屋に入るなり、彼らは一斉に深々と頭を下げ、騎士の礼を取った。
「アイゼンベルク公爵閣下にはご壮健のこと、お慶び申し上げます」
文官が、仰々しい口調で口上を述べた。
アシュレイ様は、国王の椅子と対になるように置かれた、公爵専用の豪奢な椅子にゆったりと腰を下ろした。その姿には、先ほどまでの穏やかさは欠片もなく、王家に次ぐ権力者としての圧倒的な威厳が満ち溢れている。私も、彼の後ろに控えるように、静かに佇んだ。
「それで、勅命とは何だ。もったいぶらずに申せ」
アシュレイ様の低い声が、部屋の空気を震わせる。
文官は居住まいを正すと、恭しく一通の親書をアシュレイ様に差し出した。セバスチャンさんがそれを受け取り、アシュレイ様に手渡す。
アシュレイ様は封蝋を解くと、静かに書面に目を通し始めた。
最初は、いつもと変わらぬ無表情だった。だが、読み進めるうちに、その紫の瞳に、鋭く、そして冷たい光が宿っていくのが分かった。部屋の温度が、数度下がったかのような錯覚さえ覚える。
親書を読み終えた彼は、それを静かにテーブルの上に置いた。そして、凍てつくような声で、文官に問いかけた。
「……それで、その箱の中身は、親書に書かれている通りのものなのだろうな」
「はっ。相違ございません」
文官は、アシュレイ様の威圧感に気圧されたように、額に汗を浮かべている。彼は騎士たちに目配せをすると、二人掛かりで、その桐の箱をアシュレイ様の前のテーブルへと運んだ。
そして、ゆっくりと、白い布が取り払われる。
現れたのは、剣だった。
しかし、それはもはや剣と呼べる代物ではなかった。刀身は真ん中から無残にぽっきりと折れ、柄に繋がっている部分も、刃こぼれやひび割れが無数に入っている。鞘はなく、鈍い銀色の刀身は、長い年月の間にその輝きを失い、ただの鉄塊のように見えた。
唯一、柄の部分に嵌め込まれた大きな青い宝石だけが、その剣がかつては非凡なものであったことを物語っていた。
「これは……」
私が息をのむと、アシュレイ様が私の疑問に答えるように、静かに言った。
「我が国に伝わる、伝説の聖剣『エクシード』だ」
聖剣エクシード。
その名前は、私のような世間知らずの娘でも、物語の本で読んだことがあった。百年前、大陸を闇に陥れようとした魔王を、建国の英雄王が打ち破る際に用いたとされる、伝説の剣。
「英雄王が魔王に最後の一撃を加えた際、その強大な力に耐えきれず、聖剣もまた折れたと伝えられている。以来、百年もの間、王家の宝物庫の奥深くで眠っていたはずだが……」
アシュレイ様は、鋭い視線で文官を射抜いた。
「なぜ、今になって、このような形で私の元へ届けられた? 国王陛下の真意は何だ」
その問いに、文官はごくりと喉を鳴らした。
「親書にもございました通り、陛下は噂をお聞きになられたのです」
「噂?」
「はい。アイゼンベルク公爵閣下のお傍には、いかなる壊れたものでも元に戻すという、奇跡の力を持つ乙女がいる、と」
その言葉が向けられたのが、私であることは明らかだった。使者たちの視線が、好奇と不信の色をない交ぜにして、私へと突き刺さる。
私はたまらず、アシュレイ様の背後に身を隠した。
「陛下は、その力の真偽を確かめたいと仰せです。もしその力が本物であるならば、この折れたる聖剣を修復し、王家への揺るぎなき忠誠の証として示されたし、と。……それが、国王陛下からの勅命にございます」
部屋の中に、重い沈黙が落ちた。
私の力が、ついに王宮にまで知られてしまった。そして、国王陛下は、私の力を試そうとしている。
アシュレイ様は、何も言わなかった。ただ、その紫の瞳の奥で、静かで、しかし激しい怒りの炎が燃え上がっているのが、彼の隣にいる私には痛いほど分かった。
彼は、私が政治の道具として利用されることを、何よりも嫌悪している。
壊れた聖剣。国王の勅命。
それは、私たちの穏やかな日々の終わりを告げると共に、私の運命の歯車を、大きく、そして否応なく回し始める合図だった。
76
あなたにおすすめの小説
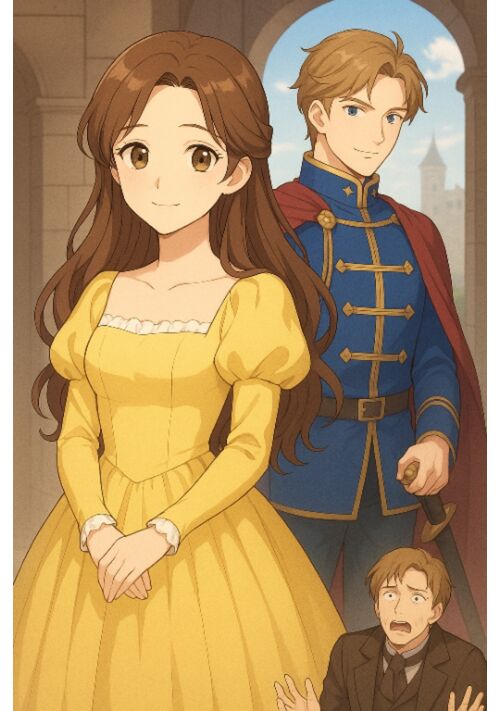
地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします
有賀冬馬
恋愛
子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。
唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。
もう二度と恋なんてしない。
そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。
彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。
彼は、この国の王太子だったのだ。
「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。
一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。
私に助けを求めてきた彼に、私は……

【完結】家族に愛されなかった辺境伯の娘は、敵国の堅物公爵閣下に攫われ真実の愛を知る
水月音子
恋愛
辺境を守るティフマ城の城主の娘であるマリアーナは、戦の代償として隣国の敵将アルベルトにその身を差し出した。
婚約者である第四王子と、父親である城主が犯した国境侵犯という罪を、自分の命でもって償うためだ。
だが――
「マリアーナ嬢を我が国に迎え入れ、現国王の甥である私、アルベルト・ルーベンソンの妻とする」
そう宣言されてマリアーナは隣国へと攫われる。
しかし、ルーベンソン公爵邸にて差し出された婚約契約書にある一文に疑念を覚える。
『婚約期間中あるいは婚姻後、子をもうけた場合、性別を問わず健康な子であれば、婚約もしくは結婚の継続の自由を委ねる』
さらには家庭教師から“精霊姫”の話を聞き、アルベルトの側近であるフランからも詳細を聞き出すと、自分の置かれた状況を理解する。
かつて自国が攫った“精霊姫”の血を継ぐマリアーナ。
そのマリアーナが子供を産めば、自分はもうこの国にとって必要ない存在のだ、と。
そうであれば、早く子を産んで身を引こう――。
そんなマリアーナの思いに気づかないアルベルトは、「婚約中に子を産み、自国へ戻りたい。結婚して公爵様の経歴に傷をつける必要はない」との彼女の言葉に激昂する。
アルベルトはアルベルトで、マリアーナの知らないところで実はずっと昔から、彼女を妻にすると決めていた。
ふたりは互いの立場からすれ違いつつも、少しずつ心を通わせていく。

聖女の力を妹に奪われ魔獣の森に捨てられたけど、何故か懐いてきた白狼(実は呪われた皇帝陛下)のブラッシング係に任命されました
AK
恋愛
「--リリアナ、貴様との婚約は破棄する! そして妹の功績を盗んだ罪で、この国からの追放を命じる!」
公爵令嬢リリアナは、腹違いの妹・ミナの嘘によって「偽聖女」の汚名を着せられ、婚約者の第二王子からも、実の父からも絶縁されてしまう。 身一つで放り出されたのは、凶暴な魔獣が跋扈する北の禁足地『帰らずの魔の森』。
死を覚悟したリリアナが出会ったのは、伝説の魔獣フェンリル——ではなく、呪いによって巨大な白狼の姿になった隣国の皇帝・アジュラ四世だった!
人間には効果が薄いが、動物に対しては絶大な癒やし効果を発揮するリリアナの「聖女の力」。 彼女が何気なく白狼をブラッシングすると、苦しんでいた皇帝の呪いが解け始め……?
「余の呪いを解くどころか、極上の手触りで撫でてくるとは……。貴様、責任を取って余の専属ブラッシング係になれ」
こうしてリリアナは、冷徹と恐れられる氷の皇帝(中身はツンデレもふもふ)に拾われ、帝国で溺愛されることに。 豪華な離宮で美味しい食事に、最高のもふもふタイム。虐げられていた日々が嘘のような幸せスローライフが始まる。
一方、本物の聖女を追放してしまった祖国では、妹のミナが聖女の力を発揮できず、大地が枯れ、疫病が蔓延し始めていた。 元婚約者や父が慌ててミレイユを連れ戻そうとするが、時すでに遅し。 「私の主人は、この可愛い狼様(皇帝陛下)だけですので」 これは、すべてを奪われた令嬢が、最強のパートナーを得て幸せになり、自分を捨てた者たちを見返す逆転の物語。

銀狼の花嫁~動物の言葉がわかる獣医ですが、追放先の森で銀狼さんを介抱したら森の聖女と呼ばれるようになりました~
川上とむ
恋愛
森に囲まれた村で獣医として働くコルネリアは動物の言葉がわかる一方、その能力を気味悪がられていた。
そんなある日、コルネリアは村の習わしによって森の主である銀狼の花嫁に選ばれてしまう。
それは村からの追放を意味しており、彼女は絶望する。
村に助けてくれる者はおらず、銀狼の元へと送り込まれてしまう。
ところが出会った銀狼は怪我をしており、それを見たコルネリアは彼の傷の手当をする。
すると銀狼は彼女に一目惚れしたらしく、その場で結婚を申し込んでくる。
村に戻ることもできないコルネリアはそれを承諾。晴れて本当の銀狼の花嫁となる。
そのまま森で暮らすことになった彼女だが、動物と会話ができるという能力を活かし、第二の人生を謳歌していく。

罰として醜い辺境伯との婚約を命じられましたが、むしろ望むところです! ~私が聖女と同じ力があるからと復縁を迫っても、もう遅い~
上下左右
恋愛
「貴様のような疫病神との婚約は破棄させてもらう!」
触れた魔道具を壊す体質のせいで、三度の婚約破棄を経験した公爵令嬢エリス。家族からも見限られ、罰として鬼将軍クラウス辺境伯への嫁入りを命じられてしまう。
しかしエリスは周囲の評価など意にも介さない。
「顔なんて目と鼻と口がついていれば十分」だと縁談を受け入れる。
だが実際に嫁いでみると、鬼将軍の顔は認識阻害の魔術によって醜くなっていただけで、魔術無力化の特性を持つエリスは、彼が本当は美しい青年だと見抜いていた。
一方、エリスの特異な体質に、元婚約者の伯爵が気づく。それは伝説の聖女と同じ力で、領地の繁栄を約束するものだった。
伯爵は自分から婚約を破棄したにも関わらず、その決定を覆すために復縁するための画策を始めるのだが・・・後悔してももう遅いと、ざまぁな展開に発展していくのだった
本作は不遇だった令嬢が、最恐将軍に溺愛されて、幸せになるまでのハッピーエンドの物語である
※※小説家になろうでも連載中※※

あなたが「いらない」と言った私ですが、溺愛される妻になりました
有賀冬馬
恋愛
「君みたいな女は、俺の隣にいる価値がない!」冷酷な元婚約者に突き放され、すべてを失った私。
けれど、旅の途中で出会った辺境伯エリオット様は、私の凍った心をゆっくりと溶かしてくれた。
彼の領地で、私は初めて「必要とされる」喜びを知り、やがて彼の妻として迎えられる。
一方、王都では元婚約者の不実が暴かれ、彼の破滅への道が始まる。
かつて私を軽んじた彼が、今、私に助けを求めてくるけれど、もう私の目に映るのはあなたじゃない。

冷徹侯爵の契約妻ですが、ざまぁの準備はできています
鍛高譚
恋愛
政略結婚――それは逃れられぬ宿命。
伯爵令嬢ルシアーナは、冷徹と名高いクロウフォード侯爵ヴィクトルのもとへ“白い結婚”として嫁ぐことになる。
愛のない契約、形式だけの夫婦生活。
それで十分だと、彼女は思っていた。
しかし、侯爵家には裏社会〈黒狼〉との因縁という深い闇が潜んでいた。
襲撃、脅迫、謀略――次々と迫る危機の中で、
ルシアーナは自分がただの“飾り”で終わることを拒む。
「この結婚をわたしの“負け”で終わらせませんわ」
財務の才と冷静な洞察を武器に、彼女は黒狼との攻防に踏み込み、
やがて侯爵をも驚かせる一手を放つ。
契約から始まった関係は、いつしか互いの未来を揺るがすものへ――。
白い結婚の裏で繰り広げられる、
“ざまぁ”と逆転のラブストーリー、いま開幕。

精霊の森に追放された私ですが、森の主【巨大モフモフ熊の精霊王】に気に入られました
腐ったバナナ
恋愛
王都で「魔力欠損の無能者」と蔑まれ、元婚約者と妹の裏切りにより、魔物が出る精霊の森に追放された伯爵令嬢リサ。絶望の中、極寒の森で命を落としかけたリサを救ったのは、人間を食らうと恐れられる森の主、巨大なモフモフの熊だった。
実はその熊こそ、冷酷な精霊王バルト。長年の孤独と魔力の淀みで冷え切っていた彼は、リサの体から放たれる特殊な「癒やしの匂い」と微かな温もりに依存し、リサを「最高のストーブ兼抱き枕」として溺愛し始める。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















