24 / 100
第24話:執事と騎士団長
しおりを挟む
オルゴールの音色が屋敷に響いたあの日から、公爵邸の空気はまた一段と温かみを増したように感じられた。
アシュレイ様の笑顔を見る機会が、格段に増えたのだ。それは、私と二人きりの時に見せてくれる特別な笑顔だけではない。執務中にふと書類から顔を上げた時や、使用人たちに指示を出すほんの僅かな合間にも、その口元には穏やかな笑みが浮かんでいることが多くなった。
その変化は、屋敷に住む全ての人々の心を明るく照らしていた。誰もが、主君の心の氷が溶けていくのを、自分のことのように喜んでいた。
私もまた、その幸せな空気の中で、穏やかな日々を送っていた。彼を癒やし、彼に癒やされる。その温かい循環が、私の日常の全てだった。
その日の午後、私はマーサさんから頼まれて、アシュレイ様の書斎へ焼き菓子と新しい紅茶を運んでいた。彼は午前中からずっと、領地から届いた報告書の確認に追われているらしかった。
書斎の扉をそっとノックすると、中から「入れ」という、いつもより少しだけ低い声が聞こえた。仕事に集中している時の彼の声だ。
「失礼いたします、アシュレイ様。お茶をお持ちいたしました」
私が声をかけると、机に向かっていた彼ははっとしたように顔を上げた。そして、私の姿を認めた瞬間、それまでの厳しい表情が嘘のようにふわりと綻ぶ。
「ああ、リナリアか。ありがとう。ちょうど一息つきたいと思っていたところだ」
その変わり身の早さに、彼の隣に控えていた壮年の執事は、表情こそ変えなかったが、その眉をかすかに動かした。
この方こそ、アイゼンベルク公爵家に長年仕える執事長のセバスチャンさんだ。銀色になり始めた髪を綺麗に整え、常に背筋を伸ばしたその佇まいは、非の打ち所がない完璧な執事そのものだった。彼は、アシュレイ様が幼い頃からその成長を見守ってきた、最も信頼の厚い側近の一人だとマーサさんから聞いていた。
私はセバスチャンさんに小さく会釈をしてから、アシュレイ様の机の空いているスペースにトレイを置いた。
「クッキーが焼きたてでしたので。お仕事の邪魔にならないと良いのですが」
「邪魔なものか。君が来てくれただけで、凝り固まった頭がほぐれるようだ」
アシュレイ様はそう言うと、私が淹れた紅茶を一口飲み、心底安らいだように息をついた。そして、クッキーを一つ手に取ると、悪戯っぽく微笑んで私に差し出した。
「君も、一つどうだ? 味見をしてもらわないと、毒見役が務まらないだろう?」
「も、もう! アシュレイ様!」
以前の私なら恐縮して固まってしまうところだったが、最近では彼のこういう冗談にも、少しだけ慣れてきていた。私が頬を膨らませて見せると、彼は楽しそうに笑い、そのクッキーを自分の口へと運んだ。
その一連のやりとりを、セバスチャンさんはただ静かに見守っていた。彼の老練な瞳には、主君のこれまでにない人間らしい姿に対する深い感慨と、その変化をもたらした私という存在への、静かな査定の色が浮かんでいるように見えた。
私がお茶を出し終えて書斎を辞去しようとした時、廊下の向こうからがっしりとした体躯の男性がこちらへ向かってくるのが見えた。
赤みがかった茶色の髪を短く刈り込み、日に焼けた肌には歴戦の証である古傷がいくつか刻まれている。公爵邸の豪華な内装には少し不釣り合いなほど、武骨で精悍な印象の人物だった。
彼こそ、アシュレイ様が率いる騎士団の団長、ギルバート・フォン・シュタイナー様。アシュレイ様の右腕として戦場を駆け、その背中を幾度となく守ってきた、最も信頼する戦友でもある。
ギルバート団長は、書斎から出てきた私と鉢合わせになると、少し驚いたように足を止めた。そして、私の質素な身なりと、どこにでもいるような控えめな様子を見て、怪訝そうに眉をひそめた。
「……あんたが、噂の?」
その声は、彼の屈強な見た目通り、低く、腹に響くような声だった。
私は彼の無遠慮な視線に少しだけ怯みながらも、スカートの裾をつまんで丁寧にお辞儀をした。
「リナリア・エルフィールドと申します」
「……ギルバートだ」
彼はぶっきらぼうに名乗ると、私の背後にある書斎の扉へと視線を向けた。その時、扉が内側から開かれ、アシュレイ様が顔を覗かせた。
「ギルバートか。ちょうどいいところに来た。入れ」
「はっ。失礼します、公爵様」
ギルバート団長は、アシュレイ様に対しては完璧な騎士としての礼を取った。しかし、彼の視線は、アシュレイ様が私に向ける表情を見て、再び驚きに固まった。
アシュレイ様は、ギルバート団長が来たことで、私との時間が終わってしまうのが名残惜しいとでも言うように、少しだけ不満げな顔をしていたのだ。
「リナリア、下がっていい。だが、夕食は必ず一緒に。君の好きな魚料理を用意させてあるからな」
「はい、アシュレイ様」
私にそう告げる声は、とろけるように甘い。その声色と、団長に向ける厳格な主君としての声色との差に、おそらくギルバート団長は眩暈でも覚えたことだろう。彼は唖然とした表情で、私とアシュレイ様を交互に見比べていた。
その日の夕方。私は庭で、マーサさんと共にハーブを摘んでいた。
そこへ、執務室での報告を終えたらしいギルバート団長が、セバスチャンさんと共にやってきた。
「……リナリア嬢」
先ほどよりは幾分か和らいだ声で、ギルバート団長が私を呼んだ。
「少し、よろしいかな」
私は立ち上がって彼に向き直る。彼の真剣な眼差しに、少しだけ緊張した。
「先ほど、公爵閣下から全て伺った。あんたの持つ不思議な力のこと、そして、あの方の呪いを癒しているということも」
彼はそう言うと、ごしごしと自分の頭を掻いた。
「正直、まだ信じられん。だが……」
彼はそこで言葉を切ると、私をまっすぐに見つめた。
「閣下の、あんなお顔を拝見したのは、何年ぶりだろうな。……いや、戦場でお会いしてから、初めてかもしれん」
その声には、深い実感がこもっていた。
「俺は、呪いに苦しむ閣下の姿を、誰よりも近くで見てきた。戦友として、何もできん自分が、歯がゆくてならなかった。……だが、あんたは、それを成し遂げている」
彼は、私の目の前まで来ると、その屈強な身体をためらいなく折り曲げ、深く、深く頭を下げた。
「……団長様!?」
私は驚いて声を上げた。騎士団長という高位の貴族が、私のような者に頭を下げるなど、あってはならないことだった。
「礼を言う、リナリア嬢。我が主君を救ってくれて、心から感謝する」
彼は顔を上げずに、そう言った。
「そして、これは俺個人からのお願いだ。どうか、これからも、閣下のことをよろしく頼む。あの方の傍に、居てやってくれ」
その声は、主君を心から敬愛する、忠実な騎士の声だった。
私の胸に、熱いものが込み上げてくる。
「……はい」
私は、涙声になるのをこらえて、はっきりと答えた。
「もちろんです。それが、私の役目ですから」
私のその返事を聞いて、ギルバート団長はようやく顔を上げた。その武骨な顔には、吹っ切れたような、晴れやかな笑みが浮かんでいた。
その様子を、少し離れた場所から見ていたセバスチャンさんが、静かに私に近づいてきた。
「リナリア様」
彼は、初めて私を「様」付けで呼んだ。そして、完璧な所作で、深々とお辞儀をした。
「このセバスチャンも、ギルバートと同じ想いでございます。リナリア様こそ、このアイゼンベルク公爵家が長年待ち望んだ、真の『主』のお一人。今後は、この身の全てを懸けて、リナリア様をお守りし、お仕えする所存でございます」
その言葉は、メイド長のマーサさんが誓ってくれた時と同じくらい、私の心を強く、温かく震わせた。
執事長セバスチャン、騎士団長ギルバート。
アシュレイ様が最も信頼する二人の側近が、今、私を認め、忠誠を誓ってくれた。
私はもう、一人ではない。
この公爵邸には、私を支え、守ってくれる人たちが、こんなにもいる。
その温かい事実に、私の心は、どこまでも満たされていくのだった。
アシュレイ様の笑顔を見る機会が、格段に増えたのだ。それは、私と二人きりの時に見せてくれる特別な笑顔だけではない。執務中にふと書類から顔を上げた時や、使用人たちに指示を出すほんの僅かな合間にも、その口元には穏やかな笑みが浮かんでいることが多くなった。
その変化は、屋敷に住む全ての人々の心を明るく照らしていた。誰もが、主君の心の氷が溶けていくのを、自分のことのように喜んでいた。
私もまた、その幸せな空気の中で、穏やかな日々を送っていた。彼を癒やし、彼に癒やされる。その温かい循環が、私の日常の全てだった。
その日の午後、私はマーサさんから頼まれて、アシュレイ様の書斎へ焼き菓子と新しい紅茶を運んでいた。彼は午前中からずっと、領地から届いた報告書の確認に追われているらしかった。
書斎の扉をそっとノックすると、中から「入れ」という、いつもより少しだけ低い声が聞こえた。仕事に集中している時の彼の声だ。
「失礼いたします、アシュレイ様。お茶をお持ちいたしました」
私が声をかけると、机に向かっていた彼ははっとしたように顔を上げた。そして、私の姿を認めた瞬間、それまでの厳しい表情が嘘のようにふわりと綻ぶ。
「ああ、リナリアか。ありがとう。ちょうど一息つきたいと思っていたところだ」
その変わり身の早さに、彼の隣に控えていた壮年の執事は、表情こそ変えなかったが、その眉をかすかに動かした。
この方こそ、アイゼンベルク公爵家に長年仕える執事長のセバスチャンさんだ。銀色になり始めた髪を綺麗に整え、常に背筋を伸ばしたその佇まいは、非の打ち所がない完璧な執事そのものだった。彼は、アシュレイ様が幼い頃からその成長を見守ってきた、最も信頼の厚い側近の一人だとマーサさんから聞いていた。
私はセバスチャンさんに小さく会釈をしてから、アシュレイ様の机の空いているスペースにトレイを置いた。
「クッキーが焼きたてでしたので。お仕事の邪魔にならないと良いのですが」
「邪魔なものか。君が来てくれただけで、凝り固まった頭がほぐれるようだ」
アシュレイ様はそう言うと、私が淹れた紅茶を一口飲み、心底安らいだように息をついた。そして、クッキーを一つ手に取ると、悪戯っぽく微笑んで私に差し出した。
「君も、一つどうだ? 味見をしてもらわないと、毒見役が務まらないだろう?」
「も、もう! アシュレイ様!」
以前の私なら恐縮して固まってしまうところだったが、最近では彼のこういう冗談にも、少しだけ慣れてきていた。私が頬を膨らませて見せると、彼は楽しそうに笑い、そのクッキーを自分の口へと運んだ。
その一連のやりとりを、セバスチャンさんはただ静かに見守っていた。彼の老練な瞳には、主君のこれまでにない人間らしい姿に対する深い感慨と、その変化をもたらした私という存在への、静かな査定の色が浮かんでいるように見えた。
私がお茶を出し終えて書斎を辞去しようとした時、廊下の向こうからがっしりとした体躯の男性がこちらへ向かってくるのが見えた。
赤みがかった茶色の髪を短く刈り込み、日に焼けた肌には歴戦の証である古傷がいくつか刻まれている。公爵邸の豪華な内装には少し不釣り合いなほど、武骨で精悍な印象の人物だった。
彼こそ、アシュレイ様が率いる騎士団の団長、ギルバート・フォン・シュタイナー様。アシュレイ様の右腕として戦場を駆け、その背中を幾度となく守ってきた、最も信頼する戦友でもある。
ギルバート団長は、書斎から出てきた私と鉢合わせになると、少し驚いたように足を止めた。そして、私の質素な身なりと、どこにでもいるような控えめな様子を見て、怪訝そうに眉をひそめた。
「……あんたが、噂の?」
その声は、彼の屈強な見た目通り、低く、腹に響くような声だった。
私は彼の無遠慮な視線に少しだけ怯みながらも、スカートの裾をつまんで丁寧にお辞儀をした。
「リナリア・エルフィールドと申します」
「……ギルバートだ」
彼はぶっきらぼうに名乗ると、私の背後にある書斎の扉へと視線を向けた。その時、扉が内側から開かれ、アシュレイ様が顔を覗かせた。
「ギルバートか。ちょうどいいところに来た。入れ」
「はっ。失礼します、公爵様」
ギルバート団長は、アシュレイ様に対しては完璧な騎士としての礼を取った。しかし、彼の視線は、アシュレイ様が私に向ける表情を見て、再び驚きに固まった。
アシュレイ様は、ギルバート団長が来たことで、私との時間が終わってしまうのが名残惜しいとでも言うように、少しだけ不満げな顔をしていたのだ。
「リナリア、下がっていい。だが、夕食は必ず一緒に。君の好きな魚料理を用意させてあるからな」
「はい、アシュレイ様」
私にそう告げる声は、とろけるように甘い。その声色と、団長に向ける厳格な主君としての声色との差に、おそらくギルバート団長は眩暈でも覚えたことだろう。彼は唖然とした表情で、私とアシュレイ様を交互に見比べていた。
その日の夕方。私は庭で、マーサさんと共にハーブを摘んでいた。
そこへ、執務室での報告を終えたらしいギルバート団長が、セバスチャンさんと共にやってきた。
「……リナリア嬢」
先ほどよりは幾分か和らいだ声で、ギルバート団長が私を呼んだ。
「少し、よろしいかな」
私は立ち上がって彼に向き直る。彼の真剣な眼差しに、少しだけ緊張した。
「先ほど、公爵閣下から全て伺った。あんたの持つ不思議な力のこと、そして、あの方の呪いを癒しているということも」
彼はそう言うと、ごしごしと自分の頭を掻いた。
「正直、まだ信じられん。だが……」
彼はそこで言葉を切ると、私をまっすぐに見つめた。
「閣下の、あんなお顔を拝見したのは、何年ぶりだろうな。……いや、戦場でお会いしてから、初めてかもしれん」
その声には、深い実感がこもっていた。
「俺は、呪いに苦しむ閣下の姿を、誰よりも近くで見てきた。戦友として、何もできん自分が、歯がゆくてならなかった。……だが、あんたは、それを成し遂げている」
彼は、私の目の前まで来ると、その屈強な身体をためらいなく折り曲げ、深く、深く頭を下げた。
「……団長様!?」
私は驚いて声を上げた。騎士団長という高位の貴族が、私のような者に頭を下げるなど、あってはならないことだった。
「礼を言う、リナリア嬢。我が主君を救ってくれて、心から感謝する」
彼は顔を上げずに、そう言った。
「そして、これは俺個人からのお願いだ。どうか、これからも、閣下のことをよろしく頼む。あの方の傍に、居てやってくれ」
その声は、主君を心から敬愛する、忠実な騎士の声だった。
私の胸に、熱いものが込み上げてくる。
「……はい」
私は、涙声になるのをこらえて、はっきりと答えた。
「もちろんです。それが、私の役目ですから」
私のその返事を聞いて、ギルバート団長はようやく顔を上げた。その武骨な顔には、吹っ切れたような、晴れやかな笑みが浮かんでいた。
その様子を、少し離れた場所から見ていたセバスチャンさんが、静かに私に近づいてきた。
「リナリア様」
彼は、初めて私を「様」付けで呼んだ。そして、完璧な所作で、深々とお辞儀をした。
「このセバスチャンも、ギルバートと同じ想いでございます。リナリア様こそ、このアイゼンベルク公爵家が長年待ち望んだ、真の『主』のお一人。今後は、この身の全てを懸けて、リナリア様をお守りし、お仕えする所存でございます」
その言葉は、メイド長のマーサさんが誓ってくれた時と同じくらい、私の心を強く、温かく震わせた。
執事長セバスチャン、騎士団長ギルバート。
アシュレイ様が最も信頼する二人の側近が、今、私を認め、忠誠を誓ってくれた。
私はもう、一人ではない。
この公爵邸には、私を支え、守ってくれる人たちが、こんなにもいる。
その温かい事実に、私の心は、どこまでも満たされていくのだった。
86
あなたにおすすめの小説

追放された公爵令息、神竜と共に辺境スローライフを満喫する〜無敵領主のまったり改革記〜
たまごころ
ファンタジー
無実の罪で辺境に追放された公爵令息アレン。
だが、その地では神竜アルディネアが眠っていた。
契約によって最強の力を得た彼は、戦いよりも「穏やかな暮らし」を選ぶ。
農地改革、温泉開発、魔導具づくり──次々と繁栄する辺境領。
そして、かつて彼を貶めた貴族たちが、その繁栄にひれ伏す時が来る。
戦わずとも勝つ、まったりざまぁ無双ファンタジー!

【完結】家族に愛されなかった辺境伯の娘は、敵国の堅物公爵閣下に攫われ真実の愛を知る
水月音子
恋愛
辺境を守るティフマ城の城主の娘であるマリアーナは、戦の代償として隣国の敵将アルベルトにその身を差し出した。
婚約者である第四王子と、父親である城主が犯した国境侵犯という罪を、自分の命でもって償うためだ。
だが――
「マリアーナ嬢を我が国に迎え入れ、現国王の甥である私、アルベルト・ルーベンソンの妻とする」
そう宣言されてマリアーナは隣国へと攫われる。
しかし、ルーベンソン公爵邸にて差し出された婚約契約書にある一文に疑念を覚える。
『婚約期間中あるいは婚姻後、子をもうけた場合、性別を問わず健康な子であれば、婚約もしくは結婚の継続の自由を委ねる』
さらには家庭教師から“精霊姫”の話を聞き、アルベルトの側近であるフランからも詳細を聞き出すと、自分の置かれた状況を理解する。
かつて自国が攫った“精霊姫”の血を継ぐマリアーナ。
そのマリアーナが子供を産めば、自分はもうこの国にとって必要ない存在のだ、と。
そうであれば、早く子を産んで身を引こう――。
そんなマリアーナの思いに気づかないアルベルトは、「婚約中に子を産み、自国へ戻りたい。結婚して公爵様の経歴に傷をつける必要はない」との彼女の言葉に激昂する。
アルベルトはアルベルトで、マリアーナの知らないところで実はずっと昔から、彼女を妻にすると決めていた。
ふたりは互いの立場からすれ違いつつも、少しずつ心を通わせていく。
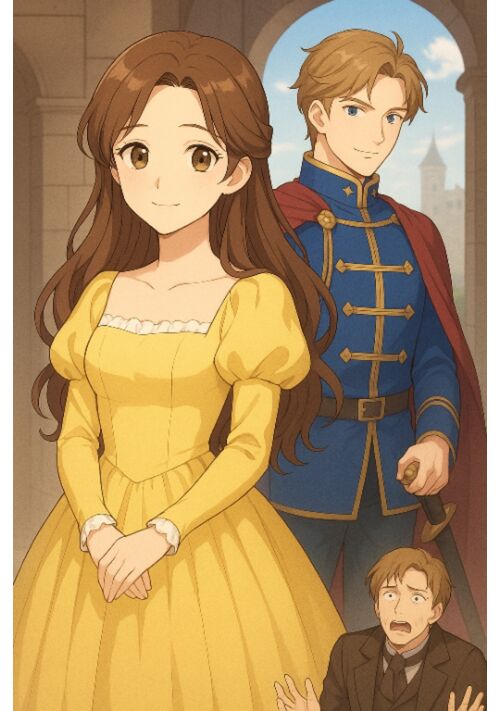
地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします
有賀冬馬
恋愛
子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。
唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。
もう二度と恋なんてしない。
そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。
彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。
彼は、この国の王太子だったのだ。
「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。
一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。
私に助けを求めてきた彼に、私は……

銀狼の花嫁~動物の言葉がわかる獣医ですが、追放先の森で銀狼さんを介抱したら森の聖女と呼ばれるようになりました~
川上とむ
恋愛
森に囲まれた村で獣医として働くコルネリアは動物の言葉がわかる一方、その能力を気味悪がられていた。
そんなある日、コルネリアは村の習わしによって森の主である銀狼の花嫁に選ばれてしまう。
それは村からの追放を意味しており、彼女は絶望する。
村に助けてくれる者はおらず、銀狼の元へと送り込まれてしまう。
ところが出会った銀狼は怪我をしており、それを見たコルネリアは彼の傷の手当をする。
すると銀狼は彼女に一目惚れしたらしく、その場で結婚を申し込んでくる。
村に戻ることもできないコルネリアはそれを承諾。晴れて本当の銀狼の花嫁となる。
そのまま森で暮らすことになった彼女だが、動物と会話ができるという能力を活かし、第二の人生を謳歌していく。

『婚約破棄された聖女リリアナの庭には、ちょっと変わった来訪者しか来ません。』
夢窓(ゆめまど)
恋愛
王都から少し離れた小高い丘の上。
そこには、聖女リリアナの庭と呼ばれる不思議な場所がある。
──けれど、誰もがたどり着けるわけではない。
恋するルミナ五歳、夢みるルーナ三歳。
ふたりはリリアナの庭で、今日もやさしい魔法を育てています。
この庭に来られるのは、心がちょっぴりさびしい人だけ。
まほうに傷ついた王子さま、眠ることでしか気持ちを伝えられない子、
そして──ほんとうは泣きたかった小さな精霊たち。
お姉ちゃんのルミナは、花を咲かせる明るい音楽のまほうつかい。
ちょっとだけ背伸びして、だいすきな人に恋をしています。
妹のルーナは、ねむねむ魔法で、夢の中を旅するやさしい子。
ときどき、だれかの心のなかで、静かに花を咲かせます。
ふたりのまほうは、まだ小さくて、でもあたたかい。
「だいすきって気持ちは、
きっと一番すてきなまほうなの──!」
風がふくたびに、花がひらき、恋がそっと実る。
これは、リリアナの庭で育つ、
小さなまほうつかいたちの恋と夢の物語です。

精霊の森に追放された私ですが、森の主【巨大モフモフ熊の精霊王】に気に入られました
腐ったバナナ
恋愛
王都で「魔力欠損の無能者」と蔑まれ、元婚約者と妹の裏切りにより、魔物が出る精霊の森に追放された伯爵令嬢リサ。絶望の中、極寒の森で命を落としかけたリサを救ったのは、人間を食らうと恐れられる森の主、巨大なモフモフの熊だった。
実はその熊こそ、冷酷な精霊王バルト。長年の孤独と魔力の淀みで冷え切っていた彼は、リサの体から放たれる特殊な「癒やしの匂い」と微かな温もりに依存し、リサを「最高のストーブ兼抱き枕」として溺愛し始める。

罰として醜い辺境伯との婚約を命じられましたが、むしろ望むところです! ~私が聖女と同じ力があるからと復縁を迫っても、もう遅い~
上下左右
恋愛
「貴様のような疫病神との婚約は破棄させてもらう!」
触れた魔道具を壊す体質のせいで、三度の婚約破棄を経験した公爵令嬢エリス。家族からも見限られ、罰として鬼将軍クラウス辺境伯への嫁入りを命じられてしまう。
しかしエリスは周囲の評価など意にも介さない。
「顔なんて目と鼻と口がついていれば十分」だと縁談を受け入れる。
だが実際に嫁いでみると、鬼将軍の顔は認識阻害の魔術によって醜くなっていただけで、魔術無力化の特性を持つエリスは、彼が本当は美しい青年だと見抜いていた。
一方、エリスの特異な体質に、元婚約者の伯爵が気づく。それは伝説の聖女と同じ力で、領地の繁栄を約束するものだった。
伯爵は自分から婚約を破棄したにも関わらず、その決定を覆すために復縁するための画策を始めるのだが・・・後悔してももう遅いと、ざまぁな展開に発展していくのだった
本作は不遇だった令嬢が、最恐将軍に溺愛されて、幸せになるまでのハッピーエンドの物語である
※※小説家になろうでも連載中※※

【悲報】氷の悪女と蔑まれた辺境令嬢のわたくし、冷徹公爵様に何故かロックオンされました!?~今さら溺愛されても困ります……って、あれ?
放浪人
恋愛
「氷の悪女」――かつて社交界でそう蔑まれ、身に覚えのない罪で北の辺境に追いやられた令嬢エレオノーラ・フォン・ヴァインベルク。凍えるような孤独と絶望に三年間耐え忍んできた彼女の前に、ある日突然現れたのは、帝国一冷徹と名高いアレクシス・フォン・シュヴァルツェンベルク公爵だった。
彼の目的は、荒廃したヴァインベルク領の視察。エレオノーラは、公爵の鋭く冷たい視線と不可解なまでの執拗な関わりに、「新たな不幸の始まりか」と身を硬くする。しかし、領地再建のために共に過ごすうち、彼の不器用な優しさや、時折見せる温かい眼差しに、エレオノーラの凍てついた心は少しずつ溶かされていく。
「お前は、誰よりも強く、優しい心を持っている」――彼の言葉は、偽りの悪評に傷ついてきたエレオノーラにとって、戸惑いと共に、かつてない温もりをもたらすものだった。「迷惑千万!」と思っていたはずの公爵の存在が、いつしか「心地よいかも…」と感じられるように。
過去のトラウマ、卑劣な罠、そして立ちはだかる身分と悪評の壁。数々の困難に見舞われながらも、アレクシス公爵の揺るぎない庇護と真っ直ぐな愛情に支えられ、エレオノーラは真の自分を取り戻し、やがて二人は互いにとってかけがえのない存在となっていく。
これは、不遇な辺境令嬢が、冷徹公爵の不器用でひたむきな「ロックオン(溺愛)」によって心の氷を溶かし、真実の愛と幸福を掴む、ちょっぴりじれったくて、とびきり甘い逆転ラブストーリー。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















