15 / 35
第三章 二人の公爵令嬢
第十五話 皇妃になりたい者とならない者
しおりを挟む「――あれ? セバスチャンの葉っぱだ」
自分の失態をきっかけに始まった母の散髪実演会にはさほど興味を引かれないらしいシオンは、ヴィオラントの腕から抜け出し、皇帝執務室の窓から顔を出して外を眺めていた。
と、ふいに、窓辺に置かれたガラス容器が目に留まる。
それを覗き込んだシオンは、見覚えのある中身に両目をぱちくりさせた。
つい先ほどまでアメジストみたいなそれを濡らしていた涙は、もうすっかり乾いてしまっている。
「ふうん……なんか、ちっさ」
彼は単に事実を述べただけで、その蔦執事セバスチャンの若葉――ソフィリアが誕生日祝いとして贈られ、スミレがプチセバスと命名した――を貶める意図はなかった。
しかし、小さな子供に小さいと言われて、プチセバスの矜持はおおいに傷つけられたらしい。
――ぴしっ
気安く触れようと伸びてきたシオンの手の甲を、その蔓の先が打った。
「……生意気なヤツ」
もちろんシオンの方も、これにはむっとした顔をする。
彼はぷくりと頬を膨らませると、子供らしいふくふくとした指でもって、プチセバスの若葉をぴんと弾いた。
本日ヴィオラントが王城を訪れた目的も、先日のソフィリアの誕生日と同様に、財務大臣であるロートリアス公爵との会談だった。
グラディアトリアはこの数日後、両隣国――パトラーシュとコンラートの宰相を迎えて定期的に開かれる、三国間宰相会議を控えている。
それに先駆け、長年友好的な関係にある隣国パトラーシュとの間では新たな通商条約の制定が進められており、ヴィオラントは相談役としてそれに関わっていた。
この国で激動の十年間を君臨し続けたその知識と経験に、ルドヴィークが習うことも頼ることまだまだあるだろう。
とはいえ彼も、玉座に就いて今年で十年目。
敬愛する兄と同じだけ、すでにグラディアトリアを引っ張ってきたことになる。
「ルドヴィーク。すまぬが、この書類に目を通してもらえるだろうか」
「承知しました。少々お待ちください」
ヴィオラントがここを訪ねてきたのは、皇帝のサインが必要だったかららしい。
ルドヴィークは手渡された書類――その、達筆な文面に目を走らせながら、執務机の方へ移動する。
部屋の中央に置かれたソファに、ヴィオラントとスミレが並んで腰を下ろし、ソフィリアがその向かいの席にモディーニを座らせた。ユリウスは不承不承ながらも、護衛騎士らしく彼女の脇に立つ。
ソフィリアがお茶の用意をする旨を告げると、ルドヴィークはそれに頷いて返しつつ、書類にサインをすべくペンに手を伸ばそうとした。
その時である。
――びしゃんっ!
突如、窓の辺りから水面を叩く音がした。
と同時に、わっ、と驚いたような声も上がる。
「シオン?」
その声の主の名を呼びながらルドヴィークが窓辺に顔を向けると、窓の外を向いて立っていたシオンも彼を振り返った。
「……ルド兄~……」
その愛くるしい顔はぐっしょりと水に濡れ、父親譲りの白銀色の前髪からはポタポタと雫が垂れている。
どうやら、プチセバスの蔓が跳ね上げた水をまともにかぶってしまったようだ。
当のプチセバスはというと、ガラス容器の中から得意げに蔓を振っている。
お茶の用意をしていたソフィリアも窓辺の様子に気づき、慌ててシオンに声をかけた。
「まあ、シオンちゃん。ごめんなさいね」
「どうしてソフィが謝るの? 悪いの、こいつなのに!」
こいつ、と指差すシオンの指を、プチセバスの蔓がまたぴしりと打った。
シオンはますます腹を立て、その蔓をぎゅっと鷲掴みにする。
「こらこら、乱暴するんじゃない」
「だって、ルド兄! こいつ、生意気でイヤなヤツなんだもんっ!」
「シオンの方が兄さんだろう。優しくしてやりなさい」
「でもぉ~」
お茶の用意で手が離せないソフィリアに代わり、ルドヴィークがハンカチを取り出してシオンの濡れた顔を拭いてやる。
湿って額に貼り付いていた前髪は、丁寧に指で梳いて左右に避けてやった。
そうして、不貞腐れた顔のままの彼をプチセバスから引き離し、椅子に腰を下ろして自身の膝に乗せてやる。
すると、シオンはたちまち機嫌を直した。
「やった! ルド兄の机だっ!」
皇帝執務室に据えられた大きな執務机に、シオンは少なからず憧れを抱いていたらしい。
自身も幼い頃、これに座って仕事をする兄ヴィオラントの姿に憧れたことのあるルドヴィークには、その気持ちがよく分かった。
「今からペンを使うからじっとしていてくれよ」
「うん、じっとしてる」
ルドヴィークはシオンを膝に抱いたまま、ようやくペンを手に取った。ヴィオラントから預かった書類にサインをするためだ。
言われた通りに膝の上でじっとしているシオンに、ルドヴィークは頬を綻ばせる。
彼は小さな白銀色の頭に顎を載せつつ、ペンの先をインクに浸した。
実に、穏やかな気持ちのまま。
――それなのに
ルドヴィークとシオンのやりとりをじっと見つめていたモディーニが、ふいに口を開いた。
「ルドヴィーク様、私に子供を産ませてくださいませ」
――ゴトンッ
「わあああっ、やばっ! ルド兄! インクがっ!!」
またしても、唐突なモディーニの言葉。
驚きのあまり、ルドヴィークはペン先を引っ掛けてインクのビンを倒してしまう。
シオンの悲鳴に我に返った彼は、とっさに書類を持ち上げて、間一髪のところでインクに塗れるのを防いだ。
しかし、黒い水溜りはみるみる執務机の上を侵食していく。
ルドヴィークはひとまずシオンを膝から下ろすと、他の書類も全てインクの流れから遠ざけた。
ソフィリアもこれにはさすがにお茶の用意を中断し、布巾片手に加勢に走る。
その甲斐あって、被害は布巾を一枚真っ黒にしただけで済んだ。
ところが、それにほっとしたのも束の間……
「私、ルドヴィーク様の赤子を産みたいんです!」
「は!?」
畳み掛けるように言い放つモディーニに、ルドヴィークは盛大に顔を引き攣らせる。
「わぁお! なーにこの子! 大胆っ!!」
「随分と熱烈な……そなたも隅に置けなぬな、ルドヴィーク」
モディーニの発言を聞いたスミレとヴィオラントが、そう口々に囃し立てる。
ここでようやく、ルドヴィークは騒動の元凶に向かい合うこととなった。
「……モディーニ、そういうことは軽々しく言うものではないと……」
わざとらしく咳払いをしつつ、モディーニを窘めようとする。
しかし、彼女はすっとソファから立ち上がると、ルドヴィークの苦言を遮って続けた。
「ルドヴィーク様はよい父親になられるだろう、と先ほどお兄様もおっしゃったではありませんか。是非とも、私が産む子供の父親になってくださいませ」
まだあどけなさを残す少女の声が、淀みなく紡ぐ真剣な言葉。
居合わせた大人達は、その鬼気迫る様子に圧倒されて口を噤む。
いつもはすぐに茶々を入れるユリウスさえ、どこかたじたじとした様子でモディーニの横顔を眺めていた。
「私と、結婚してくださいませ、ルドヴィーク様」
しんと静まり返った皇帝執務室に、再びモディーニの声だけが響く。
しかし、その時である。
「――お姉さん、なに言ってんの? ルド兄は、ソフィと結婚するんだよ?」
無邪気でいて、無責任な言葉を、モディーニよりもまだずっと幼い声が紡ぐ。
シオンの声だ。
それに、大人達は今度は心底ぎょっとした。
「え……!?」
「ええっ!?」
言われた本人達――ソフィリアとルドヴィークも然りである。
仲良く溢れたインクの後始末をしていた二人が、同時に素っ頓狂な声を上げたかと思ったら、自然と顔を見合わせる。
心無しか、どちらもほんのりと頬が赤い。
すると、そんな二人がいる執務机の方に、モディーニが猛然と駆け寄ってきた。
「それは、本当でございますか!? ルドヴィーク様とソフィリア様は、そのようなご関係だったのですか!?」
執務机を両手でバンと叩き、モディーニが叫ぶ。
そのあまりの形相に驚き、シオンが窓辺の方まで後ずさった。
「そのようなこと、これまで一言もおっしゃらなかったではありませんか!」
「いや……だが、それは……」
声を荒げるモディーニに、ルドヴィークは困った顔をする。
「何も知らずに求婚していた私のことを、本当はお二人で笑っていらっしゃったのですか!?」
「そ、そんな……違いますっ!」
ついには涙を滲ませ始めた少女に、ソフィリアも慌てた。
インクで黒く汚れた布巾を置いてモディーニの側に行き、震える彼女の肩に手を添えようとする。
しかし、モディーニは逆にソフィリアの腕をがしりと掴み、強い口調のまま尋ねた。
「今ここで、はっきりと答えてくださいませ! ソフィリア様は、ルドヴィーク様の何なのですか!?」
「えっ……」
ソフィリアは一瞬答えに詰まった。しかし、すぐに気を取り直して言葉を返す。
「私は……陛下に仕える文官です。これから先も、そうありたいと思っております」
「ではソフィリア様は、陛下と結婚なさろうなどと、少しも考えていらっしゃらないのですね!?」
――ええ、もちろん
ソフィリアは、すぐさま頷いてそう答えようとした。
しかし、できなかった。
なぜだか喉が引き攣ったようになって、声が出ないのだ。
その時、ふいにルドヴィークと目が合った。
彼の青い瞳が、まっすぐにソフィリアを見つめている。
「――っ」
たちまちソフィリアは、かっと頬が熱くなるのを感じた。
そんな自身に戸惑い、彼女は赤くなった顔を隠すように、ルドヴィークから視線を逸らして俯く。
その腕を、モディーニはぐっと強い力で掴んで引いた。
「ソフィリア様、どうなのですか!? ご自身が皇妃になろうとは、考えていらっしゃらないのですね!?」
彼女はそう言って、返事を急かす。
ソフィリアはごくりと唾を呑み込むと、震える喉を叱咤して何とか声を絞り出した。
「……ええ。この国の皇妃となるのは……私ではありません」
皇妃となるのは――ルドヴィークの妻になるのは、ソフィリアではない。
そう告げたのは自分だというのに、とたんにソフィリアの胸は杭でも打ち込まれたみたいにひどく痛んだ。
母に敷かれた軌道通りに皇妃となることよりも、一文官として、そして友として、ルドヴィークとの関係を深めている毎日に幸せを感じていたはずだった。
それなのに今、ソフィリアは無意識に、自分の言葉によって傷ついた。
そして、その時、ちらりと見えたルドヴィークの表情。
それが、どこか愕然としているように感じたことを、彼女は勝手に気のせいだと結論付けてしまった。
――ばしゃん
再び、皇帝執務室に水の跳ねる音が響いた。
「わ、冷たっ……」
またしても、それをかぶったらしいシオンが悲鳴を上げる。
モディーニの勢いに驚いて後ずさった彼は、うかつにもプチセバスの射程範囲内に戻ってしまっていたのだ。
迷惑そうに眉を顰めるシオンに、プチセバスはなおもぴしゃぴしゃと水飛沫を浴びせかける。
それはまるで、彼を責めているかのようだった。
「あーあ……」
ソファに腰掛けたまま一連の騒動を見守っていたスミレが、こっそりため息をついた。
彼女は短くなった髪をふわりと揺らし、隣に座ったヴィオラントの耳元に唇を寄せる。
そして、彼にだけ聞こえる声で言った。
「ソフィとルド、こじれちゃったね」
10
あなたにおすすめの小説

虐げられ続けてきたお嬢様、全てを踏み台に幸せになることにしました。
ラディ
恋愛
一つ違いの姉と比べられる為に、愚かであることを強制され矯正されて育った妹。
家族からだけではなく、侍女や使用人からも虐げられ弄ばれ続けてきた。
劣悪こそが彼女と標準となっていたある日。
一人の男が現れる。
彼女の人生は彼の登場により一変する。
この機を逃さぬよう、彼女は。
幸せになることに、決めた。
■完結しました! 現在はルビ振りを調整中です!
■第14回恋愛小説大賞99位でした! 応援ありがとうございました!
■感想や御要望などお気軽にどうぞ!
■エールやいいねも励みになります!
■こちらの他にいくつか話を書いてますのでよろしければ、登録コンテンツから是非に。
※一部サブタイトルが文字化けで表示されているのは演出上の仕様です。お使いの端末、表示されているページは正常です。

愛する旦那様が妻(わたし)の嫁ぎ先を探しています。でも、離縁なんてしてあげません。
秘密 (秘翠ミツキ)
恋愛
【清い関係のまま結婚して十年……彼は私を別の男へと引き渡す】
幼い頃、大国の国王へ献上品として連れて来られリゼット。だが余りに幼く扱いに困った国王は末の弟のクロヴィスに下賜した。その為、王弟クロヴィスと結婚をする事になったリゼット。歳の差が9歳とあり、旦那のクロヴィスとは夫婦と言うよりは歳の離れた仲の良い兄妹の様に過ごして来た。
そんな中、結婚から10年が経ちリゼットが15歳という結婚適齢期に差し掛かると、クロヴィスはリゼットの嫁ぎ先を探し始めた。すると社交界は、その噂で持ちきりとなり必然的にリゼットの耳にも入る事となった。噂を聞いたリゼットはショックを受ける。
クロヴィスはリゼットの幸せの為だと話すが、リゼットは大好きなクロヴィスと離れたくなくて……。

【完結】婚約破棄された令嬢の毒はいかがでしょうか
まさかの
恋愛
皇太子の未来の王妃だったカナリアは突如として、父親の罪によって婚約破棄をされてしまった。
己の命が助かる方法は、友好国の悪評のある第二王子と婚約すること。
カナリアはその提案をのんだが、最初の夜会で毒を盛られてしまった。
誰も味方がいない状況で心がすり減っていくが、婚約者のシリウスだけは他の者たちとは違った。
ある時、シリウスの悪評の原因に気付いたカナリアの手でシリウスは穏やかな性格を取り戻したのだった。
シリウスはカナリアへ愛を囁き、カナリアもまた少しずつ彼の愛を受け入れていく。
そんな時に、義姉のヒルダがカナリアへ多くの嫌がらせを行い、女の戦いが始まる。
嫁いできただけの女と甘く見ている者たちに分からせよう。
カナリア・ノートメアシュトラーセがどんな女かを──。
小説家になろう、エブリスタ、アルファポリス、カクヨムで投稿しています。

今宵、薔薇の園で
天海月
恋愛
早世した母の代わりに妹たちの世話に励み、婚期を逃しかけていた伯爵家の長女・シャーロットは、これが最後のチャンスだと思い、唐突に持ち込まれた気の進まない婚約話を承諾する。
しかし、一か月も経たないうちに、その話は先方からの一方的な申し出によって破談になってしまう。
彼女は藁にもすがる思いで、幼馴染の公爵アルバート・グレアムに相談を持ち掛けるが、新たな婚約者候補として紹介されたのは彼の弟のキースだった。
キースは長年、シャーロットに思いを寄せていたが、遠慮して距離を縮めることが出来ないでいた。
そんな弟を見かねた兄が一計を図ったのだった。
彼女はキースのことを弟のようにしか思っていなかったが、次第に彼の情熱に絆されていく・・・。
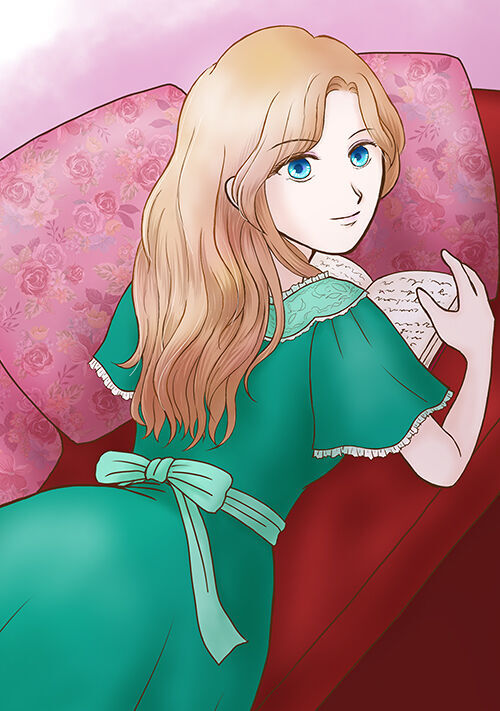
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

婚約者を妹に譲ったら、婚約者の兄に溺愛された
みみぢあん
恋愛
結婚式がまじかに迫ったジュリーは、幼馴染の婚約者ジョナサンと妹が裏庭で抱き合う姿を目撃する。 それがきっかけで婚約は解消され、妹と元婚約者が結婚することとなった。 落ち込むジュリーのもとへ元婚約者の兄、ファゼリー伯爵エドガーが謝罪をしに訪れた。 もう1人の幼馴染と再会し、ジュリーは子供の頃の初恋を思い出す。
大人になった2人は……

P.S. 推し活に夢中ですので、返信は不要ですわ
汐瀬うに
恋愛
アルカナ学院に通う伯爵令嬢クラリスは、幼い頃から婚約者である第一王子アルベルトと共に過ごしてきた。しかし彼は言葉を尽くさず、想いはすれ違っていく。噂、距離、役割に心を閉ざしながらも、クラリスは自分の居場所を見つけて前へ進む。迎えたプロムの夜、ようやく言葉を選び、追いかけてきたアルベルトが告げたのは――遅すぎる本心だった。
※こちらの作品はカクヨム・アルファポリス・小説家になろうに並行掲載しています。

愛する人は、貴方だけ
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
下町で暮らすケイトは母と二人暮らし。ところが母は病に倒れ、ついに亡くなってしまう。亡くなる直前に母はケイトの父親がアークライト公爵だと告白した。
天涯孤独になったケイトの元にアークライト公爵家から使者がやって来て、ケイトは公爵家に引き取られた。
公爵家には三歳年上のブライアンがいた。跡継ぎがいないため遠縁から引き取られたというブライアン。彼はケイトに冷たい態度を取る。
平民上がりゆえに令嬢たちからは無視されているがケイトは気にしない。最初は冷たかったブライアン、第二王子アーサー、公爵令嬢ミレーヌ、幼馴染カイルとの交友を深めていく。
やがて戦争の足音が聞こえ、若者の青春を奪っていく。ケイトも無関係ではいられなかった……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















