16 / 35
第四章 公爵令嬢の矜持
第十六話 強かな女
しおりを挟む「困ったわね。何がいけないのかしら……」
「日光に当てすぎなんじゃないか?」
時刻は午前八時を過ぎた頃。
始業時間まで三十分を切った皇帝執務室にて、お揃いの深い栗色の頭を突き合わせているのは、ソフィリアとユリウス――ロートリアス公爵家の姉弟だ。
ペリドットを彷彿とさせる彼らの黄緑色の瞳は、日の光が差し込む明るい窓辺に置かれたガラス容器の中を熱心に見つめている。
ガラス容器には水が張られ、小さな植物がぷかぷかと浮かんでいた。
ソフィリアの二十六歳の誕生日に、レイスウェイク大公爵家の摩訶不思議な蔦執事セバスチャンから贈られた、その若葉である。
スミレによってプチセバスと命名されたそれは、ソフィリアが日中の大半を過ごす皇帝執務室で育てられていた。
ところが、そろそろ十日が過ぎようというのに、発育の具合がいまいちのようでいまだに根も出ない。
ユリウスが言うように日の光が強すぎるのかと思って日陰に移動させてはみたが、余計に元気がなくなってしまい、慌てて元の場所に戻したのは昨日のこと。
もともと植物の扱いに慣れていないソフィリアは、どうしたものか、と顎に片手を当ててため息を吐く。
しかしながら、プチセバスの発育不全の他にももう一つ、彼女にため息を吐かせる原因があった。
「……まったく、あっちは鬱陶しいくらい元気なんだけどな」
「こら、ユリウス。そんな言い方はしないのよ」
苦虫を噛み潰したような顔をする弟を窘めつつ、ソフィリアもその視線の先に目をやって苦笑を浮かべる。
この部屋の主であるグラディアトリアの皇帝ルドヴィークは、始業時間を待たずにすでに執務机に向かっていた。
とはいえ、彼が働き者なのはいつものことであり、問題はその前に陣取る人物である。
癖のある赤毛が、その人が声を発するたびにふわふわと背中で揺れた。
「――ですから私、きっとルドヴィーク様のお役に立ってみせますわ!」
「いや、気持ちはありがたいが……」
「遠慮なさらないでくださいまし! さあさ、何をいたしましょう? 書類の整理ですか? それとも、机の上の整頓でしょうか?」
「うわっ、待て待て! 頼むから、そこの書類の山には触ってくれるな! 順番が分からなくなると面倒なんだ!」
執務机に乗り上げるようにして迫るのは、ソフィリアの誕生日の翌日にグラディアトリアへとやってきた、隣国パトラーシュの公爵令嬢モディーニである。
物腰柔らかで親しみやすい皇帝であると人気のルドヴィークも、仕事に関することならば、自身の父や祖父のような年長者でも容赦無く叱り飛ばす気概があるのだが、今はたった十六歳の少女相手にたじたじになっている。
初対面からルドヴィークとの結婚を望んでいたモディーニの要求は、先日ついに〝子供を産ませろ〟なんてところまで達した。
それ以来、以前にも増してぐいぐいと――それこそ所構わず人目を憚らず迫ってくる彼女に、ルドヴィーク本人はもちろん、その補佐官として一緒に過ごす時間の長いソフィリアも、さすがに辟易し始めている。
そしてそれは、モディーニのお守り役を命じられているユリウスも同じだった。
ユリウスはちっと舌打ちをすると、こちらに背中を向けているモディーニに大股で近づいていく。
母が見たら卒倒しそうな弟の柄の悪さに、ソフィリアは苦笑いを深めずにはいられなかった。
「おい、いい加減にしろ。朝の挨拶をするだけだと言うから連れてきてやったのに、陛下の邪魔をするんじゃない。ご迷惑だろうが」
「まあ、失礼な! 邪魔なんてしないわ! 私は、ルドヴィーク様のお手伝いをしたいだけだもの!」
「わからないやつだな。国家機密に関わる書類だってあるっていうのに、パトラーシュの人間であるお前に触らせるわけないだろう」
「私はもう、パトラーシュに戻る気はありませんわ!」
こうした、モディーニとユリウスのやりとりもすっかり見慣れたもので、当のルドヴィークは彼らと執務机に溜まった書類を見比べてやれやれといった顔をしている。
このままでは自分も彼も仕事を始められないと判断したソフィリアは、一枚の書類を手にとって、睨み合うモディーニとユリウスの間に割り込んだ。
「それでは、モディーニさん。図書館に行ってこちらの書類に関する資料を揃えていただけるよう、司書長にお願いしてきていただけないかしら? とっても大事な案件なの」
「大事な案件!? そのお使いは、私がルドヴィーク様のお役に立つことになりますか!?」
「ええ、もちろん。さあ、ユリウスもそろそろ騎士団に顔を出さないといけないでしょう? モディーニさんを図書館にお送りして、早く行きなさい」
「やれやれ……騎士団の詰所と図書館は反対方向なんだけどな」
うんざり顔のユリウスは、使命感に目を輝かせるモディーニに引っ張られるようにして皇帝執務室を後にする。
すると、扉が閉まるのを待ちかねたかのように、ルドヴィークが口を開いた。
「大事な案件とは? モディーニにいったい何の書類を渡したんだ?」
「王宮の造園に関する今季の定期報告書です」
「は? それって基本的には事後報告で、いつも私が形式上サインするだけのやつじゃなかったか?」
「ええ、司書長もご存知だと思います。ですから、モディーニさんがそんなものを持って陛下のために資料を探しに来たと言えば、こちらの意図を察してうまく足止めしてくださいますよ」
その答えに納得した顔をするルドヴィークに向かって、それに、とソフィリアは続ける。
「モディーニさんが今後どうなさりたいのか――先ほどユリウスに言ったように、本当にもうパトラーシュに戻る気はないのか、それとも相続問題の熱りが覚めれば戻るつもりなのかは分かりません。ですが、もしも陛下の役に立ちたいという言葉が本心なのでしたら、図書館に通い詰めて勉学に励むのが彼女にとって得策かと思います。かつての私がそうであったように……」
公爵令嬢という地位に驕り、愚かな行いの末に皇妃候補から外れたソフィリア。
それから自分を見つめ直した彼女は、父の勧めで王宮の図書館に通い詰め、博識な司書長に師事することで、公爵令嬢ではなく一文官として新たな人生へと踏み出した。
それをそのままモディーニに踏襲させようというつもりはない。
けれど、父親という強固な庇護者を亡くした彼女のこれからを思えば、知識はいくらあっても困らないだろう。
そんなソフィリアの考えを黙って聞いていたルドヴィークだったが、ふと手元に視線を落として呟いた。
「……ソフィは、私がモディーニを側に置いても構わないと思っているのか?」
「陛下?」
言葉の意図が掴めず問い返すソフィリアに、ルドヴィークは小さくかぶりを振って、何でもないと答える。
そうして、気持ちを切り替えるみたいに大きく一つ深呼吸すると、執務机の傍に積まれていた書類を手に取った。
「さあ、やっと静かになったんだ。仕事を始めよう」
「はい……」
そのまま沈黙が落ちた皇帝執務室には、書類を捲る音だけがパラパラと小さく響く。
一部始終を見ていたプチセバスが、窓辺でぴちゃんと水を跳ねさせた。
「――ソ、ソフィ!」
午後のお茶の時間が近づいた頃である。
所用のため、とある部屋の扉を叩こうと片手を上げていたソフィリアは、息急き切って名を呼ばれて後ろを振り返った。
声の主は、母后陛下付きの侍女ルリである。
「まあ、ルリ? どうしたの、そんなに慌てて」
「た、大変! 大変なんです!」
ソフィリアがただならぬ様子の親友と向かい合ったと同時に、今しがた彼女がノックしようとしていた扉が内側から開いた。
顔をのぞかせたのは、ルリの夫である宰相クロヴィス。
ソフィリアが訪ねようとしていたのは、宰相執務室だったのである。
どうしました? と優しい声で問うクロヴィスとソフィリアを縋るように見上げて、ルリが口を開く。
「モ、モディーニさんが、ご令嬢達の一団に連れ去られてしまったんです!!」
「……ほう、連れ去られたとは穏やかではないですね」
「まさか、誘拐でしょうか」
眼鏡を指で押し上げるクロヴィスと顔を見合わせ、かつてスミレを我が物にせんと王宮から連れ去った前科のあるソフィリアは身構える。
しかし、よくよくルリの話を聞いてみると、どうやら彼女の言う〝連れ去られた〟には語弊がありそうだ。
朝から図書館へ〝おつかい〟に出されていたモディーニだが、正午を前にして一度皇帝執務室に戻ってきていた。
司書長が正しくソフィリアの意図を察した末に見繕った〝資料〟を抱えて。
その後彼女は、資料が揃うまでの間に勧められた本の続きが気になるとかで、昼食後再び図書館に足を運んでいたのだ。
けれども、目的の本を読み終わってしまったのか、それとも単純に飽きたのか、図書館から出て一人きりで王宮の廊下を歩いていたところで、件の令嬢達とばったり出会してしまったらしい。
そうして、一言二言言葉を交わしたモディーニが、彼女達に囲まれるようにして一緒に歩き去る姿を、中庭を挟んで向かいの廊下を偶然通りがかったルリが目撃してしまった、というわけだ。
それを聞いたソフィリアはクロヴィスと再び顔を見合わせ、しかし今度は苦笑いを浮かべた。
「うーん……ちょうどお茶の時間ですからね。庭園に面したテラスにでも向かったのでしょう」
「はい、王宮の庭園はこの季節薔薇が見事ですから、連日お茶会が開かれている模様です」
「えっ……、あの、クロヴィス様もルリも、どうしてそんなに落ち着いていらっしゃるんですか!? こうしている間にも、モディーニさんがっ……!!」
たった一人異国の王宮で過ごす年若い少女が、友好的とは言い難い女性の一団に連れ去られた。
にもかかわらず、全くもって焦る様子のない親友と夫の姿は、ルリには随分と薄情に映ったようだ。
とたんに悲しそうな顔をするルリの頭を、ソフィリアとクロヴィスはにこにこしながら左右から撫でる。
「あのね、ルリ。心配しなくても、たぶんお茶に誘われただけよ? ご令嬢達はなにもモディーニさんを取って食ったりしないわ」
「で、でも……あの方達を一人で相手するなんて……モディーニさん、大丈夫でしょうか……?」
「異国の皇帝相手に子供を産ませろなんて直談判してくるお嬢さんが、大人しくご令嬢達にいびられると思います? 返り討ちにするのが落ちでしょう」
「そ、そうかもしれませんが……」
多くの貴族にとって、小さなお茶会であろうと立派な社交の場である。
そこでの会話を通して人脈を広げ、あるいは腹を探り合い、社交会での自身の立ち位置を強固なものにしなければならない。
妾腹とはいえ、父である前レイヴィス公爵に溺愛されて嫡出子にも劣らない生活をしてきたというモディーニもそれを重々承知しているはずだ。
それでも、グラディアトリアの令嬢達からの誘いに乗ったのだから、彼女達からの宣戦布告に応じる気概があったということだろう。
令嬢達も馬鹿ではない。モディーニが断れば、無理に参加させるようなことはしないはずだ。
だからソフィリアもクロヴィスも、モディーニを心配する必要はないと考えたのだが、ルリだけは違った。
「でも……でも、やっぱりお一人では心細い思いをなさるのではないでしょうか……」
母后陛下の宮で寝泊まりしていることもあり、その侍女であるルリはモディーニと接する時間が多い。
自身も貴族の妾腹で苦労した過去を持つことから、モディーニに強く同情を抱いてもいた。
まるで我が子を案ずる母のような憂い顔をするルリに、さすがに良心が痛んだソフィリアは今一度クロヴィスと顔を見合わせる。
そうして、しばしの逡巡の後、観念したみたいに言った。
「分かったわ、ルリ。私が行って様子を見てきましょう。何事もなければ戻ってきますし、万が一モディーニさんが困っているようでしたら、適当に理由を付けて連れて帰ってきます」
「は、はい……ありがとう、ソフィ! あの、私も一緒に行きます!」
とたん、ルリの顔に浮かんだ安堵の笑み。そこに、自分に向けられる多大な信頼を感じて、ソフィリアは何ともくすぐったい気分になる。
この笑顔のためならば、少々の面倒事も苦にはならないと思えた。
「そういうわけです、閣下。ルリをお借りして様子を見て参りますので、こちらにサインをお願いします。後ほどいただきに上がりますので」
「その必要はありません。早急にサインをして、私がルドに届けておきましょう。ルリの憂いを払拭するためにあなたの時間をいただくのです。それくらいさせてください」
妻のためならば何だって厭わないクロヴィスの申し出に、ソフィリアは素直に甘えることにする。
宰相のサインで完成する書類を彼に預けると、ルリと連れ立って宰相執務室に背を向けた。
クロヴィスはそれを微笑ましそうに見送っていたが、ふと手元の書類に目を落としたとたん、彼には珍しくしまったという顔をする。
「私としたことが……書類の内容も確認せずに迂闊なことを言いましたね」
というのも、彼が今しがたソフィリアから受け取った書類。
実は、先日から皇帝と宰相の間で意見が割れ、再考を求めて突き返し続けていた事案に関するものだったからだ。
それなのにクロヴィスは、早急にサインをしてルドヴィークに届けると宣言してしまった。
彼はしばしの間、忌々しげに件の書類を睨んでいたが、やがて眉間の皺を解いて深々とため息を吐いた。
「悔しいですが仕方ありません。今回ばかりは、こちらが折れるしかないですね。いやはや、ソフィリアも随分と強かになったものです。一体誰に似たんでしょう。顔が見たいですね」
きっと、最初の上司に似たのでしょうよ。
そう言って、クロヴィスに鏡を差し出せる猛者はその場にはいなかった。
10
あなたにおすすめの小説

愛する旦那様が妻(わたし)の嫁ぎ先を探しています。でも、離縁なんてしてあげません。
秘密 (秘翠ミツキ)
恋愛
【清い関係のまま結婚して十年……彼は私を別の男へと引き渡す】
幼い頃、大国の国王へ献上品として連れて来られリゼット。だが余りに幼く扱いに困った国王は末の弟のクロヴィスに下賜した。その為、王弟クロヴィスと結婚をする事になったリゼット。歳の差が9歳とあり、旦那のクロヴィスとは夫婦と言うよりは歳の離れた仲の良い兄妹の様に過ごして来た。
そんな中、結婚から10年が経ちリゼットが15歳という結婚適齢期に差し掛かると、クロヴィスはリゼットの嫁ぎ先を探し始めた。すると社交界は、その噂で持ちきりとなり必然的にリゼットの耳にも入る事となった。噂を聞いたリゼットはショックを受ける。
クロヴィスはリゼットの幸せの為だと話すが、リゼットは大好きなクロヴィスと離れたくなくて……。

虐げられ続けてきたお嬢様、全てを踏み台に幸せになることにしました。
ラディ
恋愛
一つ違いの姉と比べられる為に、愚かであることを強制され矯正されて育った妹。
家族からだけではなく、侍女や使用人からも虐げられ弄ばれ続けてきた。
劣悪こそが彼女と標準となっていたある日。
一人の男が現れる。
彼女の人生は彼の登場により一変する。
この機を逃さぬよう、彼女は。
幸せになることに、決めた。
■完結しました! 現在はルビ振りを調整中です!
■第14回恋愛小説大賞99位でした! 応援ありがとうございました!
■感想や御要望などお気軽にどうぞ!
■エールやいいねも励みになります!
■こちらの他にいくつか話を書いてますのでよろしければ、登録コンテンツから是非に。
※一部サブタイトルが文字化けで表示されているのは演出上の仕様です。お使いの端末、表示されているページは正常です。
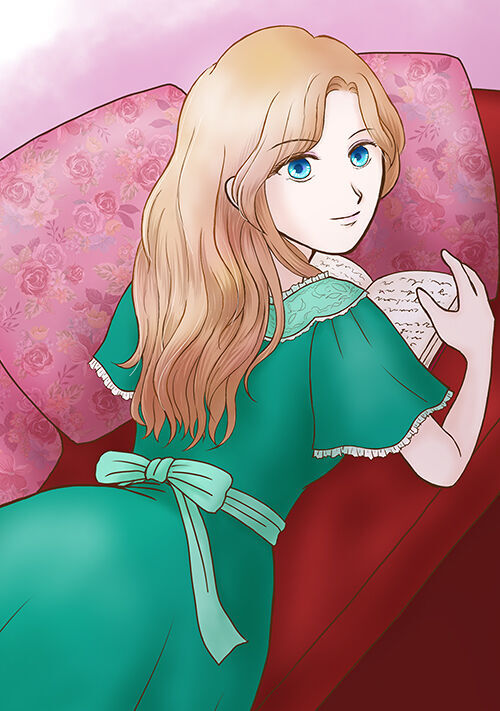
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

【完結】婚約破棄された令嬢の毒はいかがでしょうか
まさかの
恋愛
皇太子の未来の王妃だったカナリアは突如として、父親の罪によって婚約破棄をされてしまった。
己の命が助かる方法は、友好国の悪評のある第二王子と婚約すること。
カナリアはその提案をのんだが、最初の夜会で毒を盛られてしまった。
誰も味方がいない状況で心がすり減っていくが、婚約者のシリウスだけは他の者たちとは違った。
ある時、シリウスの悪評の原因に気付いたカナリアの手でシリウスは穏やかな性格を取り戻したのだった。
シリウスはカナリアへ愛を囁き、カナリアもまた少しずつ彼の愛を受け入れていく。
そんな時に、義姉のヒルダがカナリアへ多くの嫌がらせを行い、女の戦いが始まる。
嫁いできただけの女と甘く見ている者たちに分からせよう。
カナリア・ノートメアシュトラーセがどんな女かを──。
小説家になろう、エブリスタ、アルファポリス、カクヨムで投稿しています。

婚約者を妹に譲ったら、婚約者の兄に溺愛された
みみぢあん
恋愛
結婚式がまじかに迫ったジュリーは、幼馴染の婚約者ジョナサンと妹が裏庭で抱き合う姿を目撃する。 それがきっかけで婚約は解消され、妹と元婚約者が結婚することとなった。 落ち込むジュリーのもとへ元婚約者の兄、ファゼリー伯爵エドガーが謝罪をしに訪れた。 もう1人の幼馴染と再会し、ジュリーは子供の頃の初恋を思い出す。
大人になった2人は……

今宵、薔薇の園で
天海月
恋愛
早世した母の代わりに妹たちの世話に励み、婚期を逃しかけていた伯爵家の長女・シャーロットは、これが最後のチャンスだと思い、唐突に持ち込まれた気の進まない婚約話を承諾する。
しかし、一か月も経たないうちに、その話は先方からの一方的な申し出によって破談になってしまう。
彼女は藁にもすがる思いで、幼馴染の公爵アルバート・グレアムに相談を持ち掛けるが、新たな婚約者候補として紹介されたのは彼の弟のキースだった。
キースは長年、シャーロットに思いを寄せていたが、遠慮して距離を縮めることが出来ないでいた。
そんな弟を見かねた兄が一計を図ったのだった。
彼女はキースのことを弟のようにしか思っていなかったが、次第に彼の情熱に絆されていく・・・。

P.S. 推し活に夢中ですので、返信は不要ですわ
汐瀬うに
恋愛
アルカナ学院に通う伯爵令嬢クラリスは、幼い頃から婚約者である第一王子アルベルトと共に過ごしてきた。しかし彼は言葉を尽くさず、想いはすれ違っていく。噂、距離、役割に心を閉ざしながらも、クラリスは自分の居場所を見つけて前へ進む。迎えたプロムの夜、ようやく言葉を選び、追いかけてきたアルベルトが告げたのは――遅すぎる本心だった。
※こちらの作品はカクヨム・アルファポリス・小説家になろうに並行掲載しています。

残念な顔だとバカにされていた私が隣国の王子様に見初められました
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
公爵令嬢アンジェリカは六歳の誕生日までは天使のように可愛らしい子供だった。ところが突然、ロバのような顔になってしまう。残念な姿に成長した『残念姫』と呼ばれるアンジェリカ。友達は男爵家のウォルターただ一人。そんなある日、隣国から素敵な王子様が留学してきて……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















