17 / 35
第四章 公爵令嬢の矜持
第十七話 紅茶の上手な淹れ方
しおりを挟むグラディアトリア城の庭園は、隣国コンラート出身の高名な植物学者ロバート・ウルセルが手掛けたことで知られる。
先帝ヴィオラントが彼に師事し、その庭園を深く愛したこともあり、ロバート亡き後も弟子の庭師達によって美しいままに整えられてきた。
庭園の所々に立つ東屋にはテーブルと椅子が置かれ、お茶を楽しめる憩いの場となっている。
モディーニと令嬢達がいたのは、そんな中の一つ――後宮からほど近い場所にある、高い垣根に囲まれた穴場の東屋だった。
すぐ側には樹齢百年を超える大きなアカシアの木が立っていて、季節になると枝葉を埋め尽くすほどにふわふわとした黄色い小花でいっぱいになる。
ただのロートリアス公爵令嬢でしかなかった頃のソフィリアも、お気に入りの場所だった。
皇帝ルドヴィークが未婚のため、現在グラディアトリア城の家政を取り仕切る女主人は母后エリザベスである。
令嬢達が頻繁に城に足を運んでくるのも、彼女が貴族の子女に対して社交の場を提供することに積極的なおかげだった。
給仕もまた、母后が用意した後宮付きの侍女が請け負うことになっている。
つまり……
「侍女は給仕役とともに、見張りの役目も兼ねている。母后陛下の侍女の目があるから、ご令嬢達もモディーニさんに対してあんまりなことはできない、ということですか?」
「そういうことね。ちょっとした言葉の応酬くらいならば侍女も目を瞑るでしょうが、度が過ぎる暴言、ましてや暴力なんて振るおうものなら母后陛下に報告を上げられて、最悪の場合は社交界から追放されてしまいますもの」
お茶会が開かれている東屋からは死角になる垣根に隠れて、ソフィリアとルリはそうヒソヒソと言い交わす。
ルリが言うように見張り役も兼ねるだけあって、この時モディーニ達の給仕をしていたのは母后陛下に長く仕える年嵩の侍女――ルリも見習い時代に世話になった侍女だった。
彼女が目を光らせているおかげもあってか、お茶会は表面上は和やかに進んでいる。
モディーニとテーブルを囲んでいるのは綺麗に着飾った四人の令嬢で、ソフィリアはその全員と面識があった。
場を仕切っているのが侯爵令嬢で、その取り巻きのうち二人は伯爵令嬢、一人は子爵令嬢――モディーニがグラディアトリアにやってきた日の昼間、廊下で出会したソフィリアをお茶に誘ったのと同じ面子だ。
今回モディーニに声をかけたのは、突然皇帝の周囲をうろつき始めた余所者への牽制と、あわよくば歳若く世間知らずな印象の彼女がお茶会で失敗することを期待してのことだったろう。
とはいえ、庶子として生まれながら嫡出子と同等に育てられたというのは本当のことのようで、モディーニは普段の奔放さはどこへやら、非の打ち所がない完璧な所作でカップを傾けている。
当てが外れたらしい令嬢達は、時折なんとも言えない表情で顔を見合わせた。
「さあ、ルリ。これで安心したでしょう?」
「はい……お手を煩わせて申し訳ありません」
モディーニの平然とした様子に、取り立てて騒ぐ必要はなかったとルリもようやく納得したようだ。
畏まって謝罪の言葉を述べた後、彼女はソフィリアに向かってはにかんだみたいに笑った。
「ソフィ、付き合ってくれてどうもありがとう」
「いいえ、お礼を言うのはむしろ私の方だから」
「えっと……それは、どういうことかしら?」
「ふふ、気にしないで。こっちの話よ」
きょとんとして首を傾げるルリに、ソフィリアはにっこりと満面の笑みで応える。
なんといっても、宰相閣下が首を縦に振ってくれないせいで、ここ数日皇帝陛下の――ひいては、その補佐官であるソフィリアの頭を悩ませていた案件がようやく先に進みそうなのだ。
書類にサインをして皇帝に届けると宣言したからには、今回ばかりは宰相閣下も譲歩してくれるだろう。
騙し打ちのような真似をしてしまったことは否めないが、後悔はしていない。
交渉相手に隙を見せてはならない――かつてそうソフィリアに教え込んだのは、他ならぬ宰相閣下自身なのだから。
宰相執務室の前でルリと出会えた幸運と、泣く子も黙る鬼宰相も彼女が関わると少なからず注意力が散漫になることを利用した、ソフィリアの機転がもたらした大勝利である。
手強い元上司と議論を戦わせる時間が浮いたのだし、今日はのんびりと午後のお茶が楽しめそうだ。
そうほくほくしながら、ソフィリアがルリとともに王宮の中に戻ろうとした、その時である。
「――それにしても、前レイヴィス公爵閣下も酔狂でいらっしゃるわ。どれだけ愛情をかけようとも庶子は庶子。社交界に居場所なんてありませんのに」
憂いを帯びた顔を作ってそう告げたのは、令嬢達の筆頭である侯爵令嬢だった。
すかさず、加勢するように二人の伯爵令嬢がそれに続く。
「お気の毒ですわ。ご自身は公爵令嬢のおつもりなのに、世間は誰もそうとは認めてくれないんですもの」
「モディーニさんだって、好きで庶子に生まれたわけじゃありませんのにねえ」
彼女達は揃って物憂げなため息を吐くが、モディーニの生い立ちに同情しているわけではないのは明白だった。
子爵令嬢だけは口を噤んでいたが、だからといってモディーニの味方をするつもりもないようだ。
「ソフィ……」
ルリがまた不安そうな顔をするが、ソフィリアは無言で首を振る。
見張り役の侍女も、憂いのこもった目でモディーニを見たが、令嬢達の言葉を止めようとする素振りはなかった。
令嬢達の言葉は意地の悪いものではあるが、第三者が介入しなければならないほど悪質ではない、と判断されたのだ。
というのも、モディーニが妾腹であることは、紛うことない事実だからだ。
生まれは本人の責任ではないが、それが配慮されるほど貴族の社会は甘くはない。
モディーニ自身も覚悟の上だろう。令嬢達の言葉に何も返すこともなく黙ってカップを傾けている。
自分でお茶の誘いを受けたからには、毒を盛られてでもいない限り、一杯は飲まなければならない。
逆を言うと、一杯飲み干しさえすれば責務を果たしたことになる。
モディーニは賢明にも、嘲笑を滲ませる令嬢達に構うことなく、ようやく空になったカップをソーサーに戻すと、おいしいお茶をごちそうさまでした、と笑顔のまで浮かべて退出しようとした。
しかし、その余裕の表情が令嬢達の逆鱗に触れてしまったらしい。
「新しいレイヴィス公爵閣下は少々お考えが足りない方なのかしら。古くから続く友好国の城に、よりにもよって庶子を寄越すだなんて」
現レイヴィス公爵――つまり、腹違いの長兄ライアンを貶める言葉を侯爵令嬢が口にしたとたん、椅子から立ち上がろうとしていたモディーニの体が強張った。
それを気にも留めない伯爵令嬢達が口々に続ける。
「まさか、グラディアトリアとパトラーシュの関係に水を差すおつもりなのかしら?」
「まあ! そんな不穏なお考えの方がパトラーシュの筆頭公爵だなんて、こわいわぁ!」
さらに、さっきは黙っていた子爵令嬢も口を開いた。
「きっと、厄介払いをなさりたかったのでしょう」
とたん、ガタンと大きな音を立ててモディーニが椅子から立ち上がる。
四人の令嬢達も給仕の侍女も、もちろんその場から離れようとしていたソフィリアとルリもぎょっとした。
さらに、ぐっと俯いて唇を噛み締めていたモディーニの手が、テーブルの側に置かれたワゴンの上のポットを引っ掴む。
それを見て、まずいと思ったソフィリアは、反射的に垣根から飛び出していた。
「――モディーニさん!!」
コン、と音を立てて、陶器のポットの蓋がテーブルで跳ねた。
幸い、ポットの中身が空であったおかげで、真っ白いテーブルクロスが紅茶に塗れるのを免れ、とっさに背後からモディーニを抱き留めたソフィリアは安堵のため息をつく。
しかしながら、モディーニがポットの中身をテーブルの上に――いや、その向こうにいる令嬢達に向かってぶちまける心算だったのは明白。
彼女の豹変とソフィリアの思わぬ登場に呆気に取られていた令嬢達も我に返り、あからさまに眉を顰めた。
そして、モディーニの無作法を批難しようと、揃って口を開こうとしたが――
「あらあら、大変。皆さん、カップが空ではありませんか。――そうだわ、二杯目は私がお淹れしてもよろしいかしら?」
「「「「「「えっ!?」」」」」」
ソフィリアが先手を打った。
令嬢達もモディーニも、慌ててついてきたルリまでも驚いた顔をする。
しかし、侍女はさすがに場数を踏んでいるだけある。すぐさまソフィリアの意図を察し、新しい湯と椅子を手配すると申し出た。
その隙に、ソフィリアは抱き留めていたモディーニを有無を言わさぬ力で椅子に座り直させる。
そして、丸まりそうになる彼女の背をぐっと押して胸を張らせると、その耳元に囁いた。
「堂々となさいませ。相手に付け入る隙を与えてはなりません」
「ソフィリア様……」
そうこうしている内に、侍女が新しいお湯を持って戻ってくる。彼女に頼まれたのか、不承不承といった様子ながら椅子を二脚担いで現れたのは、ユリウスだった。
ソフィリアは侍女に丁寧に礼を言い、苦笑いを浮かべて弟を労うと、改めてモディーニをお茶会に誘った令嬢達に向かい合う。
そもそも、どうしてソフィリアとルリがここにいるのか、なんて疑問に令嬢達が気づく隙を与えてはならない。
敬愛する宰相閣下の教えを忠実に守りるため、ソフィリアは彼女達が我に返る前に畳みかけた。
「いつも誘っていただいてもお断りするばかりでしたでしょう? お詫びに、今日は私に振る舞わせてくださいな」
「ソ、ソフィリア様が、手ずからお茶を……?」
令嬢達の中で最初に口を開いたのは、先ほどモディーニが逆上する決定打を与えた子爵令嬢だった。
信じられないような顔をする彼女と、おずおずと顔を見合わせる伯爵令嬢達、そして想定外の事態には弱いのか、いまだ呆気にとられた様子の侯爵令嬢に、ソフィリアは冗談めかして続ける。
「まあ、皆さんったらひどいわ。私にお茶を淹れるのなんて無理だと思っていらっしゃるのね? ですが私、こう見えても手慣れているんですよ? ――そうよね? ルリ、モディーニさん」
「は、はいっ」
「……はい」
「ついでに、ユリウス」
「ついでとはなんだ、ついでとは」
慌てて頷くルリと、いつもの威勢はどこへやら、蚊の鳴くような声で返事をするモディーニ。
成り行きを見守るつもりか、騎士らしく少し離れた場所に控えたユリウスは、モディーニのらしからぬ様子に片眉を上げた。
ここで、皇帝ルドヴィークまでも毎日ソフィリアの淹れたお茶を飲んでいる事実を告げるのは賢明ではない。
令嬢達をやり込めるのが目的ならば覿面だが、別にソフィリアは彼女達と戦いたいわけではないのだから。
お茶の誘いを受けて立ったモディーニが、無事それを完遂できればいい。
そうすれば、ルリの憂いも払拭できるだろうし、しぶしぶ書類にサインしてくれているであろうクロヴィスにも面目が立つのだ。
ソフィリアは令嬢達の視線を感じつつ、ワゴンの上に用意された数種類の茶葉から馴染み深いものを選ぶ。
とはいえ、紅茶を淹れるのは実際さほど難しいことではない。
ポットとカップにお湯を注いであらかじめ温めておく。
一人分の茶葉は種類にもよるがだいたいティースプーン一杯分で、それを人数分入れる。
茶葉を入れたポットには、できるだけ沸騰したてのお湯を手早く、勢いよく注ぐといい。
すぐに蓋をして、茶葉の大きさに合わせてしっかりと蒸らし、時間がきたらスプーンで軽く一混ぜ。
濃さが均一になるよう、茶漉しを通しながら人数分のカップに回して注ぎ入れる――という、基本の手順を守りさえすれば、誰でもできることだ。
けれども、侯爵令嬢も、二人の伯爵令嬢も、子爵令嬢も自分で紅茶を淹れたことはないのだろう。
ソフィリアだって、公爵令嬢という肩書きに驕り高ぶっていた時代は、自分で紅茶を淹れようだなんて考えもしなかった。
けれど……
「やってみると、案外楽しいものです――さあ、入りましたよ。皆さんのお口に合えばいいのですが」
熱湯を注がれたポットの中の茶葉みたいに、ソフィリアの凝り固まっていた人生も、八年前の大きな過ちをきっかけにゆっくりと解けて今に至る。
「……おいしい」
おそるおそるカップに口をつけた侯爵令嬢が、思わずといったふうにそう呟いた時――ソフィリアはまた一つ、世間知らずの公爵令嬢だった時には味わえなかった誇らしさを知った。
10
あなたにおすすめの小説

虐げられ続けてきたお嬢様、全てを踏み台に幸せになることにしました。
ラディ
恋愛
一つ違いの姉と比べられる為に、愚かであることを強制され矯正されて育った妹。
家族からだけではなく、侍女や使用人からも虐げられ弄ばれ続けてきた。
劣悪こそが彼女と標準となっていたある日。
一人の男が現れる。
彼女の人生は彼の登場により一変する。
この機を逃さぬよう、彼女は。
幸せになることに、決めた。
■完結しました! 現在はルビ振りを調整中です!
■第14回恋愛小説大賞99位でした! 応援ありがとうございました!
■感想や御要望などお気軽にどうぞ!
■エールやいいねも励みになります!
■こちらの他にいくつか話を書いてますのでよろしければ、登録コンテンツから是非に。
※一部サブタイトルが文字化けで表示されているのは演出上の仕様です。お使いの端末、表示されているページは正常です。

愛する旦那様が妻(わたし)の嫁ぎ先を探しています。でも、離縁なんてしてあげません。
秘密 (秘翠ミツキ)
恋愛
【清い関係のまま結婚して十年……彼は私を別の男へと引き渡す】
幼い頃、大国の国王へ献上品として連れて来られリゼット。だが余りに幼く扱いに困った国王は末の弟のクロヴィスに下賜した。その為、王弟クロヴィスと結婚をする事になったリゼット。歳の差が9歳とあり、旦那のクロヴィスとは夫婦と言うよりは歳の離れた仲の良い兄妹の様に過ごして来た。
そんな中、結婚から10年が経ちリゼットが15歳という結婚適齢期に差し掛かると、クロヴィスはリゼットの嫁ぎ先を探し始めた。すると社交界は、その噂で持ちきりとなり必然的にリゼットの耳にも入る事となった。噂を聞いたリゼットはショックを受ける。
クロヴィスはリゼットの幸せの為だと話すが、リゼットは大好きなクロヴィスと離れたくなくて……。

【完結】婚約破棄された令嬢の毒はいかがでしょうか
まさかの
恋愛
皇太子の未来の王妃だったカナリアは突如として、父親の罪によって婚約破棄をされてしまった。
己の命が助かる方法は、友好国の悪評のある第二王子と婚約すること。
カナリアはその提案をのんだが、最初の夜会で毒を盛られてしまった。
誰も味方がいない状況で心がすり減っていくが、婚約者のシリウスだけは他の者たちとは違った。
ある時、シリウスの悪評の原因に気付いたカナリアの手でシリウスは穏やかな性格を取り戻したのだった。
シリウスはカナリアへ愛を囁き、カナリアもまた少しずつ彼の愛を受け入れていく。
そんな時に、義姉のヒルダがカナリアへ多くの嫌がらせを行い、女の戦いが始まる。
嫁いできただけの女と甘く見ている者たちに分からせよう。
カナリア・ノートメアシュトラーセがどんな女かを──。
小説家になろう、エブリスタ、アルファポリス、カクヨムで投稿しています。

今宵、薔薇の園で
天海月
恋愛
早世した母の代わりに妹たちの世話に励み、婚期を逃しかけていた伯爵家の長女・シャーロットは、これが最後のチャンスだと思い、唐突に持ち込まれた気の進まない婚約話を承諾する。
しかし、一か月も経たないうちに、その話は先方からの一方的な申し出によって破談になってしまう。
彼女は藁にもすがる思いで、幼馴染の公爵アルバート・グレアムに相談を持ち掛けるが、新たな婚約者候補として紹介されたのは彼の弟のキースだった。
キースは長年、シャーロットに思いを寄せていたが、遠慮して距離を縮めることが出来ないでいた。
そんな弟を見かねた兄が一計を図ったのだった。
彼女はキースのことを弟のようにしか思っていなかったが、次第に彼の情熱に絆されていく・・・。
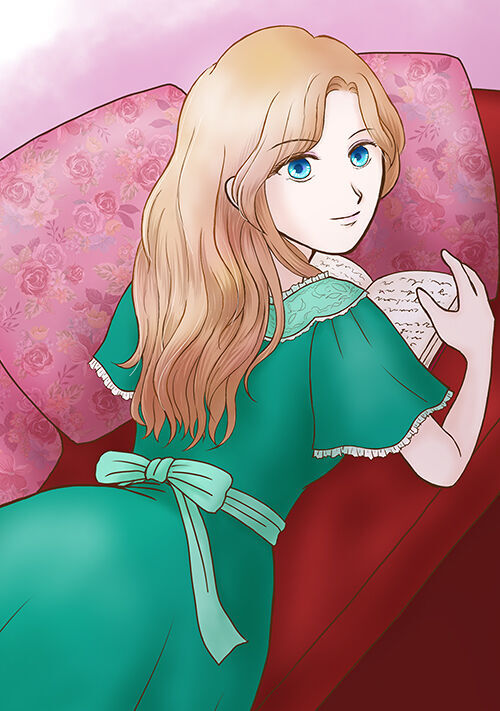
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

婚約者を妹に譲ったら、婚約者の兄に溺愛された
みみぢあん
恋愛
結婚式がまじかに迫ったジュリーは、幼馴染の婚約者ジョナサンと妹が裏庭で抱き合う姿を目撃する。 それがきっかけで婚約は解消され、妹と元婚約者が結婚することとなった。 落ち込むジュリーのもとへ元婚約者の兄、ファゼリー伯爵エドガーが謝罪をしに訪れた。 もう1人の幼馴染と再会し、ジュリーは子供の頃の初恋を思い出す。
大人になった2人は……

P.S. 推し活に夢中ですので、返信は不要ですわ
汐瀬うに
恋愛
アルカナ学院に通う伯爵令嬢クラリスは、幼い頃から婚約者である第一王子アルベルトと共に過ごしてきた。しかし彼は言葉を尽くさず、想いはすれ違っていく。噂、距離、役割に心を閉ざしながらも、クラリスは自分の居場所を見つけて前へ進む。迎えたプロムの夜、ようやく言葉を選び、追いかけてきたアルベルトが告げたのは――遅すぎる本心だった。
※こちらの作品はカクヨム・アルファポリス・小説家になろうに並行掲載しています。

愛する人は、貴方だけ
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
下町で暮らすケイトは母と二人暮らし。ところが母は病に倒れ、ついに亡くなってしまう。亡くなる直前に母はケイトの父親がアークライト公爵だと告白した。
天涯孤独になったケイトの元にアークライト公爵家から使者がやって来て、ケイトは公爵家に引き取られた。
公爵家には三歳年上のブライアンがいた。跡継ぎがいないため遠縁から引き取られたというブライアン。彼はケイトに冷たい態度を取る。
平民上がりゆえに令嬢たちからは無視されているがケイトは気にしない。最初は冷たかったブライアン、第二王子アーサー、公爵令嬢ミレーヌ、幼馴染カイルとの交友を深めていく。
やがて戦争の足音が聞こえ、若者の青春を奪っていく。ケイトも無関係ではいられなかった……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















