27 / 35
第六章 満月の下の騒動
第二十七話 月光に萌ゆる
しおりを挟む「ソフィ、これ……」
「ソフィリア様……これを」
そう言って、シオンとモディーニがそれぞれおずおずと差し出してきたのは、切られた髪と一緒に地面に落ちていたカンザシと、スカーフごと引き剥がされたブローチだった。
二人に礼を言ってそれらを受け取ったソフィリアは、地面に腰を下ろしたまま、まずは手慣れた様子でスカーフを巻く。
傍らに膝を付いたルドヴィークがやたらと熱心に見つめてくるものだから、どうにもこうにも照れくさかった。
最後にスカーフの合わせ目にブローチを飾ると、彼はうんと満足げに頷く。
それにソフィリアもほっとしたものの、続いてカンザシに視線を落として、ここでようやく髪が切られてしまったことを実感する。
「この髪ではカンザシは挿せませんね。せっかくスミレが贈ってくれたのに……申し訳ないです」
スミレがくれたのは、ソフィリアの長い髪を一つにまとめるための髪飾りだ。
毛束をくるっと巻いたところに、太い串のようなそれを挿し込んで留めるのだが、髪がこんなに短くなってしまっては上手く使えないだろう。
綺麗な白磁の玉や金のビーズにぶら下がってキラキラと揺れるペリドットは、どちらかというと地味な色合いのソフィリアの髪に彩りを与えてくれてとても気に入っていたし、何より大好きな親友が吟味に吟味を重ねて贈ってくれたものだった。
たちまちしょんぼり肩を落とすソフィリアに、ルドヴィークが気遣わしげに寄り添う。
そんな二人の様子に柔らかに目を細めて口を開いたのは、スミレの夫であるヴィオラントだった。
「気に病む必要はない。髪が伸びれば、また着けてやってくれ」
「大公閣下……」
ヴィオラントは自分とお揃いのシオンの髪を撫でながら、それに、と続ける。
「スミレはきっと、今度はその短い髪に似合う飾りを選ぶ楽しみができたと言って喜ぶだろう。スミレが喜ぶ顔を見られるのは私も嬉しい」
「父上、そういうところだよ」
相変わらず妻への愛情を開けっ広げにする先帝陛下に、その息子は呆れ顔だ。
そんな親子のやりとりがおかしくて、ソフィリアはルドヴィークと顔を見合わせて微笑む。
モディーニはプリペットの垣根の側に立って、こちらを遠巻きに眺めていた。
その隣に立つユリウスは相変わらず、いかにも仕方なくといった表情である。
彼らの頭上では、まんまるい月が一同を見下ろしていた。
そんな中、ふとある疑問を抱いたソフィリアが口を開く。
「――ところで、陛下。どうして、私達がここにいるのが分かったんですか?」
実は、ソフィリアとモディーニの危機をルドヴィーク達に知らせた者がいた。
ソフィリアに叱られてすごすごと客室に戻ったと思われていた、オズワルドである。
モディーニの手を引いて駆け出すソフィリアと、ナイフを持ってそれを追いかけていく男を目撃したオズワルドは、慌てて人を呼びに王宮へと走った。
直前に、ソフィリアにぎゃふんと言わされていたこともあり、凶器を持った男は自分一人の手には負えないと考えたのだろうが、その判断は正しかったといえよう。
王宮に辿り着いた彼が、警護に当たっていた騎士に助けを求めようとしたところに、ヴィオラントやロレットー公爵と連れ立ったルドヴィークが通りかかったのは、まったくの偶然だった。
オズワルドから話を聞いたルドヴィークは、警護の騎士達が止めるのも聞かずに庭園へと駆け出し、兄であるヴィオラントもそれに続く。
ユリウスに知らせたのは、伯父のロレットー公爵だったようだ。
とはいえ、広大なグラディアトリア城の庭園の中、王宮よりも城門に近い場所にいたソフィリア達を見つけ出すのは容易ではなかっただろう。
それなのに、ルドヴィークがこんなに早く駆けつけることができたのは、実は偶然でも奇跡でもなかった。
「あの目印のおかげだな。月明かりに照らされて、遠くからでもよく見えたんだ」
「目印、ですか?」
ソフィリアはルドヴィークが指差す先――頭上を見上げて、あっと声を上げる。
「あれは――もしかして、プチセバス!?」
シオンが、次いで男が現れた茂みのすぐ側に立つ木の上に、さっきソフィリアの懐から吹っ飛んでいったプチセバスらしきものの姿があった。
ソフィリアを驚かせたのは、その有様だ。
なんと、葉と茎、蔓からなる自身を用いて、でかでかと下向きの矢印を形作っているではないか。
それが、ルドヴィークの言うように月に照らされて、ソフィリア達の居場所を伝える目印の役目を果たしていたのである。
「それにしても……どうして急にあんなに成長しているんでしょうか?」
つい先ほどまで、プチセバスはまだ小さな若葉で、茎や蔓を含めても両手に収まるくらいの大きさでしかなかった。
それなのに木の上の彼は、いまや茎も蔓も立派に伸び、葉だって何枚にも増えている。
あまりに急激な成長をしたプチセバスの姿に、ソフィリアは戸惑いを隠せなかった。
幸い、この場には植物に詳しい者が居合わせた。ヴィオラントだ。
この王城の庭を作ったロバート・ウルセルに師事していたばかりか、プチセバスの大本であるレイスウェイク大公爵家の蔦執事セバスチャンも、元々は彼の実験と偶然が重なった末の産物らしい。
ヴィオラントは、仰向きすぎて後ろにひっくり返りそうになったシオンを抱き上げると、興味深そうにプチセバスを見上げて言った。
「植物には、月明かりで成長するものもあるという。あれは、太陽の光よりも月の光の方が合うのだろう」
「まあ、それで……どうりで、昼間に窓辺に置いてもなかなか育たないわけです」
なかなか成長しない彼にずっと気を揉んでいたが、思いがけない出来事によってその原因が判明した。
そうこうしているうちに、当のプチセバスも事態が収拾したことに気づいたのだろう。
お役御免とばかりに、木の上からしゅるしゅると降りてくる。
植物らしからぬその活動的な姿に、見慣れていないモディーニは完全に引いてしまって、側に立つユリウスの袖を縋るみたいに握りしめた。
一方、地面に腰を下ろしたままのソフィリアは、黄緑色の葉と茎と蔓でもって、褒めて褒めてとばかりに戯れ付かれる。
動物とは違って体温のないその身はひんやりとして、何だか不思議な心地がする。
今回こうして、ルドヴィーク達に危険を知らせることでソフィリアを救ってくれたプチセバスも、八年前にスミレを攫った無知で傲慢な公爵令嬢ソフィリアを止めたのも、蔦執事セバスチャンから分かたれたポトスだった。
八年前は、ソフィリアは父の一存によって皇妃候補から外れることになったのだが、しかしよくよく考えてみれば、あの時に愚かな行いを止めてもらえたからこそ、今のソフィリアがあるのかもしれない。
そう思うと、最初に出会ったポトスもまた、彼女に人生を見つめ直す機会を与え、自立した一人の人間へと成長させた功労者と言えるだろう。
「……ありがとう、プチセバス」
ソフィリアは、万感の思いを込めてそう呟く。
そんな彼女の不揃いの髪を、さっきルドヴィークがそうしたように、緑色の柔らかな葉が慈しむように撫でた。
王宮の方が徐々に騒がしくなってきた。
パトラーシュの騎士団の制服を着た者を、グラディアトリアの騎士達が連行したとあっては、騒ぎになって当然だろう。
ましてや、前者にグラディアトリアの皇帝補佐官が襲われているのを目撃したオズワルドは、コンラートからの客人である。
三国間宰相会議は明日で終了するはずだったが、今回ばかりはつつがなくとはいかないようだ。
ルドヴィークと自分の明日の予定は立て直す必要がありそうだ、とソフィリアは人知れずため息を吐く。
そんな彼女に、ほら、と片手を差し出してきたのは、先に立ち上がったルドヴィークだ。
けれども、ソフィリアはその手をじっと見つめるばかりで、なかなか取ろうとはしない。
不思議に思ったルドヴィークが、首を傾げかけた時だった。
「……陛下、お願いがあるのですが」
「うん?」
「あっ……いいえ、やっぱりいいです。なんでもないです」
「んん?」
ソフィリアは愛想笑いを浮かべてルドヴィークから顔を逸らすと、離れたところでモディーニと並んで立っている弟を呼ぼうとする。
ところが、ルドヴィークがすかさずそれを遮った。
「なんなんだ、ソフィ。私に何か言いかけたんじゃないのか?」
「そうなんですけど……やっぱり、ユリウスに頼もうかと……」
彼女にしては珍しく歯切れの悪い様子に、せっかく立ち上がっていたルドヴィークが、不服そうな顔をしてしゃがみ直してしまう。
どういうことだ、と詰め寄られてしまえば、ソフィリアは観念するしかなかった。
「あの、たいへんお恥ずかしい話なんですが……実はその、腰が抜けてしまいまして」
「ん? 腰?」
「はい。この通り、立てそうにありませんので、ユリウスにおぶって行ってもらおうかと」
「おぶって……」
腰が抜けたと白状したソフィリアに、ルドヴィークは一瞬ぽかんとした顔をする。
けれどもすぐに、さっきよりもさらに不服そうな表情になって、彼女に詰め寄った。
「納得いかないんだが? ユリウスはよくて、なぜ私ではだめなんだ」
「だって、陛下……パトラーシュとコンラートの方達がいらっしゃっているんですよ? 部下をおぶっている姿なんか見られてしまっては、陛下の沽券にかかわりますでしょう? その点、ユリウスは弟ですから、少々体裁が悪かろうが心が痛みません」
「ちょっと、聞こえてますけどー。こっちも、子守りで手一杯なんですけどねー?」
「……っ、子守りって言わないでください!」
二人のやりとりに、ユリウスがしかめっ面で口を挟む。
その言い草が不服だったらしいモディーニは、慌てて彼の袖から手を離してきっと睨みつけた。
しかし、その後に続いたユリウスとモディーニの言い合う声も、ルドヴィークの耳には入ってはいなかったようだ。
彼は額と額がぶつかりそうなくらいに顔を近づけると、ソフィリアの瞳を覗き込んで言った。
「――お前に虚勢を張らせなければ保てないような沽券なら必要ない。さっき、そう言っただろう」
そうして、これ以上の問答は不要とばかりに、有無を言わさず彼女を抱き上げる。
背におぶうのではなく、背中と膝の裏に腕を回して、それはそれは大事そうに。
「へ、陛下……!?」
予想外の展開に、さしものソフィリアも目を白黒させた。
そんな二人をヴィオラントの首筋に抱き着いて見守っていたシオンが、ぷにぷにの頬を父のそれに押し付けつつ呟く。
「ああういうのを〝怪我の功名〟って言うんだよね? 父上」
「ああ、そうだな」
末弟の頼もしい背中と、愛妻そっくりの息子のしたり顔に、ヴィオラントもその美貌をほのかに綻ばせた。
10
あなたにおすすめの小説

虐げられ続けてきたお嬢様、全てを踏み台に幸せになることにしました。
ラディ
恋愛
一つ違いの姉と比べられる為に、愚かであることを強制され矯正されて育った妹。
家族からだけではなく、侍女や使用人からも虐げられ弄ばれ続けてきた。
劣悪こそが彼女と標準となっていたある日。
一人の男が現れる。
彼女の人生は彼の登場により一変する。
この機を逃さぬよう、彼女は。
幸せになることに、決めた。
■完結しました! 現在はルビ振りを調整中です!
■第14回恋愛小説大賞99位でした! 応援ありがとうございました!
■感想や御要望などお気軽にどうぞ!
■エールやいいねも励みになります!
■こちらの他にいくつか話を書いてますのでよろしければ、登録コンテンツから是非に。
※一部サブタイトルが文字化けで表示されているのは演出上の仕様です。お使いの端末、表示されているページは正常です。

愛する旦那様が妻(わたし)の嫁ぎ先を探しています。でも、離縁なんてしてあげません。
秘密 (秘翠ミツキ)
恋愛
【清い関係のまま結婚して十年……彼は私を別の男へと引き渡す】
幼い頃、大国の国王へ献上品として連れて来られリゼット。だが余りに幼く扱いに困った国王は末の弟のクロヴィスに下賜した。その為、王弟クロヴィスと結婚をする事になったリゼット。歳の差が9歳とあり、旦那のクロヴィスとは夫婦と言うよりは歳の離れた仲の良い兄妹の様に過ごして来た。
そんな中、結婚から10年が経ちリゼットが15歳という結婚適齢期に差し掛かると、クロヴィスはリゼットの嫁ぎ先を探し始めた。すると社交界は、その噂で持ちきりとなり必然的にリゼットの耳にも入る事となった。噂を聞いたリゼットはショックを受ける。
クロヴィスはリゼットの幸せの為だと話すが、リゼットは大好きなクロヴィスと離れたくなくて……。

【完結】婚約破棄された令嬢の毒はいかがでしょうか
まさかの
恋愛
皇太子の未来の王妃だったカナリアは突如として、父親の罪によって婚約破棄をされてしまった。
己の命が助かる方法は、友好国の悪評のある第二王子と婚約すること。
カナリアはその提案をのんだが、最初の夜会で毒を盛られてしまった。
誰も味方がいない状況で心がすり減っていくが、婚約者のシリウスだけは他の者たちとは違った。
ある時、シリウスの悪評の原因に気付いたカナリアの手でシリウスは穏やかな性格を取り戻したのだった。
シリウスはカナリアへ愛を囁き、カナリアもまた少しずつ彼の愛を受け入れていく。
そんな時に、義姉のヒルダがカナリアへ多くの嫌がらせを行い、女の戦いが始まる。
嫁いできただけの女と甘く見ている者たちに分からせよう。
カナリア・ノートメアシュトラーセがどんな女かを──。
小説家になろう、エブリスタ、アルファポリス、カクヨムで投稿しています。

今宵、薔薇の園で
天海月
恋愛
早世した母の代わりに妹たちの世話に励み、婚期を逃しかけていた伯爵家の長女・シャーロットは、これが最後のチャンスだと思い、唐突に持ち込まれた気の進まない婚約話を承諾する。
しかし、一か月も経たないうちに、その話は先方からの一方的な申し出によって破談になってしまう。
彼女は藁にもすがる思いで、幼馴染の公爵アルバート・グレアムに相談を持ち掛けるが、新たな婚約者候補として紹介されたのは彼の弟のキースだった。
キースは長年、シャーロットに思いを寄せていたが、遠慮して距離を縮めることが出来ないでいた。
そんな弟を見かねた兄が一計を図ったのだった。
彼女はキースのことを弟のようにしか思っていなかったが、次第に彼の情熱に絆されていく・・・。
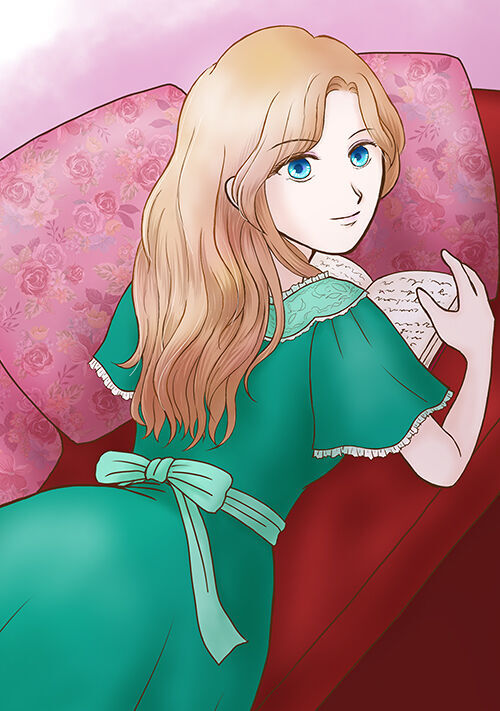
ゲームには参加しません! ―悪役を回避して無事逃れたと思ったのに―
冬野月子
恋愛
侯爵令嬢クリスティナは、ここが前世で遊んだ学園ゲームの世界だと気づいた。そして自分がヒロインのライバルで悪役となる立場だと。
のんびり暮らしたいクリスティナはゲームとは関わらないことに決めた。設定通りに王太子の婚約者にはなってしまったけれど、ゲームを回避して婚約も解消。平穏な生活を手に入れたと思っていた。
けれど何故か義弟から求婚され、元婚約者もアプローチしてきて、さらに……。
※小説家になろう・カクヨムにも投稿しています。

婚約者を妹に譲ったら、婚約者の兄に溺愛された
みみぢあん
恋愛
結婚式がまじかに迫ったジュリーは、幼馴染の婚約者ジョナサンと妹が裏庭で抱き合う姿を目撃する。 それがきっかけで婚約は解消され、妹と元婚約者が結婚することとなった。 落ち込むジュリーのもとへ元婚約者の兄、ファゼリー伯爵エドガーが謝罪をしに訪れた。 もう1人の幼馴染と再会し、ジュリーは子供の頃の初恋を思い出す。
大人になった2人は……

P.S. 推し活に夢中ですので、返信は不要ですわ
汐瀬うに
恋愛
アルカナ学院に通う伯爵令嬢クラリスは、幼い頃から婚約者である第一王子アルベルトと共に過ごしてきた。しかし彼は言葉を尽くさず、想いはすれ違っていく。噂、距離、役割に心を閉ざしながらも、クラリスは自分の居場所を見つけて前へ進む。迎えたプロムの夜、ようやく言葉を選び、追いかけてきたアルベルトが告げたのは――遅すぎる本心だった。
※こちらの作品はカクヨム・アルファポリス・小説家になろうに並行掲載しています。

愛する人は、貴方だけ
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
下町で暮らすケイトは母と二人暮らし。ところが母は病に倒れ、ついに亡くなってしまう。亡くなる直前に母はケイトの父親がアークライト公爵だと告白した。
天涯孤独になったケイトの元にアークライト公爵家から使者がやって来て、ケイトは公爵家に引き取られた。
公爵家には三歳年上のブライアンがいた。跡継ぎがいないため遠縁から引き取られたというブライアン。彼はケイトに冷たい態度を取る。
平民上がりゆえに令嬢たちからは無視されているがケイトは気にしない。最初は冷たかったブライアン、第二王子アーサー、公爵令嬢ミレーヌ、幼馴染カイルとの交友を深めていく。
やがて戦争の足音が聞こえ、若者の青春を奪っていく。ケイトも無関係ではいられなかった……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















