5 / 7
5.熱に浮かされた本音
しおりを挟む
「リネー、良く働いているな。お前もようやく役に立つ時が来た」
いつものように屋敷を訪ねて来た父親を部屋へと通す。
いつもなら部屋に入るなり宝飾品を機嫌よく物色し始めるのに、今日はまっすぐに窓の側に立つリネーの元へと歩いてきた。
「これを、お前に」
美しい小瓶だった。少量の液体が入っている。
「無味無臭の毒だそうだ。飲めばすぐに死に至る。暴れたり、叫んだりする暇もないくらいすぐに死ぬ」
「………………アルベルトは、すでに貴族界で信用を失っています。なぜそこまで執着するのです。そのままにしておいてもいずれ……」
「私が気に食わないんだ。気に食わない、私が取り入るはずだった隣国の伯爵家に気に入られているのも、貴族院の重鎮に目を掛けられて未だに守られているのも。王室もそうだ、これだけの証拠を出して、それでも態度を保留にしている。今後の処分については未定だという」
「……アルベルトのせいじゃない」
「目障りだ。領地を経営して大人しくしていればいいものを、今後貴族の金の流れを監督し、商売も取引相手の身元を明らかにするための監督をするなんて提言をされたらたまったもんじゃない。なぁ、お前も良く知っているだろう。貴族っていうのは大変なんだ。そんな綺麗ごとだけじゃやっていけない」
アルベルトの仕事をよく知りはしなかったが、あの清廉潔白な男は、正面切って貴族に喧嘩を売ったらしい。
利権にがんじがらめの貴族からすれば、金の流れと物の流れを明らかにし、疎明せよ等と言われて応じることなどできないだろう。事実、彼らは禁止されている賄賂も受け入れているし、それが暗黙の了解になっている。賄賂を積めば積むほど取引を続けて貰えるのだ。
「………………ですが、っ……」
何か、父親を止める術がないかと、考えを巡らせる。指先が冷えていた。握らされた小瓶が異様に冷たい。
「はは、情でも移ったか。リネー、わかっているだろう。実行しなければ、お前がどうなるか」
父親が帰った後、いつものようにいくつもの宝飾品が持ち帰られたショーケースを見て、リネーは終わりのない道を歩いているかのような気持ちになった。
例えば、じゃあこの小瓶の中身を、アルベルトに飲ませて、目の前で死ぬアルベルトを見て、得られるものはなんだろう。事態が動いた時にラニは少し離れた町の修道院へと移り住んで、リネーの側を離れてしまった。いずれ結婚相手が見つかった時の為の花嫁修業だと言って、抵抗したラニを無理矢理に連れて行ってもらった。
アルベルトがいなくなって、ラニももう側にいなければ、リネーのもとに残るものは何だろうか。
「こうするのも久しぶりですね」
「……ああ」
アルベルトの部屋を訪ねて、夜の茶会をしないかと誘いをかけたのは始めてだった。
珍しく目元に隈の残るアルベルトの顔を見て、一つ、息を吸う。ラニがいないのでマグヌスに茶器の手配を頼んで、二人でティールームへと向かった。以前はよく通っていたのに、アルベルトが自宅謹慎になってからはここへ来ることは無かった。美しい茶器が用意されて、紅茶が注がれるとマグヌスは部屋から出て行った。
ここで茶会をする時はいつも二人きりになる。そうして欲しいとアルベルトが言いつけてあるからだ。
「早くこの事態が落ち着いてくれるといいんですが」
「…………王室からはまだ何も言われていないのか」
「ええ、まだ特に何も」
父親の言う通り、あれから随分と時間が経っている。それでもまだ王室からの処分が通達されていないのは、通例よりも時間が掛かっているように思えた。
「……父上から、お前が、……その、反対されるような事を言ったと聞いた。父上も心配していたが、大丈夫なのか」
勿論心配などしていなかったが、それは言葉の綾だ。
「反対されるようなこと? ああ、監督機関を置く話ですか。ええ、しましたね。諸外国を見ても、監督機関が無いのはうちの国だけなんですよ。だから商売が拡がらない。過去からの利権と、金を持った人間だけが儲かる仕組みでは、国民が豊かにならないでしょう?」
いつもと違って、一瞬鋭い目をしたアルベルトの言葉に驚く。
「…………それは、」
「いいんです。俺はそれほど身分が高いわけでもないので、言いたい事言ったってそのうち若造のやる事だと許してもらえますよ」
(…………許してもらえるだろうか)
少なくとも、リネーの父親は許さない。許さないから、今、リネーの手元にあの小瓶があるのだ。
「……お前のしてることが間違っているとは思わない。でも、どうか慎重に、……お前を許してくれるばかりじゃないだろう、世間は」
「はは、手厳しい。肝に銘じておきますよ」
「私は……できればお前に、……幸せに生きて欲しい」
胸が熱い。火照って、熱があるようだった。ポケットの小瓶が重たく感じる。
「……リネー? どうしたんですか」
(…………俺は、お前が死ぬところを見たくないし、もうあの父親に支配される人生を生きるのにも疲れた)
何がきっかけだっただろうか。今まで溜めて来たものが一気に溢れたかのようだった。
(疲れた、本当に……)
何かを願うのも、何かを期待するのも、いつか、誰か、もしかしたら救ってくれるのかもしれないと、心の片隅に残していた期待を持っていることに疲れてしまった。
「リネー」
ぼろり、とこぼれた涙をアルベルトがそっと指先で救う。
きっとアルベルトはリネーを救う存在ではない。
いつか誰かに殺されるか、それかリネーに殺されるかだ。今になってようやくわかった。ずっと期待していたのだ。いつか、アルベルトが、リネーを救ってくれるかもしれないと、期待していた自分に気が付いてしまった。リネーだけを見て、リネーをこの環境から救いだして、父親の手の届かないところで、ずっと平和にぬくぬく暮らしたかったのだ。
(それが俺の望むもの)
けれどきっと、これから貴族社会にメスを入れたいのだと言うアルベルトの側でそれは叶わない。
父親の手はアルベルトの側にいても伸びてくるし、リネーの人生はすでにもう罪で染まってしまっている。平穏な、ぬくぬくと、何の心配もせずに生きていけるような人生など、もう叶わないのだとわかって途端に糸が切れたかのように涙が止まらなくなってしまった。
アルベルトの指先が、こぼれる涙を拭って、それから頬を撫でて、耳に触れて、それから首筋へとゆっくり動いていく。
首筋にたどり着いた指先が、少し長く首筋に触れて、それからアルベルトの掌が首筋を撫でた。
「…………リネー、薬は持っていますか?」
「……?」
尋ねられた言葉の意味がわからずに、首をかしげると、アルベルトが考え込むような表情になる。眉根を寄せて、じっくりとリネーを観察するような目つきは初めてみたものだった。
随分と長い間考え込んでいるアルベルトを同じように見つめ返す。
「……はぁ、まぁ、もう仕方ないか」
心なしかアルベルトの耳が赤くて、それから、額に汗をかいているように見えた。
「…………アル? 熱でも……」
「熱があるのは貴方ですよ、リネー。……しばらくヒートは来てないって言ってましたね。部屋に行きましょう」
(あ……これ、ヒートか……)
どうりでひどく感傷的で感情的だと思った、と、自覚した途端に熱が上がったのを感じる。こうなってしまえばもうどうしようもない。もっと早くに気が付けていれば薬の服用で、多少マシにもなっていたかもしれないが、もうこのくらい熱がある状態では今からいつもの薬を服用しても効かないだろう。アルベルトに凭れ掛かるように言われて、首に腕を回して体重を寄せると、そのまま抱えるようにして持ち上げられた。
「タイミングが悪い……いや、良かったのか?」
独り言のように話すアルベルトの声が近い。アルベルトの身体も随分と熱くなっていて、いい匂いがする。ヒートの時に側にアルファがいたことがないせいで知らなかったが、どうやらアルファの匂いで発情開始からピークを迎えるまでが各段に早まるらしい。いつもなら熱がじわじわ出て数日かけてピークを迎えるはずの発情が、今すでに限界一歩手前くらいまで来ている。アルファの匂いも、身体を支えられる体温も、何もかもが気持ちがいい。
アルベルトの匂いが充満した私室へと連れて行かれて、本格的にピークを迎えたらしいヒートのせいで何も考えられなくなる。
いつも私室を訪ねてもこんなにアルベルト匂いがすると感じたことはなかったので、ヒートでフェロモンを嗅ぎ取る嗅覚が鋭くなっているのだろうという推測くらいはまだできたが、覆いかぶさって来るアルベルトの動きが何をしようとしているのかがわからずに、ただ触れてくる手を目でうろうろと追ってしまう。
「リネー、最初にした約束の通り、貴方の最初のヒートが来たので番にします」
いいですね? と首を傾げられたので、つられるようにして頷く。つがいに、と言われてふいに頭に『今更?』という言葉が浮かんだが、それほど嫌だと思うことでもなかったし、アルベルトがそうしたいのなら身をゆだねてもいいと思って目を閉じる。
「…………俺の番にしたからには、貴方は俺のものですからね」
熱に浮かれて、目を閉じていても耳元で心臓が血液を送る音が聴こえてくる。どく、どく、どくと流れる音の側で、掠れて消えそうな声で言われた言葉は夢に浮かされたような言葉だった。
「っ、ァ」
誰かと肌を触れ合わせるのも、溺れるくらいに口づけられるのも経験がなくて呼吸が乱れてしまう。
はぁ、はぁ、と荒い呼吸で肩を揺らしていると、息が整うまでの間は額、瞳、こめかみ、耳に順番に口づけされて、気が休まる暇が無い。
「……、っ、アル……もう、」
「もうちょっと、慣らしましょう……はぁ、俺もきつい」
顎を伝う汗を拭って、髪をかき上げたアルベルトは近くの水差しから水をグラスに注いで、一気に飲み干した。そういえば喉が渇いたかもしれない、と思っていると、少しだけ身体を起こすのを手伝ってくれてグラスを渡された。冷えた水が喉を通っていくのが気持ちいい。随分と喉を使って声を出していたのか、水が流れると少しだけ喉が痛んだ。
「大丈夫ですか?」
「ん……」
とてもじゃないが顔を上げられない。何度か性器を擦られて達したおかげで、少しだけ冷静になれていた。一糸まとわぬ姿で、今までそんな恋人のように触れ合った事もなかったのに、ヒートで何も考えられずにただセックスを強請る姿を見せてしまってどんな顔をしていいかもわからない。
盗み見たアルベルトはいつもは柔和な笑みを浮かべているのに、いつもとは違う表情を浮かべていた。互いに体温も上がっていて、汗もかいている。肌も紅潮しているのにも関わらず、どこか冷静で、冷えた表情をしているように見える。確かにアルベルトの性器は昂っていて、今すぐにでもリネーを求めているのがわかるのに、そこには体の昂りとは別の感情があるように思えた。
「ひ……! あッ……、んん、……」
ヒートのおかげですっかり濡れた後孔は何の抵抗もなくアルベルトの指を飲み込んでいく。
はぁ、と一つ熱い息が耳元で聞こえた、その音にも身体が震えてしまう。もう挿入したって受け入れられるだろうくらいには解れているにも関わらず、思いのほかアルベルトは慎重だった。後孔を解しながら、身体の隅々を触れられる。胸の飾りも触れられて、舐められて、そんなところで快感を拾うこともなかったのに、いつから自分の身体はこんなにも淫らになってしまったのだろうか。
いつものヒートであれば薬を飲んで、熱が出て、多少布団にもぐって熱を発散すれば収まっていたのに、今は何度性器を擦られて達しても熱が収まらない。
濡れた後孔がアルファの熱い性器を受け入れられるのを、今か今かと待ち望んで悦んでいるのを感じてしまう。
「……リネー」
挿れますね、と言われた頃には熱に浮かされすぎて正常な判断などできなくなっていた。
後ろから押し潰されるように体重を掛けられて、質量のあるペニスが体内に押し込まれていく。物を受け入れた事のないはずの後孔が、まるでそれを飲みこむ事を知っていたかのように奥へ奥へと飲み込んでいく。リネーの意に反して腹の奥まで飲み込んだペニスが、突き当りにぶつかってようやくその動きを止めた。
後ろから首筋を撫でられて、あまりに熱い指先の感触にぞわぞわと快感が背筋を駆けあがる。呼吸がままならないリネーの為に、少しだけ待ってくれているのだろう。アルベルトは止まっているはずなのに、リネーの胎内が更に飲み込もう、飲み込もうと勝手に動くせいで余計にじれったい。
「っ、は……リネー、噛みます」
首筋を舐められて、腰を更に強く押し付けられて、無意識に身体が逃げそうになったのを押さえつけられて、アルベルトの歯が首筋へと当てられる。オメガであるせいで、ずっと晒す事のなかった首筋が無防備にも晒されて、歯が立てられている事に単純に恐怖を覚えた。オメガと判明してから誰にも触れさせてなかった場所だ。
リネーの身体が固まったことに気が付いたのか、一瞬、アルベルトから躊躇した気配を感じたが、次の瞬間には痛みと共に、凄まじい快感が体内を駆け巡った。
「あ、ぁ゛ッ―――――!」
そこから先は記憶がない。ただひたすらに気持ちが良くて、身体を乱暴に揺すぶられて、食べる事も飲むことも忘れて発情していた。
途中介護のようにアルベルトに食事を与えられたりもしていたが、熱に浮かされたリネーは随分と性に奔放にアルベルトの性を強請っていた。それだけは覚えている。
数日の酷いヒートを経験して、目が覚めたら隣にアルベルトが眠っていた。
声を出そうとしたら、声がかすれて出なかった。喉も痛い気がする。身体の節々も痛い。少し体を起こそうとしただけで、腰が痛い。汚れていたはずのシーツは交換されて、身体に残る汚れも拭われていた。それすらもアルベルトにすべて任せていたのだから、本当にこのオメガという性は厄介だ。人間としての生活もままならなくさせてしまう。
ここまで酷いのは初めてだったが、とてもじゃないがこれが続くなら耐えられない。
「…………まだ、熱い」
手を頬に当てると、まだ熱が引いていなかった。あんなにも熱を発散させたのにとも思うが、あと少しヒートが抜けるには時間がかかるのだろう。
けれどこの程度であれば薬に頼って散らす事も出来そうだった。ふとベッドサイドのテーブルを見れば水差しと果実、それからヒートの薬に、隣にはリネーが服のポケットに入れていた小瓶が置かれていた。リネーの服のポケットに入れていたものだが、汗をかいたし、洗濯にでも回されたときに、中に入っていた物を取り出してくれたのだろう。
隣で眠るアルベルトの表情はあどけない。普段見ている柔和な笑みとも、セックスの時の冷ややかな表情とも違う。
(…………何だかスッキリしたな)
セックスをする前の、あのどこにも行けない、どうやっても自分の願いが叶わないと知った絶望の感情はきっとヒートの時のフェロモンの乱れによる不安定さだったのだろう。
けれど、あの感情の揺らぎがあったからこそ、自分の本心に気が付いてしまった。
誰かを信頼しながら、寄り添いながら、穏やかに暮らしたいだけなのだ。それをアルベルトに期待していた。父親の言いなりの生活から救い出してくれないかと願っていた。けれど、たぶん、アルベルトにはアルベルトの願いがあるのだ。そしてそこにはきっと、リネーを救うことなど入っていない。
国民を豊かにすることを、この国を繁栄させることを願っている男の側で、こんなにも些細な望みしか持てない自分は相応しくない。
アルベルトがアルファで良かった。アルファであれば、番が消失しても、影響はさほどないと聞く。オメガはアルファがいなくなれば生きていけないけれど。
そっと、小瓶を手にして、蓋を開けてみる。瓶のフチに鼻を近づけて匂いを嗅いでみるが、父親が言った通り無味無臭の代物だった。これを飲めば一息に死ねるのだと言う。
数日前に、疲れた、と思ったのは、ヒートの熱に浮かされた故の考えだったけれど、けれどそれでもやはり、今、リネーの心情に一番近いのはそれだ。疲れてしまった。どう頑張っていいのかもわからない、どうしていいのかもわからない。けれどもう父親に従うのは嫌だった。
(だって、アルベルトは死ぬには勿体ない)
きっと、アルベルトを殺せば、次のターゲットを示されるに違いない。いつまで経ってもリネーがあの男から解放される事は無い。
それがわかってしまった。
いや、本当はもうずっと前から気が付いていた。
ただ、弱いフリをして、誰かに助けて貰えるのを期待していただけだったのだ。
手にした液体を飲み干すだけで、もう何もかもから解放されるのだと思うとそれはどうにもリネーには眩しいものに見えた。
「飲むんですか?」
口をつけようか、どうしようか、と迷いながら、口元へ少しだけ小瓶を近づけたところで、手にしていた小瓶を取り上げられた。アルベルトだ。ここには二人しかいないのだから、当たり前だ。リネーでなければ、その小瓶を持っているのはアルベルトの他にいない。
「……薬です」
「では俺が飲みましょう、数日置きっぱなしだったので悪くなっていないか試します」
そう言って、止める暇もなくアルベルトが小瓶の中身を傾ける。
まるでスローモーションで動いているかのようにゆっくりと、アルベルトが液体を飲もうとする姿が目に焼き付いた。
脳から信号を送る前に、唇が小瓶に着きそうになるのを見て、反射的に小瓶をアルベルトの手から叩き落した。ぱしゃり、と液体がシーツへと沁み込んでいく。
「っ、っ……! は……! な、にを…………‼」
心臓がうるさかった。
目の前が真っ白になった。
慌ててアルベルトの口元を確かめる。一口飲んだら即死する液体だと言っていた。
それならば少しでも体に付着していたのなら、すぐにでも洗い流さなければいけない。両手でアルベルトの顔を引き寄せて、じっくりと見聞する。手で口元を触って、濡れている個所がないかを確かめる。
「の、飲み込んでないか……⁈ 口に入ってないか‼⁉」
「…………薬なのでは?」
「……っ、」
薬だ、と咄嗟についた嘘を思えば、このリネーの反応は明らかにおかしかった。
リネーを落ち着かせるように背中をポンポンと叩かれた。思った以上に近い距離になってしまっていたことを思い出して、少しだけ身体を引こうとしたのに、逆に腰を掴まれて引き寄せられてしまった。胸元にアルベルトが顔を埋めてくる。
「リネー、大丈夫」
大丈夫だと言われて、何が大丈夫かもわからないのに、肩の力が抜けてしまった。
「………………あれは、お前を殺すための毒だった。……私の父親が用意をした、それを、私が……」
それ以上が言葉にできなくて、そっと目を閉じると、腰に回されていた腕に更に力が込められた。
「貴方が俺を殺したかった?」
「っ、そんなわけ……」
「ああ、それなら良かった」
何が良かったというのだろう。あと一歩、何かが違っていれば、アルベルトの飲み物には毒薬が入れられていた。
それくらい、アルベルトはリネーに気を許していたし、リネーもアルベルトに許されている自負があった。あと一歩だったのだ。
「……お前の、他国との密通も私が捏造した書類が原因だ。私を王室に突き出せばいい、証言をする。マリアンヌ嬢との不貞の噂も……私が……」
「すべて貴方が悪かった?」
「………………そう、……そうだ」
父親に逆らえなかったのは、リネーの心の弱さのせいだ。父親に見捨てられれば生きていけなくなる。けれど、何もかもをさらけ出してしまった今、おそらく相応の罰が下るのだろう。今回の件は最悪お家取り潰し、爵位のはく奪になれば、父親がいてももはやリネーは生きていけない。
(ああ、でも犯罪者となれば貴族の牢には入れるかもしれない。住む場所くらいはあるか)
北の僻地にある、貴族の犯罪者を幽閉しておく城がある。そこで一生を過ごすのかもしれない。だとしてももはやどうでもいい。
「…………アルベルト、すまなかった」
リネーの父親が罪に問われれば、多少はアルベルトの望む未来を叶えやすくなるだろうか。
アルベルトの身体に跨って、抱えられている。いつもより上の目線からアルベルトを見下ろすのは新鮮な心地だ。淡いサファイアの瞳は、まるで何もかも見据えたかのような美しさだった。
「はぁ、まぁ、じゃあ惚れた弱みと言う事で、許しますよ。リネー」
「え、ン」
言われた言葉の意味がわからなくて、その意図を尋ねようと開いた口を唇で塞がれた。
目の前のアルベルトが目を閉じて、それからゆっくりと目を開く。息を触れ合わせて、もう一度キスをされて、そのまま後ろへと押し倒された。指先で、首の後ろを撫でられる。今はガーゼが当てられているそこにはしっかりとアルベルトの歯型がある。触れられるだけで、まだ身体に燻る性感がくすぐられて、ぞわぞわと背筋が震えてしまう。
「……ここ、噛んだからには、リネーは俺のものでいいんですよね?」
「………………なに、を」
「貴方が俺のものになるからには、ちゃんと守ります」
安心してください、と言いながら額にキスを落とすアルベルトは、いつもとは雰囲気が違った。抱かれている時に見せたような冷えた表情に、少しだけ口元が笑っていて、機嫌は悪くなさそうだが。
「守るって……」
「とにかくまずはヒートが終わるのを待ちましょう。今日からは薬を飲んで、それから俺がいいと言うまでこの部屋から出ないで」
いつものように屋敷を訪ねて来た父親を部屋へと通す。
いつもなら部屋に入るなり宝飾品を機嫌よく物色し始めるのに、今日はまっすぐに窓の側に立つリネーの元へと歩いてきた。
「これを、お前に」
美しい小瓶だった。少量の液体が入っている。
「無味無臭の毒だそうだ。飲めばすぐに死に至る。暴れたり、叫んだりする暇もないくらいすぐに死ぬ」
「………………アルベルトは、すでに貴族界で信用を失っています。なぜそこまで執着するのです。そのままにしておいてもいずれ……」
「私が気に食わないんだ。気に食わない、私が取り入るはずだった隣国の伯爵家に気に入られているのも、貴族院の重鎮に目を掛けられて未だに守られているのも。王室もそうだ、これだけの証拠を出して、それでも態度を保留にしている。今後の処分については未定だという」
「……アルベルトのせいじゃない」
「目障りだ。領地を経営して大人しくしていればいいものを、今後貴族の金の流れを監督し、商売も取引相手の身元を明らかにするための監督をするなんて提言をされたらたまったもんじゃない。なぁ、お前も良く知っているだろう。貴族っていうのは大変なんだ。そんな綺麗ごとだけじゃやっていけない」
アルベルトの仕事をよく知りはしなかったが、あの清廉潔白な男は、正面切って貴族に喧嘩を売ったらしい。
利権にがんじがらめの貴族からすれば、金の流れと物の流れを明らかにし、疎明せよ等と言われて応じることなどできないだろう。事実、彼らは禁止されている賄賂も受け入れているし、それが暗黙の了解になっている。賄賂を積めば積むほど取引を続けて貰えるのだ。
「………………ですが、っ……」
何か、父親を止める術がないかと、考えを巡らせる。指先が冷えていた。握らされた小瓶が異様に冷たい。
「はは、情でも移ったか。リネー、わかっているだろう。実行しなければ、お前がどうなるか」
父親が帰った後、いつものようにいくつもの宝飾品が持ち帰られたショーケースを見て、リネーは終わりのない道を歩いているかのような気持ちになった。
例えば、じゃあこの小瓶の中身を、アルベルトに飲ませて、目の前で死ぬアルベルトを見て、得られるものはなんだろう。事態が動いた時にラニは少し離れた町の修道院へと移り住んで、リネーの側を離れてしまった。いずれ結婚相手が見つかった時の為の花嫁修業だと言って、抵抗したラニを無理矢理に連れて行ってもらった。
アルベルトがいなくなって、ラニももう側にいなければ、リネーのもとに残るものは何だろうか。
「こうするのも久しぶりですね」
「……ああ」
アルベルトの部屋を訪ねて、夜の茶会をしないかと誘いをかけたのは始めてだった。
珍しく目元に隈の残るアルベルトの顔を見て、一つ、息を吸う。ラニがいないのでマグヌスに茶器の手配を頼んで、二人でティールームへと向かった。以前はよく通っていたのに、アルベルトが自宅謹慎になってからはここへ来ることは無かった。美しい茶器が用意されて、紅茶が注がれるとマグヌスは部屋から出て行った。
ここで茶会をする時はいつも二人きりになる。そうして欲しいとアルベルトが言いつけてあるからだ。
「早くこの事態が落ち着いてくれるといいんですが」
「…………王室からはまだ何も言われていないのか」
「ええ、まだ特に何も」
父親の言う通り、あれから随分と時間が経っている。それでもまだ王室からの処分が通達されていないのは、通例よりも時間が掛かっているように思えた。
「……父上から、お前が、……その、反対されるような事を言ったと聞いた。父上も心配していたが、大丈夫なのか」
勿論心配などしていなかったが、それは言葉の綾だ。
「反対されるようなこと? ああ、監督機関を置く話ですか。ええ、しましたね。諸外国を見ても、監督機関が無いのはうちの国だけなんですよ。だから商売が拡がらない。過去からの利権と、金を持った人間だけが儲かる仕組みでは、国民が豊かにならないでしょう?」
いつもと違って、一瞬鋭い目をしたアルベルトの言葉に驚く。
「…………それは、」
「いいんです。俺はそれほど身分が高いわけでもないので、言いたい事言ったってそのうち若造のやる事だと許してもらえますよ」
(…………許してもらえるだろうか)
少なくとも、リネーの父親は許さない。許さないから、今、リネーの手元にあの小瓶があるのだ。
「……お前のしてることが間違っているとは思わない。でも、どうか慎重に、……お前を許してくれるばかりじゃないだろう、世間は」
「はは、手厳しい。肝に銘じておきますよ」
「私は……できればお前に、……幸せに生きて欲しい」
胸が熱い。火照って、熱があるようだった。ポケットの小瓶が重たく感じる。
「……リネー? どうしたんですか」
(…………俺は、お前が死ぬところを見たくないし、もうあの父親に支配される人生を生きるのにも疲れた)
何がきっかけだっただろうか。今まで溜めて来たものが一気に溢れたかのようだった。
(疲れた、本当に……)
何かを願うのも、何かを期待するのも、いつか、誰か、もしかしたら救ってくれるのかもしれないと、心の片隅に残していた期待を持っていることに疲れてしまった。
「リネー」
ぼろり、とこぼれた涙をアルベルトがそっと指先で救う。
きっとアルベルトはリネーを救う存在ではない。
いつか誰かに殺されるか、それかリネーに殺されるかだ。今になってようやくわかった。ずっと期待していたのだ。いつか、アルベルトが、リネーを救ってくれるかもしれないと、期待していた自分に気が付いてしまった。リネーだけを見て、リネーをこの環境から救いだして、父親の手の届かないところで、ずっと平和にぬくぬく暮らしたかったのだ。
(それが俺の望むもの)
けれどきっと、これから貴族社会にメスを入れたいのだと言うアルベルトの側でそれは叶わない。
父親の手はアルベルトの側にいても伸びてくるし、リネーの人生はすでにもう罪で染まってしまっている。平穏な、ぬくぬくと、何の心配もせずに生きていけるような人生など、もう叶わないのだとわかって途端に糸が切れたかのように涙が止まらなくなってしまった。
アルベルトの指先が、こぼれる涙を拭って、それから頬を撫でて、耳に触れて、それから首筋へとゆっくり動いていく。
首筋にたどり着いた指先が、少し長く首筋に触れて、それからアルベルトの掌が首筋を撫でた。
「…………リネー、薬は持っていますか?」
「……?」
尋ねられた言葉の意味がわからずに、首をかしげると、アルベルトが考え込むような表情になる。眉根を寄せて、じっくりとリネーを観察するような目つきは初めてみたものだった。
随分と長い間考え込んでいるアルベルトを同じように見つめ返す。
「……はぁ、まぁ、もう仕方ないか」
心なしかアルベルトの耳が赤くて、それから、額に汗をかいているように見えた。
「…………アル? 熱でも……」
「熱があるのは貴方ですよ、リネー。……しばらくヒートは来てないって言ってましたね。部屋に行きましょう」
(あ……これ、ヒートか……)
どうりでひどく感傷的で感情的だと思った、と、自覚した途端に熱が上がったのを感じる。こうなってしまえばもうどうしようもない。もっと早くに気が付けていれば薬の服用で、多少マシにもなっていたかもしれないが、もうこのくらい熱がある状態では今からいつもの薬を服用しても効かないだろう。アルベルトに凭れ掛かるように言われて、首に腕を回して体重を寄せると、そのまま抱えるようにして持ち上げられた。
「タイミングが悪い……いや、良かったのか?」
独り言のように話すアルベルトの声が近い。アルベルトの身体も随分と熱くなっていて、いい匂いがする。ヒートの時に側にアルファがいたことがないせいで知らなかったが、どうやらアルファの匂いで発情開始からピークを迎えるまでが各段に早まるらしい。いつもなら熱がじわじわ出て数日かけてピークを迎えるはずの発情が、今すでに限界一歩手前くらいまで来ている。アルファの匂いも、身体を支えられる体温も、何もかもが気持ちがいい。
アルベルトの匂いが充満した私室へと連れて行かれて、本格的にピークを迎えたらしいヒートのせいで何も考えられなくなる。
いつも私室を訪ねてもこんなにアルベルト匂いがすると感じたことはなかったので、ヒートでフェロモンを嗅ぎ取る嗅覚が鋭くなっているのだろうという推測くらいはまだできたが、覆いかぶさって来るアルベルトの動きが何をしようとしているのかがわからずに、ただ触れてくる手を目でうろうろと追ってしまう。
「リネー、最初にした約束の通り、貴方の最初のヒートが来たので番にします」
いいですね? と首を傾げられたので、つられるようにして頷く。つがいに、と言われてふいに頭に『今更?』という言葉が浮かんだが、それほど嫌だと思うことでもなかったし、アルベルトがそうしたいのなら身をゆだねてもいいと思って目を閉じる。
「…………俺の番にしたからには、貴方は俺のものですからね」
熱に浮かれて、目を閉じていても耳元で心臓が血液を送る音が聴こえてくる。どく、どく、どくと流れる音の側で、掠れて消えそうな声で言われた言葉は夢に浮かされたような言葉だった。
「っ、ァ」
誰かと肌を触れ合わせるのも、溺れるくらいに口づけられるのも経験がなくて呼吸が乱れてしまう。
はぁ、はぁ、と荒い呼吸で肩を揺らしていると、息が整うまでの間は額、瞳、こめかみ、耳に順番に口づけされて、気が休まる暇が無い。
「……、っ、アル……もう、」
「もうちょっと、慣らしましょう……はぁ、俺もきつい」
顎を伝う汗を拭って、髪をかき上げたアルベルトは近くの水差しから水をグラスに注いで、一気に飲み干した。そういえば喉が渇いたかもしれない、と思っていると、少しだけ身体を起こすのを手伝ってくれてグラスを渡された。冷えた水が喉を通っていくのが気持ちいい。随分と喉を使って声を出していたのか、水が流れると少しだけ喉が痛んだ。
「大丈夫ですか?」
「ん……」
とてもじゃないが顔を上げられない。何度か性器を擦られて達したおかげで、少しだけ冷静になれていた。一糸まとわぬ姿で、今までそんな恋人のように触れ合った事もなかったのに、ヒートで何も考えられずにただセックスを強請る姿を見せてしまってどんな顔をしていいかもわからない。
盗み見たアルベルトはいつもは柔和な笑みを浮かべているのに、いつもとは違う表情を浮かべていた。互いに体温も上がっていて、汗もかいている。肌も紅潮しているのにも関わらず、どこか冷静で、冷えた表情をしているように見える。確かにアルベルトの性器は昂っていて、今すぐにでもリネーを求めているのがわかるのに、そこには体の昂りとは別の感情があるように思えた。
「ひ……! あッ……、んん、……」
ヒートのおかげですっかり濡れた後孔は何の抵抗もなくアルベルトの指を飲み込んでいく。
はぁ、と一つ熱い息が耳元で聞こえた、その音にも身体が震えてしまう。もう挿入したって受け入れられるだろうくらいには解れているにも関わらず、思いのほかアルベルトは慎重だった。後孔を解しながら、身体の隅々を触れられる。胸の飾りも触れられて、舐められて、そんなところで快感を拾うこともなかったのに、いつから自分の身体はこんなにも淫らになってしまったのだろうか。
いつものヒートであれば薬を飲んで、熱が出て、多少布団にもぐって熱を発散すれば収まっていたのに、今は何度性器を擦られて達しても熱が収まらない。
濡れた後孔がアルファの熱い性器を受け入れられるのを、今か今かと待ち望んで悦んでいるのを感じてしまう。
「……リネー」
挿れますね、と言われた頃には熱に浮かされすぎて正常な判断などできなくなっていた。
後ろから押し潰されるように体重を掛けられて、質量のあるペニスが体内に押し込まれていく。物を受け入れた事のないはずの後孔が、まるでそれを飲みこむ事を知っていたかのように奥へ奥へと飲み込んでいく。リネーの意に反して腹の奥まで飲み込んだペニスが、突き当りにぶつかってようやくその動きを止めた。
後ろから首筋を撫でられて、あまりに熱い指先の感触にぞわぞわと快感が背筋を駆けあがる。呼吸がままならないリネーの為に、少しだけ待ってくれているのだろう。アルベルトは止まっているはずなのに、リネーの胎内が更に飲み込もう、飲み込もうと勝手に動くせいで余計にじれったい。
「っ、は……リネー、噛みます」
首筋を舐められて、腰を更に強く押し付けられて、無意識に身体が逃げそうになったのを押さえつけられて、アルベルトの歯が首筋へと当てられる。オメガであるせいで、ずっと晒す事のなかった首筋が無防備にも晒されて、歯が立てられている事に単純に恐怖を覚えた。オメガと判明してから誰にも触れさせてなかった場所だ。
リネーの身体が固まったことに気が付いたのか、一瞬、アルベルトから躊躇した気配を感じたが、次の瞬間には痛みと共に、凄まじい快感が体内を駆け巡った。
「あ、ぁ゛ッ―――――!」
そこから先は記憶がない。ただひたすらに気持ちが良くて、身体を乱暴に揺すぶられて、食べる事も飲むことも忘れて発情していた。
途中介護のようにアルベルトに食事を与えられたりもしていたが、熱に浮かされたリネーは随分と性に奔放にアルベルトの性を強請っていた。それだけは覚えている。
数日の酷いヒートを経験して、目が覚めたら隣にアルベルトが眠っていた。
声を出そうとしたら、声がかすれて出なかった。喉も痛い気がする。身体の節々も痛い。少し体を起こそうとしただけで、腰が痛い。汚れていたはずのシーツは交換されて、身体に残る汚れも拭われていた。それすらもアルベルトにすべて任せていたのだから、本当にこのオメガという性は厄介だ。人間としての生活もままならなくさせてしまう。
ここまで酷いのは初めてだったが、とてもじゃないがこれが続くなら耐えられない。
「…………まだ、熱い」
手を頬に当てると、まだ熱が引いていなかった。あんなにも熱を発散させたのにとも思うが、あと少しヒートが抜けるには時間がかかるのだろう。
けれどこの程度であれば薬に頼って散らす事も出来そうだった。ふとベッドサイドのテーブルを見れば水差しと果実、それからヒートの薬に、隣にはリネーが服のポケットに入れていた小瓶が置かれていた。リネーの服のポケットに入れていたものだが、汗をかいたし、洗濯にでも回されたときに、中に入っていた物を取り出してくれたのだろう。
隣で眠るアルベルトの表情はあどけない。普段見ている柔和な笑みとも、セックスの時の冷ややかな表情とも違う。
(…………何だかスッキリしたな)
セックスをする前の、あのどこにも行けない、どうやっても自分の願いが叶わないと知った絶望の感情はきっとヒートの時のフェロモンの乱れによる不安定さだったのだろう。
けれど、あの感情の揺らぎがあったからこそ、自分の本心に気が付いてしまった。
誰かを信頼しながら、寄り添いながら、穏やかに暮らしたいだけなのだ。それをアルベルトに期待していた。父親の言いなりの生活から救い出してくれないかと願っていた。けれど、たぶん、アルベルトにはアルベルトの願いがあるのだ。そしてそこにはきっと、リネーを救うことなど入っていない。
国民を豊かにすることを、この国を繁栄させることを願っている男の側で、こんなにも些細な望みしか持てない自分は相応しくない。
アルベルトがアルファで良かった。アルファであれば、番が消失しても、影響はさほどないと聞く。オメガはアルファがいなくなれば生きていけないけれど。
そっと、小瓶を手にして、蓋を開けてみる。瓶のフチに鼻を近づけて匂いを嗅いでみるが、父親が言った通り無味無臭の代物だった。これを飲めば一息に死ねるのだと言う。
数日前に、疲れた、と思ったのは、ヒートの熱に浮かされた故の考えだったけれど、けれどそれでもやはり、今、リネーの心情に一番近いのはそれだ。疲れてしまった。どう頑張っていいのかもわからない、どうしていいのかもわからない。けれどもう父親に従うのは嫌だった。
(だって、アルベルトは死ぬには勿体ない)
きっと、アルベルトを殺せば、次のターゲットを示されるに違いない。いつまで経ってもリネーがあの男から解放される事は無い。
それがわかってしまった。
いや、本当はもうずっと前から気が付いていた。
ただ、弱いフリをして、誰かに助けて貰えるのを期待していただけだったのだ。
手にした液体を飲み干すだけで、もう何もかもから解放されるのだと思うとそれはどうにもリネーには眩しいものに見えた。
「飲むんですか?」
口をつけようか、どうしようか、と迷いながら、口元へ少しだけ小瓶を近づけたところで、手にしていた小瓶を取り上げられた。アルベルトだ。ここには二人しかいないのだから、当たり前だ。リネーでなければ、その小瓶を持っているのはアルベルトの他にいない。
「……薬です」
「では俺が飲みましょう、数日置きっぱなしだったので悪くなっていないか試します」
そう言って、止める暇もなくアルベルトが小瓶の中身を傾ける。
まるでスローモーションで動いているかのようにゆっくりと、アルベルトが液体を飲もうとする姿が目に焼き付いた。
脳から信号を送る前に、唇が小瓶に着きそうになるのを見て、反射的に小瓶をアルベルトの手から叩き落した。ぱしゃり、と液体がシーツへと沁み込んでいく。
「っ、っ……! は……! な、にを…………‼」
心臓がうるさかった。
目の前が真っ白になった。
慌ててアルベルトの口元を確かめる。一口飲んだら即死する液体だと言っていた。
それならば少しでも体に付着していたのなら、すぐにでも洗い流さなければいけない。両手でアルベルトの顔を引き寄せて、じっくりと見聞する。手で口元を触って、濡れている個所がないかを確かめる。
「の、飲み込んでないか……⁈ 口に入ってないか‼⁉」
「…………薬なのでは?」
「……っ、」
薬だ、と咄嗟についた嘘を思えば、このリネーの反応は明らかにおかしかった。
リネーを落ち着かせるように背中をポンポンと叩かれた。思った以上に近い距離になってしまっていたことを思い出して、少しだけ身体を引こうとしたのに、逆に腰を掴まれて引き寄せられてしまった。胸元にアルベルトが顔を埋めてくる。
「リネー、大丈夫」
大丈夫だと言われて、何が大丈夫かもわからないのに、肩の力が抜けてしまった。
「………………あれは、お前を殺すための毒だった。……私の父親が用意をした、それを、私が……」
それ以上が言葉にできなくて、そっと目を閉じると、腰に回されていた腕に更に力が込められた。
「貴方が俺を殺したかった?」
「っ、そんなわけ……」
「ああ、それなら良かった」
何が良かったというのだろう。あと一歩、何かが違っていれば、アルベルトの飲み物には毒薬が入れられていた。
それくらい、アルベルトはリネーに気を許していたし、リネーもアルベルトに許されている自負があった。あと一歩だったのだ。
「……お前の、他国との密通も私が捏造した書類が原因だ。私を王室に突き出せばいい、証言をする。マリアンヌ嬢との不貞の噂も……私が……」
「すべて貴方が悪かった?」
「………………そう、……そうだ」
父親に逆らえなかったのは、リネーの心の弱さのせいだ。父親に見捨てられれば生きていけなくなる。けれど、何もかもをさらけ出してしまった今、おそらく相応の罰が下るのだろう。今回の件は最悪お家取り潰し、爵位のはく奪になれば、父親がいてももはやリネーは生きていけない。
(ああ、でも犯罪者となれば貴族の牢には入れるかもしれない。住む場所くらいはあるか)
北の僻地にある、貴族の犯罪者を幽閉しておく城がある。そこで一生を過ごすのかもしれない。だとしてももはやどうでもいい。
「…………アルベルト、すまなかった」
リネーの父親が罪に問われれば、多少はアルベルトの望む未来を叶えやすくなるだろうか。
アルベルトの身体に跨って、抱えられている。いつもより上の目線からアルベルトを見下ろすのは新鮮な心地だ。淡いサファイアの瞳は、まるで何もかも見据えたかのような美しさだった。
「はぁ、まぁ、じゃあ惚れた弱みと言う事で、許しますよ。リネー」
「え、ン」
言われた言葉の意味がわからなくて、その意図を尋ねようと開いた口を唇で塞がれた。
目の前のアルベルトが目を閉じて、それからゆっくりと目を開く。息を触れ合わせて、もう一度キスをされて、そのまま後ろへと押し倒された。指先で、首の後ろを撫でられる。今はガーゼが当てられているそこにはしっかりとアルベルトの歯型がある。触れられるだけで、まだ身体に燻る性感がくすぐられて、ぞわぞわと背筋が震えてしまう。
「……ここ、噛んだからには、リネーは俺のものでいいんですよね?」
「………………なに、を」
「貴方が俺のものになるからには、ちゃんと守ります」
安心してください、と言いながら額にキスを落とすアルベルトは、いつもとは雰囲気が違った。抱かれている時に見せたような冷えた表情に、少しだけ口元が笑っていて、機嫌は悪くなさそうだが。
「守るって……」
「とにかくまずはヒートが終わるのを待ちましょう。今日からは薬を飲んで、それから俺がいいと言うまでこの部屋から出ないで」
99
あなたにおすすめの小説

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

オメガに説く幸福論
葉咲透織
BL
長寿ゆえに子孫問題を後回しにしていたエルフの国へ、オメガの国の第二王子・リッカは弟王子他数名を連れて行く。褐色のエルフである王弟・エドアールに惹かれつつも、彼との結婚を訳あってリッカは望めず……。
ダークエルフの王族×訳アリ平凡オメガ王子の嫁入りBL。
※ブログにもアップしています

孤独の王と後宮の青葉
秋月真鳥
BL
塔に閉じ込められた居場所のない妾腹の王子は、15歳になってもバース性が判明していなかった。美少女のような彼を、父親はオメガと決め付けて遠い異国の後宮に入れる。
異国の王は孤独だった。誰もが彼をアルファと信じているのに、本当はオメガでそのことを明かすことができない。
筋骨隆々としたアルファらしい孤独なオメガの王と、美少女のようなオメガらしいアルファの王子は、互いの孤独を埋め合い、愛し合う。
※ムーンライトノベルズ様にも投稿しています。
※完結まで予約投稿しています。

捨てた筈の恋が追ってきて逃がしてくれない
Q矢(Q.➽)
BL
18歳の愛緒(まなお)は、ある男に出会った瞬間から身も心も奪われるような恋をした。
だがそれはリスクしかない刹那的なもの。
恋の最中に目が覚めてそれに気づいた時、愛緒は最愛の人の前から姿を消した。
それから、7年。
捨てたつもりで、とうに忘れたと思っていたその恋が、再び目の前に現れる。
※不倫表現が苦手な方はご注意ください。
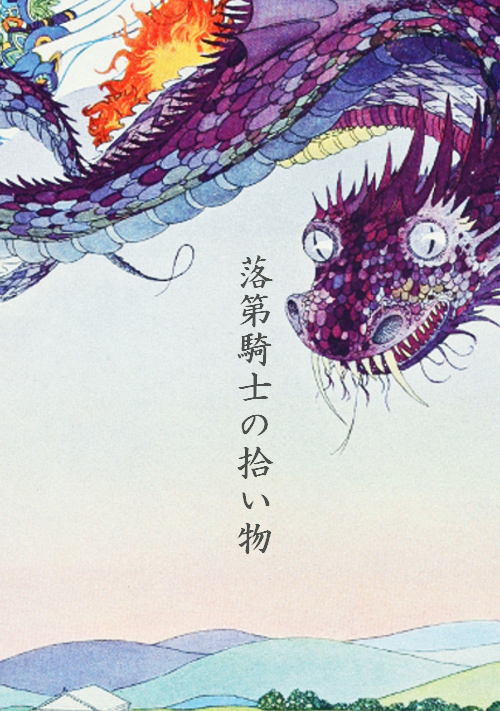
落第騎士の拾い物
深山恐竜
BL
「オメガでございます」
ひと月前、セレガは医者から第三の性別を告知された。将来は勇猛な騎士になることを夢見ていたセレガは、この診断に絶望した。
セレガは絶望の末に”ドラゴンの巣”へ向かう。そこで彼は騎士見習いとして最期の戦いをするつもりであった。しかし、巣にはドラゴンに育てられたという男がいた。男は純粋で、無垢で、彼と交流するうちに、セレガは未来への希望を取り戻す。
ところがある日、発情したセレガは男と関係を持ってしまって……?
オメガバースの設定をお借りしています。
ムーンライトノベルズにも掲載中

悪役令息(Ω)に転生したので、破滅を避けてスローライフを目指します。だけどなぜか最強騎士団長(α)の運命の番に認定され、溺愛ルートに突入!
水凪しおん
BL
貧乏男爵家の三男リヒトには秘密があった。
それは、自分が乙女ゲームの「悪役令息」であり、現代日本から転生してきたという記憶だ。
家は没落寸前、自身の立場は断罪エンドへまっしぐら。
そんな破滅フラグを回避するため、前世の知識を活かして領地改革に奮闘するリヒトだったが、彼が生まれ持った「Ω」という性は、否応なく運命の渦へと彼を巻き込んでいく。
ある夜会で出会ったのは、氷のように冷徹で、王国最強と謳われる騎士団長のカイ。
誰もが恐れるαの彼に、なぜかリヒトは興味を持たれてしまう。
「関わってはいけない」――そう思えば思うほど、抗いがたいフェロモンと、カイの不器用な優しさがリヒトの心を揺さぶる。
これは、運命に翻弄される悪役令息が、最強騎士団長の激重な愛に包まれ、やがて国をも動かす存在へと成り上がっていく、甘くて刺激的な溺愛ラブストーリー。

【完結】愛されたかった僕の人生
Kanade
BL
✯オメガバース
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。
今日も《夫》は帰らない。
《夫》には僕以外の『番』がいる。
ねぇ、どうしてなの?
一目惚れだって言ったじゃない。
愛してるって言ってくれたじゃないか。
ねぇ、僕はもう要らないの…?
独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。

オメガ公子とアルファ王子の初恋婚姻譚
須宮りんこ
BL
ノアメット公国の公子であるユーリアスは、二十三歳のオメガだ。大寒波に襲われ、復興の途にある祖国のためにシャムスバハル王国のアルファ王子・アディムと政略結婚をする。
この結婚に気持ちはいらないとアディムに宣言するユーリアスだが、あるときアディムの初恋の相手が自分であることを知る。子どもっぽいところがありつつも、単身シャムスバハルへと嫁いだ自分を気遣ってくれるアディム。そんな夫にユーリアスは徐々に惹かれていくが――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















