20 / 112
20話~古代遺跡~
しおりを挟む
~古代遺跡~
༺ ༒ ༻
遠くでラッパが高らかに鳴り響き、同時にデュボアの号令がオアシスに響き渡る。
「休憩は終わりだ。全員、集合せよ!」
ほんの束の間、外套に身を包み、三人で横になっただけのはずだった。いつの間にか眠りに落ちていたらしい。瞼を持ち上げると、すぐ目の前、本当に拳一個分の距離にアルチュールの顔があり、思わず息をのむ。至近距離で視線がぶつかり、お互いに一拍遅れて赤くなった。
慌てて姿勢を正すと、背後でナタンも欠伸混じりに上体を起こした。眠そうな目をこすりながらも、すぐに状況を察したのか、何も言わずにきびきびと支度を始めたかと思うと、「セレスさま、またあとで」といって駆け出して行った。だが、疾走訓練の疲れがまだ残っているのか、最初の数歩は足取りがふらついて見えた。それでも必死に踏ん張り、やがて小走りに遠ざかっていく。
風の班の集合場所はここから一番遠いが、流石、勤勉実直、時間厳守な元侍従だ。頭の良さとこういうところだけは尊敬する――ヘンタイだけど。
騎士たちが次々に声を掛け合い、馬を立ち上がらせ集結の準備に入っていく。
「行くか」
アルチュールが腰を上げると、自然な動作で手を差し伸べてきた。
同じ体格の同性相手に、よくもまあ、まるで淑女や姫君にするような振る舞いが出来るものだと、呆れるやら感心するやら。
……いや、待てよ。身長は同じだか同じ体格……ではない。体格はむしろ彼の方が勝っている。厚い胸板、全体的に締まった筋肉のつき方。
俺というか、セレスタンはどうにも筋肉がつきにくい質らしい。
はかなさを削ぎ落とされたリシャール殿下、意外に鍛えられているナタン、均整のとれた筋肉を持つアルチュールと並べば、多分――と曖昧にしておきたいところだが、確実に俺はこの中で一番華奢な部類に入るだろう。
ヤバいな……。
なにがヤバいかは言いたくないが、これは、いわゆるヤバい。
俺の好きなシチュの中で、俺は今「右」の立ち位置に居ることになってしまう。
「……もう自分で立てる」
小さく首を振り、俺は自力で砂を払って身を起こし外套を羽織り直した。
ほんのわずか、アルチュールが不服そうに唇を引き結ぶ。何か言いたげな視線を寄こしてきたが、結局口にはせず、そのまま共に歩き出した。
やがて、それぞれの担当騎士のもとへ向かうため、俺とアルチュールは一度、足を止めた。
その瞬間――、
「セレス」俺の腕を掴み呼び止めたアルチュールは、いつになく真剣だった。「……気を付けてくれよ」
念を押すように言うと、アルチュールは腰に下げた革袋から一本の組紐を差し出してきた。
淡い銀糸と深い青が織り込まれた細工の細やかな紐が、光を受け、さりげなく艶やかに輝く。
「これは……?」
戸惑う俺に、アルチュールはわずかに視線を逸らしながら言った。
「今、セレスが使ってる、その髪紐と交換してくれ」
「え?」
思わず聞き返す。
「いつも剣術の稽古のときも、授業で体を動かすときも、セレスは髪を縛っているだろう。……だから」
落ち着いているのに、どこか強引さと照れが入り混じった声だった。
俺は困惑し、苦笑いを浮かべる。
「いや……それ、どう見ても俺のより高そうだろ。もったいないって」
高そうだとか、もったいないだとか、公爵家嫡男がもっぱら口にしそうにない台詞だな……と思いつつ、ごまかすようにそう言ったが、アルチュールは一歩も引かない。
観念した俺は、髪をほどいて自分の紐を外し、彼に渡した。
そして差し出された組紐で髪を結び直す。触れると、絹糸のように滑らかな感触が心地いい。
横目で見ると、アルチュールもまた俺が渡した紐を手に、自分の髪を結んでいた。
彼の指先で扱われると、ただの紐が大事な品のように見えるのだから不思議だ。
「今から、この髪紐を、俺のタリスマンにする」
アルチュールが小さく呟く。
思わず笑いそうになったが、俺も答える。
「じゃあ、俺も、アルチュールからもらったこの髪紐をタリスマンにするか」
互いに結び終えると、一瞬だけ視線がぶつかる。
「セレス、……乗馬の訓練、がんばれよ」
アルチュールが短く言った。
「ちょっと、自分が上手いからと偉そうに」
俺も返す。
言葉は少ないのに、不思議と胸の奥に温かさが残った。
「じゃあ、またあとで。……砦で」
背を向ける直前、アルチュールが少しだけ名残惜しそうに微笑んだ。
「ああ」
俺も頷き、ほんのわずか遅れて歩き出した。
ルクレールのもとへ向かうと、彼は既に手綱を握って待っていた。鋭い眼差しをこちらに向け、短く問いかける。
「少しは休めたか?」
「まあな」
俺が答えると、彼はふっと笑い、ヴァルカリオンの首を軽く叩いた。
すると、巨体の駿馬は鼻先を俺の肩に軽く押し付けてくる。小さいとはいえ額に角があるので注意しながらそっと撫でると、短く鼻を鳴らして受け入れてくれた。
その様子を見て、ルクレールが低く呟く。
「初対面の相手に、騎獣ヴァルカリオンがこうも心を許すとは……珍しい……」ルクレールは短く息を吐き、目を細めた。「この種を初めて乗りこなしたのは、始祖だと伝えられている。比較的大人しい個体同士を掛け合わせ、丈夫で従順な在来の馬の種も入れ改良が重ねられて、人を乗せても暴れない今の姿になったが、昔は近付くだけで拒み、荒野の幻獣と恐れられていた」
「ああ、知っている。現在も野生のヴァルカリオンは怖ろしいし、角はもう少し大きい」
そこで一拍置き、ルクレールは魔法布の眼帯で覆っていないほうの片眼で意味ありげに俺を見た。
「――始祖が光の力を帯びていたため、惹かれて従ったのだといわれているが……、こいつも無意識に応じているのかもしれないな」
ヴァルカリオンはさらに甘えるように俺の胸元に顔を押し付けてきた。
大きな瞳が潤んで見えて、思わず両手でその顔を抱き込むように撫でてやる。温かくて、やわらかな毛並みに指先が沈む。鼻をすり寄せる仕草が、こんな巨体なのに驚くほど愛らしい。
「……すごくかわいいな」
思わず声が漏れた。
顔を埋めるように撫でながら、ふと問いかける。
「この子は、あんたの馬なのか?」
問いかけられたルクレールは、一瞬だけ言葉を失ったように俺を見つめた。まるで、馬ではなく俺の方に意識を奪われていたかのように――何とも言い難い表情を浮かべ、ようやく口を開く。
「……ああ……、いや、違う、俺の馬じゃない。俺のは赤毛のヴァルカリオンだ。……会いたいか?」
「赤……?」
問い返した俺を見て、ルクレールは微かに目を細めた。
「俺の赤髪と同じ色合いだ。爆走させると、たてがみが風を裂いて燃え立つように揺れ、まるで炎を撒き散らしながら走るような光景になる。火焔の幻獣と見紛うほどにな」
少し興味は惹かれた。だが、ここで素直に「会ってみたい」と答えるのはなんだか癪にさわる。わざわざこの男の思惑どおりに動かされるようで、口の端まで出かかった言葉を飲み込み、曖昧に黙り込んだ。
ルクレールは穏やかに口角を上げ、手綱を捌きながら言った。
「セレス。お前を俺の愛馬のもとへ連れて行ってやるぞ」
「殿下も……一緒なら……」
条件のように答えると、彼の眼差しが愉快そう弧を描く。
「駄目だ。そうだ、なんなら今度、お前を攫ってでも行こうか」
囁かれた言葉は、物騒な響きを含んでいるのに妙に艶やかだった。
「……あんたが言うと、笑えない。悪い冗談はやめてくれ」
苦笑しながら言い返す俺の横で、ヴァルカリオンは嬉しそうに鼻を鳴らし、今度は頬を押し付けてきた。
「さあ、乗れ。そろそろみんなの準備が整いそうだ」
ルクレールが軽やかに鐙を踏み、鞍に跨る。手綱を握り直しながら、顎で俺を促す。
伸ばされた手を取り、俺もヴァルカリオンの背に身を預けた。
すぐ背後から伸びてきたルクレールの腕が、俺の両脇を抜けて手綱を握る。肩越しに感じる息遣いがやけに近く、無意識に背筋が強張った。
デュボアからオアシスを発つ号令がかかり、風・火・水・土――それぞれの属性ごとに騎士団が列を組んでいく。
乾いた砂の地平に、騎士たちが騎獣を操りながら整然と並んだ。
やがて、荒野に静寂が訪れる。
息をひそめるような一瞬の間を置いてラッパの音が轟いた。
その直後――、
「我らは盾!」
響き渡る騎士団の第一声に、砂の大地が震える。
呼応するかのように、ヴァルカリオンがその場で二度、力強く足を踏み鳴らす。
ドッドッ――と、砂を揺らす音が重なり、胸の奥まで響きわたった。
他の騎士たちと共に、ルクレールも叫ぶ。
「我らは矛!」
重なる第二声が荒野を貫いた。
「王国の礎は我らなり!」
三度目の鬨が、一斉に天を突く。
そして最後に、荒野全体を揺るがすような雄叫びが轟いた。
「おおおおおおおーーーッ!」
反響する大音声が、まるで砂漠そのものを震わせるかのように広がっていく。
ルクレールがヴァルカリオンの腹に軽く踵を当てた次の瞬間、巨体が砂を蹴り駆け出した。
視界が一気に開ける。来たとき同様、再び力強い蹄音が荒野に響き渡り、体ごと前へと押し出される感覚に、思わず息をのむ。
背後で低い声が囁いた。
「このまま砦までは駆け足だ。気を引き締めろよ」
「言われなくても……!」
強がって言い返すが、胸の奥は奇妙な高揚感に満たされていた。
しばらくして、ふと風を切る音の中、ナタンの言葉を思い出す。
――あの人、水属性なんですか?
気になって、つい口を開いた。
「なあ」
「ん? どうした?」
「あんたの属性って……何なんだ?」
一拍の沈黙。
「……赤き炎だ」
彼は告げる。答える声は低く抑えられているのに、妙に耳に残った。
「やっぱり、水じゃないのかよ……」
なんとなく、そんな予感はしていた。赤き炎だと? 似合いすぎていて、それもまたむかつく。
「なんだ?」
「なんだじゃねーだろー。だから、この隊は、水属性チームじゃないのか? ここに居る騎士も水属性だろ? なんで居るんだよ!?」
振り返ることはできなかったが、背中越しに笑みを含んだ気配を感じる。
「セレスの担当が、居ないんだから仕方ないだろう」
「あんたのせいでなあーーー!」
堪えきれず、俺は右手で肘鉄を食らわせた。だが、見事に胸甲に当たり、俺の肘に痛みが走る。
「っ……いってぇ!」
「くっ、ははははっ……!」背後でルクレールが盛大に笑い転げる。「セレス、お前はほんと退屈させないな」
からかうようで、どこか楽しげな声音。俺を弄ぶのが心底面白いらしい。
一、無許可、二、俺の担当に何か盛った、三、この隊の所属でもない、その上、四、火の属性。規律違反の役満かよ。呆れて果てて怒る気力も消え失せて行く。
「……で、それはそうと、あんた、さっき殿下と何を話していた?」
長い溜息を吐いたあと、ふいに気になって問いかける。
「どうして俺がここに居るのか、と聞かれた」
ルクレールは軽く肩を揺らし、笑いを引きずったまま答えた。
「……それで、なんて答えたんだ?」
問い返すと、ほんの一瞬、背後の気配が真剣味を帯びる。
耳に落ちた声は、妙に低く、そしてはっきりとしていた。
「セレス、お前に会いに来た」
胸の奥が、強く打ち鳴らされた。
「……はあ?」
「セレスに会いに来た!」
もう一度、今度は高らかに言い放つルクレール。
駄目だ、一瞬で顔が熱い。
同じ方向を向いて並んでいるこの状況が、今ほどありがたく思えたことはない。互いの表情を確かめることもできず、見せることもできない――それだけで救われている気がした。
不意に胸の奥で、別の感覚が芽を出す。
嫌だ。知りたくなかった。
俺は、こいつを嫌ってなんかいない。むしろ――気に入っている。
俺はそれから、沈黙を守った。
色恋沙汰に慣れきった男が、恋愛ごとに経験の乏しい俺の動揺を見抜けないはずがない。きっと、こいつは、今の俺の胸の内を読み取っているはずだ。
掌まで熱い。腹が立つ腹が立つ。だが、何か口にすれば、すべて知られてしまうような気がして……言葉を呑み込むしかなかった。
――やがて、荒野の先に薄暗い森林の縁が見えてくる。樹々の間を進むうちに、木漏れ日が揺らめき、視界が開ける。そして遠くに、陽光に照らされた石造りの砦の影が浮かび上がった。
ロクノール森林、第一研究塔の砦――魔物の住処との境界線に位置する重要拠点。つい最近、カナードが綻びの見えた魔力防壁の補修作業を行った場所だ。
王族の視察も年に数度行われるため、石壁は威厳を放ち、内部も魔法防御を兼ねた堅牢な構造になっている。今回の行程では、騎士たちはもちろん、学院の生徒たちもここに滞在することになる。
中庭でヴァルカリオンから降りると、先に地面に下りていたルクレールが手綱を引き、俺の体を支えてくれた。
その直後、背後からヴァルカリオンが俺の外套の裾を咥えて引っ張り、さらに鼻先で軽く肩を小突いてくる。
また「触れ」とせがんでいるのだろう。
「……本当にかわいいな、お前は」
思わず苦笑し、頬を撫でる。すると、ヴァルカリオンは満足げに短く鼻を鳴らした。
「この子に名前はあるのか?」
「ああ、パイパーだ」
「パイパー……、今日はありがとう。明日もまた世話になる」
言葉を口にした途端、昔、祖母の家にいた犬の姿が脳裏に蘇った。別れ際、よく額に口づけをしてやった。
同じように角に気をつけながら、俺はそっとパイパーの額へ唇を寄せた。
パイパーが目を細めて鼻を鳴らす。懐かしい仕草に、胸の奥がじんわりと温かくなる。
そんなやりとりを横目に見ながら、ルクレールが兜を脱ぐと前髪をかき上げながら距離を詰めてきた。
「かわいいのは、セレスのほうだ」
「……え?」
ルクレールの片腕が俺の腰をさらうように回り込む。半ば抱き上げられる形で体が持ち上がり、驚く間もなく彼の力で位置を移される。
そのまま馬の首筋の近くから腹のあたりへと押しやられ、背中がヴァルカリオンの逞しい胴と密着した。
「っ……おい、何をっ!」
反射的に身をよじろうとするが、逃げ場はない。パイパーが驚くほどの強さではなく、それでいて拒めない加減で、彼の掌が俺を留めていた。
壁ドンならぬ、『馬ドン』か……などと考えていると、間近に迫ったルクレールの影が、低い声とともに覆いかぶさる。
「セレスタン……」
顔が近い。
さらに、ルクレールがわずかに身を傾け、額と額が触れ合った。
熱を帯びた体温が伝わってきて、思考が一瞬止まる。
目を逸らそうにも、彼の視線に捕らえられて逃げられない。
「ルクレールっ、人が居るだろう!」
「やっと名前を呼んでくれたな」
「くそっ、兎に角、離れろっ」
「何のために、わざわざこの広い中庭の隅にヴァルカリオンを止めたと思っている」囁きは低く落ち着いていて、むしろ余裕すら漂わせている。「ここなら、誰にも見られやしない」
その言葉に背筋が震えた。嫌悪からではない、もっと別の熱に突き動かされるような震えだった。
少し離れた場所では、生徒たちが次々と馬から降りている。
オアシスのときと同様、疲労困憊の顔で地面にへたり込む者、ふらつきながら騎士に肩を貸してもらう者が続出していた。寮監と担当騎士が右へ左へと駆け回り、水を飲ませたり、倒れ込んだ生徒を支えたりと慌ただしい。
逃げ場のない距離で、彼の額がまだ俺の額に触れている。熱が伝わるたびに、心臓が喉までせり上がってくるのを抑えられなかった。
「……魔眼の力、を、使うな」
絞り出すように言うと、ルクレールはわずかに片眼を細め、それから大きく見開いた。
「力は使っていない」低い声が耳を打つ。「今こうして震えているなら――それはセレスの本心だ」
胸の奥を見透かされたようで、恥ずかしさと悔しさが入り混じり、耐えきれず目を閉じてしまう。
直後、額に感じていた重なりがふっと離れた。
恐る恐る瞼を持ち上げると、ルクレールは地面に片膝をつき頭を垂れ、俺の右手をそっと取っていた。
「……俺のことも労ってくれ」
真摯な声音に、喉の奥が熱くなる。
「今日は……ありがとう」
そのとき、ルクレールの唇が俺の手の甲に触れる。軽く口づけを落とすと、彼は何事もなかったように立ち上がり、外套の裾を払った。
「指導員と騎士には、狭いが個室が用意されている。……そっちは大部屋だろう? 寝苦しかったら、俺のところに来い」
「よっ、余計、寝れないわっ!」
反射的に言い返すと、ルクレールの口元が愉快そうに緩んだ。
からかい半分なのは分かっている。分かっていても、心臓の鼓動がやけに耳に残るのが悔しい。
༺ ༒ ༻
そのまま騎士と生徒はそれぞれの宿泊棟へと案内された。
属性ごとに割り当てられた広い大部屋で過ごすことになり、俺も脱いだ外套を大雑把に抱えて中に足を踏み入れる。
石造りの壁に沿ってカーテン付きの二段の簡易寝台が並び、縦にスライドする窓にはヴェール・アンシャンテ――魔法で強化された月映石の硝子板――がはめ込まれていた。外気や瘴気を遮断しながら視界を確保できる実用的な造りで、砦では標準装備とされている。
傾きかけた陽がそれを透過し、森の縁を金色に染めながら室内へ穏やかな光を落とす。
腰に下げていた革袋を壁に掛けると、ようやく全身の力が抜けた。身体の節々が痛い。
部屋を見渡したところ、みんな思い思いに寝台へ腰を下ろし、疲れた顔で横になったり、水筒を傾けたりしていた。ただ、何人か姿が見えないことに気付く。救護室に行っているのだろうな……、と想像しながら視線を戻す。
夕飯までは部屋から出てはならないが自由時間だと伝えられており、しばしの間、緊張から解き放たれる。
俺は外套を畳んで枕元に置き、ベッドに大の字になって倒れ込むと深く息を吐いた。
「なあ、セレス、さっきの騎士団の立ち回り、凄かったな!」
上の寝台からひょこりと顔を覗かせ身を乗り出してきたのは、ヴァロンタン・マルセル・ガルニエ――ガーゴイル討伐後、回廊から手を振って来たうちの一人だ。
元気だな、お前。
担当騎士が、馬ドンとかするやつじゃないんだろうな。いや、そんなことをするのは、あの野郎ぐらいか。
俺は今、身体の疲労もそこそこあるが、精神の消耗を痛感している。疲れたよ、パト〇〇シュ……。体も心もぐったりだ。
あっ、そういえばヴァロンタンは、ヴァルカリオンの疾走訓練のあともぴんぴんしていた。なるほど、ガルニエ辺境伯の三男――こいつはアルチュールと同じ、野生児だった。
彼は、俺が返事をするより早く、身振り手振りを交えて続けた。
「馬上でのあの鬨! あんなの、教本じゃ絶対に学べないよな。痺れるだろ!」
「確かに、一体感が凄まじかった」
「でもさ、俺の担当騎士、凄く怖いんだけど」
「いやいや、それがまた『騎士様』って感じだろ」
他の仲間たちも、肩をすくめたり、笑ったりしながら会話に加わっていく。
どこの女子会のトークだよ、これ。
数日前、レオが言っていた。
この課外授業が終わると、けっこうな数の生徒が騎士に手紙を出す。
憧れとか、感謝とか――時には……恋文まで。
聞いていたネージュが、レオの見えない所で、カタカタカタカタと震えていたのは、言うまでもない。
ああ、寝る前にネージュに連絡を入れなければ……。いや、今、彼は自分の推しの部屋に居るから、まあいいか。
にぎやかなやり取りを耳にしながら、俺は腕を額にかざした。
ルクレールのことさえなければ、今ごろ俺は、特大の「ぐふぅ」を心の中で連発していたことだろう。
尊い空間に居るはずなのに、さっきの彼の行動が頭の奥で反芻思考され、どうにも心がざわついて仕方ない。
騎士が跪く元々の意味ぐらい、俺だって知っている。ドメワン原作本編では、アルチュールがリシャールにやった。永遠の忠誠だ。ただ、この物語の中で手に口づけを落とすのは、忠誠を誓い、敬い、愛を誓う、または、乞うときだ――助けて、ネージュパパ。
あ、駄目だ、あいつ震えて泣き出して歓喜して叫ぶだけだよ、この案件。
やがて、廊下に足音が響き、デュラン副官が夕食の時間を告げに来た。各部屋から一斉にざわめきが広がり、生徒たちはそれぞれの属性ごとに食堂へと誘導されていく。
石造りの大食堂は、焚き火のような暖かな灯りに包まれ、すでに運ばれている料理の香りに、空腹を思い出した腹が小さく鳴る。
席は決まっており、隣に座った者と簡単な言葉を交わしながら、差し出されたパンやスープを口に運ぶ。訓練の疲れを忘れたかのように、皆ほっとした表情を浮かべていた。
俺も匙を手に取り、温かな味を喉に流し込みながら、ようやく一息ついた。
食事を終えると、再び各部屋へと戻された。魔物との境界線に位置する砦の特性上、夜間は外出禁止とされており、廊下には安全を確保するため、砦の隊士が見張りとして配置されている。
部屋には簡素ながらもシャワー室と水回りが直結しており、不便は感じない設備だった。
厚い石壁に守られた空間は外の静寂と切り離され、かすかな水音や寝台の軋む音が、妙に際立って聞こえる。疲労と緊張の余韻がまだ残る中で、俺たちはそれぞれの持ち場に落ち着き、次第に部屋全体が安らぎの空気に包まれていった。
寝台へ腰を下ろし、同室の生徒たちがそれぞれ静かな時間を過ごし始めたころ――。
コン、コン。
窓ガラスを叩く小さな音に、思わず肩が跳ねた。外はもうすっかり闇に沈み、森の輪郭がぼんやりと浮かんでいる。その影の中に、見慣れた金の髪が揺れていた。
༺ ༒ ༻
遠くでラッパが高らかに鳴り響き、同時にデュボアの号令がオアシスに響き渡る。
「休憩は終わりだ。全員、集合せよ!」
ほんの束の間、外套に身を包み、三人で横になっただけのはずだった。いつの間にか眠りに落ちていたらしい。瞼を持ち上げると、すぐ目の前、本当に拳一個分の距離にアルチュールの顔があり、思わず息をのむ。至近距離で視線がぶつかり、お互いに一拍遅れて赤くなった。
慌てて姿勢を正すと、背後でナタンも欠伸混じりに上体を起こした。眠そうな目をこすりながらも、すぐに状況を察したのか、何も言わずにきびきびと支度を始めたかと思うと、「セレスさま、またあとで」といって駆け出して行った。だが、疾走訓練の疲れがまだ残っているのか、最初の数歩は足取りがふらついて見えた。それでも必死に踏ん張り、やがて小走りに遠ざかっていく。
風の班の集合場所はここから一番遠いが、流石、勤勉実直、時間厳守な元侍従だ。頭の良さとこういうところだけは尊敬する――ヘンタイだけど。
騎士たちが次々に声を掛け合い、馬を立ち上がらせ集結の準備に入っていく。
「行くか」
アルチュールが腰を上げると、自然な動作で手を差し伸べてきた。
同じ体格の同性相手に、よくもまあ、まるで淑女や姫君にするような振る舞いが出来るものだと、呆れるやら感心するやら。
……いや、待てよ。身長は同じだか同じ体格……ではない。体格はむしろ彼の方が勝っている。厚い胸板、全体的に締まった筋肉のつき方。
俺というか、セレスタンはどうにも筋肉がつきにくい質らしい。
はかなさを削ぎ落とされたリシャール殿下、意外に鍛えられているナタン、均整のとれた筋肉を持つアルチュールと並べば、多分――と曖昧にしておきたいところだが、確実に俺はこの中で一番華奢な部類に入るだろう。
ヤバいな……。
なにがヤバいかは言いたくないが、これは、いわゆるヤバい。
俺の好きなシチュの中で、俺は今「右」の立ち位置に居ることになってしまう。
「……もう自分で立てる」
小さく首を振り、俺は自力で砂を払って身を起こし外套を羽織り直した。
ほんのわずか、アルチュールが不服そうに唇を引き結ぶ。何か言いたげな視線を寄こしてきたが、結局口にはせず、そのまま共に歩き出した。
やがて、それぞれの担当騎士のもとへ向かうため、俺とアルチュールは一度、足を止めた。
その瞬間――、
「セレス」俺の腕を掴み呼び止めたアルチュールは、いつになく真剣だった。「……気を付けてくれよ」
念を押すように言うと、アルチュールは腰に下げた革袋から一本の組紐を差し出してきた。
淡い銀糸と深い青が織り込まれた細工の細やかな紐が、光を受け、さりげなく艶やかに輝く。
「これは……?」
戸惑う俺に、アルチュールはわずかに視線を逸らしながら言った。
「今、セレスが使ってる、その髪紐と交換してくれ」
「え?」
思わず聞き返す。
「いつも剣術の稽古のときも、授業で体を動かすときも、セレスは髪を縛っているだろう。……だから」
落ち着いているのに、どこか強引さと照れが入り混じった声だった。
俺は困惑し、苦笑いを浮かべる。
「いや……それ、どう見ても俺のより高そうだろ。もったいないって」
高そうだとか、もったいないだとか、公爵家嫡男がもっぱら口にしそうにない台詞だな……と思いつつ、ごまかすようにそう言ったが、アルチュールは一歩も引かない。
観念した俺は、髪をほどいて自分の紐を外し、彼に渡した。
そして差し出された組紐で髪を結び直す。触れると、絹糸のように滑らかな感触が心地いい。
横目で見ると、アルチュールもまた俺が渡した紐を手に、自分の髪を結んでいた。
彼の指先で扱われると、ただの紐が大事な品のように見えるのだから不思議だ。
「今から、この髪紐を、俺のタリスマンにする」
アルチュールが小さく呟く。
思わず笑いそうになったが、俺も答える。
「じゃあ、俺も、アルチュールからもらったこの髪紐をタリスマンにするか」
互いに結び終えると、一瞬だけ視線がぶつかる。
「セレス、……乗馬の訓練、がんばれよ」
アルチュールが短く言った。
「ちょっと、自分が上手いからと偉そうに」
俺も返す。
言葉は少ないのに、不思議と胸の奥に温かさが残った。
「じゃあ、またあとで。……砦で」
背を向ける直前、アルチュールが少しだけ名残惜しそうに微笑んだ。
「ああ」
俺も頷き、ほんのわずか遅れて歩き出した。
ルクレールのもとへ向かうと、彼は既に手綱を握って待っていた。鋭い眼差しをこちらに向け、短く問いかける。
「少しは休めたか?」
「まあな」
俺が答えると、彼はふっと笑い、ヴァルカリオンの首を軽く叩いた。
すると、巨体の駿馬は鼻先を俺の肩に軽く押し付けてくる。小さいとはいえ額に角があるので注意しながらそっと撫でると、短く鼻を鳴らして受け入れてくれた。
その様子を見て、ルクレールが低く呟く。
「初対面の相手に、騎獣ヴァルカリオンがこうも心を許すとは……珍しい……」ルクレールは短く息を吐き、目を細めた。「この種を初めて乗りこなしたのは、始祖だと伝えられている。比較的大人しい個体同士を掛け合わせ、丈夫で従順な在来の馬の種も入れ改良が重ねられて、人を乗せても暴れない今の姿になったが、昔は近付くだけで拒み、荒野の幻獣と恐れられていた」
「ああ、知っている。現在も野生のヴァルカリオンは怖ろしいし、角はもう少し大きい」
そこで一拍置き、ルクレールは魔法布の眼帯で覆っていないほうの片眼で意味ありげに俺を見た。
「――始祖が光の力を帯びていたため、惹かれて従ったのだといわれているが……、こいつも無意識に応じているのかもしれないな」
ヴァルカリオンはさらに甘えるように俺の胸元に顔を押し付けてきた。
大きな瞳が潤んで見えて、思わず両手でその顔を抱き込むように撫でてやる。温かくて、やわらかな毛並みに指先が沈む。鼻をすり寄せる仕草が、こんな巨体なのに驚くほど愛らしい。
「……すごくかわいいな」
思わず声が漏れた。
顔を埋めるように撫でながら、ふと問いかける。
「この子は、あんたの馬なのか?」
問いかけられたルクレールは、一瞬だけ言葉を失ったように俺を見つめた。まるで、馬ではなく俺の方に意識を奪われていたかのように――何とも言い難い表情を浮かべ、ようやく口を開く。
「……ああ……、いや、違う、俺の馬じゃない。俺のは赤毛のヴァルカリオンだ。……会いたいか?」
「赤……?」
問い返した俺を見て、ルクレールは微かに目を細めた。
「俺の赤髪と同じ色合いだ。爆走させると、たてがみが風を裂いて燃え立つように揺れ、まるで炎を撒き散らしながら走るような光景になる。火焔の幻獣と見紛うほどにな」
少し興味は惹かれた。だが、ここで素直に「会ってみたい」と答えるのはなんだか癪にさわる。わざわざこの男の思惑どおりに動かされるようで、口の端まで出かかった言葉を飲み込み、曖昧に黙り込んだ。
ルクレールは穏やかに口角を上げ、手綱を捌きながら言った。
「セレス。お前を俺の愛馬のもとへ連れて行ってやるぞ」
「殿下も……一緒なら……」
条件のように答えると、彼の眼差しが愉快そう弧を描く。
「駄目だ。そうだ、なんなら今度、お前を攫ってでも行こうか」
囁かれた言葉は、物騒な響きを含んでいるのに妙に艶やかだった。
「……あんたが言うと、笑えない。悪い冗談はやめてくれ」
苦笑しながら言い返す俺の横で、ヴァルカリオンは嬉しそうに鼻を鳴らし、今度は頬を押し付けてきた。
「さあ、乗れ。そろそろみんなの準備が整いそうだ」
ルクレールが軽やかに鐙を踏み、鞍に跨る。手綱を握り直しながら、顎で俺を促す。
伸ばされた手を取り、俺もヴァルカリオンの背に身を預けた。
すぐ背後から伸びてきたルクレールの腕が、俺の両脇を抜けて手綱を握る。肩越しに感じる息遣いがやけに近く、無意識に背筋が強張った。
デュボアからオアシスを発つ号令がかかり、風・火・水・土――それぞれの属性ごとに騎士団が列を組んでいく。
乾いた砂の地平に、騎士たちが騎獣を操りながら整然と並んだ。
やがて、荒野に静寂が訪れる。
息をひそめるような一瞬の間を置いてラッパの音が轟いた。
その直後――、
「我らは盾!」
響き渡る騎士団の第一声に、砂の大地が震える。
呼応するかのように、ヴァルカリオンがその場で二度、力強く足を踏み鳴らす。
ドッドッ――と、砂を揺らす音が重なり、胸の奥まで響きわたった。
他の騎士たちと共に、ルクレールも叫ぶ。
「我らは矛!」
重なる第二声が荒野を貫いた。
「王国の礎は我らなり!」
三度目の鬨が、一斉に天を突く。
そして最後に、荒野全体を揺るがすような雄叫びが轟いた。
「おおおおおおおーーーッ!」
反響する大音声が、まるで砂漠そのものを震わせるかのように広がっていく。
ルクレールがヴァルカリオンの腹に軽く踵を当てた次の瞬間、巨体が砂を蹴り駆け出した。
視界が一気に開ける。来たとき同様、再び力強い蹄音が荒野に響き渡り、体ごと前へと押し出される感覚に、思わず息をのむ。
背後で低い声が囁いた。
「このまま砦までは駆け足だ。気を引き締めろよ」
「言われなくても……!」
強がって言い返すが、胸の奥は奇妙な高揚感に満たされていた。
しばらくして、ふと風を切る音の中、ナタンの言葉を思い出す。
――あの人、水属性なんですか?
気になって、つい口を開いた。
「なあ」
「ん? どうした?」
「あんたの属性って……何なんだ?」
一拍の沈黙。
「……赤き炎だ」
彼は告げる。答える声は低く抑えられているのに、妙に耳に残った。
「やっぱり、水じゃないのかよ……」
なんとなく、そんな予感はしていた。赤き炎だと? 似合いすぎていて、それもまたむかつく。
「なんだ?」
「なんだじゃねーだろー。だから、この隊は、水属性チームじゃないのか? ここに居る騎士も水属性だろ? なんで居るんだよ!?」
振り返ることはできなかったが、背中越しに笑みを含んだ気配を感じる。
「セレスの担当が、居ないんだから仕方ないだろう」
「あんたのせいでなあーーー!」
堪えきれず、俺は右手で肘鉄を食らわせた。だが、見事に胸甲に当たり、俺の肘に痛みが走る。
「っ……いってぇ!」
「くっ、ははははっ……!」背後でルクレールが盛大に笑い転げる。「セレス、お前はほんと退屈させないな」
からかうようで、どこか楽しげな声音。俺を弄ぶのが心底面白いらしい。
一、無許可、二、俺の担当に何か盛った、三、この隊の所属でもない、その上、四、火の属性。規律違反の役満かよ。呆れて果てて怒る気力も消え失せて行く。
「……で、それはそうと、あんた、さっき殿下と何を話していた?」
長い溜息を吐いたあと、ふいに気になって問いかける。
「どうして俺がここに居るのか、と聞かれた」
ルクレールは軽く肩を揺らし、笑いを引きずったまま答えた。
「……それで、なんて答えたんだ?」
問い返すと、ほんの一瞬、背後の気配が真剣味を帯びる。
耳に落ちた声は、妙に低く、そしてはっきりとしていた。
「セレス、お前に会いに来た」
胸の奥が、強く打ち鳴らされた。
「……はあ?」
「セレスに会いに来た!」
もう一度、今度は高らかに言い放つルクレール。
駄目だ、一瞬で顔が熱い。
同じ方向を向いて並んでいるこの状況が、今ほどありがたく思えたことはない。互いの表情を確かめることもできず、見せることもできない――それだけで救われている気がした。
不意に胸の奥で、別の感覚が芽を出す。
嫌だ。知りたくなかった。
俺は、こいつを嫌ってなんかいない。むしろ――気に入っている。
俺はそれから、沈黙を守った。
色恋沙汰に慣れきった男が、恋愛ごとに経験の乏しい俺の動揺を見抜けないはずがない。きっと、こいつは、今の俺の胸の内を読み取っているはずだ。
掌まで熱い。腹が立つ腹が立つ。だが、何か口にすれば、すべて知られてしまうような気がして……言葉を呑み込むしかなかった。
――やがて、荒野の先に薄暗い森林の縁が見えてくる。樹々の間を進むうちに、木漏れ日が揺らめき、視界が開ける。そして遠くに、陽光に照らされた石造りの砦の影が浮かび上がった。
ロクノール森林、第一研究塔の砦――魔物の住処との境界線に位置する重要拠点。つい最近、カナードが綻びの見えた魔力防壁の補修作業を行った場所だ。
王族の視察も年に数度行われるため、石壁は威厳を放ち、内部も魔法防御を兼ねた堅牢な構造になっている。今回の行程では、騎士たちはもちろん、学院の生徒たちもここに滞在することになる。
中庭でヴァルカリオンから降りると、先に地面に下りていたルクレールが手綱を引き、俺の体を支えてくれた。
その直後、背後からヴァルカリオンが俺の外套の裾を咥えて引っ張り、さらに鼻先で軽く肩を小突いてくる。
また「触れ」とせがんでいるのだろう。
「……本当にかわいいな、お前は」
思わず苦笑し、頬を撫でる。すると、ヴァルカリオンは満足げに短く鼻を鳴らした。
「この子に名前はあるのか?」
「ああ、パイパーだ」
「パイパー……、今日はありがとう。明日もまた世話になる」
言葉を口にした途端、昔、祖母の家にいた犬の姿が脳裏に蘇った。別れ際、よく額に口づけをしてやった。
同じように角に気をつけながら、俺はそっとパイパーの額へ唇を寄せた。
パイパーが目を細めて鼻を鳴らす。懐かしい仕草に、胸の奥がじんわりと温かくなる。
そんなやりとりを横目に見ながら、ルクレールが兜を脱ぐと前髪をかき上げながら距離を詰めてきた。
「かわいいのは、セレスのほうだ」
「……え?」
ルクレールの片腕が俺の腰をさらうように回り込む。半ば抱き上げられる形で体が持ち上がり、驚く間もなく彼の力で位置を移される。
そのまま馬の首筋の近くから腹のあたりへと押しやられ、背中がヴァルカリオンの逞しい胴と密着した。
「っ……おい、何をっ!」
反射的に身をよじろうとするが、逃げ場はない。パイパーが驚くほどの強さではなく、それでいて拒めない加減で、彼の掌が俺を留めていた。
壁ドンならぬ、『馬ドン』か……などと考えていると、間近に迫ったルクレールの影が、低い声とともに覆いかぶさる。
「セレスタン……」
顔が近い。
さらに、ルクレールがわずかに身を傾け、額と額が触れ合った。
熱を帯びた体温が伝わってきて、思考が一瞬止まる。
目を逸らそうにも、彼の視線に捕らえられて逃げられない。
「ルクレールっ、人が居るだろう!」
「やっと名前を呼んでくれたな」
「くそっ、兎に角、離れろっ」
「何のために、わざわざこの広い中庭の隅にヴァルカリオンを止めたと思っている」囁きは低く落ち着いていて、むしろ余裕すら漂わせている。「ここなら、誰にも見られやしない」
その言葉に背筋が震えた。嫌悪からではない、もっと別の熱に突き動かされるような震えだった。
少し離れた場所では、生徒たちが次々と馬から降りている。
オアシスのときと同様、疲労困憊の顔で地面にへたり込む者、ふらつきながら騎士に肩を貸してもらう者が続出していた。寮監と担当騎士が右へ左へと駆け回り、水を飲ませたり、倒れ込んだ生徒を支えたりと慌ただしい。
逃げ場のない距離で、彼の額がまだ俺の額に触れている。熱が伝わるたびに、心臓が喉までせり上がってくるのを抑えられなかった。
「……魔眼の力、を、使うな」
絞り出すように言うと、ルクレールはわずかに片眼を細め、それから大きく見開いた。
「力は使っていない」低い声が耳を打つ。「今こうして震えているなら――それはセレスの本心だ」
胸の奥を見透かされたようで、恥ずかしさと悔しさが入り混じり、耐えきれず目を閉じてしまう。
直後、額に感じていた重なりがふっと離れた。
恐る恐る瞼を持ち上げると、ルクレールは地面に片膝をつき頭を垂れ、俺の右手をそっと取っていた。
「……俺のことも労ってくれ」
真摯な声音に、喉の奥が熱くなる。
「今日は……ありがとう」
そのとき、ルクレールの唇が俺の手の甲に触れる。軽く口づけを落とすと、彼は何事もなかったように立ち上がり、外套の裾を払った。
「指導員と騎士には、狭いが個室が用意されている。……そっちは大部屋だろう? 寝苦しかったら、俺のところに来い」
「よっ、余計、寝れないわっ!」
反射的に言い返すと、ルクレールの口元が愉快そうに緩んだ。
からかい半分なのは分かっている。分かっていても、心臓の鼓動がやけに耳に残るのが悔しい。
༺ ༒ ༻
そのまま騎士と生徒はそれぞれの宿泊棟へと案内された。
属性ごとに割り当てられた広い大部屋で過ごすことになり、俺も脱いだ外套を大雑把に抱えて中に足を踏み入れる。
石造りの壁に沿ってカーテン付きの二段の簡易寝台が並び、縦にスライドする窓にはヴェール・アンシャンテ――魔法で強化された月映石の硝子板――がはめ込まれていた。外気や瘴気を遮断しながら視界を確保できる実用的な造りで、砦では標準装備とされている。
傾きかけた陽がそれを透過し、森の縁を金色に染めながら室内へ穏やかな光を落とす。
腰に下げていた革袋を壁に掛けると、ようやく全身の力が抜けた。身体の節々が痛い。
部屋を見渡したところ、みんな思い思いに寝台へ腰を下ろし、疲れた顔で横になったり、水筒を傾けたりしていた。ただ、何人か姿が見えないことに気付く。救護室に行っているのだろうな……、と想像しながら視線を戻す。
夕飯までは部屋から出てはならないが自由時間だと伝えられており、しばしの間、緊張から解き放たれる。
俺は外套を畳んで枕元に置き、ベッドに大の字になって倒れ込むと深く息を吐いた。
「なあ、セレス、さっきの騎士団の立ち回り、凄かったな!」
上の寝台からひょこりと顔を覗かせ身を乗り出してきたのは、ヴァロンタン・マルセル・ガルニエ――ガーゴイル討伐後、回廊から手を振って来たうちの一人だ。
元気だな、お前。
担当騎士が、馬ドンとかするやつじゃないんだろうな。いや、そんなことをするのは、あの野郎ぐらいか。
俺は今、身体の疲労もそこそこあるが、精神の消耗を痛感している。疲れたよ、パト〇〇シュ……。体も心もぐったりだ。
あっ、そういえばヴァロンタンは、ヴァルカリオンの疾走訓練のあともぴんぴんしていた。なるほど、ガルニエ辺境伯の三男――こいつはアルチュールと同じ、野生児だった。
彼は、俺が返事をするより早く、身振り手振りを交えて続けた。
「馬上でのあの鬨! あんなの、教本じゃ絶対に学べないよな。痺れるだろ!」
「確かに、一体感が凄まじかった」
「でもさ、俺の担当騎士、凄く怖いんだけど」
「いやいや、それがまた『騎士様』って感じだろ」
他の仲間たちも、肩をすくめたり、笑ったりしながら会話に加わっていく。
どこの女子会のトークだよ、これ。
数日前、レオが言っていた。
この課外授業が終わると、けっこうな数の生徒が騎士に手紙を出す。
憧れとか、感謝とか――時には……恋文まで。
聞いていたネージュが、レオの見えない所で、カタカタカタカタと震えていたのは、言うまでもない。
ああ、寝る前にネージュに連絡を入れなければ……。いや、今、彼は自分の推しの部屋に居るから、まあいいか。
にぎやかなやり取りを耳にしながら、俺は腕を額にかざした。
ルクレールのことさえなければ、今ごろ俺は、特大の「ぐふぅ」を心の中で連発していたことだろう。
尊い空間に居るはずなのに、さっきの彼の行動が頭の奥で反芻思考され、どうにも心がざわついて仕方ない。
騎士が跪く元々の意味ぐらい、俺だって知っている。ドメワン原作本編では、アルチュールがリシャールにやった。永遠の忠誠だ。ただ、この物語の中で手に口づけを落とすのは、忠誠を誓い、敬い、愛を誓う、または、乞うときだ――助けて、ネージュパパ。
あ、駄目だ、あいつ震えて泣き出して歓喜して叫ぶだけだよ、この案件。
やがて、廊下に足音が響き、デュラン副官が夕食の時間を告げに来た。各部屋から一斉にざわめきが広がり、生徒たちはそれぞれの属性ごとに食堂へと誘導されていく。
石造りの大食堂は、焚き火のような暖かな灯りに包まれ、すでに運ばれている料理の香りに、空腹を思い出した腹が小さく鳴る。
席は決まっており、隣に座った者と簡単な言葉を交わしながら、差し出されたパンやスープを口に運ぶ。訓練の疲れを忘れたかのように、皆ほっとした表情を浮かべていた。
俺も匙を手に取り、温かな味を喉に流し込みながら、ようやく一息ついた。
食事を終えると、再び各部屋へと戻された。魔物との境界線に位置する砦の特性上、夜間は外出禁止とされており、廊下には安全を確保するため、砦の隊士が見張りとして配置されている。
部屋には簡素ながらもシャワー室と水回りが直結しており、不便は感じない設備だった。
厚い石壁に守られた空間は外の静寂と切り離され、かすかな水音や寝台の軋む音が、妙に際立って聞こえる。疲労と緊張の余韻がまだ残る中で、俺たちはそれぞれの持ち場に落ち着き、次第に部屋全体が安らぎの空気に包まれていった。
寝台へ腰を下ろし、同室の生徒たちがそれぞれ静かな時間を過ごし始めたころ――。
コン、コン。
窓ガラスを叩く小さな音に、思わず肩が跳ねた。外はもうすっかり闇に沈み、森の輪郭がぼんやりと浮かんでいる。その影の中に、見慣れた金の髪が揺れていた。
100
あなたにおすすめの小説

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
-----------------------------------------
0時,6時,12時,18時に2話ずつ更新

悪役令嬢の兄に転生!破滅フラグ回避でスローライフを目指すはずが、氷の騎士に溺愛されてます
水凪しおん
BL
三十代半ばの平凡な会社員だった俺は、ある日、乙女ゲーム『君と紡ぐ光の協奏曲』の世界に転生した。
しかも、最推しの悪役令嬢リリアナの兄、アシェルとして。
このままでは妹は断罪され、一家は没落、俺は処刑される運命だ。
そんな未来は絶対に回避しなくてはならない。
俺の夢は、穏やかなスローライフを送ること。ゲームの知識を駆使して妹を心優しい少女に育て上げ、次々と破滅フラグをへし折っていく。
順調に進むスローライフ計画だったが、関わると面倒な攻略対象、「氷の騎士」サイラスになぜか興味を持たれてしまった。
家庭菜園にまで現れる彼に困惑する俺。
だがそれはやがて、国を揺るがす陰謀と、甘く激しい恋の始まりを告げる序曲に過ぎなかった――。
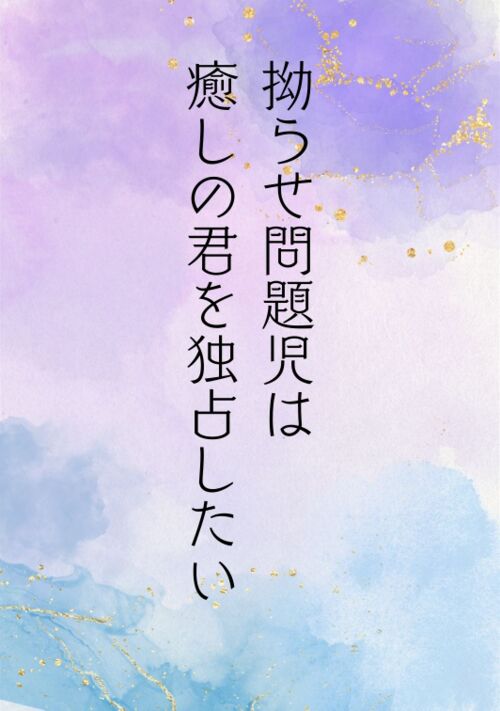
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

悪役キャラに転生したので破滅ルートを死ぬ気で回避しようと思っていたのに、何故か勇者に攻略されそうです
菫城 珪
BL
サッカーの練習試合中、雷に打たれて目が覚めたら人気ゲームに出て来る破滅確約悪役ノアの子供時代になっていた…!
苦労して生きてきた勇者に散々嫌がらせをし、魔王軍の手先となって家族を手に掛け、最後は醜い怪物に変えられ退治されるという最悪の未来だけは絶対回避したい。
付き纏う不安と闘い、いずれ魔王と対峙する為に研鑽に励みつつも同級生である勇者アーサーとは距離を置いてをなるべく避ける日々……だった筈なのになんかどんどん距離が近くなってきてない!?
そんな感じのいずれ勇者となる少年と悪役になる筈だった少年によるBLです。
のんびり連載していきますのでよろしくお願いします!
※小説家になろう、アルファポリス、カクヨムエブリスタ各サイトに掲載中です。

異世界で孵化したので全力で推しを守ります
のぶしげ
BL
ある日、聞いていたシチュエーションCDの世界に転生してしまった主人公。推しの幼少期に出会い、魔王化へのルートを回避して健やかな成長をサポートしよう!と奮闘していく異世界転生BL 執着最強×人外美人BL

すべて、お姉様のせいです
シエル
ファンタジー
私の姉は聖女だ。
我が家はごく普通の男爵家で、特に貧乏でも裕福でもない
まったく特筆すべきことがない家である。
そんな我が家の長女であるアイラが、王立貴族学院へ
入学したことで『特別』になった。
お花畑ヒロインの家族もお花畑なの?
そんなヒロイン体質の姉をもつ、セイカの苦労と涙の物語。
※ 中世ヨーロッパがモデルの架空の世界です。
※ ご都合主義なので、ご了承ください。

悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

ヒロインに婚約破棄された悪役令息
久乃り
BL
ギンデル侯爵子息マルティンは、ウィンステン侯爵令嬢アンテレーゼとの婚約を破棄されて、廃嫡された。ようするに破滅エンドである。
男なのに乙女ゲームの世界に転生したことに気が付いたとき、自分がヒロインに意地悪をしたという理由だけで婚約破棄からの廃嫡平民落ちされ、破滅エンドを迎える悪役令息だと知った。これが悪役令嬢なら、破滅エンドを避けるためにヒロインと仲良くなるか、徹底的にヒロインと関わらないか。本編が始まる前に攻略対象者たちを自分の懐に入れてしまうかして、破滅エンド回避をしたことだろう。だがしかし、困ったことにマルティンは学園編にしか出てこない、当て馬役の悪役令息だったのだ。マルティンがいなくなることでヒロインは自由となり、第2章の社交界編で攻略対象者たちと出会い新たな恋を産むのである。
破滅エンド回避ができないと知ったマルティンは、異世界転生と言ったら冒険者でしょ。ということで、侯爵家の権力を利用して鍛えに鍛えまくり、ついでに侯爵子息として手に入れたお小遣いでチートな装備を用意した。そうして破滅エンドを迎えた途端に国王の前を脱兎のごとく逃げ出して、下町まで走り抜け、冒険者登録をしたのであった。
ソロの冒険者として活動をするマルティンの前になぜだか現れだした攻略対象者たち。特にフィルナンドは伯爵子息であるにも関わらず、なぜだかマルティンに告白してきた。それどころか、マルティンに近づく女を追い払う。さらには攻略対象者たちが冒険者マルティンに指名依頼をしてきたからさあ大変。
方やヒロインであるアンテレーゼは重大なことに気がついた。最短で逆ハールートを攻略するのに重要な攻略対象者フィルナンドが不在なことに。そう、アンテレーゼもマルティンと同じく転生者だったのだ。
慌ててフィルナンドのいる薬師ギルドに押しかけてきたアンテレーゼであったが、マルティン大好きフィルナンドに追い返されてしまう。しかも世間ではマルティンが聖女だと言う噂が飛び交い始めた。
聖女になることが逆ハールートの必須条件なのに、何故男であるマルティンが聖女だと言う噂が流れたのか。不審に思ったアンテレーゼは、今度は教会に乗り込んで行った。
そして教会で、アンテレーゼはとんでもない事実を目の当たりにした。そう、本当にマルティンの周りに攻略対象者たちが群がっていたのだ。しかも、彼らは全員アンテレーゼを敵視してきたのだ。
こんなの乙女ゲームじゃないじゃない!と憤慨するアンテレーゼを置いてきぼりにして、見事マルティンはハーレムエンドを手に入れるのであった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















