43 / 84
4.魔王城の闇医者
11話
しおりを挟む
「にゃあ」
黒猫は、するするとシオンとレヴィアスの横を通り過ぎ、甘えるようにシンシアの足元にすり寄って座りこむ。
不気味な空間に足を震わせながら、シオンは薄目でシンシアの所作を見つめていた。
じゃれつく猫を優しくあやし、風船の紐にくくられた花を、水の入ったグラスに挿す。
昨日シオンたちを襲う一撃を放ったとは思えないほど優しげなその手つきが、シンシアの本質をいっそう見えにくくしていた。
さざなみのように襲う恐怖を確かに感じながら、それでも彼女から目を離すことができない。
圧倒的な魅力と周囲を凍りつかせるような存在感に、シオンはくらりと酔いそうになる。
「……近くに、巨大なモンスターが徘徊した痕跡を見つけた」
レヴィアスがおもむろに口を開く。
そういえば、今朝がた別件で調査に出ると言っていた。
それが、そのモンスターの件だったのだろうか。
「へえ、狼かい?それとも熊?」
くるくると、艶やかな金髪を指先で弄びながら、シンシアはグラスに再びワインを注ぐ。
気付けば血色の薄い彼女の頬には、わずかに朱がさしていた。
「土蜘蛛の痕跡のように見えたが……周囲には木や岩がなぎ倒されたような跡がある」
「ふふふっ、さすがにそれは大げさじゃない? それとも何? ……まさか、『変異』したっていうの?」
さも面白そうな口調から、少しずつ、探るようにシンシアがトーンダウンする。
土蜘蛛は山林の中に比較的多く存在する、とりわけ珍しくはないモンスターだ。
大きいもので体高は二メートルほど。
雑食で、野生動物を狩って食すため、大きな土蜘蛛は人間を襲うこともある。
しかし攻撃手段はその口にぎっしりと生えた牙と、腹部から出す毒や糸が主であり、木や岩をなぎ倒すほどの物理的な強靭さは無い。
……そのはずだった。
「変異の可能性を検討から除外することはできない」
サンドワームの件で、実例が生まれているからだ。
持つはずのない毒、出来るはずのない移動、種本来のポテンシャルを凌駕する、治癒スピード。
『普通に考えれば起こり得ないこと』が、実際に起きたのだから。
シオンは、二人の様子を見つめながらごくりと息を飲む。
あれだけ栄えた港町だが、戦力と言えるのはせいぜい自警団程度だろう。
眼前に広がる海に生息するモンスターたちには、長年船からの砲撃で対抗してきたと聞いた。
しかし、背後の森は比較的植生豊か、かつモンスターの活動も穏やかだった。
今も、危険どころかむしろ恵みを与えてくれる森として捉えられており、言ってしまえば無警戒だ。
レヴィアスが示唆するものが現実であるならば、その被害はどうなってしまうのだろうか。
祭りで賑わう通りや、辺りを走り回る子供たちの顔が思い浮かび、シオンは慌ててレヴィアスの顔を仰ぎ見る。
「魔王城へはもう通達を?」
「ええ」
しかし、実際の変異個体を確認できていない段階でとれる対策は限られる。
いたずらに応援を呼ぶことで、変異の状況によっては被害を拡大させるだけの結果になりかねない、というのが幹部らの判断だった。
「精鋭を数名待機させていますが、私が対象の変異個体を確認できてからの動きとなる想定です」
それではレヴィアスの負担が大きいのではないか。
ふっ、と不安がよぎるが、バルドラッド含め幹部の判断に対してシオンが口出しすることはできない。
頭で理解はしていても、募る心配にシオンの胸はざわめいていた。
当のレヴィアスは飄々とした様子でシンシアと対峙を続けている。
「仮定の段階だが……変異が立て続く理由に心当たりは?」
「残念ながら、無いわね」
「では『何か』の意志が働いている可能性は」
『何か』の意志。
この変異が、突然、偶然に起きたものではなく、誰かが計って引きおこしているのだとしたら。
「あるでしょうね、むしろその方が考えやすいくらい」
シンシアははっきりと言い切る。
その眼は、一切の酔いを感じさせない研究者のものだった。
「……わかったわ、身の振り方を考えるから、少し時間を頂戴」
グラスのワインを、ふたたびあおる。
どこか、やけになっているような雰囲気すら感じさせる飲みっぷりだ。
「正直ね、私は人間も魔物も、この後どうなろうと構わないのよ」
空になったグラスを緩やかに振る。
すこし甘ったるくなったその口調のどこかに、絶望の色が滲んでいる。
「ここでただ眠って過ごしたって構わない。この身が朽ちるその日までね」
シオンの想像をはるかに超える悠久の時を生きてきたのであろう、彼女のその言葉は重かった。
どう頑張っても、人間がその境地に至るのは難しい。
人が生まれ、死に、また生まれる。
それを何度も繰り返していく様を、彼らはどんな視線で眺めていたのだろうか。
何の感情も無い、というかのように振る舞うシンシアの指先は、可憐な紫の花を優しくなでている。
オリヴィエの名を聞いた時の彼女の反応は、『驚き』よりもむしろ『痛み』だったのかもしれない。
(……本当に、オリヴィエさんのことは実験の対象としか見ていなかったの?)
自らの体を抱くように交差された彼女の腕が、まるで痛みを覆い隠すかさぶたのように見えた。
◇
馬に乗って、シオンとレヴィアスは森を駆け下りていた。
変異した土蜘蛛と遭遇した場合には、打って出るつもりなのだろう。
レヴィアスは時折周囲を警戒しながら、馬の手綱を取っていた。
その様子に、いつ起こるかもしれない危機が、じわりと迫ってきているのだということを思い知らされる。
そしてそれは、シンシアとの交渉がより重要性を増している、ということも示していた。
「シンシアさんは、協力してくれるでしょうか……」
「わかりません。ヴァンパイア族は特に気まぐれで、彼女が言っていたように、その長寿ゆえに他者への関心も高くない」
「……でも、私にはシンシアさんがそういう人だとは思えませんでした」
レヴィアスが、一瞬押し黙る。
しばし、馬の蹄が土を蹴る鈍い音が響いた。
「あなたは……どうしても相手を好意的に見ようとしますね」
「う……いけませんか?」
出来るだけ先入観を持たないように、と思って接しているつもりだが、やはりそうなのだろうか。
騙されやすい、だとかちょろい、だとか。
そんなことを何度も言われてきた人生だ。
思い出すと、今でもほろ苦い。
「あなたの美点だと思いますが……誰にでも影の部分はあるでしょう」
「……それは」
言葉に詰まる。
表に見える部分と、そうではない影の部分。
それはきっと地続きになっているものなのだろう。
「レヴィアスさんにも、ありますか?」
風に髪をなびかせながら、シオンは独り言のように呟いた。
蹄の音と風が森を撫でる音が二人を包み、シオンの言葉はどこかに運ばれて消えたようだった。
◇
日が少しずつ沈んでいき、木々が夕日に赤く照らされるころ。
馬はゆるやかに坂道を下り、港町がだんだんと近づいていた。
ふと、シオンは町の入口近くに見知った姿を見つける。
「あれ……?リヴィオさん」
レヴィアスに断りを入れ、ゆっくり歩く馬からよいしょ、と降りる。
こちらに気が付いた様子のリヴィオに、シオンはひらひらと手を振りながら駆け寄った。
「リヴィオさん、お出かけですか?」
「ええ、ちょうどいま薬草を採りにこの辺りをウロウロしていて、店に戻るところですよ」
リヴィオは腕に抱えたかごを傾けて中身を見せてくれる。
すると、ふわりと薬草独特の香りが漂った。
「あ……お連れの方ですね?」
馬を引いてゆっくりと近づいてくるレヴィアスの姿に、リヴィオはペコリと会釈した。
それからこそっとシオンに耳打ちする。
「よかった、恋人さんですよね? 流れに任せてエリオルさんと二人きりにさせてしまったので、ちょっと心配だったんです」
「あっ……あはは、気にしてもらって、ありがとうございます」
変に否定するのも不自然だろうと思い、リヴィオの心遣いに礼を言う。
それから、リヴィオは二人が降りてきた方角を見て首をかしげる。
「それにしても、観光客の方が見て楽しい場所は、森の方には無かったでしょうに」
「えっと、ちょっとお散歩がてら、少しだけ」
確かに、観光スポットらしきものは森の方角に何もない。
ただの散策というには町から距離があるし、リヴィオが不思議に思うのは当然だ。
馬に乗って見たくて、という適当な理由をつけて、シオンは曖昧に微笑んだ。
「そう……ですか」
森の奥にあるシンシアの屋敷のことを、リヴィオは知っているのだろうか。
尋ねたい気持ちもあるが、シンシアの言葉が胸に引っかかる。
――オリヴィエの子供たちだか知らないが、その子らに決して伝えちゃいけないよ――
思い出して、すっとシオンの顔から血の気が引く。
その様子を見たのか、リヴィオが話題を変えるように微笑んだ。
「明日は祭りの最終日ですから、花火が上がりますよ。明日もまだいらっしゃるんですか?」
「ええ、明日はまだいる予定です。花火の話を聞いて私も楽しみにしてたんです」
「よかった。ぜひ楽しんでいってくださいね」
他愛もない話をひとつふたつして、リヴィオは再び会釈をすると町へと戻っていった。
祭りの明りが灯り始め、楽団が演奏する音楽が町の外まで聞こえてくる。
その華やかで軽やかな音楽が、シオンの胸でどこか空回りするように響いていた。
黒猫は、するするとシオンとレヴィアスの横を通り過ぎ、甘えるようにシンシアの足元にすり寄って座りこむ。
不気味な空間に足を震わせながら、シオンは薄目でシンシアの所作を見つめていた。
じゃれつく猫を優しくあやし、風船の紐にくくられた花を、水の入ったグラスに挿す。
昨日シオンたちを襲う一撃を放ったとは思えないほど優しげなその手つきが、シンシアの本質をいっそう見えにくくしていた。
さざなみのように襲う恐怖を確かに感じながら、それでも彼女から目を離すことができない。
圧倒的な魅力と周囲を凍りつかせるような存在感に、シオンはくらりと酔いそうになる。
「……近くに、巨大なモンスターが徘徊した痕跡を見つけた」
レヴィアスがおもむろに口を開く。
そういえば、今朝がた別件で調査に出ると言っていた。
それが、そのモンスターの件だったのだろうか。
「へえ、狼かい?それとも熊?」
くるくると、艶やかな金髪を指先で弄びながら、シンシアはグラスに再びワインを注ぐ。
気付けば血色の薄い彼女の頬には、わずかに朱がさしていた。
「土蜘蛛の痕跡のように見えたが……周囲には木や岩がなぎ倒されたような跡がある」
「ふふふっ、さすがにそれは大げさじゃない? それとも何? ……まさか、『変異』したっていうの?」
さも面白そうな口調から、少しずつ、探るようにシンシアがトーンダウンする。
土蜘蛛は山林の中に比較的多く存在する、とりわけ珍しくはないモンスターだ。
大きいもので体高は二メートルほど。
雑食で、野生動物を狩って食すため、大きな土蜘蛛は人間を襲うこともある。
しかし攻撃手段はその口にぎっしりと生えた牙と、腹部から出す毒や糸が主であり、木や岩をなぎ倒すほどの物理的な強靭さは無い。
……そのはずだった。
「変異の可能性を検討から除外することはできない」
サンドワームの件で、実例が生まれているからだ。
持つはずのない毒、出来るはずのない移動、種本来のポテンシャルを凌駕する、治癒スピード。
『普通に考えれば起こり得ないこと』が、実際に起きたのだから。
シオンは、二人の様子を見つめながらごくりと息を飲む。
あれだけ栄えた港町だが、戦力と言えるのはせいぜい自警団程度だろう。
眼前に広がる海に生息するモンスターたちには、長年船からの砲撃で対抗してきたと聞いた。
しかし、背後の森は比較的植生豊か、かつモンスターの活動も穏やかだった。
今も、危険どころかむしろ恵みを与えてくれる森として捉えられており、言ってしまえば無警戒だ。
レヴィアスが示唆するものが現実であるならば、その被害はどうなってしまうのだろうか。
祭りで賑わう通りや、辺りを走り回る子供たちの顔が思い浮かび、シオンは慌ててレヴィアスの顔を仰ぎ見る。
「魔王城へはもう通達を?」
「ええ」
しかし、実際の変異個体を確認できていない段階でとれる対策は限られる。
いたずらに応援を呼ぶことで、変異の状況によっては被害を拡大させるだけの結果になりかねない、というのが幹部らの判断だった。
「精鋭を数名待機させていますが、私が対象の変異個体を確認できてからの動きとなる想定です」
それではレヴィアスの負担が大きいのではないか。
ふっ、と不安がよぎるが、バルドラッド含め幹部の判断に対してシオンが口出しすることはできない。
頭で理解はしていても、募る心配にシオンの胸はざわめいていた。
当のレヴィアスは飄々とした様子でシンシアと対峙を続けている。
「仮定の段階だが……変異が立て続く理由に心当たりは?」
「残念ながら、無いわね」
「では『何か』の意志が働いている可能性は」
『何か』の意志。
この変異が、突然、偶然に起きたものではなく、誰かが計って引きおこしているのだとしたら。
「あるでしょうね、むしろその方が考えやすいくらい」
シンシアははっきりと言い切る。
その眼は、一切の酔いを感じさせない研究者のものだった。
「……わかったわ、身の振り方を考えるから、少し時間を頂戴」
グラスのワインを、ふたたびあおる。
どこか、やけになっているような雰囲気すら感じさせる飲みっぷりだ。
「正直ね、私は人間も魔物も、この後どうなろうと構わないのよ」
空になったグラスを緩やかに振る。
すこし甘ったるくなったその口調のどこかに、絶望の色が滲んでいる。
「ここでただ眠って過ごしたって構わない。この身が朽ちるその日までね」
シオンの想像をはるかに超える悠久の時を生きてきたのであろう、彼女のその言葉は重かった。
どう頑張っても、人間がその境地に至るのは難しい。
人が生まれ、死に、また生まれる。
それを何度も繰り返していく様を、彼らはどんな視線で眺めていたのだろうか。
何の感情も無い、というかのように振る舞うシンシアの指先は、可憐な紫の花を優しくなでている。
オリヴィエの名を聞いた時の彼女の反応は、『驚き』よりもむしろ『痛み』だったのかもしれない。
(……本当に、オリヴィエさんのことは実験の対象としか見ていなかったの?)
自らの体を抱くように交差された彼女の腕が、まるで痛みを覆い隠すかさぶたのように見えた。
◇
馬に乗って、シオンとレヴィアスは森を駆け下りていた。
変異した土蜘蛛と遭遇した場合には、打って出るつもりなのだろう。
レヴィアスは時折周囲を警戒しながら、馬の手綱を取っていた。
その様子に、いつ起こるかもしれない危機が、じわりと迫ってきているのだということを思い知らされる。
そしてそれは、シンシアとの交渉がより重要性を増している、ということも示していた。
「シンシアさんは、協力してくれるでしょうか……」
「わかりません。ヴァンパイア族は特に気まぐれで、彼女が言っていたように、その長寿ゆえに他者への関心も高くない」
「……でも、私にはシンシアさんがそういう人だとは思えませんでした」
レヴィアスが、一瞬押し黙る。
しばし、馬の蹄が土を蹴る鈍い音が響いた。
「あなたは……どうしても相手を好意的に見ようとしますね」
「う……いけませんか?」
出来るだけ先入観を持たないように、と思って接しているつもりだが、やはりそうなのだろうか。
騙されやすい、だとかちょろい、だとか。
そんなことを何度も言われてきた人生だ。
思い出すと、今でもほろ苦い。
「あなたの美点だと思いますが……誰にでも影の部分はあるでしょう」
「……それは」
言葉に詰まる。
表に見える部分と、そうではない影の部分。
それはきっと地続きになっているものなのだろう。
「レヴィアスさんにも、ありますか?」
風に髪をなびかせながら、シオンは独り言のように呟いた。
蹄の音と風が森を撫でる音が二人を包み、シオンの言葉はどこかに運ばれて消えたようだった。
◇
日が少しずつ沈んでいき、木々が夕日に赤く照らされるころ。
馬はゆるやかに坂道を下り、港町がだんだんと近づいていた。
ふと、シオンは町の入口近くに見知った姿を見つける。
「あれ……?リヴィオさん」
レヴィアスに断りを入れ、ゆっくり歩く馬からよいしょ、と降りる。
こちらに気が付いた様子のリヴィオに、シオンはひらひらと手を振りながら駆け寄った。
「リヴィオさん、お出かけですか?」
「ええ、ちょうどいま薬草を採りにこの辺りをウロウロしていて、店に戻るところですよ」
リヴィオは腕に抱えたかごを傾けて中身を見せてくれる。
すると、ふわりと薬草独特の香りが漂った。
「あ……お連れの方ですね?」
馬を引いてゆっくりと近づいてくるレヴィアスの姿に、リヴィオはペコリと会釈した。
それからこそっとシオンに耳打ちする。
「よかった、恋人さんですよね? 流れに任せてエリオルさんと二人きりにさせてしまったので、ちょっと心配だったんです」
「あっ……あはは、気にしてもらって、ありがとうございます」
変に否定するのも不自然だろうと思い、リヴィオの心遣いに礼を言う。
それから、リヴィオは二人が降りてきた方角を見て首をかしげる。
「それにしても、観光客の方が見て楽しい場所は、森の方には無かったでしょうに」
「えっと、ちょっとお散歩がてら、少しだけ」
確かに、観光スポットらしきものは森の方角に何もない。
ただの散策というには町から距離があるし、リヴィオが不思議に思うのは当然だ。
馬に乗って見たくて、という適当な理由をつけて、シオンは曖昧に微笑んだ。
「そう……ですか」
森の奥にあるシンシアの屋敷のことを、リヴィオは知っているのだろうか。
尋ねたい気持ちもあるが、シンシアの言葉が胸に引っかかる。
――オリヴィエの子供たちだか知らないが、その子らに決して伝えちゃいけないよ――
思い出して、すっとシオンの顔から血の気が引く。
その様子を見たのか、リヴィオが話題を変えるように微笑んだ。
「明日は祭りの最終日ですから、花火が上がりますよ。明日もまだいらっしゃるんですか?」
「ええ、明日はまだいる予定です。花火の話を聞いて私も楽しみにしてたんです」
「よかった。ぜひ楽しんでいってくださいね」
他愛もない話をひとつふたつして、リヴィオは再び会釈をすると町へと戻っていった。
祭りの明りが灯り始め、楽団が演奏する音楽が町の外まで聞こえてくる。
その華やかで軽やかな音楽が、シオンの胸でどこか空回りするように響いていた。
0
あなたにおすすめの小説

凡夫転生〜異世界行ったらあまりにも普通すぎた件〜
小林一咲
ファンタジー
「普通がいちばん」と教え込まれてきた佐藤啓二は、日本の平均寿命である81歳で平凡な一生を終えた。
死因は癌だった。
癌による全死亡者を占める割合は24.6パーセントと第一位である。
そんな彼にも唯一「普通では無いこと」が起きた。
死後の世界へ導かれ、女神の御前にやってくると突然異世界への転生を言い渡される。
それも生前の魂、記憶や未来の可能性すらも次の世界へと引き継ぐと言うのだ。
啓二は前世でもそれなりにアニメや漫画を嗜んでいたが、こんな展開には覚えがない。
挙げ句の果てには「質問は一切受け付けない」と言われる始末で、あれよあれよという間に異世界へと転生を果たしたのだった。
インヒター王国の外、漁業が盛んな街オームで平凡な家庭に産まれ落ちた啓二は『バルト・クラスト』という新しい名を受けた。
そうして、しばらく経った頃に自身の平凡すぎるステータスとおかしなスキルがある事に気がつく――。
これはある平凡すぎる男が異世界へ転生し、その普通で非凡な力で人生を謳歌する物語である。
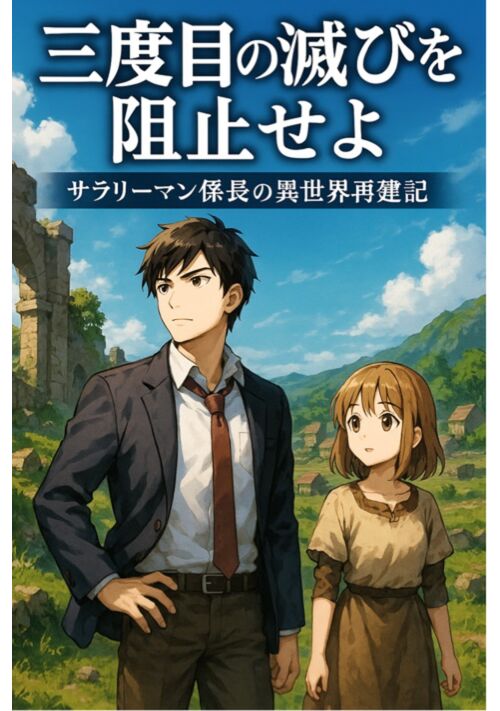
『三度目の滅びを阻止せよ ―サラリーマン係長の異世界再建記―』
KAORUwithAI
ファンタジー
45歳、胃薬が手放せない大手総合商社営業部係長・佐藤悠真。
ある日、横断歩道で子供を助け、トラックに轢かれて死んでしまう。
目を覚ますと、目の前に現れたのは“おじさんっぽい神”。
「この世界を何とかしてほしい」と頼まれるが、悠真は「ただのサラリーマンに何ができる」と拒否。
しかし神は、「ならこの世界は三度目の滅びで終わりだな」と冷徹に突き放す。
結局、悠真は渋々承諾。
与えられたのは“現実知識”と“ワールドサーチ”――地球の知識すら検索できる探索魔法。
さらに肉体は20歳に若返り、滅びかけの異世界に送り込まれた。
衛生観念もなく、食糧も乏しく、二度の滅びで人々は絶望の淵にある。
だが、係長として培った経験と知識を武器に、悠真は人々をまとめ、再び世界を立て直そうと奮闘する。
――これは、“三度目の滅び”を阻止するために挑む、ひとりの中年係長の異世界再建記である。

『規格外の薬師、追放されて辺境スローライフを始める。〜作ったポーションが国家機密級なのは秘密です〜』
雛月 らん
ファンタジー
俺、黒田 蓮(くろだ れん)35歳は前世でブラック企業の社畜だった。過労死寸前で倒れ、次に目覚めたとき、そこは剣と魔法の異世界。しかも、幼少期の俺は、とある大貴族の私生児、アレン・クロイツェルとして生まれ変わっていた。
前世の記憶と、この世界では「外れスキル」とされる『万物鑑定』と『薬草栽培(ハイレベル)』。そして、誰にも知られていない規格外の莫大な魔力を持っていた。
しかし、俺は決意する。「今世こそ、誰にも邪魔されない、のんびりしたスローライフを送る!」と。
これは、スローライフを死守したい天才薬師のアレンと、彼の作る規格外の薬に振り回される異世界の物語。
平穏を愛する(自称)凡人薬師の、のんびりだけど実は波乱万丈な辺境スローライフファンタジー。

異世界でゆるゆるスローライフ!~小さな波乱とチートを添えて~
イノナかノかワズ
ファンタジー
助けて、刺されて、死亡した主人公。神様に会ったりなんやかんやあったけど、社畜だった前世から一転、ゆるいスローライフを送る……筈であるが、そこは知識チートと能力チートを持った主人公。波乱に巻き込まれたりしそうになるが、そこはのんびり暮らしたいと持っている主人公。波乱に逆らい、世界に名が知れ渡ることはなくなり、知る人ぞ知る感じに収まる。まぁ、それは置いといて、主人公の新たな人生は、温かな家族とのんびりした自然、そしてちょっとした研究生活が彩りを与え、幸せに溢れています。
*話はとてもゆっくりに進みます。また、序盤はややこしい設定が多々あるので、流しても構いません。
*他の小説や漫画、ゲームの影響が見え隠れします。作者の願望も見え隠れします。ご了承下さい。
*頑張って週一で投稿しますが、基本不定期です。
*本作の無断転載、無断翻訳、無断利用を禁止します。
小説家になろうにて先行公開中です。主にそっちを優先して投稿します。
カクヨムにても公開しています。
更新は不定期です。

転生したみたいなので異世界生活を楽しみます
さっちさん
ファンタジー
又々、題名変更しました。
内容がどんどんかけ離れていくので…
沢山のコメントありがとうございます。対応出来なくてすいません。
誤字脱字申し訳ございません。気がついたら直していきます。
感傷的表現は無しでお願いしたいと思います😢
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ありきたりな転生ものの予定です。
主人公は30代後半で病死した、天涯孤独の女性が幼女になって冒険する。
一応、転生特典でスキルは貰ったけど、大丈夫か。私。
まっ、なんとかなるっしょ。

高校生の俺、異世界転移していきなり追放されるが、じつは最強魔法使い。可愛い看板娘がいる宿屋に拾われたのでもう戻りません
下昴しん
ファンタジー
高校生のタクトは部活帰りに突然異世界へ転移してしまう。
横柄な態度の王から、魔法使いはいらんわ、城から出ていけと言われ、いきなり無職になったタクト。
偶然会った宿屋の店長トロに仕事をもらい、看板娘のマロンと一緒に宿と食堂を手伝うことに。
すると突然、客の兵士が暴れだし宿はメチャクチャになる。
兵士に殴り飛ばされるトロとマロン。
この世界の魔法は、生活で利用する程度の威力しかなく、とても弱い。
しかし──タクトの魔法は人並み外れて、無法者も脳筋男もひれ伏すほど強かった。

転生魔竜~異世界ライフを謳歌してたら世界最強最悪の覇者となってた?~
アズドラ
ファンタジー
主人公タカトはテンプレ通り事故で死亡、運よく異世界転生できることになり神様にドラゴンになりたいとお願いした。 夢にまで見た異世界生活をドラゴンパワーと現代地球の知識で全力満喫! 仲間を増やして夢を叶える王道、テンプレ、モリモリファンタジー。

家庭菜園物語
コンビニ
ファンタジー
お人好しで動物好きな最上悠は肉親であった祖父が亡くなり、最後の家族であり姉のような存在でもある黒猫の杏も、寿命から静かに息を引き取ろうとする。
「助けたいなら異世界に来てくれない」と少し残念な神様と出会う。
転移先では半ば強引に、死にかけていた犬を助けたことで、能力を失いそのひっそりとスローライフを送ることになってしまうが
迷い込んだ、訪問者次々とやってきて異世界で新しい家族や友人を作り、本人としてはほのぼのと家庭菜園を営んでいるが、小さな畑が世界には大きな影響を与えることになっていく。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















