6 / 13
第六章
しおりを挟む
彼は声を低めながらも、激しく詰め寄ってきた。しかし、ここは公の場だ。先ほどのように手を上げることはできない。
「何のことでしょうか?」
私は冷静に、それでいて芝居がかった驚きの表情を作って答えた。
「私は、言われた通りにドレスを仕立てただけです。まさか、あのような粗悪な縫製だったとは......王都一の仕立て職人の作品だと伺っておりましたが」
叔父の顔が、更に赤くなった。
私は、ここぞとばかりに声を少し大きくした。周囲の貴族たちに聞こえるように。この機会を逃すわけにはいかない。
「それに」
一拍置いて、私は続けた。
「あのドレスを仕立てたのは、確かに私です。ミレイユは、私の作ったドレスを『王都一の仕立て職人の作品』と偽って、社交界で自慢していらしたようですが」
その言葉に、周囲が大きくざわめいた。貴族たちの視線が、私と叔父の間を行き来する。
「まさか......」
「じゃあ、今まで彼女が社交界で着ていたドレスも全部?」
「使用人に作らせていたなんて......」
「それを自分の手柄のように......」
貴族たちの囁き声が、波のように広間に広がっていく。その声は最初は小さかったが、次第に大きくなり、やがて広間全体を包み込んだ。令嬢たちは扇で口元を隠しながら、興奮した様子でひそひそと話し合っている。男性貴族たちも、眉をひそめて叔父を見つめていた。
叔父の顔が、見る見るうちに真っ青になった。先ほどまでの怒りに満ちた赤さは消え失せ、まるで幽霊のように血の気が引いている。額の汗が、一筋、また一筋と頬を伝って落ちていく。
これまで何年もかけて、ミレイユを着飾らせて良縁を得ようとしていた計画。社交界での評判を築き、有力貴族との縁組を狙っていた全ての目論見が、まるで砂の城のように、音を立てて崩れていく。
叔父の口が、何か言おうとして開閉を繰り返している。しかし、言葉が出てこない。周囲の視線が、針のように彼を刺している。
「それは興味深い話だな」
その時、人混みが割れて、ライアン侯爵が近づいてきた。彼の赤い髪が、シャンデリアの光を受けて炎のように輝いている。その隣には――私は息を呑んだ――ヴィルフォール公爵もいた。
二人の登場に、周囲のざわめきが一瞬止んだ。彼らの存在感が、広間の空気を一変させる。公爵の灰色の瞳が、冷たく叔父を見据えていた。
「ローレンス子爵」
ライアンが一歩前に出て、叔父に向き直った。その声は先ほどまでの優しさとは打って変わって、厳格さを帯びている。
「説明していただけますか?なぜ、正統な令嬢であるセレスティーナ様に、使用人同然の仕事をさせていたのか」
叔父の喉が、ごくりと動いた。彼の目が泳ぎ、視線が定まらない。
「それは......この子が、その......望んで」
震える声で、叔父は言い訳を始めた。しかしその声には、全く説得力がない。
「嘘はよくないですよ」
ライアンの緑の瞳が、冷たく光った。その表情からは、先ほどまでの温和さが完全に消えている。これが、公爵の右腕として名を馳せる男の本当の顔なのだろう。
彼はゆっくりと、しかし確実に言葉を続けた。
「私が調べたところによると、貴方はセレスティーナ様の財産管理権を悪用し、ローレンス家の資産を私腹を肥やすために使っていたとか」
その言葉に、叔父が大きく息を呑んだ。彼の体が、目に見えて震え始める。
私も驚きで目を見開いた。ライアン侯爵が、私の財産について調査していた?いつ?なぜ?
「証拠もありますよ」
ライアンは懐から、折りたたまれた書類を取り出した。それを広げる音が、静まり返った広間にはっきりと響く。
「ローレンス家の財産記録と、貴方の個人的な浪費の記録。面白いことに、数字が見事に一致するんです。この豪華な馬車、屋敷の増築、高価な宝飾品......全てセレスティーナ様の財産から支払われていますね」
これは予想外だった。私は茫然と立ち尽くしている。まさか、ライアン侯爵が事前に調査していたとは。彼は一体、いつから私のことを?
周囲のざわめきが、再び大きくなった。今度は驚愕と非難の色が濃い。
「後見人の立場を悪用するとは」
「恥知らずな」
「あの娘が可哀想に」
貴族たちの声が、叔父を取り囲む。
その時、ヴィルフォール公爵が一歩前に出た。
彼の存在感は圧倒的だった。一歩踏み出しただけで、広間全体が再び静寂に包まれる。まるで、彼の周りだけ時間が違う速度で流れているかのようだ。公爵の黒い正装が、彼の威厳を更に際立たせている。
公爵は、冷たい灰色の瞳で叔父を見下ろした。その視線には、一片の慈悲もない。
「ジェラルド・ローレンス」
公爵の声が、広間に響き渡った。低く、それでいて明瞭な声。それは宣告のように重く、誰もが息を潜めてその言葉を待った。
「貴殿を、後見人の資格剥奪の上、横領の罪で告発する」
一拍の間。
「セレスティーナ・ローレンスの後見は、本日をもって王室が引き受ける」
「何のことでしょうか?」
私は冷静に、それでいて芝居がかった驚きの表情を作って答えた。
「私は、言われた通りにドレスを仕立てただけです。まさか、あのような粗悪な縫製だったとは......王都一の仕立て職人の作品だと伺っておりましたが」
叔父の顔が、更に赤くなった。
私は、ここぞとばかりに声を少し大きくした。周囲の貴族たちに聞こえるように。この機会を逃すわけにはいかない。
「それに」
一拍置いて、私は続けた。
「あのドレスを仕立てたのは、確かに私です。ミレイユは、私の作ったドレスを『王都一の仕立て職人の作品』と偽って、社交界で自慢していらしたようですが」
その言葉に、周囲が大きくざわめいた。貴族たちの視線が、私と叔父の間を行き来する。
「まさか......」
「じゃあ、今まで彼女が社交界で着ていたドレスも全部?」
「使用人に作らせていたなんて......」
「それを自分の手柄のように......」
貴族たちの囁き声が、波のように広間に広がっていく。その声は最初は小さかったが、次第に大きくなり、やがて広間全体を包み込んだ。令嬢たちは扇で口元を隠しながら、興奮した様子でひそひそと話し合っている。男性貴族たちも、眉をひそめて叔父を見つめていた。
叔父の顔が、見る見るうちに真っ青になった。先ほどまでの怒りに満ちた赤さは消え失せ、まるで幽霊のように血の気が引いている。額の汗が、一筋、また一筋と頬を伝って落ちていく。
これまで何年もかけて、ミレイユを着飾らせて良縁を得ようとしていた計画。社交界での評判を築き、有力貴族との縁組を狙っていた全ての目論見が、まるで砂の城のように、音を立てて崩れていく。
叔父の口が、何か言おうとして開閉を繰り返している。しかし、言葉が出てこない。周囲の視線が、針のように彼を刺している。
「それは興味深い話だな」
その時、人混みが割れて、ライアン侯爵が近づいてきた。彼の赤い髪が、シャンデリアの光を受けて炎のように輝いている。その隣には――私は息を呑んだ――ヴィルフォール公爵もいた。
二人の登場に、周囲のざわめきが一瞬止んだ。彼らの存在感が、広間の空気を一変させる。公爵の灰色の瞳が、冷たく叔父を見据えていた。
「ローレンス子爵」
ライアンが一歩前に出て、叔父に向き直った。その声は先ほどまでの優しさとは打って変わって、厳格さを帯びている。
「説明していただけますか?なぜ、正統な令嬢であるセレスティーナ様に、使用人同然の仕事をさせていたのか」
叔父の喉が、ごくりと動いた。彼の目が泳ぎ、視線が定まらない。
「それは......この子が、その......望んで」
震える声で、叔父は言い訳を始めた。しかしその声には、全く説得力がない。
「嘘はよくないですよ」
ライアンの緑の瞳が、冷たく光った。その表情からは、先ほどまでの温和さが完全に消えている。これが、公爵の右腕として名を馳せる男の本当の顔なのだろう。
彼はゆっくりと、しかし確実に言葉を続けた。
「私が調べたところによると、貴方はセレスティーナ様の財産管理権を悪用し、ローレンス家の資産を私腹を肥やすために使っていたとか」
その言葉に、叔父が大きく息を呑んだ。彼の体が、目に見えて震え始める。
私も驚きで目を見開いた。ライアン侯爵が、私の財産について調査していた?いつ?なぜ?
「証拠もありますよ」
ライアンは懐から、折りたたまれた書類を取り出した。それを広げる音が、静まり返った広間にはっきりと響く。
「ローレンス家の財産記録と、貴方の個人的な浪費の記録。面白いことに、数字が見事に一致するんです。この豪華な馬車、屋敷の増築、高価な宝飾品......全てセレスティーナ様の財産から支払われていますね」
これは予想外だった。私は茫然と立ち尽くしている。まさか、ライアン侯爵が事前に調査していたとは。彼は一体、いつから私のことを?
周囲のざわめきが、再び大きくなった。今度は驚愕と非難の色が濃い。
「後見人の立場を悪用するとは」
「恥知らずな」
「あの娘が可哀想に」
貴族たちの声が、叔父を取り囲む。
その時、ヴィルフォール公爵が一歩前に出た。
彼の存在感は圧倒的だった。一歩踏み出しただけで、広間全体が再び静寂に包まれる。まるで、彼の周りだけ時間が違う速度で流れているかのようだ。公爵の黒い正装が、彼の威厳を更に際立たせている。
公爵は、冷たい灰色の瞳で叔父を見下ろした。その視線には、一片の慈悲もない。
「ジェラルド・ローレンス」
公爵の声が、広間に響き渡った。低く、それでいて明瞭な声。それは宣告のように重く、誰もが息を潜めてその言葉を待った。
「貴殿を、後見人の資格剥奪の上、横領の罪で告発する」
一拍の間。
「セレスティーナ・ローレンスの後見は、本日をもって王室が引き受ける」
331
あなたにおすすめの小説

老伯爵へ嫁ぐことが決まりました。白い結婚ですが。
ルーシャオ
恋愛
グリフィン伯爵家令嬢アルビナは実家の困窮のせいで援助金目当ての結婚に同意させられ、ラポール伯爵へ嫁ぐこととなる。しかし祖父の戦友だったというラポール伯爵とは五十歳も歳が離れ、名目だけの『白い結婚』とはいえ初婚で後妻という微妙な立場に置かれることに。
ぎこちなく暮らす中、アルビナはフィーという女騎士と出会い、友人になったつもりだったが——。

婚約破棄されたので、もう誰の役にも立たないことにしました 〜静かな公爵家で、何もしない私の本当の人生が始まります〜
ふわふわ
恋愛
王太子の婚約者として、
完璧であることを求められ続けてきた令嬢エリシア。
だがある日、彼女は一方的に婚約を破棄される。
理由は簡単だった。
「君は役に立ちすぎた」から。
すべてを失ったはずの彼女が身を寄せたのは、
“静かな公爵”と呼ばれるアルトゥール・クロイツの屋敷。
そこで待っていたのは――
期待も、役割も、努力の強要もない日々だった。
前に出なくていい。
誰かのために壊れなくていい。
何もしなくても、ここにいていい。
「第二の人生……いえ、これからが本当の人生です」
婚約破棄ざまぁのその先で描かれる、
何者にもならなくていいヒロインの再生と、
放っておく優しさに満ちた静かな溺愛。
これは、
“役に立たなくなった”令嬢が、
ようやく自分として生き始める物語。
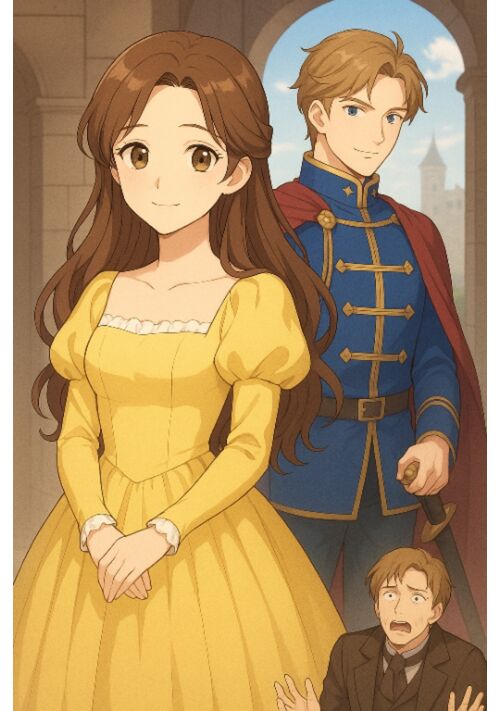
地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします
有賀冬馬
恋愛
子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。
唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。
もう二度と恋なんてしない。
そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。
彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。
彼は、この国の王太子だったのだ。
「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。
一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。
私に助けを求めてきた彼に、私は……

婚約破棄されるはずでしたが、王太子の目の前で皇帝に攫われました』
鷹 綾
恋愛
舞踏会で王太子から婚約破棄を告げられそうになった瞬間――
目の前に現れたのは、馬に乗った仮面の皇帝だった。
そのまま攫われた公爵令嬢ビアンキーナは、誘拐されたはずなのに超VIP待遇。
一方、助けようともしなかった王太子は「無能」と嘲笑され、静かに失墜していく。
選ばれる側から、選ぶ側へ。
これは、誰も断罪せず、すべてを終わらせた令嬢の物語。
--

醜貌の聖女と呼ばれ、婚約破棄されましたが、実は本物の聖女でした
きまま
恋愛
王国の夜会で、第一王子のレオンハルトから婚約破棄を言い渡された公爵令嬢リリエル・アルヴァリア。
顔を銀の仮面で隠していることから『醜貌の聖女』と嘲られ、不要と切り捨てられた彼女は、そのまま王城を追われることになる。
しかし、その後に待ち受ける国の運命は滅亡へと向かっていた——

婚約破棄された伯爵令嬢ですが、辺境で有能すぎて若き領主に求婚されました
おりあ
恋愛
アーデルベルト伯爵家の令嬢セリナは、王太子レオニスの婚約者として静かに、慎ましく、その務めを果たそうとしていた。
だが、感情を上手に伝えられない性格は誤解を生み、社交界で人気の令嬢リーナに心を奪われた王太子は、ある日一方的に婚約を破棄する。
失意のなかでも感情をあらわにすることなく、セリナは婚約を受け入れ、王都を離れ故郷へ戻る。そこで彼女は、自身の分析力や実務能力を買われ、辺境の行政視察に加わる機会を得る。
赴任先の北方の地で、若き領主アレイスターと出会ったセリナ。言葉で丁寧に思いを伝え、誠実に接する彼に少しずつ心を開いていく。
そして静かに、しかし確かに才能を発揮するセリナの姿は、やがて辺境を支える柱となっていく。
一方、王太子レオニスとリーナの婚約生活には次第に綻びが生じ、セリナの名は再び王都でも囁かれるようになる。
静かで無表情だと思われた令嬢は、実は誰よりも他者に寄り添う力を持っていた。
これは、「声なき優しさ」が、真に理解され、尊ばれていく物語。

【完結】身代わりに病弱だった令嬢が隣国の冷酷王子と政略結婚したら、薬師の知識が役に立ちました。
朝日みらい
恋愛
リリスは内気な性格の貴族令嬢。幼い頃に患った大病の影響で、薬師顔負けの知識を持ち、自ら薬を調合する日々を送っている。家族の愛情を一身に受ける妹セシリアとは対照的に、彼女は控えめで存在感が薄い。
ある日、リリスは両親から突然「妹の代わりに隣国の王子と政略結婚をするように」と命じられる。結婚相手であるエドアルド王子は、かつて幼馴染でありながら、今では冷たく距離を置かれる存在。リリスは幼い頃から密かにエドアルドに憧れていたが、病弱だった過去もあって自分に自信が持てず、彼の真意がわからないまま結婚の日を迎えてしまい――

地味で役に立たないと言われて捨てられましたが、王弟殿下のお相手としては最適だったようです
有賀冬馬
恋愛
「君は地味で、将来の役に立たない」
そう言われ、幼なじみの婚約者にあっさり捨てられた侯爵令嬢の私。
社交界でも忘れ去られ、同情だけを向けられる日々の中、私は王宮の文官補佐として働き始める。
そこで出会ったのは、権力争いを嫌う変わり者の王弟殿下。
過去も噂も問わず、ただ仕事だけを見て評価してくれる彼の隣で、私は静かに居場所を見つけていく。
そして暴かれる不正。転落していく元婚約者。
「君が隣にいない宮廷は退屈だ」
これは、選ばれなかった私が、必要とされる私になる物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















