23 / 37
22
しおりを挟む
「……あの並木通りで私が襲われて、グランに助けてもらったあの日の前日……私は18の誕生日を迎えたの。いつもどおり、埃だらけの自室で、誰にも祝われない誕生日を」
「…………」
「でも、今回の誕生日だけは例年と違って、私は熱を出して寝込んでいたの。お母さまの形見のベッドを、壊されたボロボロのアリサのベッドと無理やり交換させられて、数少ないお母さまのドレスをすべて目の前で切り裂かれて、ショックで寝込んでいたの」
思い出すだけであの時の恐怖が蘇るようだ。
恐怖で身体が震えだしそうになるのを、グランが包み込んだミレーの指先にキスをして、柔和に微笑んだ。
「大丈夫だ、ミレー。ここには誰もミレーを傷つける人はいない。だから、安心して話してくれ」
その笑顔に、強張っていた緊張がほぐれていくようで、誘われるように口が勝手にあの日のことを話していた。
熱に浮かされているのに暖もまともに取れない毛布に包まって、必死に寒さと戦っているミレーに、氷水の入ったタライをミレーの後頭部に投げつけたこと。
そのことで意識が朦朧としているミレーに構うことなく、アリサが社交界で話題のオリヴァーという公爵子息を狙っているので、汚らしいミレーという姉の存在が邪魔だから死んでほしいと言われたこと。
「……そこからは、もうよく覚えていないわ、ただ、気づいたら朝になっていて、明るくなった部屋で、私の体調も楽になっていて……」
「…………」
グランが穏やかな表情を努めようとしているのがわかった。自分の手を優しく包み込んでいたグランの手から、怒りに耐えるような震えが伝わってきたからだ。
背後で毛布をあてがってくれていたイリーも、ぐっと手に力が入ったようで、肩にわずかな圧を感じたが、そんなことは気にならなかった。
他人の怒りを肌で感じても怖くないと思ったのは、生まれて初めてだった。
そんなことを思いながら、ミレーは続けた。
「だから、グランと結婚するのなら……平民と結婚するのなら、許されるんじゃないかって、思っていたの。私は、グランを見下してしまっていたんだと思うわ」
その言葉に、グランは頭を振る。
「それは見下していたんじゃない。ミレーがグランという存在に安心して自分を預けてくれようとしたってことなんだ。……それなのに、こんなに怖がらせて、オレこそごめん」
優しく諭され、ミレーの目の視界が見えなくなる。
双眸からあふれ出した熱い液状のせいで、視界が歪んでしまったのだ。
ただとめどなく溢れてくるものが邪魔で、自分の手の甲で乱暴に拭いたいのに、グランがその手をしっかりと握っているからそれができない。
そうでなくても、今のミレーには身体を自分で動かす気力もなかったのだ。
今まで許されずに緊張で強張っていた身体が、ようやく許され、息を吸うことが出来たようで、安堵して身体の力が抜けてしまっていた。
力が抜けたことで、ミレーが前へ倒れ、グランの胸に身体を預ける形となった。
それを、グランは受け入れるように包み込んで、優しく抱きしめてくれた。
「……グラン」
また涙があふれ出してしまう。
その雫はすべて、グランの衣服に染み込んでいってしまう。
グランの着ている上等な布地は、それを吸っても痕にならない。
少し前まで、下町に暮らしているグランがどうしてこのように上等そうな衣服を身に付けているのか不思議に思わなくもなかったが、爵位ある立場だと知った今なら納得がいった。
「……可愛いミレー、いままでずっと泣けずに、一人で頑張って生きてきたんだな。偉いぞ。これからは、今まで一人で苦しんできた以上の時間を、オレとの幸せのために使ってはくれないか?」
「……オリヴァーであるあなたは、こんな丁寧な話し方をするのね」
顔を上げたミレーの目元にたまった雫が、グランの厚い指で拭われた。
ハッキリした視界の先で、愛おしいひとが微笑んでいる。
艶やかな黒い前髪の隙間から覗く黒曜石の瞳がミレーを見つめて、夜の空に星が散りばめられているように美しく見えた。
「……私、あなたがグランでもオリヴァーでも、変わらない一人の人間として愛したいです。それでも、良いですか?」
「……それは、とっても嬉しい」
「……ありがとう。私、死を恐れないで、あなたと添い遂げることを望みます。たとえ結果的に義妹に命を奪われようとも……」
しっかりとグランを見据えて告げた決心は、グランの唇に閉ざされ吸い込まれた。
「っ」
ミレーの唇に乗ったあたたかいぬくもりに驚きつつ、眼前いっぱいに広がる黒曜の空とそこに瞬く星の光を眺めながら、ミレーも瞳を細めて受け入れた。
「……やらせねぇよ。今言ったばかりだろうが。今までミレーが独りぼっちで苦しんできた以上の時間を、オレと幸せに生きることに使ってくれって。ミレーのことはオレが守るから。
これからのミレーの人生を幸せで満たすために、オレと一緒に生きてほしい。約束してくれ。これからの長い時間を、オレと一緒に生きてくれるって」
それは、途方もない夢のことのように思えた。
そのようなことが、本当に可能なのだろうかと目を見開く。
だが、本当に叶えられても、ただの夢に過ぎなかったとしても、ミレーは構わなかった。
「約束します。だから、私からも一つお願いをしていい?」
「なんだ?」
優しく微笑んでミレーを見つめるグランに、ミレーは『おねがい』をした。
物心ついた頃から、ミレーにはおねだりやおねがいをすることが許されなかった。それは義妹のアリサだけに許された特権だった。
だから、もしこれが本当に現実の幸福であるというのなら、それを教えてもらいたかったのだ。
昨日食べたハニートーストより甘い味で、自分の舌を溶かしてほしいと、ねだったのだ。
そう伝えるとグランは、余裕をなくした熱のこもった表情を近づけて、ミレーの唇に吸い付いた。
そして暖かい舌をミレーの唇に強引に滑りこませ、ミレーの口内を蹂躙していった。
「ぐら……っ」
息ができなかった。
息を吸う間さえ与えられず、ミレーもグランの呼吸を奪うようにグランの口内へ舌を伸ばした。
何度も何度もそうやって互いの舌を絡みあわせて、ようやく満足したようにお互いの唇が離れた。
ミレーはそれを名残惜しく感じないこともないが、正直呼吸が限界だったので、助かったと思う気持ちも同時に湧いた。
お互いの呼吸しか聞こえなくなったと思っていた空間に、気まずそうな咳払いが割り込んでいた。
「んっんんっ!」
惚けた脳が次第に覚醒していく。
我に返ったミレーの視界の先で、マルクが顔を真っ赤にして目を逸らせながら「そろそろここを出る支度をしても良いかい? 町のみんなも起きてくる頃だ」と告げた。
ようやく冷静さを取り戻したと同時に、理性を失ってとんでもないことをしていた自覚をして、また冷静さを失った。
恥ずかしさを押し殺しながら、ミレーは必死にこくこくと頷いた。
グランはそんなミレーの様子を安心したように眺めながら、ミレーの赤い髪をかき乱すように乱暴に撫でた。
それは、彼なりの照れ隠しだろうか。
彼の見せた新鮮な一面を知れ、ミレーは心がこそばゆくなるのを覚えながら、すでに支度をはじめているイリーのほうへ向かった。
「…………」
「でも、今回の誕生日だけは例年と違って、私は熱を出して寝込んでいたの。お母さまの形見のベッドを、壊されたボロボロのアリサのベッドと無理やり交換させられて、数少ないお母さまのドレスをすべて目の前で切り裂かれて、ショックで寝込んでいたの」
思い出すだけであの時の恐怖が蘇るようだ。
恐怖で身体が震えだしそうになるのを、グランが包み込んだミレーの指先にキスをして、柔和に微笑んだ。
「大丈夫だ、ミレー。ここには誰もミレーを傷つける人はいない。だから、安心して話してくれ」
その笑顔に、強張っていた緊張がほぐれていくようで、誘われるように口が勝手にあの日のことを話していた。
熱に浮かされているのに暖もまともに取れない毛布に包まって、必死に寒さと戦っているミレーに、氷水の入ったタライをミレーの後頭部に投げつけたこと。
そのことで意識が朦朧としているミレーに構うことなく、アリサが社交界で話題のオリヴァーという公爵子息を狙っているので、汚らしいミレーという姉の存在が邪魔だから死んでほしいと言われたこと。
「……そこからは、もうよく覚えていないわ、ただ、気づいたら朝になっていて、明るくなった部屋で、私の体調も楽になっていて……」
「…………」
グランが穏やかな表情を努めようとしているのがわかった。自分の手を優しく包み込んでいたグランの手から、怒りに耐えるような震えが伝わってきたからだ。
背後で毛布をあてがってくれていたイリーも、ぐっと手に力が入ったようで、肩にわずかな圧を感じたが、そんなことは気にならなかった。
他人の怒りを肌で感じても怖くないと思ったのは、生まれて初めてだった。
そんなことを思いながら、ミレーは続けた。
「だから、グランと結婚するのなら……平民と結婚するのなら、許されるんじゃないかって、思っていたの。私は、グランを見下してしまっていたんだと思うわ」
その言葉に、グランは頭を振る。
「それは見下していたんじゃない。ミレーがグランという存在に安心して自分を預けてくれようとしたってことなんだ。……それなのに、こんなに怖がらせて、オレこそごめん」
優しく諭され、ミレーの目の視界が見えなくなる。
双眸からあふれ出した熱い液状のせいで、視界が歪んでしまったのだ。
ただとめどなく溢れてくるものが邪魔で、自分の手の甲で乱暴に拭いたいのに、グランがその手をしっかりと握っているからそれができない。
そうでなくても、今のミレーには身体を自分で動かす気力もなかったのだ。
今まで許されずに緊張で強張っていた身体が、ようやく許され、息を吸うことが出来たようで、安堵して身体の力が抜けてしまっていた。
力が抜けたことで、ミレーが前へ倒れ、グランの胸に身体を預ける形となった。
それを、グランは受け入れるように包み込んで、優しく抱きしめてくれた。
「……グラン」
また涙があふれ出してしまう。
その雫はすべて、グランの衣服に染み込んでいってしまう。
グランの着ている上等な布地は、それを吸っても痕にならない。
少し前まで、下町に暮らしているグランがどうしてこのように上等そうな衣服を身に付けているのか不思議に思わなくもなかったが、爵位ある立場だと知った今なら納得がいった。
「……可愛いミレー、いままでずっと泣けずに、一人で頑張って生きてきたんだな。偉いぞ。これからは、今まで一人で苦しんできた以上の時間を、オレとの幸せのために使ってはくれないか?」
「……オリヴァーであるあなたは、こんな丁寧な話し方をするのね」
顔を上げたミレーの目元にたまった雫が、グランの厚い指で拭われた。
ハッキリした視界の先で、愛おしいひとが微笑んでいる。
艶やかな黒い前髪の隙間から覗く黒曜石の瞳がミレーを見つめて、夜の空に星が散りばめられているように美しく見えた。
「……私、あなたがグランでもオリヴァーでも、変わらない一人の人間として愛したいです。それでも、良いですか?」
「……それは、とっても嬉しい」
「……ありがとう。私、死を恐れないで、あなたと添い遂げることを望みます。たとえ結果的に義妹に命を奪われようとも……」
しっかりとグランを見据えて告げた決心は、グランの唇に閉ざされ吸い込まれた。
「っ」
ミレーの唇に乗ったあたたかいぬくもりに驚きつつ、眼前いっぱいに広がる黒曜の空とそこに瞬く星の光を眺めながら、ミレーも瞳を細めて受け入れた。
「……やらせねぇよ。今言ったばかりだろうが。今までミレーが独りぼっちで苦しんできた以上の時間を、オレと幸せに生きることに使ってくれって。ミレーのことはオレが守るから。
これからのミレーの人生を幸せで満たすために、オレと一緒に生きてほしい。約束してくれ。これからの長い時間を、オレと一緒に生きてくれるって」
それは、途方もない夢のことのように思えた。
そのようなことが、本当に可能なのだろうかと目を見開く。
だが、本当に叶えられても、ただの夢に過ぎなかったとしても、ミレーは構わなかった。
「約束します。だから、私からも一つお願いをしていい?」
「なんだ?」
優しく微笑んでミレーを見つめるグランに、ミレーは『おねがい』をした。
物心ついた頃から、ミレーにはおねだりやおねがいをすることが許されなかった。それは義妹のアリサだけに許された特権だった。
だから、もしこれが本当に現実の幸福であるというのなら、それを教えてもらいたかったのだ。
昨日食べたハニートーストより甘い味で、自分の舌を溶かしてほしいと、ねだったのだ。
そう伝えるとグランは、余裕をなくした熱のこもった表情を近づけて、ミレーの唇に吸い付いた。
そして暖かい舌をミレーの唇に強引に滑りこませ、ミレーの口内を蹂躙していった。
「ぐら……っ」
息ができなかった。
息を吸う間さえ与えられず、ミレーもグランの呼吸を奪うようにグランの口内へ舌を伸ばした。
何度も何度もそうやって互いの舌を絡みあわせて、ようやく満足したようにお互いの唇が離れた。
ミレーはそれを名残惜しく感じないこともないが、正直呼吸が限界だったので、助かったと思う気持ちも同時に湧いた。
お互いの呼吸しか聞こえなくなったと思っていた空間に、気まずそうな咳払いが割り込んでいた。
「んっんんっ!」
惚けた脳が次第に覚醒していく。
我に返ったミレーの視界の先で、マルクが顔を真っ赤にして目を逸らせながら「そろそろここを出る支度をしても良いかい? 町のみんなも起きてくる頃だ」と告げた。
ようやく冷静さを取り戻したと同時に、理性を失ってとんでもないことをしていた自覚をして、また冷静さを失った。
恥ずかしさを押し殺しながら、ミレーは必死にこくこくと頷いた。
グランはそんなミレーの様子を安心したように眺めながら、ミレーの赤い髪をかき乱すように乱暴に撫でた。
それは、彼なりの照れ隠しだろうか。
彼の見せた新鮮な一面を知れ、ミレーは心がこそばゆくなるのを覚えながら、すでに支度をはじめているイリーのほうへ向かった。
3
あなたにおすすめの小説

差し出された毒杯
しろねこ。
恋愛
深い森の中。
一人のお姫様が王妃より毒杯を授けられる。
「あなたのその表情が見たかった」
毒を飲んだことにより、少女の顔は苦悶に満ちた表情となる。
王妃は少女の美しさが妬ましかった。
そこで命を落としたとされる少女を助けるは一人の王子。
スラリとした体型の美しい王子、ではなく、体格の良い少し脳筋気味な王子。
お供をするは、吊り目で小柄な見た目も中身も猫のように気まぐれな従者。
か○みよ、○がみ…ではないけれど、毒と美しさに翻弄される女性と立ち向かうお姫様なお話。
ハピエン大好き、自己満、ご都合主義な作者による作品です。
同名キャラで複数の作品を書いています。
立場やシチュエーションがちょっと違ったり、サブキャラがメインとなるストーリーをなどを書いています。
ところどころリンクもしています。
※小説家になろうさん、カクヨムさんでも投稿しています!

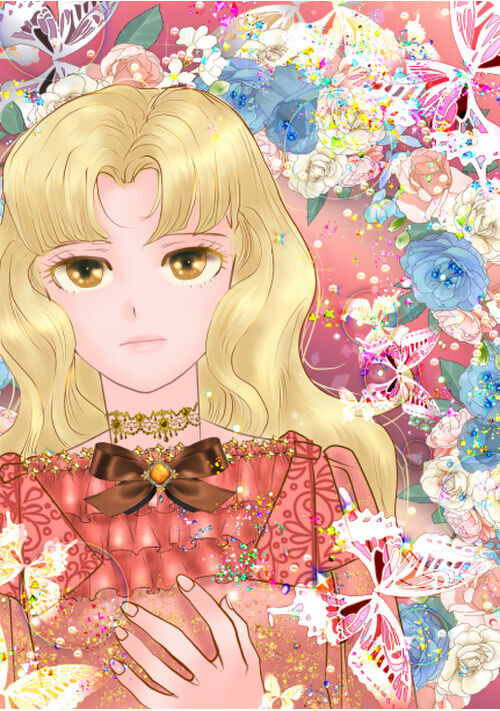
好きだと先に言ったのはあなたなのに?
みみぢあん
恋愛
スタッドリー男爵令嬢ニーナは、友人にレブデール子爵令息のケインを紹介される。
出会ったばかりのケインに『好きだ』と告白された。それ以来、ニーナは毎日のように求愛され続けた。
明るくてさわやかなケインが好きになってゆき、ニーナは“秘密の恋人”となった。
――だが、しだいにケインから避けられるようになり、ニーナは自分の他にも“秘密の恋人”がケインにはいると知る。

僕の婚約者は今日も麗しい
蒼あかり
恋愛
公爵家嫡男のクラウスは王命により、隣国の王女と婚約を結ぶことになった。王家の血を引く者として、政略結婚も厭わないと覚悟を決めていたのに、それなのに。まさか相手が子供だとは......。
婚約相手の王女ローザもまた、国の安定のためにその身を使う事を使命としていたが、早い婚約に戸惑っていた。
そんなふたりが色々あって、少しづつ関係を深めていく。そんなお話。
変わり者の作者が、頑張ってハッピーエンドを目指します。
たぶん。きっと。幸せにしたい、です。
※予想外に多くの皆様に読んでいただき、驚いております。
心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。
ご覧いただいた皆様に幸せの光が降り注ぎますように。
ありがとうございました。

【王国内屈指の公爵家の令嬢ですが、婚約破棄される前に婚約破棄しました。元婚約者は没落したそうですが、そんなの知りません】
はくら(仮名)
恋愛
更新はマイペースです。
本作は別名義で『小説家になろう』にも掲載しています。

婚約破棄されたので田舎で猫と暮らします
たくわん
恋愛
社交界の華と謳われた伯爵令嬢セレスティアは、王太子から「完璧すぎて息が詰まる」と婚約破棄を告げられる。傷心のまま逃げるように向かったのは、亡き祖母が遺した田舎の小さな屋敷だった。
荒れ果てた屋敷、慣れない一人暮らし、そして庭に住みついた五匹の野良猫たち。途方に暮れるセレスティアの隣には、無愛想で人嫌いな青年医師・ノアが暮らしていた。
「この猫に構うな。人間嫌いだから」
冷たく突き放すノアだが、捨て猫を保護し、傷ついた動物を治療する彼の本当の姿を知るうちに、セレスティアの心は少しずつ惹かれていく。
猫の世話を通じて近づく二人。やがて明かされるノアの過去と、王都から届く縁談の催促。「完璧な令嬢」を脱ぎ捨てた先に待つ、本当の自分と本当の恋——。

あなたを忘れる魔法があれば
美緒
恋愛
乙女ゲームの攻略対象の婚約者として転生した私、ディアナ・クリストハルト。
ただ、ゲームの舞台は他国の為、ゲームには婚約者がいるという事でしか登場しない名前のないモブ。
私は、ゲームの強制力により、好きになった方を奪われるしかないのでしょうか――?
これは、「あなたを忘れる魔法があれば」をテーマに書いてみたものです――が、何か違うような??
R15、残酷描写ありは保険。乙女ゲーム要素も空気に近いです。
※小説家になろう、カクヨムにも掲載してます

愛する人は、貴方だけ
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
下町で暮らすケイトは母と二人暮らし。ところが母は病に倒れ、ついに亡くなってしまう。亡くなる直前に母はケイトの父親がアークライト公爵だと告白した。
天涯孤独になったケイトの元にアークライト公爵家から使者がやって来て、ケイトは公爵家に引き取られた。
公爵家には三歳年上のブライアンがいた。跡継ぎがいないため遠縁から引き取られたというブライアン。彼はケイトに冷たい態度を取る。
平民上がりゆえに令嬢たちからは無視されているがケイトは気にしない。最初は冷たかったブライアン、第二王子アーサー、公爵令嬢ミレーヌ、幼馴染カイルとの交友を深めていく。
やがて戦争の足音が聞こえ、若者の青春を奪っていく。ケイトも無関係ではいられなかった……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















