36 / 37
35
しおりを挟む
「おはようございます」
「おはよう……カミラ」
グランディア公爵家に来てから、3か月ほどの月日が経った。
ミレーがこの邸に迎え入れられた翌朝から、目の前でカーテンを開けてくれている、桃色のお団子ヘアをした若い女性がミレーの専属メイドとなり、毎日世話をしてくれている。
他にも何名かメイドはいるが、彼女たちはこの専属メイド・カミラの指示に従って動く。主な指示はカミラが出していた。
カミラの声は鈴の音のように涼やかで、つい聞き惚れてしまう。
(イリーさんも鈴の音のような声だったけど、違う音のように聞こえる)
カミラはイリーの姉だと言う。
それ以上のことをカミラは話そうとしないし、ミレーもしつこく聞かなかった。
カミラはカーテンを開いて、入ってきた朝の陽ざしを部屋の中に充満させると、ミレーの顔を洗う手伝いをしてくれた。
それから今日身につけるドレスの着付けを手伝ってくれ、髪を梳かして軽く化粧をしてくれた。
はじめの頃のミレーは、メイドにペコペコ頭を下げるし、敬語を使ってしまうし、それを注意されれば謝ってしまい、オリヴァーにもたしなめられていた。
だがそこは、オリヴァーがたしなめるより、カミラがたしなめるほうが効果はあった。
「メイドに敬語を使うたび、名前を『さん』付けするたび、そうされたメイドから給料を一パーセントずつ減らしていくよう当主へ申告させていただきます」
「私じゃなくて、カミラさんたちから!?」
「はい。今『さん』付けされたので、私の給料から一パーセント引かれました」
それが申し訳なさすぎて、ミレーから血の気が引いた。だからミレーは、敬語も、『さん』付けもしないよう全力で頑張った。
その甲斐あって、最初の一回以降は、誰の給料も引かれていないという。
「カミラには頭があがらないだろう?」
オリヴァーはミレーの話を聞くと、そう言って楽しそうに笑った。
「笑い事じゃないよ……本当に気がどうかしてしまうかと思った……」
「オレの時はわりと早くに慣れてくれたじゃねえか」
「それは……なんか、わりとしっくり馴染んで……。でも、私実家ではメイドより下の立場だったから……」
「習慣って、慣れると息を吸うように難が無いのに、それを改善しようとするとすごく苦労するよな……」
「オリヴァーもそうだったの?」
「……オレがこの邸に来た時に世話係をしたのがカミラでな、オレも言葉遣いからマナー、生活態度まで全部うるさく直されたものだ」
オリヴァーが昔を思い出しながら、顔をしかめてつらつらと語っていた。
「え、オリヴァーが小さい頃から世話係を? ……カミラって若く見えるけど、一体今いくつ……」
そこまで言ってから、ミレーは口をつぐんだ。
女性の年齢に触れるなど、タブーであったからだ。
それはオリヴァーも同じようで、二人して黙って食事を続けた。
傍では二人の様子を眺めて、カミラがにっこりと笑みを浮かべていた。
「それにしても、ミレーはすっかりここでの生活に馴染んできたよな」
オリヴァーにそう言われ、ミレーは少し困った。
朝食を取り終え、今はオリヴァーと二人で庭園に来ていた。
気候も穏やかになり、庭園では春の花が咲き誇っている。
ダファディルという黄色い水仙の前で、ミレーは屈んでその花を眺めながら声を漏らした。
「……どう、かな」
「どうした?」
ミレーの曖昧な返しに、オリヴァーも一緒に屈み込み、ミレーを背中から抱きしめるように寄りかかった。
「どうした?」
そしてもう一度同じ言葉をかけられ、ミレーはオリヴァーに甘えるように胸に頭を預けながら言った。
「……ここの人たちには、とても良くしてもらっているけれど、私は今まで体験したことのない生活にまだ慣れていないから。全然実感ないや」
オリヴァーとの婚約を前提に、この邸で淑女教育や貴族として身に付けておくべきマナー、基礎的な科目の勉強などを学ばせてもらっている。
ありがたいことだが、今まで自分と縁がなさ過ぎて、自分が恥じ入るばかりなのだ。
知らなかったことが多すぎる、出来ないことが多すぎる、そういったことが積み重なって、ミレーは自分がますますみじめになっていくのだ。
自己の評価など底辺にあるものだと思っていたが、まだ底があるとは思わなかった。
そう花を見つめながら告げると、オリヴァーはミレーのつむじ辺りに、自身の顎をぐりぐりと押し付けた。
「ちょ、ちょっと……」
「あのなぁ、ミレー。お前は今までこういう生活に馴染みが無かったんだろう? だったら最初は出来なくて当たり前だろう。それなのに、三ヶ月でここまで出来るようになっているのが凄いってオレは言っているんだよ」
「……三ヶ月もかかってこれしか出来ていないのよ」
ますます自分がみじめになる。
そう思っていると、オリヴァーが軽く握った拳を、今まで顎で抑えていたつむじへグリグリと押し当ててきた。
「何するのよ!」
「ミレーが酷いことを言うからだろう?」
「酷いコトって何よ!」
「『三ヶ月もかかってこれしか』って、嫌味かよ」
「何が嫌味なの!」
「オレは8歳の時にこの邸へ来て、次期グランディア公爵家の当主となるべく、色々なことを学ばされた。それまで下町で庶民として暮らしていた生活とはまるで違う世界に、オレは馴染むまで2年かかったし、今も馴染んでいるとは言いきれない」
「え……?」
オリヴァーは完全にこの邸に馴染んでいるよ、と驚いて振り向いて見ると、彼は寂しそうな表情で微笑んでいた。
「まぁ、それはオレが『貴族になんかなるものか』って反抗していたのもあるかもしれないが、オレは貴族に向いていないんだろうって満足もしていた。でも、『ミレーと会うまでで良いから、オリヴァーという貴族を演じてみてはどうだ』って父上に言われたから、そう見せられるように取り繕っているだけだ。少し皮を剝げば、あっという間にオリヴァーという人間は瓦解して消える。……それは今も変わらない」
「……ハリボテってこと?」
「そうだな。ミレーに会うまでだけの、ハリボテ。でも、公爵家で暮らすようになって、下町で暮らしていた頃よりも元気になっていくミレーを見ていたら……あぁ、ミレーはやっぱり貴族なんだな、って、思って……」
「……オリヴァー?」
「オレとはやっぱり、棲む世界が違うんじゃないかって……」
「オリヴァー!」
ミレーの呼びかけにも応じず、ぶつぶつと卑屈なことを呟き始めたオリヴァーに強く呼びかければ、彼はようやく我に返った。
「……あ」
「なんでそんなことを言うの? 私とあなたの住む世界が違うなんて、そんな悲しいこと、どうして言うの? 私なんかと結婚するのが、やっぱり嫌になったの?」
「おはよう……カミラ」
グランディア公爵家に来てから、3か月ほどの月日が経った。
ミレーがこの邸に迎え入れられた翌朝から、目の前でカーテンを開けてくれている、桃色のお団子ヘアをした若い女性がミレーの専属メイドとなり、毎日世話をしてくれている。
他にも何名かメイドはいるが、彼女たちはこの専属メイド・カミラの指示に従って動く。主な指示はカミラが出していた。
カミラの声は鈴の音のように涼やかで、つい聞き惚れてしまう。
(イリーさんも鈴の音のような声だったけど、違う音のように聞こえる)
カミラはイリーの姉だと言う。
それ以上のことをカミラは話そうとしないし、ミレーもしつこく聞かなかった。
カミラはカーテンを開いて、入ってきた朝の陽ざしを部屋の中に充満させると、ミレーの顔を洗う手伝いをしてくれた。
それから今日身につけるドレスの着付けを手伝ってくれ、髪を梳かして軽く化粧をしてくれた。
はじめの頃のミレーは、メイドにペコペコ頭を下げるし、敬語を使ってしまうし、それを注意されれば謝ってしまい、オリヴァーにもたしなめられていた。
だがそこは、オリヴァーがたしなめるより、カミラがたしなめるほうが効果はあった。
「メイドに敬語を使うたび、名前を『さん』付けするたび、そうされたメイドから給料を一パーセントずつ減らしていくよう当主へ申告させていただきます」
「私じゃなくて、カミラさんたちから!?」
「はい。今『さん』付けされたので、私の給料から一パーセント引かれました」
それが申し訳なさすぎて、ミレーから血の気が引いた。だからミレーは、敬語も、『さん』付けもしないよう全力で頑張った。
その甲斐あって、最初の一回以降は、誰の給料も引かれていないという。
「カミラには頭があがらないだろう?」
オリヴァーはミレーの話を聞くと、そう言って楽しそうに笑った。
「笑い事じゃないよ……本当に気がどうかしてしまうかと思った……」
「オレの時はわりと早くに慣れてくれたじゃねえか」
「それは……なんか、わりとしっくり馴染んで……。でも、私実家ではメイドより下の立場だったから……」
「習慣って、慣れると息を吸うように難が無いのに、それを改善しようとするとすごく苦労するよな……」
「オリヴァーもそうだったの?」
「……オレがこの邸に来た時に世話係をしたのがカミラでな、オレも言葉遣いからマナー、生活態度まで全部うるさく直されたものだ」
オリヴァーが昔を思い出しながら、顔をしかめてつらつらと語っていた。
「え、オリヴァーが小さい頃から世話係を? ……カミラって若く見えるけど、一体今いくつ……」
そこまで言ってから、ミレーは口をつぐんだ。
女性の年齢に触れるなど、タブーであったからだ。
それはオリヴァーも同じようで、二人して黙って食事を続けた。
傍では二人の様子を眺めて、カミラがにっこりと笑みを浮かべていた。
「それにしても、ミレーはすっかりここでの生活に馴染んできたよな」
オリヴァーにそう言われ、ミレーは少し困った。
朝食を取り終え、今はオリヴァーと二人で庭園に来ていた。
気候も穏やかになり、庭園では春の花が咲き誇っている。
ダファディルという黄色い水仙の前で、ミレーは屈んでその花を眺めながら声を漏らした。
「……どう、かな」
「どうした?」
ミレーの曖昧な返しに、オリヴァーも一緒に屈み込み、ミレーを背中から抱きしめるように寄りかかった。
「どうした?」
そしてもう一度同じ言葉をかけられ、ミレーはオリヴァーに甘えるように胸に頭を預けながら言った。
「……ここの人たちには、とても良くしてもらっているけれど、私は今まで体験したことのない生活にまだ慣れていないから。全然実感ないや」
オリヴァーとの婚約を前提に、この邸で淑女教育や貴族として身に付けておくべきマナー、基礎的な科目の勉強などを学ばせてもらっている。
ありがたいことだが、今まで自分と縁がなさ過ぎて、自分が恥じ入るばかりなのだ。
知らなかったことが多すぎる、出来ないことが多すぎる、そういったことが積み重なって、ミレーは自分がますますみじめになっていくのだ。
自己の評価など底辺にあるものだと思っていたが、まだ底があるとは思わなかった。
そう花を見つめながら告げると、オリヴァーはミレーのつむじ辺りに、自身の顎をぐりぐりと押し付けた。
「ちょ、ちょっと……」
「あのなぁ、ミレー。お前は今までこういう生活に馴染みが無かったんだろう? だったら最初は出来なくて当たり前だろう。それなのに、三ヶ月でここまで出来るようになっているのが凄いってオレは言っているんだよ」
「……三ヶ月もかかってこれしか出来ていないのよ」
ますます自分がみじめになる。
そう思っていると、オリヴァーが軽く握った拳を、今まで顎で抑えていたつむじへグリグリと押し当ててきた。
「何するのよ!」
「ミレーが酷いことを言うからだろう?」
「酷いコトって何よ!」
「『三ヶ月もかかってこれしか』って、嫌味かよ」
「何が嫌味なの!」
「オレは8歳の時にこの邸へ来て、次期グランディア公爵家の当主となるべく、色々なことを学ばされた。それまで下町で庶民として暮らしていた生活とはまるで違う世界に、オレは馴染むまで2年かかったし、今も馴染んでいるとは言いきれない」
「え……?」
オリヴァーは完全にこの邸に馴染んでいるよ、と驚いて振り向いて見ると、彼は寂しそうな表情で微笑んでいた。
「まぁ、それはオレが『貴族になんかなるものか』って反抗していたのもあるかもしれないが、オレは貴族に向いていないんだろうって満足もしていた。でも、『ミレーと会うまでで良いから、オリヴァーという貴族を演じてみてはどうだ』って父上に言われたから、そう見せられるように取り繕っているだけだ。少し皮を剝げば、あっという間にオリヴァーという人間は瓦解して消える。……それは今も変わらない」
「……ハリボテってこと?」
「そうだな。ミレーに会うまでだけの、ハリボテ。でも、公爵家で暮らすようになって、下町で暮らしていた頃よりも元気になっていくミレーを見ていたら……あぁ、ミレーはやっぱり貴族なんだな、って、思って……」
「……オリヴァー?」
「オレとはやっぱり、棲む世界が違うんじゃないかって……」
「オリヴァー!」
ミレーの呼びかけにも応じず、ぶつぶつと卑屈なことを呟き始めたオリヴァーに強く呼びかければ、彼はようやく我に返った。
「……あ」
「なんでそんなことを言うの? 私とあなたの住む世界が違うなんて、そんな悲しいこと、どうして言うの? 私なんかと結婚するのが、やっぱり嫌になったの?」
3
あなたにおすすめの小説

差し出された毒杯
しろねこ。
恋愛
深い森の中。
一人のお姫様が王妃より毒杯を授けられる。
「あなたのその表情が見たかった」
毒を飲んだことにより、少女の顔は苦悶に満ちた表情となる。
王妃は少女の美しさが妬ましかった。
そこで命を落としたとされる少女を助けるは一人の王子。
スラリとした体型の美しい王子、ではなく、体格の良い少し脳筋気味な王子。
お供をするは、吊り目で小柄な見た目も中身も猫のように気まぐれな従者。
か○みよ、○がみ…ではないけれど、毒と美しさに翻弄される女性と立ち向かうお姫様なお話。
ハピエン大好き、自己満、ご都合主義な作者による作品です。
同名キャラで複数の作品を書いています。
立場やシチュエーションがちょっと違ったり、サブキャラがメインとなるストーリーをなどを書いています。
ところどころリンクもしています。
※小説家になろうさん、カクヨムさんでも投稿しています!

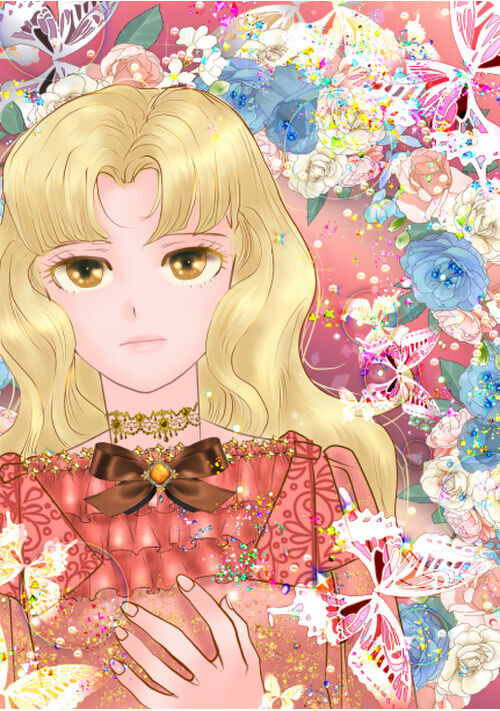
好きだと先に言ったのはあなたなのに?
みみぢあん
恋愛
スタッドリー男爵令嬢ニーナは、友人にレブデール子爵令息のケインを紹介される。
出会ったばかりのケインに『好きだ』と告白された。それ以来、ニーナは毎日のように求愛され続けた。
明るくてさわやかなケインが好きになってゆき、ニーナは“秘密の恋人”となった。
――だが、しだいにケインから避けられるようになり、ニーナは自分の他にも“秘密の恋人”がケインにはいると知る。

僕の婚約者は今日も麗しい
蒼あかり
恋愛
公爵家嫡男のクラウスは王命により、隣国の王女と婚約を結ぶことになった。王家の血を引く者として、政略結婚も厭わないと覚悟を決めていたのに、それなのに。まさか相手が子供だとは......。
婚約相手の王女ローザもまた、国の安定のためにその身を使う事を使命としていたが、早い婚約に戸惑っていた。
そんなふたりが色々あって、少しづつ関係を深めていく。そんなお話。
変わり者の作者が、頑張ってハッピーエンドを目指します。
たぶん。きっと。幸せにしたい、です。
※予想外に多くの皆様に読んでいただき、驚いております。
心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。
ご覧いただいた皆様に幸せの光が降り注ぎますように。
ありがとうございました。

【王国内屈指の公爵家の令嬢ですが、婚約破棄される前に婚約破棄しました。元婚約者は没落したそうですが、そんなの知りません】
はくら(仮名)
恋愛
更新はマイペースです。
本作は別名義で『小説家になろう』にも掲載しています。

婚約破棄されたので田舎で猫と暮らします
たくわん
恋愛
社交界の華と謳われた伯爵令嬢セレスティアは、王太子から「完璧すぎて息が詰まる」と婚約破棄を告げられる。傷心のまま逃げるように向かったのは、亡き祖母が遺した田舎の小さな屋敷だった。
荒れ果てた屋敷、慣れない一人暮らし、そして庭に住みついた五匹の野良猫たち。途方に暮れるセレスティアの隣には、無愛想で人嫌いな青年医師・ノアが暮らしていた。
「この猫に構うな。人間嫌いだから」
冷たく突き放すノアだが、捨て猫を保護し、傷ついた動物を治療する彼の本当の姿を知るうちに、セレスティアの心は少しずつ惹かれていく。
猫の世話を通じて近づく二人。やがて明かされるノアの過去と、王都から届く縁談の催促。「完璧な令嬢」を脱ぎ捨てた先に待つ、本当の自分と本当の恋——。

あなたを忘れる魔法があれば
美緒
恋愛
乙女ゲームの攻略対象の婚約者として転生した私、ディアナ・クリストハルト。
ただ、ゲームの舞台は他国の為、ゲームには婚約者がいるという事でしか登場しない名前のないモブ。
私は、ゲームの強制力により、好きになった方を奪われるしかないのでしょうか――?
これは、「あなたを忘れる魔法があれば」をテーマに書いてみたものです――が、何か違うような??
R15、残酷描写ありは保険。乙女ゲーム要素も空気に近いです。
※小説家になろう、カクヨムにも掲載してます

愛する人は、貴方だけ
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
下町で暮らすケイトは母と二人暮らし。ところが母は病に倒れ、ついに亡くなってしまう。亡くなる直前に母はケイトの父親がアークライト公爵だと告白した。
天涯孤独になったケイトの元にアークライト公爵家から使者がやって来て、ケイトは公爵家に引き取られた。
公爵家には三歳年上のブライアンがいた。跡継ぎがいないため遠縁から引き取られたというブライアン。彼はケイトに冷たい態度を取る。
平民上がりゆえに令嬢たちからは無視されているがケイトは気にしない。最初は冷たかったブライアン、第二王子アーサー、公爵令嬢ミレーヌ、幼馴染カイルとの交友を深めていく。
やがて戦争の足音が聞こえ、若者の青春を奪っていく。ケイトも無関係ではいられなかった……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















