25 / 26
巻の二十五、交わりの意味
しおりを挟む
「……ちゃんと説明してよね」
夜遅く。
二人で戻った瑠璃宮の室で。
わたしと揃いの夜着に着替えた如飛を睨みつける。
即位の儀のあと、含元殿の前に集まった、宮殿に入りきれなかった兵士たちの前に姿を見せた時も、即位の祝宴でも。ずっと、ずっと黙って、横に立って、それらしく笑ってたけど。
だからって、「はい、そうですか」って納得したわけじゃないのよ!
説明! 説明しなさい!
わたし、皇后は辞退するって、前に言ったじゃない!
「この衣装のことか?」
「そっ……」
それも訊きたいことだけどっ!
「お前が俺のために衣装を縫ってたのは知っている。糸を用意するように命じたのは、俺だからな」
そうだ。そうです。そうでした。
糸とか皎月さんが持ってきてくれたけど。そこに、彼が関係してないわけがないんだった。だって、皎月さんは彼の部下だし。
わたしが縫ってたことは、彼に筒抜けだったと。
「途中で、縫うのを止めたみたいだったが。俺は、未完成であっても、これを着て即位したかった。お前が設えてくれたものだ。これ以上に、俺の即位にふさわしい衣はない」
グウ。
そう言われると、中途半端な刺繍しかない衣であっても、最高の衣に思えてくる。
「さて、どこから話せばよいかな」
怒るわたしを前に、一人寝台に腰を下ろした如飛。衣のことを話してる時より、声の高さがグンッと落ちた。
「俺は、幼い頃から妃は一人、乙女だけでよいと決めてきたんだ」
「乙女だけ?」
「ああ。……少し長くなるが、聴いてくれるか?」
即位の時とも、その後の宴席の時とも違う。
とても真面目で、とても思い悩んだような表情。
「わかったわ」
怒りは一旦置いといて、話し、聴いてあげる。
「俺の父、先の皇帝は、慣習に倣って皇后、玻璃妃と、陰陽の乙女、瑠璃妃を持っていた。それが当たり前だったし、皇帝として統治するためには、それが普通だった。玻璃妃に子を産ませ、瑠璃妃と交わって陰陽を整える。俺を産んだのは、皇后、玻璃妃だしな」
少し前かがみになった彼が、膝の上で手を組む。
「だが。だが、母は、本来、叔父の妻になる女性だったんだ」
「――え?」
それって、どういうこと?
「瑠璃妃と玻璃妃、ともに揃っていないと即位できない。だから、父は、陰陽の乙女を見つけ出すと同時に、母を皇后に選んだ。母が……、皇族に連なる娘だったから――というのが表向きの理由だな。裏は、異母弟である叔父と母の幸せそうな関係を妬ましく思ったから。それと、母を妻にすることで、叔父の力が増すことを恐れたから」
「そんな……」
「叔父は、異母兄である俺の父の言うことに従うしかなかった。母を渡さなければ、それは次期皇帝に対する反逆だ。叔父だけでなく、母も処刑される。だから、叔父は母を手離した。そして叔父は、母と離れても母を思い慕い、誰とも結婚せずにいる」
そこまで話して、如飛が手で顔を覆った。
「それに比べ、最低な男だよ、俺の父は。愛し合ってた異母弟たちを引き離して、母に俺を産ませたのだから」
手を離して、深く深く息を吐き出した。
「それでも、父が母を愛して大事にすれば、救いもあっただろう。でも父はそうはしなかった。母が俺を孕んだことで、母を捨てた。母の居た玻璃宮にも、皇太子だった俺の琥珀宮にも、一度も訪れなかった。子が生まれればそれでよし、弟と母の仲を引き裂けば、それで満足だったんだろう」
わざとだろう。
如飛が明るく話してくれるけど、聴いてるわたしのお腹には、ドンドン鉛が詰められていくような感じがした。
「母を大事にしなかった父は、自身の乙女でもある瑠璃妃に対しても同じだった。乙女は、陰陽を整えるための道具に過ぎない。だから、遠征先にもどこにでも連れて行って、嫌がる乙女を無理やり犯していた」
グッ。
「俺も一度だけ見たことがあるんだ。後宮の庭で。心を壊して、身動ぎ一つしない乙女にのしかかり、欲望をぶつけるだけの父の姿を……」
「もういい! もう、言わなくていい!」
話す如飛が、辛そうで。話しながら、自分を傷つけ血を流してる用に見えて、思わず彼を抱きしめる。
「ありがとう、里珠」
腕の中で、如飛が囁いた。
「俺は、あれを見た時からずっと心に誓っていたんだ。愛するなら乙女だけを。身を捧げてもらわなければ国を治められないというのなら、乙女だけを愛そうと」
「如飛……」
「だが、人というものは難しいな。身を捧げてもらうのだから愛さねばと思っていたのに。今では、愛しいと思うからこそ愛したいと思っている」
「きゃっ!」
グイッと抱き寄せられた腰。予想してなかった如飛の動きに、均衡を崩した体が、彼の上にしなだれる。
「里珠。俺はお前が好きだ。愛してる。陰陽の乙女だからじゃない。お前がお前だから、愛おしい」
「如飛」
「お前が乙女でなかったとしても、俺はお前を愛さずにいられなかっただろう」
なにそれ。ナニソレ、ナニソレ。
言葉と、眼差し、伝わる鼓動。そしてわたしを抱きしめる腕。
そのすべてに、口がわななき、目が熱くなってくる。
「わ、わたしも如飛が好き」
「里珠……」
うれしい。そこまで想ってくれて。わたしを大事にしてくれて。
でも。
「でも……、わたし、アナタの子を産んであげられない……」
陰陽の乙女は、どれだけ交わろうとも子を成せない。
どれだけ精を注がれても、子ができることはない。
「知って、いたのか……」
その問いかけに、我慢できなかった涙が溢れ、「うん」と小さく頷くことしかできなかった。
ごめんなさい。
それほどまでに、愛してくれても、わたしはアナタになにも返してあげられないの。
「そうか」
シュルっと衣擦れの音がした。如飛が動いたんだ。
「だがな。それは間違いかもしれないぞ」
「ま、間違い?」
ファサッと、わたしの体が寝台に横たえられる。
「陰陽の乙女が子を産んだ記録はない。だがな」
シュルシュル。お腹の辺りで音がする。
「初代皇帝の皇后、二代皇帝の母は、陰陽の乙女だ」
「え?」
溢れ続けていた涙が引っ込んだ。
二代皇帝の――母?
「初代も二代も、存在が伝説に近いから、本当かどうか、真偽は疑わしいけどな。だが、陰陽の乙女が皇后になって、子を産んだ。それが二代目皇帝だという伝説が残っている」
「じゃ、じゃあ、わたし、子を産めるのっ!?」
「かもしれんな。試してみるか?」
ニヤッといたずらっぽく如飛が笑う。
って、ちょっと! いつの間にわたしの帯を外してたのよ!
帯を解かれたせいで夜着がはだけ、わたしの首元からおへその下まで、彼の目の前に晒される。
「子ができぬでもよい。こうして交わるのは、陰陽を整えるためでも、子を成すためでもない」
グッと身を乗り出した如飛。
「お前を愛しいと思うからこそ。愛しいお前と一つになりたい。お前に俺を刻みつけたいと思うから交わるのだ」
笑いが消え、残った真摯な瞳に、わたしが映る。
泣きそうになって、グッと唇を噛みしめ、彼だけを見つめるわたしが。
「世の中には、どれだけ愛し合おうとも、子ができぬ夫婦も居ると聴く。俺たちも、そういう夫婦であってもよいと思っている。まあ、皇帝としては民に不実かもしれんが。しかし、俺に子がいなくても叔父上がいる。叔父上でダメだと言うのなら……。そうだな。皇族の誰かから養子をもらってもいいかもしれん」
「如飛……」
「そろそろよいか? 俺はお前を愛したくて仕方ないんだが?」
「もうっ!」
軽く言った彼に、笑ってみせたかったのに。
笑った頬を、こらえきれなかった涙が流れ落ちる。
「里珠」
その涙を指で拭ってくれた如飛。そのまま誘われるように、笑みを残した彼の唇に、自分のを重ねる。何度もなんども角度を変えて。深く、浅く口づけをくり返す。
「ンッ、アッ……」
彼の手も、唇も何もかも。
わたしのどこに触れれば、わたしに淫らな熱が灯るのか。わたしがよがるのか。
すべてを熟知しているのだろう。
触れられるたび、求められるたび、わたしに火が灯る。
もっとほしくて。甘くねだるように、体をしならせる。
「里珠……」
名を呼ばれ、うながされ。
「如飛……」
応じるように、脚を開き、彼を受け入れる。
「アッ、イッ、アアッ……」
まるで、わたしの失った半身を取り戻したように。わたしの中にピッタリ沿う彼のイチモツ。抱きしめれば、溶け合って混じってしまいそうに感じる彼の肌。熱。
見つめ合い、微笑み合っては、口づけを交わす。
時に激しく乱暴に。時に甘く優しく。
寝台の上、一つの獣のように蠢き、相手を求める。
「アッ、アアッ、アァアア、ア――ッ!」
「グッ、里珠っ!」
二人で、絶頂の階を駆け上る。
ドクンとわたしの奥で脈打った彼のイチモツ。
「アッ、ヒッ、ア、アッ……」
熱い吐精に、ビクビクと体が震える。
「里珠、愛してる」
「わたし、も……」
言って、体のつながりを解かないまま、どちらからともなく口づける。舌を絡め、唾液を混ぜる。
(アッ……)
それだけで、わたしの奥で、彼のイチモツが、またグンッと大きくなったのを感じた。大きくなっただけじゃない。少しずつ、ユルユルと腰を前後される。
(また、くれるんだ……)
子はできないかもしれない。けど、愛されている証を、またわたしの奥に刻みつけてくれる。
それがうれしくて、幸せで。
わたしも、彼の動きに合わせて、腰を揺らす。
「里珠」
わたしの動きに彼も気づいたのだろう。
身を起こした彼の動きが一層激しくなった。
快感に、わたしの体に酩酊したように、狂ったように腰を打ち付けてくる。
「アアッ、如飛、如飛っ!」
快楽に押し流されそうで。救いを求めて彼の名を呼ぶ。
「里珠、里珠っ!」
伸ばした手に、指を絡められ、そのまま手を敷布に押し付けられた。
飛び散る彼の汗。満ちる淫らな匂い。熱。
バチュバチュと肉のぶつかる音。グチュグチュというかき混ぜられる水音。
「アッ、イッ、イイッ、イクッ……!」
絶叫し、大きく背を反らす。同時に、また精を吐き出される。
何度もなんども愛する人に満たされて。
わたしは、世界で一番幸せな女だ。
夜遅く。
二人で戻った瑠璃宮の室で。
わたしと揃いの夜着に着替えた如飛を睨みつける。
即位の儀のあと、含元殿の前に集まった、宮殿に入りきれなかった兵士たちの前に姿を見せた時も、即位の祝宴でも。ずっと、ずっと黙って、横に立って、それらしく笑ってたけど。
だからって、「はい、そうですか」って納得したわけじゃないのよ!
説明! 説明しなさい!
わたし、皇后は辞退するって、前に言ったじゃない!
「この衣装のことか?」
「そっ……」
それも訊きたいことだけどっ!
「お前が俺のために衣装を縫ってたのは知っている。糸を用意するように命じたのは、俺だからな」
そうだ。そうです。そうでした。
糸とか皎月さんが持ってきてくれたけど。そこに、彼が関係してないわけがないんだった。だって、皎月さんは彼の部下だし。
わたしが縫ってたことは、彼に筒抜けだったと。
「途中で、縫うのを止めたみたいだったが。俺は、未完成であっても、これを着て即位したかった。お前が設えてくれたものだ。これ以上に、俺の即位にふさわしい衣はない」
グウ。
そう言われると、中途半端な刺繍しかない衣であっても、最高の衣に思えてくる。
「さて、どこから話せばよいかな」
怒るわたしを前に、一人寝台に腰を下ろした如飛。衣のことを話してる時より、声の高さがグンッと落ちた。
「俺は、幼い頃から妃は一人、乙女だけでよいと決めてきたんだ」
「乙女だけ?」
「ああ。……少し長くなるが、聴いてくれるか?」
即位の時とも、その後の宴席の時とも違う。
とても真面目で、とても思い悩んだような表情。
「わかったわ」
怒りは一旦置いといて、話し、聴いてあげる。
「俺の父、先の皇帝は、慣習に倣って皇后、玻璃妃と、陰陽の乙女、瑠璃妃を持っていた。それが当たり前だったし、皇帝として統治するためには、それが普通だった。玻璃妃に子を産ませ、瑠璃妃と交わって陰陽を整える。俺を産んだのは、皇后、玻璃妃だしな」
少し前かがみになった彼が、膝の上で手を組む。
「だが。だが、母は、本来、叔父の妻になる女性だったんだ」
「――え?」
それって、どういうこと?
「瑠璃妃と玻璃妃、ともに揃っていないと即位できない。だから、父は、陰陽の乙女を見つけ出すと同時に、母を皇后に選んだ。母が……、皇族に連なる娘だったから――というのが表向きの理由だな。裏は、異母弟である叔父と母の幸せそうな関係を妬ましく思ったから。それと、母を妻にすることで、叔父の力が増すことを恐れたから」
「そんな……」
「叔父は、異母兄である俺の父の言うことに従うしかなかった。母を渡さなければ、それは次期皇帝に対する反逆だ。叔父だけでなく、母も処刑される。だから、叔父は母を手離した。そして叔父は、母と離れても母を思い慕い、誰とも結婚せずにいる」
そこまで話して、如飛が手で顔を覆った。
「それに比べ、最低な男だよ、俺の父は。愛し合ってた異母弟たちを引き離して、母に俺を産ませたのだから」
手を離して、深く深く息を吐き出した。
「それでも、父が母を愛して大事にすれば、救いもあっただろう。でも父はそうはしなかった。母が俺を孕んだことで、母を捨てた。母の居た玻璃宮にも、皇太子だった俺の琥珀宮にも、一度も訪れなかった。子が生まれればそれでよし、弟と母の仲を引き裂けば、それで満足だったんだろう」
わざとだろう。
如飛が明るく話してくれるけど、聴いてるわたしのお腹には、ドンドン鉛が詰められていくような感じがした。
「母を大事にしなかった父は、自身の乙女でもある瑠璃妃に対しても同じだった。乙女は、陰陽を整えるための道具に過ぎない。だから、遠征先にもどこにでも連れて行って、嫌がる乙女を無理やり犯していた」
グッ。
「俺も一度だけ見たことがあるんだ。後宮の庭で。心を壊して、身動ぎ一つしない乙女にのしかかり、欲望をぶつけるだけの父の姿を……」
「もういい! もう、言わなくていい!」
話す如飛が、辛そうで。話しながら、自分を傷つけ血を流してる用に見えて、思わず彼を抱きしめる。
「ありがとう、里珠」
腕の中で、如飛が囁いた。
「俺は、あれを見た時からずっと心に誓っていたんだ。愛するなら乙女だけを。身を捧げてもらわなければ国を治められないというのなら、乙女だけを愛そうと」
「如飛……」
「だが、人というものは難しいな。身を捧げてもらうのだから愛さねばと思っていたのに。今では、愛しいと思うからこそ愛したいと思っている」
「きゃっ!」
グイッと抱き寄せられた腰。予想してなかった如飛の動きに、均衡を崩した体が、彼の上にしなだれる。
「里珠。俺はお前が好きだ。愛してる。陰陽の乙女だからじゃない。お前がお前だから、愛おしい」
「如飛」
「お前が乙女でなかったとしても、俺はお前を愛さずにいられなかっただろう」
なにそれ。ナニソレ、ナニソレ。
言葉と、眼差し、伝わる鼓動。そしてわたしを抱きしめる腕。
そのすべてに、口がわななき、目が熱くなってくる。
「わ、わたしも如飛が好き」
「里珠……」
うれしい。そこまで想ってくれて。わたしを大事にしてくれて。
でも。
「でも……、わたし、アナタの子を産んであげられない……」
陰陽の乙女は、どれだけ交わろうとも子を成せない。
どれだけ精を注がれても、子ができることはない。
「知って、いたのか……」
その問いかけに、我慢できなかった涙が溢れ、「うん」と小さく頷くことしかできなかった。
ごめんなさい。
それほどまでに、愛してくれても、わたしはアナタになにも返してあげられないの。
「そうか」
シュルっと衣擦れの音がした。如飛が動いたんだ。
「だがな。それは間違いかもしれないぞ」
「ま、間違い?」
ファサッと、わたしの体が寝台に横たえられる。
「陰陽の乙女が子を産んだ記録はない。だがな」
シュルシュル。お腹の辺りで音がする。
「初代皇帝の皇后、二代皇帝の母は、陰陽の乙女だ」
「え?」
溢れ続けていた涙が引っ込んだ。
二代皇帝の――母?
「初代も二代も、存在が伝説に近いから、本当かどうか、真偽は疑わしいけどな。だが、陰陽の乙女が皇后になって、子を産んだ。それが二代目皇帝だという伝説が残っている」
「じゃ、じゃあ、わたし、子を産めるのっ!?」
「かもしれんな。試してみるか?」
ニヤッといたずらっぽく如飛が笑う。
って、ちょっと! いつの間にわたしの帯を外してたのよ!
帯を解かれたせいで夜着がはだけ、わたしの首元からおへその下まで、彼の目の前に晒される。
「子ができぬでもよい。こうして交わるのは、陰陽を整えるためでも、子を成すためでもない」
グッと身を乗り出した如飛。
「お前を愛しいと思うからこそ。愛しいお前と一つになりたい。お前に俺を刻みつけたいと思うから交わるのだ」
笑いが消え、残った真摯な瞳に、わたしが映る。
泣きそうになって、グッと唇を噛みしめ、彼だけを見つめるわたしが。
「世の中には、どれだけ愛し合おうとも、子ができぬ夫婦も居ると聴く。俺たちも、そういう夫婦であってもよいと思っている。まあ、皇帝としては民に不実かもしれんが。しかし、俺に子がいなくても叔父上がいる。叔父上でダメだと言うのなら……。そうだな。皇族の誰かから養子をもらってもいいかもしれん」
「如飛……」
「そろそろよいか? 俺はお前を愛したくて仕方ないんだが?」
「もうっ!」
軽く言った彼に、笑ってみせたかったのに。
笑った頬を、こらえきれなかった涙が流れ落ちる。
「里珠」
その涙を指で拭ってくれた如飛。そのまま誘われるように、笑みを残した彼の唇に、自分のを重ねる。何度もなんども角度を変えて。深く、浅く口づけをくり返す。
「ンッ、アッ……」
彼の手も、唇も何もかも。
わたしのどこに触れれば、わたしに淫らな熱が灯るのか。わたしがよがるのか。
すべてを熟知しているのだろう。
触れられるたび、求められるたび、わたしに火が灯る。
もっとほしくて。甘くねだるように、体をしならせる。
「里珠……」
名を呼ばれ、うながされ。
「如飛……」
応じるように、脚を開き、彼を受け入れる。
「アッ、イッ、アアッ……」
まるで、わたしの失った半身を取り戻したように。わたしの中にピッタリ沿う彼のイチモツ。抱きしめれば、溶け合って混じってしまいそうに感じる彼の肌。熱。
見つめ合い、微笑み合っては、口づけを交わす。
時に激しく乱暴に。時に甘く優しく。
寝台の上、一つの獣のように蠢き、相手を求める。
「アッ、アアッ、アァアア、ア――ッ!」
「グッ、里珠っ!」
二人で、絶頂の階を駆け上る。
ドクンとわたしの奥で脈打った彼のイチモツ。
「アッ、ヒッ、ア、アッ……」
熱い吐精に、ビクビクと体が震える。
「里珠、愛してる」
「わたし、も……」
言って、体のつながりを解かないまま、どちらからともなく口づける。舌を絡め、唾液を混ぜる。
(アッ……)
それだけで、わたしの奥で、彼のイチモツが、またグンッと大きくなったのを感じた。大きくなっただけじゃない。少しずつ、ユルユルと腰を前後される。
(また、くれるんだ……)
子はできないかもしれない。けど、愛されている証を、またわたしの奥に刻みつけてくれる。
それがうれしくて、幸せで。
わたしも、彼の動きに合わせて、腰を揺らす。
「里珠」
わたしの動きに彼も気づいたのだろう。
身を起こした彼の動きが一層激しくなった。
快感に、わたしの体に酩酊したように、狂ったように腰を打ち付けてくる。
「アアッ、如飛、如飛っ!」
快楽に押し流されそうで。救いを求めて彼の名を呼ぶ。
「里珠、里珠っ!」
伸ばした手に、指を絡められ、そのまま手を敷布に押し付けられた。
飛び散る彼の汗。満ちる淫らな匂い。熱。
バチュバチュと肉のぶつかる音。グチュグチュというかき混ぜられる水音。
「アッ、イッ、イイッ、イクッ……!」
絶叫し、大きく背を反らす。同時に、また精を吐き出される。
何度もなんども愛する人に満たされて。
わたしは、世界で一番幸せな女だ。
1
あなたにおすすめの小説

番探しにやって来た王子様に見初められました。逃げたらだめですか?
ゆきりん(安室 雪)
恋愛
私はスミレ・デラウェア。伯爵令嬢だけど秘密がある。長閑なぶどう畑が広がる我がデラウェア領地で自警団に入っているのだ。騎士団に入れないのでコッソリと盗賊から領地を守ってます。
そんな領地に王都から番探しに王子がやって来るらしい。人が集まって来ると盗賊も来るから勘弁して欲しい。
お転婆令嬢が番から逃げ回るお話しです。
愛の花シリーズ第3弾です。

君は番じゃ無かったと言われた王宮からの帰り道、本物の番に拾われました
ゆきりん(安室 雪)
恋愛
ココはフラワーテイル王国と言います。確率は少ないけど、番に出会うと匂いで分かると言います。かく言う、私の両親は番だったみたいで、未だに甘い匂いがするって言って、ラブラブです。私もそんな両親みたいになりたいっ!と思っていたのに、私に番宣言した人からは、甘い匂いがしません。しかも、番じゃなかったなんて言い出しました。番婚約破棄?そんなの聞いた事無いわっ!!
打ちひしがれたライムは王宮からの帰り道、本物の番に出会えちゃいます。

番は君なんだと言われ王宮で溺愛されています
ゆきりん(安室 雪)
恋愛
私ミーシャ・ラクリマ男爵令嬢は、家の借金の為コッソリと王宮でメイドとして働いています。基本は王宮内のお掃除ですが、人手が必要な時には色々な所へ行きお手伝いします。そんな中私を番だと言う人が現れた。えっ、あなたって!?
貧乏令嬢が番と幸せになるまでのすれ違いを書いていきます。
愛の花第2弾です。前の話を読んでいなくても、単体のお話として読んで頂けます。

『冷徹社長の秘書をしていたら、いつの間にか専属の妻に選ばれました』
鍛高譚
恋愛
秘書課に異動してきた相沢結衣は、
仕事一筋で冷徹と噂される社長・西園寺蓮の専属秘書を務めることになる。
厳しい指示、膨大な業務、容赦のない会議――
最初はただ必死に食らいつくだけの日々だった。
だが、誰よりも真剣に仕事と向き合う蓮の姿に触れるうち、
結衣は秘書としての誇りを胸に、確かな成長を遂げていく。
そして、蓮もまた陰で彼女を支える姿勢と誠実な仕事ぶりに心を動かされ、
次第に結衣は“ただの秘書”ではなく、唯一無二の存在になっていく。
同期の嫉妬による妨害、ライバル会社の不正、社内の疑惑。
数々の試練が二人を襲うが――
蓮は揺るがない意志で結衣を守り抜き、
結衣もまた社長としてではなく、一人の男性として蓮を信じ続けた。
そしてある夜、蓮がようやく口にした言葉は、
秘書と社長の関係を静かに越えていく。
「これからの人生も、そばで支えてほしい。」
それは、彼が初めて見せた弱さであり、
結衣だけに向けた真剣な想いだった。
秘書として。
一人の女性として。
結衣は蓮の差し伸べた未来を、涙と共に受け取る――。
仕事も恋も全力で駆け抜ける、
“冷徹社長×秘書”のじれ甘オフィスラブストーリー、ここに完結。


勘違い妻は騎士隊長に愛される。
更紗
恋愛
政略結婚後、退屈な毎日を送っていたレオノーラの前に現れた、旦那様の元カノ。
ああ なるほど、身分違いの恋で引き裂かれたから別れてくれと。よっしゃそんなら離婚して人生軌道修正いたしましょう!とばかりに勢い込んで旦那様に離縁を勧めてみたところ――
あれ?何か怒ってる?
私が一体何をした…っ!?なお話。
有り難い事に書籍化の運びとなりました。これもひとえに読んで下さった方々のお蔭です。本当に有難うございます。
※本編完結後、脇役キャラの外伝を連載しています。本編自体は終わっているので、その都度完結表示になっております。ご了承下さい。

一途な皇帝は心を閉ざした令嬢を望む
浅海 景
恋愛
幼い頃からの婚約者であった王太子より婚約解消を告げられたシャーロット。傷心の最中に心無い言葉を聞き、信じていたものが全て偽りだったと思い込み、絶望のあまり心を閉ざしてしまう。そんな中、帝国から皇帝との縁談がもたらされ、侯爵令嬢としての責任を果たすべく承諾する。
「もう誰も信じない。私はただ責務を果たすだけ」
一方、皇帝はシャーロットを愛していると告げると、言葉通りに溺愛してきてシャーロットの心を揺らす。
傷つくことに怯えて心を閉ざす令嬢と一途に想い続ける青年皇帝の物語
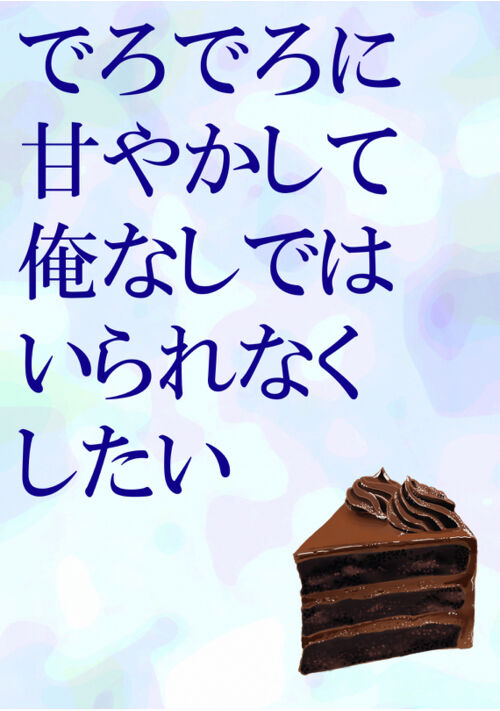
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















