16 / 45
第1章
リズの思い
しおりを挟む
美しいベルベットが張られた長椅子に、ゆっくりとリズを降ろして、兄は言った。
「リズ。意地を張らずに、少しここで休むんだ」
その声には、兄の不安がはっきりと示されていた。
何度も示されたその不安に申し訳ない心地がして、リズはとうとう頷き、ひじ掛けに身体を持たせかけた。
正直なところ、このまま目を閉じ寝てしまいたい気持ちだった。
殿下と踊っていた時に受けた精神的な衝撃が、身体へも及んだらしく、リズは、突然、体に重さを感じて、完璧な笑顔を浮かべて立っている自分を褒めたたえたい状態になってしまった。
笑顔を浮かべ周囲に気取らせないようにしていたつもりだったが、リズの異変は殿下に伝わっていたらしい。
4曲目が始まっても殿下は踊ることはなく、リズの腰に手を回し「氷の王子」の笑顔を周りに投げかけ畏怖させながら、ゆっくりとダンスの場所から離れ始めてくれた。
そして、今度こそ迎えに来た兄が一瞬鋭い視線を殿下と交わし合った後、リズをさりげなく支えながら、いかなる挨拶も誘いも忘れさせてしまう笑顔を振りまき、広間から連れ出してくれたのだ。
人の目が無くなった途端、リズは立つことも難しくなってしまい、兄に抱き上げられここまで運んでもらっている。
「とても腹立たしいけれど、この部屋は主を憚って人も近づきにくいし、守護の結界も張ってある。休むには最適な部屋だ」
兄の言葉に誘われて、部屋をゆっくりと見回してみる。
リズには守護の結界は感じ取れないが、王宮の一室とあって、公爵家で育ったリズの目から見てもその上質さに感嘆する調度が品よく配置されている。
中でも目を引くのは、壁にかけられているクロシア国章を精緻に縫い込んだタペストリーだ。端の房飾りには輝石が付けられている。
「お兄様。ここはもしかすると無断で入ってよい部屋ではないのでは――」
「あの腹黒で器の小さい王太子は、リズになら喜んで使わせるだろう。そもそもあの馬鹿が浮かれたためにこんなことになったのだから、僕の天使が遠慮する必要は欠片もない」
対面して罵詈雑言を浴びせなければ、王室法が定める不敬罪には抵触しないと思いつつもリズはそわそわとしてしまう。
つまり、ここは王太子殿下の居室のようだ。
一刻も早く、兄に自分の体調を安心してもらい退室しなければ、とリズは焦るものの、長椅子に腰かけた途端、あまりの心地よさに気が緩んでしまったのか体に力が全く入らない。
兄がそんなリズの状態を見逃すはずもなく、リズの手を握った。
「いいかい。この部屋には守護の結界が強く張られている。ここで待っていておくれ。温かい飲み物と王宮の侍医――、いや守護師の方がいいか、捉まる方を連れて来させよう」
「お兄様。そこまでは――」
リズの言葉を笑顔で押し切り、兄は部屋から出ていってしまった。
一人、大きな部屋に取り残され、リズは思わず溜息を吐く。
王宮で働く侍従や侍女たちは、舞踏会のためにまだまだ目の回る忙しさのはずだ。
迷惑をかけてしまう以前に、侍女たちを捉まえること自体が難しいだろう。
私が不甲斐ないためなのに――
穴を掘って閉じこもりたいほどの自己嫌悪に苛まれる。
今までの人生を、自分の目標のみを見つめ、向けられてきた真摯な思いを軽んじ続けた自分の行いだけでも穴に飛び込みたいのに、そのことに気が付いて衝撃を受けるなど、情けなさを通り越して、自分自身に呆れてしまう。
思いに沈み込んでいると、ノックと同時にドアが開いた。
「お兄―― 」
厳しい空気を纏って部屋に入ってきた人物を認めて、リズは言葉を切った。
気力をかき集めて長椅子から立ち上がり礼を取る。
「大変失礼を致しました。ヴィクター殿下」
鷹揚に頷いたヴィクター殿下は、冷たい青の瞳でリズに座ることを促した。
王族への敬意を示すために、その配慮をリズが笑顔で跳ね除けると、厳めしい顔は溜息を吐き、小さく「座りなさい。ひどい顔だ」とはっきりと促した。
先ほどの諍いの後にも関わらず示された配慮にリズは内心驚きながらも、ありがたく座らせてもらう。
その様子を見てほんの僅かに頷くと、ヴィクター殿下はすっと表情を消して問いかけた。
「見事なダンスだった。エドワードから求婚されたのかね」
リズは目を瞠った。
ヴィクター殿下との話題は、先ほどの『赤の光』になると思っていただけに、話題を唐突に感じてしまったのだ。
求婚については、国王陛下の意向を受けて公式のものとはなっていないため、王室でも公爵家でも内密にされている。
週に一度公爵家に殿下が訪れる理由も、「学友」たる兄と話し合うためとされている。
つまり、リズはこう答えるしかなかった。
「そのような畏れ多いことはあり得ません」
ヴィクター殿下は、口の端を僅かにゆがめたものの、追及はしなかった。
「まぁ、よい。貴女はエドワードの求婚をはっきりと断りなさい。私から陛下に貴女の断りを伝え、彼の下にはローラを嫁がせる」
あまりに突然の話に、リズは一瞬言われたことが理解できなかった。
やがて理解が及ぶと、再び呆然としてしまう。
断る?ローラ嬢と結婚?
冷え切った青の瞳が、リズを見据えた。
「貴女に教えてもらったのだよ。王太子妃が『紅の花』を身に纏えば、国中の女性が再び『紅の花』を求めるようになるだろう」
何という安直な――
ラタ帝国の皇妃陛下は国中の女性の憧れを受ける存在だったから、『紅の花』は広まったのだ。
けれど、思わず零しそうになったリズの本音は飲み込まれた。
ヴィクター殿下の一番の意図が分かったからだ。
私が王太子妃となり、一層、『赤の光』の人気が高まることを避けるためなのだわ
リズは自分の身体から重さが消え去ったのを感じた。同時に体の隅々まで新鮮な空気が染み渡るような心地がした。
冷静な思考をする気力がリズに蘇る。
ここでの返答は、将来の王太子妃だけの問題ではなく、『赤の光』の将来も、引いてはラタ帝国との友好にも関わる事態だ。
一切、言質を取られるようなことは避けなければ。
もう一度、求婚などされていないと出発点を否定するべきかしら。
いえ、また同じ話の流れに戻ってしまう。
リズが打開策を探していると、眼前の温もりを全く感じ取れない冷徹な青の瞳は、その瞳に似合いの言葉をゆっくりと放った。
「殿下が貴女に想いを寄せていたとしても、王族に生まれた者として、婚姻が自由にできるものではないということは、殿下も娘も弁えているはずだ」
リズは一切表情を動かさないまま、胸の内でこの皮肉な事態を笑っていた。
ほんの1時間前のリズなら、殿下の婚約者候補から外れるこの申し出に飛びついていたはずだ。
穏やかな人生を歩む第一歩が踏めたと、意気揚々としていただろう。
ほんの1時間前のことなのに――
リズの黙考を拒否と捉えたのだろうか、ヴィクター殿下は一瞬目を伏せ、小さくため息を吐いた後、上着の内ポケットから小さな袋を取り出した。
一体何を取り出したのかとリズは息を詰めて凝視した物は、王宮の格調高い部屋で目にするとは思わないものだった。
それは木の枝だった。長さは10センチほどの短いもので、特に先端を尖らせてもいないその枝は、一見したところ、脅威を感じさせるものではない。
「この枝が何の木のものかは分からないだろうね」
リズは瞬きをするのみにとどめた。
確かに普通のご令嬢なら分からないはずだ。
けれど、リズには枝の白い樹皮を見た瞬間、名前が分かっていた。
ヴィクター殿下は、リズの断定を裏付ける。
「トクシコという木だ」
木に含まれる油分は激しいかぶれを引き起こす。それでも、樹液は良質な蝋となり、木材の防水に使われるため、地域によってはその毒性を知りながらも、栽培しているところもある。
リズが知識を掘り起こし、現実から目を逸らしてみても、低い声がリズを引き戻す。
「その麗しい美貌をこのように損ねたくはないだろう」
ヴィクター殿下は手袋を外し、素手でその枝を握りしめる。
リズは眉を顰めた。
枝にするために切り落とした時点で、樹液が出ているはずだ。もちろん、油分も。
ヴィクター殿下の手は、見る見るうちに赤く染まっていく。枝に触れていない手首まで染まり始めている。
この方、この油分に対して、かなり敏感な方なのだわ。
トクシコへの反応は個人差が大きい。
樹液が出ていなければ反応が出ない人もいれば、近くを歩いただけで反応が出る人もいる。
「殿下、枝を離してください」
それは殿下の身体を案じての言葉であったが、リズの意図は伝わらなかった。
リズが怯えていると思ったのだろう。ヴィクター殿下は口角を上げ、幾分柔らかな口調で再び告げる。
「美しい顔をこうしたくなければ、求婚を断りなさい」
殿下の手は、鮮烈な赤みと腫れを見せていた。微かに呼吸の乱れも聞こえている。
劇症と言っていい状態だ。
「枝を離して――」
「断りなさい――!こうなりたいのか!」
リズの身体に怒りが駆け巡った。
気が付けば言葉を叩きつけていた。
「あの方を見くびらないでください!」
予想もしない言葉だったのだろう。ヴィクター殿下の目が僅かに大きくなる。
リズはその青の瞳に視線を据える。
一度溢れ出た言葉は、止まることはなかった。
「あの方は、私の容姿がどうなろうとお気持ちを変える方ではありません」
――私も、貴女が公爵令嬢でなく、その女神の美を持っていなければと、何度も、数えきれないほど考えた――、
あの言葉が嘘偽りのない心のままのものだということは、今のリズには分かっていた。
リズの胸に再び痛みが蘇る。
「その程度の想いでしたら、私はここまで苦しくはありません!」
私はあの方に想いを返すことはできない。
けれど、いえ、だからこそ――
「私は、このような理由であの方をお断りすることは致しません!」
あの方の想いにかけて、私はこのような理由は認めない!
リズはすっと長椅子から立ち上がった。
「枝を離すのです!」
リズが迷いなく、ヴィクター殿下へ一歩踏み出したとき、全てのことが起こった。
眩しい閃光と大きな音と共に天井が割れ、護衛が飛び降りながらヴィクター殿下を蹴り倒す。
タペストリーの裏から、艶やかな金の髪を乱しながら殿下が飛び出し、リズの目の前が青い光で染まったときには、殿下はリズを抱え込み床に倒れ込んだ。
痛いほどの強さで抱き込まれたリズの耳は、掠れた小さな声を捉えていた。
「貴女の容姿がどうなろうとこの想いは変わらない」
さらにリズが喘ぐほどの強さで抱きしめた後、殿下は小さく囁いた。
「けれど、貴女が自ら傷つくことは耐えられない。絶対に」
「リズ。意地を張らずに、少しここで休むんだ」
その声には、兄の不安がはっきりと示されていた。
何度も示されたその不安に申し訳ない心地がして、リズはとうとう頷き、ひじ掛けに身体を持たせかけた。
正直なところ、このまま目を閉じ寝てしまいたい気持ちだった。
殿下と踊っていた時に受けた精神的な衝撃が、身体へも及んだらしく、リズは、突然、体に重さを感じて、完璧な笑顔を浮かべて立っている自分を褒めたたえたい状態になってしまった。
笑顔を浮かべ周囲に気取らせないようにしていたつもりだったが、リズの異変は殿下に伝わっていたらしい。
4曲目が始まっても殿下は踊ることはなく、リズの腰に手を回し「氷の王子」の笑顔を周りに投げかけ畏怖させながら、ゆっくりとダンスの場所から離れ始めてくれた。
そして、今度こそ迎えに来た兄が一瞬鋭い視線を殿下と交わし合った後、リズをさりげなく支えながら、いかなる挨拶も誘いも忘れさせてしまう笑顔を振りまき、広間から連れ出してくれたのだ。
人の目が無くなった途端、リズは立つことも難しくなってしまい、兄に抱き上げられここまで運んでもらっている。
「とても腹立たしいけれど、この部屋は主を憚って人も近づきにくいし、守護の結界も張ってある。休むには最適な部屋だ」
兄の言葉に誘われて、部屋をゆっくりと見回してみる。
リズには守護の結界は感じ取れないが、王宮の一室とあって、公爵家で育ったリズの目から見てもその上質さに感嘆する調度が品よく配置されている。
中でも目を引くのは、壁にかけられているクロシア国章を精緻に縫い込んだタペストリーだ。端の房飾りには輝石が付けられている。
「お兄様。ここはもしかすると無断で入ってよい部屋ではないのでは――」
「あの腹黒で器の小さい王太子は、リズになら喜んで使わせるだろう。そもそもあの馬鹿が浮かれたためにこんなことになったのだから、僕の天使が遠慮する必要は欠片もない」
対面して罵詈雑言を浴びせなければ、王室法が定める不敬罪には抵触しないと思いつつもリズはそわそわとしてしまう。
つまり、ここは王太子殿下の居室のようだ。
一刻も早く、兄に自分の体調を安心してもらい退室しなければ、とリズは焦るものの、長椅子に腰かけた途端、あまりの心地よさに気が緩んでしまったのか体に力が全く入らない。
兄がそんなリズの状態を見逃すはずもなく、リズの手を握った。
「いいかい。この部屋には守護の結界が強く張られている。ここで待っていておくれ。温かい飲み物と王宮の侍医――、いや守護師の方がいいか、捉まる方を連れて来させよう」
「お兄様。そこまでは――」
リズの言葉を笑顔で押し切り、兄は部屋から出ていってしまった。
一人、大きな部屋に取り残され、リズは思わず溜息を吐く。
王宮で働く侍従や侍女たちは、舞踏会のためにまだまだ目の回る忙しさのはずだ。
迷惑をかけてしまう以前に、侍女たちを捉まえること自体が難しいだろう。
私が不甲斐ないためなのに――
穴を掘って閉じこもりたいほどの自己嫌悪に苛まれる。
今までの人生を、自分の目標のみを見つめ、向けられてきた真摯な思いを軽んじ続けた自分の行いだけでも穴に飛び込みたいのに、そのことに気が付いて衝撃を受けるなど、情けなさを通り越して、自分自身に呆れてしまう。
思いに沈み込んでいると、ノックと同時にドアが開いた。
「お兄―― 」
厳しい空気を纏って部屋に入ってきた人物を認めて、リズは言葉を切った。
気力をかき集めて長椅子から立ち上がり礼を取る。
「大変失礼を致しました。ヴィクター殿下」
鷹揚に頷いたヴィクター殿下は、冷たい青の瞳でリズに座ることを促した。
王族への敬意を示すために、その配慮をリズが笑顔で跳ね除けると、厳めしい顔は溜息を吐き、小さく「座りなさい。ひどい顔だ」とはっきりと促した。
先ほどの諍いの後にも関わらず示された配慮にリズは内心驚きながらも、ありがたく座らせてもらう。
その様子を見てほんの僅かに頷くと、ヴィクター殿下はすっと表情を消して問いかけた。
「見事なダンスだった。エドワードから求婚されたのかね」
リズは目を瞠った。
ヴィクター殿下との話題は、先ほどの『赤の光』になると思っていただけに、話題を唐突に感じてしまったのだ。
求婚については、国王陛下の意向を受けて公式のものとはなっていないため、王室でも公爵家でも内密にされている。
週に一度公爵家に殿下が訪れる理由も、「学友」たる兄と話し合うためとされている。
つまり、リズはこう答えるしかなかった。
「そのような畏れ多いことはあり得ません」
ヴィクター殿下は、口の端を僅かにゆがめたものの、追及はしなかった。
「まぁ、よい。貴女はエドワードの求婚をはっきりと断りなさい。私から陛下に貴女の断りを伝え、彼の下にはローラを嫁がせる」
あまりに突然の話に、リズは一瞬言われたことが理解できなかった。
やがて理解が及ぶと、再び呆然としてしまう。
断る?ローラ嬢と結婚?
冷え切った青の瞳が、リズを見据えた。
「貴女に教えてもらったのだよ。王太子妃が『紅の花』を身に纏えば、国中の女性が再び『紅の花』を求めるようになるだろう」
何という安直な――
ラタ帝国の皇妃陛下は国中の女性の憧れを受ける存在だったから、『紅の花』は広まったのだ。
けれど、思わず零しそうになったリズの本音は飲み込まれた。
ヴィクター殿下の一番の意図が分かったからだ。
私が王太子妃となり、一層、『赤の光』の人気が高まることを避けるためなのだわ
リズは自分の身体から重さが消え去ったのを感じた。同時に体の隅々まで新鮮な空気が染み渡るような心地がした。
冷静な思考をする気力がリズに蘇る。
ここでの返答は、将来の王太子妃だけの問題ではなく、『赤の光』の将来も、引いてはラタ帝国との友好にも関わる事態だ。
一切、言質を取られるようなことは避けなければ。
もう一度、求婚などされていないと出発点を否定するべきかしら。
いえ、また同じ話の流れに戻ってしまう。
リズが打開策を探していると、眼前の温もりを全く感じ取れない冷徹な青の瞳は、その瞳に似合いの言葉をゆっくりと放った。
「殿下が貴女に想いを寄せていたとしても、王族に生まれた者として、婚姻が自由にできるものではないということは、殿下も娘も弁えているはずだ」
リズは一切表情を動かさないまま、胸の内でこの皮肉な事態を笑っていた。
ほんの1時間前のリズなら、殿下の婚約者候補から外れるこの申し出に飛びついていたはずだ。
穏やかな人生を歩む第一歩が踏めたと、意気揚々としていただろう。
ほんの1時間前のことなのに――
リズの黙考を拒否と捉えたのだろうか、ヴィクター殿下は一瞬目を伏せ、小さくため息を吐いた後、上着の内ポケットから小さな袋を取り出した。
一体何を取り出したのかとリズは息を詰めて凝視した物は、王宮の格調高い部屋で目にするとは思わないものだった。
それは木の枝だった。長さは10センチほどの短いもので、特に先端を尖らせてもいないその枝は、一見したところ、脅威を感じさせるものではない。
「この枝が何の木のものかは分からないだろうね」
リズは瞬きをするのみにとどめた。
確かに普通のご令嬢なら分からないはずだ。
けれど、リズには枝の白い樹皮を見た瞬間、名前が分かっていた。
ヴィクター殿下は、リズの断定を裏付ける。
「トクシコという木だ」
木に含まれる油分は激しいかぶれを引き起こす。それでも、樹液は良質な蝋となり、木材の防水に使われるため、地域によってはその毒性を知りながらも、栽培しているところもある。
リズが知識を掘り起こし、現実から目を逸らしてみても、低い声がリズを引き戻す。
「その麗しい美貌をこのように損ねたくはないだろう」
ヴィクター殿下は手袋を外し、素手でその枝を握りしめる。
リズは眉を顰めた。
枝にするために切り落とした時点で、樹液が出ているはずだ。もちろん、油分も。
ヴィクター殿下の手は、見る見るうちに赤く染まっていく。枝に触れていない手首まで染まり始めている。
この方、この油分に対して、かなり敏感な方なのだわ。
トクシコへの反応は個人差が大きい。
樹液が出ていなければ反応が出ない人もいれば、近くを歩いただけで反応が出る人もいる。
「殿下、枝を離してください」
それは殿下の身体を案じての言葉であったが、リズの意図は伝わらなかった。
リズが怯えていると思ったのだろう。ヴィクター殿下は口角を上げ、幾分柔らかな口調で再び告げる。
「美しい顔をこうしたくなければ、求婚を断りなさい」
殿下の手は、鮮烈な赤みと腫れを見せていた。微かに呼吸の乱れも聞こえている。
劇症と言っていい状態だ。
「枝を離して――」
「断りなさい――!こうなりたいのか!」
リズの身体に怒りが駆け巡った。
気が付けば言葉を叩きつけていた。
「あの方を見くびらないでください!」
予想もしない言葉だったのだろう。ヴィクター殿下の目が僅かに大きくなる。
リズはその青の瞳に視線を据える。
一度溢れ出た言葉は、止まることはなかった。
「あの方は、私の容姿がどうなろうとお気持ちを変える方ではありません」
――私も、貴女が公爵令嬢でなく、その女神の美を持っていなければと、何度も、数えきれないほど考えた――、
あの言葉が嘘偽りのない心のままのものだということは、今のリズには分かっていた。
リズの胸に再び痛みが蘇る。
「その程度の想いでしたら、私はここまで苦しくはありません!」
私はあの方に想いを返すことはできない。
けれど、いえ、だからこそ――
「私は、このような理由であの方をお断りすることは致しません!」
あの方の想いにかけて、私はこのような理由は認めない!
リズはすっと長椅子から立ち上がった。
「枝を離すのです!」
リズが迷いなく、ヴィクター殿下へ一歩踏み出したとき、全てのことが起こった。
眩しい閃光と大きな音と共に天井が割れ、護衛が飛び降りながらヴィクター殿下を蹴り倒す。
タペストリーの裏から、艶やかな金の髪を乱しながら殿下が飛び出し、リズの目の前が青い光で染まったときには、殿下はリズを抱え込み床に倒れ込んだ。
痛いほどの強さで抱き込まれたリズの耳は、掠れた小さな声を捉えていた。
「貴女の容姿がどうなろうとこの想いは変わらない」
さらにリズが喘ぐほどの強さで抱きしめた後、殿下は小さく囁いた。
「けれど、貴女が自ら傷つくことは耐えられない。絶対に」
1
あなたにおすすめの小説
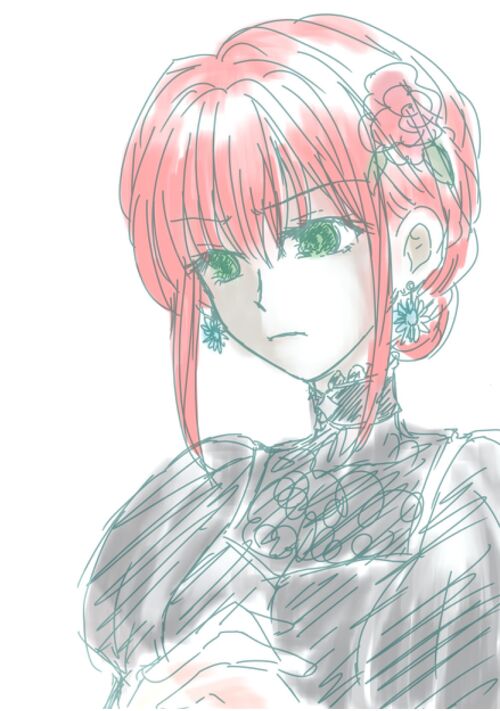
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

【完結】公爵家の秘密の愛娘
ゆきむらさり
恋愛
〔あらすじ〕📝グラント公爵家は王家に仕える名門の家柄。
過去の事情により、今だに独身の当主ダリウス。国王から懇願され、ようやく伯爵未亡人との婚姻を決める。
そんな時、グラント公爵ダリウスの元へと現れたのは1人の少女アンジェラ。
「パパ……私はあなたの娘です」
名乗り出るアンジェラ。
◇
アンジェラが現れたことにより、グラント公爵家は一変。伯爵未亡人との再婚もあやふや。しかも、アンジェラが道中に出逢った人物はまさかの王族。
この時からアンジェラの世界も一変。華やかに色付き出す。
初めはよそよそしいグラント公爵ダリウス(パパ)だが、次第に娘アンジェラを気に掛けるように……。
母娘2代のハッピーライフ&淑女達と貴公子達の恋模様💞
🔶設定などは独自の世界観でご都合主義となります。ハピエン💞
🔶稚拙ながらもHOTランキング(最高20位)に入れて頂き(2025.5.9)、ありがとうございます🙇♀️


これが運命ではなかったとしても
gacchi(がっち)
恋愛
アントシュ王国に生まれたルーチェ王女は精霊付きのため、他人と関わらないように隔離されていたが、家族には愛され不自由でも幸せに育っていた。そんなある日、父と兄が叔父に毒を盛られ捕縛される事件が起こり、精霊に守られ無事だったルーチェは塔へと閉じ込められる。半年後、ルーチェを助けてくれたのは隣国の国王の命令で派遣されてきた王弟アルフレッド。保護されたルーチェは隣国へと連れて行かれるが、そこでは生き別れの双子の妹シンディが王女として育てられていた。

〖完結〗旦那様が愛していたのは、私ではありませんでした……
藍川みいな
恋愛
「アナベル、俺と結婚して欲しい。」
大好きだったエルビン様に結婚を申し込まれ、私達は結婚しました。優しくて大好きなエルビン様と、幸せな日々を過ごしていたのですが……
ある日、お姉様とエルビン様が密会しているのを見てしまいました。
「アナベルと結婚したら、こうして君に会うことが出来ると思ったんだ。俺達は家族だから、怪しまれる心配なくこの邸に出入り出来るだろ?」
エルビン様はお姉様にそう言った後、愛してると囁いた。私は1度も、エルビン様に愛してると言われたことがありませんでした。
エルビン様は私ではなくお姉様を愛していたと知っても、私はエルビン様のことを愛していたのですが、ある事件がきっかけで、私の心はエルビン様から離れていく。
設定ゆるゆるの、架空の世界のお話です。
かなり気分が悪い展開のお話が2話あるのですが、読まなくても本編の内容に影響ありません。(36話37話)
全44話で完結になります。

木こりと騎士〜不条理に全てを奪われた元宰相家令嬢は、大切なものを守るために剣をとる〜
温故知新
恋愛
剣と魔法を王族や貴族が独占しているペトロート王国では、貴族出身の騎士たちが、国に蔓延る魔物ではなく、初級魔法1回分の魔力しか持たない平民に対して、剣を振ったり魔法を放ったりして、快楽を得ていた。
だが、そんな騎士たちから平民を守っていた木こりがいた。
騎士から疎まれ、平民からは尊敬されていた木こりは、平民でありながら貴族と同じ豊富な魔力を持ち、高価なために平民では持つことが出来ないレイピアを携えていた。
これは、不条理に全てを奪われて1人孤独に立ち向かっていた木こりが、親しかった人達と再会したことで全てを取り戻し、婚約者と再び恋に落ちるまでの物語である。
※他サイトでも公開中!

貴方だけが私に優しくしてくれた
バンブー竹田
恋愛
人質として隣国の皇帝に嫁がされた王女フィリアは宮殿の端っこの部屋をあてがわれ、お飾りの側妃として空虚な日々をやり過ごすことになった。
そんなフィリアを気遣い、優しくしてくれたのは年下の少年騎士アベルだけだった。
いつの間にかアベルに想いを寄せるようになっていくフィリア。
しかし、ある時、皇帝とアベルの会話を漏れ聞いたフィリアはアベルの優しさの裏の真実を知ってしまってーーー

【完結】アラサー喪女が転生したら悪役令嬢だった件。断罪からはじまる悪役令嬢は、回避不能なヤンデレ様に溺愛を確約されても困ります!
美杉日和。(旧美杉。)
恋愛
『ルド様……あなたが愛した人は私ですか? それともこの体のアーシエなのですか?』
そんな風に簡単に聞くことが出来たら、どれだけ良かっただろう。
目が覚めた瞬間、私は今置かれた現状に絶望した。
なにせ牢屋に繋がれた金髪縦ロールの令嬢になっていたのだから。
元々は社畜で喪女。挙句にオタクで、恋をすることもないままの死亡エンドだったようで、この世界に転生をしてきてしあったらしい。
ただまったく転生前のこの令嬢の記憶がなく、ただ状況から断罪シーンと私は推測した。
いきなり生き返って死亡エンドはないでしょう。さすがにこれは神様恨みますとばかりに、私はその場で断罪を行おうとする王太子ルドと対峙する。
なんとしても回避したい。そう思い行動をした私は、なぜか回避するどころか王太子であるルドとのヤンデレルートに突入してしまう。
このままヤンデレルートでの死亡エンドなんて絶対に嫌だ。なんとしても、ヤンデレルートを溺愛ルートへ移行させようと模索する。
悪役令嬢は誰なのか。私は誰なのか。
ルドの溺愛が加速するごとに、彼の愛する人が本当は誰なのかと、だんだん苦しくなっていく――
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















