20 / 45
番外編
紫水晶に誓いをたてる
しおりを挟む
彼女のことをいつから想っていたのかは分からない。
初めて彼女の思考に触れた時からかもしれない。
初めてあの澄んだ紫水晶の瞳を見た時かもしれない。
もしくは、もっと別の時だったのかもしれない。
けれども、初めて彼女を護りたいと思ったときのことは、はっきりと思い出すことができる。
あの紫水晶を曇らせたくはないと、体の奥から沸き上がるような強い思いを初めて抱いた瞬間は、今でも鮮やかに思い浮かぶ。
きっと忘れることなどできない。
この命が尽きるまで。もしかしたら、命が尽きたとしても。
◇
おや、あの木の魔素がいつもより少ない。病気になったのだろうか。
ヒューは馬車の窓から見える大木に目を留め、訝しむ。
少し距離があってもはっきりとした存在感を放つその大木は、公爵家へ行く道中のヒューの和みになっていた。齢を重ねた大木は魔素を多く蓄え、ヒューの目にはことさらに包み込むような優しさを感じさせてくれるのだ。
ヒューの暮らす侯爵家の庭は、ここ最近の晴天続きによる雨不足のためだろうか、幾分、草木に勢いがなく魔素が薄れていたので、この大木を見て魔素を感じることを楽しみにしていた。
けれども、今日は大木の魔素が少なくなり、存在感も弱々しく感じる。
大木の幹は腕を伸ばした大人が何人かで抱える太さだ。樹齢も優に数百年は超えているだろう。とうとうその命を終えてしまうのかもしれないと、ヒューは一抹の寂しさを覚えた。
「ヒュー、どうしたのだい?」
向かいにくつろいで座っている父が穏やかに、しかし、僅かな心配を隠し切れずに問いかけてくる。
ヒューはゆっくりと首を振りながら、父の憂いを払った。
自然の命の理を嘆いても仕方ないのだから。
◇
今日もヒューは公爵家に遊びに来ていた。
厳密にいえば、暇があれば父にせがんでいつも公爵家に遊びに来ている。初めて会った時から、公爵家の天使と妖精は、遊びに来るヒューを親しみを持って受け入れてくれた。
特に天使は、彼のことを分かりやすく慕ってくれている。
庭に出て、3人で遊び始めてすぐ、楽しそうな、温かな、くすぐったいような、思考とも呼べない思念と共に、ヒューの頬がはっきりと浮かび上がる。
ヒューがそれを読み取ると同時に、いつも通り、リズは彼の頬をそっと人差し指で突く。
まただ…。
ヒューは内心、溜息を付いた。
公爵家に顔を出すようになり、すぐに気が付いたことだが、――気が付かない方がおかしいぐらいだけれど、リズはヒューの頬をとにかく気に入っているようで、必ず、一度はこうして彼の頬を突くのだ。
決して嫌なわけではない。くすぐったいけれど痛くもないし、むしろリズに突かれるのは心地よいし、何より、彼女はさっと指をひっこめた後、満面の笑みを浮かべてくれる。
ヒューは天使の輝くような笑みが好きだし、気が付けば笑みを返している自分も知っている。
けれど、ヒューはいつしか物足りなさを感じるようになっていた。
自分の頬以外も、もっとリズに好きになってもらえないだろうかと。
僕は欲張りなのだろうな。
この兄妹に出会う前には、同じ年頃の子どもと目を合わすことすらできていなかったというのに、今では自分の色々なところをもっと好きになって欲しいと願っている。
会うたびに膨らんでいくヒューの願いを読み取ったのだろう。いつものように頭に吹雪が入り込んできたけれど、慣れた吹雪は無視して、そんなことをつらつらと彼は考えていた。
「ヒュー。ヒューの好きな木の葉の色が一段と鮮やかだわ。魔素が増えたの?」
愛らしい声に、埒もない願望と吹雪がかき消された。
リズが指さす、公爵家の庭で一番の大木に目を向けた。その大木も魔素を含んでいて、ヒューには心地よい存在であることをリズに伝えたことがある。
木に目を向けた途端、ヒューは体が強張った。
夏に向けて健やかに緑を深めた葉を風に揺らした大木は、魔素が薄れていた。
木に勢いがあるのに、魔素が薄れている――
ヒューは体が冷えていくのを感じながら、瞳を閉じた。
目に入る情報を遮断すれば、目に見えない情報がヒューの五感に入り込む。ヒューは公爵家の庭の隅々まで魔素の気配を探った。
いつもは探らずともヒューにその気配を伝えてくる魔素の気配を探る時点で、既に予期できたはずだった。
それでも認めたくなくて排除した事実が、彼に突き付けられる。
庭全体の、いや、彼が感じ取れる範囲の全ての魔素が薄れていた。
――――!!
突如、ヒューは、道中の大木と、侯爵家の庭の魔素が薄くなった事実が結びついた。
「ヒュー!!どうしたの?しっかりして!」
「『落ち着くんだ!!』」
遠くで二人の声が響いている。しかし、ヒューにはその声が意味をなさなかった。
この国の魔素は少なくなっている。今に無くなってしまうのかもしれない――
彼の頭に、彼の存在全てにあることは、その恐怖だけだった。
彼のすべてを支配するその恐怖に、呼吸をすることもできなかった。
自分のもう一つの空気ともいえる魔素がなくなれば、自分の魔力はどうなるのだろう――
魔力がなくなるなど、ヒューには体の一部をもぎ取られることと同じだった。
襲い掛かる未来の喪失感に、ヒューは息ができず喘いだ。
死という言葉が脳裏に過ったとき、
「『生きているわ!』」
閃光のような思考が、ヒューの身体を駆け抜けた。
同時に身体は抱きしめられていた。
「『ヒュー!生きているわ!魔素がなくても生きているわ――!』」
その眩しい思考は、ヒューの意識を絡めとっていた激しい喪失感を薙ぎ払った。意識が戻り、次いで呼吸が戻り、酸素が行き渡る。もっと酸素を求めて大きく息を吸い込むと、リズが背中を撫でてくれていたことに気が付いた。
死への恐怖は体の芯にまだ根付き、手足は冷たいままだったが、それでも背中に温もりを感じて、ヒューは目頭が熱くなる。
僕の天使は、僕に光をくれる
光と温もりに導かれて、ヒューの視界はようやく現実に戻った。
自分を見つめる美しい紫水晶の瞳は、涙を溜めて今にも溢れ出しそうだ。
彼と目が合って、彼女が目元を緩めた拍子に、ぽろりと雫が溢れ出た。頬を伝うその雫がとても綺麗に思えて、ヒューは見惚れていた。
呆けたヒューを心配したのだろう。
もう一度、リズがそっと背中を撫でてくれた。
――その時、体が吹き飛ばされそうな鮮烈な記憶が流れ込んできた。
むせ返る、きつい臭い。
体の全て、そして意識の全てが切り刻まれる激痛。
救いを求めて死を願うほどの激痛の中でも、途切れることのない『彼女』の哀しみ。
――突然に断ち切られた彼女の生。
信じられないリズの記憶に引きずられ、ヒューは再び息ができなくなった。
何もかもが閉ざされた闇に落ち込んでいくようだった。
ひたすら救いを求めて喘いだとき、一条の光が差し込んだ。
「『生きているわ』」
煌めくような思考だった。光を受けて輝く水面のようだった。
その煌めきは、生きているこの瞬間が彼女にとってどれほど素晴らしいものであるかを伝えてくる。奇跡でもたらされた瞬間を、いかにかけがえのないものと彼女が感じているかを教えてくれた。
彼女の感じる幸せがヒューを満たしてくれた。
魔素がなくなったとき、自分の失うものがどれだけ大きいかは想像が付かない。
それでも、彼女の感じる眩しいほどの幸せが自分には残されているのだ。
それが自分にとっても幸せに感じるかは分からないヒューだったが、確かな希望を掴むことができた。
「ありがとう」
魔力が立ち上るほど、心からの感謝を込めて思いを口にすると、リズはゆっくりと顔をほころばせ、柔らかな笑みを返してくれた。
彼女のまだ微かに潤んだ瞳は澄み切って、吸い込まれそうな心地がするほど美しい。
その瞳の美しさは、生まれてから今までヒューが目にしたものの中で、一番美しいものだと彼は思った。
紫の瞳で自分の全てが清められていく心地がした。
紫の清らかな美しさを見ると、あれほど苦しい記憶を彼女が抱えていることなど嘘のようだ。
ヒューの瞳から涙が零れた。
彼女が慌ててもう一度ヒューを抱きしめてくれる。
ヒューの涙は止まらなかった。
彼女の澄んだ美しさは、凄惨な、理不尽な死を乗り越えた結果がもたらした、澄んだ強い意志の現われに思えた。
それでも、出会ってから彼女は決してその記憶をヒューの前で浮かび上がらせたことはなかった。きっと、ヒューが死の恐怖を感じなければ、彼は知らずにいたはずだ。
それほど深く、深く記憶を押し込めたことが、彼女の哀しみの大きさを伝えていた。
彼女を護りたい――
浮かび上がった渇望は、強い魔力と共に彼の身体を駆け抜けた。
彼女の哀しみを癒したい。
彼女がかけがえのないと感じる幸せを護りたい。
この紫の瞳を輝かせるためなら、どんなことでも惜しまない。
自分の全てを差し出して、この美しい瞳を護って見せる。
途切れることなく次々と沸き上がる強い思いに押し出されるようにして、ヒューは言葉を紡いだ。
「僕は強くなるよ」
彼の誓いの意図はリズに伝わるはずもなかったけれど、彼の脅えがなくなったことは伝わったようだ。
リズは驚きに目を瞬かせた後、満面の笑みを浮かべてヒューに抱き着いた。
即座に馴染みの吹雪が頭に吹き込んできたことを感じながら、ヒューは自分の護るべき天使をしっかりと抱きしめていた。
強くなって見せる。
でも、何から始めようか。
柔らかな白金の髪を撫でながら、早速、未来の計画に思案を巡らしたヒューは、リズの頭越しに、一段と激しさを増した吹雪を送り込む銀の美貌が目に入った。
ヒューの口の端がはっきりと上がる。
まず手始めは、この吹雪を跳ね返すことができることを目標にしよう。
初めて彼女の思考に触れた時からかもしれない。
初めてあの澄んだ紫水晶の瞳を見た時かもしれない。
もしくは、もっと別の時だったのかもしれない。
けれども、初めて彼女を護りたいと思ったときのことは、はっきりと思い出すことができる。
あの紫水晶を曇らせたくはないと、体の奥から沸き上がるような強い思いを初めて抱いた瞬間は、今でも鮮やかに思い浮かぶ。
きっと忘れることなどできない。
この命が尽きるまで。もしかしたら、命が尽きたとしても。
◇
おや、あの木の魔素がいつもより少ない。病気になったのだろうか。
ヒューは馬車の窓から見える大木に目を留め、訝しむ。
少し距離があってもはっきりとした存在感を放つその大木は、公爵家へ行く道中のヒューの和みになっていた。齢を重ねた大木は魔素を多く蓄え、ヒューの目にはことさらに包み込むような優しさを感じさせてくれるのだ。
ヒューの暮らす侯爵家の庭は、ここ最近の晴天続きによる雨不足のためだろうか、幾分、草木に勢いがなく魔素が薄れていたので、この大木を見て魔素を感じることを楽しみにしていた。
けれども、今日は大木の魔素が少なくなり、存在感も弱々しく感じる。
大木の幹は腕を伸ばした大人が何人かで抱える太さだ。樹齢も優に数百年は超えているだろう。とうとうその命を終えてしまうのかもしれないと、ヒューは一抹の寂しさを覚えた。
「ヒュー、どうしたのだい?」
向かいにくつろいで座っている父が穏やかに、しかし、僅かな心配を隠し切れずに問いかけてくる。
ヒューはゆっくりと首を振りながら、父の憂いを払った。
自然の命の理を嘆いても仕方ないのだから。
◇
今日もヒューは公爵家に遊びに来ていた。
厳密にいえば、暇があれば父にせがんでいつも公爵家に遊びに来ている。初めて会った時から、公爵家の天使と妖精は、遊びに来るヒューを親しみを持って受け入れてくれた。
特に天使は、彼のことを分かりやすく慕ってくれている。
庭に出て、3人で遊び始めてすぐ、楽しそうな、温かな、くすぐったいような、思考とも呼べない思念と共に、ヒューの頬がはっきりと浮かび上がる。
ヒューがそれを読み取ると同時に、いつも通り、リズは彼の頬をそっと人差し指で突く。
まただ…。
ヒューは内心、溜息を付いた。
公爵家に顔を出すようになり、すぐに気が付いたことだが、――気が付かない方がおかしいぐらいだけれど、リズはヒューの頬をとにかく気に入っているようで、必ず、一度はこうして彼の頬を突くのだ。
決して嫌なわけではない。くすぐったいけれど痛くもないし、むしろリズに突かれるのは心地よいし、何より、彼女はさっと指をひっこめた後、満面の笑みを浮かべてくれる。
ヒューは天使の輝くような笑みが好きだし、気が付けば笑みを返している自分も知っている。
けれど、ヒューはいつしか物足りなさを感じるようになっていた。
自分の頬以外も、もっとリズに好きになってもらえないだろうかと。
僕は欲張りなのだろうな。
この兄妹に出会う前には、同じ年頃の子どもと目を合わすことすらできていなかったというのに、今では自分の色々なところをもっと好きになって欲しいと願っている。
会うたびに膨らんでいくヒューの願いを読み取ったのだろう。いつものように頭に吹雪が入り込んできたけれど、慣れた吹雪は無視して、そんなことをつらつらと彼は考えていた。
「ヒュー。ヒューの好きな木の葉の色が一段と鮮やかだわ。魔素が増えたの?」
愛らしい声に、埒もない願望と吹雪がかき消された。
リズが指さす、公爵家の庭で一番の大木に目を向けた。その大木も魔素を含んでいて、ヒューには心地よい存在であることをリズに伝えたことがある。
木に目を向けた途端、ヒューは体が強張った。
夏に向けて健やかに緑を深めた葉を風に揺らした大木は、魔素が薄れていた。
木に勢いがあるのに、魔素が薄れている――
ヒューは体が冷えていくのを感じながら、瞳を閉じた。
目に入る情報を遮断すれば、目に見えない情報がヒューの五感に入り込む。ヒューは公爵家の庭の隅々まで魔素の気配を探った。
いつもは探らずともヒューにその気配を伝えてくる魔素の気配を探る時点で、既に予期できたはずだった。
それでも認めたくなくて排除した事実が、彼に突き付けられる。
庭全体の、いや、彼が感じ取れる範囲の全ての魔素が薄れていた。
――――!!
突如、ヒューは、道中の大木と、侯爵家の庭の魔素が薄くなった事実が結びついた。
「ヒュー!!どうしたの?しっかりして!」
「『落ち着くんだ!!』」
遠くで二人の声が響いている。しかし、ヒューにはその声が意味をなさなかった。
この国の魔素は少なくなっている。今に無くなってしまうのかもしれない――
彼の頭に、彼の存在全てにあることは、その恐怖だけだった。
彼のすべてを支配するその恐怖に、呼吸をすることもできなかった。
自分のもう一つの空気ともいえる魔素がなくなれば、自分の魔力はどうなるのだろう――
魔力がなくなるなど、ヒューには体の一部をもぎ取られることと同じだった。
襲い掛かる未来の喪失感に、ヒューは息ができず喘いだ。
死という言葉が脳裏に過ったとき、
「『生きているわ!』」
閃光のような思考が、ヒューの身体を駆け抜けた。
同時に身体は抱きしめられていた。
「『ヒュー!生きているわ!魔素がなくても生きているわ――!』」
その眩しい思考は、ヒューの意識を絡めとっていた激しい喪失感を薙ぎ払った。意識が戻り、次いで呼吸が戻り、酸素が行き渡る。もっと酸素を求めて大きく息を吸い込むと、リズが背中を撫でてくれていたことに気が付いた。
死への恐怖は体の芯にまだ根付き、手足は冷たいままだったが、それでも背中に温もりを感じて、ヒューは目頭が熱くなる。
僕の天使は、僕に光をくれる
光と温もりに導かれて、ヒューの視界はようやく現実に戻った。
自分を見つめる美しい紫水晶の瞳は、涙を溜めて今にも溢れ出しそうだ。
彼と目が合って、彼女が目元を緩めた拍子に、ぽろりと雫が溢れ出た。頬を伝うその雫がとても綺麗に思えて、ヒューは見惚れていた。
呆けたヒューを心配したのだろう。
もう一度、リズがそっと背中を撫でてくれた。
――その時、体が吹き飛ばされそうな鮮烈な記憶が流れ込んできた。
むせ返る、きつい臭い。
体の全て、そして意識の全てが切り刻まれる激痛。
救いを求めて死を願うほどの激痛の中でも、途切れることのない『彼女』の哀しみ。
――突然に断ち切られた彼女の生。
信じられないリズの記憶に引きずられ、ヒューは再び息ができなくなった。
何もかもが閉ざされた闇に落ち込んでいくようだった。
ひたすら救いを求めて喘いだとき、一条の光が差し込んだ。
「『生きているわ』」
煌めくような思考だった。光を受けて輝く水面のようだった。
その煌めきは、生きているこの瞬間が彼女にとってどれほど素晴らしいものであるかを伝えてくる。奇跡でもたらされた瞬間を、いかにかけがえのないものと彼女が感じているかを教えてくれた。
彼女の感じる幸せがヒューを満たしてくれた。
魔素がなくなったとき、自分の失うものがどれだけ大きいかは想像が付かない。
それでも、彼女の感じる眩しいほどの幸せが自分には残されているのだ。
それが自分にとっても幸せに感じるかは分からないヒューだったが、確かな希望を掴むことができた。
「ありがとう」
魔力が立ち上るほど、心からの感謝を込めて思いを口にすると、リズはゆっくりと顔をほころばせ、柔らかな笑みを返してくれた。
彼女のまだ微かに潤んだ瞳は澄み切って、吸い込まれそうな心地がするほど美しい。
その瞳の美しさは、生まれてから今までヒューが目にしたものの中で、一番美しいものだと彼は思った。
紫の瞳で自分の全てが清められていく心地がした。
紫の清らかな美しさを見ると、あれほど苦しい記憶を彼女が抱えていることなど嘘のようだ。
ヒューの瞳から涙が零れた。
彼女が慌ててもう一度ヒューを抱きしめてくれる。
ヒューの涙は止まらなかった。
彼女の澄んだ美しさは、凄惨な、理不尽な死を乗り越えた結果がもたらした、澄んだ強い意志の現われに思えた。
それでも、出会ってから彼女は決してその記憶をヒューの前で浮かび上がらせたことはなかった。きっと、ヒューが死の恐怖を感じなければ、彼は知らずにいたはずだ。
それほど深く、深く記憶を押し込めたことが、彼女の哀しみの大きさを伝えていた。
彼女を護りたい――
浮かび上がった渇望は、強い魔力と共に彼の身体を駆け抜けた。
彼女の哀しみを癒したい。
彼女がかけがえのないと感じる幸せを護りたい。
この紫の瞳を輝かせるためなら、どんなことでも惜しまない。
自分の全てを差し出して、この美しい瞳を護って見せる。
途切れることなく次々と沸き上がる強い思いに押し出されるようにして、ヒューは言葉を紡いだ。
「僕は強くなるよ」
彼の誓いの意図はリズに伝わるはずもなかったけれど、彼の脅えがなくなったことは伝わったようだ。
リズは驚きに目を瞬かせた後、満面の笑みを浮かべてヒューに抱き着いた。
即座に馴染みの吹雪が頭に吹き込んできたことを感じながら、ヒューは自分の護るべき天使をしっかりと抱きしめていた。
強くなって見せる。
でも、何から始めようか。
柔らかな白金の髪を撫でながら、早速、未来の計画に思案を巡らしたヒューは、リズの頭越しに、一段と激しさを増した吹雪を送り込む銀の美貌が目に入った。
ヒューの口の端がはっきりと上がる。
まず手始めは、この吹雪を跳ね返すことができることを目標にしよう。
2
あなたにおすすめの小説
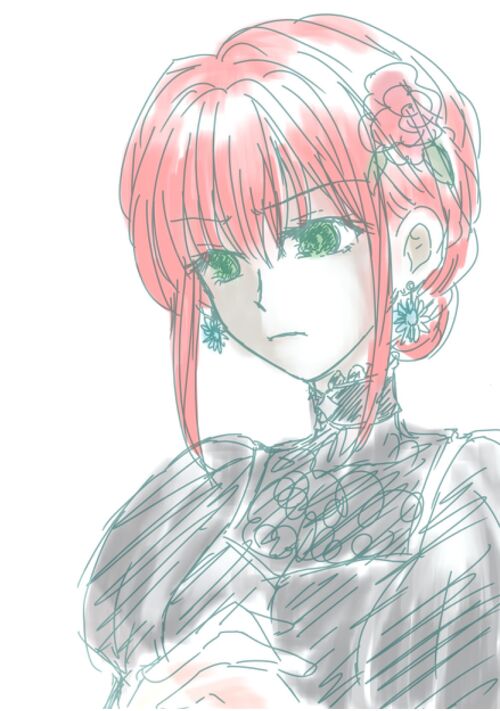
捨てられた悪役はきっと幸せになる
ariya
恋愛
ヴィヴィア・ゴーヴァン公爵夫人は少女小説に登場する悪役だった。
強欲で傲慢で嫌われ者、夫に捨てられて惨めな最期を迎えた悪役。
その悪役に転生していたことに気づいたヴィヴィアは、夫がヒロインと結ばれたら潔く退場することを考えていた。
それまでお世話になった為、貴族夫人としての仕事の一部だけでもがんばろう。
「ヴィヴィア、あなたを愛してます」
ヒロインに惹かれつつあるはずの夫・クリスは愛をヴィヴィアに捧げると言ってきて。
そもそもクリスがヴィヴィアを娶ったのは、王位継承を狙っている疑惑から逃れる為の契約結婚だったはずでは?
愛などなかったと思っていた夫婦生活に変化が訪れる。
※この作品は、人によっては元鞘話にみえて地雷の方がいるかもしれません。また、ヒーローがヤンデレ寄りですので苦手な方はご注意ください。

追放された薬師は、辺境の地で騎士団長に愛でられる
湊一桜
恋愛
王宮薬師のアンは、国王に毒を盛った罪を着せられて王宮を追放された。幼少期に両親を亡くして王宮に引き取られたアンは、頼れる兄弟や親戚もいなかった。
森を彷徨って数日、倒れている男性を見つける。男性は高熱と怪我で、意識が朦朧としていた。
オオカミの襲撃にも遭いながら、必死で男性を看病すること二日後、とうとう男性が目を覚ました。ジョーという名のこの男性はとても強く、軽々とオオカミを撃退した。そんなジョーの姿に、不覚にもときめいてしまうアン。
行くあてもないアンは、ジョーと彼の故郷オストワル辺境伯領を目指すことになった。
そして辿り着いたオストワル辺境伯領で待っていたのは、ジョーとの甘い甘い時間だった。
※『小説家になろう』様、『ベリーズカフェ』様でも公開中です。

大嫌いな従兄と結婚するぐらいなら…
みみぢあん
恋愛
子供の頃、両親を亡くしたベレニスは伯父のロンヴィル侯爵に引き取られた。 隣国の宣戦布告で戦争が始まり、伯父の頼みでベレニスは病弱な従妹のかわりに、側妃候補とは名ばかりの人質として、後宮へ入ることになった。 戦争が終わりベレニスが人質生活から解放されたら、伯父は後継者の従兄ジャコブと結婚させると約束する。 だがベレニスはジャコブが大嫌いなうえ、密かに思いを寄せる騎士フェルナンがいた。

モラハラ王子の真実を知った時
こことっと
恋愛
私……レーネが事故で両親を亡くしたのは8歳の頃。
父母と仲良しだった国王夫婦は、私を娘として迎えると約束し、そして息子マルクル王太子殿下の妻としてくださいました。
王宮に出入りする多くの方々が愛情を与えて下さいます。
王宮に出入りする多くの幸せを与えて下さいます。
いえ……幸せでした。
王太子マルクル様はこうおっしゃったのです。
「実は、何時までも幼稚で愚かな子供のままの貴方は正室に相応しくないと、側室にするべきではないかと言う話があがっているのです。 理解……できますよね?」

〖完結〗旦那様が愛していたのは、私ではありませんでした……
藍川みいな
恋愛
「アナベル、俺と結婚して欲しい。」
大好きだったエルビン様に結婚を申し込まれ、私達は結婚しました。優しくて大好きなエルビン様と、幸せな日々を過ごしていたのですが……
ある日、お姉様とエルビン様が密会しているのを見てしまいました。
「アナベルと結婚したら、こうして君に会うことが出来ると思ったんだ。俺達は家族だから、怪しまれる心配なくこの邸に出入り出来るだろ?」
エルビン様はお姉様にそう言った後、愛してると囁いた。私は1度も、エルビン様に愛してると言われたことがありませんでした。
エルビン様は私ではなくお姉様を愛していたと知っても、私はエルビン様のことを愛していたのですが、ある事件がきっかけで、私の心はエルビン様から離れていく。
設定ゆるゆるの、架空の世界のお話です。
かなり気分が悪い展開のお話が2話あるのですが、読まなくても本編の内容に影響ありません。(36話37話)
全44話で完結になります。

職業『お飾りの妻』は自由に過ごしたい
LinK.
恋愛
勝手に決められた婚約者との初めての顔合わせ。
相手に契約だと言われ、もう後がないサマンサは愛のない形だけの契約結婚に同意した。
何事にも従順に従って生きてきたサマンサ。
相手の求める通りに動く彼女は、都合のいいお飾りの妻だった。
契約中は立派な妻を演じましょう。必要ない時は自由に過ごしても良いですよね?

公爵令嬢は嫁き遅れていらっしゃる
夏菜しの
恋愛
十七歳の時、生涯初めての恋をした。
燃え上がるような想いに胸を焦がされ、彼だけを見つめて、彼だけを追った。
しかし意中の相手は、別の女を選びわたしに振り向く事は無かった。
あれから六回目の夜会シーズンが始まろうとしている。
気になる男性も居ないまま、気づけば、崖っぷち。
コンコン。
今日もお父様がお見合い写真を手にやってくる。
さてと、どうしようかしら?
※姉妹作品の『攻略対象ですがルートに入ってきませんでした』の別の話になります。

【完結】公爵家の秘密の愛娘
ゆきむらさり
恋愛
〔あらすじ〕📝グラント公爵家は王家に仕える名門の家柄。
過去の事情により、今だに独身の当主ダリウス。国王から懇願され、ようやく伯爵未亡人との婚姻を決める。
そんな時、グラント公爵ダリウスの元へと現れたのは1人の少女アンジェラ。
「パパ……私はあなたの娘です」
名乗り出るアンジェラ。
◇
アンジェラが現れたことにより、グラント公爵家は一変。伯爵未亡人との再婚もあやふや。しかも、アンジェラが道中に出逢った人物はまさかの王族。
この時からアンジェラの世界も一変。華やかに色付き出す。
初めはよそよそしいグラント公爵ダリウス(パパ)だが、次第に娘アンジェラを気に掛けるように……。
母娘2代のハッピーライフ&淑女達と貴公子達の恋模様💞
🔶設定などは独自の世界観でご都合主義となります。ハピエン💞
🔶稚拙ながらもHOTランキング(最高20位)に入れて頂き(2025.5.9)、ありがとうございます🙇♀️
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















